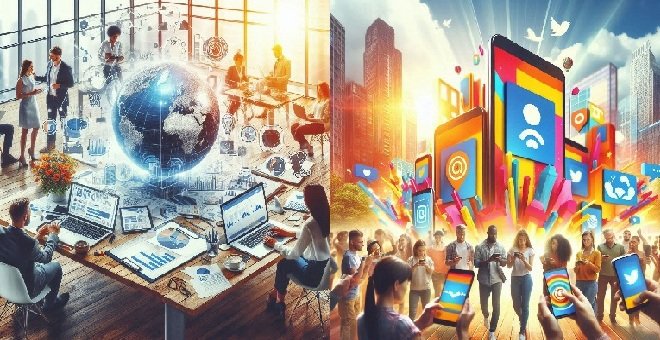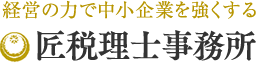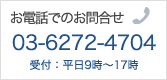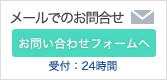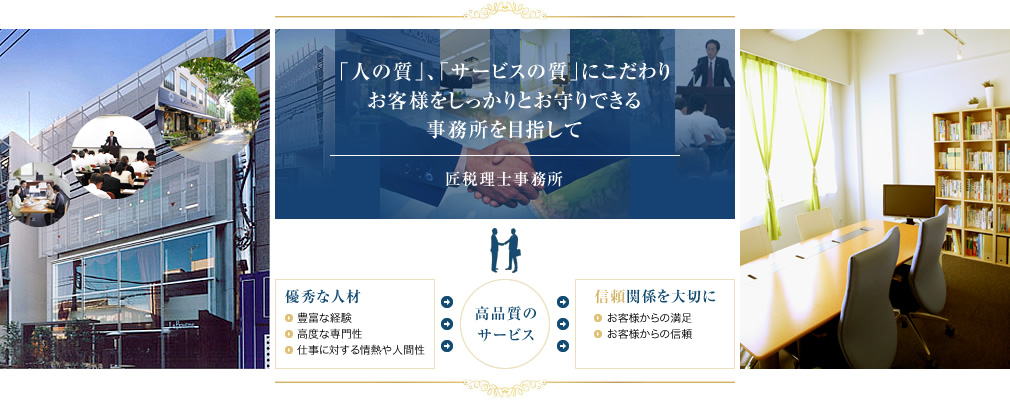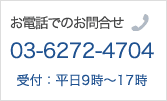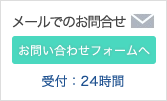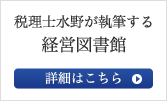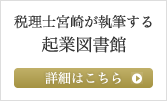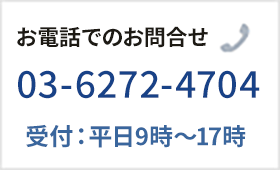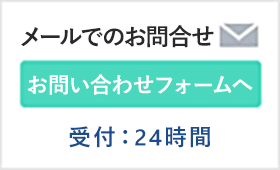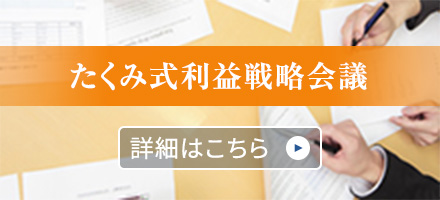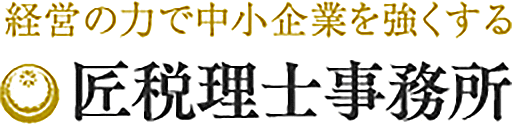建設業者の決算報告とは?決算書・試算表作成ポイントとは
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
はじめまして。建設業担当の税理士 水野です。
建設業・建築業はIT業など他の業種に比べて
決算書作成では注意が必要になります。
なぜなら、建設業・建築業は決算書の提出先が
① 融資・借入を受けている金融機関
② 国土交通大臣または都道府県知事と他の業種に比べて【 ②の分 】が多いからです。
②の決算報告の提出がないと
以下の悪影響が生じるおそれがあります。
・建設業業種の追加ができなくなる
・一般許可や特定許可の新規申請ができなくなる
・建設業許可の更新申請ができない
・公共工事の入札参加資格を得られない
・取引先の信用悪化につながる場合がある
だから建設業・建築業はIT業など他の業種に比べて
決算書作成ではより注意が必要になります。

建設業許可の決算報告と役割とは
建設許可を有する方は、事業年終了から4ヶ月以内に
建設業の決算報告書(事業年度終了報告書)を提出する義務があります。
一般的な中小企業の場合では、
決算日である事業年度の終了から2ヶ月に税務署に税務申告・納付を行う必要があります。
この税務署への税務申告から2ヶ月以内に建設業の決算報告が必要になります。
つまり、12月決算の会社なら提出期限は4月末です。◆東京都知事許可の場合には以下が必要です。
・変更届出書(別紙8)
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度の工事施工金額
・法人:十五号・十六号・十七号・十七号の二財務諸表
・個人:十八号、十九号 財務諸表
・事業報告書(特例有限会社を除く株式会社限定)
・使用人数(変更時のみ)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人一覧表
・定款(変更時のみ)
・健康保険等の加入状況(変更時のみ)
・納税証明書

そして、これらの建設業の決算報告には、
以下大きく2つの役割があります。
【 建設業許可更新をする時に必要 】決算報告をしないと、許可更新申請ができなくなり、
結果、大規模工事受注が出来なくなります。
これによる逸失利益は相当なものになりますので、決算報告は必ず期日までにしましょう!
【 建設業の適正な経営状況把握で必要 】決算報告を基に経営事項審査など各種分析行って
会社の課題を把握します。
これにより経営改善事項が浮き彫りになりますが、
決算報告をしないと、これらの機会を失うため、
改善事項が不透明になります。
決算報告の基、試算表・決算書作成ポイント
国土交通大臣又は都道府県知事に提出する
決算報告はどのように作成されるのでしょうか?
この作成の流れを抑える事で
決算報告作成のポイントがつかめます。
【 決算報告作成までの流れ 】【 1 】 毎月税理士に領収書・請求書などを送る
【 2 】 税理士にて月間業績を把握する試算表作成
【 3 】 試算表を12か月分まとめた決算書作成
【 4 】 決算書を建設業勘定へ行政書士が表示修正
大きく分けると上記工程で決算報告を作成します。

決算報告作成でポイントになるのは、
試算表12か月分の決算書を税理士が作成時に
決算上の利益など決算報告の主要箇所の約9割は、完了している事です。
実際より売上を増やすなど粉飾決算は違法ですが、
実際を的確に表現することがポイントになります。当たり前に聞こえますが、
これは、会計的にかなり高度な技術を要します。
特に建設業は以下2点が、ポイントになります。
① 適正な収益の認識基準を会計に適用する
【 工事完成基準】工事完成・引渡しの日とするのが原則的な取り扱い
【 工事進行基準】工事の進行割合に応じて収益・費用を認識する
工事進行基準が強制される場合とは
下記の要件に合致する長期大規模工事では工事進行基準が強制されます。
・着手日から目的物の引き渡し日の期間が1年以上
・請負対価が10億円以上であること
・請負対価額の2分の1以上が目的物の引渡し日から
1年を経過する日以後に支払われるものでない
建設業は一取引当たりの工事金額が大きいため、
上記のような特殊な収益計上基準も対応できることが技術的に求められます。

② 適切な在庫金額の把握が建設業では重要
完成工事原価は、工事完成に直接かかった費用です。
完成工事原価は、いつ仕入・外注されたものでも、
当期に完成されたものについてかかった費用を
計算することが重要です。
そこで次のような算式を用いて計算します。
【 完成工事原価 = A + B - C 】 A 期首未成工事支出金 B 工事原価 C 期末未成工事支出金【 期首未成工事支出金 】
前期以前に仕入の材料や外注費で前期未完成で
前期末で在庫となっていたもの
(つまりは前年の決算時点の在庫)
【 工事原価 】
→ 材料費や外注費など当期工事にかかった費用
【 期末未成工事支出金 】
→ 今期の仕入・外注費だが期末に完成納品されずに在庫となったもの
この金額が次の期では期首棚卸高となります。

棚卸し・在庫管理は完成工事原価に大影響
大企業などは多くの人・商品がかかわるため
品質不良や盗難などを避けるために日々在庫を
コンピュータ管理しているのが一般的ですが、
中小企業のように社長=会社のオーナーになると
在庫管理は税務申告のため行う事が多いです。
そのため期首未成工事=期末未成工事なら
当期仕入分や外注した分=完成工事原価 となりますのでイメージと決算書が合うのですが、
期首未成工事支出金 > 期末未成工事支出金では、
前年の在庫を今年に販売したわけですから、
こちらの分を今年の完成工事原価の計算では、
加味しなくてはなりません。

数字入れて例にしてみると
A 期首未成工事支出金・・・・・400
B 当期工事原価・・・・・・・・・・・1,000
C 期末未成工事支出金・・・・・100
400+1,000=1,400(前年在庫と今年仕入分)
1,400-100(決算時点在庫)=1,300
(完成した工事原価)
以外にこの在庫を販売するために使った分 ( 400-100=300 )が、 頭にあるイメージの完成工事原価と 決算書の完成工事原価にズレを起こしやすいので、 毎月月末に在庫を集計し計上すべきです。在庫管理をしっかり行うことを通じて、
的確な完成工事原価が分かるようになります。
完成工事原価がしっかりと分かれば、
売上総利益(粗利)が把握でき、
粗利が把握できれば利益の8割が決まりますので、
経営判断や節税対策が効果的に行えます。
このように在庫計上は大変ですが、【 重要 】です!税理士事務所によって、毎月の在庫計上はせず、
期末に税金の計算時のみ行うところもありますが
在庫計上してないため、赤字の試算表に毎月なり、
金融機関の融資ではマイナスの評価です。
匠税理士事務所では建設業支援に力を入れており、
毎月在庫を集計・計上した的確な試算表を作成し、
資金調達の成功率を上げるように取り組みます。
結果、【 資金調達成功率は9割超 】となってます。

建設業の決算書・試算表は在庫把握がポイント
今期仕入をした材料費が1億円あって、
これに対する工事が翌期完成・納品の場合には
今期の経費ではなく、翌期の経費とすべきです。しかし、これを在庫に計上していないと
今期の経費が増えることになるため、結果として、利益が減少することになってしまいます。
上記はあくまで1億という分かりやすい例ですが、
建設業の案件では、Aという案件に外注費・材料費で
数百件が関係してくるという事は普通にあり、
これらが今期完成案件か未完成案件かを区分集計し
在庫金額を適切に会計上反映する必要があります。
その際には、工事管理台帳と会計帳簿連携させ、
収益費用が適切に会計上で計上されているのかを
分析・検証する必要が出てきます。

今期、材料や外注費などが先行して1億円出ていて、
この案件の売り上げが翌期に計上される場合には、
期末の在庫として1億円が計上される事になります。
金融機関融資では、この1億の在庫金額の集計が、 1円単位で積み上がって、本当に実在するのか否かの 検証が必ず行われます。なぜなら、在庫金額を大きくし、利益を大きく見せる
粉飾決算を見抜き、適切な審査を行うためです。
在庫金額の集計を的確に行うのは難しいのですが、
利益に与える影響が大きい重要な項目と言えます。
匠税理士事務所には起業・経営セミナー講師の
建設業に強い世界4大会計事務所出身で税理士が、建設業のお客様の金融機関格付けを上げながら、
一般・特定建設業許可の取得更新を支援します。

建設業許認可専門の行政書士の申請代行
この建築業や建設業許可申請の取得は一見、
自分でできそうですが実際やると複雑です。
しかし、500万以上の工事請負に許可は必要です。
そこで匠税理士事務所では建設業許認可申請に特化した行政書士が申請代行します。【↓】
→東京都建設業許可の新規取得・申請代行
建築業や建設業許可申請の専門家である 行政書士に許可申請を任せるメリットは などがあります。 東京都・神奈川県の建設業許可申請はこちら【↓】 許可申請につきましては、専属の行政書士が 建設業許可を取得できない場合も、 なぜ取得できないのか、どれ位の期間 どうすれば取得できるかなど見直しを提案します。 弊所では、建設業に特化した行政書士と連携して、 東京都知事許可申請から国土交通大臣許可申請や 【 一般許可 から 特定許可 】まで対応します。 お客様のご要望・今後の事業展開を伺った上で 公共工事入札・経営審査の改善提案も可能です。 税務顧問契約なしで、東京都や神奈川県での建設業許認可申請代行のみも承っております。 これまでの豊富な経験とノウハウを活かし、他では難しかった案件にもしっかりと対応しております。 建設業 新規申請(知事・一般) 新規申請(大臣・一般) 申請内容・案件で個別見積もりになりますので お気軽にご相談ください。 上記法定費用は、建設業許可申請を行う際の国や都道府県等に納める税金等で手続で決まってます。 更新手続きや業種追加も対応し、更新に必要な会計書類も匠税理士事務所が行政書士と連携し東京都や神奈川県全域に対応致します。 ◇一般建設業許可 → 土木や解体工事など一般建設業許可業種や、資格登録要件とは ◇特定建設業許可 ◇入札に必須の経営事項審査(経審) 行政書士対応地域は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都・神奈川県全域となります。 匠税理士事務所では、世界4大会計事務所出身で 経営セミナーで講師を務める税理士水野を中心に、 建設業・建築業の経営者様と一緒に利益が出て お金が残る会社づくりをサポートします。 税理士水野が執筆する特定許可資格取得と 一般許可資格取得の違い以外の建設業の
お役立ち情報は、下記よりご確認下さい。 利益が出て、お金が残る会社づくりへの道!! → 建設業・建築業で粗利率はどのくらいが平均?経営改善ポイント 建設業でおススメな販路である入札制度のご紹介 → 入札とは?わかりやすく説明。入札メリット・流れ・落札も解説 節税対策で会社に利益を残す方法と税務調査解説 人気記事から過去の記事まで全て収録 【↓】 匠税理士事務所では、建設業や建築業のお客様が 多くいらっしゃるため建設業や建築業の税務知識や 経営コンサルティングなどに強みがあります。 特定業許可と一般許可の取得申請代行から 建設業の経営者の方向け経営コンサルティングと 独立開業される方に向け起業支援を軸に、 会計税務など高度な専門性とノウハウを駆使し、 社長様の悩み課題に一件一件丁寧に取り組みます。 ◇所属税理士やサービスはこちらから 【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】 一般許可と特定許可資格取得の相談も可能! ◇建設業・建築業限定の起業家向け無料相談会 ◇起業支援・法人化サービス 建設業・建築業で粗利率改善への 経営支援から会計・経理など全てお任せの 会社設立サービスはこちらから確認下さい。 【 → 目黒区の税理士による会社設立】 ◇補助金/補助金サービス (設備などモノ) 補助金申請書の作成代行と助成金申請・コンサルティング (人材の採用や育成)助成金申請代行《起業、創業や雇用の助成金≫ 執筆者・文責:税理士 水野智史 2025年10月の内容の建設業者の決算報告とは?決算書・試算表作成ポイントとは お役に立てましたら幸いでございます。 シェア又はフォローで応援をお願いします!! #建設業決算報告 #決算報告 #建設業決算書
【 9割超の高い成功率の許認可取得 】
【 取得への壁に対する打開策の提案 】
【 申請代行で仕事に集中できること 】
建設業許可が取得可能か 初回無料相談実施中

東京都や神奈川県全域対応の建設業許可申請
・申請報酬 126,000円~
・法定費用 90,000円
・申請報酬 147,000円~
・法定費用 150,000円
建設業・建築業の経営者向けお役立ち情報
【 粗利確保に強靭な販路が不可欠! 】
【 利益確保したら次は節税が重要!】
【 建設業の役立ち情報まとめ!】
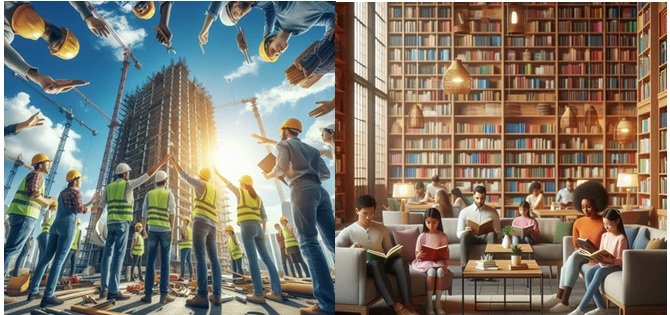
匠税理士事務所の建設業向けサービス