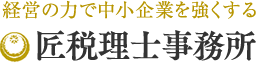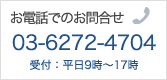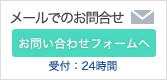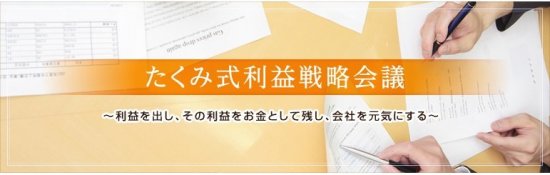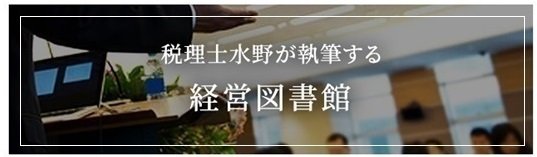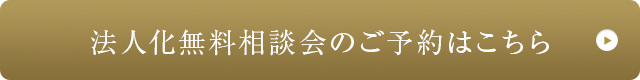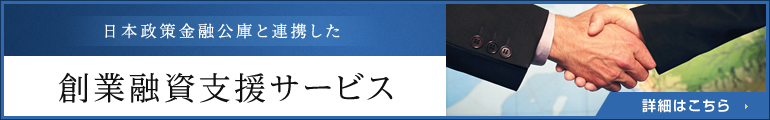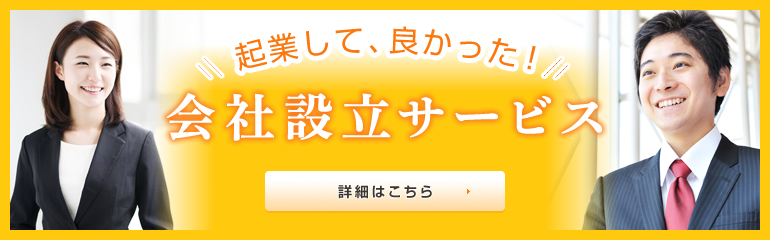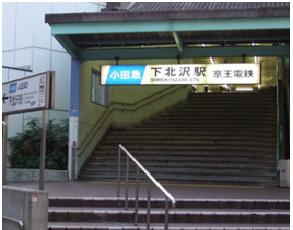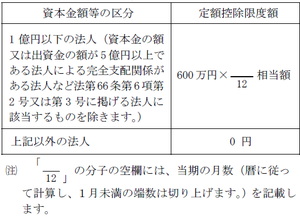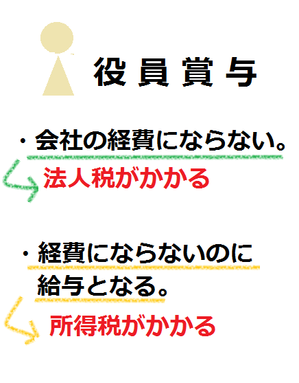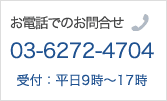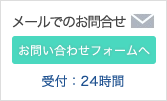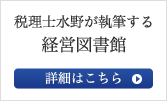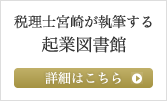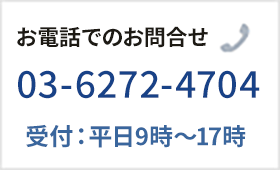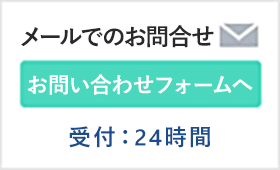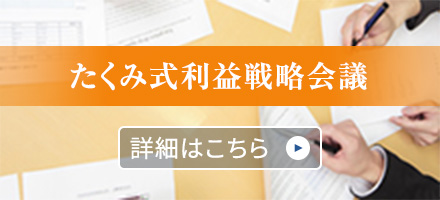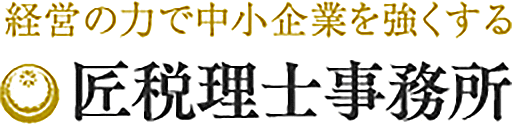匠よりお知らせ
起業創業・独立開業のやり方とは?おすすめの資金調達方法 (24/07/17)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は起業創業・独立開業支援に力を入れてます。
今回は起業するには、どんなやり方があるかに加え
資金調達の方法についてもまとめてみました。
起業創業や独立開業のやり方とは
起業創業や独立開業には、大きく3つが必要です。
1 何を売るのか、お客様に支持されるは何か決める 2 自社の商品・サービスを販売する組織形態を決める 3 1と2を実現するために必要な資金を調達する
まず上記1は自社の存在意義ともいえますが、
自社の商品・サービスは何か、それは他社と比べ何が
優れていて、お客様に支持されるのか考えます。
実際に商品・サービスが良ければ売れますから、
売上から経費を差し引き、利益(儲け)が出ます。
起業や独立開業成功は、【 商品・サービスが魅力的か】これが始まりで、優れていれば知ってもらう事で
お客様に支持されて、儲かるというわけです。
サービス業なら前職での技術力やノウハウが軸になり、
世の中に無い商品であればその機能や効果など
商品力・権利関係が軸になるわけです。
【 何を売るかを決める 】、起業の第一歩です。自社商品を販売する独立開業の組織形態決定
この売れる商品・サービスがあれば、儲けが出ますから
次は儲けをしまう【 箱 = 組織 】を決めます。
この箱には、個人事業主 と 株式会社・合同会社など会社が大きく分けてあります。
個人事業主での独立開業の方法は、
・会社のように設立費用がかからない
・自分である程度できる簡単な帳簿で対応可能
というメリットがありますが、
・会社に比べ信用力が低く融資・採用に適さない
・利益が出た時に節税の幅が狭いというデメリットがあります。

一方、会社での独立開業の方法は、
・信用力があり融資や求人では有利
・利益が出た時、節税幅が広いメリットがありますが、
・登録免許税など設立費用の約25万がかかる
・帳簿が複雑なため自分では難しいなどデメリットがあります。
個人事業主 と 株式会社・合同会社など会社は、
メリットやデメリットが表裏一体のイメージで、
最初はそんなに売上がたたないかもしれないし、
いつまで続けるか分からないという場合には、
個人事業主にしておいた方がおすすめです。逆に、最初から前職のお客様などとの取引が
既に決まっている場合や資金調達・採用も
積極的に行うことが決まっている場合には、
株式会社・合同会社など会社がおすすめです。これらはどちらの方法・やり方が良いわけでなく、
経営観や人生観の問題ですので、
起業創業や独立開業される方の今後のビジョンと
あわせて決めるべきです。
資金調達は、どんな方法・やり方がおすすめ
自社の存在意義である商品・サービスは何か、
そしてその経営を行う組織(箱)が決まると
後はこれらを実現する資金の調達が必要です。
商品であれば材料・機械を買うための独立開業資金が
必要になりますし、サービスであれば人材や店舗確保に
一定量の事業資金が必要です。
事業経営は、雪だるま作りと非常に似ています。
小さい雪玉を大きい雪だるまにするには、
かなりの労力が必要になりますが、
ある程度、最初から大きい雪玉があると、 加速度的に大きい雪だるまになります。
これは資金が最初からある程度確保出来ていれば、
材料や機械・人材・店舗などで制約を受けないため、
仕事のオファーがあれば対応できるため
利益がでやすく、お金がたまりやすいことを意味し
資金確保が出来なければ、オファーが来ても
材料や機械・人材・店舗などで制約がかかり
一部受けられないということを意味します。
つまり商品力・販売力があっても、資金力がないため
事業展開にスピードがないという事になるわけです。

それでは起業創業や独立開業の資金調達は
どんな方法・やり方がおすすめかといいますと、
1 日本政策金融公庫の創業融資 2 各自治体の制度融資これらがおすすめです。
なぜなら、起業創業や独立開業はリスクがあり、
通常の銀行などの金融機関は担保などがなければ、融資対応しませんが、
上記2つは、国と自治体で経済活性化などの目的を有し、
起業創業や独立開業のリスクも考えてくれるからです。
匠税理士事務所の起業創業や独立開業支援
上記を決めれば、後は税理士などの専門家が
書類作成しますので、事業は開始できます。
起業創業や独立開業するには、どうすればいいか
色々考えると大変な感じがしますが、
お客様に喜んで頂ける商品・サービスで
【 必要な売上が上がればよい 】のです。組織形態や資金調達の選択や書類の作成は
専門家活用で簡単に済んでしまいます。
資金調達方法・やり方のポイントは以前に下記で
まとめましたので、こちらから確認下さい。
【→ 起業・開業の貯金や自己資金はいくらまで貯める、用意すべき?】
匠税理士事務所で、税理士以外も社労士や弁護士、
司法書士とチームを編成し起業創業や独立開業を支援します。
そのため会社設立の登記からその後の会計や経理、
給与計算や契約書作成、助成金や補助金対応などの
【起業に必要な全てがそろう事務所】です。匠税理士事務所の税理士やサービスは、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

創業融資は、世界4大会計事務所出身の税理士が
創業計画書の作成から面談立会いまでサポートし
【 融資成功率9割超 】の実績を有しております。サービス詳細はこちらから確認下さい。

匠税理士事務所の起業創業や独立開業向け
サービス一覧はこちらからご確認下さい。

匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資など独立開業支援を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
起業創業・独立開業のやり方とは?おすすめの資金調達方法につき最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
日本政策金融公庫(国金)や銀行からの融資・借入調達支援 (24/04/26)
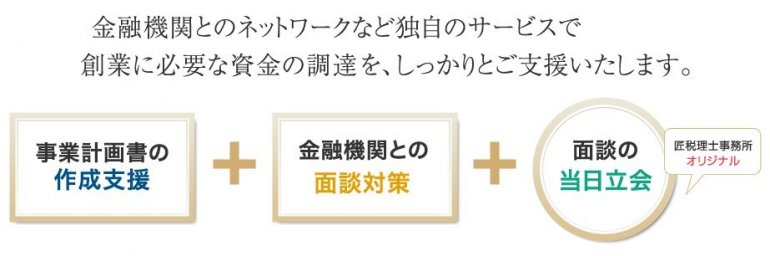
会社経営の重要な目的の一つは、
利益による資金の増加を最大化することです。
どんなに素晴らしい技術や人材があったとしても、
資金がなくなれば倒産してしまうため
金融機関と良好な関係は経営者の大切な役割です。
弊所は黒字化と資金調達を得意する会計事務所で、
利益戦略会議とキャッシュストック経営を軸に
1 儲かって、
2 お金が残る会社作りをお手伝いしております。
創業以来、起業と黒字戦略に専門特化し、
企業の成長期に必要となる適正な資金調達では
融資支援サービスを提供するなかで
サービスを研鑽し続けノウハウを蓄積して参りました。
資金調達の成功率は9割超と確かな実績で
多くの経営者様に選んで頂いているサービスです。
(※顧問契約お客様限定のサービスとなります。)
融資支援サービスの内容
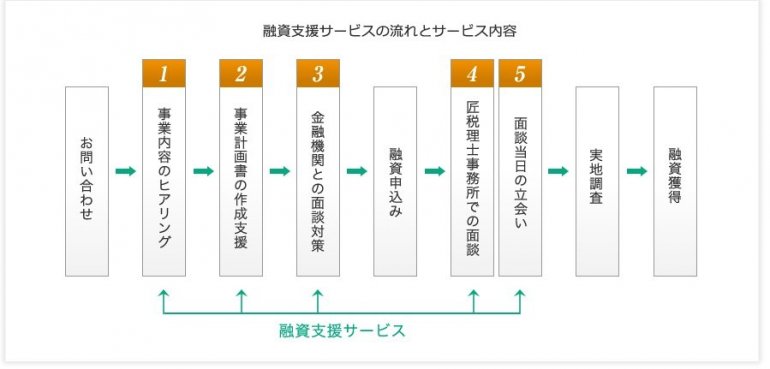 画像の拡大表示はこちら
画像の拡大表示はこちら
匠税理士事務所の融資支援サービスでは、
 まで行う「きめの細かいサービス」が特徴です。
まで行う「きめの細かいサービス」が特徴です。
日本政策金融公庫との連携により
特別に匠税理士事務所の会議室で面談を行って頂き
融資面談の当日は私共も立ち会います。
融資を利用する(資金調達の交渉)のポイント
融資では既に事業や会社を経営されている方を
既業者といいます。既業者は「事業の実績」があり
これまでの実績が評価の対象となります。
○金融機関の考え方
融資には色々な考え方があるかと思いますが、
金融機関の考え方は、非常にシンプルです。
1 何のために
2 幾ら必要で
3 返せるか
【 1と2は、借入れの目的です。 】
「赤字補填のために、資金5,000万必要」という
申請が金融機関に届いた時、どうでしょうか。
金融機関の審査担当者の気持ちなれば、
本当に返せるのかが、問題になります。
そして立派な事業計画書が届きます。
この計画書をみて実際にお金を貸すでしょうか。

一方、毎年最終利益で3,000万円程出ていて、
来年大型案件受注に備え一時的資金の不安定に対し
余裕をもって事前に5,000万借りたいケース。
どちらが、金融機関が好むか一目瞭然です。
金融機関はお金を貸し、利息で収益を上げるため
より手堅い案件に融資をします。
株主配当や決算公表しますから、
貸出した資金の回収不能を極めて嫌がります。
だから、晴れた日には傘を貸すが、
雨が降ったら傘を貸さないと例えられます。
これは金融機関の立場になれば当然ですね。
○資金調達で大切なこと
融資による資金調達で大切なことは何か。
それは融資申請のタイミングです。1 現在、黒字。(晴れている。)
2 現在、黒字だが、今後マイナスの要素がある
(曇るかもしれない)
3 回復の傾向にある。(曇りのち、晴れ)
この3パターンであれば、
資金調達はかなりの確率で成功できます。

反対に、
1 現在赤字
2 以前は黒字だったが、最近は赤字続き
このパターンを金融機関は嫌がります。
○設備資金と運転資金
匠税理士事務所では、決算書や試算表を確認し、
適時タイミングよく適切な融資を提案し、
資金を獲得できるようコンサルティングします。
適時タイミングよく事前に融資を利用することで
仮に何らかの外的環境要因で赤字になっても、
会社は既に資金が確保された状態となっており、
成功確率の低い申請の必要がなくなります。
また、適時タイミング、つまり黒字決算の時点で
申請しておけば利率など好条件を引き出せます。
融資成功率を高める判断材料を用意すべき
前項で記載の通り、金融機関へは返せるか
この資料準備というアプローチが大切です。
毎月の損益が会社の経営状況を正しくあらわすよう
会計設計し早期に損益を出さなければなりません。
◇融資成功には、何が重要なのでしょうか
お金を返せることを証明する資料だと考えます。
例えば黒字経営の状態であれば
決算書、会社の預金残高、退職金の積み立てなど留保型の生命保険など
今しっかりと儲かっていて、
お金をもっている事を証明できれば良いのです。
短期つなぎ資金であれば資金繰り表で、
- 何のために
- 幾ら必要か を証明するための資料です。
例えば1億円の工事案件を請け、5月に納品7月に
入金となるが5月までに原価相当の7,000万の
材料・外注費の先払いがある。
この場合、大規模案件の原価支払に7,000万円が
4月まで必要な事を資金繰り表で証明します。
そして、根拠資料として、
- 1億円の工事の請書・契約書と、
- 外注の工事原価の見積書を提出することで、
金融機関は 1 何のために 2 幾ら必要 かを
把握できるわけです。
ただ、使途と金額が明確でも、
貸したお金が返ってこなければ大問題となります。
だから資金繰り表を高い精度で作成したとしても、
ただ資金の用途の証明にすぎません。
こうした理由から金融機関はお金を返せることを
証明する資料を最重要に位置づけます。
毎月の経営会議や決算検討会では、
経営セミナー講師の世界4大会計事務所出身税理士が、今後の事業展開・業績の予測・獲得可能な資金総量を
的確にコンサルティングします。
サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
規模は年商2,000万~10億まで対応可能です。
匠税理士事務所はこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
ゴールは、儲かって、お金が残る会社作り
結果として、儲かっていてお金がある会社には、
お金が集まりビジネスチャンスが広がります。
これは、雪だるまを作るときに、
最初は小さな雪玉がある一定の大きさになると
加速度的に大きくなることに似ています。
最初の創業融資では、上限1,000万円ですが、
黒字経営で会社の財産が増える度に融資の枠も
大きくなり加速度的に会社が大きくなるわけです。
ここで借入金が増えることはよくない。
という考えもありますが、
・預金残高 1億円で、借入金1億円の会社
・預金残高100万円で無借金会社
どちらが経営的に安定しているでしょうか?
答えは、預金残高1億円で借入1億円の会社です。
万が一納品トラブルで入金が遅れる事態が起きても
1億円の現金があれば運転資金には困りません。
また、大型案件の受注チャンスがきても
お金の心配することなく受けられます。
だから、儲かっている会社を作って、
お金がたまるようにすることは重要なのです。
借入金の金利 < 事業の利益率と考えると、
借入を上手に活用しお金を上手にコントロールし
会社の成長が加速するのです。
このように会社の成長には、
1 儲かって、
2 お金が残る会社作り が重要と考えてます。
匠税理士事務所では、会社成長期のポイントは
1 利益が出るように仕組みを作ること
2 黒字化ができれば、随時資金調達で内部留保
3 資金を活用して、より利益を上げる
これが【 王道 】だと考えております。
◇匠税理士事務所の融資支援サービスの特徴
- STEP1 資金計画表の作成コンサルティングにより必要な資金額と理由を確認します。
- STEP2 融資支援サービスにより事業計画書や面談対策を行います。
- STEP3 キャッシュストック経営の考えのもと、資金調達が必要のない体質をつくります。
- STEP4 黒字経営を必達し、返済資金を捻出するため利益戦略会議で黒字経営を継続します。
上記、STEP1から4で会社のお金に対する体質を変えていきながら、強い会社を作り、かつ成長期には思い切って資金調達を実施します。STEP1とSTEP3、STEP4まで包括的に行うことが弊社の特徴です。
融資サービスは、創業融資支援サービスと同じ内容となりますので、ご参考にしていただけましたら幸いです。
◇コンサルティングサービス
こちらのページでは、融資を利用するにあたって経営者の皆様に知っておいていただきたい点について記載致します。融資をご利用予定の経営者様は、是非ご一読ください。
執筆者・文責:税理士 水野智史
◇経営とお金の情報館
匠税理士事務所は税理士の直接対応にこだわる会計事務所です。 (21/06/13)
匠税理士事務所は、【 税理士が窓口担当 】となり、
お客様の税務・経営のご相談を承ります。
当たり前のことのようですが、
税理士と直接何年も会ってない・・という理由で
弊所に変更される社長様が多いのも事実です。
この仕事の仕方は、2008年事務所を設立してから
これまで継続し、今後も変えることはありません。
税理士の直接担当にこだわる理由
お客様である経営者の方のご相談は、
【売上】・【お金】・【人】・【法務】・【税務】 と多岐にわたります。
このような悩みに対応するためには、
税務に加え、実際に自身が経営者であり、
お客様のお悩みを理解し対応を一緒に考えることが
重要であると考えているからです。
お客様のご相談内容は、税理士が対応しますので
税務会計はもちろんですが、
・得意先とトラブルになった場合の法務相談
・従業員ともめた場合の労務相談
・商標権や意匠権などの権利関係の相談などにも
提携弁護士や社会保険労務士、弁理士と連携し
お客様が安心し本業に集中できるようサポートします。

派手なことよりも、当たり前を当たり前に
また、事務所の仕事の方針として、
派手なことをやるより、
【当たり前を当たり前にする】を大事にします。【当たり前とはお客様の約束を必ず守る事です。】
話をしていた仕事の進め方や打ち合わせの仕方、
仕事の納期などは必ず守ります。
逆にこれらが守れなくなるような
無理なご新規の受注は行わず、
既存のお客様の満足度・お約束が守れる事務所であることを最優先としております。
小さい事務所だけど、いい事務所といわれるよう
今までもこれからも取り組んで参ります。
人材の質でNo1の会計事務所を目指します。
お客様から安心してお仕事をお任せ頂けるように
人材のレベルには徹底的にこだわり、
優秀な人材で構成した会計事務所を目指します。
採用基準から社内研修などへこだわりから、
世界4大会計事務所出身の税理士が現場を統括し 仕事内容・情報を把握し、品質にこだわります。サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
規模は年商2,000万~10億まで対応可能です。
匠税理士事務所はこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の概要 】
最後までお目通し頂きありがとうございました。
経営者が現場にいる会社と現場と乖離し距離ある会社 (20/11/14)
経営者が現場にいる会社と乖離し距離ある会社。どちらが良い業績を上げられるでしょうか?
この質問に対し色々と考えはあると思いますが、
経営者が現場にいる会社ではないでしょうか。
そもそも経営とは何か
経営とは、
1 商品・サービスの開発・改善
2 販売・営業活動
3 生産・供給活動
4 資本・財務
5 人材
この5つの要素のバランスを見極め、
時代の流れを読んでどこに今は比重をかけるか という司令塔のような仕事だと考えます。
そうなると、この5つの要素をバランス理解し、
時流を読み的確に判断する必要があるわけです。
現場主義の経営者だからできることとは
現場主義の経営者の会社は、業績が良いです。例えばお客様からのクレームが現場にいれば、
すぐ耳に入り、商品開発・改善が迅速に行えます。
販売先選定も、どのチャネルからのお客様が
会社にとって良いのかもよく見えます。
また、外注先の仕事を見るだけで、
自社の得意先を満足させられるか、
お客様に迷惑をかけないかもすぐ判断できます。
現場でないと分からない事が多いのです。
リーマンショック・コロナ禍など危機こそ現場へ
リーマンショック・コロナ危機など有事の時こそ、
これまでの常識が非常識になり、
これまでの戦い方が通用しなくなるため、
いち早い迅速な判断が求められるます。
そこで会社で一番優れた人材が先頭にいることで、
これらの判断が可能になりますし、
社員の士気も大きく上がります。
例えば前回のコロナ危機でも、
資金調達を早々に対応している場合は、
比較的調達が容易にできていましたが、
段々と難しくなってたのではないでしょうか。
経営者が現場にいれば対応策はすぐ浮かびます。
どれ位の資金調達すべきか判断も早くなります。
一方で現場と乖離し距離ある会社は
こうした判断が難しくなります。

また、お客様のニーズ・客層の変化なども
現場にいることで多くのことが分かります。
変化の時代は、チャンスの時代でもあります。
この危機こそ現場に戻ることで、
チャンスをつかめるのではないでしょうか。
実際、コロナ後に急成長した会社の特徴として
・現場主義の強い経営者がいる
・コロナ融資等で低金利で大量の資金を獲得した
こうした共通項があります。
匠税理士事務所の経営支援
弊所では世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 【お客様の会社に利益とお金を残すこと】を理念に経営支援に取り組んでおります。
サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
規模は年商2,000万~10億まで対応可能です。
匠税理士事務所はこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

【 サービス 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
危機の中で生き残るための経営対策 (20/10/10)
これまでも、バブル崩壊、リーマンショックや
コロナなど様々な危機がありました。
今後も様々な危機が起き、
大きな影響が出てくることがあると思います。
それでは危機の中で企業がすべきことは
何でしょうか。
色々とあると思いますが、
【 生き残ること 】だと思います。
企業には、お客様、社員の方とその家族、
経営者とその家族と様々な人が絡んでいるので
生存は、企業にとって最優先課題となります。そのため、
1 資金調達を再優先で、限度額まで検討する
2 各種支援制度を活用する
3 環境の変化を見極め、自社の勝負所を決める
が重要になります。

危機で優先すべき手は資金調達などの守り
資金調達など守りを最優先にするのは、
生き残ることが最優先だからです。
企業は一時的な赤字ではつぶれません。
赤字が続けばお金がなくなり、給与が払えず、
業者さんの支払ができず取引が出来なくなり、
つぶれてしまいます。
つまり、資金が底をつきるとつぶれます。
これを避けねばなりません。
だから、まず有事に行うべきは、資金調達です。
実際に、危機的な状況が数十年も続くことはなく
現時点では資金調達をしやすい環境にあります。
景気には必ず底があって、回復の傾向に入ると
いうことをこれまで繰り返していますので、
そこまで持ちこたえるために、
資金調達を行い時間を稼ぐ必要が出てきます。例えばコロナ危機の際は、コロナ融資は無利息で
返済期間も長いという破格の条件となってました。
こうした制度を活用し時間を稼ぎます。
同時並行で、返す必要がない補助金や助成金などの支援制度をフル活用しましょう。
これは意外に忘れられがちです。
【 まずはこれらで守りを固めます。』
守りを固め、どのように本業を立て直すか
資金調達や給付金などの制度を活用した後は、
景気が戻るまで、固定費を削減するか、
売上確保の攻めにでるかという流れになりますが、
固定費削減は、何でも削ればよいわけではなく、
必要なものは残し、不必要は削るという視点に、
【削ったものが再生可能なものか否かという視点】を持つことが重要です。
車などのモノはまた買うことはできますが、
優秀な人材は急には育ちませんし、
再び採用できるかはわかりません。

再生不能な経営資源は何とか残しておかないと、
売上を伸ばすときにブレーキになりかねません。
売上を伸ばしていくには
これは今後どのようなニーズが起きて、
どこにお金が集まりそうなのかを把握し、
その中で自社の強みをどのように活かすかを
見極めた上で攻めるという流れとなります。
危機の際には、底がみえていないため
誰もが不安な状況ですが、
世の中に人が存在する以上、人の役に立つことで、 売上はあがります。実際にコロナの際は運送業の方は、
人が外出せず欲しいものを届けることで、
売上を伸ばされており、
欲しい商品と人を結びつける
IT企業も伸びています。
これまでとは違った形で、
【 自社の強みを活かし人の役に立てないか 】を考えると活路が見いだせるかもしれません。
自社の勝負する路が決まれば、
より多くの方に知ってもらう活動となります。
つまり販売促進・営業です。これは知ってもらう努力な何でもする。
WEB・SNS・広告・DMなど費用対効果が高いものに
より多く投資をし効果を出すという流れです。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 匠税理士事務所は経営支援に取り組んでいます。匠税理士事務所サービスはこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
【 関連記事 】
【 サービス 】
デザイナーやコーディング(コーダー)などIT業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方 (19/06/02)
匠税理士事務所のホームページへの
ご訪問ありがとうございます。
弊所はデザイナー・クリエイティブ業・IT業に特化した
税理士が所属する会計事務所で、
今回はクリエイティブ事業のお客様から多く相談を
頂きます源泉所得税の考え方・計算方法と納付書の
書き方を分かりやすくまとめてみました。
源泉所得税の考え方・計算方法とは
まず源泉所得税とは、会社から個人の外注先に
100,000円を支払うとすると、
仕事の内容によっては、
100,000円 × 10.21% =10,210円を
外注先から徴収し、89,790円のみ外注先に支払い
10,210円は会社が源泉税を納付する制度です。まとめると以下のような表になります。
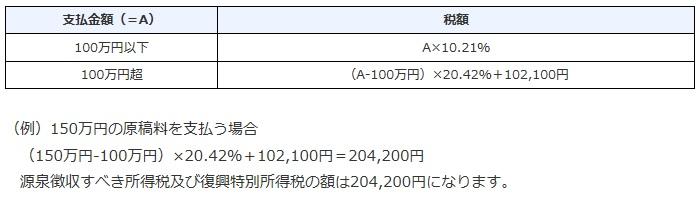
なお、ここでポイントになるのは、
相手先が株式会社や合同会社などの法人なのか、
個人事業主かで源泉税の扱いが変わることです。
【源泉徴収の必要性】
外注先が株式会社や合同会社など法人である場合
【源泉徴収の必要はありません。】 外注先が個人事業主である場合 【源泉徴収が必要と不要な場合があります。】(仕事内容で源泉の必要有無が分かれます)
デザイナークリエイティブ、IT業で源泉所得税が必要とされる仕事の範囲とは
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の
源泉徴収の対象となる範囲は、
法律で以下のように区分されております。
逆に言うとここで列挙されていないものは、 原則、源泉徴収の必要がないことになるのです。 1 原稿料や講演料など2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、テニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5 芸能人や芸能プロダクションを営む
個人に支払う報酬・料金
6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、
客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆる
バンケットホステス・コンパニオンやキャバレーに
勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を
約することにより一時に支払う契約金
8 広告宣伝のため賞金や馬主に支払う競馬賞金
デザイナー・クリエイティブ業・IT業に関係するのは、
上記1号の原稿料業務(デザイン報酬・著作権使用料))
などデザイナー報酬が源泉徴収の対象になります。
逆に、要件定義、システム設計やプログラミング、クライアントなどとのディレクション、 HTMLやCSS、Javatといった言語を使用した コーディング、環境テスト等に関する報酬は、 こちらに規定されていないため、 源泉徴収の必要がないということになるのです。
デザイナークリエイティブ、IT業の源泉所得税の計算方法
個人の方に外注費を支払う場合で、
上記の源泉徴収対象になる内容の場合には、
所得税を天引きして納税する必要がございます。
それでは、源泉税の計算方法及び納付書記載方法は
具体的にはどのようになるのでしょうか。
1.源泉所得税の計算方法について
① 外注さんから消費税について請求されていないケース ( 請求書で消費税が区分されていない場合 )
・外注費 100,000円(消費税込み)
・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円
・支払額 100,000円-10,210円=89,790円
② 外注さんから消費税について請求されているケース ( 請求書で消費税が区分されている場合 )
・外注費 100,000円(消費税抜き)
・消費税 100,000円 × 10%=10,000円
・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円
・支払額 100,000円 + 10,000円 - 10,210円
=99,790円
※原則、税込額に10.21%をかけ天引きしますが、
請求書で報酬と消費税が明確に区分されてれば、
税抜金額に10.21%とすることも可能です。
納付書の書き方と納付方法
外注さんからお預かりした源泉税は、
支払った月の翌月10日までに納付書を作成して、
銀行または郵便局で納付する必要がございます。
例:6月30日に外注さんにお支払いした場合には、
7月10日が納期限となります。
納期限より一日でも過ぎてしまいますと、
不納付加算税や延滞税などペナルティを負担する可能性がありますので注意が必要です。
ちなみに不納付加算税は、原則納付額の10%です。
納付書の書き方は次のようになります。
なお、こちらは書き損じがあると金融機関などへ
持参しても納付できないことがございますので、
最低限必要な記載事項に留めてます。
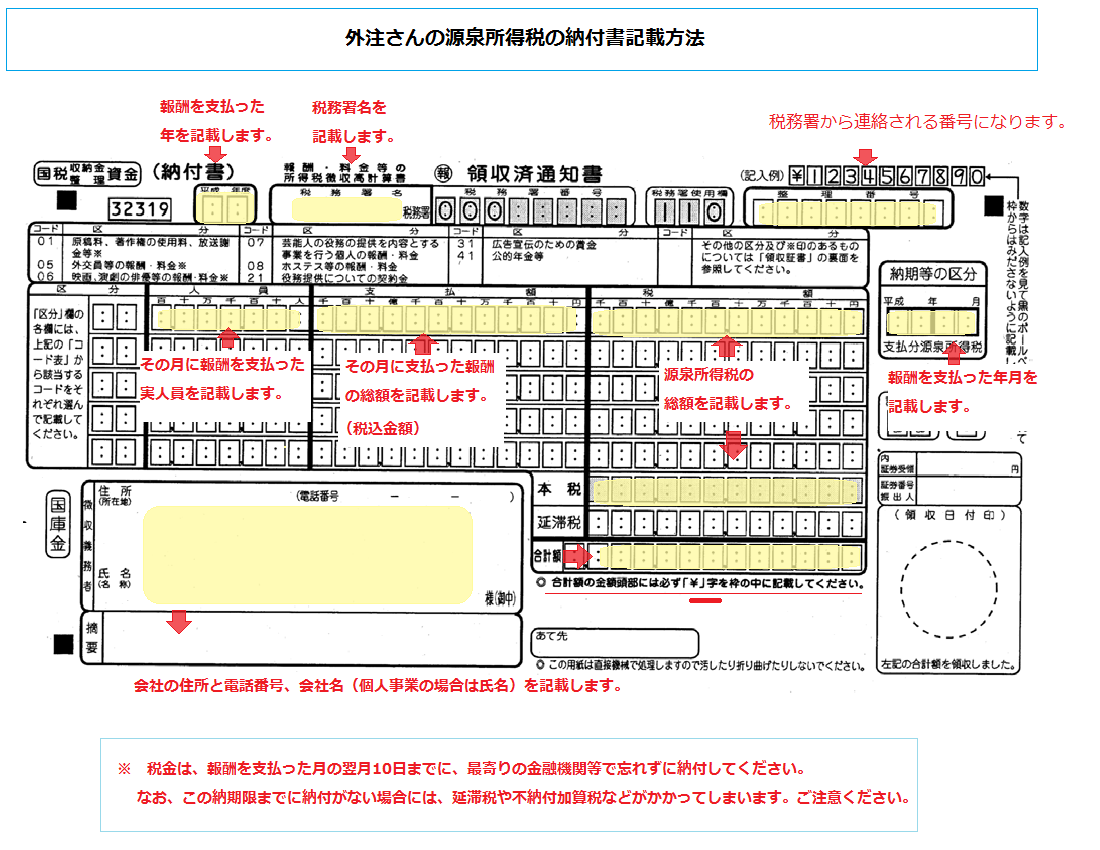
IT業界が得意な税理士・会計事務所は匠税理士事務所のサービス紹介
目黒区という土地柄、IT事業を経営されている
お客様とのお付き合いが多くIT業の税務や
経営コンサルティングの事例が豊富です。
匠税理士事務所の税理士は、40代です。
IT事業は、日々変化を遂げている事業のため、
若さと経験値が大切かと考えております。
IT分野で事業をされてる方、IT分野で起業、創業を
ご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所サービスはこちらから

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
◇IT事業を経営されているお客様向けサービス
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
IT業界で株式会社・合同会社などの
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
これからIT業で起業をお考え方にむけた
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
デザイナーやコーディング(コーダー)で独立開業の方に
会計経理や税務申告、経営支援などの
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人IT業から会社に組織変更するための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#デザイナー源泉所得税
#源泉所得税
起業時の販売戦略-粗利の低い商品を加味した商品構成 (19/05/31)
起業支援を専門とする匠税理士事務所の
ホームページへのご訪問ありがとうございます。
こちらのページでは、起業時の商品構成など販売面での経営お役立ち情報について記載しております。
起業後の経営で注意をすべき販売戦略

経営者は常に市場から受け入れられる商品やサービスを見つけて
経営上理想の商品は、【 粗利が高い商品 】 です。
つまり「高い売価」で「原価の抑えた商品」です。
通常の販売活動は、粗利が高い商品の販路や得意先を確保することが重要です。
ここで問題となることは、どの会社にも
【粗利が低い商品】が必ず存在することです。
粗利率の低い商品にどう取り組んだ商品構成にすべきか
この粗利の低い商品は、
【 会社に貢献していない商品 】 でしょうか。この問題を議論する前に、
確認しなければならない点があります。
それは粗利の求め方です。

粗利とは、
売上から原価を差し引いて求めます。
→商品を仕入れて売る会社様であれば、
商品の仕入代金が原価となります。
→サービスを売っている会社様であれば、
人件費・外注費の作業時間が原価となります。
→物を作って売っている会社様であれば、
材料の仕入に外注・人件費が原価となります。
この粗利だけに注目すれば、
会社の業績が良くなるという結論に至ります。
しかし、この考えは必ずしも正しいと言えません。
例えば、起業間もない会社が、
粗利の低い商品の販売を中止したとします。
起業間もない会社は得意先の数も、
販路も安定していません。
この状態で粗利・合理性のみを追い
粗利の低い商品の販売を中止してしまうと
経営が急激に不安定になりがちです。
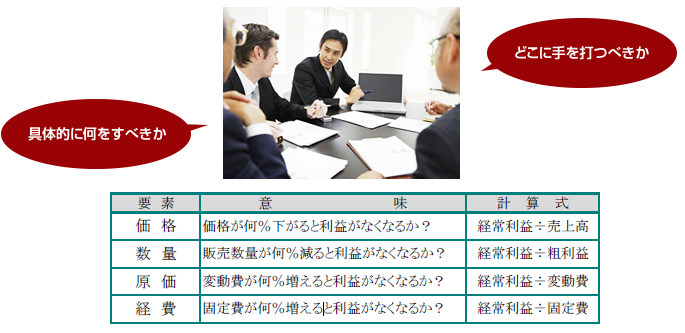
つまり、粗利の低い商品の販売を中止したときに
①その商品を販売中止にしたときに、
毎月の経費に見合う他の売り上げがあるか
②その商品を買うことで知り合えたであろう
見込み客へのアプローチを他のアプローチできる
ような市場や販路が確立されているか
③粗利の高い商品を購入してもらうために
充分な環境が完成しているか

このような問題をクリアして商品構成を決定しないと
起業時の経営は大きくバランスを崩してします。
値引きと粗利率の高低を組み合わせた商品構成は違う
粗利率の高低を組み合わせた商品構成は
値引き販売とは違います。
元々粗利の低い商品を作り、得意先や販路、
市場での情報収集が完了した段階で
粗利の高い商品へシフトするための商品戦略です。
値引きすると売価は中々戻りません。
それは本来の価値が幾らか不明になるからです。起業時の販売戦略には、起業時にあった戦略を
使用することも方法の一つです。
匠税理士事務所の起業や独立・開業支援
匠税理士事務所は、起業と黒字戦略に専門特化した会計事務所です。
お客様のお役に立てる事務所であるためには
【人材の質・サービスの質】が重要と考えます。
当会計事務所の税理士やサービスはこちらから

【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
目黒区や世田谷区、品川区などで税理士をお探しの方はご相談下さい。
(関連記事:売上総利益・粗利を決める売価決定の重要性)
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・起業支援を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
法人化や法人成りによる消費税の免税や節税対策 (19/04/19)
個人事業を何年かやって事業が伸びてきたとき、
株式会社や合同会社にする法人化・法人成りを検討する方も多いと思います。
法人化で節税対策の幅が広がることや、
取引先の信用UPなどメリットも考えられますが、
そのメリットの中でも大きなものが、法人化の消費税免税による節税効果です。そこで今回は、法人化や法人成りをした場合の
消費税の免税による節税効果につきまとめます。
【2023年10月開始のインボイス制度・2割特例も解説】

消費税義務は次のような場合に原則発生します。
個人事業者の場合・・・・・・原則として前々年の課税売上高が1,000万円を超えた方
株式会社や合同会社の場合・・原則として前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えた方
個人事業の消費税を納める義務の判定イメージ
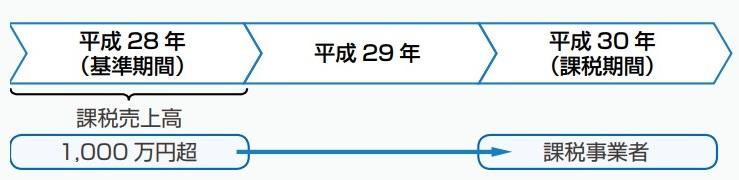
会社の消費税を納める義務の判定イメージ
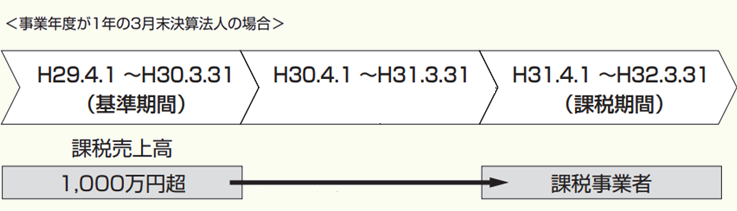
※引用国税庁
※基準期間.個人事業者の方は課税期間の前々年をいいます。
※課税売上高.消費税が課税される取引の売上金額
つまりは、2年前の課税売上を軸に消費税を納める義務があるか否かの判定を行います。
そのため、前々期の課税売上高が1,000万円以下の場、原則消費税義務がない免税です。
ちなみに消費税を納める義務があることになると、
1 売上でお客様から預かった消費税
2 仕入で業者さんへ支払った消費税
3 納付すべき消費税(=1-2)
で計算した消費税を納めなくてはなりません。
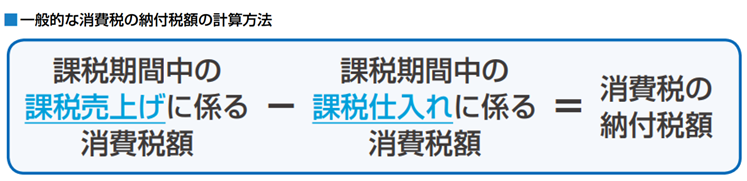
この本来納めなくてはいけないお客様から預かった消費税と払った消費税の差の上記3の消費税が、
納める義務がない場合は、手元残ることにとなるので節税効果が生じます。
法人化の消費税免税の節税効果とはこのことです。なお、基準期間のない事業年度でもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、
1,000万円以上である場合など、注意が必要な部分もあります。詳しく解説していきます。
法人化や法人成りでの消費税免税の仕組みと節税効果
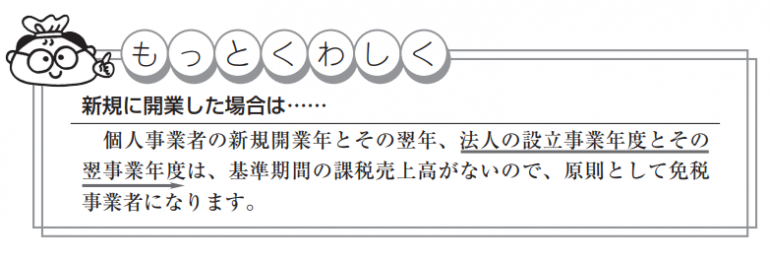
法人化や法人成りでの消費税免税の仕組みと節税効果は次の通りです。
個人事業主が株式会社や合同会社を設立し、法人化することで、
「会社」という固有の権利と義務が、個人とは別に生まれます。
つまり自分以外の第三者誕生というイメージです。個人と株式会社や合同会社などの会社では全くの別人格ですので、
そもそも会社設立後の第1期と第2期については、
消費税の課税事業者の判定に際して用いる「基準期間」が存在しません。これにより、法人化前の個人事業主のときに、消費税の免税事業者であったか否かに関わらず、
会社として消費税が免税となる期間(節税可能期間)が新たに生じます。
こうした制度を活用し、個人事業の創業後、事業規模が大きくなった段階で法人化すれば、
【 1 個人事業の創業時の2年間(第1・2期)に加えて、】 【 2 法人化後に最長でさらに2年間 】、 最長で4年間ダブルで消費税の納税義務の免除による節税効果が得られます。
<例>個人事業時代に2年間免税で節税をして、
X1年からはじめて消費税を納めることになった個人事業主の方が、
X2年から株式会社に法人化・法人成りの場合。
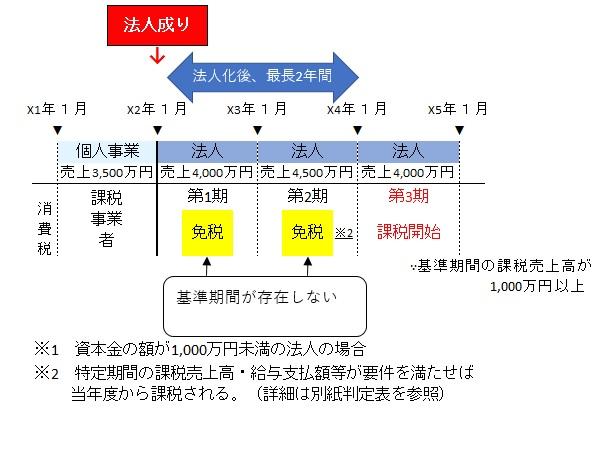
法人化や法人成りで消費税免税の節税を考えるなら資本金と給与にも注意
法人化による消費税免税節税は注意点があります。
<1>設立時の資本金
<2>給与の設定
簡略化したものとなりますが、どのようなことなのか解説していきたいと思います。
設立時の資本金について
新しく作る会社の資本金を1,000万円以上にして設立してしまうと、
本来消費税を納めなくても良いという免税制度を活用した節税ができなくなってしまいます。
事業年度開始の日で判定されるため、作った後では遅いため十分な注意が必要です。
具体的には、事業年度開始の日の資本金が1,000万円以上の場合、設立一期目から、消費税を納める必要があることになります。
法人化には、会社設立コストもかかりますから、
新設会社の免税(消費税を納めなくてもよい)期間による節税は上手く活用したいところです。
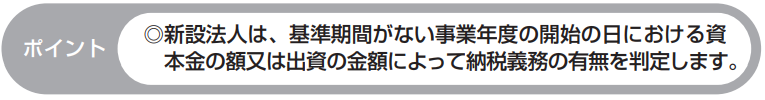
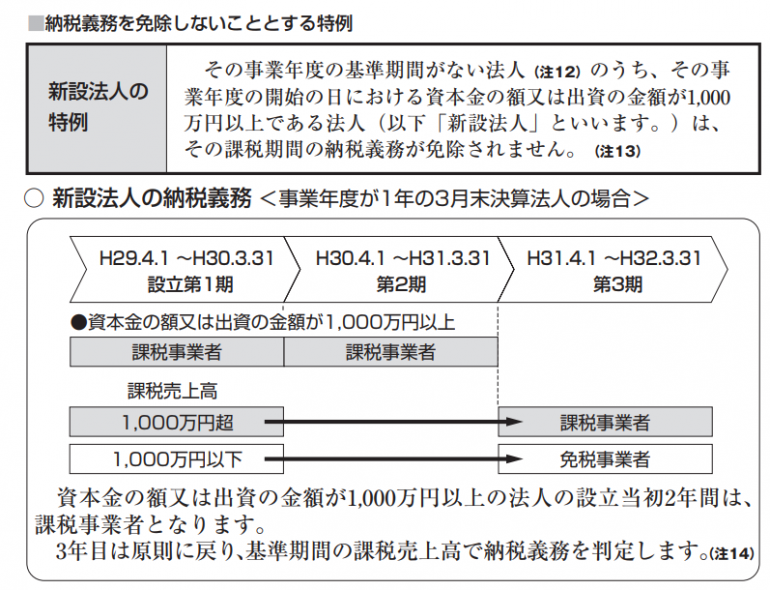
消費税の改正により新たに加わった免税による節税の論点
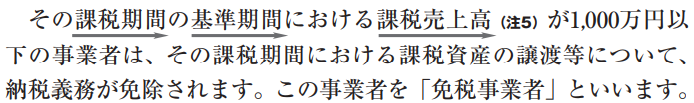
これまでは、上記のように資本金にさえ注意すれば設立1期目と2期目は、
消費税の免税(おさめなくてもよい)という節税ができました。
注意が必要になった消費税の免税による節税
平成23年改正で上記消費税の納税義務判定に加え、
1.基準期間(前々期)における課税売上高が1,000万円以下であった場合、通常は免税となりますが
2.特定期間の課税売上高(又は給与等支払額の合計額)が1,000万円を超えた場合
当課税期間から課税事業者となるという要件が追加されました。
特定期間
1 個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
2 法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
つまり、前年度の半年の課税売上が1,000万円を超えてしまうと、原則として消費税の納税義務が出てしまい
第1期は前年がないからよいわけですが、
第2期からは、ここに気を付けないと消費税を納める必要が出てくるわけです。
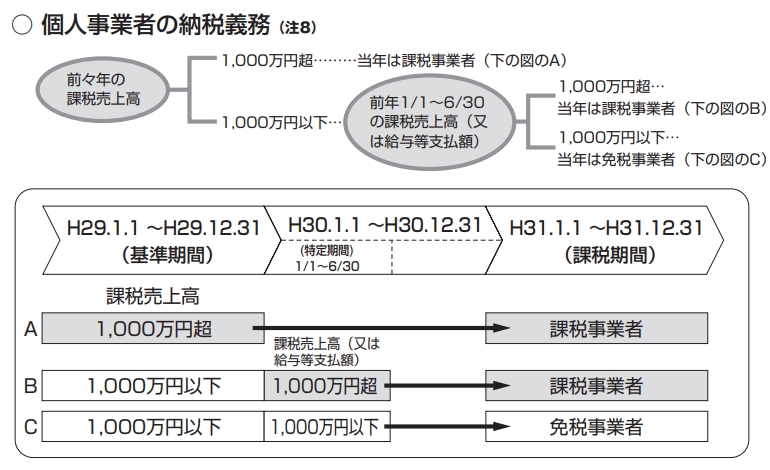
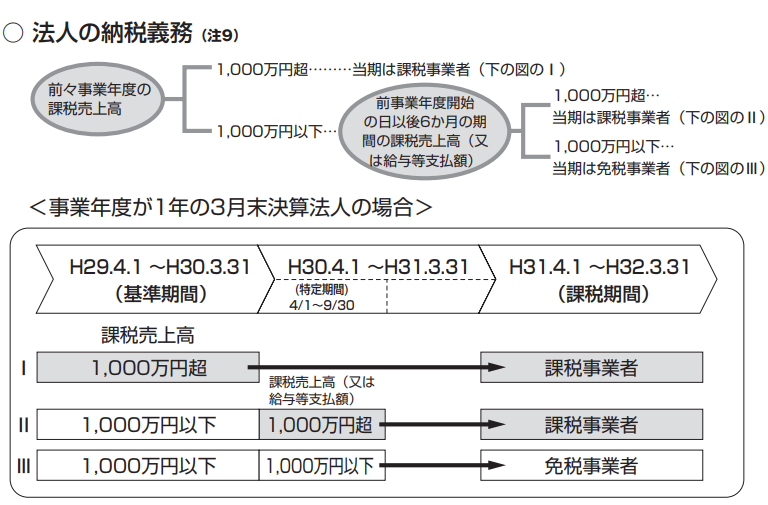
こちらにつきましては、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)掲載 「消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)」が
免税による節税が可能かわかりやすいため、下記に引用しております。
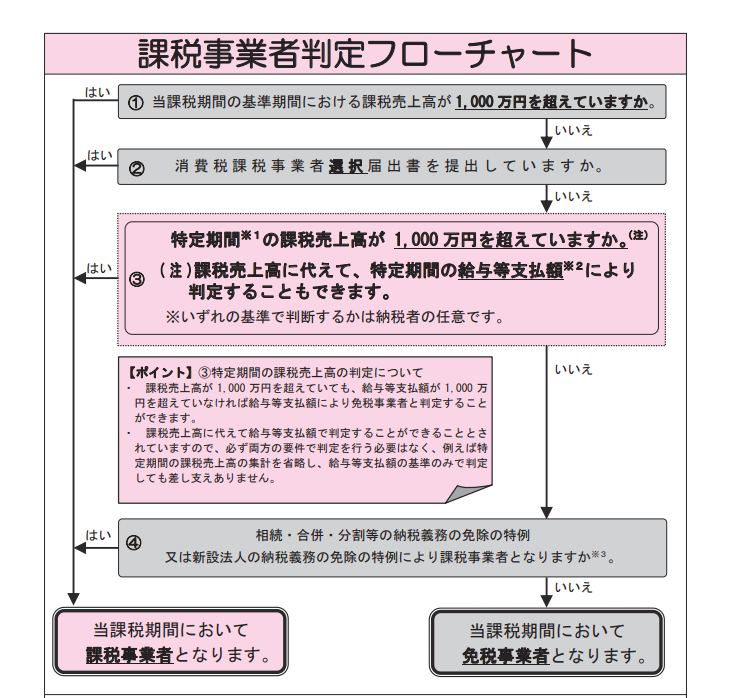
つまり、資本金を1,000万円未満にして免税による節税を考えても、更に以下のポイントがあるというわけです、
法人化で消費税免税の節税を考えるには、給与設定のタイミングも大切
法人化される場合には、課税売上金額が半年で1,000万円を超える方も多いのではないでしょうか?
そのような場合に重要になるのは、初年度の役員給与やスタッフさんの給与設定です。課税売上金額が半年で1,000万円を超えても、
給与等支払額が1,000 万円を超えていなければ、
給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

なお、課税売上高に代えて給与等支払額で判定することができることとされていますので、
必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、
例えば特定期間の課税売上高の集計を省略し、給与等支払額の基準のみで判定も可能ですので、
あまり人員を必要としない事業の場合は、こちらをうまく活用し消費税免税による節税を考えてもよいのではないでしょうか?
課税売上金額も給与の調整も難しい場合には1年目を7か月以下に
法人化・法人成りで消費税免税で節税したいが、特定期間の課税売上金額は1,000万円を超えてしまうし、
給与についても人を多く雇用する業種であるため1,000万円超えてしまうという場合には、
法人設立設立時において初年度の期間を7ヶ月以下にすることで、 短期事業年度となる前事業年度は特定期間とはならないとされています。この場合の特定期間判定が無くなるのではなく、特定期間判定をする時期が前々事業年度に移行することになり、
新設法人の場合は前々事業年度が存在しないので、特定期間での判定は必要なくなり、
少し短い第1期目と第2期目まで消費税免税による節税を行うということも検討すべきです。
このように売上も給与も多額になりそうな場合には、1期目を7か月以下にすることで、
約1年半の消費税免税で節税効果をうけることを検討してみても良いかもしれません。
消費税免税とインボイス登録・2割特例
2023年10月からインボイス制度が開始しました。
インボイス(適格請求書発行事業者)が開始される前は
上記免税制度を活用して節税対策が主流でした。
しかし、最初から大手と取引が決まってる場合は、
インボイス(適格請求書発行事業者)登録していないと
商取引に支障が出る場合も出てくるため、
かなりの割合の方が本来は上記制度で免税ですが、
インボイス(適格請求書発行事業者)登録することで
免税でなく消費税課税事業者を選択されます。
このように本来免税なのに消費税課税で酷なため
救済措置的な制度としてあるのが2割特例です。

インボイス制度を機に免税からインボイス発行事業者で
課税事業者になった方は仕入税額控除の金額を、
特別控除税額(売上消費税8割相当)とできます。
結果、売上消費税の2割を納付し終了という制度です。
消費税免税に比べて2割のみ納付が出ますが
ほぼ免税に近い効果で、インボイス登録できるため 得意先にも迷惑をかけない制度で現在主流です。但し、2割特例を適用できる期間は、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
将来法人化したい方はチャンスかもしれません。
匠税理士事務所の法人化や法人成り支援サービス
【 法人化・法人成りに必要な全てがそろう税理士事務所 】をコンセプトに、匠税理士事務所では個人事業主の方に向けて法人化や法人成りのご相談を承っております。
・株式会社や合同会社にしてみたいが、消費税免税の節税などやデメリットを聞きたい。
・法人化のラインや消費税免税の節税以外にも、社会保険など自分の業種はどうなのか知りたい。
このようなニーズにお応えするための相談会も行っております。

消費税免税など節税に関する法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
また、実際に株式会社や合同会社を設立された場合には、消費税免税の節税以外にも
資本金は幾らにするのか、決算期はいつにするのかという会社の基本設計を一緒になって考え、
登記の代行から社会保険加入手続き、経理の代行から税務申告まで承っております。
法人化・法人成りをご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
【 → 世田谷・目黒・品川など東京での法人化・法人成り 】◆消費税の免税以外にも法人化による節税効果は他にもあります。
詳細はこちらからご確認をお願い致します。
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリット 】
◆法人化や法人成りについての情報を掲載した情報館のバックナンバーはこちらです。
◆法人成り以外のサービスや料金などにつきましては、こちらからご確認をお願い致します。
【 → 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】※引用国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-06
上記コンテンツは、参考情報としてご覧いただいております。
消費税免税や節税情報の取り扱いや免責事項などをご確認の上、ご利用ください。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
法人化や法人成りを行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
起業・創業も使える小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行 (19/03/14)
匠税理士事務所では起業や創業支援に力を入れております。
スタートアップ企業の生命線は資金調達であるため、以下の方面での資金調達にも注力しています。
1 日本政策金融公庫など金融機関による迅速かつ確実性の高い【 創業融資による資金調達 】 2 将来返還不要の【 各種補助金制度による資金調達 】世田谷区や目黒区、品川区など東京都での創業融資による資金調達実績では、
世界4大会計事務所出身の税理士が高度な専門性を駆使し、トップクラスの実績を誇っております。

創業融資などの支援で起業されたお客様より、
「 起業時や創業時でも使える補助金はないでしょうか。」 とご相談を頂くことがあります。
回は、起業・創業も使える小規模事業者持続化補助金についてまとめます。
小規模事業者持続化補助金とは、起業家も使える補助金制度
小規模事業者持続化補助金とは、どんな制度の補助金なのかといいますと、
小規模事業者等が、販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する補助金制度です。WEB制作や販促用のチラシ・パンフレットの作成、生産性の向上に資するソフトウェアなどが対象になり、
PCやオフィス用品といった汎用性がある設備投資は対象にはならないという補助金です。
このように起業や創業時に一定の要件を満たすような設備投資など経費の支払いを行った場合には、
その一部を補助金事務局に申請し、承認されれば補助してもらえるという制度です。
創業融資(借入)との違いは、補助金は借入と異なり返済しなくてよいということです。
上手に活用できれば、起業成功のアドバンテージになることは間違いありません。
 【 小規模事業者持続化補助金の制度内容 】
【 小規模事業者持続化補助金の制度内容 】
【 補助上限 】
[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円 ※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ賃金引上げ枠
→ 販路開拓の取組に加え、事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上である小規模事業者
卒業枠
→ 販路開拓の取組に加え、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超え事業規模を拡大する小規模事業者
後継者支援枠
→ 販路開拓の取組に加え、「アトツギ甲子園」においてファイナリストに選ばれた小規模事業者
創業枠
→ 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
インボイス枠
→ 免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者として登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者
【 補助率 】
2/3 ( 賃金引上げ枠のうち赤字事業者は 3/4)【 対象経費 】
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費
上記を読むと複雑な感じがしますが、専門家を活用するとほとんど代行してもらえますし、起業時や創業時は、売上確保のためHPや名刺、パンフレットの作成など販路開拓等がかかせません。
そのため、これらのための初期投資として大きな経費・費用の支払いが出ても、
国などから補助してもらえるは、創業時の資金調達手段として効果的です。
そのため、このような小規模事業者持続化補助金を活用するのは起業成功に重要なのです。
創業時の小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行
匠税理士事務所では補助金申請に特化した専門家である中小企業診断士・行政書士と連携し、
小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行を承っております。
補助金について興味があるので、制度について話を聞いてみたい。という方もお気軽にご相談ください。
中小企業診断士が丁寧にお客様の事業内容などをヒアリングし、
補助金の要件をクリアできそうか否かをコンサルティング致します。
補助金の要件をクリアできそうな場合には、補助金申請書類の作成代行も承っておりますので、
小規模事業者持続化補助金の申請から採択までをしっかりとサポート致します。
だた、補助金には特有のデメリットがあり、こちらを理解した上での検討が重要です。
匠税理士事務所では、お客様の利益がしっかりと確保できそうにない場合には、 補助金申請をお勧めしないようにしております。
設備などモノやサービスへの投資に対する補助の補助金の申請、
人材の採用や育成の助成制度である助成金の申請代行
の詳細は、下記の各サービスページをご確認ください。
◇補助金サービス(設備などモノ)
【税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
◇助成金サービス(人材の採用や育成)
【税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
◇会社概要
◇TOPページ
世田谷区や目黒区、品川区など東京を中心に起業や創業支援に定評がある会計事務所です。
<各種補助金別のサービスへのリンク>
② IT導入補助金
<中小企業が生産性向上を目的に、業務効率化やDXに向けITツール(ソフトウェアやアプリケーション、サービス等)の導入を支援するための補助金>につきましても、お気軽にお問い合わせください。
建築士・設計事務所の会社設立・起業創業・独立開業は匠税理士 (19/03/14)
建築士・設計事務所で新たに会社設立したい方へ
弊所では、起業や創業の支援を行っております。
こちらは、これから会社をつくり法人で起業を
お考えの方に向けたコンテンツとなります。
建築士・設計事務所の独立時 最初の課題
建築士や設計事務所で、独立や開業され、
最初の課題は、 【 生き残ること 】 です。
つまり売上を上げて利益を確保することです。
売上を上げるには、
【 1 】設計等の技術力・サービスが優れていること 【 2 】良い事をお客様に知ってもらうことと、 適正な売価を設定すること大きく分けて、この2点が重要になります。
【 1 】は、一級建築士、二級建築士など設計事務所で
起業創業しようと考えらるわけですから、
建築設計や監理など技術力・サービス力には
実績がある方が多く、問題はほとんどありません。
問題となりやすいは、上記の【 2 】です。

技術力のある建築士・設計事務所であることを知ってもらうこと
【 2 】については、会社員の時代には、
あまり意識することがありません。
しかし、良い事をお客様に知ってもらう事が、
売上確保では最重要になります。
一般的な【 マーケティング 】という言葉だと、
難しい気がしますが、要するに、
"良いことをお客様に知ってもらえれば良い"ので
"知ってもらう努力は、何でもやれば良い"のです。例えば、下記のようなものがすぐに検討できます。
やらないよりはやった方が良いわけで、
こうした努力を積み重ねれば重ねるほど、
受注の確率が上がることになります。

ただし、重要なのは、予算・期限を決めることです。
特に予算の上限を決めることは非常に重要です。
事業は、【 何年も続くマラソン 】です。息切れしてしまうような猛ダッシュは避け、
長期間で軌道に乗せ続けることが必要です。
獲得が軌道にのり、受注見込みがある程度立てば、
創業融資で、受注事業を本格的に軌道に乗せます。
建築士・設計事務所の起業は、創業融資が必要
建築士や設計事務所の受注案件で、
【 工事の請負がある場合 】請負開始から外注費や仕入れ、現場諸経費の立替
→代金回収まで間持ちこたえる資金力が必要です。
【建築や設計が長期スパンで行われる場合
受注から代金の改修まで時間がかかるため、
代金回収まで間持ちこたえる資金力が必要です。
沢山受注があることは、大変素晴らしいことです。
しかし、起業で最も注意すべき点は、
【急成長期の資金ショートによる黒字倒産】です。建築士や設計事務所で独立開業して成功するには、 この資金の問題を乗り越える必要があるわけです。

弊所では、建築士や設計事務所での起業創業では、
日本政策金融公庫の創業融資を提案します。
初回創業融資上限は、【 原則1,000万円 】です。
運転資金の場合、5年返済で利率2%程になり、
月間17万程返済していくことになります。
利率2%なら年間金利は、20万円をきりますので、
これより利益を上げれば、借りた方が得なのです。
資金調達に成功できれば、売上を確保する努力を
地道に行うのみで、経営がしやすくなります。
建築士や設計事務所向けサービス
匠税理士事務所には、世界4大会計事務所出身で
経営セミナーや商工会議所の経営指導員向け講師の
税理士が起業や独立開業を支援致します。
建設業や建築業は、一取引当たりの金額が大きく、
ハイリスク・ハイリターンな特性の事業で、【お金の付き合い方】・【利益が出る仕組み】など経営手腕が重要です。
弊所では、お客様に【 お金 】・【 利益 】が残るよう
会計データを活用した経営コンサルティングを通じ
経営をしっかりとサポートします。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の税理士は匠税理士事務所 】

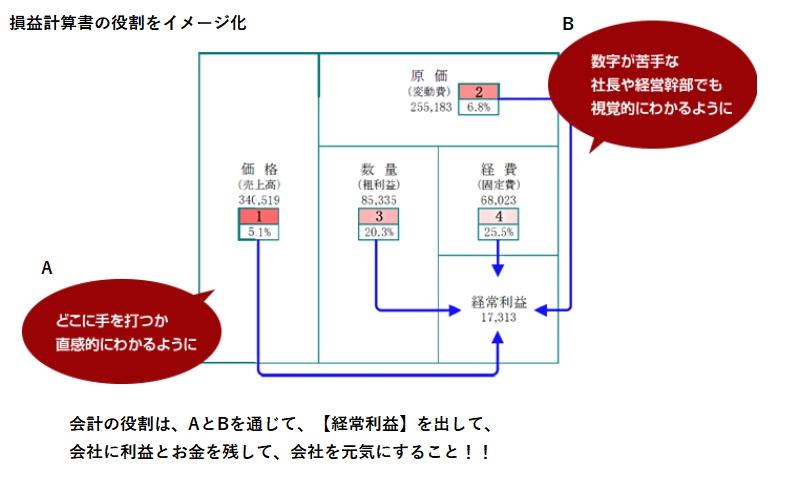
◇建築業許可申請サービス

◇建築業向け創業融資サービス

◇建築業向け会社設立サービス
◇建築業で 税理士変更の法人お客様 や 個人のお客様 はこちら
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇お役立ち情報
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
建築士・設計事務所向け黒字戦略とキャッシュ経営
【 黒字経営の情報館 】
【 黒字経営サービス 】
執筆者・文責:税理士 水野智史
#建築士税理士 #設計事務所税理士
一人親方とは?独立開業で一人親方になるには、法人化も解説 (19/03/14)
ご訪問頂きありがとうございます。
弊所は世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 【建設業の独立開業】に力を入れる事務所です。・今回は、一人親方とは何か?
・建設業や建築業で独立開業するには?
・一人親方になるにはどうすればよいのか?
・事業規模が大きくなって会社にする法人化
についてまとめました。
一人親方とは何か? 独立開業するには?
一人親方とは、建設業や建築業で社員を雇用せず、事業主と親族だけで事業を行なう形態をいいます。
簡単にいうとフリーランスというイメージです。・どんな仕事を幾らで請けるのか、
・あるいは請けないのか?
・外注先の利用など独自で決めて、独自で動く。
上手くいけば稼げ、上手くいかないと損します。 つまり、ハイリスク・ハイリターンな形態です。一方、建設業や建築業で会社員として働けば、
毎月一定額の給与が入ってきて安定してます。
どちらが良いかは、それぞれの人生観・仕事観で、
一概にどちらがよいということはありません。

一人親方では、仕事の内容やお客様を選べたり
価格の設定が可能になるメリットがあります。
大きく収入を伸ばし自分の思うように
仕事を作り、組織を作ることもできます。
一方デメリットは、一人であるが故に、
病気怪我・事故で収入が途絶えてしまう事です。
また、大企業と直接取引できないこともあるため、
人を雇い法人で起業する方が良い場合あります。
それでは、一人親方で成功するには
どのような条件が必要なのでしょうか?
一人親方で独立開業し成功する条件やポイント
一人親方で、【独立開業して成功する条件】は、
いろいろとあると思いますが、
【工事受注できる方=売上を上げれる方】です。
売上を上げるには、
⓵・・高い技術力や専門性
②・・得意先や外注先から信頼される人間性
③・・材料等の確保のために必要な資金力
これらを全て兼ね備えている必要がございます。独立開業し技術力・人間性に自信があるけれども、
資金面だけ自己資金が少ないという方は、
日本政策金融公庫などから資金調達するという
創業融資で弱点を補うこともできます。
売上を確保できれば、
【入金は早く・支払は遅く】の資金繰り原則を抑え 【売上最大化 + 経費最小化 = 粗利最大化】を行うというポイントを抑えて黒字経営にして、
独立開業して成功する確率を高められるのです。
このような儲かる仕組みづくりをして、
会社に利益・お金を残すというプラスサイクルを生み出し
この利益とお金を、【 人 】や【 モノ 】に投資して 事業を拡大するのが、成功の方程式となります。
個人事業を株式会社にする法人化や組織形態
一人親方で独立開業するときに、
⓵個人事業主として独立開業する方法
②はじめから株式会社など会社で独立開業する方法
③個人事業が軌道にのったら会社にする方法
大きく分けて3つの方法があります。
【はじめから株式会社など会社で起業する方法】
開業後から売り上げが継続的に立つ予定があり
創業融資や許可申請もはじめから検討したい場合、
法人での起業が向いています。
また、法人ではないと取引ができない場合や、
従業員がいる場合なども法人起業が適してます。
法人で起業される方向けサービスはこちら
【 → 起業のお客様向けサービス一覧 】

【個人事業で起業し軌道にのったら会社する方法】
それでは、最初から個人事業主にしたら
ずっと個人事業かというとそうではありません。
個人事業を引き継いで、
株式会社など会社にすることも可能です。
これを【 法人化 や 法人なり 】といいます。
株式会社など会社にすることのメリットは、
・節税の幅が広くなる
・求人などで有利になる
・消費税免税や低い税率を利用した節税
・退職金制度を活用した節税
がある一方、
社会保険の強制加入などデメリットもあります。
◇個人事業から株式会社へ 法人化はこちら。

【個人事業主として独立開業する方法】
個人事業で独立開業する最大のメリットは
コストがかからず気軽に始められる形態です。
メリットやデメリット
匠税理士事務所では、お客様の状況をヒアリングし
会社 又は 個人の有利不利をお伝えし、
【法人起業・個人起業・法人化】を支援します。建設業や建築業の独立開業支援サービス
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

建設業や建築業に強い匠税理士事務所
 【 建設業に必要な全てがそろう事務所 】をかかげ
【 建設業に必要な全てがそろう事務所 】をかかげ
税務会計や経営コンサルティングは税理士が担当し
給与計算や社会保険など人事労務などの問題は
労務の専門家の社会保険労務士が対応します。
法律問題は弁護士が対応し、建設業許可申請は
行政書士がチームで対応しますので
社長様は本業に集中していただけます。◇事務所概要
匠税理士事務所サービスラインはこちら
◇建築業許可申請サービス

◇建築業向け創業融資サービス

◇建築業向け会社設立サービス
◇建設業の法人化・法人成りサービス
関連記事 → 建設業や建築業の個人から法人化・法人成り
◇法人のお客様は、こちらです。
◇個人のお客様は、こちらです。
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇お役立ち情報
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
こちらは、個人事業主の方向けのコンテンツです。
◇法人のお客様は、こちらです。
◇個人のお客様は、こちらです。
外部リンク
ファーストコンテックは、建設業界に特化した人材派遣会社。技術者が不安なく働きキャリアアップできる環境づくりを⽬指します。
→ 株式会社ファーストコンテック|建設業界に特化した人材派遣
執筆者・文責:税理士 水野智史
工務店やリフォーム・内装の会社設立・創業融資・起業は匠税理士 (19/03/14)
匠税理士事務所は工務店やリフォーム・内装業など
【建設業の起業支援】に力をいれる事務所です。
工務店やリフォーム・内装業で独立開業するための起業支援では
【 社名と本店所在地 】のみをお決め頂ければ、書類作成や登記は税理士・司法書士にお任せという
起業支援・会社設立サービスをご用意しております。
また書類作成のみの起業支援や会社設立ではなく、
経営セミナーや創業セミナーで講師を務める 世界4大会計事務所出身の税理士を軸に【会社設立後の起業成功】までお手伝いします。
これまでに多くの起業支援を担当させて頂き、
工務店やリフォーム・内装業での起業成功には、
1 お金の調達で、成功する 2 そのお金を活かし、増やす【経営】に成功するという2つの成功が重要であると考えております。

資金が重要なのは、工務店やリフォーム業・内装業は、
一案件当たりの取引金額が大きいため、 多くの資金を必要とする特徴に起因します。基になる資金が少なければ動かせる
【 材料 】・【 人員 】に制限がかかるため、
対応できる仕事量や規模も制限がかかります。
結果、技術的には優れていても資金面で不安が残り
大規模な工事が請けられないということになり、
利益確保が難しくなってしまいます。
このようなことことから、
工務店やリフォーム・内装業で会社設立をして、
成功には資金調達が、【 最大の壁 】になります。
例えば、入金と支払いのサイクルで考えると、
①・・入金は概ね1~2か月後(1.5か月)
②・・工期は概ね1ヶ月~2か月(1.5か月)
③・・支払いは1ヶ月後という標準的な会社なら、
1.5か月 + 1.5か月 - 1ヶ月 = 2か月分不足です。仮に、会社を維持する人件費・家賃など150万なら最低300万は自己資金が必要となるのです。
一方、自己資金が十分で起業される方はまれで、
万が、一納品のトラブルや得意先の入金が少しでも遅れると資金的に更に厳しくなります。

工務店やリフォーム・内装の起業で成功するには
工務店やリフォーム業・内装業の起業成功は
創業融資による資金調達に大きく左右されます。この創業融資の成功には、
会社設立・社会保険・建設業許可が必要になります。一見、創業融資と上記は関係ないように感じますが
融資条件で【 建設業許可 】が求められるからです。
なぜなら建設業許可があれば500万円以上の大規模
工事が請けられ返済力があると見られるためです。
逆に許可が無いと返済力が低下し、 創業融資成功率も下がるというわけです。建設業許可は会社謄本・社会保険が必要になるため
会社設立・社会保険加入・建設業許可の適時完了は融資成功では、大変重要な条件になるのです。
またこれら3つを同時に動かすため、
工務店やリフォーム業・内装業の起業では
特に力量が必要になります。
匠税理士事務所では、起業セミナーで講師を務め、 世界4大会計事務所出身の税理士が担当します。これら3つを同時進行で進める経験が豊富で、
一生に一度の起業が成功するようサポートします。担当税理士・サービスはこちらで確認下さい。
【→ 起業・黒字戦略の匠税理士事務所】

独立・開業・起業向けサービスはこちらから↓
【→ 起業のお客様 サービス一覧】
工務店・リフォーム業・内装業で会社設立はこちらから↓


起業に伴う創業融資はスピード感が重要
入金まで材料・外注費・人件費が多額に出るため、
工務店やリフォーム・内装の起業成功では、
創業融資の結果が大きく影響します。
ここで重要なのは、創業融資のスピード感です。
具体的には、創業融資の申請時期です。
【最速の申請】は、会社設立・社会保険切替・建設業許可申請の手続を進め、
【 同時並行 】で日本政策金融公庫の 創業融資による借入を進めることです。そして融資申請時期を出来る限り早くする理由は、
日本政策金融公庫創業融資による借入で、
幾ら調達できるか早くに分かれば、
他の切り口での資金獲得の検討や、
事業規模縮小など早く考えられるからです。

逆にこれを同時進行で行わないと、
許可は取れたが資金調達が未完了で
創業計画書の作成から借入の申し込み
入金までの約1か月から2か月の期間、
機材などが買えず、【事業停止】にもなりえます。
弊所は、創業融資による資金調達を重視しており
こちらの業務には、経営セミナーでも講師を務める世界4大会計事務所出身の税理士が対応致します。
創業融資の成功率はトップクラスとなってます。担当する税理士や専門家はこちらから
【 → 匠税理士事務所の概要 】

工務店やリフォーム・内装業向け創業融資はこちら
【 → 創業融資による資金調達 】

工務店やリフォーム・内装業の会社設立
工務店やリフォーム・内装業でこれから株式会社や合同会社など会社設立する場合は、
決算期と資本金など基本設定がとても重要です。決算期をしっかりと考えて決めないと、
税金が毎年生じやすい会社になってしまい
資本金も考えないと消費税が大きく変わります。
当会計事務所では、お客様の今後のビジョンや事業内容をしっかりヒアリングした上で
株式会社や合同会社など会社設立致します。
会社設立後の建設業許可申請や
社会保険手続きの代行はもちろんですが、
経理など本業以外は全てお任せいただけます。
【 起業に必要な全てがそろう会計事務所 】を軸に東京都や神奈川県で創業支援を行います。
◇工務店やリフォーム業・内装業に向けた会社設立・創業融資など起業支援はこちら。
【 → 匠税理士事務所の会社設立 】
工務店やリフォーム・内装の会社設立・起業の流れ
会社設立・起業後の具体的な流れを説明します。
今回は、現在会社に勤務され5月起業を考え
【 8/10退職、9月から稼働 】を例にします。
【 会社設立から建設業許可取得までの流れ 】⓵ 5月に税理士と打ち合わせ
会社名、本店の場所、資本金など新会社の設計決定
【 → 同時に創業計画書作成と必要資料用意 】
② 1週間程で司法書士にて⓵の設計書で登記手続
③ 登記申請から2~3週間で謄本入手
④ 謄本入手と同時に創業融資の申込銀行口座の開設・税務署などの届出書
⑤ 勤務先の退社後に社会保険の変更手続
→ 2~3週間で新設法人の保険証入手
⑥ ⑤の後、すぐに許可申請
→ 約1か月で建設業許可取得
建設業の起業は、上記の流れとなります。
大変そうですが、専門家チームを活用すると、
一度打ち合わせで、会社名など必要事項を 決めてしまえば、後はお任せとなります。このスケジュールを表にしますと下記になります。
(官公庁の混雑具合で、多少前後します。また下記表は余裕をもったスケジュールになっています。)
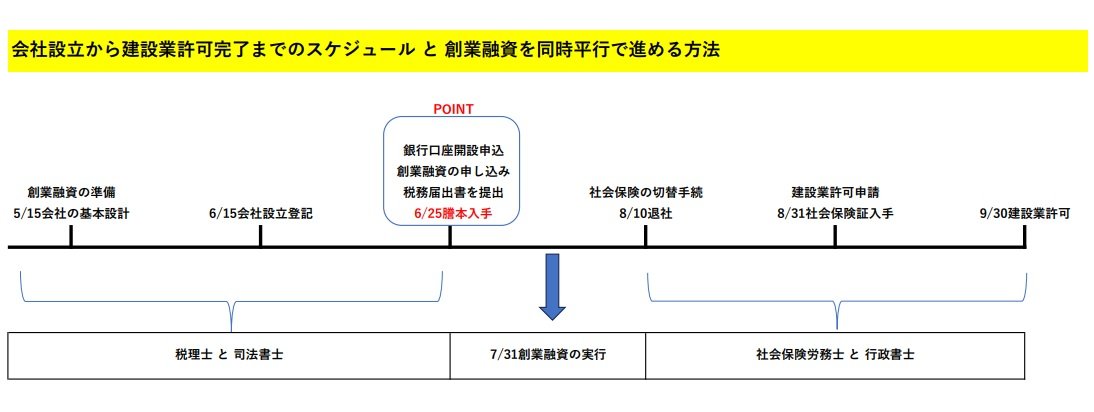
建設業許可申請にも対応の会計事務所
工務店やリフォーム・内装業を始める際、500万円以上の大型案件を受注するために、許可申請が必要になります。
また、創業計画書の売上を達成するには、大型案件の遂行が必要であるため、許可取得が創業融資条件となることもあります。
つまり、許可の失敗=創業融資の失敗 という展開になってしまいます。そこで匠税理士事務所では、建設業専門の行政書士と連携し許可申請も対応します。
これまで10年以上仕事をしておりますが
【 創業融資と許可成功率は100%です。】もちろん、獲得が困難であると判断した場合には、そのようにご説明させて頂きます。
また決算期ごとの更新にも対応しますので、
お客様は本業に集中していただくことが可能です。
◇工務店やリフォーム・内装業の許可申請サービス
当会計事務所は、工務店やリフォーム・内装業のお客様の
会社設立・創業融資など起業成功を支援できる
専門性の高い社員・提携先にこだわってます。

◇会社設立や創業融資など起業・独立・開業相談会
会社設立や創業融資など起業・独立・開業をお考えの方に向けて相談会を開催中。
建設業は、【 建築工事、土木一式工事、舗装工事、とび・土木工事、大工工事、左官工事、石工事、タイル、れんが、ブロック、屋根、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ、板金、ガラス、熱絶縁工事、さく井工事、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事 他全29種 】の分野で許可申請と更新が必要です。
起業創業や独立開業に伴う許可申請を
行政書士が代行致します。
【→建設業許可申請サービス】
工務店やリフォーム・内装業の方向けの経営お役立ち情報
◇工務店やリフォーム・内装業などのお客様に向け、経営お役立ち情報を配信しております。
工務店やリフォーム・内装業の方に向けた創業融資や会社設立など起業支援につき最後まで御覧頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
これから10年後も生き残る建設業や建築業の会社経営とは (19/03/14)
『 10年後も生き残る 建設業や建築業の会社 』
どんな会社でしょうか?
色々な考え方があると思いますが、私共では 【 儲かって、お金と人が残る会社 】だと考えます。
建設業や建築業は、お客様・発注者の要望に沿って
建築物を建設するという仕事であり、
材料を仕入れ、職人さんが組み立てる仕事です。
今はこの材料が高騰し、人材は少子化と職人さんの高齢化で確保が難しくなっています。
この傾向は今後も更に続くことが予想されます。
材料の確保にはお金が必要ですし、人材確保は更に難しく、採用・教育・定着にもお金が必要です。
ゆとりある経営には、お金を生み出す儲け
つまり利益が必要となります。

①決算まで利益確定できない
→建設業向会計を適用し、完成工事の利益が毎月分かる会計を設計する。
②利益がでない
→原価や工数、取引先毎の粗利が管理できるよう提案する。
③資金が不足
→利益不足か、お金の流れの問題点か、一時的な受注過多かによって資金調達や改善を行う。
案件ごとに利益が出ていて、お金の流れに問題がなければ、現状のまま経営されて良いと思います。
利益が少ない、工期の長い案件を受注する、
大型案件受注の場合、利益着目の経営が大切です。
そうした方に、この記事がお力になれば幸いです。
儲けの源泉である粗利で商売の8割は決まる
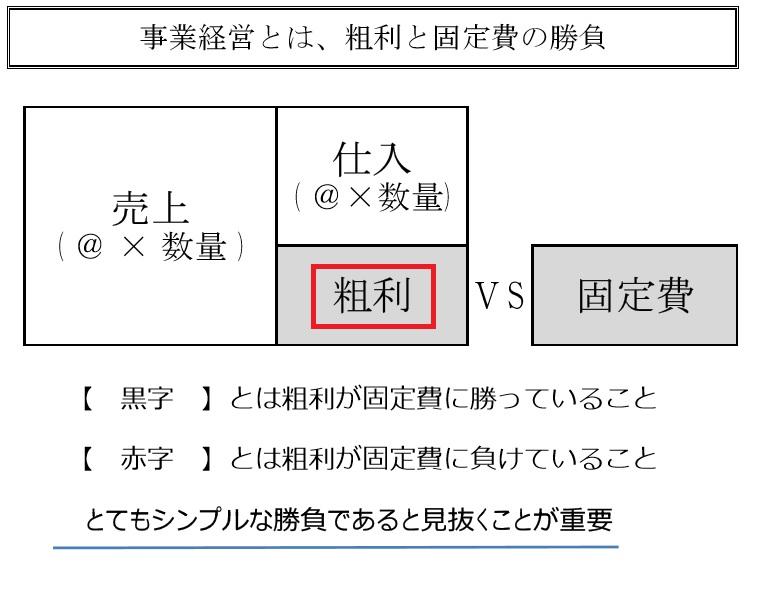
お金を生み出す儲けは、売上から材料費・外注費など原価を除いた粗利から生まれます。
この粗利から人件費や家賃など会社を維持するための経費である固定費を差し引いたものが、
【 本業の利益である営業利益=儲け 】です。したがって、粗利が確保できる会社は、しっかりと本業の儲けである営業利益が黒字となります。
この営業利益が黒字の会社は、
長期的にドンドンお金がたまっていき、
より良い材料・人材を確保していき、更に利益を
出していくというプラスのサイクルになります。
逆に営業利益が赤字なら、お金が減りますので、
良い材料・人材を確保するのが困難になるという
マイナスのサイクルになってしまいます。
そのため、まず儲かる商売の仕組み作りの軸である
【 粗利の最大化 】が重要となるのです。
利益とお金がたまる会社づくりのポイント解説は
こちらからご確認下さい。
【利益が残る、利益が増える会社作りのポイント】入出金サイクルを軸にお金がたまる会社を作る
儲けがでると、会社にお金がたまってきます。
ただ、お金がたまる会社作りには、長期的でなく、
より早くお金がたまる会社にする意識が重要です。
そのために、【入金は早く、支払いは遅く】という
入金と支払サイクルを取引先と交渉したり、
大規模工事は原価相当を前金で頂くなどお金が
たまりやすい仕組みを作ることになります。
例えば、預金残高5,000万円で、売上10,000万円
3か月後入金で、材料外注など原価5,000万円が
月末支払の場合、月末の預金残高は0円になり、
3か月後の預金残高は10,000万円になります。
一方、預金5,000万で売上10,000万1か月後入金で
材料外注費など原価5,000万も1か月後払の場合
預金残高は5,000万が底になり、
1か月後の預金残高は10,000万円になります。

前者の場合、入金まで一時的に資金が厳しくなり、
他の大きな工事の支払いができず、後者の場合、お金はありますので他の工事も
同時並行で進め利益をあげられます。
もちろん、融資などでつなぐことは出来ますが、
より多くのお金を動かせ、お金をためやすいのは、
【入金は早く・支払いは遅く】という入出金サイクルを
作った会社であることは明らかです。
【お金がたまる会社づくりのポイント解説】
儲かる仕組みでお金がたまる会社を作ると、
銀行もよりお金を低い金利で貸してくれたり、
優秀な人材により良い条件を出せるため、
人も採用しやすいなどプラスサイクルにつながります。
10年後も生き残る建設業や建築業の会社経営は、
【 地道に利益率の改善を行い、】
【 入金と支払の条件の交渉することを通じ、】
儲かる仕組みと、お金がたまる会社づくりをし、
材料・人材の争奪戦に勝ち残れる会社ではないでしょうか。
匠税理士事務所は経営支援に力を入れております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

経営成績表決算書・経営事項審査(経審)
決算書で、これまでの経営結果が分かります。
まず利益剰余金をみると会社経営がこれまで
順調なのか否かが分かりますし、
現預金など流動資産と負債バランスみると、
お金がたまりやすい会社か否か分かります。
経営成績表の決算書を基に計数化したものが、
経営事項審査(経審)で、こちらを基に入札評価がされます。

結果、儲かっている会社、お金がたまる会社は、
入札や新規得意先で多くのチャンスが入ってくる
好循環が生まれます。
こうした理由からこれから10年後も生き残る建設業や建築業の会社経営とは、
【儲かってお金がたまる会社作りを目指す経営】ではないかと考えております。
以下で利益はどこから生まれるか、【利益の源泉】につき記載します。【 建設業界・建築業界で利益を出すには工事と人材選択が重要】
また、これからの建設業界での生き残りでは、
売価の最大化への取り組みは不可欠です。
こちらでは積算見積もりを通じて【 売価最大化 】につき記載します。【 建設業・建築業で会社の利益を最大化する売価経営戦略とは】
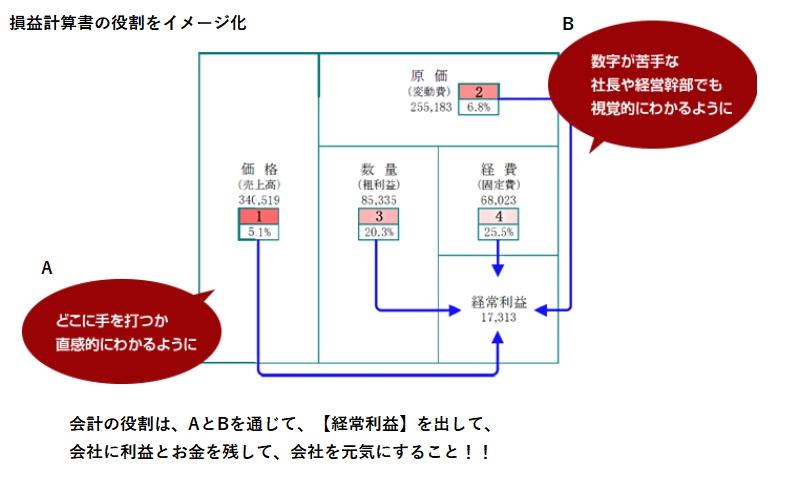
建設業や建築業の経営支援に強い会計事務所
匠税理士事務所は、目黒区自由が丘にある事務所で
経営セミナー講師の世界4大会計事務所出身の税理士が
経営コンサルティングを担当します。
毎月の会計・税務はもちろんですが、これらの数字を活用した経営コンサルティングを通じて、
会社の黒字化とお金がたまる会社づくりをサポートします。
建設業の企業様向け匠税理士事務所の経営サポート詳細はこちらからご確認下さい。
担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇建設業の関連記事
○法人のお客様
○個人のお客様
給与計算や社会保険の手続きをはじめ、
建設業許可申請や更新業務・入札参加のための
サポートを提携行政書士・社会保険労務士とチーム対応します。
建設業許可申請はこちらから確認下さい。
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
建設業・建築業の起業資金の調達など
創業融資サービスはこちらから確認下さい。
【 → 税理士による創業融資 】
建設業・建築業で株式会社・合同会社など
会社設立サービスはこちらから確認下さい。
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
10年後も生き残る建設業の経営支援など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で独立開業し会社に変更するための
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 東京都で税理士の法人化・法人成り】
◇匠税理士事務所概要

◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇お役立ち情報
執筆者・文責:税理士 水野智史
#建設業10年後
#建設業会社経営
デザイナーや広告代理の会社設立・創業融資・起業は匠税理士事務所 (19/03/14)
WEBサイトにご訪問ありがとうございます。
弊所は、デザイナーや広告代理店などクリエィティブ事業に強い会計事務所です。
デザイナー・広告代理店などクリエィティブ業は、
時流、技術革新など最先端をゆく事業であるため、
取り巻く環境(得意先の趨勢・業界の動き)が変動し、業績が浮き沈みしやすい性格があります。 一方で利益率が高く、流れに乗れれば利益を出しやすい事業という特徴もあります。この性質から資金を比較的多めに留保しておき、環境の変化に臨機応変に対応できる体制を常に構築しておく必要があります。
そこで重要なのは、創業融資などの資金調達と、
資金を社内に蓄えながら税額を圧縮する留保型節税対策とがとても重要になります。

デザイナーや広告代理店の起業成功は、創業融資がポイント
デザイナーや広告代理店、クリエイティブな事業をこれから行うため起業する場合には、
以下のような流れとなります。
現在会社勤務で、【5月起業を考え、8/10退職、9月から稼働 】を例に説明します。
【 会社設立から事業開始までの流れ 】
⓵ 5月に税理士と打ち合わせ
会社名、本店の場所、資本金など新会社の設計決定
【 → 同時に創業計画書作成と必要資料用意 】② 1週間程で司法書士にて⓵の設計書で登記手続
③ 登記申請から2~3週間で謄本入手
④ 謄本入手と同時に創業融資の申込
銀行口座の開設・税務署などの届出書
⑤ 勤務先の退社後に社会保険の変更手続
このスケジュールを表にしますと下記になります。
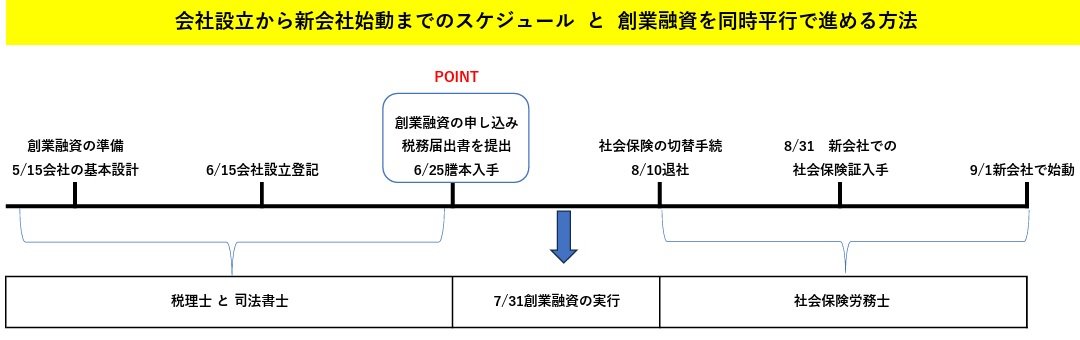
ポイントは、会社設立・社会保険の切り替え・税務署等官公庁への届出という手続き業務を進め、
【 同時 】に日本政策金融公庫の創業融資による資金調達を進めておくことです。起業時は、資金的に余裕がないため、できる限り早く軌道にのせる必要がありますが、
日本政策金融公庫の創業融資は申し込みから実行まで1か月ほど要します。
日本政策金融公庫創業融資を同時に進めることで、この1カ月を無駄にしないで済みますし、
創業融資による資金調達で、幾ら借り入れができるか早くに分かれば、
他の方法での資金調達の検討や、規模・初期投資の縮小を早く判断できるからです。
 なお、この創業融資は、一般的に1,000万円が初回限度額となります。
なお、この創業融資は、一般的に1,000万円が初回限度額となります。
最初から1,000万円を超えるような調達計画の場合には、見直した方が無難です。
ここで無事資金調達ができれば、安心して事業に打ち込むことが出来るようになり、
広告制作やデザインに集中できるといった好循環にもつながります。
また、最初から納品までに時間がかかる大規模案件がきても対応が可能になります。
このような理由から匠税理士事務所では、デザイナーや広告代理店で起業される方に向け、
創業融資の支援を行っております。
詳細はこちらからご確認をお願い致します。

デザイナーや広告代理店の起業支援に強い税理士による会社設立
匠税理士事務所では、世界4大会計事務所出身の節税対策に詳しい税理士がデザイナーや広告代理店の起業支援を行っております。
デザイナーや広告代理店などクリエィティブ業は、
一取引当たり金額が大きく、少人数対応なため、
比較的利益が出やすいという特徴がございます。
そのため、稼いだ利益をしっかりと会社に残すための留保型の節税対策が重要になるのです。そして節税対策でとても重要なのは、決算期です。
この決算期をしっかりと考えて決めておかないと、
予想外の税額が出てしまう事につながります。
そこで匠税理士事務所では、初回面談で会社名や資本金などの会社の基本設計を行うときに
事業の流れである商流を、しっかりと伺った上で、【 最適の決算期 】をご提案致します。
会社設立後も、経理は全てお任せで代行させて頂き、高度な専門性を駆使した利益のシミュレーションから節税対策まで行います。
詳細はこちらからご確認をお願い致します。
起業後の経理代行や経営支援、節税も充実の税理士事務所
起業した後は、売上確保やお金の調達以外にも経理や給与計算など
色々とやるべきことが出てきます。
これら本業以外のことを全て自分で対応するとなると、時間がかなりとられてしまうのも事実です。また、こうした経理や給与計算に対応できる人材を創業当初から雇用するのは、
人件費が膨らみますし、採用が困難なため得策とはいえません。
このような起業家の方を支援するため、匠税理士事務所では、経理は書類を送るだけで、
後はお任せの経理代行・タイムカードに打刻するだけで対応の給与計算など
社長が本業に集中できるようサポート致します。
また、会社拡大の際の資金繰りや利益率など経営の問題につきましても、
世界4大会計事務所出身で経営セミナー講師を務める税理士がコンサルティング致します。このように匠税理士事務所は、経理や給与計算など本業以外の代行と経営支援を通じて、
お客様の事業発展のお手伝いを行っている税理士事務所です。
所属税理士やスタッフなど事務所の詳細につきましては、こちらからご確認を頂けましたら幸いです。
【 → 匠税理士事務所について 】

起業時や創業時に活用できる補助金や助成金も対応可能
匠税理士事務所では、起業時や創業時の資金調達方法の一環として、
補助金や助成金の活用も提案致しております。
起業時は設備投資や創業に伴い人材を雇用するなど大きな投資の機会が出てきます。
その際に、一部の支出を国の制度を利用して補助してもらうという発想も重要です。匠税理士事務所では、補助金専門の中小企業診断士や、
助成金に特化した社会保険労務士と連携して起業時の資金調達をサポート致します。
起業時に活用できる補助金や助成金につきましては、こちらからご確認をお願いします。
→ 起業・創業も使える小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行
デザイナーや広告代理店などクリエィティブ事業に強い税理士や会計事務所に
顧問契約を変更したいというお問い合わせも多く頂いております。
デザイナーや広告代理店などクリエィティブ事業の方に向けた匠税理士事務所のご案内は
こちらからご確認をお願いします。
→ デザイナーや広告代理店の税理士・会計事務所は匠税理士事務所

デザイナー、クリエイターや広告代理店を個人で経営する場合は、
源泉所得税などが重要となります。こちらにつきましてもお役立ち情報をまとめております。
【 デザイナー・コーディング(コーダー)などIT業の源泉税 】
匠税理士事務所のサービスや料金はこちら
→ 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所
会計事務所の起業支援対応エリア:世田谷区・目黒区・品川区など東京都23区全域の創業独立の成功をサポート
ビル・店舗管理やクリーニンク・清掃業に強い会計事務所は匠税理士 (19/03/14)
匠税理士事務所は、ビル・店舗の清掃管理やメンテナンス、クリーニングなど清掃業に詳しい税理士事務所です。
こちらは、これから既に顧問税理士さんがおり、税理士変更をお考えのハウスクリーニング・清掃業のお客様に向けた記事となります。
◇起業される方はこちらです。
ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業の特徴は、初回は機材などの購入費用がかかりますが、
これらを取り揃えると人材の採用と確保がポイントになります。
いい人材を確保できれば、固定契約による安定的した収入を軸に、
スポットでの契約を織り交ぜることで、比較的収益を安定化させることができる特徴があります。
逆に人材の確保が難しければ、案件数をふやせなくなるため、収益は低下するという特徴があります。
ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業で成功するには
ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業で成功するには、
【 人材の採用 と 確保 で同業他社と差別化 】これが重要です。いい人材が採用出来て、辞めずに残ってくれる会社は、案件数を右肩上がりに増やせます。
工具や道具はお金を出せば変えますので、やはり人材が生命線。
この人材の採用と確保でノウハウを有しているか否かが非常に重要となります。
さらに言えば、稼いだ利益をこの人材の採用と確保に投資できるかどうかということです。

粗利をしっかりと残せる元請けになる努力
ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業などは、
【 粗利 > 固定費 】、つまり黒字となるよう粗利率が適正になっているかがとても重要です。
粗利が高い業種では、人材を余分に確保しても安定的に経営ができますし、
様々な打ち手を打つことができます。
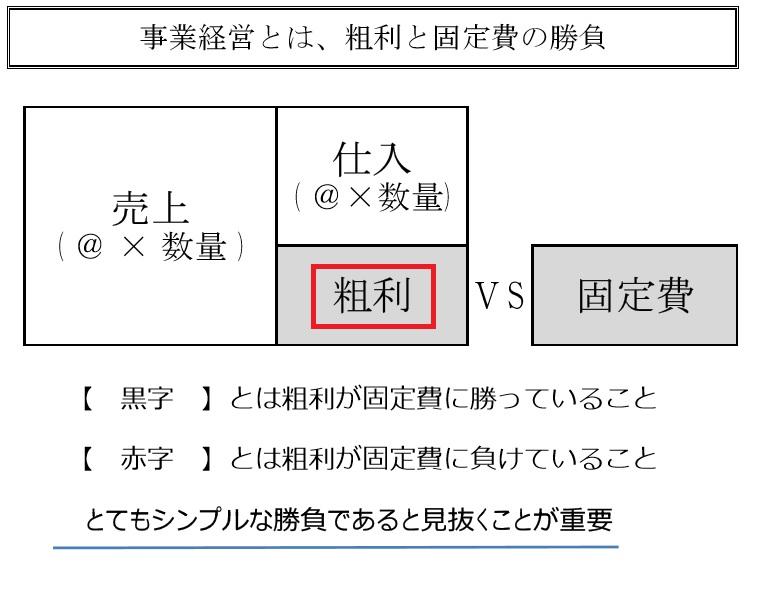
そして粗利率を確保するためには、元請けになることが極めて重要です。
それではビル・店舗管理やクリーニンク・清掃業で元請けになるにはどうすればよいのでしょうか?
・目の前の仕事を全力で行い紹介を増やす
・紹介をしてくれそうな提携先を増やす
・HPやSNSといったWEBなどインターネット広告を行う
・チラシやポスターなど広告を行う
など知ってもらう努力は、何でもやること。
そして、知ってもらって選んでもらうということで、
客数が増えて、高い売価の交渉が可能になる。という好循環が生まれます。営業・販売促進というと何だか大変そうですが、
自社のことを知ってもらうための努力は何でもやるという姿勢が重要です。
ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業に強い匠税理士事務所
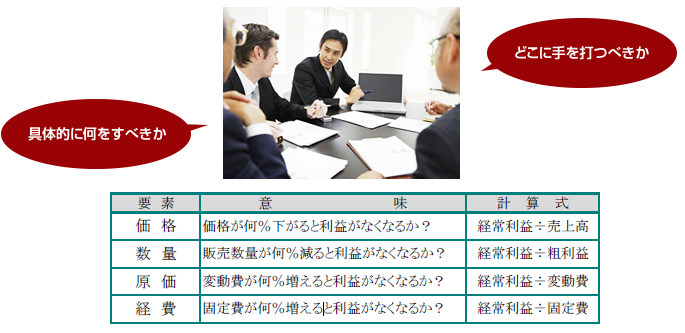
匠税理士事務所には、ビル・店舗の清掃管理、クリーニングに強い税理士が所属しております。
世界4大会計事務所出身で経営セミナーで講師を務めており経営のアドバイスや節税対策コンサルティングにも定評がございます。
また、給与計算や社会保険手続きなど人事労務については、社会保険労務士と連携し
日本政策金融公庫などの金融機関とも連携し融資のサポートも行っております。
ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業の社長様が本業に集中できる環境を提案致します。◇匠税理士事務所の所属税理士や提携の専門家
【 → 自由が丘の匠税理士事務所概要 】
【 → 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所...TOPページ 】
会計事務所対応地域/世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域・神奈川

ビル・店舗の清掃管理、クリーニングで株式会社など経営をされている方で、税理士変更をご検討中の方はお気軽にご相談ください。
ビル・店舗の清掃管理、クリーニングなど清掃業のお客様向けサービス
ビル・店舗管理やクリーニンク・清掃業に強い会計事務所をお探しの方は匠税理士事務所へご相談下さい。
お金が不足しないキャッシュストック経営や資金調達や黒字戦略会議が特徴的なサービスで、起業と黒字戦略に特化した会計事務所です。サービスはこちらからご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
建設業や建築業の経営事項審査(経審)とは?簡単に解説 (19/03/14)
建設業や建築業で会社経営をされている方は、
【 経営事項審査(経審)】という言葉を何度か耳にされると思います。
この経営事項審査(経審)とは、何でしょうか?
色々な説明があると思いますが、簡単に解説すると、
【 毎年の会社経営に関する健康診断 】 これが一番しっくりと分かりやすい気がします。
この会社の健康診断を数字化した成績表が、【 経営事項審査(経審)】であり、
この経営事項審査では、経営の規模・状態・技術・その他の項目につき、
29の業種ごとに計数化して評価測定することになります。
入札に参加しようとする建設業者は、それぞれの許可業種に応じて経審を受けなくてはなりません。
そして東京都や区、市町村などの各自治体が自分たちの公共工事を発注する際に、
工事の規模や求められる技術レベルなどに応じて、
この工事は経営事項審査(経審)〇〇点以上なら大丈夫という一つの指標にしたり、
民間工事でも相手企業の与信調査(信頼できる会社かどうかの判断)に使われるのが主な目的です。

経営事項審査(経審)を受けるとどんなメリットがあるのかを解説
なんとなく大変そう、難しそうな経営事項審査(経審)・・・・・
それでは多くの会社が、経営事項審査(経審)=会社の健康診断を
毎年受けるのは何故でしょうか? これを受けると多くの良いことがあるのです。
経審メリット 1 公共工事の入札に参加可能になる
東京都や区、市町村などの各自治体の工事は、比較的メリットが多いです。
例えば利益確保がしやすい、代金の回収が確実など民間工事に比べると割が良い工事が多いですが、
公共工事は入札に参加して落札(工事を受注)しなければなりません。
入札に参加する場合には建設業法第27条の23で、
経営事項審査(経審)を受けなければならないと規定されているため避けては通れないのです。
◇ 公共工事の入札とは何か、メリットのまとめはこちらからご確認ください。
【 関連記事 →入札とは?わかりやすく説明。入札メリット・流れ・落札も解説 】
経審メリット 2 自社分析を通じて現状を簡単に把握できる
【 敵を知り 己を知れば 百戦危うからず 】という孫子の兵法にあるように
自社の状況を的確に分析するという経審は、毎年の会社経営状態が健康なのか、
そうでない場合は、資金面・人事面・売上面などどこに問題が出ているか把握し、改善策の気づきになります。
毎年経審を受けることで人間の体のように早期発見、治療ができます。
会社の場合には、発見が遅いと赤字(お金が流れ出ます)、優秀な人材が退職し流れ出ます。
これを毎年経審を受けることで、会社を離れてみて、修正するというイメージです。
また、役員貸付金や債務超過など経営事項審査(経審)で問題になる項目は、
金融機関で融資を受けるときにも問題になる項目でもあります。
建設業・建築業は業種的には資金を多く必要とするため、銀行との付き合いは重要で、
課題に向き合うことで、お金や人がどんどん利益を生み、
銀行が融資をしたくなる会社に近づくことにもなります。

また、入札である以上、落札して受注できることもあれば、
ライバルである同業他社に競り負けることもあると思います。
そうなると何故負けたのか、他社はどんな工夫をした経営をしているのか
自社が追いつくには・・・・という他社との分析という視点が経営に加わります。
これはスポーツや勉強と同じでライバルがいる方が確実に成長します。
経営事項審査(経審)に参加する場合には、
CIIC(一般財団法人 建設業情報管理センター)で経審の結果を見ることができます。
自社の結果もライバルに見られてしまいますが、
特別な事情がない限りは、同業他社との競争をしている方が経営の改善を通じて
利益を出せる体質になる場合がほとんどです。
改善を意識している会社とそうでない会社どちらが良くなるのかは明らかですね。
もちろん、匠税理士事務所でも利益が出るように経審を基に毎期決算の度にコンサルティング致します。
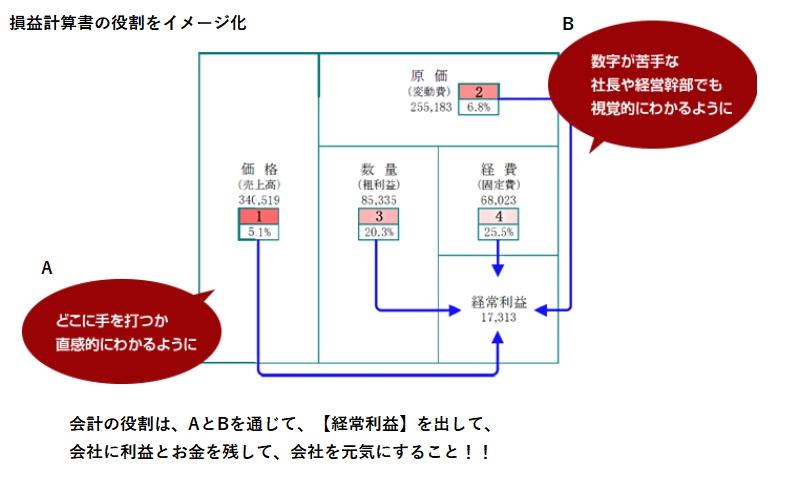
匠税理士事務所の建設業や建築業の経営支援サービス
匠税理士事務所は、建設業や建築業の経営に必要なすべてがそろう会計事務所を目指しています。会計税務サービスは当然ですが、社会保険や給与計算など人事労務や、
建設業の許可申請サービスもご用意致しております。
これは提携している人事労務の専門家である社会保険労務士や、
許可申請の専門家である行政書士とのチームで仕事をすることで実現しております。
また、工事での納品トラブルや代金の未回収など法務問題にも、
提携の弁護士と連携して対応致しますし、資金調達が必要な会社様には、
日本政策金融公庫や銀行・信用金庫など提携の金融機関のラインで資金調達もサポートします。
各分野のスペシャリストが専門性を発揮することで本業以外のこともしっかりと対応でき、
お客様が本業に集中できる環境づくりに取り組みます。
◇所属税理士や提携先などは、こちらです。
【 → 匠税理士事務所の概要 】【 → 仕事への考え方 】

◇建設業専門の行政書士による建設業許可申請代行サービスは、こちらです。
☆建設業許可申請サポート
建設業や建築業の経営ノウハウや経営ポイントの解説
◇建設業や建築業の経営のポイント解説
利益とお金がたまる会社づくりのポイント解説はこちらからご確認下さい。
【 利益が残る、利益が増える会社づくりのポイント解説 】
【 お金がドンドンたまる会社づくりのポイント解説
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
◇建設業や建築業の起業相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇東京都23区の匠税理士事務所TOP
世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所
世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所
◇建設業や建築業サービス
○法人のお客様
○個人のお客様
建設業や建築業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方 (19/03/14)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は建設業に詳しい税理士がいる事務所です。
今回は建設業の会社様からご相談を頂きます
源泉所得税の考え方とその計算方法や
納付書の書き方をかんたんにまとめました。
源泉徴収する所得税の考え方・計算方法とは
まず源泉所得税とは、会社から個人の外注先に
100,000円を支払うとすると、
仕事の内容によっては、
100,000円 × 10.21% =10,210円を
外注先から徴収し、89,790円のみ外注先に支払い
10,210円は会社が源泉税を納付する制度です。まとめると以下のような表になります。
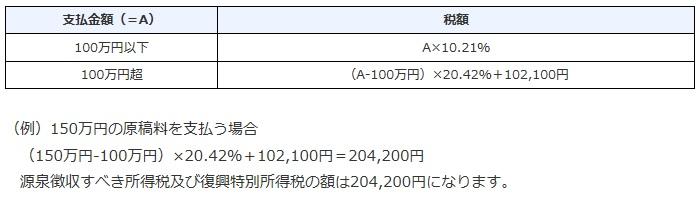
なお、ここでポイントになるのは、
相手先が株式会社や合同会社などの法人なのか、
個人事業主かで源泉税の扱いが変わることです。
【源泉徴収の必要性】 ・外注先が株式会社や合同会社など法人の場合【 源泉徴収の必要はありません。 】
・外注先が個人事業主である場合【源泉徴収が必要 と 不要な場合があります。】
(仕事内容で源泉の必要有無が分かれます)
建設業や建築業で源泉所得税が必要な仕事の範囲
報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の
源泉徴収の対象となる範囲は、
法律で以下のように区分されております。
逆に言うとここで列挙されていないものは、 原則、源泉徴収の必要がないことになるのです。1 原稿料や講演料など
2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、テニスの 選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
5 芸能人や芸能プロダクションを営む
個人に支払う報酬・料金
6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、
客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆる
バンケットホステス・コンパニオンやキャバレーに
勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を
約することにより一時に支払う契約金
8 広告宣伝のため賞金や馬主に支払う競馬賞金
建設業の源泉税計算方法・納付に関係するのは、
・土地家屋調査士の業務に関する報酬・料金
・測量士又は測量士補の業務に関する報酬・料金
・建築士の業務に関する報酬・料金
・建築代理士の業務に関する報酬・料金
などが源泉徴収の対象になります。
逆に個人事業の職人さんの作業に関する報酬は、 こちらに規定されていないため、 源泉徴収の必要がないということになるのです。建設業や建築業の源泉所得税の計算方法
個人の方に外注費を支払う場合で、
上記の源泉徴収対象になる内容の場合には、
所得税を天引きして納税する必要がございます。
それでは、源泉税の計算方法及び納付書記載方法は
具体的にはどのようになるのでしょうか。
1.源泉所得税の計算方法について
① 外注さんから消費税を請求されていないケース
( 請求書で消費税が区分されていない場合 )
・外注費 100,000円(消費税込み)
・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円
・支払額 100,000円-10,210円=89,790円
② 外注さんから消費税を請求されているケース
( 請求書で消費税が区分されている場合 )
・外注費 100,000円(消費税抜き)
・消費税 100,000円 × 10%=10,000円
・源泉税 100,000円 × 10.21%=10,210円
・支払額 100,000円 + 10,000円 - 10,210円
=99,790円
※原則、税込額に10.21%をかけ天引きしますが、
請求書で報酬と消費税が明確に区分されてれば、
税抜金額に10.21%とすることも可能です。
納付書の書き方と納付方法
外注さんからお預かりした源泉税は、
支払った月の翌月10日までに納付書を作成して、
銀行または郵便局で納付する必要がございます。
例:6月30日に外注さんにお支払いした場合には、
7月10日が納期限となります。
納期限より一日でも過ぎてしまいますと、
不納付加算税や延滞税などペナルティを負担する可能性がありますので注意が必要です。
ちなみに不納付加算税は、原則納付額の10%です。
納付書の書き方は次のようになります。
なお、こちらは書き損じがあると金融機関などへ
持参しても納付できないことがございますので、
最低限必要な記載事項に留めてます。
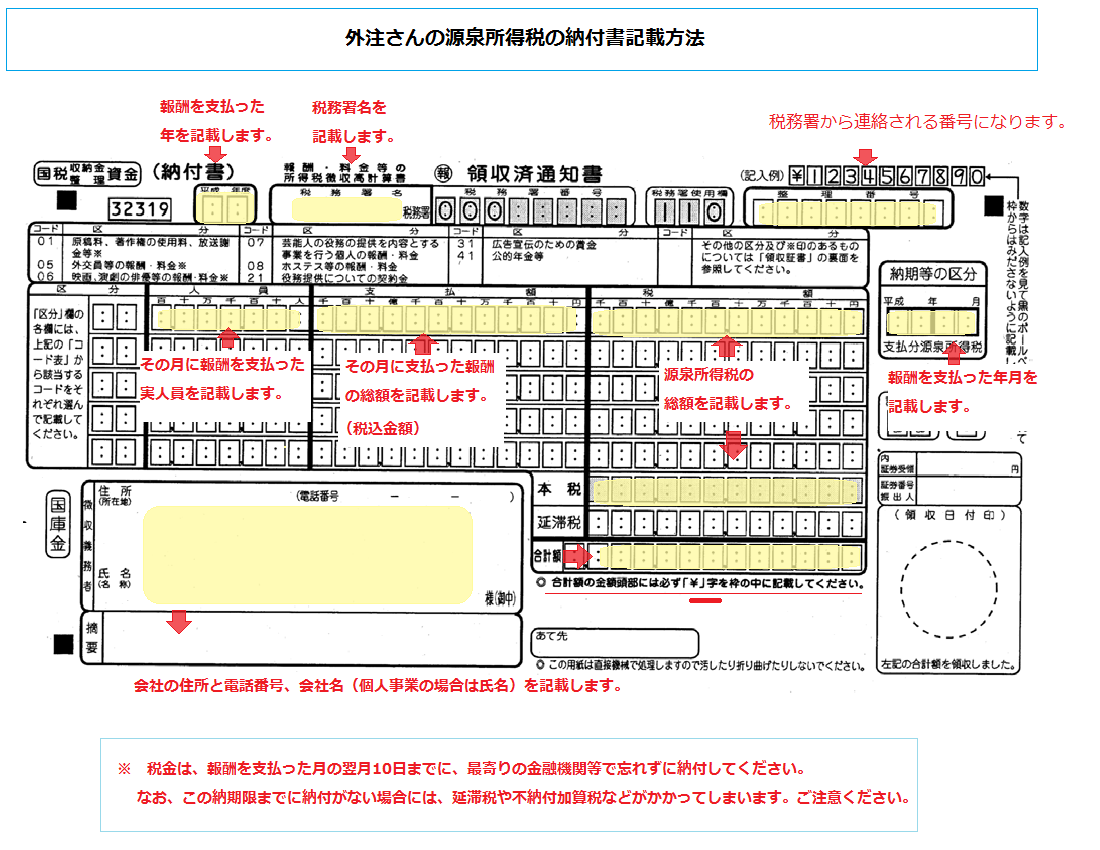
建設業や建築業に強い匠税理士事務所の紹介
匠税理士事務所では、建設業や建築業のお客様が
多くいらっしゃるため建設業や建築業の税務知識や
経営コンサルティングノウハウが豊富など強みがございます。
匠税理士事務所サービスや税理士はこちら

担当税理士や提携専門家はこちらを確認下さい。
【 →自由が丘の税理士は匠税理士事務所】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
建設業・建築業での起業資金調達など
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
建設業・建築業で会社を作るための
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
納付書の書き方など経理教室・経理代行など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人から会社に組織変更するための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
◇建設業や建築業の方に向けたサービスはこちら
○法人のお客様
建設業や建築業でこれから起業をしたい、会社設立をしたい方
建設業や建築業で税理士変更したい方
○個人のお客様
建設業や建築業でこれから独立をしたい、個人事業の方
建設業や建築業で個人事業を株式会社にしたい方
◇建設業や建築業の起業相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#納付書書き方
#源泉所得税納付書
#源泉納付書書き方
ハウスクリーニング・清掃業の会社設立・起業創業・独立開業は匠税理士 (19/03/14)
匠税理士事務所は清掃業の起業支援に強い会計事務所です。
こちらは、これから起業される方に向けた記事となります。
◇既に顧問税理士さんがおり、税理士変更をお考えのハウスクリーニング・清掃業のお客様はこちらです。
清掃業は、開業資金がかからない一方で、 粗利率が高く、どの時代にも必要にされるという非常に魅力的な事業です。
このクリーニング・清掃業で独立開業する場合は、大きく以下の2つが重要になります。
1・・お客様に満足していただける技術力とノウハウ 2・・車両や機材などの初期投資と集客にかかる資金上記の1は、これからクリーニング・清掃業で起業を考えられている方の多くは、
技術力とノウハウには自信があると思います。
したがって起業時の課題になるのは、2の開業資金の確保となります。
クリーニング・清掃業の創業融資による資金調達と起業支援
得意先によりハウスクリーニングなのか、店舗やビルなどの清掃・原状回復業、メンテナンスなのかを問わず、
機材の初期設備投資は必要ですし、
これらを載せて現場へ移動するための車両は不可欠になります。
また、すぐに得意先に恵まれるケースはまれで、
多くの場合は不動産管理会社様やオーナーに自社を知っていただくため営業活動も必要になります。
そのため、会社の維持費で月額固定費の半年分と初期の設備投資の資金を確保しておくことが重要になるのです。
こうした初期設備投資と運転資金で最低300万円、できれば500万円は確保し起業するのが理想です。

創業融資支援サービス
匠税理士事務所では、起業時の資金調達の重要性を熟知しております。
創業融資に強い税理士が計画書作成をサポートし、金融機関との融資面談にも同席し、融資による資金獲得成功を支えます。
日本政策金融公庫と連携した創業融資による資金調達でトップクラスの実績がございますのでクリーニング・清掃業で独立開業の際は、お気軽にご相談ください。
クリーニング・清掃業の起業時の課題を理解した税理士が、創業融資による資金調達を問題解決をお手伝い致します。
◇創業融資支援サービス
◇創業融資の情報館
クリーニング・清掃業の会社設立 | 独立開業サポート
会社で独立開業をするときには、社名や会社の決算期、資本金などをどうするかという基本設計が必要です。
これを誤ってしまうとと
また、
匠税理士事務所では、初回お客様の今後の展望やお考えをじっくりとヒアリングし、最適な会社の設計ができるようサポートします。
【 一生に一度の会社設立成功 】のため 株式会社や合同会社などの会社設立の登記から税務署や都税事務所への届出、<社会保険事務所への手続きなどもお手伝いします。
◇会社設立サービス
◇会社設立の情報館
起業や創業支援に強い匠税理士事務所の特徴
弊所は、【 起業に必要な全てがそろう会計事務所 】をコンセプトに、会計や経理、税務のアウトソーシング以外にも給与計算、社会保険手続きなどの労務、
契約書作成やレビューなどの法務にも対応できる環境をご用意しております。
そのため、提携先の社会保険労務士や弁護士、中小企業診断士などは、各業界でトップレベルの人材でチームを編成しております。
経営のご相談は、世界4大会計事務所出身で、経営セミナーで講師を務める税理士が対応致します。
事業が伸びるにしたがって、見えにくくなる会社の課題
粗利面は適正なのか、資金繰りに問題は無いのか、社員の採用教育面など人事関連は適正かという経営面のご相談もお任せください。

◇所属税理士や提携先の専門家など事務所概要
→ 目黒区自由が丘の40代若手税理士や会計事務所...匠税理士事務所の会社概要
→ 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所...TOPページ

◇ハウスクリーニング・清掃業のお客様向けその他のサービス
既にハウスクリーニング、原状回復工事やメンテナンス管理など清掃業を経営されている方で、
税理士法人や会計事務所の変更をご検討されている方は、下記をご確認いただけますと幸いです。
◇既に顧問税理士さんがおり、税理士変更をお考えのハウスクリーニング・清掃業のお客様はこちらです。
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所で、
ハウスクリーニング、原状回復工事やメンテナンス管理など清掃業の会社設立・創業融資など独立開業支援に強い会計事務所です。
建設業の残業・時間外労働2024年上限規制と建築業人手不足 (19/03/14)
【2024年・令和6年4月】から建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制が始まります。
建設業界の人手不足は深刻で、若手を中心に人材流出をストップさせるため働き方や、環境改善が必要です。
人手不足は他の業種でも深刻ですので、
人材獲得や確保のため改善が進められており、設業界から異業種へ人材流出を止められません。
このような厳しい環境のなかでも、
2024年4月から建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制が始まります。この残業・時間外労働の上限規制に備えるためにも業務効率の見直しや人材の配置などの改善など対策が必要になります。

建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制とはどんな制度
労働基準法では会社に所定労働時間を定めることを義務づけています。
この所定労働時間を超え社員を労働させる場合には【 時間外労働 】となり、以下のような上限が設けられています。
1 残業時間上限は、原則月45時間、年360時間
2 特別な事情がない場合、上限を超えられない
3 特別な事情で、労使合意ある場合も、
年720時間以内、複数月平均80時間内(休日含む)
月100時間以内(休日労働を含む)を超えられず、45時間を超えるのは年6カ月まで。
と残業・時間外労働を法律で定義づけてます。これまでは、建設業は残業・時間外労働の上限規制の適用除外となっていました。
そのため、少数精鋭の会社も、何とか個の力で乗り切ることができたところもあると思います。
この適用除外が2024年3月31日終了します。 2024年4月からは一般企業と同じように上限規制ルールを守らないといけません。
2024年4月からは一般企業と同じように上限規制ルールを守らないといけません。
残業・時間外労働の上限規制は、月45時間ですが
これは1日になおせば約2時間になります。かなり短いのではないでしょうか?
特に建設業や建築業は、仕事の納期との関係や、
地盤の問題など想定外の事項が出てきたり臨機応変な対応が求めらる事業です。
このような特徴からどうしても残業が多くなりがちな事業でもあります。
しかし、このような事をいってはいられません。
仮に2時間を超える残業・時間外労働が常態化している状態であれば、
すぐに業務効率化・人材確保と育成や配置転換などの環境改善など対策が急務となります。
残業・時間外労働の上限規制問題は、工事の進め方を難しくするだけにとどまらず、
割増賃金率大きく上昇するで人件費が増加し、
利益を圧迫することも理解することが重要です。
中小の建設会社の場合、
1日8時間・週40時間を超える残業・時間外労働は、割増率25%で給与計算するように定められてます。
残業・時間外労働は、割増率%を2023年4月以降は50%に引き上げなくてはなりません。
これまでゼネコンなど大企業は割増賃金率50%で義務化されてたのですが、 中小の建設会社にも及ぶ形になるのです。
建設業・建築業界に残業・時間外労働の上限規制によるよる人件費の向上の影響を考えると、
時間外労働の上限規制を超えないように残業削減の努力するだけで業績を出すのは難しくなります。
ならなら、工事で社員が残業すると割増賃金率50%が適用になるわけですから、
人件費アップで給与が上がれば社会保険料も連動して上がりますので、
確保できる利益は減少する展開になります。できるだけ所定時間内で作業を行えるようにし、社員に残業をさせないための工夫が求められます。
建設業の経営支援が充実の匠税理士事務所
匠税理士事務所では、時間外労働・残業規制対応への人員増加、割増賃金等の人件費増に利益確保をどうするか利益戦略コンサルティングを行います。
黒字になるか、赤字になるかは、
【 粗利 】 VS 【 固定費 】で決まります。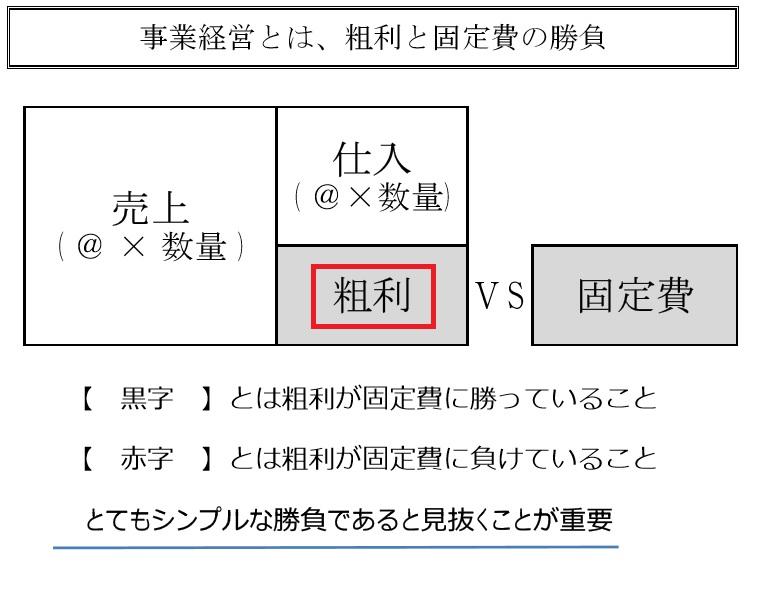
人件費増加で固定費が増えるなら、粗利をそれ以上に増やばいいだけです。
【 弊所には世界4大会計事務所出身 】経営セミナー講師を歴任する40代税理士が所属し独自コンサルティングサービスを用意してます。
これらを通じて、【お客様に利益とお金を残すこと】、
を使命に事業に取り組んでおります。
結果として、多くの建設業の方に支持頂いてます。サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
◇サービスページ
◇法人のお客様
◇個人のお客様
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇相談会建設業許可申請の代行
【 黒字経営サービス 】
財務会計や税務申告、節税対策など建設業に必要な全てがそろう税理士事務所で年商3,000万~10億まで対応可能です。
匠税理士事務所のサービス全般は、こちらでご確認をお願い致します。

2024年4月~給与計算・就業規則も対応人事労務コンサルティング
2024年4月からの建設業・建築業界での残業・時間外労働の上限規制に対応するため
人事労務のスペシャリストである社会保険労務士と連携した人事労務コンサルティングも対応します。
給与計算や組織化のための就業規則など人事労務の専門家である社会保険労務士が
お客様の大切な会社をしっかりとお守りします。
建設業のお客様には、残業・時間外労働2024年上限規制問題も
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】といって頂けるような環境をご用意しております。◇労務コンサルティングサービス
【 → 人事労務コンサルティングサービス 】

建設業界の残業時間や時間外労働に関する2024年4月・令和6年4月からの上限規制と建築業人手不足につき最後まで御覧頂きありがとうございました。
建設業キャリアアップシステム・ccus登録義務化やメリット・デメリットとは? (19/03/14)
建設業界は、リニア・万博・マンションなど工事増加に対し
人材確保が追い付かない人手不足状態にあります。
更に2024年4月から残業上限規制が始まり、 この人手不足の状況は加速するものと思われます。この人手不足が深刻化する建設業界対策一環で
国土交通省が建設キャリアアップシステム・CCUS制度を始めてます。
建設キャリアアップシステム・CCUSでは、
建設業に関する社員の保有資格や社会保険加入履歴、就業履歴等を管理する制度目的があります。
国土交通省は2023年度から「全工事でCCUSの完全実施」を目指しており
大手ゼネコンなど建設会社のみの制度ではなく
中小建設会社に関係する制度です。
(将来、ccus登録義務化は想定されます)
建設業界や建築業界のマイナンバーカードのように
中小建設会社から大手のゼネコンまで全ての建設業を対象にしたいという制度となります。
 建設キャリアアップシステム・CCUSの具体的な制度運用ポイントは以下のようになります。
建設キャリアアップシステム・CCUSの具体的な制度運用ポイントは以下のようになります。
1 技能者情報を登録したICカード・ccusカード交付
2 登録技能者が現場に入る際、ccusカード読み取り
3 登録技能者ごとの現場就業実績・研修受講記録
4 登録技能者のレベルでCCUSカードが
4段階のレベルに色分けされる
5 所属技能者のレベルや人数等に応じ
施工能力が4段階レベルで格付けされ、
団体・国土交通省サイトで公示される

建設キャリアアップシステム・ccusメリット・デメリットの解説
建設キャリアアップシステム・ccus最大のメリットは、
登録技能者の技術・専門性が把握可能になる点で工事の元請け事業者に対し
「自社にはこうした有資格者が在籍している」
ということをしってもらいやすくなります。
会社の専門性や技術力を先方に伝えられれば、 良さをしってもらうことで利益を確保した 【適正な売価】の設定が行えます。確保した利益で建設業界・建築業界の社員の方は
技術力・専門性を示しやすくなり、給与アップなど
待遇改善が期待できます。
また、これまでは建設業界や建築業界で
負担だった工事作業員名簿の作成や、
建設業退職金共済(建退共)の手続きも
建設キャリアアップシステム・CCUSで効率化されます。

建設キャリアアップシステム・CCUSが
普及しづらい要因でもデメリットとしては、
システム利用でコストがかかる点です。
登録料は会社資本金に応じ、負担額は変わります。
また、これとは別にシステム管理者ID利用料金、現場利用料を支払う必要があります。
建設キャリアアップシステム・CCUSの費用は、初回登録時支払えば終わりではなく、
登録料は5年、管理者ID料は毎年かかります。
更に現場利用料は工事現場で作業員が
勤務する都度料金が生じます。
建設キャリアアップシステム・ccusを導入するときは、
社内の環境を整備し効率化が出来たり、
得意先が建設キャリアアップシステム・ccusを正しく評価し
売価に反映してくださるような会社が
得意先に多いようであれば
【 メリット > デメリット 】となりますので、CCUSは実行ですが、逆でれば単に負担が増える形になってしまいます。

キャリアアップシステム・ccus登録義務化前にすべき事
社員の技術力や専門性が分かりやすくなることは
人材が充実している建設会社はプラスに働きます。
なぜなら社員の技術力や専門性で、新規工事の受注や優秀な人材獲得などにつなげることができます。
一方で高い技術力や専門性を有する人材が
現在でも不足している建設会社は、
ますます優秀な人材や工事を獲得することが
難しくなる可能性があります。
建設キャリアアップシステム・ccusの普及率が向上し
加入しなければ工事できない状況になる前に
高い技術力・専門性を有する優秀な人材獲得に
動かなくてはいけません。
そのためには、自社の強みと弱みを把握した上で
利益を増やし、良い会社になる事が大切です。
建設業や建築業に強い匠税理士事務所
匠税理士事務所では、
建設キャリアアップシステム・ccusに対応し、
魅力的な会社作りのため利益をいかに確保するか
利益戦略コンサルティングを行います。
世界4大会計事務所出身で経営セミナー講師を 担当する40代税理士がコンサルティングを行います。これらを通じて、
【会社様に利益とお金を残すこと】を使命に事業に取り組んでおり、
結果建設業・建築業のお客様に支持頂いてます。
サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
規模は年商2,000万~10億まで対応可能です。
匠税理士事務所はこちらでご確認下さい。

担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
建設キャリアアップシステム・CCUSの取得運用代行
匠税理士事務所は建設業専門の行政書士と連携し
建設キャリアアップシステム・ccus取得運用代行を行います。
制度の内容について聞いてみたい、
毎年の更新業務なども含め全て任せたい
このようなご要望にもしっかり対応します。
料金は社員数と資本金にもよりますが、
【 3万円~ 】にて承っております。
詳細は会社規模を伺って個別見積りとなります。
お気軽にお問い合わせください。
ccus登録義務化に備え建設業キャリアアップシステムにつき
話を聞いてみたいという方もお気軽にご相談下さい。
また建設業許可申請・更新代行をご要望の方は、
こちらをご確認ください。
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
◇サービスページ
◇法人のお客様
◇個人のお客様
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
【 黒字経営サービス 】
◇その他お役立ち情報はこちらよりご確認下さい
建設業キャリアアップシステム・ccus登録義務化や
メリット・デメリットとはどんな制度なのか?
について御覧頂きありがとうございました。
匠税理士事務所ではccus登録義務化に備えた
建設業キャリアアップシステム申請代行に対応しております。
お気軽にご相談下さい。
対応エリア:世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
建設業キャリアアップシステム対応の会計事務所です。
執筆者・文責:税理士 水野智史
土木や解体工事など一般建設業許可業種・資格登録要件とは (19/03/14)
建設業・建築業に強い匠税理士事務所サイトへご訪問ありがとうございます。
弊所では多くの建設業の会社様の経営支援に携わっております。
この建設業・建築業で非常重要なのは、
1 一般建設業許可の資格登録 2 安定した運転資金の確保この2点です。
建設業の最大の特徴は、1回当たりの取引金額が、大きいことです。
そのため、受注から納品までしっかり経営できれば、大きな利益を上げれるという特徴があります。
この特徴を最大限に活かすためにも、
【一般建設業許可の資格登録】と【運転資金確保】が必要になるのです。
一般建設業許可の資格登録のメリットと要件
一般建設業許可の資格登録する最大のメリットは、
1件請負金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の大規模案件受注が可能になることです。逆に一般建設業許可の資格登録がされていないと、次のような軽微工事しか請けられません。
・建築一式工事では、1件の請負額が1,500万円未満の工事、
・木造住宅(延床面積の1/2以上が居住用の建物)で延べ床150㎡未満
・建築一式工事以外の工事は、1件の請負額が500万円未満の案件
これらの軽微工事しか請けられなければ、
建設業・建築業の最大の強みである1回当たりの取引金額が大きいことに制限がかかってしまいます。そのため、匠税理士事務所では、建設業・建築業で事業経営をされるお客様に一般建設業許可の資格登録を提案致しております。
 【 それでは一般建設業許可の資格登録の要件にはどのようなものがあるのでしょうか? 】
【 それでは一般建設業許可の資格登録の要件にはどのようなものがあるのでしょうか? 】
一般建設業許可の資格登録要件には、大きく以下の項目があります。
1・常勤役員等
2・専任技術者
3・営業所
4・誠実性
5・欠格要件
6・社会保険
7・財産的基礎
これらをすべて満たせれば、一般建設業許可の資格登録ができます。
一方で許可業者で1つでも要件を欠くことになれば一般建設業許可の資格登録は失効します。
上記のうち1~5まではこれまでの経歴、積み重ねとなりますが、
会社設立など起業創業で気をつけたいのは、 社会保険と財産的基礎となります。
社会保険(健康保険・厚生年金)及び雇用保険に入っていなければ、
一般建設業許可の資格登録は出来ないということになりますので、
資格取得をしたいタイミングを考えた社会保険の加入が重要になるということです。
一般建設業許可資格登録の財産的基礎要件
一般建設業許可の財産的基礎要件とは、簡単にまとめると以下の通りです。
【 財産的基礎要件 次のいずれかに該当すること 】
①自己資本額(純資産合計)が500万円以上
②500万円以上の資金調達能力があること
③直近5年東京都知事許可を受け継続営業した実績
一言でいうと大きな案件を行えるだけの体力・実績があるかということです。建設業は扱う金額も大きいので、途中で案件がストップしてしまうと、
社会へに与える影響も大きいため財産的基礎要件は厳格なものになっています。
一般建設業許可の資格登録業種の区分
このように様々な要件をクリアすることで、
一般建設業許可を以下の区分に応じて資格登録することになります。
一般建設業許可の資格登録は、2種類の一式工事27種類の専門工事の計29業種に分かれます。

建設業許可の区分別29業種
土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび・土工・コンクリート工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイル・れんが・ブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事
匠税理士事務所では、一般建設業許可の資格登録など専門の行政書士と連携し、
一般建設業許可資格取得の新規申請を代行します。
詳細はこちらからご確認下さい。↓
特定建設業許可の資格登録をご検討されている方はこちらをご確認ください。
一般建設業許可の後は資金確保が大切
それでは、残りの課題の資金の確保に移ります。
大きな工事を請けることが出来る資格登録ができても、実際に仕事を受注して、無事工事納品し、入金完了という取引を実行しないと、
会社の成長はありえません。
建設業界や建築業界は、一回当たりの工事金額が大きくなり、完成時に大きな売上が上がる一方で、完成まで材料費や外注費といった経費が多額になる
【ハイリスク・ハイリターン】な面があります。
そのため、工期延期などによる入金時期の遅れなどにも対応できる安定した資金を有しているかが、
とても重要になるのです。
安定した資金を常に有している会社は、複数の工事も同時並行で対応することが出来ますし、
外注先活用など豊富な選択肢がとれます。
逆に資金が不足すると、入金遅れの連鎖倒産や、
工事の受注能力に制限がかかり、一件の工事が終わり入金があってから、
次の案件にかかるというスピード感にかける展開になってしまいます。
このように建設業界や建築業界では、
【一般建設業許可の資格取得】と【資金確保】が事業成功のポイントになるのです。匠税理士事務所には、建設業に強い世界4大会計事務所出身の税理士が所属しており、
世田谷区や目黒区、品川区のエリアでトップクラスの融資成功率がございます。
日本政策金融公庫や各種金融機関も連携して事業計画書の作成支援や、
融資面談の立ち合いなど普通の会計事務所では行わない内容もしっかりサポートします。

◇その他のお役立ち情報は、こちらよりご確認下さい
建設業界や建築業界向け黒字戦略とキャッシュ経営
◇サービスページ
◇法人のお客様
◇個人のお客様
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
【 黒字経営サービス 】
◇一般建設業許可や特定建設業許可の資格登録の申請に対応の匠税理士事務所

一般建設業許可資格や特定建設業許可の資格取得の申請や更新手続き代行以外にも対応しております。お気軽にご相談下さい。
最後までご覧頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
補助金申請代行の中小企業診断士・行政書士との提携募集 (19/03/14)
匠税理士事務所では、お客様の補助金申請代行に対応していただける
中小企業診断士の先生・行政書士の先生との提携を募集しております。
事業再構築補助金やIT補助金など各種制度に基づく補助金が発表されるたびに、
タイムリーに情報をキャッチアップし、お客様にご提案していただき、
補助金の申請代行までサポートしていただけるような中小企業診断士の先生・行政書士の先生だとありがたいです。
私たちが、業務提携先や事業提携先に求めることは、
それぞれの分野の専門家が、その専門性を発揮することを通じて、
「 お客様の利益の最大化に貢献できること 」 です。この理念に共感して頂ける方は、匠税理士事務所の税理士水野宛に
メールの場合には、WEBサイトのお問い合わせフォームよりメールを送信願います。
世田谷区目黒区、品川区を中心とする匠税理士事務所について
弊所は世田谷区や目黒区、品川区など東京都を中心に起業・創業支援に力を入れている会計事務所です。
そのため、30代から40代の経営者の方が多く、業績が伸びている会社様が多いのが特徴で、
機材や大型車両の購入、新店舗や新規ビジネスモデルの構築といったニーズの設備投資の際に、
補助金のご相談を頂くことが多くございます。
このようなご要望にも適格にお応えできる事務所づくりを行いたいと考えております。
現在の社会保険労務士の先生や司法書士の先生とは、10年以上の付き合いとなり、
今回の補助金申請専門の中小企業診断士の先生・行政書士の先生ともこのような関係を築ければと考えております。
もちろん、補助金の申請代行に必要な決算書や税務申告書などの書類などにつきましては、
お客様よりご了承を頂けましたら、連携して全面的にご協力致します。
匠税理士事務所との業務提携をご検討頂ける方は、一度ご連絡を頂けましたら幸いでございます。
弊所の所属税理士やスタッフ、提携先など事務所の概要につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
目黒区自由が丘の40代若手税理士や会計事務所は匠税理士事務所

最後までお目通し頂きありがとうございました。
匠税理士事務所のサービスラインや料金など全体事項につきましては、
こちらよりご確認下さい。
世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所
工務店や建設会社・建築会社の会計事務所は匠税理士事務所 (19/03/14)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は工務店や建設会社・建築会社に強い事務所で、
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に儲けをお金として残し、会社の財務を強くする
【 経営コンサルティンング 】に力を入れています。工務店や建設会社・建築会社の経営のポイントは
1 【お金がたまる】入金 と 出金の仕組み作り 2 【豊富な資金】を【低金利】で調達する事です。これは、他業と比較し多く資金が必要なためです。
一件当たりの受注金額が、数百万から数千万という
売上に対して、原価も約7割から8割生じて、
工事期間も比較的長くなるため、サービス業などに比べて一時的に立て替えるお金の金額と期間が長く
資金を多く必要とするという性格に起因します。

例えば、入金と支払いのサイクルで考えると、
①・・入金は概ね1~2か月後(1.5か月)
②・・工期は概ね1ヶ月~2か月(1.5か月)
③・・支払いは1ヶ月後という標準的な会社なら、
1.5か月 + 1.5か月 - 1ヶ月 = 2か月分不足です。仮に会社を維持する人件費・家賃で月500万なら
500万×2か月=1,000万資金が必要となります。
これを入金1か月後、支払2か月後にできれば、
1か月 + 1.5か月 - 2ヶ月 = 0.5か月分不足となり500万×0.5か月=250万の対応でよいわけす。
事業拡大で維持費が500万から1,000万になれば
この問題は更に大変になってしまいます。

もちろん相手先との交渉が必要になりますが、
何もしなければ貯まりやすい会社になりません。
【 入りは早く、出は遅く 】この原則を抑えた
地道な努力と交渉、取引先探しが第一に必要です。
このお金がたまりやすい仕組みが出来れば、
次は【豊富な資金】を【低金利】で調達します。
【お金がたまる仕組み=頑丈な容器】を作って 【お金という大量の水】を流し込むわけです。これは、より多くの資金を保有している会社は、
同時に大型の案件をこなすことが可能となり、
より稼ぐことができることを意味します。
逆に資金量が少ないと受注数に制限が生じ、
完成による利益 ≒ 完成までの会社維持費となり中々お金と利益がたまりにくいことも意味します。
これは、雪だるまを作るときに、
最初からある程度大きい雪玉の方が、
加速度的に大きくなるイメージと近いものがあり
【所有資金と会社の成長速度】は比例するのです。
工務店や建設会社・建築会社は融資が重要
借入が嫌いだという社長様もいらっしゃいます。
無借金は素晴らしいことだと思いますが、
【 A 預金1,000万の 無借金会社 】
【 B 預金1億円・借入金1億円の会社 】
はどちらが成長するでしょうか?
答えは、Bの預金1億円・借入金1億円の会社です。
なぜなら預金1,000万の無借金会社は、
預金1,000万の範囲でしか、
外注先・材料仕入れができないため、
規模の大きな工事を請けられないからです。
借入が嫌なら、預金口座にそのまま置いておき
大型案件が来たら動かし、入金後は利益分増える。
そして雪だるまのように預金残高は増えていく。利息は、金利1%~2%程なので、
利益率がこれを超えればプラスの取引となります。
現在、借入が嫌で無借金であるが、
中々利益が出ないという会社の場合は
資金調達でお金の力を利用すべきだといえます。
社長の力のみではなく、お金を活用=人や外注先、設備投資・工事機械の活用となるわけです。
 資金調達をしても、高級車など私用で使わず、
資金調達をしても、高級車など私用で使わず、事業へ適切に投下するという考えがあれば、
融資・借入は怖くなく、お金の力を利用して会社を成長させることが出来るのです。
それでは、資金調達で一番のポイントは
何でしょうか?
融資による資金調達の成功で大切なこと
金融機関や日本政策金融公庫に融資を申し込むと、
1 融資希望額の【満額】の資金調達成功
2 融資希望額の【一部のみ】の資金調達
3 融資してもらえない
融資結果は、この3パターンのどれかになります。結果が早く分かれば、事業規模のを拡大・縮小や、
他の金融機関で資金調達の検討が行えます。
逆にこの融資の結果が遅れると、
仕事を受けたが、資金繰りがまわらない
大型案件が来たが請けられない
といったことが起きてしまいます。
上記のように工務店や建設会社・建築会社融資は、
申し込みのタイミングが最重要なのです。1 【現在、黒字。晴れている。】
2 【現在、黒字だが、曇るかもしれない】
3 【回復の傾向にある。曇りのち、晴れ】
この3パターンであれば、
資金調達はかなりの確率で成功できます。逆に、
1 現在赤字
2 以前は黒字だったが、最近は赤字続き
このパターンを金融機関は嫌がります。匠税理士事務所では、決算書や試算表を確認し、
適時タイミングよく、適切な融資をご提案し、資金を獲得できるようコンサルティング致します。
資金計画表や利益戦略など経営セミナーで講師を務め、
融資成功率は9割を超える実績を有しており、これまで工務店や建設会社・建築会社の方に
多くのご支持を頂ております。
匠税理士事務所のサービス・料金はこちらから
【 → 起業と黒字戦略の匠税理士事務所】
担当税理士や提携専門家はこちらをご確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の概要】

工務店や建設・建築会社の節税対策と税務調査
お金の調達に成功するとスタッフや外注先を活用して
仕事を完了させ利益を増やするようになります。
安定した資金調達に成功すれば、
より多くの人間・材料を動かせますので、
利益が出るようになります。

利益に対し約3割が税金として課税されますが、
利益は出来る限り社内にためておき、
不景気や臨時的な事故などに備えるという考えから節税対策は非常に重要です。そしてこのように節税対策をして、
決算税務申告を行います。
申告内容に疑問があると税務調査が行われます。
合法的に節税対策をすることは問題ないですし、 税務調査で何も心配する必要がない事になります。 このように利益を出して、効果的な節税対策を行い社内の蓄えである内部留保を増やして、
このように利益を出して、効果的な節税対策を行い社内の蓄えである内部留保を増やして、
【 会社を強くすること 】が、工務店や建設会社
建築会社の発展には非常に重要なのです。
工務店や建設会社・建築会社など建設業に向け、
世界4大会計事務所出身の税理士が、節税対策や経営コンサルティングを行います。
工務店や建設会社・建築会社など建設業を担当する税理士の詳細につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
年商2,000万~10億まで広く対応可能です。
法人のお客様向けサービス一覧
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
起業のお客様向けサービス一覧
【→ 起業されるお客様向けサービス一覧】
個人の方向けサービス一覧
【→ 個人の方向けサービス一覧】
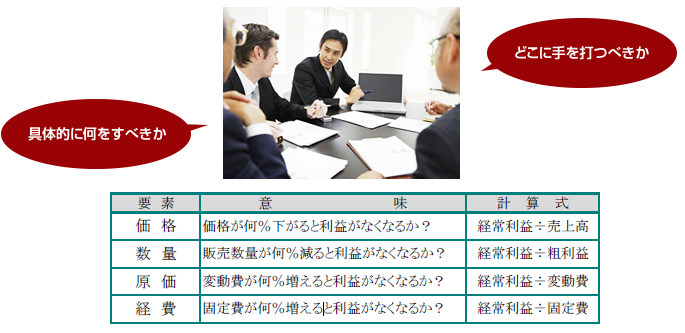
【 弊所独自の経営コンサルティングサービス 】
建設業許可申請の代行をご要望の方は、
こちらをご確認ください。
以下で起業や経営お役立ち情報を記載してます。
株式会社や合同会社など会社設立サービス詳細はこちらからご確認下さい。

日本政策金融公庫や金融機関の創業融資の詳細はこちらからご確認をお願いします。

弊所では、関与先の9割以上が黒字経営という実績を有しております。
匠税理士事務所で執筆致しました経営に関する記事につきましては、
こちらからご確認をお願い致します。
利益とお金がたまる会社づくりのポイント解説はこちらからご確認下さい。
【 利益が残る、利益が増える会社づくりのポイント解説 】 【 お金がドンドンたまる会社づくりのポイント解説 【 建設業や建築業の経営事項審査(経審)とは?簡単に解説 【 一般競争入札と指名競争入札とは何かをわかりやすく解説東京都23区を中心とする匠税理士事務所について
建設業や建築業で起業・創業・独立をお考えの方で
株式会社や合同会社などの会社設立をお考えの方はこちらからご確認をお願い致します。【関連記事 →建設業や建築業の会社設立・創業融資なら匠税理士事務所 】
【関連記事 →工務店やリフォーム・内装の会社設立・創業融資・起業は匠税理士 】
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所です。
建設業の企業様向け匠税理士事務所の経営サポート詳細はこちらからご確認下さい。
建設業や建築業で個人事業主化から株式会社や合同会社など会社にしたい方向け法人化こちらから
今回は工務店や建設会社・建築会社の経営ポイント
についてまとめてみました。
こちらは、既に顧問税理士さんがおり、
税理士変更をお考えの工務店や建設会社・建築会社
のお客様に向けたページとなります。
◇これから起業される方はこちらからご確認下さい

工務店や建設会社・建築会社に強い税理士は、世田谷区や目黒区、品川区、大田区、渋谷区など東京都や川崎市・横浜市など神奈川県全域に対応しております。
執筆者・文責:税理士 水野智史
電気工事、通信、管、機械器具設置工事など設備に強い匠税理士 (19/03/14)
ホームページをご確認頂きありがとうございます。
弊所は建設業や建築業に強い会計事務所です。
今回は建設業許可に定める工事業種全29業種のうち
電気工事・電気通信工事・管工事・機械器具設置工事、
建物内インフラ工事である設備工事の経営ポイントを
下記にてまとめました。

電気工事・電気通信・管工事・機械器具設置工事の経営ポイント
設備工事業は、工事を行うための材料仕入と 人件費の原価のため資金が多く必要になります。
そのため、当分野で会社設立し起業創業する方に、
日本政策金融公庫の創業融資を提案しています。
また、すでに会社を経営されているお客様には、
資金繰り表の作成や大型案件受注時には、
経営安定化の観点から融資を提案しています。
◇電気工事は、なぜ資金に経営ポイントがあるのか
例えば、納品から2か月後に入金がされ、
工期は一か月、材料費など原価は1か月後払いでは
工事期間1か月間の運転資金、工事完了後の材料と
外注費の原価支払いをしてから2か月して入金。
無事に工事代金が入金されたとしても、
立替のお金がかなり必要になるというわけです。

この他にも資材を運ぶ車両など初期の設備投資が
多くかかるという特徴もあり、
また技術力が問われますので社員の方の採用と、
育成といった人的投資も必要になります。
このような投資をしっかりと行えれば、
比較的粗利率が高い事業ですので、
中長期で利益が出やすいのも特徴です。 経営ポイント① 事業骨格をお金がたまる体質に変えること
② しっかりと利益を出すこと
③ ①と②を実施後、融資を積極的に検討する
④ 技術力や設備にしっかりと投資すること

電気工事・電気通信・管工事・機械器具設置工事など設備工事はお金の力を活かすことが重要
設備工事業の商流を大きく区分しますと、
1 お客様のご要望を伺い、工事全体像をイメージ
2 材料の仕入れ
3 工事を行い設備を設置する
という流れとなります。
1の全体像のイメージと全体の統括・管理は
自社で行い、2と3は仕入先・外注先と連携という
スタイルでの経営が多くなります。
結果として、お金が多ければ多いほど販売面では、
営業にお金をかけられ、生産で材料を多く仕入、
多くの外注先を活用して多く工事を行えますので、
比較的利益が出やすくなる好循環が生まれます。
逆に資金力がないと工事を上記のような流れで
行えなくなるという悪循環になり、
人件費や家賃といった固定費を粗利でまかなえず、 赤字経営にもつながってしまいます。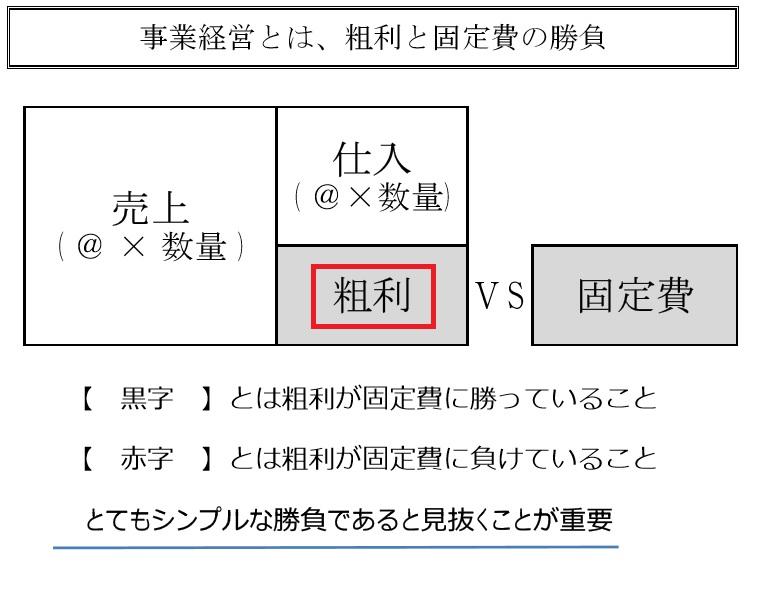
ここでポイントになるのは、融資でお金を
調達できればOKではない事です。
電気工事・電気通信・管工事・機械器具設置工事など
設備工事はお金を必要としますので、
1 入金は早く
2 支払は遅く
3 工事期間は出来る限り短く という
【お金がたまるサイクル=お金がたまる仕組み】を
作っておくことが一番重要です。
お金がたまる仕組みを作った上で、 外部から資金調達をするのがポイントです。

この仕組みがないと、穴が開いたバケツに
水を入れるようにお金が流出してしまいます。
上記のお金がたまる仕組みは、
理論的には簡単に感じますが、
商売は相手がありますので、
地道な交渉と良い関係を築ける業者の方を
探すという積み上げが必要となります。
お金がたまる仕組みを作って資金を調達し、
お金の力を活用し、着実に工事をこなして利益を
出す型が設備工事経営のポイントだと考えます。
後はこの稼いだ利益を人材の獲得と育成、
これをサポートする人材に投資するということで
事業の成長速度が加速度的に増します。設備工事など建設業に強い税理士が所属する会計事務所
匠税理士事務所には、設備工事など建設業の
経営コンサルティングに強い税理士が所属しております。
【 儲かって利益が残り、お金が増える会社作り 】のお手伝い想いの基、会計・財務データを
活用した経営コンサルティングを行います。
世界4大事務所では大手ゼネコンも担当し、
経営セミナーで講師も担当しております。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

設備工事など建設業のお客様向けのサービス
◇建設業の許可申請
◇日本政策金融公庫と提携した融資など資金調達サービス
◇サービスページ
◇法人のお客様
◇個人のお客様
・建設業や建築業で個人事業主化から株式会社や合同会社など会社にしたい方向け法人化
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇お役立ち情報
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所です。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#電気工事税理士 #設備工事税理士
建設業界・建築業界で利益を出すには工事と人材選択が重要 (19/03/14)
匠税理士事務所では、建設業の会社様の経営支援に力を入れています。
2008年のリーマンショックの不況時から現在までの流れを見ると、大きな変化が起きています。
それは、発注先が下請け会社を選ぶという流れから
【下請会社】が、工事内容で元請を選ぶ流れです。この兆候の原因はシンプルです。
【職人が、工事量に対し不足しているからです。】
2024年から建設業界・建築業界でも残業時間規制がかかるなど人手不足の問題はより深刻化することが予想されます。

それでは、どのように経営するか?
答えはシンプルで、技術力が高い社員を、より良い条件の工事にあてて利益を上げる。
この結論に至るのではないでしょうか?
逆に案件を選ばなければ、利益確保ができない。
利益確保できなければ、社員さんの給与・賞与など待遇改善や採用教育活動が出来ず、
人材退職で戦力が低下し、受注がままならない事態につながります。
この理由のため、受注する工事案件を選ぶと事は、とても重要なのです。建設業界・建築業界で工事を選ぶには自社を選んでもらえるかが大切
それでは、より良い条件工事を選ぶにはどうすればよいのでしょうか?
それは、【 多くの発注先から声がかかる会社になる。】
それでは、どんな特徴で選んでもらうようになるかということですが、大きく2つに分かれます。
1 低価格で選んでもらう → 【 工事量で勝負 】 2 経験値や施工管理など技術力→ 【 質で勝負 】どちらも立派な戦略ですので一概にどちらが良いとはいえませんが、
1を選んだ場合は低価格なため、社員さんの給与や家賃など会社を維持するため最低限かかる維持費である固定費を確保するために、ある程度の工事量をこなさなければ必要粗利確保ができません。
ある程度の工事数を完了させるには、大量の人手が必要になります。

一方で2を選んだ場合は、発注先は経験や技術など品質を求めてますので、
値段勝負よりは、これまでの実績や社員さんの保有資格・特許技術などで勝負になります。
一取引当たりの金額が大きければ、数をこなす必要はないので、
比較的会社を維持していくために最低限かかる維持費である固定費分の粗利確保が可能になります。
もちろん、工事数は少なくて良いので、人手はあまり要しません。
【 粗利>固定費なら黒字 】で、逆なら赤字。事業経営は至ってシンプルです。
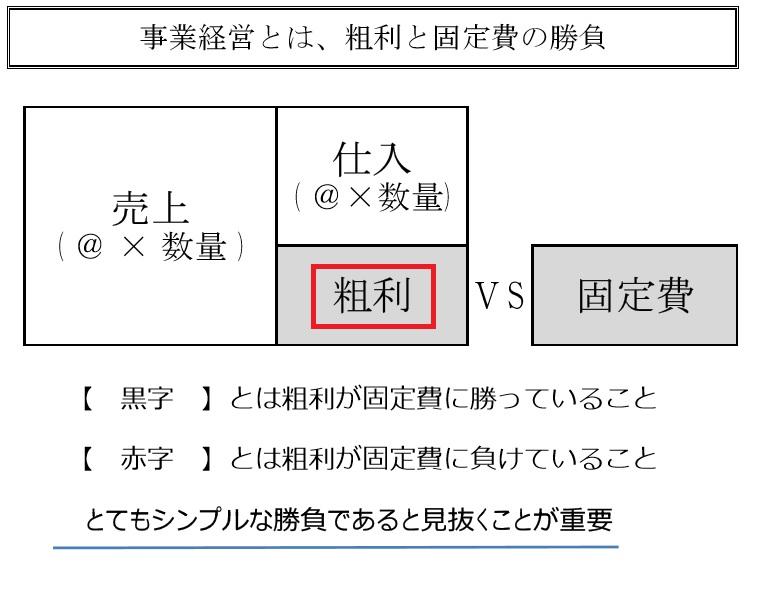 それでは、人手不足が深刻な現状でどちらの戦略が有利かというと、
2の品質で選んでもらうことが重要になわけです。
それでは、人手不足が深刻な現状でどちらの戦略が有利かというと、
2の品質で選んでもらうことが重要になわけです。
しっかりとした売価で、利益が確保が出来れば、
採用活動・育成・社員の待遇改善が出来るため、優秀な人材が集まりやすくなります。
そして応募して下さる人が増えれば、その中から優秀な人材を選ぶ。
選ぶことが、【利益の源泉】というわけです。逆に低価格で利益確保が出来なければ、優秀な人材は辞めてしまい、
採用活動もできないため補充がきかず、工事できないというマイナスサイクルに陥ります。
【 良い仕事の獲得→利益確保→人材強化・育成 】プラスのサイクルが非常に重要なのです。

建設業の販売営業とは?受注増加には何をすればよいのか?
販売営業、具体的に何をしたら良いか・・
方法は色々とあると思いますが、
【自社の良さを知ってもらう】これが営業です。知ってもらうための努力は、予算と投下時間を決めて全てやる。
例えば下記のような方法が考えられます。
・自社のこれまでの実績など掲載したHPを作る
・SNS等で現場の様子や会社の雰囲気を発信する
・取引のある会社様に新商品の案内をする
これらは当然のことように感じますが、実施すれば色々な会社の方に知ってもらえます。
そして、知ってもらえれば、自社を選んでもらえる可能性は上がります。
バッターボックスに立たなければ、打てません。それでは、知ってもらっても、選んでもらえない・声がかからなければ、どのようにすれば良いでしょうか?
【答えは、選んでもらえるよう、声がかかるように改善する事だと思います。】
・実績がなくて選んでもらえない。
・高度な技術者・資格の保有者がいない。
・有名な得意先がなかったり、販売網を持っていない。
この問題なら、最初は実績のために価格勝負し、実績ができて声がかかるようになれば、価格はもとに戻して(上げていき)、利益を確保できるよう直していくことも選択肢です。
・実績ができたら、大手有名先から声がかかるような特殊技術・工法に磨きをかける
・資格取得を自ら行う又は技術取得のための研修に投資する
このように選んでもらえるように、質で勝負できるような会社になるように経営者が強い信念をもって経営を行うことが重要です。
 販売実績が豊富な会社で、一流の有名企業と取引をしていて、
高度な技術者・資格保有状況が、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録されている。
販売実績が豊富な会社で、一流の有名企業と取引をしていて、
高度な技術者・資格保有状況が、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録されている。
色んな会社からオファーがかかる気がしませんか?
このような会社づくりをじっくりと進めていく、そして、随時知ってもらうことに力を入れる。
【知ってもらい、選んでもらい、その中で選ぶ】これが建設業の販売営業で大事だと考えます。
建設業界・建築業界が専門の匠税理士事務所
匠税理士事務所は、お客様の黒字化に豊富な経験とノウハウがある会計事務所です。多く経営セミナーを担当する世界4大会計事務所出身の税理士が、黒字化の経営コンサルティングを行います。
建設業界・建築業界の粗利率は平均20%ですが弊所ではお客様と一緒になって毎月改善に取り組み平均で粗利率30%~40%となっております。
各種経営支援サービスラインにつきましては、こちらよりご確認下さい。
→ 世田谷区・目黒区・品川区の税理士は黒字戦略の匠税理士事務所

◇サービスページ
◇法人のお客様
◇個人のお客様
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。

◇お役立ち情報
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
建設業界や建築業界向け黒字戦略とキャッシュ経営
【 黒字経営の情報館 】
【 黒字経営サービス 】
◇事務所の概要
税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域と神奈川県
特定建設業許可の資格取得まで建設建築業界で成功するには (19/03/14)
建設業に強い匠税理士事務所のHPへご訪問ありがとうございます。
建設業界や建築業界は、大きく3つのステージ に分かれます。
1 社長一人の規模・・・・・・・・・・年商3,000万円
2 社長・社員数名の規模・・・・・年商3,000~3億円
3 社長・社員10名以上の規模・年商3億円~

どのステージが良いということはなく、生き方や、経営観によりますが、
建設業界や建築業界で会社を大きくしていきたいという場合には、
【 現状より少し大きいサイズの容器を用意する 】 これが重要です。そして、この容器が一杯になったら、もう少し大きい容器に変える。
これがポイントです。
そして建設業での容器が、建設業許可になり、この資格が重要で、一般許可をお持ちの会社は、すぐに特定許可の資格取得の準備をおススメします。
例えば一般建設業許可があれば、
1件の請負工事が500万円以上 (建築一式工事では1,500万円)の工事を受けることが出来ます。
一件500万円程の中型工事を数回受注できれば、上記のステージ2の年商3,000万までは到達しやすくなります。

一般建設業許可を取得するための財産要件は下記のようになります。
【 次のいずれかに該当すること 】
①自己資本額(純資産合計)が500万円以上
②500万円以上の資金調達能力があること
③直近5年東京都知事許可を受け継続営業した実績
(今回は財産面の要件のみ記載します。)
一般建設業許可取得し事業を伸ばし、
年商が3億円に到達、事業的に成功してくると、特定建設業許可が視野に入ってきます。【 特定建設業許可 】を取得すると発注者から直接請け負う元請の立場で、
4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の金額を下請会社に外注する
【大規模工事】が請けられるようになります。
例えば、発注者から1億円で受注した工事を協力会社など外注先に6,000万で工事を進める場合です。
このような大規模工事受注には、特定建設業許可の資格取得を行う必要が出てきます。
特定建設業許可の資格取得
それでは特定建設業許可の資格取得は、どんな要件があるのでしょうか。
特定資格の財産面の要件のみを記載してみますが、かなり厳しい要件となります。
 【 次のすべてに該当すること 】
【 次のすべてに該当すること 】
①欠損額が資本金額の20%以下であること
②流動比率が75%以上
③資本金額が2,000万円以上
【 ④自己資本額(純資産計)が4,000万円以上 】
建設業や建築業の多くの会社様の税務顧問をさせて頂いておりますが、
特定建設業許可の資格取得成功は高難易度です。
一番の壁は、自己資本(資本金 + これまでの利益の累積が4,000万)という要件です。これは、仮に資本金が5,000万円で会社を設立してもその後、赤字が続き2,000万累積赤字があれば
5,000万円‐2,000万=3,000万が自己資本となり、アウトというわけです。
そのため、特定建設業許可の資格には、単に預金残高が多いだけでは難しく、
会社がしっかりと黒字経営できているなど財務体質の健全性が高いレベルで求めらます。一方で1件1億の取引をどんどん受注成功し、無事納品なら、成長速度は加速度的に早くなります。
そのため、年商3億円の会社が、特定建設業許可の資格取得をして、2~3年程で10億近い規模になったということは普通に起こりえます。
匠税理士事務所では、特定建設業許可資格取得のためのサポートをを行っております。
特定資格の新規取得や更新手続きの詳細はこちらからご確認下さい。↓
一般建設業許可の資格登録をご検討されている方はこちらをご確認ください。
特定建設業許可の資格取得と資金調達が成功に必要
特定建設業許可の資格取得とあわせて成功に重要なのは、資金調達です。
一般建設業許可と特定建設業許可のいずれにも、厳しい財産要件がありますが、
これは建設業界や建築業界は、工事の受注から納品、入金まで材料費や外注費の立替といった多くの資金が必要になるという特徴が一つの理由です。

そのため、特定建設業許可の資格取得が出来れば、工事受注額が大きくなるにつれて
立替材料・外注費金額が増加する展開になります。
こうした立替資金の増加に対応するためにも、
先を見越した資金調達の成功が重要になるのです。
また、資金を大量に調達するということは、
金利にもより慎重に取り組まないというけないということも意味します。例えば1,000万円の借入を年2%で行った場合には、利息は20万ですが、
1億円を年2%で借入した場合、利息は200万となり、金利が少し変わるだけで車が買えてしまうということも起こりえます。

したがって、特定建設業許可の資格取得によって、大きな容器が確保できた後は、
その容器に安定した豊富な資金という水を、低い金利で注入する必要が出てきます。
これが出来れば、大型工事もふまえた受注のための営業に注力し、
豊富な資金を活用し外注先・社員さんと協力し案件に集中して取り組むというサイクルとなります。
特定資格取得など建設業に強い匠税理士事務所の経営支援
匠税理士事務所では、建設業専門の行政書士と連携して一般から特定建設業許可の資格取得から各種金融機関と連携した資金調達成功までサポート致します。
各種経営セミナーで講師を務める世界4大会計事務所出身の税理士が、
黒字化のための道筋から資金調達など財務改善のためのコンサルティングを行っております。
弊所では各業界トップレベルの専門家がチームで対応します。
経営支援は、こちらよりご確認下さい。
◇サービスページ
◇法人のお客様
◇個人のお客様
◇特定資格取得など起業相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向け特定資格取得など起業相談会を開催中

◇お役立ち情報
特定建設業許可の資格登録以外の建設業・建築業の経営ノウハウを掲載中
特定資格取得代行以外の黒字戦略とキャッシュ経営支援も充実
【 黒字経営の情報館 】
【 黒字経営サービス 】
◇特定建設業許可の資格取得に対応の匠税理士事務所
特定許可の資格取得につき最後までご覧頂きありがとうございました。
建設業・建築業で会社の利益を最大化する売価経営戦略とは (19/03/14)
建設業や建築業の経営支援に強い匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
【建設業・建築業で利益を最大化する経営戦略】につき記載します。
利益の最大化への道筋は、非常にシンプルです。
この粗利益から会社を維持するための 3 の固定費を差し引いた営業利益(本業の利益)が、
金融機関ではもっとも重視してみられます。
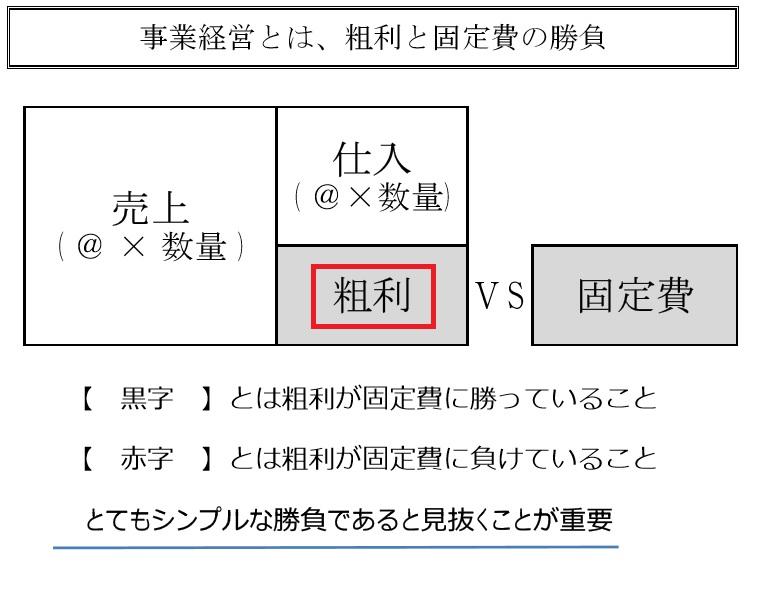
営業利益がしっかりと確保できている建設・建築会社は、本業でしっかりと稼げている会社であり、評価・格付けは高く、資金調達がしやすかったり、大手の与信調査で高評価を受け、受注しやすくなります。
もちろん、入札などの経営事項審査(経審)でも、プラスに働きます。
利益が出ている会社には、お金と人が集まってくるので、工事も集まってきます。
逆に利益がない会社からは、離れていきます・・・
今は、建設業・建築業は人手不足の時代ですので、職人さんはより良い条件の会社に移りやすい状況にあります。
営業利益の最大化は、会社の経営で取り組まなければいけない命題です。

今回は、営業利益の最大化に最も重要な要素である請負金額・受注額など売価最大化を掘り下げます。
建設業・建築業の売上(請負金額・受注額)の最大化は見積り・積算が重要
建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均は、概ね20%ですが、
弊所建設業の関与先様の粗利率は平均30%~40%になっております。
お話をしていて感じることは、積算にとても注力されているということです。
積算とは、工事にかかる材料や外注費などの原価総額を積み上げていき、これに確保したい利益をのせ見積りを作るのです。
経験値が高い方であればあるほど、この見積り作成時に決めた利益を最終納品段階でも確保します。

逆に粗利率が低い場合は、この積算の時点で問題が生じているケースが多くあります。
この見積り作業は、黒字経営の軸になるといっても過言ではありません。
なぜなら、見積りを出して金額につき発注者・受注者の双方が合意し建設・建築工事の請負契約書を締結します。
上記は建設・建築で普通の商流ですが、2つの大きな意味が出てきます。
【1 期限までに納品しなければならない義務。】
【2 納品後に請負金額・受注額がもらえる権利】

見積り時点で失敗し、受注時点で利益がでないような工事の場合どうでしょうか?
建設・建築工事を期限までに完成納品しなければならない義務は、契約で生じていますから、期限までに納品しなければなりません。
契約違反すると違約金という展開もありえます。逆に低い見積りで契約した発注者はどうでしょう。
依頼した時点で、利益は確定となります。
このように見積り時点で、黒字工事か赤字工事かは、概ね決まってしまうのです。それでは、建設・建築業界では得意先とどのような関係が理想でしょうか。
発注者・受注者共に【 共存共栄 】関係が理想
建設・建築業で理想の関係は、【 共存共栄 】です。発注者・受注者ともに利益が残る利益配分がされた関係です。
どちらか一方のみ利益が出て、片方が儲からないのではその取引は長く続きません。
見積りで確保したい適正な利益をのせて提示し、取引が流れるのは悪いことではありません。取引が流れたのは、お互いに利益配分を行うという気持ちがないからで、そのような取引を継続しても長期的には良い結果につながりません。
一方で、適正な見積りを出し、取引が流れても他工事を請ける機会と人的リソースは残りますし、
むしろお断りしなければいけない利益が出ない案件を請けることのほうが、建設・建築の会社経営で良くないのではないでしょうか。

時折、今回は赤字になるけど次回はいい工事がもらえるから・・・
ということもあるかもしれませんが、
ほとんどは次回も赤字工事になることが多いです。それは、赤字の建設・建築工事を請けた側は、当然赤字になりますが、発注した側は、安く買えたので黒字です。
このような取引を相手先に求めるというのは、発注者・受注者ともに利益が残る利益配分の関係に問題があると思います。
経営者が利益を求めず、利益を出すことをあきらめてしまうと、
会社・社員・その家族全員が大変になります。
だから、経営者は利益を最大化するという強い想いをもって経営に臨まなければいけません。その一歩が、慎重な見積りと積算に裏付けされた強い売価となります。

慎重で丁寧な見積りを作っておけば、工事の途中で地盤が弱いので補強が必要など
当初想定していた条件が異なった場合に、追加工事の請求を協議できます。
〇〇一式という大雑把な見積りだと、当初の見積もりに含まれているという展開にもつながります。
このように建設・建築業で丁寧な見積りと積算によるしっかりとした売価の実現が、
利益最大化の第一歩になり、失敗すると取り返しが難しくなるのです。
【値決めは経営】【売価はお客様に理解していただける金額で、自社も儲かる値段の一点】と京セラの稲森和夫さんが名言を残されております。
値決めは商売で最重要項目ですので、経営者自らが行うべきなのです。
その上で全行程の原価を知る仕組みをつくり、原価が予算内に収まるよう管理しなければなりません。
建設業・建築業の経営戦略コンサルティングに強い匠税理士事務所
匠税理士事務所では、会計や経理データを活用し、建設業・建築業の会社様の経営コンサルティングに力を入れております。
会社の良かったところや改善すべきところもしっかりお伝えし、売価の改善・原価の削減・固定費の縮小などコンサルティング致します。
会社様が儲かって利益が出て、お金が残ることを目標にサポートいたします。
◇匠税理士事務所のTOP

◇建設業や建築業に向けたお役立ち情報
建設業や建築業の経営戦略に関するノウハウを掲載してます。
◇建設業の許可申請サービス
建設業界や建築業界向け利益戦略とキャッシュ経営
【 黒字経営の情報館 】
【 黒字経営サービス 】
◇建設業や建築業サービス
○法人のお客様
○個人のお客様
◇建設業・建築業の会社に強い匠税理士事務所
税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域と神奈川県
建設業・建築業で会社の利益を最大化する経営戦略を最後までご覧頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
建設業や建築業、工務店の起業・創業・開業相談会は匠税理士 (19/03/14)
匠税理士事務所では、工務店や建設会社など
【建設業・建築業の方限定】で起業したい方に
起業相談会を行っております。
工務店や建設会社など建設業や建築業での
起業・創業・開業の成功は、以下がポイントです。
【 建設業や建築業の起業成功ポイント 】【 1 】 事業自体の一取引当たりの金額が大きく、
かつ車両や機材など初期投資に資金を要するため、
創業時の資金調達である創業融資の成否が、
事業の今後の成長速度を大きく左右する。
【 2 】 建設業の許可申請を通じ建設業許可
取得成否が今後の工事受注に大きく影響するが
取得には、様々な要件をクリアしなければならない。
つまり、起業に多くの【お金が必要】になることと、 大型案件受注には【資格が必要】という特徴が、 建設業や建築業にはあるのです。そのため、この二点が建設業や建築業で
起業・創業・開業成功のポイントになるのですが、
ここからは業界特有事項への対応を記載します。

建設業や建築業、工務店で起業・創業・開業するときの資金調達のポイント
建設業や建築業、工務店の起業・創業・開業のときに
これまで起業支援致しましたお客様の9割近い方が
創業融資を活用されております。
その理由は上記の通り、建設業や建築業は、
一取引の金額が大きく、かつ車両や機材など
【 初期の設備投資 】に資金を要するからです。
この起業・創業・開業の資金調達と考えた時に、
真っ先に銀行が思い浮かぶかもしれませんが、
銀行は創業融資で1番に検討すべきでありません。
起業・創業・開業などスタートアップの時期の創業融資で 頼りになるのは、【 日本政策金融公庫 】です。
日本政策金融公庫(通称:公庫)とは、
日本政府が株主・運営する銀行のイメージで、
中小企業の資金調達のサポートを行います。
日本政策金融公庫は、⽇本経済の成⻑発展へ貢献を
理念に掲げ、国の政策に基づき、新たな事業の創出、
事業再生、事業承継、海外展開、エネルギー対策や、
DX推進及び事業の再構築を後押しています。
そのため、利益追求の民間銀行など金融機関と
事業や組織の目的が異なります。
また、日本政策金融公庫は国が運営母体であり、
起業・創業・開業といったスタートアップの時期という 比較的リスクの高い創業融資も融資することで、 新たな事業の創出を重視しており、 最終的に国自体の成長発展を目的としています。
一方で、民間の金融機関は利益を追求しますので、
比較的リスクの高い創業融資には、
あまり積極的ではない傾向があります。
そのため起業・創業・開業などスタートアップ期の
資金調達は日本政策金融公庫を検討すべきです。
しかし、日本政策金融公庫での資金調達では、
初回融資は1,000万円が上限となることが多く、 建設業・建築業など多額の資金が必要な業種は、 【他のチャネルの資金調達】が、必要になってきます。弊所は日本政策金融公庫の創業融資で、
トップクラスの成功率と実績がございます。
また、日本政策金融公庫以外の金融機関と
連携することによる資金調達も行っており、
1,000万以上の資金が必要なお客様にも
臨機応変に対応が可能です。
創業融資ときくと、何だか難しそうな感ですが、
そんなことはありません。
お客様から起業・創業・開業される内容を伺い、
必要資金と自己資金状況を伺い、どのチャネルで
幾ら調達が可能かを一緒になって考えます。
また、創業計画書は建設業や建築業の起業に
強い税理士が作成をサポート致しますので、
多くのお客様にお喜び頂いております。

建設業許可の新規取得と申請代行
お金の調達の次に考えるべきは、仕事の獲得です。
そして仕事の獲得で大切になるのは、
【 建設業許可の新規取得 】です。
この建設業の許可無しでは、一件の請負代金が 500万円以上の工事の受注が出来なくなります。特に大手と取引の予定のある建設会社では、
建設業許可取得は条件で求められることが多く、
日本政策金融公庫の創業融資でもこちらの取得が、 創業融資の条件に付くことさえあります。そのため、建設業の許可申請の新規取得が成否は
創業融資による資金調達と同様に事業展開に
大きな影響を及ぼします。
そこで弊所は、建設業許可特化の行政書士が、
起業・創業・開業される方や社員の方の経歴など伺い
建設業の許可申請の新規取得はできそうなのか否か
しっかりとアドバイス致します。
また、現時点で建設業許可の取得が難しい場合は、
どの条件をクリアすれば、建設業許可取得可能か
丁寧にコンサルティング致します。

【建設業や建築業の方限定!】税理士の起業・創業・開業相談会
弊所では、建設業や建築業の方限定で
起業・創業・開業の相談会を行っております。
世界4大会計事務所出身の税理士が担当させて頂きお客様の事業に関する考えやビジョンを伺い、
資金調達チャネルや金額と経営ポイントなどをマンツーマンで対応させて頂きます。
またご要望のは、建設業許可申請についても
専門の行政書士がコンサルティング致します。
出来る限りしっかりとお客様のお話を伺い、
アドバイスをさせて頂きたいため、
【 月間2名まで 】の対応とさせて頂いてます。1.無料お問い合わせフォームにてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.予約期日に、ご来所ください。特段ご持参いただく資料はございません。
◇場所→ 匠税理士事務所の会議室
◇料金→ 約1時間 1万円
◇予約→ 匠税理士事務所へのお問い合わせ
※お客様へ
税理士法での守秘義務がございますので、安心してご相談頂けます。
担当者の枠に限りがございます。予約に空きがない際には、ご予約を承れないことがございます。
一部でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

◇建設業の関連記事
◇法人のお客様
◇個人のお客様
建設業や建築業向けのサービス
◇建築業許可申請サービス

◇建築業向け創業融資サービス

◇建築業向け会社設立サービス
○建築業向け法人化サービス
◇補助金/補助金サービス
(設備などモノ) 補助金申請書の作成代行と助成金申請・コンサルティング
(人材の採用や育成)助成金申請代行《起業、創業や雇用の助成金≫
◇お役立ち情報
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
会計事務所の起業支援対応エリア:世田谷・目黒・品川・渋谷区・大田区・港区など東京都23区全域の創業をサポート
執筆者・文責:税理士 水野智史
#建設業起業 #建設業独立開業
等々力で税理士や会計事務所をお探しなら匠税理士事務所 (19/03/14)
ご来訪ありがとうございます。
匠税理士事務所は等々力近くの会計事務所で、
【高度な専門性】と【技術力】に評判があり、
世界4大会計事務所出身の税理士を中心に、 各業界トップレベルの専門家のチーム力が強みです。したがって、税務会計以外の法務や人事労務、
建設許可申請といったご相談にも対応可能です。
税理士やサービスは、こちらでご確認下さい。

等々力で会社設立など独立開業・起業支援
世田谷区の等々力で会社設立し起業や独立開業を
お考えの方に向け起業支援を行ってます。
会社設立代行は、専門の司法書士と連携し、
一度の打ち合わせで完了する
シンプルでご負担にならない形式です。また資本金は幾らにした方がよいのか、
インボイスはどうすべきかという税務相談も
起業セミナー講師を務める税理士が担当しますので
安心してご依頼頂けます。
起業支援担当の税理士・事務所概要はこちらから

世田谷区の等々力で起業や独立開業される方向けの
会社設立サービスはこちらです。
等々力の創業融資による創業支援
当会計事務所は日本政策金融公庫や、
城南信用金庫の等々力支店、みずほ銀行と
連携し等々力など世田谷区の創業融資を行います。
起業や独立開業されるに創業融資による
資金調達は重要な課題となりますが、
弊所は世田谷区の税理士・会計事務所の中でも、
9割超のトップクラスの融資成功率がございます。また創業融資では事業計画書の作成支援や
融資面談の立ち合いなどまで対応致します。
創業融資による創業支援はこちらでご確認下さい。
弊所紹介で優遇がある金融機関もございます。
詳細は下記をご確認下さい。

世田谷区の自治体による制度融資はこちら
【 → 世田谷区の制度融資の仕組みと創業融資 】
等々力の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は等々力など世田谷全域対応)
等々力の会計経理や確定申告・法人化の代行
匠税理士事務所は、世田谷区の等々力から
すぐの自由が丘駅徒歩2分にある会計事務所です。
40代税理士が中心の人の質やサービスの質に
こだわっております。
等々力など世田谷区の会社様の経理や会計、
確定申告のご相談にも対応してますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人で土地や不動産を売却した場合の
確定申告や法人化などを承っております。
サービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
等々力で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

等々力の法人化・会社設立の登記情報
等々力など世田谷区で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
法人化・会社設立に伴う商業法人登記は
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が法人化・会社設立など登記の際、
対応する行政窓口となります。
世田谷区の等々力の方に向けた税理士事務所、
会計事務所の採用・求人情報はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
等々力での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#等々力税理士
#等々力会社設立
庭師や造園業・土木工事業などに強い会計事務所は匠税理士 (19/03/14)
匠税理士事務所へご来訪ありがとうございます。
弊所は、庭師など造園業・土木工事などの建設業に力を入れている会計事務所です。
庭師、造園業・土木工事業での会社経営では、
【優れた社員の技術】と【サポートする機材・装備】を 掛け合わせたサービスが、【 商品 】です。あとはこの優れたサービスをより良いお客様に
どのようしてに知っていただくか、
一度ご利用いただいたお客様から、【リピート】を
頂けるか否かが、成功のポイントになります。
また、そもそもお庭を有していますので、
得意先は富裕層が多いのも特徴の一つであり、
ある一定のお客様数に到達した場合には、
【 利益確保がしやすい 】という特徴があります。

そして【 利益を人材・機材へ投資 】することで、
よりお客様のニーズに応えられるようになり、
事業拡大していくのも、この事業の特徴です。
逆にいうと人材は技術の習得・経験値の蓄積など
急には成長はできませんので、
長期的な経営の視点を持ち合わせてないと
事業成長にブレーキがかかってしまいます。
このように順調に事業拡大できるか否かは、
建築業許可申請・社会保険・資金調達・人材確保と 教育や育成・設備投資といった地道な準備を【 必要な時期に、必要なだけ 】できるか
これが事業成功の成功ポイントになります。

また造園業は、園芸サービス業と造園工事があります。
園芸サービス業や植木業(主として庭園作りや、
又は手入れなどを行うもの)とは、
主として請負で築庭,庭園樹の植樹,庭園・花壇の手入れなどを行う事業所をいいます。
これに類似する事業に造園工事業があります。
庭師・造園業や土木工事業は建設許可が重要
造園工事とは、整地、樹木の植栽、景石すえ付けで
庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の
屋上等を緑化し又は植生を復元する工事とされ、
【 請負金額500万円以上の造園工事 】には、
建設業許可申請が必要です。
日本標準産業分類で、前者の庭師・園芸サービス業は
農業,林業に分類されます。

後者造園工事業は、土木工事業(土木工事を行い
土木施設を完成する事業所、庭園、公園、緑地等の
苑地の築造工事を行う事業所、しゅんせつ工事
及びこれを伴う土木工事業)に分類されます。
庭師・園芸サービス業や植木業といった事業を 基本的な収益の柱としながら、ご要望に応じて、 造園工事を受注するケースはよく耳にします。庭師・園芸サービス業や造園工事で会社設立して
起業する場合は、お客様にお応えできないことで
他社の参入余地というスキが生じないように
建設業許可申請を最初に行い、いつでも受注できる 万全の準備を進めておくのが得策です。庭師・造園業や土木工事が得意な会計事務所
匠税理士事務所では、
【 庭師・造園業・土木工事など建設業に必要なすべてがそろう会計事務所 】を目指しております。そのため、税務会計など経理業務は当然ですが、
建設業許可申請以外に社会保険加入や給与計算、
日本政策金融公庫や金融機関などの創業融資や、
資金調達・補助金・助成金もサポートします。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

前述の建設業許可申請までの過程では、
社会保険加入についても求められますので、
建設業許可手続きの前に社会保険の加入も
社会保険労務士とチームでサポートします。
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら

次に庭師・園芸サービスや造園工事など土木工事、
いずれの業務を行われる場合にも、
作業車両や機材が必要になるため
初期投資が大きくなるのが特徴です。そのため、会社設立し、起業する場合には、
日本政策金融公庫などを通じて創業融資で
資金調達をされることをお勧めします。

匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、
品川区など東京都で【成功率9割超】と
トップクラスの創業融資支援実績を有します。
創業融資計画書の作成支援をはじめ、
日本政策金融公庫と提携することで特別に
弊所で融資審査をして頂くことも可能です。
こうした環境をご用意することで、
庭師・造園業や土木工事など建設業を営む
社長様が本業に集中できるよう努めてます。
詳細はこちらからご確認をお願いします。

庭師や造園業・土木工事業に強い税理士
匠税理士事務所には経営セミナーで講師を務める
世界4大会計事務所出身の税理士が所属し、庭師・造園業や土木工事業様を担当致します。
毎月の経理や会計・財務のデータを活用して、
【 儲かって、お金がたまる会社づくり 】をお客様と一緒になって取り組みます。
庭師・造園業や土木工事業での株式会社や
合同会社など会社設立し起業を検討中の方は、
起業に必要な全てがそろうサービスラインを
ご用意してますので、こちらを確認下さい。

弊所では、関与先の9割以上が黒字経営という
実績を有しております。
匠税理士事務所の経営記事につきましては、
こちらからご確認をお願い致します。
利益とお金がたまる会社づくりのポイント解説は
こちらからご確認下さい。
【利益とお金が増える会社づくりのポイント解説】 【 お金がドンドンたまる会社づくりのポイント解説 【 建設業や建築業の経営事項審査(経審)とは?簡単に解説 【 一般競争入札と指名競争入札とは何かをわかりやすく解説建設業の企業様向け匠税理士事務所の経営サポート詳細はこちらからご確認下さい。
建設業や建築業で個人事業主化から株式会社や合同会社など会社にしたい方向け法人化についてはこちらから
執筆者・文責:税理士 水野智史
#造園業税理士 #土木工事業税理士
建設業や建築業の税務調査と税金節税対策ポイント (19/03/14)
ホームページの閲覧ありがとうございます。
弊所は建設業や建築業が得意な会計事務所です。
今回は建設業や建築業の税務調査と税金対応、
【 節税対策ポイント】につきまとめました。
国税庁が発表している下記の表にあるように
建設業や建築業は、税務調査対象とされやすい
10種類の事業のうち3事業にあがっています。
税務調査は会社から提出された決算書や、
税務申告書の内容を税務署・国税局で確認し、
調査先を選定し、調査官から電話が入ってから
税務調査の実施という流れとなります。
何故、建設業は税務調査が多い業種なのでしょう?
飲食店や美容業等といった現金商売は、
現金売上を計上してないかの確認などのため、
税務署・国税局の税務調査が行われやすいのですが
建設業や建築業の場合は、
【 一取引が大きいため 】売上計上時期が適正か、 対応する在庫計上が正しくされているかが、 【 税務調査で注意されるポイント 】です。1案件で1億円の工事の売上計上時期がずれると
これに対応する税金もかなり大きくなり、
【 申告漏れによるペナルテイも多く課せられる 】ことから重点調査業種となる傾向があります。
つまり1件の取引金額が大きい【ハイリスク・ハイリターン】
という建設業や建築業の特性に起因するのです。
そして税務調査でトラブルが起き、
重加算税などペナルティが課されると、
頻繁に税務調査が行われる要管理先と認定される
【負のサイクル】につながるので注意が必要です。
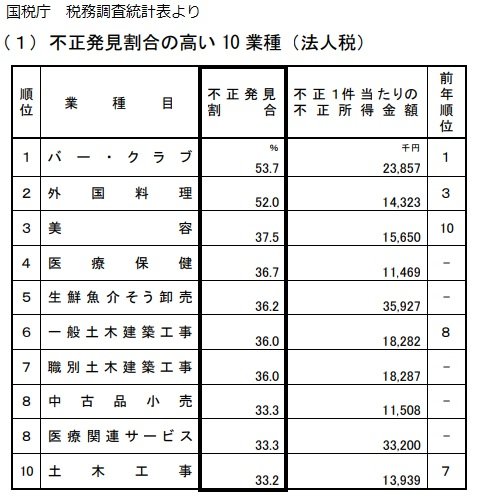
建設業や建築業の税金と節税対策のポイント
建設業や建築業で会社を経営している場合には、
大きく分けて2つの税金がかかってきます。
1 稼いだ利益に課される法人税・住民税・事業税これらは売上から経費を差し引いた利益に
税率をかけて税金を計算するという性質で、
【 利益の増減 】と【 税金の増減 】は一致します。
つまり節税対策を通じて、法律の範囲内で
経費を増やすことができれば、
利益と連動し、税金が減少する性質を有します。
こうした性質から法人税・法人住民税と事業税は、
【 節税対策の余地が大きい税金 】といえます。 2【 売上消費税 から 経費消費税 】を引く消費税
2【 売上消費税 から 経費消費税 】を引く消費税
消費税は売上と共に預かった消費税から
経費と共に支払った消費税を差し引いて、
差額を国と地方に納付するという性格の税金です。
例えば、税込110円売上から材料税込55円につき
消費税の税額計算だけに着目しますと、
10円(売上消費税)-5円(材料消費税)=5円の納税消費税は売上が発生すると生じる税金ですので、
【 節税対策の余地は少ない 】性質を有します。このような性格を有する消費税でも、
大きく節税対策を行う方法としては、
基準期間(前々年)の課税売上高が、
5,000万以下の場合、実際仕入などの経費でなく
建設業の場合、70%を概算経費とみなし計算する
【簡易課税制度選択】の検討が効果的です。建設業・建築業の節税は決算3か月前にに行う
節税対策のポイントは、仕事と同じで
【 早めに対応して対策を打つ 】 のが重要です。利益が1,000万円出ると、約3割の300万円という
【法人税・法人住民税と事業税】が生じます。
これに節税対策を税法の範囲で行い500万にすると
税金は500万×30%=150万となります。
つまり、150万円税金が減少することになります。
150万利益を上げるのも商売で大事なことですが、
150万節税対策を行うことも大事なことです。
いずれも150万円のお金に変わらないので・・
それでは、法人税・法人住民税と事業税を
節税対策で効果的におさえるには、
何が重要かというと、まずは利益の予測です。
12月決算では12月31日で会社の会計期間を
しめることになります。
つまり、12月31日までは今年の経費で、
1月1日からは来年の経費ということになります。
仮に12月25日で利益1,000万円です。
節税対策で翌期に買いたい備品などは無いですか?
と税理士事務所に言われるとどうでしょうか?
1,000万の買い物を1週間では到底無理ですし、
備品販売の会社から物が届く期間も考えると
何も出来ずに12月31日を迎える展開になります。
一方、決算3か月前の10月頃に利益が分かれば
どのようになるでしょうか?
オフィスの修繕から人材採用のため経費など色々と
やりたいことは、浮かぶのでないでしょうか?
早めに準備すれば打ち手も的確で効果的ですが、
ぎりぎりになると打ち手は荒く、雑になり、
最終的に法をまたぐ=脱税にもなりかねません。
このような理由から節税対策ポイントは仕事と同じ、 【 早めに対応し対策をうつ 】のが重要です。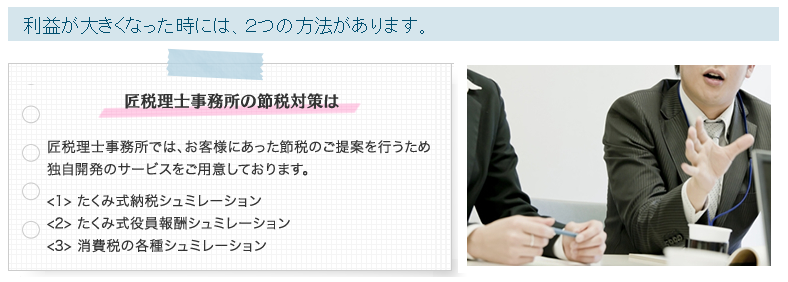 攻めと守りの二つの節税方法
攻めと守りの二つの節税方法
【1】将来の利益につながる投資型の攻めの節税
【2】資金を留保し万が一に備える守り型の節税
お客様の事業展開と利益状況を総合的に判断し
攻めと守りのバランスよい節税を提案致します。
建設業や建築業の節税対策に強い会計事務所
匠税理士事務所は、大手ゼネコンを担当していた
世界4大会計事務所出身の税理士が所属してます。 上場企業では株主配当の利益を計算するため税金がどれ位生じそうなかを決算前に
8~9割の精度で税額見込計算を行います。この考え方で【 独自自社で制作したシステム 】で
決算3か月前に利益の予測を実施、
今期はどれ位の利益がなのか予測し、
税額のシミュレーションを行います。
このままではどれ位の税額になりそうか把握、
多くの節税方法から効果的な節税対策の選択、提案しお客様にご検討していただきます。
シミュレーションのメリットは、2つです。
【 1:早い時期に税金がどれ位か分かること 】 【 2:効果的な節税対策ができること 】2008年に事務所を設立して以来、
これまで多くのお客様にご利用頂いておりますが、
おかげさまで大変ご好評を頂いております。

匠税理士事務所では節税対策を提案した
税理士が税務調査にも立ち会いますので、
これまで多くのお客様にお任せ頂いてます。
◇建設業や建築業を担当する税理士は、
こちらからご確認をお願いします。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

弊所では、関与先の9割以上が黒字経営です。
◇利益とお金がたまる会社づくりのポイント解説は、こちらからご確認下さい。
【 利益が残る、利益が増える会社づくりのポイント解説 】 【 お金がドンドンたまる会社づくりのポイント解説 】 【 建設業や建築業の経営事項審査(経審)とは?簡単に解説 】 【 一般競争入札と指名競争入札とは何かをわかりやすく解説 】◇建設業許可申請の代行は、こちらをご確認ください。
◇建設業や建築業のお客様向け 匠税理士事務所のサービス
○法人のお客様
○個人のお客様
◇建設業や建築業のお客様限定の相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#建設業税務調査 #建設業節税対策
事業再構築補助金とは?申請書類の作成代行と申請代行 (19/03/14)
匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。
弊所では、事業再構築補助金申請書類の作成代行に特化した専門家が申請をサポートします。
今回はこの事業再構築補助金とは?どんな制度なのかについてまとめてみました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が困難中、
今後の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することを通じて、日本経済の構造転換を促すことが重要であるためこれを支援するという補助金です。
そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切って
事業再構築に取り組む中小企業等の挑戦を支援しようという趣旨となり、
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、
思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金です。

事業再構築補助金対象事業の類型及び補助率等
事業再構築補助金の対象事業には、
1 成長枠
成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援。
中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 1/2)
補助金額 従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円
2 グリーン成長枠
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の
課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援
中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 2/3)
中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 1/2)
補助金額【従業員数 20 人以下】100 万円 ~ 4,000 万円
3 卒業促進枠
成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等
に成長する事業者に対する上乗せ支援。
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助金額 成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる。
4 大規模賃金引上促進枠
成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む
事業者に対する上乗せ支援。
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助金額 100 万円 ~ 3,000 万円
5産業構造転換枠
国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援。
中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2
補助金額 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円
6 サプライチェーン強靱化枠
サプライチェーン強靱化枠では、海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する
国内生産拠点を整備(国内回帰)する事業者を支援
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
補助金額 1,000万円~5億円
7 最低賃金枠
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中
小企業等の事業再構築を支援。
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
補助金額
【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円
8 物価高騰対策・回復再生応援枠
業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰
等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援
中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2
補助金額【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円
【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,500 万円
この上記8つの事業類型があります。
(上記は原則的扱いであり一部例外もございますが、今回は省略します。)
なお、同一法人・事業者での各事業類型への応募は、1回の公募につき1申請に限ります。
(一部例外あり。複数事業を計画中の場合は、事業計画書中に複数計画の内容を記載し申請することは可能)。
事業再構築補助金の申請書類の作成のポイント
事業再構築補助金の申請書類の作成では、様々なポイントがありますが、
特に以下の点が申請書類では重要となります。
1 コロナの影響で売上が減少していること
2 新分野展開、業態転換、事業・業種転換等といった指針に示す「事業再構築」を行うこと
3 認定経営革新等支援機関(国の認定を受けた税理士・中小企業診断士等の専門家)と事業計画を策定すること
また、補助金申請の際にはしっかりと各補助金制度を理解した上で、要件をクリアできそうか?
障害となるのはどの事項で、それに対してどのような申請書を作成すべきかというノウハウが重要です。
弊所では補助金申請に特化した中小企業診断士と連携することで、
お客様が安心して補助金申請を行えるようにサポート致しております。
◇補助金サービス(設備などモノ)
◇会社概要
◇TOPページ
世田谷区や目黒区、品川区など東京を中心に起業や創業支援に定評があり、
補助金や助成金など起業に重要な全てがそろう会計事務所です。
<各種補助金別のサービスへのリンク>
① 起業・創業も使える小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行
② IT導入補助金
<中小企業が生産性向上を目的に、業務効率化やDXに向けITツール(ソフトウェアやアプリケーション、サービス等)の導入を支援するための補助金>につきましても、お気軽にお問い合わせください。
制度は随時改訂されます。最新の情報の確認は、各官公庁の情報にてご確認をお願い致します。
補助金や助成金とは?補助金申請書の作成代行と助成金申請 (19/03/14)
補助金や助成金、とても似ている名称ですが、両者は全く異なる制度です。
◇助成金は、
「 人材 」に関して、一定の要件をみたせば、受給できるもので厚生労働省が管轄しています。
雇用調整助成金やキャリアアップ助成金といった < 人材の採用と育成 > につき国が助成する制度です。
この助成金の専門家は、人事労務の専門家である社会保険労務士の専門領域となります。
◇補助金は、
事業に必要な「 設備などモノ 」 を購入する際に、一定の要件を満たせば、一部を国や地方公共団体が補助するという経済産業省がメインの制度になります。

このように助成金と補助金は、【 人 】と【 モノ 】の支援という内容の違いと
受給できる割合が、助成金は比較的高い一方で、補助金は助成金に比べて低くなる というのが特徴です。
匠税理士事務所では、助成金に特化した社会保険労務士と、補助金に特化した行政書士・中小企業診断士など専門家と連携し、助成金 と 補助金 の両制度の申請代行を承っております。
補助金申請書の作成代行やコンサルティング
◇補助金獲得までの流れ【1】 事業再構築補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金など各制度の理解
【2】 各補助金の制度で、自社の場合は、どの制度が使えそうか判断する
【3】 補助金の制度にあわせて事業計画書を作成して申請
【4】 補助対象となる設備等への投資
【5】 要件と照らした上で、経済産業省等が認可・採択・実行 → 入金

◇補助金の基本的な考え方
補助金は、支払った投資額の 1/2 や 2/3 を国などが補助してくれるという制度です。
例えば、100万円払って欲しいものを買い、50万を国が補助してくれるというイメージです。
上手く活用できれば大きなチャンスとなる補助金、メリットばかりに見える制度ですが、デメリットを把握したうえで活用するか否かの意思決定が必要です
補助金申請のデメリットとリスク、注意点
補助金申請の専門家報酬 注意点①
1)1つ目の注意点は、中小企業診断士や行政書士等の専門家 報酬 > 補助金 というケースです。
補助金で10万円補助してもらえても、専門家報酬がこれを上回るとメリットが消えてしまいます。
補助金が少額であれば、かける時間と報酬に見合う補助金の額かどうかを判断する必要があります。
2)合わせて気を付けたい論点として、報酬の支払い方です。
補助金の申請代行の報酬は、【 着手金なしで、成功報酬のみ。】 これが理想です。
結果を出さないと報酬につながらないわけですから、仕事の精度があがるのは当然です。
逆に着手金が高いところは、補助金がおりなくても、着手金が入りますので、
補助金はおりず、着手金のみ支払った というトラブルにならないように注意が必要です。
補助金の性格 注意点②
事業再構築補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金など補助金には、
共通のデメリット・リスクがあります。
それは、物を買って支払ってから、補助金の申請になるということです。つまり、お金が先に出る。そして要件をみたして審査に採択(合格)ができなければもらえない。
また、事業再構築補助金等のように申請から入金まで元々時間がかかる補助金もあります。
そして補助金がもらえると思って、物を買ったがもらえなかった・・・・・
これは危険です。資金繰りの厳しい会社なら、更にリスクは膨らみます。
こうした補助金のデメリットとリスクに対応するには、
事業再構築補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金など補助金の制度を理解して、
・確実に審査に採択(合格)できそうなのか?
・何が問題になり、どうやって超えるのか?
これらのポイントを的確に抑えることです。

そして、審査に採択(合格)しやすい事業計画書を中小企業診断士などの専門家と一緒に作成し、
専門家が有するノウハウと専門性をフル活用することです。
補助金と共に考えておきたい資金計画と投資計画 注意点③
事業再構築補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金など
どの補助金も最初に大きな支払いが出ます。
そして補助金が入るまでの期間は立て替えとなり、資金繰りは厳しくなります。
これは元々資金繰りが厳しい会社は、補助金の利用に向いていないということを意味します。何故なら、大きな支払い → 補助金がおりなかった → 更に経営悪化 という負のサイクルとなるからです。
また、補助金がもらえるからといって、
大して必要でない設備投資をするという考えもよろしくありません。
何故なら補助金は出るかもしれませんが、一部は自腹になりますし、
本当に必要でない余計なものは、会社の経営改善に役に立たず失敗するケースの方が多いからです。

このように補助金を活用すべきなのは、資金的に余裕があり、
事業に必要な設備投資計画がしっかりとできている会社であるということが出来ます。
匠税理士事務所の補助金申請代行
匠税理士事務所では、お客様が補助金制度を活用しきれるように
補助金申請代行を専門とする中小企業診断士・行政書士と連携して、お客様に補助金制度の説明と
事業内容のヒアリングを通じたコンサルティングを行います。
・事業再構築補助金・IT導入補助金・小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金など補助金の制度で
利用できそうな制度の提案を致します。
・補助金申請にあたり、資金調達の必要があるお客様には、資金調達のための事業計画書を作成し、金融機関と連携し資金を調達します。
匠税理士事務所は、日本政策金融公庫や信用金庫など、各金融機関と連携しており世田谷区や目黒区、品川区など東京都でも資金調達の実績はトップクラスです。

◇料金とサービス内容
○サービス内容
設備投資計画に基づき、補助金申請に特化した中小企業診断士が、補助金申請書類の作成代行から採択までサポート致します。
○料金
完全成果報酬(制度により10%~15%)
制度について興味があるので一度話を聞いてみたいという方はお気軽にお問い合わせください。
(税務顧問契約を頂いてない会社様でも補助金申請代行のみ相談したいうケースにも対応しております。)
<各種補助金別のサービスへのリンク>
① 起業・創業も使える小規模事業者持続化補助金の申請書作成代行
③ IT導入補助金
<中小企業が生産性向上を目的に、業務効率化やDXに向けITツール(ソフトウェアやアプリケーション、サービス等)の導入を支援するための補助金>につきましても、お気軽にお問い合わせください。
助成金申請の代行やコンサルティング
補助金以外にも人事労務の専門家である社会保険労務士を中心とした助成金申請代行も承っております。助成金申請も、成功報酬形式を採用しておりますので、ご相談いただけましたら幸いです。
・これからスタッフを採用し、教育したいため助成金を活用したい。
・何か使えそうな助成金の制度全般について知りたい。
このような助成金のご相談は、下記よりお願い致します。
◇助成金サービス
【税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
◇会社概要
◇TOPページ
世田谷区や目黒区、品川区など東京を中心に起業や創業支援に定評がある会計事務所です。
建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所 (19/03/14)
匠税理士事務所のWEBサイトへ
ご訪問ありがとうございます。
弊所は建設業や建築業の個人事業主から
株式会社や合同会社などに組織変更する
【法人化・法人成り】の実績が豊富な事務所です。最初は個人事業主の形態で始めてみたが、
得意先からの信頼を積み上げて、
受注工事も増え、株式会社など会社にしたい方は
【 法人化 】を検討されてもよいかもしれません。
なぜなら建設業の場合には、IT業やサービス業など
建設業以外の業種では、デメリットになる点が、
建設業はメリットに変えられる特徴があるためです。
個人事業主から会社にする法人化・法人成り
【 建設業・建築業で法人化・法人成りのポイントは、】
法人化のメリットやデメリットを理解し、 今後の流れを抑え、判断する慎重な姿勢です。なぜなら、法人化は金融機関の借り入れ引継ぎ
社会保険の加入手続きから建設業許可申請など
多くの手続きが必要にとなりますし、
何より得意先・仕入先に手続きを依頼するためです。そのため、個人事業主から会社にしたけれど、
個人事業に戻したいというわけにはいきません。法人化や法人成りで失敗しないためには、
個人事業主から会社にする場合の長所や短所を
理解した上で慎重に実行することが重要です。
 【 インボイス改正後の法人化や法人成りの長所 】
【 インボイス改正後の法人化や法人成りの長所 】
・消費税免税又はインボイスで課税事業者になっても
2割特例で【 消費税を大幅節税できる。 】
・一定所得から所得税より法人税率が低くなり
税率差を利用した節税できる。
・保険活用など退職金で節税対策が可能になる。
・株式会社など会社にした方が、
採用でも有利になり人材不足解消が期待できる。
【 法人化や法人成りの短所 】・株式会社を設立するには、
登録免許税等の諸費用が25万円ほどかかる。
・社会保険が、【 強制加入 】になる。
【→ 短所ですが、建設業では長所にもなります。】上記が一般的な法人化や法人成りの
長所と短所として挙げられます。
【 個人事業主の所得税率と税金の仕組み解説 】
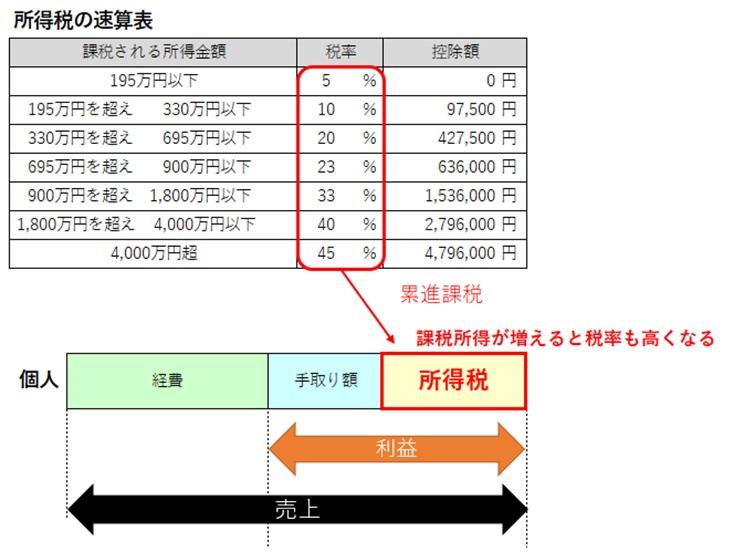
【 株式会社など法人の税率と税金の仕組み解説 】
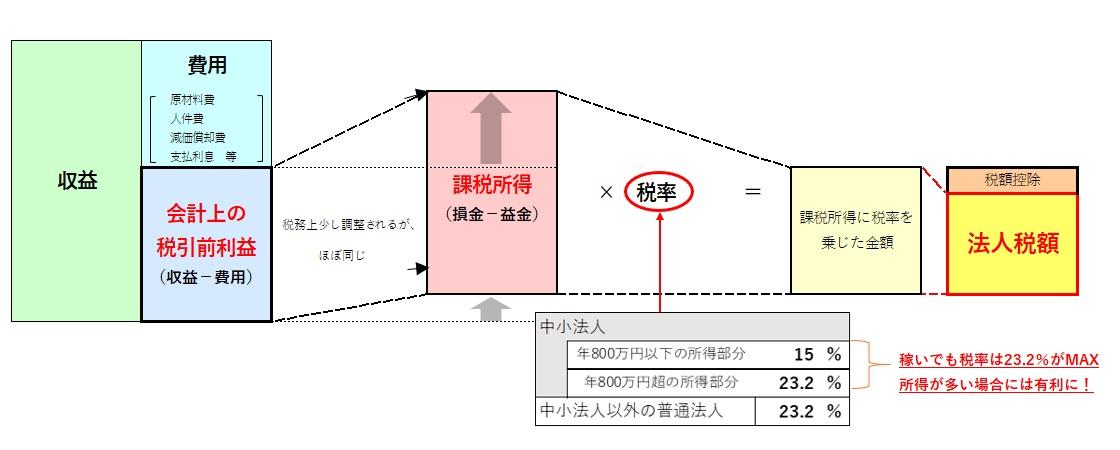
建設業の法人化・法人成りはどう判断すべきか
それでは、建設業や建築業での法人化の判断は
どうすればよいのでしょうか?
建設業や建築業の方は、建設業の許可取得で
大型案件工事が受注可能になりますが、
建設業許可では、社会保険加入が必要とされます。このため、【社会保険加入】がITやサービス業など
建設業以外では、【短所】になりがちですが、
建設業許可取得で、大型案件を受注できれば より多くの利益を上げることができるため、 建設業では、【 長所 】になる事が多いのです。
また会社設立の費用である25万円は、
消費税免税 又は 2割特例節税で回収できるため、
今後、建設業許可をとって大型案件を受注し、
事業拡大したい場合、ほぼ法人化が有利となります。匠税理士事務所の法人化・法人成りサービス
匠税理士事務所は、建設業や建築業に強い税理士が
建設業や建築業の法人化・法人成りを担当します。
まずお客様の経営状況を的確に把握するため、
過去2年分の確定申告書と決算書を確認し、
消費税の納税義務の状況や利益の状況、 今後の事業展開などを確認した上で、法人化・法人成りの長所や短所を説明します。
会社にするメリットが少ない場合にも、
正直にお伝えしますので、
10社ご相談を頂いて6~7社のみが会社にされ、 残りは個人事業で継続されることが多いです。◇法人成りのサービスはこちらから↓
建設業や建築業の法人成り相談会
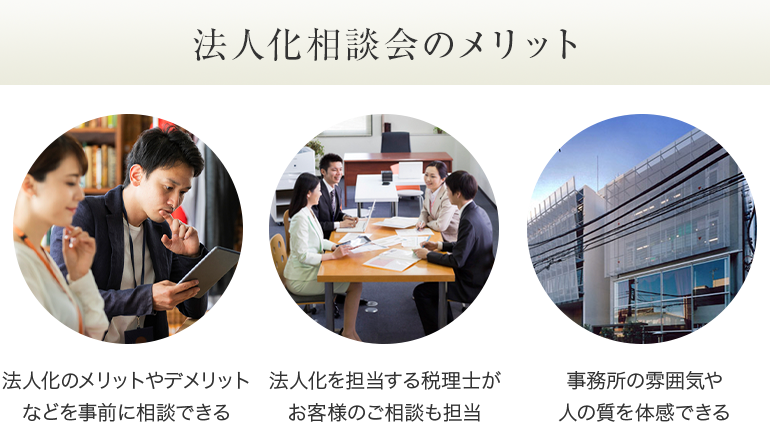

無料相談会のご予約は、
お手数ではございますが下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にて
ご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、
ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様と打ち合わせ後削除し、勧誘連絡等一切致しません。
無料相談では回答できない事もございます。
法人成りを担当する税理士・専門家詳細はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】
◇当会計事務所のサービス全般はこちらから
【 → 起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】
東京都や神奈川県全域対応の会計事務所です。

法人成りに伴う社会保険加入手続き
匠税理士事務所では、人事労務の専門家である
社会保険労務士とも提携しておりますので、
株式設立にあたっての社会保険加入手続きや、
社員の方を雇用されることになった場合の
人事労務手続きにも対応可能です。
特に建設業や建築業は社会保険の加入について
厳しい確認がされリスクある事業ですので
労災や労務トラブルなどにも備えが必要です。人事労務専門家の社労士と法務の専門家の弁護士で
社長様が本業に集中できる環境をサポートします。
◇給与計算や社会保険手続きサービス
建設業や建築業の建設業の許可申請
また、法人成りをして大型の工事案件を
受注される際は建設業許可申請も必要になります。
匠税理士事務所では、法人化・法人成りに伴う
官公庁の手続きと社会保険の手続きと連動して、
建設業の許可申請を専門とする行政書士が
許可申請の代行を行っております。
建設業許可を将来取得したい方にも、
現状の分析と残りどのような要件を充足できれば
建設業許可がとれるかコンサルティングも行ってます。
建設業の許可申請にご興味のある方はこちらから
ご確認をお願い致します。
建設業や建築業の法人化・法人成り代行と会社設立
匠税理士事務所では、
建設業や建築業の法人成りに必要な全てをご用意致しております。世田谷区や目黒区、品川区など東京都で建設業や
建築業の会社を立ち上げたい方はご相談ください。
◇建築向け創業融資サービス

◇建築向け会社設立サービス
◇法人成りの情報館バックナンバーはこちらです。
◇法人のお客様は、こちらです。
◇個人のお客様は、こちらです。
◇お役立ち情報
建設や建築の経営ノウハウを掲載しております。
今回の記事では2023年(令和5年)のインボイス改正後の消費税2割免税を加味して記載しておりますが、
最終的なご判断は自己責任でお願いいたします。
執筆者・文責:税理士 水野智史
防水塗装工事や内装仕上工事業に強い会計事務所は匠税理士 (19/03/13)
匠税理士事務所へご来訪ありがとうございます。
弊所は、防水塗装工事や内装仕上工事業など
建設業に強い会計事務所です。
防水塗装工事や内装仕上工事業というお仕事は、 【技術・ノウハウ】の占める割合が大きいのが特徴です。特殊な加工を行うことを主としますので、
こうした【技術・ノウハウ】を持つ社員や外注先を
確保することが、極めて重要となります。
一方で職人さんの高齢化に伴って、
この人手不足が深刻な分野でもあります。
特殊な技術・ノウハウは、すぐ身に着けることが難しく、
時間をかけ人材採用・教育を行うことが重要で、
この採用と教育ができる会社は、
安定的に事業を伸ばしていける傾向があります。
逆に人を確保できなければ、
外注先の活用という選択肢になりますが、
社内のスタッフに比べて割高になり利益が減るため
人材が生命線の事業ということができます。
防水工事・塗装工事や内装仕上工事業の資金調達に強い会計事務所
防水工事・塗装工事や内装仕上工事業は、
他の建設業に比べ建材仕入の金額は低くなり、
事業が軌道に乗るまでの初期の設備投資を
うまく切り抜けれるかが、ポイントになります。
代表的な初期投資では、現場の工具や
それを乗せるための車両などになります。
この初期投資のための資金調達をしっかりと
安定的に行うことに成功できれば、
【売上の早期回収】+【支払を遅くする】という資金サイクルの基本を抑えることで、
会社のお金は上手に流れていきます。

そのため防水工事・塗装工事や内装仕上工事業で
起業や独立開業される方に初期投資に備えて、
日本政策金融公庫の創業融資を提案しています。
金利は2%程で、500万円を5年返済で借りれば、
元金は、500÷60か月=月額で約8万円の返済。
金利は月額で約8,000円ほどですので、
借入を生かし、それ以上に稼げばいいのです。無事に資金調達に成功することができて、
良い人材の採用又は外注先を活用して
利益が確保できる仕事を請けて
納品ができればお金は着実に増えていきます。

こうして事業を軌道にのせ、更に人に投資すれば、
より多くの利益が上がります。
防水工事・塗装工事や内装仕上工事業の成功ポイント【1】創業融資の資金調達で初期投資を行う
【2】人材の採用と教育の仕組みを作る
【3】臨機応変に対応でき外注先を増やしておく
ということをしっかりと行うことが重要です。
匠税理士事務所では、日本政策金融公庫と連携して
創業融資による資金調達を得意としております。
起業に強い税理士がしっかりサポートしますので、
【融資の成功率は95%】を超えてます。創業計画書の作成などご要望の方は、
こちらからご確認をお願い致します。

建設業許可申請や入札、社会保険など建設業に必要な全てを用意する税理士事務所
匠税理士事務所は、建設業専門の行政書士と連携し
税務会計は当然ですが、建設業の許可申請から
入札手続の代行やキャリアップシステムにも対応しており、
建設業に必要な全てがそろう会計事務所です。外国の方を雇用される場合は、就労ビザ対応の
行政書士と連携し、人材面のサポートも可能です。
また、世界4大会計事務所出身の税理士が在籍し
経営セミナーで講師を務めておりますので、
経営コンサルティングも好評です。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

匠税理士事務所の所属税理士や提携先の専門家は、
こちらからご確認をお願い致します。
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

【 → 仕事への考え方 】
建設業の起業・創業・独立をお考えの方で、
株式会社や合同会社などの会社設立をお考えの方はこちらからご確認をお願い致します。【関連記事 →建設業や建築業の会社設立・創業融資なら匠税理士事務所 】
防水工事・塗装工事や内装仕上工事業で建設業許可
申請代行を要望の方は、こちらを確認下さい。
販路拡大のため公共工事の入札にご関心のある方はこちらからご確認ください。
【関連記事 →入札とは?わかりやすく説明。入札メリット・流れ・落札も解説 】
建設業の企業様向け匠税理士事務所の経営サポート詳細はこちらからご確認下さい。
建設業や建築業で個人事業主化から株式会社や合同会社など会社にしたい方向け法人化についてはこちらから
執筆者・文責:税理士 水野智史
#防水塗装工事税理士 #内装仕上工事税理士
建設業・建築業で粗利率はどのくらいが平均?経営改善ポイント (19/03/06)
建設業や建築業の経営分析・経営改善のお仕事を
させていただくことが多いのですが、
多くの経営者の方の相談として、
【 1 売上は伸びているが、利益が残らない。 】
【 2 売上はあるが、お金が残っていない。 】
ということがあります。
共通項は、売上は上がっているということです。
つまり、売上【量】は上がっていますが、
利益【質】に課題があるということです。そのため、経営改善次第では、黒字化は可能です。
建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均は、概ね20%です。
匠税理士事務所では、お客様と一緒になって、
下記のような経営改善に取り組みますので、
弊所の建設業のお客様の粗利率は平均30%~40%になっております。
黒字・赤字の8割は、粗利率で決まります。
そもそも、粗利(売上総利益)とは何でしょう?
売上から仕入や外注費などの原価を除いた利益が、これが粗利(売上総利益)です。
売上高 - 売上原価 = 粗利(売上総利益)そして、売上に占める粗利(売上総利益)割合、これが粗利率(売上総利益率)= 完成工事高総利益率です。
粗利から会社維持の固定費(給与・家賃)を除いて
最終的には利益が残れば【 黒字 】、粗利が固定費に足りなければ【 赤字 】というわけです。このように経営は非常にシンプルです。
固定費である人件費や家賃は社長の意思決定で、
人員を削減したり、オフィス縮小などで、
減少させることは可能ですので、粗利の最大化が
会社経営のポイントになります。

粗利(売上総利益)の大きい会社は、人が多くて
多少無駄な経費があっても黒字になります。
逆に粗利が少なければ、どんなに経費削減、
コストダウンをしても赤字体質になりがちです。
このようなことから事業経営の8割は、
粗利(売上総利益)で決まります。
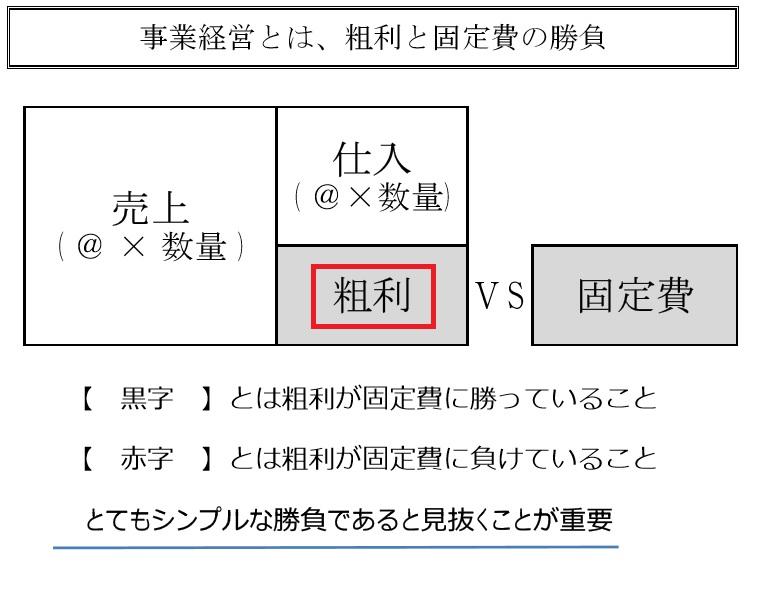
では粗利率(売上総利益率)・完成工事高総利益率の改善は、何故難しいのでしょうか?
それは、売上高-売上原価=粗利(売上総利益)なので
【粗利最大化】=【売上最大化】と【仕入・外注費等の原価最小化】が必要になるからです。1 売上最大化 = 得意先と売価交渉 が必要
2 原価最小化 = 仕入・外注先と交渉 が必要
というように社長の意思だけでなく、相手先と交渉が必要なため粗利率(売上総利益率)の改善は難しいのです。それでは、建設業・建築業の会社の場合の粗利率の平均はどれくらいで、
どれ位を目標にすればよいのでしょう?
建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均はどれくらい?改善方法は?
建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均は、概ね20%です。
そのため、現在20%の会社はこれに安心せずに、
25%から30%を目指していないといけません。
何故なら材料費・人件費は下がることはなく、 長期的には上昇していくからです。それでは、粗利率(売上総利益率)の改善には
どのようにすればよいのでしょうか?
【 1 売上高の最大化 】 ≪ 方法1 販路の強化 ≫ →得意先数を増やし、工事単価を見直す得意先と価格交渉をするということは、
無事に【 交渉成立 】又は【 交渉決裂 】
の大きく2つの結果になります。
前者であれば良いのですが、交渉の場合には下手をすると今後の取引にも支障が出てきます。
そこで得意先数を20%程の利益率でも良いので会社経営が安定する規模まで増やしておき、
万が一の場合にも動揺しない状態が必要です。
ある程度得意先数がそろったら、
一気に価格交渉をするのではなく、
一社一社全体のバランスを見て進めていくという流れとなります。これは忙しすぎて工事が請けられないという状況をイメージしていただくと
忙しい時期には、安い工事は請けません
ということになるのではないでしょうか?
 ≪ 方法2 取り扱い商品構成の変更 ≫
≪ 方法2 取り扱い商品構成の変更 ≫
現在、技術のみ提供し組み立てのみの場合は、
ここに材料を自社で仕入をして、組み立てまで行うというイメージだと分かりやすいかもしれません。
技術のみ提供し組み立てのみの場合の粗利に
材料の仕入まで行うことで、材料の小売り分の粗利も確保するという発想です。
ある会社からまとめて材料を一括して仕入れると
確かに手間や時間はかかりませんが、
安く仕入れて、高く売るチャンスを逃してます。
材料を仕入れる際に、インターネットで単価を調べて仕入先に交渉してから、
できる限り安く仕入れをすることでも原価率は下がります。この一手間が粗利の確保につながります。
≪ 方法3 手数料ビジネスの余地はないか検討 ≫発注主のニーズの中で、提携先を使うことで解決できそうな工事がある場合、
業者さんを紹介することで紹介手数料などを頂く
というビジネスがないか検討しましょう。
手数料ビジネスは金額的には僅かでも、 【 粗利率100% 】なわけですので効果大です。『 現場でお客様の声に耳を傾け、自分の知り合いでお客様の問題を解決できそうである。 』
この発想が手数料ビジネスの原理原則です。
現場のお客様の声から今一度考えてみましょう!
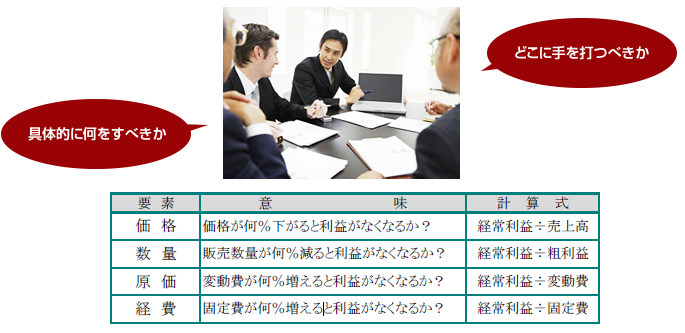 【 仕入・外注費の原価の最小化 】
【 仕入・外注費の原価の最小化 】
≪ 仕入先と外注先の強化 ≫
→仕入先と外注先数を増やし、単価を見直す
これは得意先の価格交渉と同じく、
無事交渉がまとまることもあれば、
交渉決裂もありえるため、質・単価同じ水準の
仕入先と外注先を何社か確保したうえで、
より条件が良い仕入先と外注先にシフトしていくという考えです。
これも得意先同様にある程度数がそろったら、
一気に交渉をするのではなく、
一社一社全体のバランスを見て進める流れとなります。
売上も仕入・外注費などの原価も、利益率を高めるには、【 選ぶ 】という作業が重要で、
【 より良い条件を選ぶこと 】=【 利益率の改善 】ともいえます。そのためには、より多くの条件の中から選べる状況を生み出せるか、
この努力を繰り返すことが、条件の改善→利益率の改善につながるのです。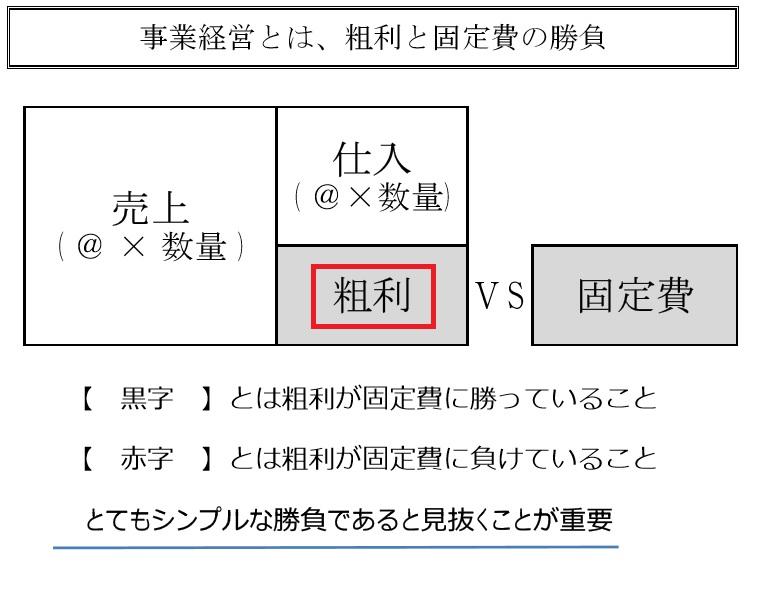
赤字会社の立て直しや黒字会社の更なる黒字化には
次の【 4つが経営のポイント 】になります。
1 会社維持費(固定費・・人件費・家賃)の削減 2 仕入先・外注先の条件の見直しをかけることで、 原価率の改善 → 粗利率の改善 3 1と2の実行後、客数増化の販売促進 ( 1と2で出た利益を販促へ投資 ) 4 得意先が増えたら、条件のよいところにシフトし 粗利率の更なる改善この1から4の流れをポイントを抑えて実行することで
ほとんどの会社は黒字化出来ます。

匠税理士事務所では、建設業を中心に経営コンサルティングに力を入れており、
弊所の建設業のお客様の粗利率は平均30%~40%になっております。
◇建設業の企業様向け経営サービス
それでは黒字化成功後の次の課題は何でしょう?
利益が出て、お金が残る会社が理想です
売価・原価の見直しを通じて粗利を最大化し、
利益が出るようにするのと同時に、お金がたまる会社づくりが重要です。【 黒字で利益がでる=お金がたまる 】 だから問題ないじゃないか と考えがちですが、
お金がたまる会社づくりにはポイントがあります。
◇以前にまとめたこちらの記事も確認下さい。
匠税理士事務所では、世界4大会計事務所出身で経営セミナーで講師を務める税理士が、建設業・建築業の経営者様と一緒に利益が出てお金が残る会社づくりをサポートします。
会計や税務の知識を駆使しながら、社長様の悩み課題に一件一件丁寧に取り組みます。
◇所属税理士や提携先は、こちら

◇建設業許可申請サポートサービス
建設業許可申請はこちらから確認下さい。
◇建設業・建築業のサービス
○法人のお客様
○個人のお客様
◇建設業・建築業のお役立ち情報
◇建設業・建築業限定の相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇起業支援・法人化サービス
建設業・建築業で粗利率を改善するまで
資金確保などを支援するための
創業融資サービスはこちらから確認下さい。
【 → 税理士による創業融資】
建設業・建築業で粗利率改善への
経営支援から会計・経理など全てお任せの
会社設立サービスはこちらから確認下さい。
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
補助金・助成金などにも対応で経営改善する
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業創業支援】
個人で独立開業した建設業で粗利確保できたため、
会社にする法人化はこちらからご確認下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#建設業粗利率
#建築業粗利率
建設業・建築業の資金繰りと銀行借入・融資の運転資金調達 (19/03/03)
匠税理士事務所は、建設業や建築業の経営支援に
力を入れている会計事務所です。
建設業や建築業のお客様の最大の悩みは
【 資金繰り 】がもっとも多いのですが、
これは事業の性格上、取引金額が高額であり、
かつ 次のような取引の流れになるためです。
1 材料の仕入れ
2 外注費の支払い・給与の支払い
3 工事完了後、1~2か月後に入金
入金まで材料の支払い・外注費の支払いが先行し、
工期が長い事業であれば1か月から6か月、
無事納品して2か月後に入金。

しかも1,000万の取引で、原価率を70%とすると、
無事2か月後に入金されれば、問題ないのですが、
得意先の資金繰りが厳しく入金されない、
原価700万の支払で更に経営が難しくなります。
こうした流れで起こるのが、
売上・利益があるが、支払不能になる黒字倒産です。建設業や建築業で資金繰りに困らない経営
建設業や建築業でお金に困らないようにするには、
まず得意先の経営に問題がないかを見極めること。
意外にこの作業をされてない会社が多いのですが、
この見極めをしっかりとしないと工事はしたが
お金が入ってこない【最悪の展開】になります。
つまり上記では工事原価700万円が出ていく分、
【 損 】になるというわけです。
一生懸命に頑張ったのに、
倒産という【 黒字倒産 】は絶対に回避です。
得意先の経営状態に問題がないようなら、
【 入りは早く、出は遅く 】という 入出金サイクルを決めることが次に大事です。大規模工事なら原価は、前金で交渉しましょう。
この交渉が難しいようなら、
【 3分の1 又 は2分の1完成した段階 】で入金してもらうというように入金を早くし、
一方で材料の支払い又は外注費の支払いを
仕入又は作業後の2か月後にするなど、
支払いのタイミングと入金のタイミングを
できる限りそろえていくという努力です。
お金がたまる仕組みづくりをしてから、 次に儲ける(利益を出す)仕組みが重要です。
建設業や建築業の銀行借入・融資の考え方
資本金500万円で会社をはじめ、
最初から上記のように工事原価700万円が出ていく仕事が受注できた場合、
入金までお金が不足することになります。
そのため、銀行借入・融資による資金調達を
上手に活用する必要が出てきますが、
銀行借入・融資には大きく2つの考え方があります。
【 短期間の銀行借入・融資 】これは、半年ほどの工事受注に成功した場合、
完成し入金までの半年から1年間のみ短期間で
借り入れを行うという借り方です。
この方法は、資金が必要な時のみ調達できますので
立ち上げたばかりの会社でまだ資金力がない場合は
大変有効な方法となります。
一方で比較的金利は高めに設定されることが多く、かつ得意先の財務状態が問題なく
工事の請負契約書が出ていることや、
常に資金不足でなく、受注案件立替えの資金が
必要なことを資金繰り表で証明できるなど
銀行・金融機関が融資しても無事回収が
できることの説明が条件になります。

この取引を繰り返せば、利益相当が会社にたまり、
返済の実績を積めば、融資枠が増えたり、
下記に述べる長期融資も検討してもらえます。
【 運転資金など長期間の銀行借入・融資 】入金までの一時的な期間をカバーする短期融資に対して、会社を経営していくための運転資金として、
5年ほどの期間で借り入れする長期融資があります。

このメリットは、ずばり会社にある程度のお金を
常に安全資金としておいておけることで、
安心して経営をでき材料が安いときに
大量に仕入在庫をもてること、急に仕事がきても お金を心配せず受注など選択が増えることです。金融機関としては、融資期間が長くなればなるほど
会社のリスクは上がるため、短期に比べ融資額は
小さくなりがちですが、活用したいところです。
それでは会社の資金繰り・キャッシュフローを
良くするためにはとのように金融機関と付き合い
融資を受けるべきでしょうか?
答えは色々とあると思いますが、
最終的に【短期・長期の両方を併用】することです。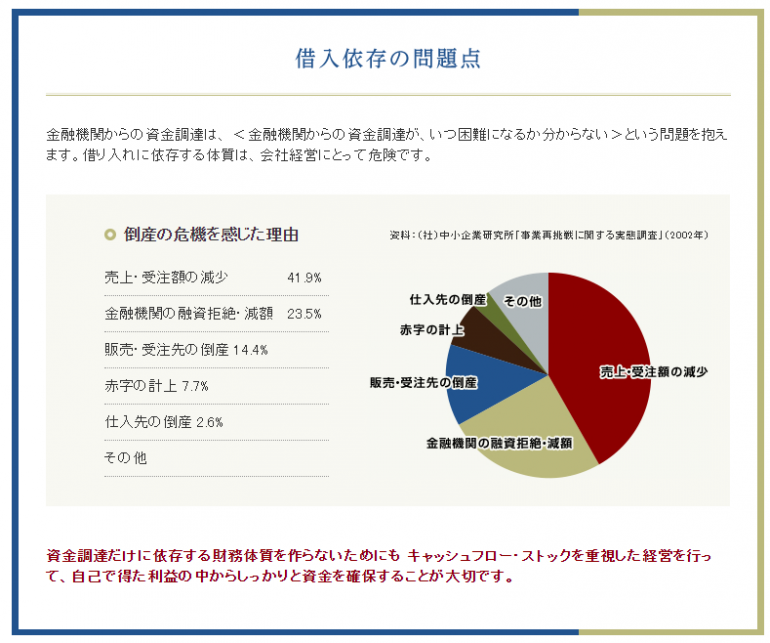
長期融資で運転資金として5年から10年で
お金を借りておき会社の資金の安定性を高めながら
小・中規模工事に対応し大型工事が受注できれば
短期融資で対応するというどちらに転んでも
資金に困らない経営が理想ではないでしょうか。
この小・中・大規模工事に上手に対応することで 利益を上げる速度を加速させ、利益の内部留保を進めるながら金融機関と信頼を積み重ねるのが、 建設業や建築業の経営の【 王道 】だと考えます。
お金がたまる仕組みが出来たら、たまる速度をあげるための利益率(粗利率)の改善を行うと、
加速度的にお金が増える良いサイクルつながります。
◇利益率(粗利率)の改善は、
以前にまとめたこちらの記事もご確認下さい。
建設業や建築業に強い匠税理士事務所概要
弊所は、利益最大化と資金繰りの改善を通じて
儲かって、お金がたまる会社作りを支援してます。
大型案件が決まりそうなので短期融資を受けたいが
資金繰り表の作成を手伝ってほしい、
運転資金の調達をサポートしてほしいなどの
ご相談にも対応しております。
◇所属税理士や提携専門家は、こちら
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
建設業や建築業の方に向けたサービスや
事務所のご案内はこちらから
【→ 建設業や建築業に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都全域に対応する会計事務所

建設業や建築業のお客様向けサービス一覧 匠税理士事務所では、建設業や建築業の経営のすべてがそろう事務所を目指しております。
特に経営コンサルティングでは経営セミナーで講師を務める世界4大会計事務所出身の税理士が
儲かってお金が残る会社作りをサポートします。
建設業許可申請は、専門の行政書士が対応します。
☆建設業許可申請サポート
◇建設業・建築業のサービス
○法人のお客様
○個人のお客様
◇建設業・建築業の相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇建設業・建築業のお役立ち情報
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
建設業・建築業で独立開業や創業支援、
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
建設業・建築業で株式会社を作るなど
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
建設業・建築業の資金繰り改善のための
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
経理代行から節税対策、経営支援など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で独立開業し会社に組織変更する
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#建設業借入 #建設業融資
一般競争入札とは・指名競争入札とは何かわかりやすく解説 (19/02/01)
・公共工事の入札に興味があるが、
一般と指名制度はどんな内容?
・興味あるけど、何となく難しそう・・・・
・参加している会社は大きいので、
うちにはまだ早いかなぁ~、けど気になる・・・
このように思われる方も多いと思います。
そこで今回は、入札にはどのようなものがあるのかをわかりやすく解説します。
入札には、たくさんの種類がありますが、
大きく分けると、
【一般競争入札】と【指名競争入札】があります。一般競争入札とは? 入札制度を解説
形式で一番多いのは、
やはり一般競争入札です。
一般競争入札とは、細かい条件なしに、工事案件を公表し、入札登録事業済み者が応札する方法です。
一般競争入札の方法では、条件がないため、
一番低い金額で応札した会社が落札(受注)することになります。
しかし、都道府県や市区町村など自治体など発注者が定めた最低制限価格(入札下限値の価格)を
【 下回る金額で応札すると無効 】となるので注意が必要です。

これは、コストや利益を無視した不当に安い値段で取引することで労働条件を悪化させたり、 質の悪い業者の落札を防ぐ当いう目的のためです。
ポイントになるのは、前回の落札価格や
これまでの価格の平均など統計値を用いて、 価格を検討する手法です。入札を初めて行う場合、力加減が難しいですし
一般競争入札が多くなり、
過去の実績が少なくても勝負できる長所の一方で、
価格での競り合いになるため、利益がでづらくなるという短所もあります。
ただ、入札では元請けになれるので、現在利益率の改善を検討されている場合、一度挑戦をしてみるとよいかもしれません。

指名競争入札とは? どんな制度かの説明
一般競争入札のオープンな競り合いに対し、
指名競争入札とは、入札の参加登録をしている建設業者から、過去実績や規模など一定基準に基づき、
都道府県や市区町村など自治体など発注者から 【工事案件を公表するので、入札に出ませんか?】と案内し、発注業者から指名された建設業者のみが応札できるクローズな感じのする入札方法です。
都道府県や市区町村は、税収で運営されており、
管轄地域に本店など事業所がある業者を指名し、
結果として地域活性化を図りたいなど目的もかなえられるなど利点もあります。

一方でこれまで落札をした実績の多い会社の中での工事案件の回しあいになるなど
自由競争が働かない談合(順番で落札できるよう数社間で協定を結ぶ)になる可能性もあります。
上記以外にも、随意契約や総合評価方式での入札などもありますが、
あまり一般的ではないので今回は省略致しますが、一般競争入札や指名競争入札がほとんどです。

◇入札制度全般や入札のメリット・流れの詳細は、下記よりご確認ください。
入札や落札など建設業を支援する会計事務所です。
匠税理士事務所では、東京都23区を中心に公共工事に取り組む建設業を支援する会計事務所です。
決算書の作成はもちろんですが、
許可申請取得から経営審査もサポートします。・新たな販売先に入札を検討している。
・地元建設業者が入札に参加してるので気になる。
このように入札に興味がある会社様は、
お気軽にご相談ください。
また、入札では許可申請が重要になりますが、建設業許可申請も専門の行政書士が対応します。
詳細はこちらからご確認をお願い致します。
建設業許可申請はこちらから確認下さい。
 匠税理士事務所は、建設業界に必要な全てがそろう会計事務所です。
匠税理士事務所は、建設業界に必要な全てがそろう会計事務所です。
世界4大会計事務所出身で経営セミナー講師を務める税理士が丁寧にサポート致します。
建設業向けの会計や経営コンサルティングなどに興味がある方は、こちらからご確認下さい。
◇所属税理士やサービスはこちらから


建設業や建築業のお客さま向けのサービスページ
◇建設業や建築業のサービス
◇建設業や建築業の相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇建築業に向けた起業支援
一般競争入札・指名競争入札の用意など
軌道にのるまでの起業資金調達など
創業融資サービスはこちらから確認下さい。
【 → 税理士による創業融資 】
建設業の株式会社など会社を作るための
会社設立サービスはこちらから確認下さい。
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
入札支援から補助金・助成金の獲得などの
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で独立開業した建設業を会社にする
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 東京都で税理士の法人化・法人成り】
建設業や建築業の経営ノウハウのお役立ち情報
◇お役立ち情報
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
入札に必須の経営事項審査(経審)について
建設業や建築業の資金繰りと銀行借入・融資による資金調達のポイント
一般競争入札とは何か、指名競争入札とは何かをわかりやすく解説してみましたが、
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#一般競争入札
#指名競争入札
建設業や建築業の会社設立・創業融資・起業は匠税理士事務所 (19/01/31)
ご来訪ありがとうございます。
匠税理士事務所は、建設業・建築業の会社設立など【起業・創業支援】で実績がある事務所です。
建設業や建築業で独立開業するための起業支援では
【 社名と本店所在地 】のみをお決め頂ければ、書類作成や登記は税理士・司法書士にお任せという
起業支援・会社設立サービスをご用意しております。
また書類作成のみの起業支援や会社設立ではなく、
起業セミナーや経営セミナーで講師を務める 世界4大会計事務所出身の税理士を軸に【会社設立後の起業成功】までお手伝いします。
そして、建設業で会社設立後の起業成功には、
1 資金調達で、成功する 2 資金を活かし、増やすこと【経営】に成功するという【 2つの成功 】が重要であると考えます。

なぜなら、自己資金が少なければ動かせる
【 材料 】・【 人員 】に限界があるため、
受注できる仕事量や規模・幅に制限がかかります。
結果、技術的に優れていても、資金面の問題で
大規模工事が請けられないという事になり、
利益確保が難しいという展開となります。
このようなことから、【建設業で会社設立】をして
成功するため最大の壁は、【資金調達】となります。そして、この創業融資による資金調達の成功には、
会社設立・社会保険・建設業許可が重要になります。

一見、創業融資とは関係ないように感じますが
融資条件に【建設業許可】が要求されるからです。理由は建設業許可があれば500万円以上の大規模
工事受注で返済力が高いと見られるからです。
逆に許可が無いと返済力が下がり、 創業融資の成功確率も低下します。建設業許可は会社謄本・社会保険が必要になるので
会社設立・社会保険加入・建設業許可の適時完了は、
融資成功では、非常に重要な要件になります。
建設業や建築業の起業支援の難易度が高いのは、
許可・会社設立・社会保険を同時に進める必要があり
ミスなく行う専門性とノウハウが求められるためです。
匠税理士事務所では、起業セミナーで講師を務め 世界4大会計事務所出身の税理士が在籍してます。 【お客様の一生に一度の起業を成功に導けるよう】全力でサポート致します。
サービス詳細はこちらから確認下さい。
【 → 起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】

独立・開業・起業向けサービスはこちらから
【→ 起業のお客様 サービス一覧】
建設業や建築業での会社設立はこちらから

起業成功のポイントは、創業融資の資金調達
建設業や建築業の起業成功のポイントは、
創業融資による資金調達のタイミングです。
ここでいうタイミングは、上記作業を同時に進め、【 できる限り最速 】で行うのがポイントです。
具体的には、会社設立・社会保険の切替・許可申請という手続き業務を進め、
【同時並行】で政策金融公庫の創業融資による 資金調達を進めておくことです。日本政策金融公庫創業融資による資金調達で、
幾ら借り入れができるか早くに分かれば、
他の方法での資金調達の検討や、
規模・初期投資の縮小を早く判断できるからです。

逆に同時並行で進めないと、建設許可は取れたが、お金の調達が完了しておらず、
機材の購入などが遅れ、創業計画書作成から融資の申し込み・実行までの約1か月から2か月の期間、
【 動けない 】ことになりかねません。ただ全てを税理士が行うのは難しいのも事実です。
そのため、弊所では税務手続と創業融資に注力し、
起業後の全体スケジュールを把握した上で、
建設業のお客様専属の ①税理士②司法書士③社会保険労務士④行政書士で 各分野の4人の専門家によるチームを編成し、【各専門家4人分の速度と品質】を生み出す事で
早くかつ正確な起業支援をご提供致しております。
◇起業支援担当の税理士・専門家はこちらから

日本政策金融公庫の創業融資による資金調達
建設業・建築業は、資金を多く必要とする事業です。
材料や外注費などの多額の支払いが、
工事代金の入金前に発生するため
比較的大きな資金が事業開始から必要になります。創業融資でどの位の資金準備が必要かというと
工事完了後、1~2カ月で入金というサイクルの中で
① 材料や外注費の支払いを先に行う資金
② この間の給与や家賃といったつなぎの資金
③ 初期設備投資である車両や機材などの設備資金
が必要となります。
 そこで建設業・建築業の許可申請と同時進行で
そこで建設業・建築業の許可申請と同時進行で
政策金融公庫で創業融資による調達を行います。
建設業や建築業で会社設立される方向けに
面接の立ち合いや事前の面接練習など
他社にはない独自のサービスが特徴です。
創業融資に必要な書類は、税理士が作りますので、
お客様は打ち合わせにご参加頂ければ大丈夫です。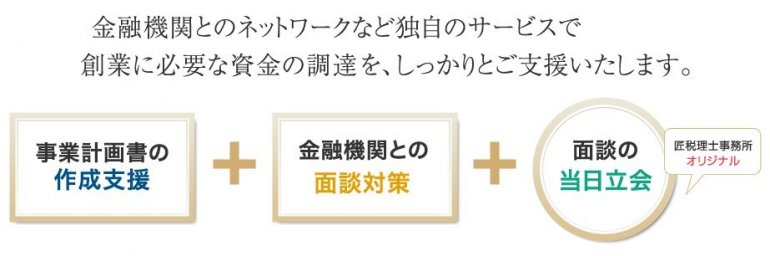
創業融資では、
【 何に、幾ら必要で、どの期間で返済するか 】分かりやすく創業計画書にまとめ、
金融機関に説明することになります。
建設業では、工事完了後、1から2カ月ほどして入金ということが多いため、
この入金までの材料などの立替・車両など
設備の投資という創業計画書が一般的です。
信用金庫様からメガバンク様まで金融機関と連携し
資金調達・創業融資で多くのノウハウがあり
また【融資成功率は90%超】トップレベルの実績です。弊所からの紹介で一部優遇もございます。
創業融資サービスは下記をご確認下さい。

起業・創業に伴う会社設立と建設業許可申請
起業して大規模な工事を受注する場合は
建設業許可を取得しなければいけません。
この建設業許可を取得するために会社設立届出書・定款と謄本・社会保険の加入が必要になります。
税理士のみでこれを全て行うと、速度は1/4ですが
行政書士・税理士・社会保険労務士のチームで行うと4倍速で行えます。またイレギュラーな事態でもそれぞれの専門家からアドバイスが得られることも利点です。
そのため匠税理士事務所では、建築業許可申請分野の専門家である行政書士と税理士・社労士が
お客様専属チームを編成し丁寧・迅速に対応します。
まずいつまでに許可を取得したいかゴールを伺い
そのゴールから逆算して会社設立をいつまで行い
社会保険加入をいつまで行うか道筋を立てます。

株式会社や合同会社の会社設立と起業支援
会社設立では許可申請専門の行政書士と連携し
① 建設業の起業支援に強い税理士が、
ご要望(会社名・本店場所・資本金)を伺った上
税務署や都税事務所への設立手続きを行います。
② このヒアリングを基に司法書士が
許可申請を前提に設計し登記を致します。
お客様は、一度税理士と打ち合わせをするのみで お任せいただいて事業に集中していただけます。 このようにして法律上、会社が出来上がります。 建設分野の会社設立や起業支援はこちらから↓ 起業して会社が出来た証明である謄本と その他必要な書類をふまえて、 人事労務の専門家であるを社会保険労務士が、 社会保険の加入手続きを代行致します。 ①建設業や建築業は、他のお仕事に比べると極めて 労働中の事故である労災が多いこと。 そのため対応を誤るとトラブルになりかねません。 役員も含め労災特別加入はポイントです。 ②起業後、建設許可申請に必要要件に、 社会保険加入があること。 匠税理士事務所では、社会保険や労働保険につき、 専門家である社会保険労務士や弁護士と提携し お手間を最小にし会社を守る体制を用意致します。 給与計算・社会保険代行サービスはこちら 【→ 社会保険や給与計算の代行サービス 】 法務・税務・社会保険など起業の手続きが終了したら 建設業許可専門の行政書士が申請代行致します。 建築業や建設許可申請の取得は一見、 自分でできそうですが、実際やると複雑です。 建設業に特化した行政書士が 建設業・建築業の許可申請サービスはこちらです↓ 建設業には、【 建築工事、土木一式工事、舗装工事、とび・土木工事、大工工事、左官工事、石工事、タイル、れんが、ブロック、屋根、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ、板金、ガラス、熱絶縁工事、さく井工事、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事 他全29種 】の分野で許可申請と更新が必要になります。 独立開業や起業創業に伴う申請などを 行政書士が代行します。

建設業の許可申請を前提とした社会保険加入手続など創業サポート


建設業で注意すべき労務の論点は2つあります。

建設業許認可申請専門の行政書士の申請代行
東京都知事許可の申請から大臣許可申請に対応し
お客様のご要望・今後の事業の方向性を伺った上で最善の提案を致します。
会社設立から創業融資など起業後の流れ

それでは、具体的に建設業で独立開業する際、
会社を辞めてからの流れを説明します。
現在会社に勤務され、5月起業を考え、
【 8/10退職、9月から稼働 】を例とします。
会社設立から建設業許可取得までの流れ
⓵ 5月に税理士と打ち合わせ
会社名、本店の場所、資本金など新会社の設計決定
【 → 同時に創業計画書作成と必要資料用意 】
② 1週間程で司法書士にて⓵の設計書で登記手続
③ 登記申請から2~3週間で謄本入手
④ 謄本入手と同時に創業融資の申込
銀行口座の開設・税務署などの届出書
⑤ 勤務先の退社後に社会保険の変更手続
→ 2~3週間で新設法人の保険証入手
⑥ ⑤の後、すぐに建設業の許可申請
→ 約1か月で建設業許可取得
建設業や建築業の起業は、上記の流れとなります。
何だか自分で全てやると頭が痛くなりそうですが、専門家チームを活用すると、
1時間半打ち合わせに参加して、社名など最低限の事を決めて頂ければ、後はお任せとなります。
このスケジュールを表にしますと下記になります。
(官公庁の混雑具合で、多少前後します。また下記表は余裕をもったスケジュールになっています。)
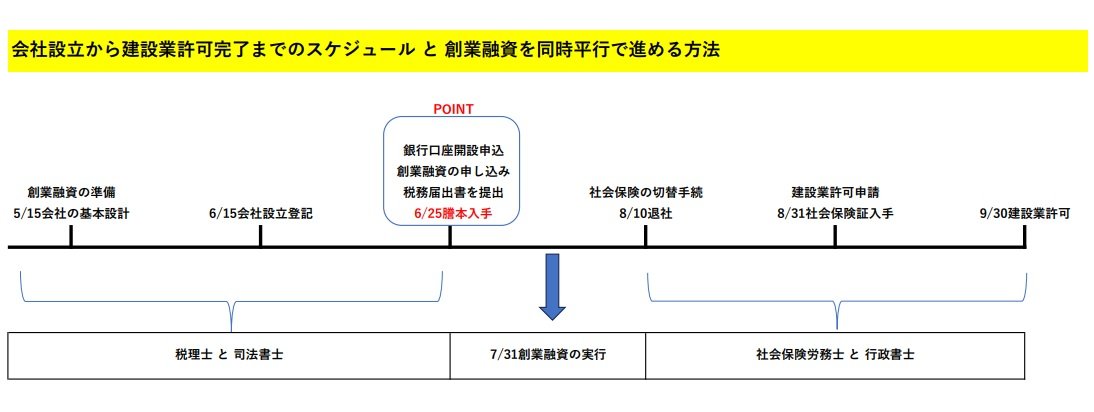
建設業や建築業に強い税理士・会計事務所
当会計事務所は建設業や建築業の起業支援に強い
税理士が所属する会計事務所です。
建設や建築は、取引金額が大きいため税務調査など
リスクが大きい業種でもあります。
税理士は一部上場ゼネコン~建設業の起業支援まで豊富な経験を有しておりますので、
会社設立から創業融資など資金調達、節税対策から
経営支援まで幅広いニーズにお応えできます。
建設・建築会社様のお悩みにお応えできるように、
人の雇用や給与計算・社会保険手続きは社労士、
許可申請は行政書士、代金未払いなどトラブルは
弁護士など幅広い各分野トップレベルの専門家と
連携しております。
人材不足対応で外国人の方の雇用を検討される方は
就労のためのビザ・VISA取得専門の行政書士とも
連携しておりますので、お問い合わせください。
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇公共工事受注のため入札
◇建設業や建築業の経営お役立ち情報
◇個人事業主で起業の方
起業後の建設業や建築業の法人化や法人成り
起業時は個人事業主で事業を行ってきたが、
株式会社など法人にしたい要望も対応してます。
法人化・法人成りは、経験豊富な税理士が、
丁寧に今後の方針などを伺いアドバイス致します。
◇建設業や建築業で個人事業主から株式会社にしたい方向け 関連記事
◇法人化サービスはこちら
会計事務所の起業支援対応エリア
世田谷・目黒・品川・渋谷区・大田区・港区など
東京都23区と神奈川県の全域
創業融資や会社設立をサポート
起業や創業融資、会社設立をお考えの方は
お気軽にお問い合わせください。
執筆者・文責:税理士 水野智史
入札とは?わかりやすく説明。入札メリット・流れ・落札も解説 (19/01/31)
弊所は、建設業の経営支援に力を入れてます。
経営支援の中で建設業の社長様から
入札に興味があるので話を聞いてみたいと
ご相談を頂くことがよくあります。
そこで今回は、建設業の入札とは何か?
落札など制度とその流れやメリットを説明します。
入札や落札とは?どういう制度なのか解説
入札とは、発注者(都道府県・市区町村など)が、工事を依頼し、
金額など諸条件で建設業者間が競り合いをすることで落札者(受注者)を決めることをいいます。
入札とはオークション(工事受注のためのレース)に参加すること、
落札とは実際に価格面などで競り勝ち、
商品を購入(工事を受注に成功)するという方が、イメージしやすいかもしれません。

入札には大きく分けて、
【 一般競争 】と【 指名競争 】があります。一般競争入札とは、全員で競い合う一般の形式で、
指名競争入札とは、都道府県・市区町村等の公共団体である発注者から
過去の実績等を総合的に加味して、お声ががかった一部の建設会社だけで入札するという制度です。
一般競争入札と指名競争入札の違いは
ページ最後に別記事にまとめてますので
そちらでご確認をお願い致します。
入札で建設工事を受注するメリットとは
【 1 元請けになれ、新たな収益を生み出せる! 】
入札で建設工事を受注するメリットとしては、
公共工事が受注できれば、元請けでの工事となり、利益が確保できることが挙げられます。
また、民間工事では、発注者からの依頼であれば、今後の付き合いもあるので、
人手不足で忙しいときや、多少採算が悪くても請けないといけないときも出てきますが、
公共工事入札の場合には、都合が悪ければ、 入札に参加しないなど臨機応変の対応が可能です。そのため、現在は民間工事が主の建設会社でも、
将来の収益源を作るとき有効な選択肢となります。

【 2 販売代金の回収不能のリスクを回避できる 】
建設会社の倒産の一番多いケースは、
資金繰りに行き詰まることです。
これを誘発するのが、
得意先からの販売代金回収不能です。
1億円の工事を請けて粗利率30%の場合で、
完成納品から2か月後に入金されることを見越していたところ、入金がされなかった・・・・

こうなると、材料代・外注費・人件費など70%の原価である7,000万円が先行し支払われてますので会社は一気に資金繰りに困ります。
建設業は、【ハイリスク・ハイリターン】なのでこのようなことは、どうしても出てきます。これが建設業の倒産が多い理由の一つです。
事業においてお金は血液です。つまり稼いだ利益・お金を事業に投下し更に稼ぐというのが基本です。
この血流が得意先の倒産などで代金未回収となると、事業活動が停止してしまいます。
これが不渡倒産・連鎖倒産です。建設業は取引額が大きく、ワンミス即アウトという危険もあります。

しかし、公共工事であれば、どうでしょうか?
東京都案件で入金されない、まず無いでしょう。
このように公共工事の場合には、
ノーリスク・ハイリターンも狙うことができます。【 3 工事実績がつめることによる相乗効果 】
起業したばかり、創業したばかりの時はお客様が、少ないのが通常です。
実績が多い会社に、仕事が多く集まるため、
民間工事では起業すぐは、不利なのは事実です。
しかし、入札ではどうでしょうか?
社歴が浅くても、工事規模の小さい工事では
大手と工夫次第で十分に渡り合えますし、
公共工事で実績を積むことで、この実績を生かし、
他の民間工事を狙うことも十分に可能になります。

このように公共工事入札に参加するメリットは、
かなり多くのあるのです。
地元で大手の建設会社、どこから大きな工事を
頻繁に請けているのだろうか?
このように思われた方も多いと思いますが、
意外に公共工事入札が多いです。
【 大手だから受注できたのではなく、受注できたから大手になった 】と考えると、
入札で取りにいく価値は多いのでないでしょうか。

入札をするには?必要なものとその流れ
入札はおいしそう、自社も挑戦してみたいが、
どうしたらいいのか分からない・・・
これが入札の大きな壁に感じますが、
意外と低いハードルです。
まず、
1 どこの公共工事の
2 どんな案件を
3 幾らほどでとりたいか
という基本戦略を設定します。
その際に、ライバル企業はどのレベルになり、
勝てそうなのか?
勝てる所から積極的に取りに行くのが重要です。
この基本戦略を決め、後は税理士・行政書士に任せ
入札手続き面は進めていく流れです。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
◇建設業向けサービス紹介はこちらから
【→建設業や建築業に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所】

匠税理士事務所の入札サポートサービス
匠税理士事務所には、経営セミナー講師を担当する世界4大事務所出身の税理士が所属しております。お客様のご要望や将来の展望を伺って、
どのような工事を攻めるのが得策かなどにつき、
ランチェスター戦略を軸に
販売面のコンサルティング致します。
また、民間工事など既存のお客様との受注とのバランスはどうなのかなど
会計財務面の側面のコンサルティングも行います。

上記で入札の方向性が決まれば、
【 1 】 毎月の経理から決算書と確定申告書を弊所で作成代行致します。
【 2 】 決算届出や経営状況分析などの手続きを建設業専門の行政書士が代行します。
【 3 】 上記を基に経審という経営の審査を受け、この結果を基に入札参加登録を行います。
【 4 】 上記で登録ができれば、経営状況で格付けされ、これに応じて入札が可能となります。
『 どこの役所のどんな工事を積極的に入札で獲得したいのか 』という基本戦略を建設業に強い税理士と打ち合わせをし、
決算や税務申告・経審など手続きは税理士と
行政書士がチームを編成しサポートします。
最初は低い格付けでスタートしても、
どこに向かいたいか方向を定め、実績を積み上げ、
より高い格付け工事に挑戦したいが、
どのようにすれば良いかコンサルティングも可能です。
担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇匠税理士事務所について

入札に必要な建設業の許可申請にも
建設業専門の行政書士が対応いたします。
入札とは何か知りたい、挑戦みたい、
許可申請のメリットも興味があるという
建設業者様はお気軽にご相談ください。
☆建設業の許可申請代行はこちらです。
◇建設業や建築業のサービス
○法人のお客様
○個人のお客様
◇建設業や建築業の相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇建設業や建築業のお役立ち情報
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
入札に必須の経営事項審査(経審)とは
一般競争と指名競争とは
入札とは?何かをわかりやすく説明しましたが、
いかがでしたでしょうか。
入札はメリットが多いので、流れを理解して
落札できるように努めていきましょう。
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
入札まで準備のための起業資金調達など
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
建設業で株式会社や合同会社などの
会社設立サービスはこちらで確認下さい。
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
入札・落札支援から会計や経理の代行など
建設業の起業・創業支援はこちらから
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で独立開業し、建設業の会社に変更する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#入札とは
#入札メリット
#入札
#落札
住民税の申告と特別徴収や普通徴収など徴収方法 (18/12/19)
住民税の確定申告って?
そんな確定申告をした覚えはないな?
それなのにどうして世田谷区や目黒区など区役所から納付書が届くのだろうか?
このように思われる方も多いと思います。
そこで今回は住民税の確定申告についての申告のあらすじを説明したいと思います。
住民税申告はどんな方法があるのか
住民税申告で主なものは、
1 会社員の方
2 自営業の方 の大きく分けて2つです。(他にもございますが、今回は省略致します。)
まずは、会社員の方(会社の社長などの役員の方も含みます)の住民税の申告は、
年末調整の際に発行される源泉徴収票を、
1月末に給与支払報告書という形で各所在市町村に提出することで完了します。
次に、自営業の方につきましては、
確定申告書を提出すると税務署から課税するための申告情報が所在市区町村に回されます。
これらのため、提出した自覚がなくても無事処理がされるのです。
逆にいうと税務署が担当する国税(所得税)の計算過程で誤りがあると、 これに連動して地方税(住民税)の計算も修正がはいることになるのです。結果として、税務調査などで修正申告を行うと、税務署からの国税に対するペナルティだけではなく、
区役所など地方税に対してもペナルティが課されてくるということになるので、
慎重に計算の上、年末調整や税務申告を行うようにしましょう。
特別徴収や普通徴収など住民税の徴収方法には2通りがある
住民税を徴収する方法には、住民税の徴収方法には住民税の徴収方法には
特別徴収や普通徴収という大きく2つの方法があります。
住民税の徴収方法は、原則として
給与から毎月住民税部分を天引く特別徴収の方法です。
これに対して、会社を介せずに納税者へ直接納付書を送ってもらって自分で納付してもらう普通徴収の方法があります。
こちらの方法はあくまで例外的な扱いになりますので、以下のような要件を満たした場合に認められます。(他の区市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下の普B~普Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)
(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)
しっかりと徴収方法が適切に記載されているかを選択し、ミスのない住民税の申告を行いましょう。
匠税理士事務所の年末調整や住民税申告の代行サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に年末調整から確定申告や住民税申告の代行も行っております。
お客様は書類をお渡し頂くだけで申告の代行を致します。
また給与計算手続きの代行も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
就業規則など各種規定の作成サービス
・労使間でのルールとなる会社の就業規則を作成し、
労使トラブルにならないようにしたい。
・会社の規模が大きくなってきたので、就業規則を作成しなければならない。
このような理由で就業規則作成をご検討の会社様は、就業規則作成も承っております。
◇関連記事
◇トップページ
【税理士・社会保険労務士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
◇専門家の詳細
自由が丘の税理士 匠税理士事務所の提携先一覧
お客様満足を高めるため、随時提携先の充実をし、お客様のご要望に即した最適な専門家が担当します。
創業や起業時の専門家、どこの誰に何を相談できるのか?K6 (18/05/29)
会社を設立されて起業、創業するとなると、 人の問題や、登記の問題、許認可申請の問題や税金・経理の問題等が出てきます。
それではこうした問題はどこの誰に相談すればよいのか。
また各分野の専門家はだれなのか。
このように思われた方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、会社を設立するに際して、どのような専門家がいてその得意とする分野は何かを記載します。

行政書士や司法書士、弁護士、税理士、会計士など各専門家の得意分野とは
1 行政書士(簡易な法務関係の書類作成や各種許可申請)
・各種許認可の申請(飲食店や建設業許可申請など)
・定款、議事録の作成
・定款認証の手続き
・各種契約書等の作成(簡易なもの。訴訟に対応できるものは弁護士)
・外国人のVISAなどの申請手続き
2 司法書士(登記業務の専門家)
・定款、議事録の作成
・定款認証の手続き
・各種契約書などの作成
・会社設立の登記
・会社の変更登記手続き
3 弁護士(訴訟まで想定した法務の専門家)
・契約書の作成やレビュー
→司法書士や行政書士でも法務の知識はあるので、契約書作成は可能ですが、
将来の訴訟対応を視野に入れた場合には、やはり契約書は弁護士にお願いすることがお勧めです。
・訴訟対応など法務全般
4 弁理士・特許事務所(商標権など各種権利関係の専門家)
・商標権や意匠権など各種ライセンスの登録
・各種権利関係の登録状況の調査
5 社会保険労務士(人事労務の専門家)
・社会保険への加入手続き
・給与計算の代行
・人事や労務に関するコンサルティング
・助成金の申請代行
4 税理士や会計士(会計や税務の専門家)
・会社設立時の届出書の作成
・経理や会計のサポートや代行
・決算書や税務申告書の作成
・会社経営のコンサルティング
・税務調査など税務署への対応
このように各専門家は、それぞれの専門分野を有しております。
頼るべき専門家は、経営課題により異なる
頼るべき専門家は、経営課題によりそれぞれ異なります。
いざというときのために、あらかじめ頼れる専門家を見つけておきましょう。
【 会社設立時に頼む専門家 】定款の作成、認証手続き
会社設立登記、その他変更登記手続き → 司法書士
建設業許可申請など各種許認可申請 → 行政書士
契約書の作成やレビュー → 弁護士
資金調達や創業融資 → 税理士
厚生労働省系助成金 → 社会保険労務士
経済産業省系助成金 → 認定支援機関
【 会社設立後に頼む専門家 】税務届出・会計・税務申告 → 税理士
社会保険等加入手続きなど労務 → 社会保険労務士
商標や特許の相談・手続き → 弁理士など特許事務所
法律相談・契約書の作成・レビュー → 弁護士
経営相談 → 税理士
大きく分けてこのように業務と専門家は区分できます。時折、行政書士さんで経理代行・創業融資の営業をしていますが、行政書士の試験に会計や経理、税務の専門知識はありませんので、これらの分野は独学で勉強しているという場合が多いようです。
上記のように業務を各専門家の専門分野に依頼することで、 専門家への報酬と各専門分野が最適化され、パフォーマンスを最大限に発揮することが可能です。
司法書士や社会保険労務士、税理士の報酬に対する源泉所得税
弁護士や税理士などに報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
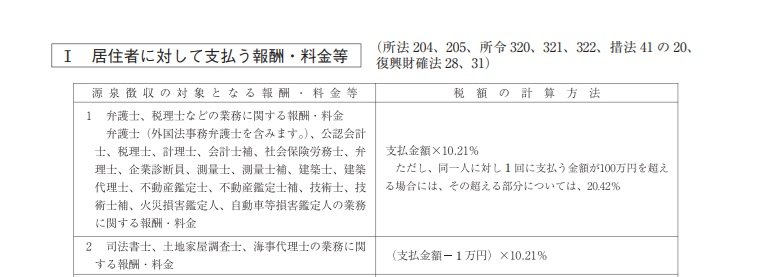
1 源泉徴収の対象となる報酬に含まれるもの
謝金、調査費、日当又は旅費等の名目で支払われるものであっても源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含まれます。
次のイ又はロは、源泉徴収の対象となる報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
イ 司法書士等に支払う金銭等であっても、支払者が国等に対し登記、申請等をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、支払手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかな場合
ロ 通常必要な範囲内の交通費、宿泊等を支払者が直接交通機関、ホテル等に支払う場合
なお報酬に、消費税が含まれている場合、原則は消費税の額を含めた金額を源泉徴収の対象とします。しかし、請求書等において、報酬と消費税の額が明確に区分されている場合は、報酬のみを源泉徴収の対象とする金額として計算することもできます。
2 源泉徴収の方法と金額
源泉徴収すべき所得税の額は、原則10.21%の税率を乗じて算出します。(詳細は上記表をご参照ください。)
3 源泉徴収した所得税を納める期限
報酬・料金等から源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。
ただし、源泉所得税の納期の特例の適用を受ければ、1月~6月までの報酬に対する源泉所得税を7月10日まで、
7月から12月までの間に支払った報酬に対する源泉所得税を翌年1月10日(納期限の特例を受けている場合には翌年1月20日)までに納めることができます。
匠税理士事務所は全ての専門家の窓口となり、お客様をしっかりサポート
弊所では、世田谷区や品川区、目黒区を中心として、起業間もないお客様のご負担を軽減できるように上記の専門家の全窓口となり、お客様のご相談に応じて提携している各分野の専門家を紹介しております。
会社概要に掲載していない提携の専門家もおりますので、お客様のご相談内容をお伺いし
お客様に各分野の専門家を紹介の上、ご自身でお選び頂いております。
匠税理士事務所の所属税理士や提携の専門家は、こちらです。
世田谷や目黒、品川など東京都全域、神奈川に対応
【 → 目黒区自由が丘の税理士は匠税理士事務所|世田谷区や品川区も対応 】
匠税理士事務所の起業・会社設立支援サービス
◇関連記事
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
◇その他の起業支援サービス
◇個人の起業サービス
法人化のメリットやデメリット、【個人事業は会社にするべき?】 (18/05/07)
匠税理士事務所の法人化担当の税理士水野です。
個人事業の規模が大きくなり、会社にすることを
【 法人化 又は 法人成り 】といいます。個人事業の法人化は大きく2つの理由があります。
【1】 ビジネス拡大(得意先の要請、採用、多店舗化)
【2】 節税メリット(役員報酬や退職金など)
一方で法人化したら、個人に戻るのは困難です。
そのため、重要事項の【 節税効果 】の理解と
同時にメリットやデメリットを知った上で、法人化を実行することが大切です。
法人化や法人成りのメリット・長所のご紹介

<★ メリット・長所一覧 ★ >
法人化の長所1
【個人と法人の税率差】による節税
メリットやデメリットの判断では、
【 節税効果 】は、重要な判断要素です。
個人の所得税は、所得により税率が上がります。
そのため一定の儲け以上になると、個人所得税率が
法人税率より高くなるので下記の所得以上なら、
法人成りを検討する時期です。
【 個人事業の所得税の仕組みと税率 】
個人所得税は、儲けにより税率が上がっていきます。現行の所得税率は、なんと最高税率45%で、
近年上がる傾向にあります。税率33%あたりから、だんだんと負担が重く感じてきます。
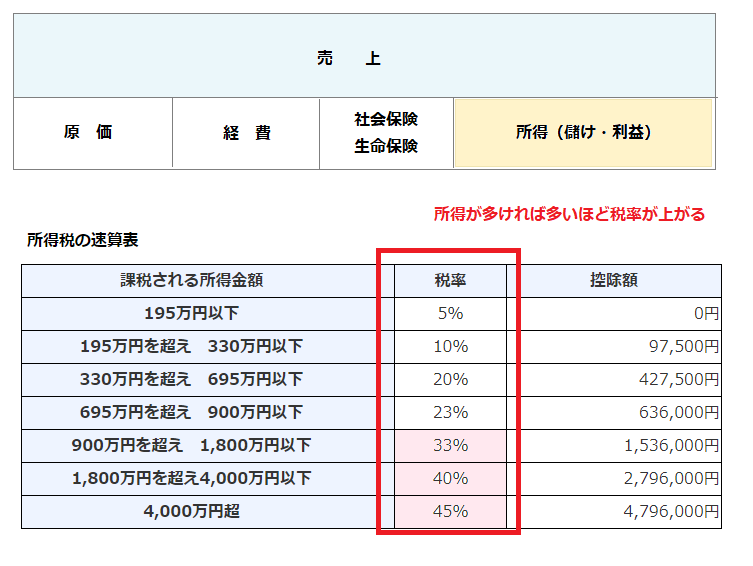
【 会社にかかる税金の仕組みと税率 】
これに対し、株式会社や合同会社などの税金は
【 最大23.2% 】、近年、減少傾向にあります。
所得税とは違い23.2%以上は上がりません。仮に900万円の所得なら
【800万円×15% + 100万円×23.2%】の税金で
5,000万円の所得であれば、
【800万円×15% + 4,200万円×23.2%】です。
所得5,000万でも大部分が23.2%税率で法人税は済んでしまうというわけです。
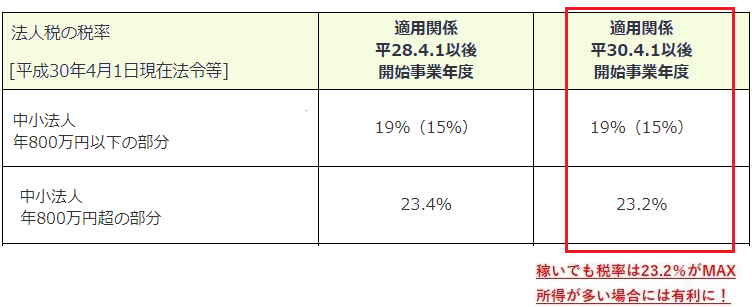
このように【個人所得税の最高税率45%】に対し、【法人税の最高税率は23.2%】であり、
所得が増えれば増えるほど、
法人成りの節税効果は、上がる形になります。
つまり、所得が多ければ多いほど会社にしたほうが税率ではメリットが生じます。
メリット:2
消費税が免税になる節税効果
要件を満たせば、【 消費税が最大2年免税 】です。
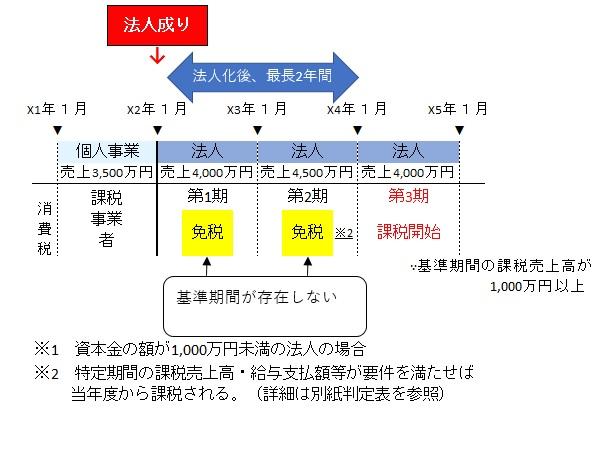
2019年10月から消費税が10%になりました。
これは個人事業を会社にする法人化の消費税免税効果がUPすることを意味します。また、2023.10月からは、適格請求書保存方式 (インボイス制度)へ移行しました。
本制度の免税は、インボイス登録番号発行がないため
免税選択で、相手先が支払った消費税の一部が
税額控除できないデメリットがあります。
結果として同じ内容の商品・サービスであれば、
【 得意先は免税事業者との取引を避ける 】
という取引の流れが想定されます。
【消費税節税するが、得意先に迷惑をかけない】 というメリットには大きな変更が起きています。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間は、
消費税免税事業者がインボイス登録をすることで消費税課税事業者になる場合、
売上にかかわる消費税の2割納付にできるという特例がございます。
こちらを活用することで、消費税免税に近い 効果を得られますので是非検討しましょう。メリット:3
退職金など節税の幅が広がる
個人事業の場合、ビジネス=自身なので、退職金をご自身に出すことで必要経費には出来ません。
しかし、会社の場合には、社長に退職金を出すことで経費化も可能です。
退職金は巨額になることが多いため、
これを利用し生命保険などで将来の退職金を交えた節税対策が可能になります。メリット:4
採用面で有利になり、人を雇用しやすい
社会保険など福利厚生が充実しますので、
株式会社は安定感が違います。
そのため優秀な人の採用が行いやすくなります。
自分なら個人事業に就職したいか、
会社に就職したいか考えると明らかですね。
法人化・法人成りのデメリット・短所のご紹介
<★ デメリット・短所一覧 ★>
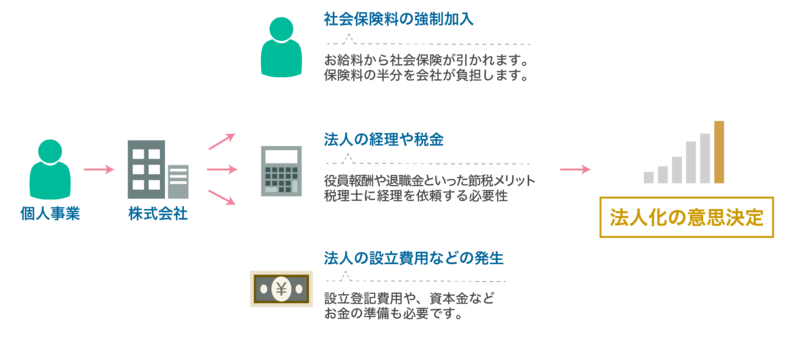
NO1
会社を作る費用が発生します。(登録免許税など実費で約20万円 + 司法書士報酬5万円ほど )
NO2
赤字の場合は個人では税金は出ませんが、
会社の場合は最低7万円の均等割が発生します。
NO3
税務申告などが複雑になるので、
税理士など専門家に依頼する必要がでます。
NO4
社会保険加入の必要です。これが一番難関です。
社会保険料負担が増えるデメリットの一方で、
保証が厚くなるというメリットがあります。
法人成りか迷ったら、ここがポイント !

それでは結論、会社にするか?
個人のまま続けるか?
どうすれば・・とお悩みになるかもしれませんが、
【 利益が出ている方なら、】
上記デメリット会社費用は消費税免税の節税効果で、約25万円の設立費用は回収できます。
また、最低7万円の均等割は
全体で考えると微々たるもので影響は少く、
利益が出るなら節税効果で回収は可能です。
最後の税理士など専門家に依頼する必要についても
個人事業で経営され、事業が大きくなると
自分で経理を行うには限界があります。
また、税務調査で税理士をつけず、自分で対応は
無理がありある程度の規模になると経営や
税務の専門知識が必要になることも事実です。
最終的に一番悩ませるのは、 社会保険への加入といったことになります。 特に人を多く雇う業種は、あなどれません。 逆に人を雇わない業種、外注が多い会社は、 社会保険負担デメリットは小さくなります。
個人から会社にする法人化判断の最終ポイント
匠税理士事務所としては
1. ビジネス上、得意先からの受注増が見込めるなど 法人化する経営面での必要性があるのか。2. 今後人を雇ったり、大きな案件の受注など 売上の規模が拡大する可能性があるのか。
これら経営面のものさしを第一に考えて、
次に節税などを考えて法人成りお勧めします。
なぜなら、節税・社会保険メリット・デメリットは、
業績が良い時と悪い時では逆転現象が生じるため、
現状損得での判断は最善でないと考えるからです。
このようなことから、
【 今後ブレない社長の経営方針(拡大 か否か) 】を軸に法人化を検討されることをお勧めします。
また最終的に判断の迷う社会保険ですが、
【ビジネス拡大のため、優秀な人材を雇用したい】というお考えがある場合には
もし、自分が就職する場合には
①会社が良いか、個人事業主が良いか
②社会保険に入っている会社が良いか
といった社員さんの立場でメリットやデメリットを考えてみると最終的な答えが出ると思います。
繰り返しになりますが、事業が伸びていく方は、 株式会社・合同会社などにする事をお勧めします。
逆に現状維持・縮小路線の場合は、
個人事業で様子をみてもよいかもしれません。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援
匠税理士事務所では、お客様の事業が
今後も順調に伸びるよう基本設計を行います。
株式会社設立、社会保険手続きや給与計算、経理、融資まで法人成りに必要な全てをサポートします。
さらに詳しいメリットやデメリットのご説明から
法人化の相談も承ってます。
お気軽にお問い合わせください。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。


【 法人化の無料相談会について 】
法人化サービスは下記よりご覧ください。
◆メリットやデメリット以外の法人成り情報館のバックナンバーはこちらです。
法人化・法人成り後サービスこちら


【5】建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
税理士・会計事務所の法人成り対応地区:世田谷・目黒・品川など東京都全地区
補足:法人化では上記の他にもいくつかのメリット・長所やデメリット・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。法人成りのメリットやデメリットの記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#法人化メリット #法人化デメリット
収入や経費、青色申告特別控除など経理や決算、確定申告のポイントや注意点 (18/04/24)
匠税理士事務所のホームぺ―ジをご覧いただきありがとうございます。
目黒区や世田谷区、品川区で個人事業主の方の法人化などの税務コンサルティングや、
会計アウトソーシング、確定申告の代行を行う会計事務所です。
今回は、個人事業のお客さまが経理や決算を行うときによくいただく質問の一部をまとめました。
個人事業の確定申告の利益・所得はどうやって計算するのか
個人事業主の確定申告で税金を計算するときの軸になるのは、
事業所得(つまり事業での利益)です。
この事業所得の計算方法は、以下のような算式にになります。
Ⅰ 事業での収入
Ⅱ 事業での経費
Ⅲ 青色申告特別控除額
(会計ソフトなどを利用している方は原則65万円控除・簡単な帳簿の方は10万円控除)
Ⅳ Ⅰ - Ⅱ - Ⅲ =事業所得
ここで重要なのは、
Ⅰ 事業での収入 と Ⅱ 事業での経費 の計算です。
それでは、これらはどのように計算するのでしょうか。
事業での収入金額の計算方法、注意点やポイントは
事業所得の確定申告を行うときに収入を今年受け取った金額で申告をしてしまいがちです。
しかし、現金主義の特例という制度以外の方は、
受け取った金額だけが確定申告上の収入というわけではありません。
これは会社員などの給与所得と異なる点です。
事業では年末までに物の引き渡しが完了していれば、代金を受け取っていなくても収入となります。
つまり、得意先に納品が完了した時点で得意先へ代金をもらう債権(売掛金)が生じているので、
この時点で収入を税務上は認識すべきであるということなのです。
したがって年末までにお金を受けとっていなくても
納品が完了していれば、「収入」になり
実際にお金を受け取ったか否か、請求したか否かは関係がありません。
逆に、代金を受け取っていても物の引き渡しが完了していなければ収入となりません。
そのため確定申告では以下のことに気をつけましょう。
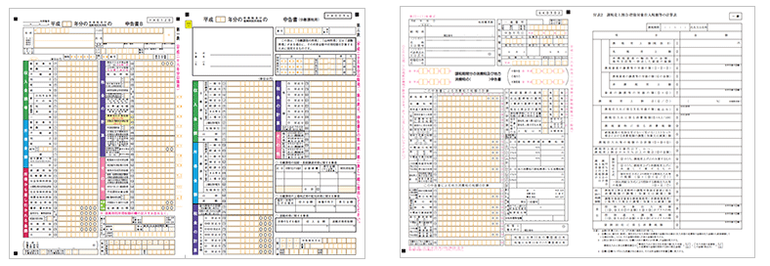
★売上の帳簿は、決算で商品の引き渡しをしたけれども、代金を受け取っていない売上も帳簿に記載しましょう。
このとき、相手の勘定科目は売掛金ですね。
※イメージでは、現金で回収している売上に、この売掛金をプラスするイメージです。
また、物を引き渡していないが代金を受け取った、いわゆる前金のときも帳簿に記載しましょう。
このときは、物の引き渡しが行われたときに売上となりますので勘定科目は前受金となります。
★自分の会社の商品をプライベートで使った時
たとえば八百屋さんが、商品を持ち帰って夕飯に使用したときなど
自分の会社の商品をプライベートに使った時は、
通常の売価で販売したものとして売上の帳簿にプラスをします。
通常の販売価格にかえて、仕入金額(仕入金額が通常の販売価格の70%より低ければ、通常の販売価格の70%)で計算することも可能です。
個人事業主の方の収入は、この論点を知らずに申告してしまい税務調査で修正が入ることが非常に多いです。
上記の点をマスターして、収入の申告漏れをしないように気をつけましょう。
なお、個人であれば、みなさんもご存じのとおり
1月1日から12月31日までの収入を確定申告で申告します。
このとき、申告の対処となる収入については、
1月1日から12月31日までの間に納品が完了したものが対象となります。
事業での必要経費の計算方法、注意点やポイントは
【 1 必要経費の内容 】
必要経費は大きく分けて以下の2つに分けられます。
(1) 売上原価項目
総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
→ これには材料の仕入代金や外注費がこれにあたります。
◇関連記事(原価は、棚卸が必要です。)
(2) 販売費及び一般管理費項目
その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
→ これには人件費や家賃など売上原価以外の項目が該当します。
【 2 経費化の時期 】
必要経費となる金額はその年で債務の確定した金額(一部債務確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。
つまり、その年に支払った場合でも、債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、
逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。
(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。(契約の成立というイメージ)
(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
つまりは、契約に基づいた仕事内容と金額が明確になっており、
これに基づく納品や作業完了がされていることということです。

【 3 経費の注意点 】
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)となるもの
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。
イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
(2) 必要経費になるものとならないものの例イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。
逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。
ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に生じた固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
このように個人事業主の方の確定申告では、どういったものが経費になるかならないかという判断をされる際に
上記のような経費の大原則をおさえておくことがとても重要です。

青色申告特別控除と帳簿の要件やポイント
上記で収入と経費を計算したら、青色申告特別控除が決まれば事業所得の計算が出来ます。
青色申告特別控除は、帳簿の精度(複式簿記か簡易簿記か)で、
65万円控除か10万円控除かが分かれます。
Ⅰ収入 - Ⅱ経費 ≦ 青色申告特別控除であれば、
事業所得がないことになり事業に関する税額がなくなるわけですから、
この青色申告特別控除MAX65万円はとても重要です。
そこで帳簿作成のポイントについて記載を致します。
通常、帳簿は、複式簿記という方法での記帳します。
売上を例にしてみると
原則として
①取引の年月日
②売上先相手方の名称
③金額
④売上の内容
を帳簿に記載します。
しかし、実務上では例えば飲食店など不特定多数に商品を販売する場合には
②売上先相手方の名称を記載することは不可能です。
このような実務上の都合に合わせるため記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく
日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
それでは、簡易的な方法での記帳とはどのようなものなのでしょうか。
通常売上は
①取引の年月日 ②売上先 ③金額 ④売上の内容を記載します。
ただし、簡易な方法での記帳では下記を満たす帳簿であれば良いことになります。
(1) 少額な現金売上→日々の合計金額のみを一括記載
(2) 小売業→日々の合計金額のみを一括記載
(3) 請求書などから内容を確認できる取引→日々の合計金額のみを一括記載
(4) 掛売上で請求書から内容を確認できるもの→現実に代金を受け取つた時に現金売上として記載(年末に売掛金を記載)
(5) 棚卸資産の家事消費等→年末に、種類別に合計金額を見積もって合計金額のみ一括記載
この省略できる項目をうまく利用して事務作業の負担を減らしながらも、
青色申告特別控除に挑戦されてもよろしいではないでしょうか。
匠税理士事務所の法人化や個人事業の確定申告など
匠税理士事務所では、個人事業の確定申告や経理の代行から節税提案、
法人化などのコンサルティングを行っております。
もちろん、青色申告特別控除にも対応しておりますので、
経理や確定申告のアウトソーシングをご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の所属税理士やスタッフの詳細につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】

個人事業を株式会社や合同会社にする法人化や法人成りについてはこちらからご確認をお願い致します。
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】確定申告や法人化など個人事業主の方以外への会社設立や創業融資など起業支援サービスや、
会社経営の方に向けた経営コンサルティングサービスの詳細につきましては、
こちらからTOPページへ移動の上で、ご確認をお願いします。
【 → 世田谷区の税理士は匠税理士事務所 】
会計分析や経営分析を活用した決算検討会・決算ミーティング (18/04/17)
匠税理士事務所では、決算後に決算検討会・決算ミーティングを実施しております。
決算が完了して、翌期に取り組むべき課題を見つけ出し、
新しい年度で経営して行くうえで目標設定を行い、会社を伸ばすお手伝いをしたいというのが目的です。
決算書は宝の宝庫、しっかり活用していきましょう
決算書は、会社の全員が頑張った一年の成績表です。
もちろん、良い所もあれば、悪い所もあります。
決算書を分析することで、経営状況について日常では見えないことが分かってきます。
【 決算分析で分かる経営の情報 】
【 1 過去数年の流れを見て、お金の流れがどのようになっているのかが分かる。 】
債権の回収サイクル / 在庫の状態 / 支払のサイクル は適正かの検証を行うことで、
どうすれば会社にお金が残るようになるのかが見えてきます。
・ つまり売上を請求してから入金されるまでに時間がかかるため、お金がないのか、
・ お金が在庫に化けているためにお金がないのか、
・ お金が入ってくるよりも随分前に仕入や外注費を支払うためにお金がないのか、
これらをしっかりと一つ一つ突き詰めていくことで、お金が残る経営体質へ変わっていきます。
お金が無くなったから、借入では、病気を治さずに輸血を行っているにすぎないため、 借入が増えていってしまいます。このようなことにならないように会社のお金の流れをしっかりと抑える必要があるのです。
◇サービスの詳細

【 2 売上から最終的に残る当期純利益までの流れが分かる。 】
利益を残すには 、どの経費の見直しが必要か、
粗利自体に問題はないのかを検証することで、黒字化への道筋が見えてきます。
そのためには、粗利に問題があるのか、固定費に問題があるのかをしっかりと見極めることが重要となります。
売上単価・仕入単価・販売数量・固定費を分析・検証することで、利益が出やすい会社づくりをお手伝い致します。
◇サービスの詳細
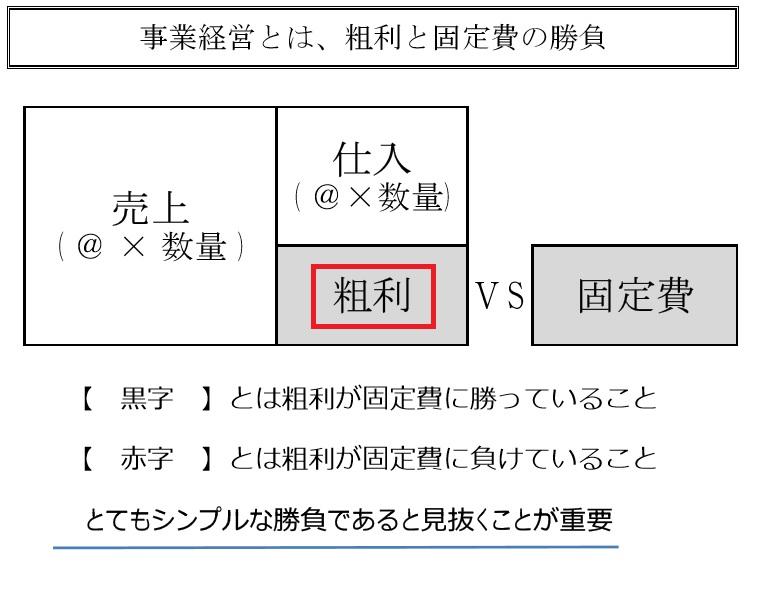
3 上記1と2を踏まえて、自社の経営状況がどのような趨勢にあるのかを把握し、
今後どのようにすると、会社が良くなるのか見えてきます。
このように会社の良い所の要因が何だったのか、悪い所の要因は何だったのかを分析し、
次年度に改善していくことで、来期はどこに向かって進むかの経営の軸を作ることができます。
匠税理士事務所の決算検討会・決算ミーティングを通じた決算分析・財務分析
匠税理士事務所では、決算検討会・決算ミーティングについて
経営セミナーなどで講師を務める税理士が決算書を基に分析を行います。
次年度に向けての改善策を一緒になって話し合う会議の形式をとっております。
日々、事業や経営に追われる経営者様にとって、一年の結果を振り返る貴重な時間であり
新たな目標と会社の微修正をかけるための時間を作り出す良い機会です。
会社の数字を有効活用して、会社経営に役立てみてはいかがでしょうか。
決算検討会の他に、借入金などがあり会社の財務バランスが思ったものとは異なっている会社様には
決算分析サービスを提案しております。
こちらのサービスでは、直近の決算書3期分をご用意して頂いております。
これは、3期分を分析することで、会社の経営状況についての傾向を把握するためです。
決算分析や財務分析に興味があるという会社様は下記をご覧いただけましたら幸いです。
◇サービスの詳細
世田谷区や目黒区、品川区など税理士の対応地域
匠税理士事務所では、目黒区や世田谷区や品川区など 東京都全域に対応しております。
目黒区の匠税理士事務所の所属税理士など詳細は、こちらです。
◇匠税理士事務所について
→目黒区自由が丘の税理士や会計事務所は匠税理士事務所...会社概要
→世田谷区の税理士は匠税理士事務所...TOPページ

リフォーム業や内装業の税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (18/04/11)
リフォーム業・内装業に詳しい匠税理士事務所HPへご来訪ありがとうございます。
リフォームや内装業の方は、クロスや床、天井、塗装、各種設備などお仕事で幅広い知識が必要となる上、
お客様からデザイン要望やキメ細かい美しい仕事など様々なニーズに応える難しい仕事です。
そのため、弊所では、
【 税務・会計・人事労務】は全てお任せ頂き、社長様はお仕事に集中して頂くよう心掛けてます。
安心してお仕事に集中できるように、
請求書や領収書など経理資料を頂ければ、
経理や会計税務は全て弊所にて対応します。
もちろん、経営面も経営セミナーで講師を務める
世界4大事務所出身の税理士がサポートします。
また、リフォームや内装など建設業界は、
【 人手不足 】が深刻です。
採用面や優秀な人材の確保でも、社会保険手続きや労務手続きはとても重要ですし、
外国の方の雇用を検討する必要も出ます。
税務や会計以外の社会保険や給与計算、雇用契約や人事労務相談などは専門家の社会保険労務士や、
ビザ取得に詳しい行政書士と連携しサポートするなど
【 建設業に必要な全てがそろう会計事務所 】を心掛けております。
匠税理士事務所の詳細につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】
法人様向けサービスはこちらから
ご確認をお願いします。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

リフォームや内装業の建設業許可申請
リフォームや内装のお仕事で信頼を積み重ねると
500万円以上の大規模な工事も出てきます。
その際に、原則として建設業許可を受けなければ、工事が出来ないことになります。
そこで匠税理士事務所では、建設業専門の行政書士と税理士が連携しリフォームや内装での建設業許可申請代行と取得のコンサルティングを行います。
現時点で取得できない場合も、
将来どうすれば建設業許可を取得できるのか、
行政書士が丁寧にサポート致します。
日本政策金融公庫や金融機関の資金調達
リフォームや内装業など建設業の特徴として、
一取引当たり一受注金額が大きくなりがちです。
また、受注から納品・入金までの期間も長期に及び
多額の材料費や外注費立替による資金繰りの悪化が懸念される職種でもあります。
匠税理士事務所は、リフォーム業や内装業に向け
東京都や川崎市・横浜市など神奈川県を軸に、
日本政策金融公庫や各種金融機関と連携して、
融資による資金調達をサポート致しております。
各種計画書の作成支援から金融機関の方の
ご紹介まで丁寧にご対応致しますので、
多くのリフォームや内装業のお客様に
大変お喜びいただいております。
詳細につきましては、こちらからご確認下さい。
個人事業から会社にする法人化も対応
リフォームや内装業のお客様には、最初は個人事業で始められる方も多くいらっしゃいますが、
しばらくすると年商2,000万円近くなり、
株式会社などにされた方が良い場合もあります。この個人形態を会社にする事を
【法人化・法人成り】といいます。匠税理士事務所では、法人化・法人成りによる
メリットやデメリットをご説明するなど
リフォームや内装業の方に向けた法人化相談会や
実際法人化される場合のサポートを行ってます。
詳細は、こちらからご確認をお願いします。
さらに詳しいメリットやデメリットのご説明から法人化のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

リフォーム業や内装業の法人化サービス
各種サービス内容や料金などにつきましては、
こちらからご確認をお願い申し上げます。
【 → 起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】

リフォームや内装業のお客様に向けたご案内を最後までお読み頂きましてありがとうございました。
会計事務所の対応エリア:世田谷・目黒・品川・大田など東京都・川崎市や横浜市など神奈川県全域
執筆者・文責:税理士 水野智史
事務所やオフィスを借りる際の礼金や敷金、仲介手数料の経費、経理処理は? (18/04/10)
起業をしてしばらくすると、人を雇うためにオフィスを借りられるというケースがほとんどです。
しかしオフィスを賃借される際に、支払った礼金や敷金などの金額が、
支払ってすぐに経費になると誤解をされていることがよくあります。
これらの金額は比較的大きな金額になりますので、損益への影響が大きいのも事実です。
そこで、今回は事務所を借りる際に、よく出てくる礼金や敷金などの項目の税務的な取り扱いについて述べます。

礼金や更新料などは複数年で経費化が原則
法人が建物を賃借するために支払った権利金や礼金などの費用で、
支出効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。
つまり、支払ったときに全額経費なるのではなく、一度資産(財産)としてあげておき、
税法の定める期間で案分して複数年で経費化することになります。
敷金などでも契約時に返還されないことが確定しているものは、礼金と同様の性格になりますので、
税務的には礼金などと同様に以下の経理処理となります。
なお、敷金や保証金のうち原状回復費用を差し引いて将来返還される部分については、預け金的な性格ですので、
経費とはならず、将来原状回復工事や修繕が行われ、これらにつき請求された際に工事費・修繕費部分が経費となります。
繰延資産となる権利金等の按分期間は次のとおりです。(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合
・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合
・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
(3) 【 (1) 及び (2)以外の権利金などの場合・・・5年 】
(契約による賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが
明らかであるときは、その賃借期間)
なお、実では5年という賃借期間はまれで、一般的には2年・3年の賃借期間で更新料がかかるケースが多いので、 賃借期間での按分した経費化が一般的です。
このようにほとんどのケースでは、上記(3)に該当します。
つまり、礼金や敷金のうち返還されないことが明らかな部分は上記(3)により経費にされることになります。

少額な礼金など繰延資産や仲介手数料は一括の経費化も可能
礼金や更新料などは上記のように複数年で費用化していくのが原則ですが、
支払金額が20万円未満の繰延資産の場合には少額繰延資産の特例として一時に費用計上することが認められています。
また、繰延資産ではない不動産業者などに支払った仲介手数料については、
その支払った時に損金の額に算入することができますし、
鍵の交換費用も同様に支払った際に経費化することが可能です。
このように事務所やオフィスの賃借ではいろいろな経費がでてきますが、
その経理処理は様々です。
特に税法では、礼金や更新料など繰延資産は複数年で経費化していくのを原則としていますが、
少額な繰延資産の場合には特例もありますので、これをうまく活用することも重要です。
例えば、利益状況をみて、初年度は黒字を出しておきたいので、 あえて複数年で経費化する方法を選択しておくといったことや、 逆に利益が出ているので、少額な繰延資産は一括で費用化するという方法を選択するということも可能です。匠税理士事務所の会社設立など起業支援サービス
匠税理士事務所は目黒区や品川区、世田谷区を中心に会社設立や創業融資など起業支援に注力しております。
・これからオフィスを借りて人を雇用したいが支出が増えるために融資を検討している。
・大きな支出が増えるので、一度資金面で相談をしたい。
・会社設立とあわせて創業融資も検討している。
このような起業家の方のお声に応えれるように、【 起業に必要なすべてがそろう税理士事務所 】を目指して、会社設立や創業融資、経理アウトソーシングや経営支援などを行っております。
匠税理士事務所の会社設立など起業支援サービスにつきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所 】
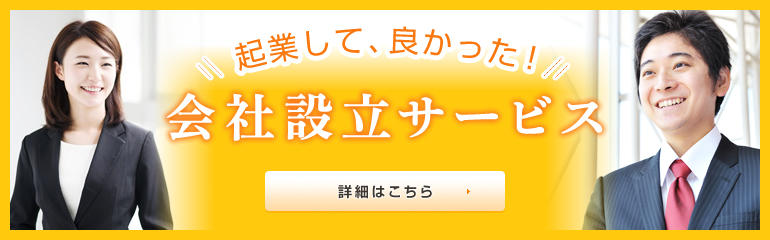
起業支援以外のサービスや税理士やスタッフの経歴、料金などにつきましては、
こちらからTOPページへ移動の上でご確認をお願い致します。
なぜ会社にするのか、株式会社や合同会社など会社設立の理由<K8> (18/04/02)
これから起業をする時、個人事業で起業するか、
合同会社や株式会社など会社にするのか、
迷うこともあると思います。
そこで、今回はなぜ会社にするのか、
会社設立の理由についてまとめてみました。
会社設立のメリット、会社にする理由とは
会社設立には節税になる、事業承継などの際に
後継者対策、融資を受けやすいなどメリットがあり
会社にする理由は、人それぞれですが、
会社にする最大のメリットは信用力でないでしょうか。
【 商売は、信頼第一 】このフレーズは生活をしていると様々なところで、
耳にしますが、事業で信頼はとても重要です。

商売は、【 信用・信頼の獲得 】から始まります。
お客さんは相手を信用することができなれば、
大切なお金を払ってくれません。
少額取引なら【 失敗しても目をつぶれる範囲 】と
購入して下さることもあるかもしれませんが、
【高額商品やサービス】では、信用がなければ、
候補にすら検討してもらうことはできません。
これはインターネットで物を買うときにレビューを
細かく確認するなどということでも表れます。
レビューがない場合は、運営者概要を見ます。
そのときに、株式会社○○ とあるのと、
個人名ではどちらが安心するのか考えると、
会社にすることで手に入れられる【信用力】は
より分かりやすくなります。
大手企業は会社しか仕事をしない傾向あり
大手企業の中には、個人事業主とは
仕事をしないところさえあります。
たとえ、これまでにいい仕事をした実績があっても
・「上司を説得できない」
・「今までに実例がない」
といった理由で断られるケースは耳にします。
個人から合同会社や株式会社にする方は、
一度はこのような経験をしたことが多いようです。
大きな会社には、必ず株主や役員が大勢います。
取引開始では多くの決済権者の稟議が必要です。
会社には多くの利害関係者が絡んでくることから、
保守的になりがちでリスクをとることを嫌がります。
このような理由から何かあったときに
【信用力や規模を重視する】ことになるため、
個人事業主と一緒に仕事をしたがらないのです。
個人事業と会社組織の差、登記制度とは
長い付き合いがある相手なら培ってきた実績で
信用を得るられますので事業に支障がありません。
しかし、初めて仕事をする相手から信用を
得ることはそう簡単ではありません。
取引先はこちらを「どれくらい信用できるか?」
見極めないと取引をしてくれません。
このような新規取引を行う際の信用でも、
「会社」という組織は役立ちます。
なぜ、会社は信頼される傾向にあるのでしょうか。 答えは会社は【 登記義務 】があるからです。法務局に登記されていれば、
だれもが会社の重要事項を閲覧できます。
本店や代表者の居場所が分からない事もないですし
だれが役員で、どういった商売をしているか、
資本金はいくらなのか、事業内容は何か
いつ設立された会社なのかなど登記事項を見れば
会社の概要が分かります。
そしてこの登記をする際には、法務局のフィルターで
虚偽登記が行えないようになっているので、
【 会社の信用力は高くなる 】のです。匠税理士事務所の会社設立・起業支援サービス
匠税理士事務所は世田谷区や目黒区、品川区を中心に会社設立など起業支援を行う会計事務所です。
これから事業を始めたいが、個人事業がいいのか、
株式会社など会社がいいのか相談したい方や、
起業資金で創業融資の話を聞きたいという方に
向けてコンサルティングを行っております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
執筆者・文責 税理士 水野智史
#なぜ会社にするのか #会社設立理由
砧や大蔵など世田谷で起業に強い会計事務所は匠税理士事務所 (18/04/01)
匠税理士事務所にご訪問ありがとうございます。
弊所は砧や大蔵など世田谷エリアで
世界4大会計事務所出身の税理士を中心に 【起業と経営支援で地域No1】を目指してます。所属税理士や業務内容など事務所全般は、
こちらからご確認をお願いします。

砧や大蔵など世田谷で会社設立など起業支援
・弊所ではいつかは、勤務先を退職して、
株式会社を設立し、成功したい方。
・個人事業が軌道にのり、
会社設立し事業を拡大したい方
私たちは、このようなお客様の夢の実現に 一緒になって取り組んでおります。株式会社を経営する上で一番重要なことは、
【 早い段階で利益を出すこと 】です。
自己資金には限りがありますし、
【生き残ること】が最優先課題だからです。
 そして起業間もないときに重要な財産は、
社長の本業への知識や経験です。
そして起業間もないときに重要な財産は、
社長の本業への知識や経験です。
株式会社を経営する上で、この知識をフル活用し、
マーケティングや営業を駆使し、市場でのしっかりとしたポジションを確立しなければなりません。
そこで匠税理士事務所では、砧や大蔵などを拠点に
【起業で必要な全てがある事務所】をコンセプトに不慣れな経理という本業への障害を取り除き、
社長様の知識・経験を活用できる環境作りに努め
サービスを通じ起業成功を支援しております。

砧公園や大蔵など世田谷で株式会社を作って
起業という夢を実現するお手伝いのため設立登記代行や許認可申請代行、
創業融資などの立ち上げから、
会計や税金の手続き代行、助成金の申請代行や
給与計算といった株式会社運営のサポート、
コンサルティングなどを取り揃えてます。
砧や大蔵担当の税理士・専門家はこちらから
【→匠税理士事務所の概要】

砧公園や大蔵など世田谷での会社設立と
その後の会計や経営を支援するサービス
砧や大蔵など創業融資による創業支援
創業時に不可欠な資金の調達には、
城南信用金庫や日本政策金融公庫など
世田谷を得意とする金融機関と連携して、
砧や大蔵など世田谷での創業融資による
創業支援も行っております。
会社設立時の融資の話を聞いてみたいという
税理士へのご相談も承っております。

砧や大蔵の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は砧や大蔵など世田谷全域対応)
砧や大蔵での経理会計や確定申告・法人化代行
弊所では砧や大蔵など世田谷エリアを中心に、
会計や経理、確定申告の代行から
高度な税務会計の専門性を駆使した
法人化などのコンサルティングを行っております。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
砧や大蔵で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

砧公園や大蔵の法人化・会社設立関連情報
砧公園や大蔵など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
砧公園や大蔵で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が砧公園や大蔵で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
砧公園や大蔵など世田谷の税理士事務所や会計事務所の求人や採用情報
弊所では砧公園や大蔵など世田谷区で
年中、求人や採用を行っております。
これは常に余裕をもった人員で、
余裕をもった業務が重要と考えるためです。
こうした取り組みもあり、
残業時間は事務所全体で皆無で、
最近の退職者はゼロです。
この好循環が、良いサービスの
原動力になると考えております。
砧や大蔵など世田谷に住まれている
税理士受験生や会計事務所勤務を検討中の方は
匠税理士事務の正社員やパートアルバイトスタッフ
求人採用情報のページをご確認頂きまして、
ご応募をいただけますと幸いです。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
もちろん、砧や大蔵など世田谷以外に
お住いのかたからのご応募も大歓迎です。
世田谷の砧で会社設立をされたお客様の声
以前の世田谷のセミナーで起業塾に参加し、
相談しやすそうな方という印象だったので、
砧から近いこの会計事務所にお願いしました。
砧の自宅で会社設立してから資金調達、経理
税金など全てお任せして大変助かっています。
これからもよろしくお願いします。
世田谷の砧 眼鏡の小売業 O社様
最後までご確認頂きありがとうございます。
砧公園(きぬたこうえん)や大蔵(おおくら)など
世田谷区以外に東京都23区全域で会社設立など起業支援・創業支援や
個人で独立開業した後の法人化・法人成りも対応します。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#砧税理士
#大蔵会社設立
自由が丘の会社設立や法人設立は自由ヶ丘の匠税理士事務所 (18/04/01)
匠税理士事務所は2008年に自由が丘に設立し、
自由が丘駅徒歩2分の場所にある事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に女性税理士や税理士科目合格者など計10名で
構成される【自由が丘で最大規模の事務所】です。
税務会計や決算申告などの対応はもちろんのこと、
【起業支援】・【経営支援】に定評がございまして高度な専門性と高い技術力を生かして
【顧客満足度で目黒No1】を目指しております。・自由が丘で会社設立を検討しており、
創業支援に強い税理士を探している。
・経営相談しやすい税理士と付き合いたい。
・創業融資や給与計算、助成金など創業の問題に
対応できる事務所を探している。
このようなご要望は、お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の所属税理士やサービスは、
こちらからご確認をお願い致します。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

自由が丘の起業支援専門の自由ヶ丘の税理士
自由ヶ丘の企業の皆様に愛される会計事務所づくりという考えを大切にし、
自由が丘近辺の専門家や金融機関との連携により
地域に密着したサービスを行っております。
会社設立・法人設立などの起業支援や
経営支援の新たなサービス作りを随時行い、
お客さまのニーズにお応えできる体制を整えてます。
自由ヶ丘の法人設立・起業支援専門の会計事務所
目黒区自由が丘1-4-10 quaranta1966 404 ( 1Fは資生堂パーラー様・お隣はラボエム様となります。)
東急東横線自由が丘駅より徒歩2分
自由が丘で起業支援や創業支援を担当する
税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 →自由が丘の匠税理士事務所の概要】

自由ヶ丘の会社設立代行など創業支援
弊所では、一生に一度の会社設立を成功につなげるため
商工会議所などで経営セミナーを担当する税理士が、
会社設立時の起業相談や経営相談を承ってます。
また、自由ヶ丘で起業される社長様に
出来る限り本業に集中していただけるように、
本業以外の法人設立業務を全て代行しております。
自由が丘で株式会社や合同会社の設立代行を
お考えの方に向け司法書士と連携した会社設立や、
社会保険加入手続き、助成金申請代行も対応します。
資本金をどうすべきか、役員や株主構成は
どうすべきかなどの相談も承っておりますので、
会社設立では会社名と本店所在地を決めれば、税理士が後はお任せで創業支援します。
会社設立や独立開業など起業してからの
経理や経営、節税対策などもフルサポート。
自由が丘の匠税理士事務所の創業支援はこちら
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
自由ヶ丘の金融機関の創業融資の資金調達
会社設立をされる場合には、
多くの場合に創業融資を検討されます。
その理由は、事業が軌道に乗るまで時間がかかり、
法人設立後の早い段階で資金不足になるからです。
赤字でも会社はつぶれませんが、
資金不足で支払いができないと事業が停止します。
匠税理士事務所では、自由ヶ丘を管轄する
城南信用金庫の自由が丘支店と連携し制度融資や、
日本政策金融公庫様と連携した創業融資を通じて
起業時の資金調達を支援します。
【 → 目黒区の創業融資・資金調達 】

会計や経理、決算、確定申告や法人化の代行
自由ヶ丘の匠税理士事務所では、
会社設立や法人設立など起業支援以外にも
会計や経理、決算、確定申告や法人化代行、
経営支援もご用意致しております。
各サービスラインの詳細や料金、
自由ヶ丘駅からのアクセスなどにつきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
【 →自由ヶ丘の匠税理士事務所の概要】
起業家の方向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業のお客様 サービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

初回の会社設立など起業相談は、
無料ですのでお気軽にご相談下さい。
創業融資などの創業支援も対応中です。
自由ヶ丘の法人設立・起業支援専門の会計事務所
匠税理士事務所
東京都目黒区自由が丘1-4-10-404
執筆者・文責:税理士 水野智史
#自由が丘起業支援
#自由が丘創業支援
会社設立後に青色申告を何故行うのか、その理由<K2> (18/03/22)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
『 起業するなら青色申告にした方がいい。 』このような事を聞かれたことがあるか思います。
そこで今回はなぜ青色申告がお勧めなのかについてまとめてみました。
青色申告の特典と、会社設立後の経理の関係
青色申告とは、何でしょうか?
青色申告といった言葉はよく、耳にします。
この青色申告は、税務上の青色申告の要件にあった帳簿に基づいた申告をいいます。
(高い水準の帳簿を作成して、その帳簿に基づいて正しい申告をする人について
税金の計算などについて、有利な取扱いが受けられることを青色申告の制度といいます。)
このようなしっかりとした帳簿(複式簿記)を基にした申告を青色申告といい、
逆に上記の青色申告要件を満たさないような簡易な帳簿によるものを白色申告といいます。

会社設立した場合の青色申告メリット
~青色申告にするメリットはなにか?~
青色申告には主に次のような特典があります。
① 赤字を10年間繰越できる。
② 税務調査で不利になりにくい。
③ 税金が少なくなる特典が沢山ある。
このうち、
②については、
会社設立時はあまり関係がありませんが、
①と③は、青色申告ではないと、
税金が数万から数百万変わることがあります。
青色申告は、提出期限が決められていて、期限内に申請書を提出したときに特典が受けられます。
逆に、期限内に間に合わなければ、白色申告となり、特典は受けられません。
青色申告の長所についての実例を踏まえた説明
実際に青色申告特典あり・なしを比較しましょう。
青色申告をしているB社
B社は、青色申告をしています。
1期目は投資が多く、300万円の赤字でした。
2期目、得意先も増え、100万の黒字となりました。
3期目、人も増え利益は1,000万円になりました。
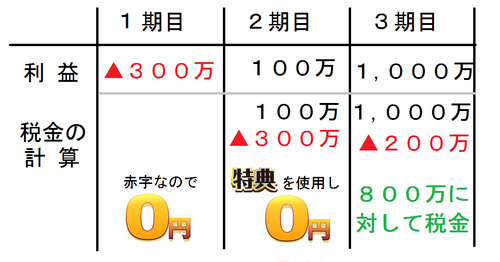
B社は、青色申告の特典を利用して、赤字を繰越、
2期目は100万円の利益について、赤字を使用することで税金がかかりません。
使用できなかった200万円は繰越して3期目の黒字と相殺、税金面では上記のようになりました。
白色申告のW社
比較しやすいようにB社とW社の業績は同じとします。
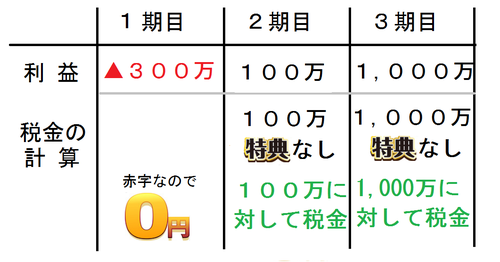
W社は、青色申告の特典がありません。
つまり1年目の赤字を繰り越すことができません。
中小企業の税率は、約30%程度です。
つまり、一年目の赤字分
300万円×30%=90万ほど
会社設立後、税金面でこれだけ大きな差が開いてしまいました。
会社を設立した後に青色申告を行うために
会社設立後、青色申告を行っているのと
青色申告を行っていないのとでは、
税金の計算結果が全く異なります。
会社設立し間もない頃は先に投資をして、
売上が不安定なため赤字なことも多く、
赤字繰越が受けられる青色申告は大切です。その他にも税金が少なくなる特典が沢山あります。
青色申告をされる人は、「青色申告承認申請書」を期限内に所轄の税務署長に提出してください。
(期限を一日でも過ぎてしまうと効果が認められませんので注意が必要です。)
(関連記事:法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き)

青色申告のための手続きをした後は、帳簿を作成して経理を行うことが必要です。
(青色申告はメリットも大きいのですが、帳簿付けがしっかりしていないと、
税務調査で青色申告の取り消しの指摘を受けることもありえますので注意しましょう。)
匠税理士事務所の起業や会社設立支援
弊所では、青色申告に対応した会計や経理
税務のアウトソーシングを提供しております。
黒字経営は、何より利益を出すことが大切です。
毎月の利益を正しく把握するためには、
収入や経費の把握からはじまります。
青色申告は会社の利益を正しく計算し、
経営内容が正確に把握できますので、
事業や会社の発展にも役立ちます。
人を雇ったり、会社を成長させていきたい時、
業績把握は大切になりますので、青色申告をされることをお勧めします。
匠税理士事務所は起業支援に力を入れてます。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

◇関連記事
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
◇その他の起業支援サービス
◇個人の起業サービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
柿の木坂の税理士や会計事務所なら匠税理士事務所 (18/03/22)
WEBサイトへご来訪ありがとうございます。
弊所は目黒区自由が丘で2008年に開業して以来、
柿の木坂など目黒区で会社設立や【起業支援】、
【 経営支援 】に取り組む会計事務所です。
匠税理士事務所の最大の特徴は、税理士やスタッフ、 専門家と提携先にこだわることによる 【高い専門性】と【サービス品質】です。匠税理士事務所の会計経理・創業支援・税務業務は、
こちらからご覧頂けましたら幸いです。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

柿の木坂の会社設立・創業融資など起業支援
起業時に気を付けるべきことは多数ありますが、
その一つに資金繰り(お金の問題)があります。
なぜ資金繰りに気を付けるかというと、
赤字で会社はつぶれませんが、
資金が無くなると会社はつぶれるからです。
まず経営者に行って頂きたいことの一つに、 起業する上で必要資金と自己資金のバランスを 正確に把握することがございます。
資金(資金管理・お金の問題)の大部分は、
売上の入金サイトと、仕入先の支払サイトに加え、
毎月の人件費・家賃を加味し考えます。
これらを加味すれば、資金の流れは把握可能です。
自己資金だけでは半年は難しい・・
このようなときは、創業融資を活用した
資金調達も選択肢に考えるとよいでしょう。
会社設立の時期はいつにすべきか、
株主構成や役員構成、決算時期など設計から、
創業融資までコンサルティングを致します。
柿の木坂を担当する税理士・事務所概要はこちら
【 → 目黒区の匠税理士事務所の概要 】

柿の木坂など目黒エリアの方に向けた会社設立は、こちらで確認下さい。
起業時の資金調達についても対応しております。
柿の木坂での創業融資はこちら

柿の木坂の会計・決算などの創業支援
弊所では起業支援に力をいれており、
会社設立・創業融資以外にも助成金や、
補助金など起業に必要なサービスを
全てご用意する会計事務所であり、
柿の木坂で会社設立後の会計・決算代行など
創業支援が充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
柿の木坂の確定申告や経理代行・法人化
経営で意外に盲点になりがちなのが、税金関係。
利益=自分のお金と考えてしまうからです。税金関係は金額が大きくなりがちですが、
どんな税金が、どれ程出てくるか
中々分かりにくく、急な支払によって
資金計画が崩れがちになります。
資金繰りのずれは、急な資金不足などにつながり
販売促進などに急ブレーキをかけたりするなど
本業に大きな影響を及ぼすのは避けたいです。
そこで匠税理士事務所では、
経理会計の初期のやり方の説明や、
税金がいくらになるか予測し効果的な節税を行い柿の木坂など目黒区で経営を支援します。
経営サポートや財務・税務コンサルティングなど
業務一覧はこちらからご確認下さい。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
柿の木坂で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

柿の木坂など目黒区の税理士事務所や会計事務所での採用・求人情報
柿の木坂(かきのきざか)など目黒区で
税理士事務所や会計事務所での
採用求人情報をお探しの方は、
こちらからご確認をお願いします。
柿の木坂など目黒エリアの方に向けた当会計事務所
紹介を御覧頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#柿の木坂税理士
#柿の木坂起業支援
法人化・法人成りでの社会保険加入によるメリットとデメリット (18/03/20)
匠税理士事務所は法人化を支援する事務所です。
法人化に関する情報を読むと法人化すると社会保険に加入しなければならないという事項が
デメリットとして挙げられることが多いようです。
これは個人事業主であれば、国民健康保険と
国民年金が各自の自己負担であるのに対して、
会社にすると社会保険料の1/2を会社にて負担しなければならないことに起因します。
社員さんがいる会社では、本来自己負担だった社会保険料を会社で負担することになるわけですから、
確かにデメリットともいえます。
一方、社会保険加入で様々なメリットもあります。今回は法人化や法人成りでの社会保険加入による
メリットとデメリットを分かりやすく記載します。

法人化での社会保険加入で保障充実メリット
社会保険加入における個人と法人の取扱いは
大きく異なります。
個人事業の場合は、社会保険に任意で加入していたとしても、加入できるのは従業員だけで、
個人事業主は原則として加入することができず、
国民健康保険と国民年金に加入となります。
しかし、法人化すれば、たとえ社長1人であっても社会保険に強制的に加入義務が生じます。
社会保険加入による保険給付面でのメリットとしては大きく以下の2つが挙げられます。
国民健康保険でも医療費の負担や、入院などで医療費の負担が高額となった場合に
受けられる高額医療費、出産したときの出産育児一時金は、健康保険と同様の給付が受けられます。
法人化などで健康保険に加入すると、国民健康保険よりさらに保険給付の面でメリットがあり、
病気やケガ、あるいは出産などで仕事ができなくなった場合に、保険給付を受けることができます。
病気やケガの場合は傷病手当金として最長1年半、出産の場合には出産手当として
産前42日間(双子の場合は98日)、産後56日間のうち、仕事をしなかった日につき、
標準報酬日額の3分の2が受給できます。
こちらのメリットはとても魅力的ですので、女性の経営者の方はこちらもよく検討すべきです。
また、産前産後休業期間及び3歳に達する子を養育するための育児休業期間については、
社会保険料が免除されるという制度もございます。

厚生年金保険に加入した場合には、国民年金と比べて保険料は高くなりますが、
受給できる年金額は増えます。
国民年金保険料は月額約16,000円と保険料は安いですが、もらえる年金額は満額でも約78万円と、
生活していく上での保障としては十分ではありません。
しかし、厚生年金は老齢基礎年金に上乗せして、支払った保険料に応じて
老齢厚生年金を受給することができ、老後資金を増やすことができます。
こちらは支給開始年齢が変更になる可能性もございますので、不透明な要素は残ります。なお、保険料は概ね法人・個人の折半ですが、それぞれの負担額は、法人においては経費とされ、
個人においては所得控除を受けることができます。

法人化は社会保険をどのように考えるべき?
これから法人化をされるに際して、確かに社会保険の負担は重要な判断基準となりますが、
上記のメリットも考える必要があります。
法人化する上での判断では、 人を多く扱う事業か否かが重要となります。なぜなら、人を多く要する事業では、社会保険料の負担も大きくなりますが、
人を多く要さない事業では、
【社保負担増 < メリット 】となるようなら社会保険加入は法人化ではデメリットではなく
メリットになるケースもございます。
自分の事業の事業構造をよく考えて、法人化・法人成りの判断をするようにしましょう。目黒区の匠税理士事務所の法人化相談会について
匠税理士事務所では、個人事業から株式会社や合同会社にするため法人化を承っております。
世田谷や目黒、品川でこれから会社設立をして法人化した方がよいのか、
専門家の意見を聞いてみたいという方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
目黒区の匠税理士事務所の法人化サービスについて
法人化後の経理代行や税務申告、社会保険加入や各種許可申請、資金調達・創業融資などに対応しております。
サービス詳細は、こちらです。
【 → 世田谷・目黒・品川など東京の法人化・法人成りは匠税理士事務所 】
◆法人化や法人成りについての情報を掲載した法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
法人化以外のサービス内容や所属税理士などにつきましては、
下記のリンクからTOPへ移動の上、会社概要などをご確認ください。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
法人化や法人成りを行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
会社で車両購入の場合に自動車ローン返済・借入期間はどれくらい? (18/03/14)
これか会社設立して起業をしたいが、
事業で営業車などを法人で購入する必要がある。
このような場合に車両はどう購入するとベストか、
お悩みの起業家の方も多いと思います。
そこで今回は起業時に会社で車両購入する場合に
【現金一括 又は 自動車ローン】のどちらがよいか?また自動車ローンの場合には、返済・借入の期間は
どれ位がよいのかについてまとめてみました。

現金購入と自動車ローンで購入の比較
現金購入と自動車ローンで購入のいずれも
自社で購入するわけですから、自社に所有権があり、
リースと異なり細かい制限がなく自由に車を扱え
経費化するスピードは、法律で決められているため
4年や6年(中古車は更に短い)で減価償却を行う
複数年で案分して経費化という基本的なところは
税法上は同じような扱いです。
大きく異なるのは、当然ですが金利部分です。
自動車ローンは4%から6%の利息が出てきます。
この利息分、現金購入が有利にも思えますが、
会社を経営しているとお金はとても重要です。
自己資金1,000万円で起業して、
年4%の金利を払っても年間で40万円。
960万は事業に運転資金で投下出来るわけですから
売上がしっかりと見込めるような場合には、
960万円を事業投下して4%以上の利益を上げて ドンドン稼ぐという発想が重要です。
こちらの事業投下と金利の両方を天秤にかけて、
自社にとってどちらがよいのか見えてきます。
自動車ローンや借入期間はどれ位がよいか?
赤字の場合でも会社はつぶれませんが、
お金がなくなれば会社は倒産します。
そこで、自己資金1,000万円に
自動車500万をローンで組むと1,500万の資産を
動かせるため事業の成長速度は上がります。
一方で自動車ローンや借入は毎月必ず
返済をしなければなりませんから、
この返済期間をどれ位に定めるかですが、
出来る限り長い期間をお勧めします。 (一般的には5年ほどが多いようです)
長期間借りると金利が多くなるようになりますが
金利で会社がつぶれることは少ないため、
自動車ローンや借入で車輌購入する場合には、
手元にできる限り長い期間お金が残り、
事業投下できる状態が続くことをお勧めます。
創業間もない時期は、自動車ローン年4%程でなく利率2%程の創業融資をご提案しております。
お客様のご協力で融資実行率9割超となってます。
詳細はこちらからご確認下さい。
【→ 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】はこちら

匠税理士事務所の会社設立や創業融資など起業支援
匠税理士事務所は世田谷区や目黒区・品川区で
創業融資など起業支援を行う会計事務所です。
これから会社設立をしたい方に向けて、
自己資金と必要資金のバランスをヒアリングし、
融資が必要な場合にはどのような方面から どれ位の借入がよいをコンサルティングします。
経営セミナーでも講師を担当する経営支援に
強い税理士が起業時の入金・出金サイクルなど
ヒアリングし資金繰りも丁寧にアドバイスします。
匠税理士事務所の会社設立や創業融資など
起業支援サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願い致します。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】

目黒区自由が丘にある匠税理士事務所
匠税理士事務所は目黒区自由が丘に2008年に
設立された会計事務所です。
40代の税理士とのスタッフで構成されており、
起業に必要なあらゆるご相談に対応できるように
【人事労務・法務・登記・許認可申請・助成金】など各分野の専門家とも連携しております。
匠税理士事務所・提携先概要は、
こちらよりご確認をお願い致します。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
補助金・助成金代行や会計・経理・経営支援など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人事業主から株式会社に変更するための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業で独立開業される方に向けた
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

執筆者・文責 税理士水野智史
#会社車両購入
#自動車ローン返済期間
#車両購入借入
大岡山で税理士や会計事務所をお探しなら匠税理士事務所 (18/03/14)
ご訪問ありがとうございます。
弊所は、目黒区大岡山すぐ自由が丘駅から
徒歩2分にある会計事務所です。
2008年事務所設立以来、大岡山など目黒区中心に経理や確定申告、起業支援を行ってきました。
匠税理士事務所の最大の特徴は、
世界4大会計事務所出身の税理士を中心とした 税理士や弁護士など専門性の高さです。税務会計など会計事務所の基本業務は当然ですが、
契約書作成や法務、登記や給与計算、社会保険など
【 事業に必要な全てがそろう会計事務所 】です。大岡山地域のお客様に向けた事務所概要や
提供業務のご案内はこちらから
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

大岡山で会社設立や創業融資など起業支援
弊所得意分野として、会社設立や創業融資など起業や独立開業支援がございます。
これまで目黒区の商工会議所や各種公的機関で
起業セミナ―講師を担当する税理士が、
大岡山など目黒区で会社設立をする際の
起業相談や資本金など設計、官公庁届出書作成など
起業や独立開業支援を行います。
お客様は税理士と1時間程打ち合わせ頂ければ、 会社が作れるような体制をご用意致しております。大岡山を担当する税理士や事務所概要はこちら
【 → 目黒区の匠税理士事務所の概要 】

大岡山など目黒区の会社設立サービス詳細はこちら。

大岡山の創業支援に強い税理士事務所
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は大岡山など目黒区に全域対応)
株式会社や合同会社など会社設立と同時並行で、
起業資金確保の創業融資支援も行ってます。
日本政策金融公庫による創業時の資金調達と、
城南信用金庫 大岡山支店やみずほ銀行など
メガバンクなど金融機関経由の目黒区制度融資
両チャネルの創業融資に豊富な実績がございます。これまで多数の融資支援実績があり、
大岡山など目黒区でトップの実績を有してます。
会社設立、開業など起業資金調達をご要望の方は、
当会計事務所によるサービスを確認下さい。
大岡山など目黒区制度融資はこちらから

経理会計、確定申告対応の大岡山近くの会計事務所
当会計事務所では、大岡山など目黒区で
会社の会計や経理の代行や、土地や不動産を
譲渡した場合の確定申告も承っております。
直接対応が難しい場合、提携を紹介させて頂くなど
大岡山など目黒区の地元の会社様にできる限り
お役に立てるような事務所運営を心掛けてます。
匠税理士事務所と提携先の詳細につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
大岡山で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

大岡山の会社設立・法人化登記情報
大岡山など目黒区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
大岡山など目黒区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 渋谷出張所 】管轄区域 目黒区
〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号
(渋谷地方合同庁舎)
上記が大岡山で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
今後も大岡山など目黒区の会社様に支持される会計事務所づくりを目指します。
最後までご確認頂きありがとうございます。
ご不明な点がございましたら
お問い合わせ頂ければ幸いです。
大岡山など目黒区の会計事務所の採用求人はこちら
【 → 東京都目黒区の会計事務所の求人・採用は匠税理士事務所】
執筆者・文責:税理士 水野智史
税理士の対応エリア:大岡山(おおおかやま)など目黒区など東京都23区全域
#大岡山税理士事務所
#大岡山会社設立
【士業の法人化】合名会社の会社設立や法人設立のメリットやデメリット (18/03/14)
匠税理士事務所のWEBサイトへご訪問ありがとうございます。
弊所は東京都を中心に法人化に力を入れている会計事務所です。
今回は法人化の中でも、士業の場合についてそのメリットやデメリットをまとめてみました。
弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など士業の方で、
事業規模が大きくなってきたので、個人事業主から会社形態に変更することを
【 法人化 】又は【 法人成り 】といいます。士業の場合の法人化では、基本的には上記いずれの士業でも合名会社に準ずる法人に該当することになります。
それでは合名会社とは基本的にはどのような組織なのでしょうか。
士業の法人化、法人成りの合名会社とはどんな会社組織なのか
士業での法人化をする場合には、合名会社に準ずる法人となりますが、
合名会社には大きく以下のような特徴がございます。
・法人格を有するので法人税の課税(個人ではない)
・出資は財産の他にも信用・労務の出資でも可能
・債権者に対しては無限責任を負う無限責任社員(これが最大の特徴)
「特許業務」、「司法書士」、「行政書士」、「社会保険労務士」及び「土地家屋調査士」など
士業法人のこれらは各々、弁理士法第47条の4第1項、司法書士法第38条第1項、行政書士法第13条の21第1項、
社会保険労務士法第25条の15の3第1項、土地家屋調査士法第35条の3第1項参照)に基づいた法人で、
「合名会社」の制度をもとに作られているので、構成員は全員 「 無限責任社員 」 となります。
基本的にはこの合名会社に準ずる法人となり、人の信用で成り立つ法人というのが最大の特徴です。
合名会社や士業法人は、無限責任社員(出資者)だけで構成されている会社であるため、
会社財産で会社債務を完済できなければ、会社の借金返済に社員個人の財産もあてる必要があり、
重い責任を負っている事になります。
このように社員個人の信用がそのまま会社の信用につながるため、
社員全員が無限責任社員である点が、有限責任社員のみで構成されている株式会社や合同会社と異なります。これはつまり事業が巨大損失のため倒産し、自己の出資金額だけで不足する場合は、
個人の財産までも返済に充てる必要があり、取り立てが執行されるという事です。
士業の法人化・法人成りは損か得か、そのメリットやデメリットとは
それでは「特許業務」、「司法書士」、「行政書士」、「社会保険労務士」、「土地家屋調査士」など
士業の法人化や法人成りは、損なのでしょうか得なのでしょうか、そのメリットやデメリットを考えてみたいと思います。
株式会社でも合同会社でも、どの組織形態にも共通のメリット(消費税免税など)・デメリットは、
別途こちらにまとめておりますので、こちらからご確認ください。
【 → 個人事業を会社にする法人化、【実際】のメリットやデメリット 】
【士業の法人化(合名会社)のメリット】・多店舗展開が可能になる
・法人が権利・義務の主体となれるため、事業承継が容易になる
・源泉所得税が不要になるため、資金繰りが良くなる
【士業の法人化(合名会社)のデメリット】・自分と別に法人分の〇〇会の会費が発生してくる。
→毎月の会費については、各士業の個人会費もそのまま支払うことになるため、
単純に個人会費と法人(合名会社分)会費を支払うことになります。
・印紙税が発生してくる。
→個人事業主の士業は、原則として領収書に印紙を貼る必要はありません。
しかし、法人化をするとこの非課税の規定は原則適用されませんので、印紙税は課税されることになります。
(参照:国税庁 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/25.htm )
なお、無限責任は、個人事業主でも負っていますから、
合名会社になっても変わらないという意味でここではあえて記載しません。
また、令和元年6月6日、社員が一人の司法書士・土地家屋調査士の法人設立を可能にする
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立しました。
今回の改正は、公布の日から1年6月以内の政令(未制定)で定める日から施行されることが、
法務省のホームページに記載されております。
【 参照:→ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00381.html 】
これまでは社員となる士業を二人以上確保する必要から、中々法人化に踏み切れなった方も、
この法改正で会社にしてみたいとお考えの方も多いと思います。
そこで今回は弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など士業の方向け法人化説明会もご用意しております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携の専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

法人化・法人成りの相談会実施中
匠税理士事務所では、個人事業主である士業の先生が、法人化される際のサポートを行っております。
事業の状況や今後の方向性をしっかりとヒアリングした上で、
メリットやデメリットをお伝えし、士業の先生の法人成りのお手伝いができればと考えております。
したがって、個人事業主のまましばらく様子を見たほうが良い場合には、
そのようにお伝えすることもございますし、合名会社にされた方が良い場合もその様にお伝えします。
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
会社設立からその後の会計経理の代行や
節税対策・経営支援などはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
士業向け法人化相談会の詳細はこちらからご確認をお願い致します。

士業向け無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
法人化・法人成りサービス
匠税理士事務所では、会社設立からその後の経理、税務のサポートはもちろんのこと、
利益が出やすくなるための経営コンサルティングに力を入れている会計事務所です。
匠税理士事務所の法人化サービス詳細につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
法人化・法人成り支援サービス の詳細はこちら
★法人化ついての情報を掲載した法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
下神明駅や大崎広小路駅近くの匠税理士事務所・会計事務所 (18/03/13)
ご訪問ありがとうございます。
弊所は、下神明駅や大崎広小路駅近くで起業サポートや
コンサルティングに力を入れる会計事務所です。
下神明駅にある東京商工会議所の品川支部様にて、
経営セミナーの講師を担当させて頂き、
【利益とお金が残る会社作り】を講演しました。弊所ではお客様の事業支援には、
【豊富な経験・高度な専門性】が必要と考えます。
そこで税理士や税務会計スタッフ・提携士業が、 各分野で一流であることが重要と考えております。所属税理士やサービスなどは、
こちらよりご確認をいただけますと幸いです。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

下神明・大崎広小路の税理士の会社設立・起業支援
匠税理士事務所では、
下神明駅や大崎広小路駅近くで会社を作る方に、
・会社を作る際にどのような株主構成にすべきか
・資本金は幾らが良いか。
・建設業許可申請をとりたいがどうしたらよいか。
など会社設立の質問やご要望に対応するため、
税理士と司法書士が下神明や大崎広小路で
会社設立をご希望のお客様を起業支援します。
下神明や大崎広小路担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

下神明駅や大崎広小路駅近くのお客様に向けた
会社設立代行など起業支援はこちらから。
下神明・大崎広小路で創業融資による創業支援
匠税理士事務所は、下神明や大崎広小路などで
起業家の方を資金調達で創業支援します。
・起業に際して一部必要な資金を借入したいが
具体的な流れを知りたい。
・どの機関から借りるべきか教えて欲しい。
このようなご要望に対して、
大崎広小路や下神明対応の日本政策金融公庫
五反田支店と連携し品川エリアのお客様に向け
創業融資による創業支援をご提供しています。
会社設立時の創業融資サービスはこちら

下神明や大崎広小路の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は下神明駅や大崎広小路など品川全域対応)
下神明や大崎広小路の経理・確定申告・法人化
匠税理士事務所は、下神明駅や大崎広小路駅で
個人事業主から株式会社に変更するための
法人化や法人成りなどの税務申告や、
確定申告や会計・経理代行も承ってます。
個人事業主・起業家の方・会社経営者の方など
それぞれの方に向けた業務一覧につきましては、
こちらよりご確認をいただけますと幸いです。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
下神明や大崎広小路の方向け確定申告や経理代行
法人化など個人サービスはこちらで確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
下神明・大崎広小路で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

品川で会社設立・起業や経営セミナー開催
下神明や大崎広小路など品川区での
起業支援の一環でセミナー活動に力を入れてます。
産業振興公社や下神明の商工会議所品川支部で
数多くの起業や経営に関するセミナーを
これまで担当し大変ご好評を頂いてます。
下神明で行われました東京商工会議所品川支部でのセミナー詳細はこちらから
【 → 品川での経営セミナー 】

下神明駅や大崎広小路駅の会社設立・法人化登記情報
品川区の下神明駅・大崎広小路駅で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
下神明駅や大崎広小路駅など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が下神明駅や大崎広小路駅で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
下神明駅や大崎広小路駅付近の税理士事務所や会計事務所の求人採用
下神明駅や大崎広小路駅付近の税理士事務所や
会計事務所での勤務をご検討中の方に向けた
匠税理士事務所の正社員やパートスタッフ
アルバイトに関する求人や採用情報のご案内です。
弊所は、ワークライフバランスを重視し、
私生活と仕事の両立を図りたいという方から
ご支持を頂いております。
大崎広小路駅(おおさきひろこうじ)や、
下神明駅(しもしんめい)など品川の方に向けた
匠税理士の求人や採用情報はこちら
下神明や大崎広小路近くで会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い会計事務所をお探しならお気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#大崎広小路税理士事務所
#大崎広小路会社設立
経堂や桜丘など世田谷近くの匠税理士事務所・会計事務所 (18/03/12)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所では世田谷区を中心に、
【 経営に伴う全てのサービスがそろう事務所 】づくりを心がけております。
事務所最大の特徴は、
【 所属税理士・提携専門家の質 】 【 経営支援サービスの質 と 幅 】です。 これらで桜丘・経堂・世田谷No1を目指しており 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
当会計事務所の税理士やサービスは、
こちらよりご確認下さい。

経堂や桜丘での会社設立や起業支援
弊所では、株式会社や合同会社などの会社設立で、
ただ事務的に会社設立登記を行うのではなく、
税理士が会計の専門性を駆使して・出資構成や資本金をいくらにすればよいのか、
・決算月はいつにすればよいのか、
・入金サイクル・支払サイクルはどうすべきか
などの会社の基本設計を
桜丘や経堂などの起業家のご要望を伺いながら
一緒になって会社を作るようにしてます。
このようにこだわるのは、
最初の枠組みをしっかりと作ることで、
【 匠税理士事務所に任せてよかった! 】と言っていただきたいという想いからです。
起業の成功をしっかりサポートする
経堂や桜丘担当の税理士・専門家はこちらから
【 → 匠税理士事務所の概要 】

対応エリア:経堂や桜丘など世田谷区
桜丘や経堂に対応の司法書士とも連携してますので
会社設立の登記の代行も対応しております。
お客様は一度1時間ほど打ち合わせのお時間を頂くだけで会社が出来上がる仕組みがございます。
匠税理士事務所の会社設立の詳細はこちらから
桜丘や経堂での創業融資での創業支援
桜丘や経堂など世田谷区で独立開業し、
これから会社を設立する起業家の多くの方が、
起業資金調達で創業融資を検討されます。
創業後間もない頃は、事業が不安定ですので、
資金調達成功が事業の成長を左右します。

そこで匠税理士事務所では、
日本政策金融公庫や各種金融機関と連携し、
創業融資による創業支援を行っております。
経堂や桜丘などで起業される方に向けて、
会社設立時に融資を受けた方がよいのか、
受ける場合にはどの金融機関から
いくら程が適正かなどのコンサルティングや
事業計画書作成から面談の打ち合わせなど
お客様の融資獲得をサポート致します。
創業融資による創業支援の詳細は、
こちらよりご確認をお願いします。
【 世田谷区の創業融資・資金調達 】

桜丘や経堂の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は桜丘や経堂など世田谷全域対応)
桜丘や経堂の会計経理や確定申告・決算代行
弊所はこれまで世田谷地域で
経営支援に力を入れてきました。
そのため経堂や桜丘などの経営者様と
多くお仕事をさせて頂いた経験を通じて、
経営に関する全てのニーズにお応えできる事務所を 目指して人材充実と提携充実を心がけてます。桜丘や経堂ご近所で税理士をお探しの方は、
お気軽にご相談をいただければ幸いです。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
経堂や桜丘の方向けの確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
経堂や桜丘で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

助成金の申請代行や許可申請サービス
経堂や桜丘エリアでこれから創業するため
創業融資の資金調達と同時に助成金も
活用を検討したい方や、助成金の申請代行を
ご検討中の方につきましても社会保険労務士と
連携してコンサルティングを行っております。
助成金は一定の要件をクリアしていれば
受けることができる制度で、
原則として返還の必要がない制度です。起業時にはこれらの活用ができないかを
桜丘や経堂など世田谷エリアに対応する
提携社労士が連携してコンサルティングします。
経堂や桜丘など世田谷に対応の助成金
申請代行サービスはこちらでご確認下さい。
また、経堂や桜丘で建設業などを始めたい方には
建設業の許可申請にも対応した行政書士が、
しっかりとサポート致しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
経堂や桜丘の法人化・会社設立関連情報
経堂・桜丘など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
経堂や桜丘で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が経堂や桜丘で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
経堂や桜丘の税理士や会計事務所の求人採用
弊所では、お客様満足度を高めるため、
常に優秀な人材を募集しております。
良質なサービスは、良質な人材からと考え、
人を大事にする会計事務所です。
【ここ6年間の退職なし】がこうした
取り組みの結果と考えており、
今後もこのように人を大事にする会計事務所で
ありたいと考えております。
経堂(きょうどう)や桜丘(さくらがおか)など
世田谷にお住いでご興味のある方はご確認下さい。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
桜丘や経堂近くで会社設立されたお客様
数年前に桜丘で会社設立して起業時から
お世話になっております。
何度か事業が厳しい時期もありましたが、
しっかりとアドバイスを下さり、
今期で10期目になりました。
今までいろいろとありがとうございました。
これからも宜しくお願い致します。
桜丘にある小売業 会社設立A様
世田谷産業公社の法人化・法人成りセミナーで
税理士の水野先生と知り合い経堂にある
自社の顧問をお願いしました。
節税では「こんな手があったか」と感動しました。
これからも頼りにしております。
経堂にお住いのデザイナー 法人化B様
桜丘や経堂での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#桜丘税理士
#経堂税理士事務所
建築士・設計事務所に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (18/02/21)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は、建築士・設計事務所の税務会計に強い
税理士が所属する会計事務所です。
こちらは、税理士の変更をご検討のお客様に
向けたコンテンツとなります。
建築士・設計事務所の経営と会計事務所選び
建設業の経営ポイント

建築士・設計事務所の特徴は、
仕入等がないため在庫を持たなくて良い反面、
高い専門性を有する人材がサービスの源になり、この人材の確保が、非常に重要になります。
また、建築設計・監理等は専門性・想像力など
知的サービスで、【 高い利益率 】はありますが、
一方で案件着手~納品までが長期にわたり、
工事代金の入金に至るまでの期間を考えると、
多めの運転資金を用意し安全経営が求められる
【 資金繰りが難しい 】業種でもあります。

建設業専門の会計事務所選びのポイント
建築設計・監理など建築士・設計事務所での
税務会計が難しく、技術が求められるのは、
案件が長期に及ぶことによる収益の計上時期と決算の利益予測・毎月の利益把握が難しいためです。
こうしたノウハウがない場合は、利益予測を誤り、
節税対策などが効果的に行えなかったり、
資金調達にふさわしくない決算書、
業績が見えない経営になることもありえます。
大型案件を受注される建設業のお客様は、
銀行との良好な関係が、必須となります。
この良好な関係に正確な試算表が必要ですが、
これには高い専門性と人材が必要となります。
弊所では黒字戦略とキャッシュストック経営を
サービス軸とし、【利益とお金を残す事】に特化した
サービスが特徴の事務所です。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

また資金調達で業界トップクラスの実績があり、
金融機関を意識した決算対応が可能です。
適正な業績把握は、経営・融資に必須ですが、
この技術がある会計事務所は少ないのが現状です。
匠税理事務所は、人の質にこだわることで
これを可能にしております。
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の税理士 匠税理士事務所 】

建築士・設計事務所に強い税理士・会計事務所
匠税理士事務所では、
東京商工会議所で経営セミナー講師を務める世界4大会計事務所出身の税理士が、
経営コンサルティングや納税予測・高度な専門性を 活かしたサービスを提供します。
税務会計以外にも、建設業では、
一案件当たりの取引金額が大きい事もあり、
納品トラブルなどは、影響も大きくなるため
場合によっては、弁護士の契約書レビュー・
作成なども提案致しております。
また従業員さんの怪我の際には、
社会保険労務士と連携し、各給付金も提案します。
税務会計以外にも、本業に集中して頂けるよう
【 建築設計に必要な全てがある会計事務所 】を理念に各業界TOPレベルの専門家と提携してます。
上場企業の税務申告を担当した税理士も所属し、
規模も年商2,000万円~10億円まで対応が可能です。
【 税理士が執筆する黒字経営の情報館 】
◇事務所概要
弊所の所属税理士や提携先の専門家はこちら
◇建築業許可申請サービス

建設業の法人のお客様 税理士変更
建設業や建築業は、一取引当たりの金額が大きく、
ハイリスク・ハイリターンな特性の事業です。
そのため、【お金との付き合い方】や、
【利益が出る仕組み】など経営手腕も重要です。
匠税理士事務所では、お客様に、
【 お金 】と【 利益 】が残るように、会計を活用した経営コンサルティングを通じ、
経営サポートを行います。
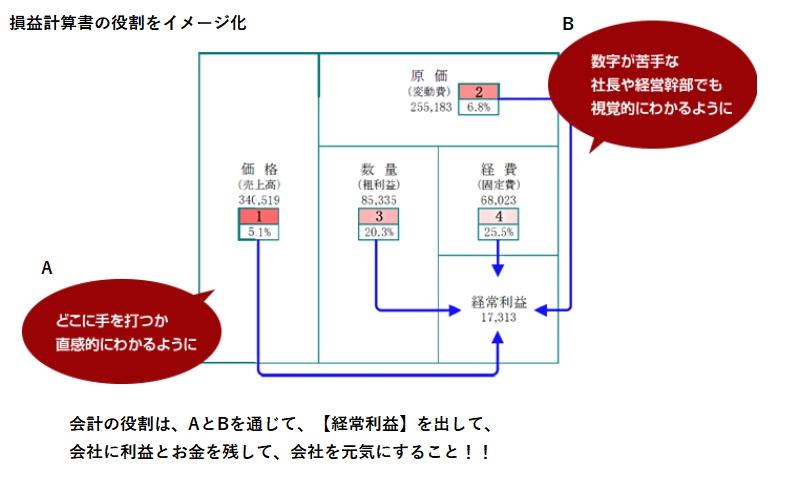
◇法人のお客様向けサービス
建設業の法人のお客様 会社設立や創業融資・税理士変更のサービス
◇会社の設立サービス
これから法人で建築士・設計事務所を立ち上げたい
お客様向け株式会社など会社設立代行サービスです。
1回の面談で今後の事業の方向性や社名、
決算時期や資本金などをヒアリングし、
登記までを代行するサービスとなります。
社名をお決め頂き、一度打ち合わせで、
起業専門の税理士と司法書士が会社設立します。
会社設立後の会計代行や建築士・設計事務所向け
経営支援も充実しております。

◇創業融資支援サービス
創業融資をご検討されている方は、
日本政策金融公庫や金融機関と連携した
創業融資支援サービスを提供しております。
創業計画書の作成サポートから当日の融資面談の
リハーサル・立ち合いなどサポートが特徴です。

◇起業のお客様向けサービス
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
建設業の個人のお客様 個人事業の起業や法人化のサービス
個人事業形態で建築士・設計事務所>開始し、
年商2,000万近くとなり株式会社などへ法人化、
法人成りを検討したいお客様に向けて、
メリットやデメリットの相談も含めた
法人化サービスを提案します。
◇建築士・設計事務所様向け 法人化相談会
法人化は、一生に一度の重要事項です。納得のいく結果になるように相談会も承っております。
◇個人の起業サービス
建設業に強い匠税理士事務所について
◇お役立ち情報
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
【税理士・会計事務所の対応地域:品川や世田谷、目黒など東京都全域】
執筆者・文責:税理士 水野智史
#建築士税理士 #設計事務所税理士
ボーナス・賞与の支払時期と決算で経費にするポイント (18/02/20)
経営者にとってもボーナスはとても重要です。
なぜなら、経営者は利益を確保し、
【 社員と一丸で稼いだ利益を、社員に還元するという利益配分感覚が求められるからです。 】
この感覚を持ち合わせていないと、人材不足の時代には社員の流出につながり、 これはお客様満足度の低下から顧客流出、売上低下という悪循環につながります。業績のいい会社は、利益率と利益配分の割合が高いため、
社員の定着率がよく、結果として好調な業績が長期的に続いている傾向があります。
逆に稼いだ利益を配分しないと、半年間など短期手には問題ないのですが、
中長期的には社員の退職率が上がり、業績が悪化するということが出てきます。
税務的にも決算でのボーナス・賞与は上手に活用する
今期の業績が好調の会社は、上記のような理由から、
ボーナス・賞与を検討すべきでしょう。
特に黒字の会社の実効税率は約30%程ですので、
1,000,000円のボーナスを支給しても、約300,000円は節税できます。
結果として実質は700,000円の負担ということになります。
赤字の会社はそもそも節税という視点はありませんから、
1,000,000円が負担となってきます。
このようなことからも黒字企業ではボーナスを支給されることが多いです。
しかし、このボーナスが損金算入される時期を的確に理解していないと税金の金額にも大きな影響を与えます。
そこで今回はボーナスを支払った場合の損金算入時期について記載します。
【 ボーナス・賞与の損金算入時期に関する規定 】
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、
それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。
なお、使用人に対して支給する賞与の額には、
使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1)労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知した日の属する事業年度においてその支給につき損金経理したものに限ります。) その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2)次に掲げる要件のすべてを満たす賞与使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、
ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給につき、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者
(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)と
その他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、
その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与その支払をした日の属する事業年度
(根拠規定: 法令72の3、法基通9-2-43~44)
上記をしっかりと理解していないと、予想していた税額より大きくことなってしまうという事態にもなりかねませんので、
特にボーナスの支給時期と決算期が近い12月決算法人は注意が必要です。
また、税務調査で余計なトラブルにならないためにも、決算日までにボーナス・賞与の支払いを完了するのがよいでしょう。
目黒区自由が丘の匠税理士事務所について
匠税理士事務所では、目黒区や世田谷区、品川区など東京都23区を中心に
会社設立などの起業支援から経営支援などの黒字化、税務コンサルティングに力を入れる会計事務所です。
賞与に関する規定や会社の人事労務に関するルールである就業規則の作成やコンサルティングにも、
提携の社会保険労務士と連携して対応しております。
匠税理士事務所の所属税理士や提携の社会保険労務士などの専門家の詳細につきましては、
こちらよりトップページに移動の上、会社概要のご確認をお願い致します。
【 → 税理士 世田谷区の匠税理士事務所 】

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
株式会社を作ったら、税金はいつ、いくら支払う?<K3> (18/02/15)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所WEBサイトへのご訪問ありがとうございます。
今回は株式会社を作った場合に、
【 どのような税金をいつ、幾らほど支払う? 】
についてまとめました。
経営者として最低限把握しておきたい税金の項目と税率をわかりやすく記載しております。
株式会社を作ったら、知っておきたい税金の基礎知識!
会社を作ったら、どんな税金を払いますか?
会社を始めたばかりだと、どんな税金を、いつまでに 支払うのかが分からず資金面で心配です。
税金について最低限の知識があれば、事前にお金を準備することができるので安心して経営できます。

ここでは、どんな時、どの位の税金を支払うか、
大まかな税金の基礎知識を解説します。
【 目次 】
1.利益にかかる法人税・法人税や事業税・住民税
2.売り上げに対してかかる消費税
3.外注さんや給与に対してかかる源泉所得税
4.契約書や領収書に対してかかる印紙税
会社決算時に利益にかかる税金 法人税・事業税・住民税とは
決算月になると、その決算月から2月以内に、
会社の儲けに対する税金を支払います。
<国に対する法人税や消費税(一部地方分あり)>と
<地方に対する住民税・事業税>の2種類です。
税金はいくら?どれ位の税率で計算方法は?
それでは、決算のときには、
いくらの税金を納めるのでしょうか?
会社の税金は、一年間の売上や経費を帳簿につけて利益を計算し、その利益に税率をかけます。
それでは、その税率がどれくらいになるのか?
一つ一つ見ていきましょう。
法人税の税率は、どれくらい?
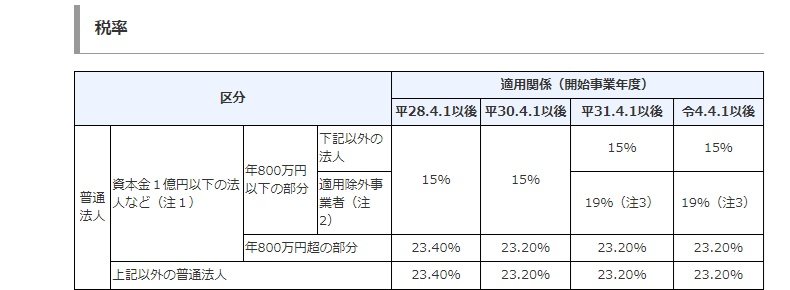
国税庁HPより
会社に関する税金で主なものとしては、
会社利益に対してかかってくる法人税があります。
法人税申告期限は事業年終了日から2か月以内です。
法人税は、会社の所得(利益)や資本金などで
税率が変わりますが、中小企業であれば
所得800万円以下は法人税は15%となりまして、
800万円超の部分は、23.2%となります。
例えば利益が1,000万円なら、
800万×15% + (1,000万-800万)×23.2%です。
法人税は、別表という税務署が定めた形式による
法人税の計算書類と決算書、勘定科目内訳書、
適用額明細書、株主資本等計算書、固定資産台帳、
概況書など添付して提出する必要があります。
会社設立後は、このような書類を必ず作成して
毎年税務署に作成する必要があります。
事業税の税率とその計算方法は
事業税も利益にたいしてかかる税金です。
法人事業税・特別法人事業税を事業税といいます。
税率は都道府県によって多少の違いがあります。
また資本金や所得(利益)に応じ、軽減税率や、
標準税率・超過税率のいずれかが適用されます。
事業税は、東京都は、儲かった所得で変わりますが
400万以下は3.5%、400万超800万以下は、5.3%、
800万円を超える部分は7.0%となります。
特別法人事業税の税率は、法人の種類によって異なりますが、資本金1億円以下の普通法人などの基準法人所得割額の税率は37%です。

法人住民税の税率とその計算方法
法人住民税は、儲けに対するものと、
均等割りがあります。
儲けに対しては「法人税割」がかかり、
儲けと関係なく会社規模で「均等割」がかかり、
合計額が法人住民税となります。
均等割りは資本金・従業員数で決められており、
赤字でもかかりますのでチェックしましょう。
例えば、東京23区内に事務所があり、
資本金が1,000万以下かつ従業員が50人以下は、
法人住民税の均等割は、7万円です。
計算方法は、法人税額に対して、税率をかけて住民税を計算するのがポイントです。
税率は17.3%と考えてください。
(地方法人税:10.3% 法人税割7.0%)
これらをまとめた実効税率は?
これらをまとめると、東京23区に所在する資本金1億円以下の中小企業の場合の標準税率のケースだと
実効税率=法人税率×(1+住民税率)+事業税率)/(1+事業税率)
簡便的に【 儲けには 約30%の税金 がかかる!! 】 と考えてください。
 ちなみに会社の法人税率は国際競争力UPと国内へ企業誘致のため税率は下げる傾向にあります。
ちなみに会社の法人税率は国際競争力UPと国内へ企業誘致のため税率は下げる傾向にあります。
売り上げに対してかかる消費税
その他に、売上については、消費税を納めます。こちらは以前記載した別の記事をご参照ください。
【詳細はこちら→会社経営と消費税の仕組み】
会社で払う税金の印紙税・源泉所得税とは
印紙税とは何か、どんな税金か
領収書や契約書を作成したら印紙を
印紙税は、領収書や契約書などを作成したとき、
書類に収入印紙を貼りつけて税金を納めます。
収入印紙は、コンビニや郵便局で手に入ります。
ポピュラーな領収書の印紙をご紹介します。
印紙税は、契約書などの内容・金額で
決められている金額の印紙を貼りつけます。
この印紙の貼り忘れを税務調査で
指摘されてしまうと罰金がかかります。
領収書や契約書を作成したら、
収入印紙を貼る習慣が大切です。
印紙税が幾らになるか個別の例は、
国税庁のこちらが分かりやすいので記載します。
(参考資料 → → 国税庁の印紙税一覧表)
給与や外注費支払いの源泉所得税とは
一日遅れただけでも罰金がかかる税金
従業員さんや役員さんに給与を支払うとき、
個人の外注さんに作業費を支払うときには、
給与や作業費から源泉所得税を引いて、
国に納めなければなりません。
この源泉所得税の金額を計算して、
自分で納付書を作って納めます。
従業員さんへの給与の源泉税 ⇒ 9人以下まで、半年に1回(届出必要)又は毎月か選択できます。
個人の外注の作業費の源泉税→毎月納めます。
怖いのが一日でも遅れると罰金がかかってしまいますので、源泉所得税には注意です。
税額も外注費と連動して増えますので、支払い忘れによるペナルティも大きくなりがちで要注意です!
震災で復興税というものがかかりますので、
こちらも合わせて確認しましょう。
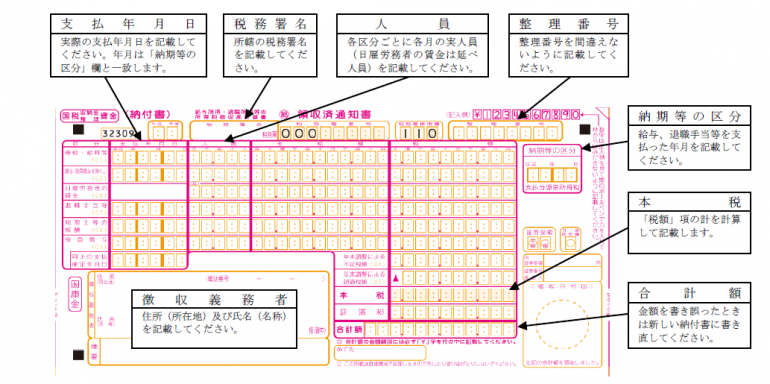
( 関連記事はこちら → デザイナーやコーディング(コーダー)などIT業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方)
(関連記事→給与計算と源泉所得税)
会社を設立した場合の税金のまとめ
この法人税や事業税などの税金には、 税率・各種控除など毎年税法の改正が入ります。会社として常に新しい税務情報が入手できるような
環境にあることも大切となります。
税改正に遅れることのないように注意しましょう。
なお、法人税では毎月帳簿作成を基に決算を行い、
計算書類(別表)・決算書(注記なども含む)、勘定科目内訳書、適用額明細(措置法を使う場合のみ)、
株主資本等計算書、固定資産台帳、事業概況書などを提出します。
こちらも忘れずに税務申告を行いましょう。
各制度では法律で定める所定書類の添付が無いと
特例の適用を受けられないものもあり要注意です。
匠税理士事務所の起業・会社設立支援
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

株式会社を作ったら税金なども出てきます。
税金の支払など起業時の資金確保のための
創業融資サービスはこちらから確認下さい。
【 → 税理士による創業融資】

株式会社・合同会社など作るための
会社設立サービスはこちらから確認下さい。
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
個人から会社を作って節税対策など
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
◇その他の起業支援サービス
会社設立後の会計や経理は全てお任せの
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
世田谷区の税理士は匠税理士事務所 ...TOPページへ
建設業許可申請はこちらから確認下さい。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など
東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業資金調達・創業融資を行う会計事務所です。
お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#会社税金
#会社税率とその計算方法
宇奈根や喜多見など世田谷近くの会計事務所は匠税理士事務所 (18/02/12)
匠税理士事務所は、宇奈根・喜多見など世田谷で、
【起業支援】と【経営支援】を行う事務所です。
これまで創業融資から会社設立などの起業支援や、
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 世田谷産業振興公社で経営セミナー講師を務めるなど経営支援で多くのノウハウを有しております。
匠税理士事務所のサービス内容・会社概要や、
所属税理士はこちらでご確認下さい。
宇奈根や喜多見の方で確定申告や経理代行も
承っております。お気軽にご相談下さい。

宇奈根や喜多見などの会社設立や起業支援
宇奈根や喜多見など世田谷地区で
これから会社設立をご検討されている方に向けて、
株式会社や合同会社の会社設立代行も承ってます。
【 起業に必要なすべてがある事務所 】を起業支援の軸としております。
宇奈根や喜多見担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

宇奈根や喜多見での株式会社・合同会社など
会社設立代行に関するサービスにつきましては、
こちらからご確認をお願いします。
宇奈根や喜多見で創業融資による創業支援
創業支援に強い匠税理士事務所では、
宇奈根や喜多見など世田谷で起業に伴う
資金調達も対応しております。
日本政策金融公庫・各種金融機関と連携した
創業支援詳細はこちらからご覧下さい。

宇奈根や喜多見の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は宇奈根や喜多見など世田谷全域対応)
宇奈根や喜多見で経理会計・確定申告・法人化
宇奈根や喜多見で経理や会計のサポートも承ってます。
経理の仕事で自社が行うべきことは何かを
個別教室で丁寧に説明致します。
【 経理初心者の方向け経理の仕事教室の内容 】経理の仕事教室では、
まず会社の一年間がどのように進んでいくのか、
そして会計の仕事には、
どのようなものが出てくるのかをお伝えします。
次にどのような資料を用意しておくべきかを、
税務調査にも対応できるように説明致します。
具体的には、
・領収書のポイント
(経費になるならないの基本的な考え方)
・請求書を発行する際のポイント
・資料の保存期間
・税務調査でトラブルになる点を説明します。

経理についての考え方が共有できましたら、
入金・支払いサイクルなどお金がたまる仕組みを一緒になって作り上げます。
この仕組みは経営で考える重要項目であるため、
今後、【 お金が残る会社 】にするには
どうすればよいかについても、
税理士とお客様でしっかり打ち合わせさせて頂き
会社にとって最善のサイクルを決定して頂きます。
卸売業や製造業といった比較的多くのお金を
必要とする事業を経営される方には、
資金計画表の作成の方法や、
資金計画表の作成講座もご用意しております。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
宇奈根や喜多見で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

宇奈根や喜多見など世田谷で会計事務所・税理士事務所の求人採用をお探しの方
当会計事務所では、一緒になって働いて頂ける
正社員スタッフ・アルバイト・パートスタッフを
随時募集致しております。
宇奈根(うなね)や喜多見(きたみ)など
世田谷エリアからもアクセス便利で、
働きやすさが自慢の会計事務所です。宇奈根や喜多見など世田谷区での採用求人に関する
詳細はこちらでご確認をお願いします。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
宇奈根や喜多見で会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#喜多見税理士
#宇奈根起業支援
法人化や法人成りの資本金や出資額はいくら?どう決める? (18/02/10)
個人事業主から株式会社や合同会社にするための
法人化や法人成りにあたって、
【 資本金決定 】はとても重要な事項の一つです。
今回は、法人化の際の資本金をいくらにするのか、
その判断のポイントについてまとめてみました。
法人化で会社の資本金を決めるポイント
資本金・出資金とは、出資者から集めた元手です。
会社からみれば返済義務のないお金であり、
出資者からみれば出したお金の範囲内でしか責任を負わない投資したお金です。
出資者は、法人化で株式や持分を取得することで
株主総会において一定の議決権を行使できます。
創業役員としては、特別決議も議決可能な出資総額の2/3以上を確保すれば、 創業役員以外からの予期せぬ議決を防止でき、 安定のため持分比率が高い方が好ましいです。
法人成りの資本金の決定
それでは資本金は幾らにしたら良いのでしょうか。
資本金の目安として、開業時にかかる設備資金 と 最低3ヶ月の運転資金の合計額を準備します。
売掛金回収にもう少し時間がかかる業種は、
もう少し多めに運転資金を考える必要があります。
また、次の4つのポイントにも注意が必要です。
1 税金面での資本金の注意点
1,000万円未満の場合、
最長で設立事業年度と翌事業年度は消費税の免税が選択可能になります。
住民税均等割は資本金が1,000万円超になると、
年額7万円から18万円になるので注意しましょう。
2 信用面での資本金の注意点
資本金は会社の信用度をはかるひとつの基準。
資本金額を取引基準としている場合もあり
あらかじめ調べておくことも重要です。
特に建設業や建築業の方は入札など競争で、
資本金が多い方が有利になることも多いため慎重に
3 創業融資での資本金の注意点
創業融資では事業資金の一定割合の資本金を
準備しているかを要件とする場合もあります。
4 許認可での資本金の注意点
許認可では資本金が許認可要件となってます。
要件を設立前に確認しておくとよいでしょう。

法人化で資本金の出資方法の選択、どんな方法がある?
出資には現金と現物があります。
現金に対しモノによる出資を現物出資といいます。現物出資には土地や建物、車や設立後販売する商品等がありますが、
評価額を算出が難しくに低い価格を計上すると、
追加で出資して穴埋めする義務を負いますから、
専門家に相談するなど慎重に行いましょう。
税理士等の証明を受けない場合には、
検査役調査が必要で、時間とお金がかかります。
ただし現物出資が500万円以下であればその必要がありませんから、
その額が500万円以下になるように調整することをお勧めします。
現物出資があった場合にはいくつかの手続きや必要書類があります。
また、現物出資の価格によっては、
出資者に所得税が課される場合も考えられます。
法人化や法人成りの無料相談会
匠税理士事務所では、法人化される前にそのメリットやデメリットをお客様の個人の確定申告書を拝見した上で、分かりやすく説明しております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。


法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
匠税理士事務所の法人化支援サービス
弊所では、資本金の決定から法人化の手続き代行、会社を作った後の経理や経営支援を承ってます。
サービスの詳細はこちらよりご確認下さい。
【 →法人化・法人成りは匠税理士事務所】
会社にしなければよかった・とならないよう
デメリットもお伝えし納得いく法人化を致します。
詳細はこちらからご確認をお願い致します。
◆法人化や法人成りについて情報を掲載した
法人化情報館のバックナンバーはこちら
◆上記の法人成り以外のお役立ち情報や、
サービス内容は、WEB上でご確認下さい。
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
法人化の資本金・出資金も検討する
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
法人成りと同時に起業資金を調達する
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
法人成りとあわせ建設業許可申請も対応します。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

執筆者・文責:税理士 水野智史
#法人化資本金 #法人化出資額
起業したいと思ったら、何をするべきかK13 (18/02/06)
WEBサイトへご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区などで会社設立など起業支援を行っており、
そのため各起業セミナーでも講師を担当させて頂いております。
今回は、【 起業したいと思うのですが、何をすればいいですか? 】 というご相談を以前に頂いたことから、こちらについて記載してみました。
まず何にいくら程のお金が必要かを考えてみましょう
起業したい = 成功したい という発想になりがちですが、
成功の前に、 【 起業したい → 生き残ること → 成功すること 】という【生き残ること】が前提条件となります。生き残るためには、お金はとても重要ですので、
まずは起業してから半年間必要になってくるお金を計算してみましょう。
必要なお金は大きく分けて、 【 設備資金 】 と 【 運転資金 】 の2つに分かれます。
1 設備資金とは、飲食店であれば機械など、IT事業であればPCや複合機などの一時的に必要なお金です。
2 運転資金とは、人件費や家賃など事業を維持していくうえで必要なお金です。
これらを計算してみて、半年間の必要なお金があれば、最低限必要なお金があるということになります。
売上の確保はできるか
会社員と起業家の最大の違いは、
会社員は、雇用契約ですので毎月給与が保証されていますが、
起業した場合には、仕事がなければお金が入ってこないというところです。
逆に仕事を任せて頂けて、お金が入ってくれば、
会社員よりも経営者の方が手元にお金が残る割合が多いですから、
比較的経営者になって成功されている方が多いような印象を受けるのはこのためでしょう。
上記で半年間起業して生きていく上で必要なお金を確保して、
売上を確保できれば、成功する確率は高くなります。

このような考え方は、創業時の創業計画書を金融機関の方が審査するときにも同様です。
つまり、 【 何に、いくら必要で、お金を無事返せるだけの売上・利益をあげれるか 】
逆を言えば、
1 必要なお金を準備して起業をして、 2 売上を上げる目途がしっかりと立っているこの2要件をクリアできると、融資での資金獲得の成功割合も事業の成功割合も上がっていくというわけです。
必要なお金を用意できているという方は、
これまで起業のためしっかりと準備をしてきたというように金融機関では評価します。
このような方は、お金を貯めれるわけですから、返せるという見方になるわけです。
逆に必要なお金は全て融資で獲得しようという発想では、
金融機関もこの方は大丈夫だろうか・・と不安になってくるわけです。
話が長くなってしまいましたが、起業したいと思ったら、
1 必要なお金をしっかりと準備していくこと 2 売上を確保できるように見込み客をしっかりと囲い込んでいくことこのような地道な準備をしていくことが重要です。
世田谷区や目黒区、品川区での会社設立や創業融資など起業支援
匠税理士事務所は、世田谷や目黒、品川を中心に会社設立や創業融資など起業支援を行っております。
これから株式会社や合同会社など会社設立をしたいという方にむけて、
会社の株主や資本金をどうすればいいのかなどコンサルティングを行ったり、
会社設立後の経理アウトソーシングや給与計算、社会保険手続代行なども承っております。
各種起業セミナーや経営セミナーでも講師を務めておりますので、経営に関するアドバイスにも定評がございます。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
法人化や法人成りをしたら決算月や決算期はどの時期がいい? (18/02/01)
匠税理士事務所にご訪問ありがとうございます。
個人事業から会社へ変更を検討される方から
【 法人化や法人成りで決算月や決算期は
どの時期がいいでしょうか? 】
というご相談をよく頂きますので、
決算月・決算期を決めるポイントをまとめました。
法人化や法人成り後、決算月・決算期や事業年度はいつがよいか
会社の利益を計算するために、
区切った期間を事業年度といいます。
個人事業主の場合は、原則として、
1月1日から12月31日の事業年度となりますが、
株式会社や合同会社など会社の場合の事業年度は、1年以内であれば自由に決めることができます。
個人事業と同様に、1月1日スタート(期首)で
12月31日を最終日(期末)とする会社であれば
【 決算月 】は、12月となります。
また4月1日~3月31日の3月決算でも良いですし
10月1日~9月30日の9月決算も自由です。
会計期間を1年でなく半年にすることも可能ですが
期間が短いと決算ごとに手間と費用で大変ですから
事業年度は1年と定める会社が大多数です。

決算期・決算月は、締めとなる最終月をいいます。
ちなみに日本は4月1日から3月31日までの3月決算が多く、外資企業は12月決算が多いです。
そしてこの事業年度の最終日を決算日から法人税、住民税、事業税、消費税などの税金の納付期限は、
原則として2か月以内となっています。
12月決算なら【 2月末が税金の納期限 】です。
法人化後の決算日の決め方、ポイントは?
上記の通り決算日は必ずしも3月末にこだわらなくても構いません。
むしろ、会社の事業内容と売上が上がる時期を
よく考えて決めるべきだと考えます。
それは棚卸商品が少ない時期を決算日にすれば、
棚卸商品を数える作業の負担も少なくなりますし、
会社の業務の閑散期を決算日にすれば、決算業務に時間をとられても本業にあまり影響しません。
なにより決算期・決算月を繁忙期にしてしまうと
繁忙期にあがった利益に対して、節税対策を講じる時間がないまま決算日がきてしまい
【 想定外の税金が・・・ 】にもなりかねません。

そこで匠税理士事務所では、
【決算期・決算月は閑散期】になるよう提案します。また、決算日2か月後の税金の納付期限と賞与や
その他支払いが重ならないようにすべきです。
消費税は設立から1年後を第1回の決算日とすると
免税事業者である期間が最大になります。
そのため、資本金の設定も非常に重要です。
匠税理士事務所の法人化や法人成り支援
匠税理士事務所では、
・そもそも法人化した方がよいのか、
しないほうがよいのか
・資本金はどうすべきか
・株主構成や役員構成はどうすべきか
・決算期はいつがいいか
などお客様のご要望や今後の展開をお伺いし、
法人化や法人成りの相談会を行っております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。


時期など法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
個人事業を株式会社など会社へ法人成りしたい方は
こちらよりサービスをご確認下さい。
【→ 法人化・法人成りは匠税理士事務所】
◆法人化や法人成りの情報を掲載した
法人化情報館のバックナンバーはこちら
法人化や法人成り以外のサービスや税理士、
社会保険労務士・司法書士・弁護士のサービスや
会計事務所をお探しの方はお気軽にお問い合わせ下さい。
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
法人化や法人成りに伴って会社を作る
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
法人化や法人成りと同時に資金調達する
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
法人化とあわせて許可の申請も対応する
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

執筆者・文責:税理士 水野智史
#法人化決算月 #法人成り決算月
30代や40代・50代で起業するのに必要な準備や用意とは<K9> (18/01/31)
終身雇用がなくなり、定年まで働くという方が
減る一方、増加してるのが起業する方の数です。
昔は脱サラといわれ、起業されるのが
珍しかったのですが、
現在はITの進歩やPCなどを駆使すれば自宅でも
事業ができるため、起業は身近になりました。
では、いつ起業するのがよいのでしょうか。

事業内容にもよりますが、
30代・40代で起業される方は、
比較的早く軌道にのるケースが多く感じます。
それでは30代・40代・50代で起業するには
何をすればよいのでしょうか。
起業・独立開業、何を用意・準備すればよいか
30代・40代・50代で起業をするにあたって、
とお考えの方も多いのではないでしょうか。
時代により起業で準備すべきものは違いますが、
いつの時代でも変わらないものは次の通りです。
優先順位別 起業に必要な準備や用意
優先順位1 起業後の資金準備や起業資金集め
優先順位1...起業後の資金
優先順位が最も高いものとしてお金があります。
事業は資金を投資し、更なる資金を獲得するため資金は最も大切です。
経営者は資金が不足すると、正しい経営判断ができない状態に追い込まれます。
この追い込まれた状態を元に戻すには、資金を投入するしかありません。
その資金の確保は
イ、金融機関からの融資
ロ、親戚などからの借入
ハ、売上を確保して資金を確保する
このような方法があります。
お金の不足した会社では
( ハ ) の売り上げを確保するために費やす時間が、お金の調達に回るという悪循環により
売上が更に落ち込んでしまいます。
悪循環に陥った時は、外部からの資金を入れるしか選択肢がありませんが、
自己資金(自分で貯蓄した資金)がなければ金融機関も動きません。

そのため会社員などお勤めのうちに
起業時に必要なものを購入するお金と
起業後、数か月間軌道に乗らなかったときにも
耐えられる事業の運営資金や生活費を確保して
それから起業をすることが必要です。
優先順位2 起業後のビジネスモデルを作り、得意先や販路の確保
優先順位2...得意先や販路の確保
次に行うべきものは、ビジネスモデル(儲けの型)を作り、得意先や販路を確保することです。
①で説明の通り、起業後は売上がなければお金が入りません。
その間も事業経費や、生活資金がかかります。
起業してしばらくは、経営よりも商売が成立するかどうかが最も重要です。
そのため、自分の商品を買ってくれる取引先や
自分の商品を売るためのルートをしっかりと
確保してからの起業が大切です。

起業時には、どんな商品を、だれに、どうやって売るか
この商売が成立するかどうかが最も重要です。
そのためには
②の得意先や販路をしっかりと確保し
①のお金の準備を完了してから
起業の手続きに入りましょう。
起業し、お金がなくなった後は修正がききません。
得意先や販路の開拓とお金も問題は大切です。
これらが準備をできれば、大部分は起業後でも、
解決できる問題となります。
◇自宅起業や在宅での一人起業は、
30代や40代・50代の起業では意外と多い
起業当初は社員を最初から雇用される方はまれで一人で起業される方が多いのが実情です。
一人起業や自宅起業の場合、固定費が削減でき、
起業当初売上が上がりにく時期をしのげます。自己資金が少ない状態で起業される場合や、建築業や製造業など多くの資金が必要な場合には、
自宅起業も一つの選択肢として上がります。
起業家を支援する匠税理士事務所の起業支援サービス
匠税理士事務所は、起業と黒字戦略に専門特化した会計事務所です。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちらから
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】
起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

(関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき? )
(関連記事: 創業融資を申し込むために必要な書類とは )
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
動物病院・獣医・ペットホテルの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (18/01/31)
匠税理士事務所のWEBサイトへアクセスありがとうございます。
弊所は、動物病院・獣医やペットホテル・ペットサロン・ドックスクールなど
ペットや動物関連の税務会計や経営支援に強い税理士・会計事務所です。
動物病院やペットホテルなど動物関連の特徴は、
他の事業に比較してスペースと人が必要になるため、固定費が高くなるところです。これは、多くの大事なお客様のペットをお預かりしたりするためですが、
この高い固定費をまなかえなくなると、赤字となるため資金繰り・経営が悪化してしまいます。
そこで最大のポイントは、
できる限り早い時期に損益分岐点売上(固定費をまかなう最低限の売上)を超える必要が出てきます。逆を言えば、家賃・人件費を超える売上・粗利を確保できれば、後はドンドン利益が出るという特徴がありますし、
売上の多くが、現金又はカードで比較的早めに回収できますので、
【入りは早く、出は遅く】という資金繰り良い業種でもあります。
また、利益率は異業種に比べて高い業種ですので、
開業当初に早く損益分岐点売上(固定費をまかなう最低限の売上)を超えれば、良い経営状態が続く業種です。

弊所では、このような動物病院・獣医・ペットホテルの経営者様に向けて、
世界4大会計事務所出身の税理士や高度な専門性を有する専門家が、節税対策や会計のサポートを行います。また、東京商工会議所や産業振興公社などで経営セミナー講師を務めるなど経営支援にも定評がございます。
所属税理士や提携の社労士・弁護士などの詳細はこちらからご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

動物病院・獣医・ペットホテルの起業支援サービス
匠税理士事務所では、これから動物病院・獣医・ペットホテルの起業をお考えの方に向けて、
株式会社や合同会社の設立など会社設立時の株主構成や決算期などのコンサルティングから登記の代行を承っております。
お客様は、会社名と本店所在地を決めて頂ければ会社が出来上がるというイメージで、大丈夫です。
会社設立サービス詳細はこちらからご確認下さい。
また、動物病院・獣医・ペットホテル・ペットサロン・ドックスクールなどペットや動物関連の事業は、
最初に内装費や保証金などの初期投資と事業を軌道に乗せるまでの時間を考えた運転資金の用意が必要です。
匠税理士事務所では、日本政策金融公庫と連携することで、創業計画書の作成支援から融資面談の立ち合いまでしっかりとサポートします。
詳細につきましては、こちらからお願いします。
人の採用・雇用など検討すべき助成金
動物病院・獣医やペットホテル・ペットサロン・ドックスクールなどペットや動物関連の事業では、最初から人を雇用される場合も多いため、助成金(人を雇用する際に要件を満たせばもらえるお金)の申請サポートも行っております。
助成金については、こちらからご確認をお願いします。
【 → 助成金申請代行《起業、創業や雇用の助成金》 】
動物病院・獣医・ペットホテルの法人化や法人成り
最初は動物病院・獣医・ペットホテル・トリマーを個人事業ではじめてみて、
ゆくゆくは株式会社や合同会社など会社にしてみたいという場合には、法人化も行っております。
法人化を行うことで消費税免税の節税なども可能になりますので、一度話を聞いてみたいという無料相談会も承っておりますので、
お気軽にご相談下さい。

【 無料相談会について 】
その他のサービスラインや料金などにつきましては、こちらからTOPページへ移動の上、ご確認下さい。
【 → 世田谷や目黒 品川の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
( 動物病院・獣医やペットホテル・ペットサロン・ドックスクール・トリマーなどが得意な税理士・会計事務所の対応エリア:世田谷や目黒、品川など東京全域 )
個人事業の確定申告で有効な節税対策とは (18/01/29)
匠税理士事務所は世田谷区や目黒区、品川区を中心に税務コンサルティングを行う会計事務所です。
個人事業主の方から 【 確定申告で有効な節税対策はありますか 】 というご質問を頂くことがございますので、
今回は個人事業の確定申告で有効な節税対策について取り上げました。
個人事業の確定申告で効果的な節税対策
当然ですが、個人事業主の方の確定申告で税金を計算する軸となるのが、事業所得です。
事業所得は以下のように計算します。
1 総収入金額 (売上)
2 必要経費 (仕入や人件費)
1 - 2 = 事業所得の金額 (利益)
総収入金額はほとんど節税の余地はありませんが、
必要経費は節税の余地が大いにあります。
例えば事業で使うPCなどの備品購入や倒産防止共済などへの加入がなどです。
ただし、余計なものを買ってしまうと、かえって税金を納めた方が
お金が残ったということも起こりえます。
例えば利益が50,000円で税率が20%だとして、50,000円のPCを買うと、
10,000円は税額が減少しますが、40,000円はPCメーカーに支払うため手元にはPCしか残りません。
このPCが不要だとすると、税金は減っていますが、不要なPCしか残っていないということになります。
もちろん、将来の収益につながる先行投資で経費を使うことは効果的な節税対策ですので、
ここで重要なのは、【 本当に必要なものなのかどうかを慎重に検討する 】 ということです。
こうした節税対策を積み重ねても税金が増えてきたという方には、次の方法をお勧めします
↓
個人事業主から株式会社や合同会社にする法人化や法人成りを検討してみる
個人事業主から株式会社や合同会社にすることを、法人化や法人成りといいます。
株式会社や合同会社にすることで、
1 利益が一定水準以上になると会社にした方が税率が低い
2 経費にできる幅が会社の方が広い
などの理由で法人化や法人成りを検討します。
上記の事業所得で節税をするには、限界があり効果も限定的なので、
利益が出るようになってくると、課税方式そのものを変更してしまうという法人化が効果的になります。
法人化のメリットやデメリットにつきましては、こちらにまとめておりますので、
ご覧いただければ幸いです。
【 → 会社にする?個人のまま? 法人化ポイント(メリット・デメリット) 】

効果がない節税対策・やってはいけない例
経費を増やすために大量に仕入を行うといいのではないか?
とお考えになるかもしれませんが、これは意味がありません。
決算日(12/31)時点で販売していない商品は、期末在庫として原価から在庫に戻すことになります。
税務調査でも期末在庫は重点的に確認されますので、ここで不正があるとペナルティの対象になります。また、20万円未満の一括償却資産の特例を適用して3年間で均等償却をしていたPCが最近調子が悪くて除却して、
全部経費にしてしまおう。と考える方もいらっしゃいますが、
さてこのとき、除却損を計上できるのでしょうか?
答えは、除却した場合であっても、3年間の均等償却を継続しますので、
このようなときに未償却部分を除却損にしてしまうと認められませんので注意が必要です。
効果がない節税対策・やってはいけないことをやってしまうと、
税務調査で指摘をうけて本来納めるべき税金に追加のペナルティ分を納めるという逆効果になるので注意しましょう!
世田谷や目黒、品川の匠税理士事務所の節税対策
弊所では世田谷区や目黒区、品川区を中心に税務コンサルティングを行っております。
節税の基本的な考え方は、早い時期に利益状況を把握して早い時期に手を打つこと
そして、効果を見極めた上で将来(法人化や法人成り)を考えることです。
先手先手でしかけるはどの仕事でも重要なように、
早い時期に利益をしっかりと把握して、適正な対策を行うのが重要です。
具体的には、9月又は10月に利益状況を把握し対策を行うのがよいと考えております。
なぜなら、1年の約7~8割が経過しているこの時期に利益も7~8割決まっています。
そこで、残り約2割を予測し、この予想した利益に基づいた税金を算定します。
この税金に対して節税対策を行うことで12月末にバタバタすることなく、安心して確定申告を迎えられます。
早い方は、8月頃から節税対策を検討され始めます。
匠税理士事務所ではをこうしたご要望にお応えするためにも納税シミュレーションをご用意しておりますので、
ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
また、節税対策を行っても税金が生じてしまう場合には、法人化や法人成りもご提案致しております。
お気軽にお問い合わせください。
サービスの詳細につきましては、こちらよりTOPページへ移動の上、
個人の方向けサービスよりご確認をお願い致します。
【 → 世田谷区の税理士は匠税理士事務所 】

三宿や太子堂など世田谷区の税理士や会計事務所 (18/01/25)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は三宿や太子堂など世田谷区での会社設立など
【起業支援・経営支援】に力を入れる事務所です。世田谷産業振興公社での起業塾講師を務め、
商工会議所創業セミナーや経営セミナー講師を担当し、
多くの起業家や経営者のお手伝いをしてきました。
最大の特徴としましては、
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 【高度な専門性・高い技術力】を活用することで、 お客様の94%が黒字経営を実現されている事です。また、お客様のご相談にお応えできるように、
法務・労務・著作権や特許権・許認可申請・助成金
資金調達など各分野のプロフェッショナルと連携してます。
所属税理士やサービスラインは、
こちらよりご確認を頂けますと幸いでございます。

三宿や太子堂の会社設立や起業支援
三宿や太子堂など世田谷で合同会社や株式会社など
会社設立したいという方に向けて、
会社設立・創業融資のスタートアップ支援を行ってます。
匠税理士事務所では、お客様の会社設立を一件一件 丁寧にサポートすることを大事にしております。それは、お客様にとって大事なイベントである
会社設立で無事成功して頂きたいからです。

会社設立をする際に株主になられる方や
役員になられる方のお話を伺い、
将来のビジョンを基にコンサルティングを行います。
会社設立後には本業に専念して頂けるように、
会計・給与計算アウトソーシングもご用意しており、
経営面や節税面ではお客様にとって
最善な選択肢を一緒になって考えます。
三宿や太子堂担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

太子堂や三宿など世田谷エリアを中心とした
匠税理士事務所の会社設立サービスは、
こちらからご確認をお願い致します。
三宿や太子堂で創業融資による創業支援
当会計事務所ではで三宿や太子堂など世田谷でも
会社設立後の創業融資でトップクラスの
創業支援の実績がございます。こうした取り組みの結果、日本政策金融公庫での
創業融資をご利用になりたいお客様に向けて
本来は日本政策金融公庫各支店での融資面談が、
匠税理士事務所にて税理士立会のもと行えるという 独自の創業融資サービスをご提供しております。
また、日本政策金融公庫の融資とともに三宿や
太子堂など世田谷の制度融資もご検討される方に、
城南信用金庫など世田谷のエリアを拠点とする
金融機関とも提携しておりますので、
三宿や太子堂など世田谷の地方自治体の制度を
活用した会社設立時の制度融資も対応可能です。
三宿や太子堂で起業するにあたり、
創業融資につき一度話を聞いてみたいという方や、
創業融資制度・自治体制度融資を利用したいが、
創業計画書の書き方や自己資金と融資バランスを
会社設立時に相談したいという方に向けて、
創業融資コンサルティングも提供してます。
三宿や太子堂で当会計事務所の創業融資による
創業支援はこちらよりご確認をお願いします。

三宿や太子堂の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は三宿や太子堂など世田谷全域対応)
三宿や太子堂の経理会計や確定申告・決算
匠税理士事務所は、
【人の質】と【サービスの質】にこだわることで、 お客様のお役に立つ税理士事務所であることを常に心掛けております。この理念のもと会計経理から決算申告の代行や
給与計算・社会保険手続きも対応致します。
利益を出すための経営支援や、
個人から会社にする法人化も承っております。
匠税理士事務所のサービスラインは
こちらよりご確認をお願い致します。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
三宿・太子堂で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

(対応エリア:太子堂や三宿など世田谷全域)
三宿や太子堂の法人化・会社設立関連情報
三宿・太子堂など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
三宿や太子堂で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が三宿や太子堂で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
太子堂や三宿近くの会計事務所・税理士事務所の採用求人
当会計事務所ではアルバイトやパートスタッフ
正社員スタッフの求人や採用を行っております。
太子堂や三宿など世田谷近くで
会計事務所でのご勤務をお考えの方は、
以下にございます求人採用に関する情報も
ご確認をいただけますと幸いです。
離職者が多いと良い仕事はできませんので、
弊所の採用求人の特徴は人が残る会計事務所です。
税理士受験生や主婦の方、正社員希望の方
それぞれニーズに沿った制度を用意しております。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
三宿(みしゅく)・太子堂(たいしどう)の方に
株式会社の会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#太子堂税理士事務所
#三宿会社設立
デザイナーや広告代理店の税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (18/01/18)
匠税理士事務所HPへ訪問ありがとうございます。
弊所は目黒の自由が丘から2分の場所にございまして、港や渋谷近くという立地とクリエィティブ業に強い高度税務が可能な世界4大会計事務所出身の税理士が所属する事もあり、
デザイナーやクリエイター、広告代理店などのお客様と多くお仕事しております。
デザイナーやクリエイター、広告代理店は、材料仕入は無いですが、
デザイン性・企画力・発想力というセンスと、時代の先を読む力が求められる難しい仕事です。
また、業種的に利益率が高いため節税の余地が多く、高度な税務テクニックが必要になる業種です。
匠税理士事務所ではデザイナーやクリエイター、広告代理店のお客様に向け決算3か月前に独自システムで利益を予測し、税額予測と効果的な節税を提案するシミュレーションを行います。
この手法は、株主配当可能利益を早期に計算する必要がある上場企業などが行っている税金見込計算や税効果会計の検証などを行う ( Tax Accrual )の考え方を取り入れたものです。
【 他の事務所では税金の連絡が決算後に行われて、急な払いが必要となり困った。 】
【 全然節税対策してくれない・・・ 】という
お悩みのデザイナーやクリエイター、広告代理店などのお客様のお役に立てる会計事務所です。
また、上場企業を担当していた税理士が所属しておりますので、
関与先様も年商5,000万~7億円と幅広い規模の方がいらっしゃいます。
匠税理士事務所の税理士やサービスは、こちらからご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

デザイナー・クリエイターや広告代理店の創業融資も対応
デザイナー、クリエイター、広告代理店の経費は、
内部スタッフに支払う人件費や外部に支払う外注費が主となります。
そのため、弊所のお客様には、【 入りは早く・出は遅く 】というサイクル改善等
キャッシュフロー・資金繰りの最適化を進言しております。
入金が1か月後、支払いは2か月後になるように取り組んで事業が軌道にのると、
高い利益率もありますので、資金的には余裕がある状態になります。

一方軌道に乗るまでデザイナーやクリエイター、
広告代理店は、ソフトやPC購入など設備投資にお金がかかったり、
与信的にも入金・支払い共に1カ月でお金が必要な状態にもなるのも事実です。
そのため、創業時には【 日本政策金融公庫や各種金融機関からの創業融資による資金調達 】をお勧め致します。
これは、仮に500万円融資を受けておくとすると、
金利は一般的に2%程ですので、500万円×2%=10万利息が生じます。
しかし、500万を借りたことでお金の心配をせず、目の前の仕事に集中できる環境が作れることで、
1件100万円の案件を無事納品できれば、
【案件の利益 > 利息10万円】という構図になり会社には十分にメリットが残ると考えるからです。
また運転資金融資は一般的に5年返済ですが、
クリエイター、デザイナーや広告代理店では5年あれば多くの場合、事業が軌道に乗ります。
そのため、創業当初の融資は検討されると良い事項となります。
弊所では、創業計画書の作成支援から当日の融資面談立ち合いまでしっかりとサポートしております。
詳細はこちらをご確認下さい。

株式会社や合同会社など会社設立にも対応
クリエイター、デザイナーや広告代理店の場合、
最初から株式会社や合同会社で始められる方が多いです。
これは様々な理由があると思いますが、やはり得意先からの要請も多いのではないでしょうか。
信頼面でも会社の方が優れていますし、
デザイナー、クリエイターや広告代理店を個人で経営する場合には、
源泉所得税など得意先にお手間をおかけしてしまうのも事実です。
【 デザイナー・コーディング(コーダー)などIT業の源泉税】
匠税理士事務所では、会社設立サポートも行っておりますので、お客様には会社名と本店の場所のみ決めて頂ければ、残りの事項は一緒になって考え、
アドバイスさせて頂きまして登記などに必要な書類も全て弊所にて対応させて頂いております。
もちろん、会社設立後の会計や給与計算、社会保険などの手続きにも対応致しておりまして、
クリエイター、デザイナーや広告代理店の方の【 起業に必要な全てがそろう会計事務所 】を事業の理念としております。
詳細につきましては、こちらからご確認下さい。

デザイナーなどクリエイティブ事業の起業や創業支援につきましては、こちらからご確認をお願いします。
【 → デザイナーや広告代理の会社設立・創業融資・起業は匠税理士事務所 】
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
弊所の料金や会計等のサービスラインにつきましては、こちらからご確認をお願いします。
【 → 世田谷区の税理士は匠税理士事務所 】
クリエイター、デザイナーや広告代理店などクリエィティブ事業・WEB制作会社様担当の税理士・会計事務所の対応可能エリア:
世田谷や目黒、品川など東京都23区全域
いい税理士や良い会計事務所の選び方・探し方とは (18/01/17)
これまで約20年近く税理士法人や会計事務所などこの業界でお仕事をしてきました。
ご新規でお客様とお会いした際にいただくご質問の中に、
【 いい税理士や良い会計事務所の選び方・探し方やポイントを教えて下さい 】というご質問がございました。そこで今回は、いい税理士や良い会計事務所の選び方・探し方について記載します。
いい税理士や良い会計事務所 = かかりつけ病院の選び方・探し方
友人や知り合いに税理士や会計士がいるということは少ないと思います。
ですが、家族が風邪をひいたり、怪我をしたら、よくいく病院は決まっていることがほとんどです。
いい税理士や会計士の選び方・探し方やポイントを考えると、
中々ご自身の中でいい基準が浮かばないのは、まわりに税理士や会計士がいないことが多いからですが、
いい病院やお医者さんの選び方や探し方なら、すぐにご自身の基準が浮かぶのではないでしょうか?病院やお医者さんには、ご自身やご家族といった大事な身体を任せることになります。
税理士や会計士には、大事な会社を任せることになりますので、これらの選び方や探し方は必然的に似てくるのです。

良い税理士やいい会計事務所にはここが重要
それでは、いい税理士の選び方や良い会計事務所の探し方に何が必要でしょうか。
いろんな考えがあるかと思いますが、
【 選ぶポイント1 】 人間性(誠意と熱意があるか) 【 選ぶポイント2 】 技術やノウハウ・知識があるかこの2つが、良い会計事務所を選ぶ上で重要なポイントだと考えます。
なぜなら、お客様のために一生懸命に取り組み、これを形にするための技術があれば
お客様のお悩みやニーズにはお応えできると考えるからです。
誠意と熱意がなければ、どんなに技術的に優秀でも、メールや電話のレスが悪かったり、
試算表や報告書が遅いといった怠慢につながりますし、
技術や修練度が低ければ、誤字脱字が多かったり、
税額計算など税務申告でもミスが多く、税務調査でペナルティを受けることなどにつながります。

実際にお客様から税理士や会計士の変更に関するご相談を頂く際の多くは、
1 メールや電話のレスなど対応が悪い 2 計算等とにかくミスが多いこれら2つのため、いい税理士や良い会計士を探しているという場合がほとんどです。
また、例外もあるかもしれませんが、
いい税理士や良い会計事務所は、値引きや激安などのセールスは行わないことが多いように感じます。
というのも値引きや激安などのセールスを行わなくても既存のお客様からのご紹介などでお客様が増えていくからです。
こちらもいい病院や良いお医者さんに行くときに、料金 > 人間性・技術となるでしょうか。 多くの場合には、 料金 < 人間性・技術 となるのではないでしょうか。また、実際に20年近く会計業界にいますが、いい事務所は税理士紹介サービスをあまり利用しません。
高度な専門性を有していれば、お客様にご満足頂けてお客様が増えていくからです。
紹介サービスは、会計事務所へお客様が支払う料金の一部が、紹介会社に流れるため、
最終的には料金をお支払いなるお客様へのサービス向上につながらないことにも起因します。
匠税理士事務所が目指す事務所
匠税理士事務所では、2008年に事務所を設立して以来、【人の質】・【サービスの質】にこだわっています。 これらにこだわることこそが、お客様のニーズやお悩みにお応えできる唯一の方法ではないかと考えるからです。そのため、むやみに規模を追うのではなく、お客様に満足していただける質を追いたいと考えております。
弊所の所属税理士やスタッフ、提携先の専門家や、
サービスライン一覧につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いでございます。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

起業家向けサービスはこちらからご確認下さい。
【 → 税理士による創業支援 】
匠税理士事務所の法人向けサービスはこちらからご確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
いい会計事務所の選び方・探し方で少しでもお役に立てると幸いでございます。
お役立ち情報やアクセスなどにつきましては、
こちらよりTOPページからご確認をお願いします。
【 → 世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所 】
駒場や東が丘など目黒区の税理士や会計事務所 (18/01/08)
目黒の匠税理士事務所のホームページへ
アクセス頂きありがとうございます。
弊所は駒場や東が丘など目黒区を拠点として、
世界4大会計事務所出身の税理士を中心に 【 起業支援 と 経営支援 】に力を入れる事務所で商工会議所目黒支部で経営セミナー講師もしています。
匠税理士事務所の軸は、
【サービス品質】と【人材の質】にこだわり、高度な専門性でお客様のお役に立つことです。
弊所の税理士やサービス全般につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

駒場や東が丘の会社設立や起業支援
駒場や東が丘など目黒でこれから株式会社や
合同会社を設立したいという方に向けて、
会社設立代行からコンサルティングを行ってます。
お客様の一生に一度の起業が成功するよう
会社設立・創業融資など起業支援を
経験豊富な税理士が直接コンサルティングします。
起業・独立開業のコンサルティングでは、
税務や会計的な視点は当然ですが、
将来的なキャッシュフローを考えた入金や出金のサイクル、
事業必要資金と自己資金とのバランスを考えて
創業融資のコンサルティングも行います。
ご要望のお客様には助成金申請や
社会保険加入手続き、各種許認可申請など
駒場や東が丘に対応する社会保険労務士や
行書書士などの専門家がチームになり、
【 起業に必要なすべてがそろう会計事務所 】 を使命にお客様のお手伝いを致します。
担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の匠税理士事務所の概要 】

駒場や東が丘などで税理士による会社設立など
起業支援は、こちらからご確認下さい。
駒場や東が丘の創業融資など創業支援
駒場や東が丘などで会社設立と同時に
起業資金の調達のための創業融資は、
こちらにてご確認をお願いします。

また、会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から補助金・助成金などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は東が丘や駒場など目黒全域対応です)
駒場や東が丘の会計や経理、確定申告代行
弊所は目黒で2008年に開業した会計事務所です。
これまで駒場や東が丘など目黒を中心に
起業支援をさせて頂きましたお客様と
長期間にわたり仕事をさせ頂いていることが
何よりありがたいことであると考えております。
今後も【人の質】・【サービスの質】にこだわり、 東が丘や駒場など目黒地域のお客様に喜んで頂ける会計事務所でありたいと考えております。
また税務会計以外のお客様のお悩みや
ご相談にも対応できるように
駒場や東が丘対応の各分野エキスパートと提携し
今後もより充実を図っていきます。
弊所サービスはこちらでご確認をお願いします。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
駒場や東が丘で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

会社設立など起業支援は上記でご確認下さい。
駒場や東が丘の会社設立・法人化登記情報
目黒区の駒場や東が丘で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
駒場・東が丘など目黒区で個人から会社設立する
法人成り・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 渋谷出張所 】管轄区域 目黒区
〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号
(渋谷地方合同庁舎)
上記が駒場や東が丘で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
駒場や東が丘など税理士事務所の求人採用
弊所ではお客様のお役に立つためには
優秀な人材が不可欠と考えており、
年中求人や採用など募集活動を行っております。
人が辞めたから補填するという姿勢ではなく、
お客様満足度を上げるため社員のゆとりをもった
仕事への取組みが重要と考えているためです。
設立以来、こうした取り組みの結果、
6年間退職者ゼロのありがたい評価を頂いてます。
駒場や東が丘など目黒地域の方で匠税理士で
勤務をご検討頂ける方はこちらで確認願います。
(駒場・こまば)や(東が丘・ひがしがおか)の方への
当会計事務所案内を御覧頂き感謝致します。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#駒場税理士
#駒場会社設立
部門別会計を活用した2号店など多店舗展開支援サービス (18/01/02)
匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。
弊所は世田谷区や目黒区、品川区を中心に会計を中心に経営コンサルティングを行う会計事務所です。
今回は会計の中でも部門別会計についてまとめてみました。
小売店やサービス業などで事業が順調に伸びてきているので、
将来は2号店を出したいという願望をもって経営されている経営者の方も多いと思います。
しかし、2号店を出すときに中心になってくれるスタッフはいるが、 自分の目が届かなくなるので心配だ・・・・・ とお悩みの方がいるのも事実です。このような場合には、部門別会計がお勧めです。
部門別会計を導入するメリットとは
2店舗目を出す場合、多くの場合は1店舗目がうまくいっているケースがほとんどです。
逆にいうと儲けの型が、1店舗目で出来ているということになります。2店舗目は、1店舗目の儲けの型にできるだけ近づけるというためにも、
1店舗目と2店舗目の売上・仕入や原価・販売管理費などの経費を区分して集計し、
1店舗目と2店舗目の差はどこにあるのかを分析することが重要です。
この差 = 課題 を解決することで、2店舗目は少しずつ1店舗目に近づいてくるようになります。これを1店舗目と2店舗目を区分せずにごちゃごちゃにしておくと、
何が原因で利益がでているのか、利益がでなくなったのかが分からなくなり、
本来は好調だった1号店まで調子を落とすという事態にもなりかねません。
数字に強い経営者は、必ず店舗ごとの長所と短所を把握し、解決策も的確にうちます。
部門別会計はこのような場合に大きく効果を出します。

匠税理士事務所の部門別会計サービス
匠税理士事務所では、部門別の会計管理を承っております。
最近従業員が増えてきて、管理に目が行き通らなくなってきたなどのお悩みをお持ちの方は、
是非、部門管理をお勧めします。
毎月ごとの各部門ごとの利益を明らかにすることで、会社全体で良いところ・悪いところが明らかになってきます。
また、部門管理導入のために特段やって頂くことはなく、経理は全て弊社にて代行するので安心です。
・今うまくいっているので、事業拡大を考えているが、目が届かなくならないか心配だ・・・
・独立志向のスタッフと共存共栄の関係を築きたいが、利益の配分など分かりやすい指標が必要だ・・
・将来的には多店舗展開を行いたいと考えている。
このようなニーズや、部門管理に興味のある方は、是非一度ご相談下さい。
匠税理士事務所の所属税理士や提携専門家、スタッフ詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 目黒区自由が丘の匠税理士事務所 】

上記以外のサービス内容や経営税務などのお役立ち情報につきましては、
下記のリンクからトップページへ移動の上で、ご確認をお願いします。
東京都 税理士 の匠税理士事務所HPへ
碑文谷や平町など目黒区の税理士・会計事務所 (18/01/01)
匠税理士事務所のホームページへ
ご来訪ありがとうございます。
弊所は碑文谷や平町などからアクセス便利な
目黒区自由が丘にある会計事務所で、
【起業支援】と【経営支援】が評判の事務所です。
匠税理士事務所の最大の特徴は、
【人の質】・【業務品質】にこだわることで、 顧客満足で【目黒No1 】を目指す事務所です。起業支援や確定申告、税務会計、料金などは、
こちらよりご確認をお願い致します。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

碑文谷や平町の会社設立などの起業支援
碑文谷や平町でこれから株式会社を設立して
独立開業や起業したいというお客様に向けて、
会社設立コンサルティングから登記代行を承ってます。
・出資金や資本金はどれくらいにするのか
またその出資割合はどうするのか
・役員構成や株主構成はどうするのか
・決算期はいつがよいのか
・定款の内容はどのようにするかなど
会社設立のポイントをお客様と一緒になって考え、
最善の会社設立になるよう支援します。
会社設立後の経理や経営支援も行いますので、 本業に集中して頂ける環境作りを手伝います。碑文谷や平町担当の税理士・事務所概要はこちら
【 → 目黒区の匠税理士事務所の概要 】

碑文谷・平町の会社設立はこちらから
碑文谷・平町の経理会計や決算確定申告の代行
匠税理士事務所は碑文谷や平町など
お客様が本業以外の問題に対応できるように
法務・人事労務・特許・許認可・VISA・登記・相続など
あらゆる分野のスペシャリストと連携し、
お客様のお困りごとを解決できるような
万全の体制をご用意致しております。
会計事務所なので税務会計しかできないではなく、
【匠税理士事務所に相談すれば何とかしてくれる】そのような存在でありたいと考えております。
当会計事務所の税務会計や確定申告、経理や
給与計算などサービスは以下でご確認下さい。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
碑文谷・平町で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

碑文谷・平町の創業融資などの創業支援
匠税理士事務所は、碑文谷・平町などで
会社設立や独立開業する方の会計経理や、
決算確定申告・補助金・助成金申請代行など
創業支援を行っております。
創業支援詳細はこちらからご確認下さい。
日本政策金融公庫や城南信用金庫の碑文谷支店
目黒区平町にある金融機関と連携した創業融資など
資金調達にも対応しております。
碑文谷や平町などで創業融資につきまして、
詳細はこちらでご確認をお願いします。

碑文谷や平町など目黒区の税理士・会計事務所での求人や採用
碑文谷や平町など目黒区の税理士・会計事務所で
就職をお考えの方はこちらから弊所の正社員や
パート・アルバイトスタッフの募集事項も
ご覧頂けましたら幸いです。
【お客様利益と社員の幸福を最大化する事務所】を
使命としており、
ここ5年間の退職者ゼロがという
働きやすさが特徴の会計事務所です。
碑文谷や平町など地元で正社員や
パートスタッフ勤務をご検討の方は、
こちらよりご確認をお願い致します。
碑文谷(ひもんや)や平町(たいらまち)のお客様
に向けた当会計事務所の案内を最後まで
ご覧くださりありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#碑文谷税理士
#碑文谷起業支援
梅丘や代田など世田谷の会計事務所は匠税理士事務所 (17/12/28)
WEBサイトへのご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所は、梅丘や代田など世田谷を中心に
【起業支援と経営支援】を行う会計事務所です。
起業・経営の成功で税理士や会計事務所が
お手伝いできることは、
1 できる限り短期間で黒字化する支援 2 経営資金の調達支援大きくこの2つに分かれます。
上記の実現には、社長が本業に専念できることが
必要不可欠となります。
そのため、弊所では経理や税務だけではなく、
人事や労務、法務や許可申請、金融機関など
【経営に必要な全ての専門家】がチーム対応します。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の税理士や提携専門家、
起業・経営支援などサービス全体につきましては、
こちらからご確認をいただけますと幸いです。
【 →世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

梅丘や代田の創業融資など起業支援
梅丘や代田など世田谷での起業をされる方に、
日本政策金融公庫、城南信用金庫やメガバンクなど
世田谷エリアに対応した金融機関と連携して、
創業融資のサポートも行っております。
・起業に際してお金は用意したが、
融資についても念のため聞いておきたい。
・自己資金と融資のバランスを知りたい。
・梅丘や代田対応の金融機関を紹介してほしい。
梅丘や代田担当の税理士・専門家はこちら
【→匠税理士事務所の概要】

(対応エリア:梅丘や代田など世田谷区)
創業融資のご相談も承っておりますので、
お気軽にご連絡ください。

梅丘・代田で会社設立代行など創業支援
梅丘や代田など世田谷で株式会社や合同会社など
会社設立を考えの方に向けまして、
司法書士と連携し基本設計・登記代行や
会社設立後の会計税務も承ってます。
梅丘や代田などで会社設立サービスは、
こちらで確認をお願いします。
梅丘や代田の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は梅丘や代田など世田谷全域対応)
梅丘や代田など世田谷で会計事務所や税理士事務所をお探しの方へ
梅丘や代田など世田谷で会計事務所や
税理士事務所をお探しの方で、
起業以外の法人化や法人成り、
確定申告の代行や会計アウトソーシング、
梅丘・代田でのコンサルティングサービスは、
下記のリンクより各サービスをご確認ください。
会社様向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
梅丘や代田の方向けサービスはこちら
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
梅丘・梅ヶ丘・代田で税理士の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

梅丘・代田の法人化・会社設立関連情報
梅丘・代田など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
梅丘・代田で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記は、こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が梅丘・代田で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
梅丘や代田で会計事務所や税理士事務所の採用求人
梅丘や代田など世田谷近くで税理士事務所や
会計事務所の勤務をご検討中の方は、
こちらから弊所の採用求人に関する情報も
ご覧いただければ幸いです。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
匠税理士事務所の創業支援サービス
匠税理士事務所は、梅丘や代田など世田谷で
これから創業をご検討されている方に向け、
会社設立前の資本金をいくらにするなど
梅丘や代田の起業支援や会社設立登記手続き、
創業に必要な資金調達のため創業融資から
助成金などのご提案を行っております。
梅丘や代田など世田谷で創業をお考えの方で
起業支援に強い会計事務所をお探しの方は、
匠税理士事務所にご相談ください。
確定申告・経理・決算も対応しておりますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
会社設立や法人化など税理士対応地域は、
梅丘(うめがおか)や代田(だいた)など
世田谷中心に東京都全域となります。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#代田税理士
#梅丘税理士
会社員や役員の方の給与所得の考え方と税金や確定申告用紙A (17/12/26)
会社員や会社役員の方の所得は、給与所得がメインの所得となります。
そこで今回は、会社員や会社役員の方で、配当所得や不動産所得など給与以外の所得が無い方が、
確定申告をされる際の税務知識の紹介として、給与所得の確定申告を取り上げたいと思います。
これらの方は確定申告書用紙A を使うことになります。
給与所得とはどのように計算するのか
給与所得の金額は、次のように計算します。
A 収入金額 (源泉徴収される前の金額) - B 給与所得控除額 = C 給与所得の金額
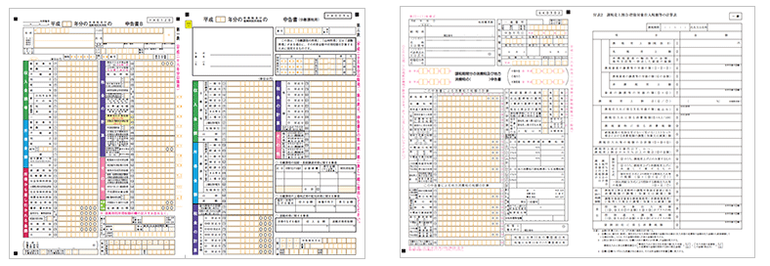
(A) 収入金額
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。
イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
ハ お金を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、簡単にいうと現金以外で受けたメリットのことです。
所得税の課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。
(B) 給与所得控除
会社員や会社役員などの給与所得では、自営業者の事業所得などのように実際の領収書や請求書を基に計算した
必要経費を差し引くことができない代わりに、所得税法で定めた各給与水準ごとに決められている
概算の経費である給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
< 関連ページ→ 国税庁の給与所得控除と説明と自動計算システム >
利益である給与所得を計算することになります。
給与所得者で実際の経費が多い場合の特例:特定支出控除
給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合で、
その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除の金額の1/2を超えるときは、
確定申告により、【 その超える部分の金額 】を 給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
(注意:平成28年前は別の算式にて計算します。上記は平成28年以降の場合の計算式です)
【 この規定が適用できるのは、 以下の特定支出に限られています 】1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出 (通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出 (転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出 (研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出 (資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出 (帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、
その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書席、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

給与所得に関する税額の計算方法
給与所得は、その支払の際に所得税が源泉徴収されていますが、
原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、
確定申告により税額を計算することとなります。
しかし、他に所得がない場合、勤務先において行われる源泉所得税の精算、
いわゆる年末調整によって確定申告を行う必要がなくなります。
(関連記事: 年末調整とは?年調のやり方や源泉徴収票の作成方法と作成代行 )
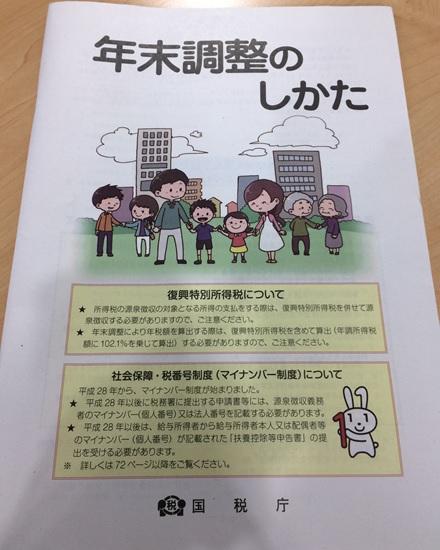
なお、給与の年間収入が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告が必要になります。
また、年末調整で精算できない寄付金控除や医療費控除などの適用を受ける方も、
確定申告によって還付を受けることになります。
このように会社員の方の給与所得は、収入は会社からの源泉徴収票で確定し、
経費は概算経費を用いられる方が多いので比較的簡単に計算することができます。
医療費控除や寄付金控除などを受けるために確定申告をご自身でされる際に少しでもお役にたてれば幸いです。
目黒区自由が丘の匠税理士事務所の事務所概要
匠税理士事務所は法人化や個人事業主の確定申告など世田谷区や目黒区、品川区を中心に
税務コンサルティングを行う会計事務所です。
主に事業に関する税務申告やコンサルティングを行っておりますが、
不動産の譲渡や不動産の賃貸に関する収入などにつきましても、
提携の専門家と連携して大規模な申告にも対応可能です。
世田谷や目黒、品川で税理士や会計事務所をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
所得税理士や提携の専門家及びサービス内容については、こちらよりご確認をお願い致します。
【 → 目黒区自由が丘の匠税理士事務所概要 】

個人事業を株式会社や合同会社へ組織変更して節税をする法人化はこちらからご確認ください。
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】上記以外の会社設立や創業融資などの起業支援や税務お役立ち情報につきましては、
こちらよりTOPページへ移動の上でご確認をお願い致します。
世田谷 税理士は匠税理士事務所へ
経営分析報告書・業績レポートサービス (17/12/12)
匠税理士事務所では、経営者の方に向けてオリジナル業績レポートを作成し、
数々の経営者の方々から以下のようなご好評を頂いております。
・会社の数字がよく分かるようになった。
・お金についてよくわかるようになった。
・自分のアイデアを実行した結果が会社の数字にどのように表れるか楽しみになった。
・税金が毎月大体幾らくらい出そうなのかわかるようになった。
弊所では 【 利益とお金が残るより良い会社づくりのお手伝い 】のために、会計データを活用してお客様の会社の課題の分析を行い、分かりやすく経営報告書にまとめております。

なぜ経理や会計データの活用が必要なのか
年商5,000万円ほどの規模であれば、感覚での経営でも問題ない場合が多いのですが、
会社の規模が大きくなってくると、 利益の出る額も大きくなる一方で、損失が出る額も大きくなってきます。つまり一つ一つの判断に、【 的確さ 】と【 早さ 】が求められるわけです。
年商5,000万円を超える規模になると人や外注先・得意先など自社をとりまく関係者が増えてくることで、
・人件費などの固定費に問題があるのか、
・外注の単価に問題があるのか、
・得意先への売上単価に問題があるのか、
・入金のサイクルが遅いのか
・出金のサイクルが早いのか
・在庫の保有期間が長いのか
など様々な問題が複雑になってくることで、
売上が伸びているのに、利益が減っている。。。。
黒字であるはずなのに、会社に利益が残っていない。。。。
といった不可解なことが起きてきます。
匠税理士事務所では、お客様から頂いた経理資料を基に会計データを作成し、
こちらにつき税理士が分析を行い、気になった事項を社長様に分かりやすく説明することで、
対応策・改善策を一緒になって考えていきます。
そしてこの改善策の実行の結果、会社にどのような兆候が出てきているのかを、
会計データを分析して報告を致します。

経営分析報告書・業績レポートはどれ位でできるのか
会社の規模が大きくなると、判断の早さも重要になりますので、
経営分析報告書・業績レポートサービスは、鮮度が重要と考えております。
そのためお客様から経理資料をお預かりしてから、【 原則 5~7営業日以内 】に納品を行っております。
また報告書はシステムで自動的に出力される画一的なものではなく、
お客様一社一社手作りで作成致しており、できる限り会社独自の問題に取り組めるように致しております。
的確な経営分析・業績把握は節税対策にも有効です
的確かつスピーディーに業績を把握しておくことで、
節税対策を効果的に行うことも可能になります。
節税対策は行き過ぎると会社が赤字になってしまいますし、
キャッシュフローを悪化させるなどのマイナスの側面もございます。
的確に業績を押さえておくこと、読むことでどの位までの節税対策を
どの時期までに行うのか決まってきます。
そして適切な時期に、的確な節税対策を実行することでバランスのよい決算内容となり税金・銀行対策・得意先への与信などにもプラスの影響が出てることで好循環のサイクルとなってきます。
匠税理士事務所の税理士やスタッフのご紹介
匠税理士事務所では世田谷区や目黒区、品川区を中心に、
経営セミナーの講師を担当するなど経営コンサルティングに力をいれております。
また上場企業の税務申告なども行っておりましたので、節税提案などの税務コンサルティングにも定評がございます。
弊所の所属税理士やスタッフ・提携専門家の詳細につきましては、
こちらよりご確認お願い致します。

税理士の対応地区は世田谷や目黒、品川など東京都23区全域となります。
ご興味のある方はぜひ一度ご連絡下さい。
上記以外のサービスや料金等につきましては、こちらよりトップページへ移動の上、
ご確認をお願い致します。
世田谷 税理士 の匠税理士事務所HPへ
簡易課税・本則課税の試算による消費税シミュレーション (17/12/05)
税率アップが度々行われている消費税ですが、
事業経営に与える影響がとても大きい税金です。
消費税の計算方法には、大きく分けると
【 本則課税 】と【 簡易課税 】がございます。
消費税は預かった税から支払った税を差引き、
納めるべき消費税を計算する税ですから
売上と共に増加し、節税余地はほぼありませんが、
消費税納付額に大きな影響を与えるのは、
1 消費税計算方法【 本則課税・簡易課税 】の選択 2 資本金1,000万未満で免税事業者の検討の大きく分けて2手が、節税では有効です。

消費税計算方法の本則課税・簡易課税とは
本則課税とは、
【 1 売上などにかかる消費税 】 【 2 仕入・外注にかかる消費税 】 【 3 1-2= 納めるべき消費税 】
という原則的な計算方法をいいます。
これに対して簡易課税とは、
【 前々年の課税売上高が5,000万以下 】で
【 簡易課税制度の適用を受ける届出 】を事前に
提出している者は、実際課税仕入れ税額を計算せず、
課税売上高から仕入控除税額の計算を行える
簡易課税制度の適用を受けることができます。
これは仕入控除税額を課税売上高に対する税額の
一定割合とするというものです。
【 1 売上などにかかる消費税 】 【 2 売上に概算経費割合(みなし率)を乗じる】 【 3 1-2= 納めるべき消費税 】本則課税と簡易課税の違いは、
ずばり仕入や外注費などの経費に関する消費税を、
実際の経費に基づいて計算するのか、
概算の経費で計算するのかという点です。
実際経費の消費税 < 概算経費割合の消費税なら 【 簡易課税の方が有利 】になるのです。
簡易課税制度の概算経費割合(みなし仕入率)
売上げを卸売業・小売業・製造業等・サービス業等・不動産業(注)及びその他の事業の【6つ】に区分し、
それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
【 みなし仕入率 】
第一種事業(卸売業)・・・・・・・・・・90%
第二種事業(小売業)・・・・・・・・・・80%
第三種事業(製造業等)・・・・・・・・70%
第四種事業(その他の事業)・・・・60%
第五種事業(サービス業等)・・・・50%
第六種事業(不動産業)・・・・・・・・40%
消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要
仮に簡易課税制度が有利となった場合に、
簡易課税制度の適用を受けるためには、
納税地を所轄する税務署長に原則として
適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」提出しなければなりません。消費税簡易課税制度選択届出書を提出した者は、
原則、2年間は本則課税計算による仕入税額の控除に
変更することはできませんので、
【 先を見通した検討 】が必要です。
特に近年のうちに大きな設備投資を
検討されている会社様は要注意です。
簡易課税・本則課税試算の消費税シミュレーション
シミュレーションによる節税対策期間
【 12月決算の会社様のケース 】
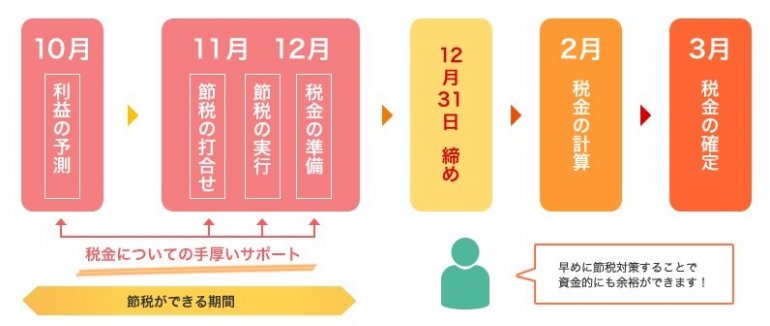
匠税理士事務所では、担当させて頂いております
お客様の決算3か月前には、
簡易課税と本則課税のどちらが会社にとって
有利なのか試算を行い将来納めるべき消費税を
シミュレーション致します。
シミュレーションの結果、お客様が適用されたい制度に
関する届出書の作成代行も行います。
お客様は、担当税理士と打ち合わせで
税務上で、【 最善の選択 】を行えます。◇匠税理士事務所サービスや概要はこちら
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

税理士の対応地区は世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域となります。
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
会社設立時の免税制度や2割特例を
活用した節税対策を加味して会社を作る
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
消費税の納税資金・起業資金の確保など
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
会計や決算確定申告、節税対策など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
個人から会社にすることで最大2年免税を
2回受けるなど消費税節税対策を加味した
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。


(注意)
一定の場合には、簡易課税制度の届出を提出しても適用ができない場合もあります。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#簡易課税試算 #簡易課税シミュレーション
固定資産税・償却資産税の申告書作成代行 (17/11/28)
固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する税金です。
ただし、東京都23区においては、特例で都が課税することになっています。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。
この償却資産税という税金について名前はあまり聞き馴染みのないですが、
固定資産税といえば聞いたことがある方も多いと思います。
固定資産税は、土地や建物についてかかる税金で、役所が税金を計算して納付書を送ってきます。
償却資産税は固定資産税の一部ですが
<違い1> 土地及び家屋以外の事業用資産で、
10万円以上のPCや機械などの固定資産に対してかかる税金です。
<違い2>1月1日現在所有している償却資産を、
その年の1月31日までに資産が所在する区にある都税事務所に申告する必要がございます。
固定資産税・償却資産税の対象になる資産
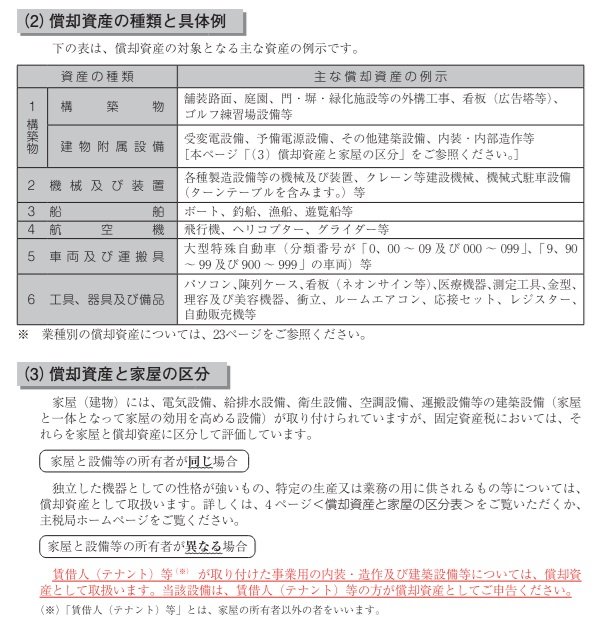
原則として、10万円以上の資産は税金の対象になります。
しかし償却資産税の申告でポイントになるのは、
一括償却資産(20万円未満の資産について3年間で1/3ずつを償却するというもの) を選択した10万円超の資産は償却資産税の対象にはならないということです。
一方で、30万円未満の少額資産の償却の特例を用いた場合には、
この償却資産税の対象になってしまうということです。
赤字の会社でも、償却資産税はかかりますので、
この償却資産税も含めて一括償却を選択するのか、
少額減価償却資産の特例を使うのかなど減価償却方法を考えることも重要です。
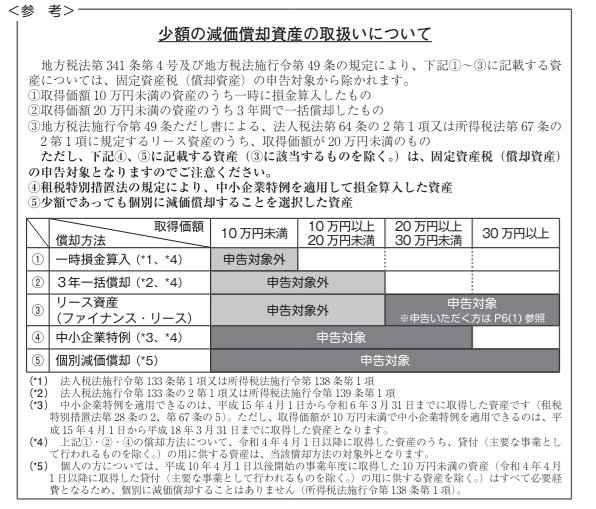
償却資産税では特にこの間違いが意外に多いのでご注意ください。
【 間違いの多い論点 】
次の資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません。1 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの
2 無形固定資産(例:アプリケーションやソフトウエア、特許権、実用新案権等)
3 繰延資産(開業費や創立費など)
4 平成20年4月1日以降のリース契約(所有権移転外リース及び所有権移転リース資産で取得価額が20万円未満のもの)
償却資産税の税率は? 税額の計算方法
償却資産税は有している財産の課税標準(わかりやすくすると財産の価値)に1.4%を乗じて計算します。
【償却資産税の計算式】【 課税標準額(1,000円未満切り捨て) × 税率(100分の1.4) = 税額(100円未満切り捨て) 】
なお、課税標準額が150万円未満の場合は、免税点以下となりますので課税されません。
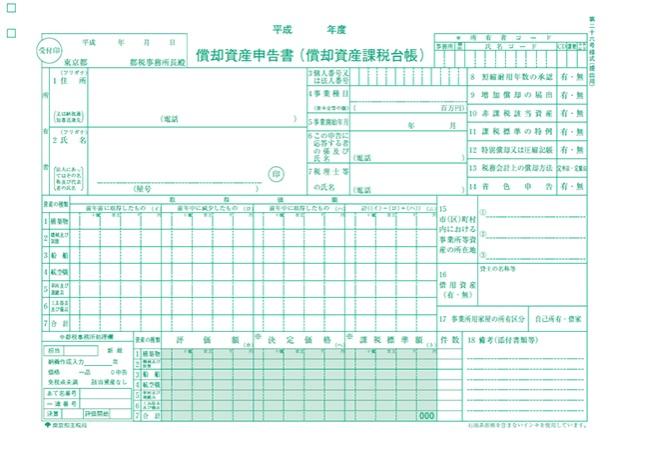
上のような用紙が年末になると、償却資産申告書の申告先の各都道府県から送られてきます。
この償却資産税の申告書が送られてこない場合には以下のケースが想定されます。
考えられる理由としましては、
1 免税点以下(課税標準が150万円未満は課税されません) 2 新規の設立で過去に申告がないこの2つが申告書が送られてこない主な理由です。
1については、税額が発生しませんので、特段問題はないのですが、
新規に株式会社や合同会社を会社設立した場合で、償却資産税の納付申告をしなければならないのに
これらの申告納付をしていなければ、罰則規定もございますので注意が必要です。
償却資産税の申告に関する罰則規定は
申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、
地方税法第353条及び第 408条に基づいて電話でのお問い合わせや資料提供の依頼、実地調査も行われます。
また、地方税法第354条の2に基づき、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行うことがあり、
上記の調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、申告内容の修正も求められる場合がございます。
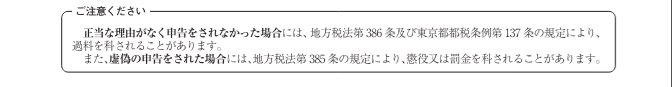
匠税理士事務所の償却資産税の申告書作成代行
匠税理士事務所では品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に
償却資産税の申告書作成の代行を承っております。
詳細につきましては、お問い合わせフォームから、お問い合わせください。
起業や開業に必要なお金の確保と資金調達先にはどこがあるか (17/11/21)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
第15回 匠税理士事務所の起業情報館をご覧頂きありがとうございます。
弊所は、世田谷区、品川区や目黒区を中心に会社設立や創業融資など起業支援に注力する会計事務所です。
今回は起業の中でも特に重要な資金調達についてまとめてみました。
起業時や開業時の大きな問題の一つとして、
起業や開業するために必要なお金をどのようにして用意するかが挙げられます。
なぜ重要かというと、赤字でも会社は潰れませんが、
お金がなくなると会社は営業ができなくなり、潰れてしまうからです。
そのため、資金の確保はとても重要なことになります。

起業や開業に必要なお金の確保と資金調達先
多くの人は自分のお金(自己資金)と誰かに出してもらったお金を
合わせて起業・開業するときの資本としています。
資金調達とは、事業を始めるのに必要なお金のうち
自己資金では足りない部分を誰かに出してもらうことをいいます。
経営者にとって会社継続のためのお金を確保し続けるということは、
得意先や仕入先をみつけることと同じように非常に重要な仕事となり、
自分の会社のお金の状況に常に気を配る必要があります。
資金調達先の種類
一般的な資金調達の方法として、
【 1 出資 】
【 2 融資 】
【 3 助成金・補助金】 があります。
経営者は会社の状況に応じて最善の資金調達の方法を検討する必要があります。
資金調達方法ごとの特徴について
①出資形式の資金調達の特徴
会社設立前に入金されます。返済義務はなく、利益がある場合だけ配当金を支払います。
経営へはお金を出す割合に応じて決定権を持ちますが、出資を獲得するのは難易度が高いといえます。
やはり自分の会社の株式をだれか他人が買ってくれるというのは難しいことです。
②融資による資金調達
一般的には会社設立後に入金されますが、設立前の場合もあります。
返済期日に返済する必要があり、利益が無くても必ず利息を支払う必要があります。
経営に口出しをされることは無く、比較的簡単に資金を獲得することができます。
③助成金・補助金による資金調達
助成金は、国などが決めた受給要件に満たしている場合は、
原則だれでも受け取ることが出来るお金です。
イメージとしては、他社との比較ではなく要件をクリアするば、比較的受給しやすいものになります。
例えばパートスタッフを正社員に転換した場合にもらえる助成金などがこれに当たります。
一方で補助金は、申請を出しても受け取れない場合があります。
補助金は多くの会社の中から審査を受けて、一部の受け取れる会社が受給できるというように
限りがあるということです。こちらは助成金に比べると確率は下がりがちになります。
また補助金は会社設立後に対象となる経費を支払った後で入金される場合が多いようです。
助成金や補助金の両社ともに返済義務はなく、利息や配当金を支払う必要もありません。
経営に口出しをされることもありませんが、融資に比べると獲得の難易度は高くなります。
起業の際の資金調達としては、経営に口出しをされずに、スピード感が重要ですので、 融資や助成金といった資金調達をお勧めします。
匠税理士事務所の会社設立や創業融資など起業支援サービス
匠税理士事務所では目黒や世田谷、品川を中心に会社設立の代行や会社設立後の経営支援を行っています。
会社設立は、初回にお客様と打ち合わせをさせて頂きまして、社長様のビジョンを伺った上で、
株主構成や役員構成はどのようにしたらよいか、
資本金や決算月はどうしたらよいか など税理士と社長様が一緒になって会社を作っていきます。
会社設立後の経理の代行や経営支援も承っておりますので、
安心して本業に集中して頂けるように努めております。匠税理士事務所の会社設立サービスの詳細につきましては、こちらからご確認をお願いします。
【 → 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立 】は匠税理士事務所
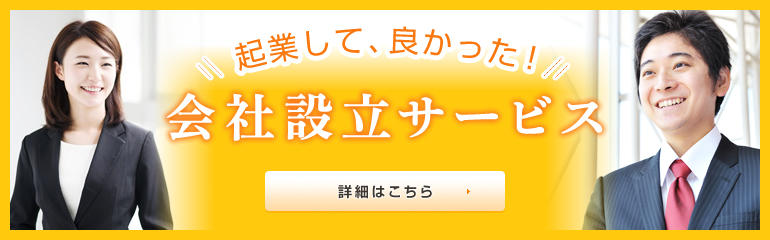
日本政策金融公庫や各種金融機関と連携した創業融資
会社設立後に必ず検討しておきたいのが、
日本政策金融公庫の創業融資や各地自治体と連携した制度融資です。
決算が完了するまでは、これまでの社長個人の実績(自己資金や経歴)とこれからのビジョン(創業計画)に基づいて融資が行われますので、比較的資金調達がしやすいという特徴があります。創業時の資金調達先である日本政策金融公庫の創業融資では、
世田谷区や目黒区、品川区のエリアを管轄されている品川区の日本政策金融公庫の五反田支店様と連携し、
創業融資の獲得をサポート致しております。
また、世田谷区や目黒区、品川区などで起業される場合に各地自治体の制度融資につきましても、
城南信用金庫様や西武信用金庫様、その他金融機関様と連携して対応致しております。
ご要望の場合には、法人口座開設もサポート致しております。
匠税理士事務所の創業融資支援サービスにつきましては、こちらからご確認をお願いします。
【 → 目黒区や品川区、世田谷区の創業融資や起業の資金調達は匠税理士事務所 】

助成金に特化した社会保険労務士のコンサルティングサービス
助成金は要件を満たせば、どの会社にも受給のチャンスがあります。
そこで弊所では助成金に特化した社会保険労務士が、お客様の状況をヒアリングし、
条件に該当するか否かの判断を行い、受給確率が高い助成金については手続きを代行致しております。
成功報酬の形式となっておりますので、お客様にはリスクが残らないというのが特徴です。
助成金支援に関するサービスにつきましては、こちらからご確認をお願いします。

上記以外のサービスラインや所属税理士などにつきましては、
こちらよりTOPへ移動の上、ご確認をお願いします。
支払調書など法定調書の作成代行 (17/11/15)
毎年1月末は法定調書の提出期限になりますので、
年末に近づくと税務署から支払調書など法定調書が送られてきます。
そこで今回は支払調書など法定調書についてまとめてみました。(こんな感じです↓)
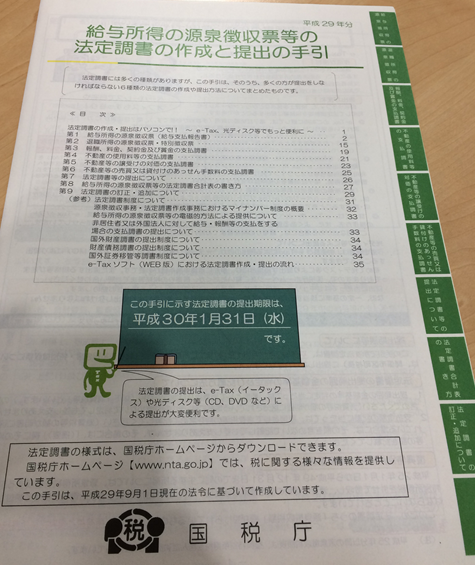
支払調書・法定調書とは何か
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る
調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいいます。
主な法定調書を作成して提出する義務がある者は、大きく分けて6つの次のとおりです。
1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、
俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。
こちらの調書を作成するためには、年末調整が重要となります。詳細につきましては、こちらからご確認下さい。
【 → 年末調整とは?年調のやり方や源泉徴収票の作成方法と作成代行 】
2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、
役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を
提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。
3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、
外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。
4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人。
5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。
上記6つがありますが、一般的に会社を経営をされている方で、提出が必要なのは、
【 上記1の給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書 】と【 上記3の報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 】です。
なぜなら、どの会社も給与は支払いますし、税理士など個人の事業主に報酬を支払う場合が多いからです。
逆に退職金や不動産の譲渡などはあまり通常の取引では出てこない場合の方が多いです。

支払調書など法定調書を提出しないとどうなるか
上記の法定調書の提出期限は、例外的な場合を除き、その年の翌年1月31日となっており、
また、その提出先は、「給与支払報告書」及び「特別徴収票」を除き、支払事務を取り扱う事務所、
事業所等の所在地を所轄する税務署となります。
一般的な会社では1と3を主に見受けます。これも税務署に提出すべき大事な書類で、
年末調整と同様にしっかりと提出しないと罰則規定がありますので注意しましょう。
匠税理士事務所の支払調書や法定調書作成代行サービス
匠税理士事務所では、年末調整から各種支払調書及び法定調書の作成代行を承っております。
お客様には社員さんごとの毎月の給与のデータを頂ければ、各書類の作成代行を承っております。
ご要望の会社様には、タイムカードから給与計算の代行も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
税務書類の作成や税務コンサルティング・給与計算の代行を担当する税理士や社労士など専門家につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の事務所概要 】

年末調整や法定調書以外のサービスラインや各種料金につきましては、
こちらよりご確認をお願い申し上げます。
【 → 目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ 】
各種許認可申請はなぜ必要か。認可の必要性と役割とは (17/11/07)
匠税理士事務所のWEBサイトへご来訪ありがとうございます。
弊所は、品川区や目黒区、世田谷区を中心に起業支援や経営支援を行う会計事務所です。
これから起業をお考えの方にとって、生命線ともいえるのが、許認可申請。
なぜなら、この許認可申請がなければ事業自体が始められなかったり、
創業融資の際に思わぬ急ブレーキということにもなりかねないからです。
そこで今回は、各種許認可申請はなぜ必要か。認可の必要性と役割についてまとめてみました。
【 許認可の必要性と役割 】許認可は私たちが身近に利用している飲食店、理容・美容関係、運送業、福祉施設などを
営業するためには全て必要となります。
起業する際は自身のビジネスに許認可が必要かを確認し、必要であれば手続きを行う必要があります。

許認可はなぜ必要?その必要性とは
許認可とは、ある一定のレベルに達した者にしか与えないことにより、
国民の安全や健康を守ることを目的としています。
そのため、許認可を受けることにより社会的な信用が増し、安心して営業をすることが可能となります。
許認可を取らずに営業を開始した場合、取引先の信用が得られないばかりか、
取引自体が出来なくなるリスクを抱えることになるため注意が必要です。
許認可の役割許認可には私たちが安心して暮らし、様々なサービスを受けられるように存在する規制としての役割があります。
もし許認可を得ずに強行に営業を開始した場合、罰則を受ける可能性があります。
本来受けるべき許認可を受けていないことが発覚した場合には、
その許認可の権限を持つ行政庁から指導が入ります。
そして結局は本来の手続きを行わなければならなくなりますし、併せて罰則も受けなくてはなりません。
規制としての許認可、どんな種類があるのか
許認可には規制としての役割がありますが、そのレベルも3種類あります。
①届出:弱い規制一定の条件さえ満たせばほぼ確実に受理される簡単な手続きのグループです。
事業を行政庁に知らせるもので、行政庁は原則として記載事項を確認し、受理するにとどまります。
例えば美容室やクリーニング店・まつ毛エクステサロンなどは営業許可以外に「届出」をする必要があります。
届出・提出・報告・申告などがこれに該当します。 ②認定:中間の規制
行政機関による一定の基準をクリアしているか否かの審査を受けたあと、
クリアしていた場合に「証明書」を交付するというものです。
例えば、賃貸住宅管理業や旅行業は「登録」が必要になります。
認定・審査・登録などがこれに該当します。
一般的には禁止であることを特定の場合に解除する場合や、特定の権利を設定する行為です。
これらの許認可手続きは、行政手続きの専門家である行政書士に依頼されることがほとんどです。
例えば、一定規模以上の建設業や運送業には「許可」が必要です。
許可・認可・免許・指定などがこれに該当します。
上記は ③許可 > ②認定 > ①届出 の順で規制が厳しくなり、許認可を受けることが難しくなります。

許認可・届出等の手続きの依頼先
安心して事業を運営するためには、
これから開始する事業についてどこで何をすればすべての許認可を得られるかを確認するのが重要です。
数多くの許認可が存在するということは、それだけ多くの規制が存在するということですので、
許認可を理解するためには根拠としている法律や法令を知ることが大切です。
以下に各許認可に対する簡単なイメージをまとめます。 ①届出が必要な場合
規制が比較的弱い届出等であれば、リスクもそれほど高くありません。
管轄の行政庁窓口に直接聞きに行ったり、自身で手続きすることも可能でしょう。 ②許可が必要な場合
許可は強い規制のため、申請書類が煩雑で時間がかかることが多いです。
そのため、時間的なコストを削減したり、専門家だけが知りえるような情報を活用するためにも、
専門家に依頼すると良いでしょう。
③許認可が必要か不明な場合事業を開始するにあたり許認可の要否が不明な場合は、
その分野に専門特化している専門家に依頼するのが良いでしょう。
許認可が必要な代表的な業種はどんな種類
各種許認可例と関連行政庁、関連法律は以下の通りです。
凡例)業種:許認可の種類、関係省庁、関連法律
①飲食店:飲食店営業許可、厚生労働省関係(保健所)、食品衛生法
②理髪店・美容店:開設届出、都道府県知事(保健所設置市については市長、東京都は特別区長)、理容師法・美容師法
③建設業・大工:建設業許可、国土交通省(土木事務所)、建設業法
④リサイクルショップ:古物商の許可、公安委員会(警察署の生活安全課)、古物営業法
⑤化粧品販売:化粧品・医療品製造販売業許可、厚生労働省関係、医薬品医療機器等法
⑥自動車解体業:自動車解体業許可、経済産業省(都道府県知事)、自動車リサイクル法
⑦ゴミの収集運搬:一般廃棄物収集運搬業許可、環境省、廃棄物の処理及び清掃に関する法律
⑧キャバクラ・ダンスホール:風俗営業の許可、都道府県公安委員会、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律
⑨探偵:探偵業届出、公安委員会(警察署の生活安全課)、探偵業の業務適正化に関する法律

匠税理士事務所の許認可申請代行サービス
弊所では、許認可申請の専門家である行政書士と連携しており、
建設業の許認可申請や廃棄物の許認可申請など各種申請の代行を承っております。
【 お客様が本業に集中できる環境づくり 】を目指して、各分野の専門家が、 許認可申請のためにコンサルティングや書類作成の代行を行います。対応エリアは世田谷や目黒、品川など東京都23区全域となりますので、
お気軽にご相談下さい。
建築業や建設業許可申請の代行サービスの詳細はこちらからご確認をお願いします。
匠税理士事務所の税理士や提携の専門家の詳細などにつきましては、
こちらからご確認をお願いします。

許可申請以外の会社設立や創業融資、経営支援など各種サービスラインにつきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
新規得意先としていい会社の見抜き方・調べ方 (17/10/31)
匠税理士事務所のホームページにご来訪ありがとうございます。
弊所は世田谷区や目黒区、品川区を中心に起業支援や経営支援に力を入れている会計事務所です。
今回は起業支援や経営支援の中で、経営者の方から頂くご相談である
【 新規得意先としていい会社の見抜き方 】 についてまとめてみました。
企業の経営者の方を悩ます事項の一つとして、得意先への貸倒があります。
貸倒とは、貸したお金が返ってこないということもありますが、多くは売上代金の回収不能です。100円のものを150円で売って本来50円の利益が出るはずが、代金が回収できなければ、
100円の商品をあげたのと同じということになってしまいます。
このような事態を避けるためにも、得意先として新たに契約をする場合に、新規得意先としていい会社かを
見抜くことは極めて重要なことです。そこで決算書を活用したその調べ方をまとめてみました。

トラブルに対応できる企業か、いい会社かは決算書から確認できる
貸倒がおこるのは、相手の会社に払う意思がないか 又は 会社にお金がないかです。
払う意思がない場合には、法律を活用したアプローチで回収は可能ですが、お金がない場合には、
中々難しいのが現状です。つまり相手先の資金状況を決算書で見抜ければリスクは大きく下がるわけです。
借入金の返済や突然の大きな支出などに耐えることが出来る安全な企業かどうかを確認するには、
その企業がすぐに動かせるキャッシュをどれだけ持っているのかを調べる必要があります。
すぐに動かせる現預金が多ければ、突然の支出や借入金の返済に対応することができるので、
その企業は安全性が高いといえます。
現在手元にあるお金でどれだけの安全性が見込めるのかを考えるために、
月の売上高に対してどれだけ現預金を持っているのかを比較する方法があります。
【 会社の安全性の具体的な計算方法 】
現預金と月の売上(平均月商)の割合は以下の方法で計算します。
手元にある現預金での安全性の求め方=現預金÷平均月商(売上高÷12)【例】:
①現預金50,000円、年間売上高600,000円の場合
→50,000÷(600,000÷12)=1
②現預金200,000円、年間売上高600,000円の場合
→200,000÷(600,000÷12)=4
上記の場合、①の企業は月商の1か月分、②の企業は月商の4か月分の現預金があるということになり
企業の安全性は②の方が高くなります。
会社の場合、現預金以外にも売掛金など比較的すぐに現金化できる資産があることが多いので、
現預金が1か月分だからといってすぐに問題が出るということではありませんが
安全性の判断の目安として、大体2か月分程度となります。

負債と比較した安全性を調べる方法
安全性を考えるうえで、平均月商と比較する方法の他に負債と比較する方法があります。
この方法では現預金が負債や借入金と比較してどれだけ有るのかを確認します。
例えば、借入金を超える額の現預金を持っている会社があるとします。
この会社は借入金を現金で返済したとしてもまだ残るため、
いつでも借入金の全額を返済できる状態にあることから実質無借金となり、
安全度は高い会社と判断できます。
間近な危機を決算書から予測する
会社の安全性を把握するために、流動資産(大体1年以内に現金化する資産)及び当座資産と流動負債(大体1年以内に支払いが求められる資産)を比べる方法があります。
【 流動比率の計算方法 】
流動比率=流動資産÷流動負債
流動比率が1以上であれば、流動資産が流動負債を超えることになり、比較的安全性の高い企業となります。
【 当座資産とは 】
流動資産のうち、より換金性が高い資産をいいます。
流動資産が1年以内に換金可能な資産に対し、現金預金・売掛金・有価証券などより短期間で換金できるものとなり、
以下の算式で求めます。
当座資産=現金預金+売上債権(受取手形・売掛金)+有価証券(上場有価証券)
【 当座比率の計算方法 】
当座比率=当座資産÷流動負債
当座比率が1以上であれば、当座資産が流動負債を超えることとなり安全性に問題がない企業といえます。
負債の償還年数から安全性を判断する
借入金などの有利子負債の支払能力が会社の将来を左右します。
そこで有利子負債の多少を確認したうえで、有利子負債償還年数を用いて検討していきます。
有利子負債償還年数を確認することで、負債の金額が年間の本業である事業で稼いだお金と比較し、
何年で返せる負債なのかを確認することができます。
1年間で稼ぐお金の金額が、1年以内に返済を求められる有利子負債の金額を下回る場合、
借入金を返済するためにまた借入をする必要がでてくる可能性があるため注意が必要です。
【 有利子負債償還年数の求め方 】
有利子負債償還年数=有利子負債(※)÷営業キャッシュ・フロー
※有利子負債=借入金+社債+リース債務
◇関連記事

どの方法がいい会社か調べるのによい方法なのか
上記で新規得意先としていい会社か否かを見抜く方法や調べ方を幾つか記載しましたが、
どの方法にも長所や短所があります。
できるだけリスクを下げたいという方は上記の全ての方法で検証するが良いでしょうし、
確認という程度で検証したいという場合には、
上記の中でキャッシュフロー計算書を用いない方法が簡単に行えると思います。
◇関連記事
【 関連記事:BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 】
匠税理士事務所の経営支援サービス
弊所では世田谷や目黒、品川で会計のアウトソーシングや給与計算などのアウトソーシングサービスを
はじめとして、会社経営者の方がより良い判断ができるような経営支援サービスをご提供致しております。
匠税理士事務所のサービスは、こちらよりご確認いただけますと幸いです。
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
◇経営お役立ち情報

契約書とは何か?その書き方や作り方、効果とは (17/10/24)
匠税理士事務所のホームページへのご訪問ありがとうございます。
弊所は、世田谷区や目黒区、品川区などを中心に、
会社設立などの起業支援や中小企業の経営支援に力を入れている会計事務所です。
起業してかれから事業をはじめるとき、既に会社を経営されている方の両方で大事なのは、契約書です。
契約書に基づいて請求書が発行され、お金のやり取りが行われ、領収書が発行されるというように、 契約書は全ての取引の軸となり、起源となる書類です。今回はこの契約書とは何か?その書き方や作り方、効果についてまとめてみました。

契約や契約書とはそもそも何か
契約とは、当事者が交わす約束事(意思表示の合致)のことです。
契約は口頭の合意によっても成立しますので、契約書が無かったとしても契約自体は成り立ちます。
しかし後で契約自体があったのか、契約内容がどのようなものであったかという点について
トラブルが起きた場合に契約書の存在が非常に重要となります。
契約書の書き方や作り方
契約書をだれが作成するかについては、契約の当事者間の力関係や慣習などにより色々なパターンが考えられますが、
大きくは下記の2つのパターンに分類されます。
①自社が作成する場合 ②相手が作成する場合契約は相手があることですので、自社で作成ができたからといって必ず自社の意見のみが
反映されるものではありませんが、基本的には自社で作成するほうが有利な場合が多いです。
契約書の提案を受ける場合(相手が作成する場合)は、
自社に不利な規定が無いか細心の注意を払って検討する必要があります。
インターネット上から契約書をダウンロードするデメリット
契約書の果たす重要な効果・役割は
①自社のビジネスをうまく進めること ②トラブルの発生時に最大の武器として使用することの2点です。すなわち契約書を作成する必要があるビジネスの目的に、
その契約書の内容が合致しているかが非常に重要となります。
近年はインターネット上で様々な契約書のひな型が公開されています。
しかし、上記の契約書はトラブルを想定して作成されたものでは無いものが多く存在します。
また契約書作成上で必須の項目が抜けていたり、違法な内容を含んでいる場合もあります。
弁護士が自身の責任で公開している場合や、有名な事例に使用された契約書など、
法律的には全く問題ない内容の例もありますが、必ずしもそれらの文例が自社のビジネスに合致しているとは限りません。
インターネット上から借りてきた契約書では、大事な部分が欠落しており、
トラブル発生時に役に立たない場合も考えられますので注意が必要です。
弁護士に契約書作成を依頼するメリットや効果とは
契約書の意義は、トラブル発生時に最大の武器としての効果を発揮することにあります。
弁護士に依頼することにより、トラブルや訴訟になった場合に
作成した契約書を武器にしてどのように戦ったら良いかについてのアドバイスを
受けながら契約書を作成できることは、大きなメリットになります。
また、作成を依頼した弁護士を顧問弁護士としたり、
その契約書によって生じたトラブルの解決を依頼する場合には、
その契約書の作成を行った弁護士が自身で作成した契約書を武器に戦ってくれるため、
充実したアフターフォローを期待することができます。
弁護士を最大限に利用可能することが可能になる効果
法律や裁判例に関する知識と経験を豊富に有し、
日本で唯一全ての法律問題を扱えるのが弁護士です。
時代とともに変化していく法律や裁判における解釈に対し、
日々様々な法律の解釈を調査して、裁判においてどのような理由で勝利しているかを研究している専門家です。
弁護士の法的知識は特に新規性の高いビジネスにおいて効果が見込まれますので、
契約書の作成を法律の専門家に依頼することで弁護士の法的知能を最大限に利用可能といえます。
匠税理士事務所の提携しております弁護士などの専門家の詳細はこちらからご確認をお願いします。
【 → 目黒区自由が丘の匠税理士事務所 】

自社の事業内容に合致した契約書を作成することの効果
契約書の作成を弁護士に依頼することで、インターネット等の文例集にはない大きなメリットがあります。
弁護士は依頼を受けると、まずはその会社の事業内容等の詳細をヒアリングします。
そのうえで、今回の契約書の内容・性質・契約書作成の目的を詳細に検討して、
その事業の目的に合った契約書を作成します。
この契約書はオーダーメイドで作成され、定型的なひな型をそのまま利用するということはまずありません。
さらに、トラブルが起きた際の対処方法なども一緒に検討していけるので安心感があります。
契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービス
匠税理士事務所では、提携の弁護士と連携することで、
お客様のニーズ・問題点に合わせた契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービスをご提供しております。
契約書の作成やレビューなど法務サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
【 → 契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービス 】
対応エリア:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区

契約書の作成やレビューなど法務以外の税務や会計などのサービスラインにつきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 世田谷や目黒、品川の税理士は匠税理士事務所 】
会社の借入金はどれ位がいい?返済力を測るには (17/10/17)
会社がつぶれてしまう一番の要因は、
借入金を返せなくなることにあります。
会社の安全性は、単に借入金の大きさでなく、
儲ける力と比較し、借入がどの位かで判断します。
借入返済力の計算方法 【分かりやすい簡易式】
借入金 ÷ 営業活動キャッシュフロー = 借入返済能力

借入金返済の軸! 営業活動キャッシュフローとは
借入金の返済の判断の軸となるものは、
損益計算書の利益の金額ではなく、
実際お稼いだおカネの金額ですので損益計算書上の利益に減価償却費を加算します。
(購入時に出たお金の按分で経費化の際、支出無し)
そして収益の中に、損益計算書の計上額と、
実際やり取りしたお金と差を加減します。
貸借対照表上の売掛金や棚卸資産の減少は、
おカネがその分回収されたので、
キャッシュフロー計算(CF)はプラスになります。また、売上を上げて売掛金を計上することは、
お金が入ってきてませんからCFでマイナスです。
負債は逆で、負債が増加するということは、
おカネを払わずにすんだということでCFプラス、
負債の減少はおカネを支払うのでマイナスします。
このようにお金を中心の考え方(キャッシュフロー)を軸に
上記の計算式で考えてみた結果が、 借入金の返済に要する年数です。【 関連記事 : BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 】
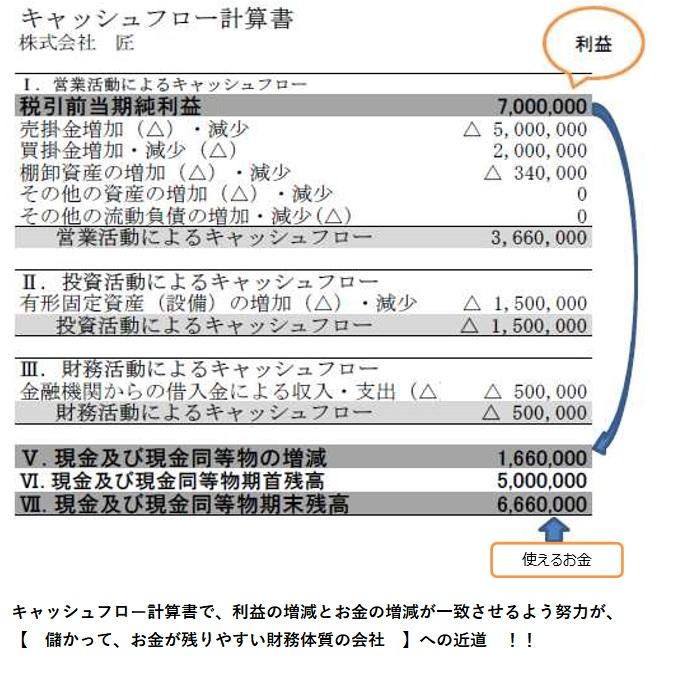
借入金の返済能力と金融機関の融資
【返済年数を基に区分すると以下のになります。】
3年未満・・安全上問題ない
4年以上10年未満・・問題ないが、やや借入金は多い
10年以上・・稼ぎと比較し借入過大、安全上問題あり
このように判断されることが一般的です。
借入金の返済年数からみてみると上記の算式で
借入を返済する力を簡単に区分しましたが、
金融機関の考え方もおおむね同じようです。
実際の融資コンサルティングの現場でも
運転資金は長くても5年ですし、 設備では7年位の返済期間が一般的です。メガバンクは更に返済期間が短くなる傾向です。

目黒区自由が丘の匠税理士事務所の経営支援
弊所では各種機関で経営セミナー講師を務めるなど
【お客様の会社に利益とお金を残すこと】に力を入れる税理士事務所です。
利益とお金を残すためには、利益が出る仕組み
お金がたまる仕組みがとても重要で、
実現できた後は、効果的な節税を提案致します。
融資などの資金調達では世界4大会計事務所出身が
計画書作成をサポートしております。
お客様のご協力のおかげ成功率9割超なってます。
◇起業のお客様 創業融資支援サービス
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
株式会社や合同会社などを作るための
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
会社の借入金はどれ位がいいか、
返済力を税理士が一緒になって検討する
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
会計経理や決算確定申告の代行など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で起業創業して会社にするための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
【 税理士の対応地域 :世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域 】
執筆者・文責 税理士 水野智史
#会社の借入金 #返済力
外国人の方が起業や日本で勤務する就労ビザ・VISA取得代行 (17/10/11)
日本で働きたい・日本で生活したいなど外国人の方が起業や日本で勤務するためには、
就労ビザ・VISAなどを取得する必要がございます。
特にITやデザイン・プログラミングなどは、海外の方から技術的に学ぶことが多いなど
外国の方を採用・求人されている日本の企業や会社様は増加傾向にあります。
外国人の方を採用する場合・求人を行う場合に、
採用人事担当の方が確認しておきたいのは、
外国人の方を採用する場合には、
外国人の求職者の方が自社で、就労できる状態なのか否かを予測した上で
検討をしなければならないということです。
これを見誤ると採用・選考の時間・費用が無駄になるというケースも出てくるというわけです。
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に
海外の方・外国人の方が、起業する場合や日本で勤務する場合に必要なビザ・VISAの取得代行に対応できるよう
就労ビザなどの取得や永住権・帰化申請などの分野に特化している行政書士と提携しております。

日本で起業・働くために必要なビザ・VISAの取得代行
日本で会社設立をして起業したり、企業で働くためにはビザ・VISAの取得が必要になります。
外国の方が日本で起業したい場合や、これから外国人の方を採用・求人したい場合には、
以下の流れでビザ・VISAの取得代行をサポート致します。
1 ビザ・VISAの取得代行に対応した専門の行政書士と打ち合わせ
2 上記の打ち合わせで必要事項の確認後、必要書類を用意
3 申請
4 取得 OR 再申請
5 再申請の場合には、何が問題だったのかを検証の上、再対応
このような流れで、就労ビザ・VISAの取得が進んで行きます。
提携専門家である行政書士は、これまで世界4大グローバルファームでの勤務経験や、 一部上場企業での法務部での勤務経験や入国管理局届出・申請取次行政書士などの高度な専門性 海外駐在も致しておりましたため、外国人の方とのコミュニケーション能力も有しております。
外国人の方のビザ申請も行っている事務所もございますが、
外国の方の在留ビザ申請のみを専門的に行う行政書士は少ないということもあり、
事務所としてビザ申請に特化し、多くの実績と豊富なノウハウがあることが強みでもあります。

就労ビザ・VISA取得のための料金・報酬
就労ビザの取得等は、提携の国際行政書士事務所での対応となります。
【 対応エリア:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区 】
就労ビザ・VISA取得のための料金
料金・報酬の目安につきましては、6万円~となります。
こちらはご依頼頂きましたお仕事の難易度やボリュームを勘案しての個別見積もりとなります。
※ 具体的な金額は、ご依頼の案件をお聞きした上で、ご契約時に個別に合意した料金となります。
※ ビザ申請が不許可になった場合には、お預かりした報酬は原則返金致します。
ただし、お客様事由による不許可や、取下げの場合は除きます。
また、業務に関連して発生した経費はご返金致しかねますのでご了承ください。
※ 受託業務に関して発生した交通費等諸経費は原則として業務報酬に含まれますが、
出張・宿泊が必要となった際は実費精算となります。
就労ビザ以外にもこれらに付随する帰化申請や永住権取得などにも対応しております。
こちらは下記の料金・報酬目安をご参照下さい。

帰化申請・日本国籍の取得支援サービス
外国人の方が日本国籍を取得することを帰化といいます。
国籍法に規定された一定の要件及び日本語能力を満たす外国人は、
帰化申請により日本に帰化することが出来ます。
帰化申請から許可まで約1年程かかりますが、
こちらは必要書類の量が多くかつご本人にとっても、重要な事項ですので
こちらの分野に詳しい行政書士が対応致します。
帰化申請・日本国籍の取得支援サービスの料金
料金・報酬の目安につきましては、200,000円~ 承っております。
難易度などにより最終的には 個別のお見積もりとなります。

目黒区自由が丘にある匠税理士事務所について
匠税理士事務所は、目黒区の自由が丘に2008年に設立した会計事務所となります。
事務所の特徴は、税理士やスタッフ、提携先など人の質にこだわる税理士事務所です。
人材にこだわることで、お客様へ高品質のサービスを提供したいと考えているからです。税理士や提携の専門家は、こちらからご確認をお願いします。

最終利益だけで大丈夫?PLの見方・読み方は要注意 (17/10/03)
これから新しく取引をする会社の与信調査として、
相手の会社の決算書や試算表を預かったが、
貸借対照表・BS(Balance Sheet)で相手の会社の現預金が沢山あるのもわかったし、
損益計算書・PL(Profit and Loss statement)の当期純利益をみて相手の会社が黒字なのも分かった。
それでは新たに取引を開始しましょう。
という決算書・試算表の見方や読み方は危険です。
このような読み方・見方では危険な点がいくつかかありますが、
今回はこのうち、PL(Profit and Loss statement)の特別利益・特別損益の項目についてまとめました。

損益計算書・PLにある特別利益、特別損失とは
損益計算書・PLにある特別利益、特別損失とは、滅多に生じない臨時の損益のことです。
例えば、保有する土地や建物を売却して利益を獲得したとき、
その利益は特別利益に計上します。
また、地震などの自然災害によって工場や建物に損失が生じたときは、
特別損失に計上されることになります。
東日本大震災では多くの会社が震災に見舞われましたが、この震災によって生じた損失は特別損失に計上していました。
特別利益、特別損益は経営者の意図で生まれることがあります。
利益がよくないときに、土地や有価証券を売却して特別利益を計上し、
利益を確保しようとします。
逆に当期の利益がいいときや、合法的に大きな節税対策をしたいというときに、
過去に購入した不動産などの含み損を処理して特別損失に計上することがあります。
例:土地を以前に1億円で購入したため、決算書では1億円と掲載されていたが、
実際に第三者に売却してみると5,000万円にしかならず、5,000万円の損失が発生するなど
このように損益計算書・PLにある特別利益、特別損失は、本来の事業とは関係のない損益で、 比較的金額が大きくなるものが多くあります。会社の理解をするためには、どうして特別利益、特別損失が生じたかを見ることが重要です。
こちらを正しく見ることで、この会社の経営の意図や経営状態を正しく把握することが可能となるのです。

貸借対照表・BS(Balance Sheet)やPL(Profit and Loss statement)は重要
貸借対照表・BS(Balance Sheet)やPL(Profit and Loss statement)など決算書や試算表を
正しく読めることはとても重要なことです。
新規の得意先の与信調査でも有効ですし、自社の経営の強みと弱みを正しく知ることができます。
BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方などにつきましては、
こちらの記事にまとめておりますのでお気軽にご確認をお願いします。
【 → BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 】
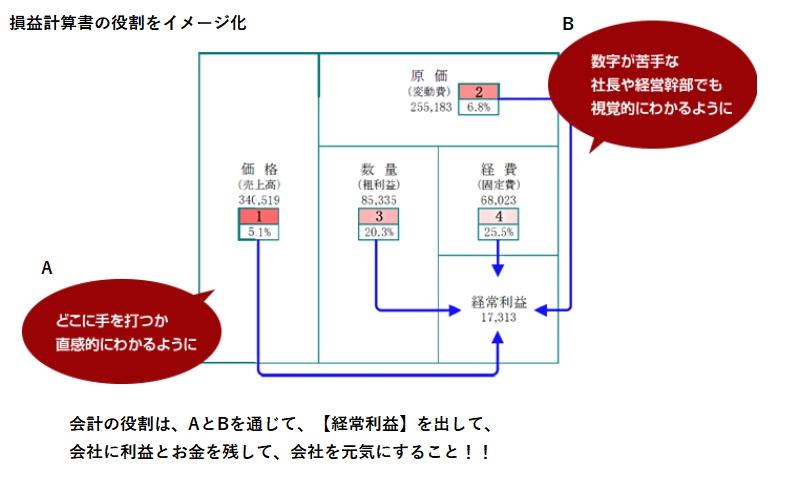
匠税理士事務所の経営支援サービス
匠税理士事務所は、お客様の会社の経営状態と適切に分析し、
経営アドバイスを行うコンサルティングサービスもご提供している会計事務所です。
・これまで何となく感覚で経営をしてきたが、数字に基づいた経営を行いたい。
・試算表や決算書は税務署への税務申告にしか利用できていないので有効活用したい
・金融機関から融資を受けたいが自社の格付けが気になる
このようなお悩みをお持ちの経営者の方のお役に立てるサービスをご用意致しております。
法人経営者向けのサービス内容はこちらよりご確認をお願いします。
【 税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域 】
上記経営支援サービス以外のサービスラインナップや所属税理士、料金や会計事務所までのアクセスなどの事務所に関する詳細な情報につきましては、こちらよりTOPページへ移動の上で、匠税理士事務所の事務所概要をご確認ください。
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
目黒区自由が丘の匠税理士事務所
期末棚卸しとは? 月末在庫管理は利益や売上原価の計算で重要 (17/09/26)
多くの事業で売上がありこれに対する原価として
売上原価があります。
そしてこの売上から売上原価を差し引いた粗利で、
商売が黒字になるか赤字になるか8割が決まると
いっても過言ではありません。
【 関連記事:売上総利益率と売上高と売上総利益(粗利)の計算式・計算方法 】
しかしこの売上原価で経営者のイメージする粗利と
実際の決算書上の粗利にズレが起きます。
それは何故でしょうか?
そこで今回は期末棚卸し・在庫管理が与える
売上原価への影響を記載しました。

売上原価や期末棚卸しとは何か?その計算式
売上原価は、売上のために直接かかった費用です。
売上原価は、いつ仕入・製造されたものでも、
当期に販売されたものについてかかった費用を
計算することが重要です。
そこで次のような算式を用いて計算します。
売上原価= A期首棚卸在庫高 + B当期製品製造原価 (当期商品仕入高) - C期末棚卸在庫高
【 期首棚卸在庫高 】
期首に前期以前に製造されたり仕入たりした
製品商品で在庫となっていたもの
(つまりは前年の決算時点の在庫)
【 当期製品製造原価 】
→材料費など当期の製品製造にかかった費用
【 当期商品仕入高 】
→当期に商品を仕入れた費用
【 期末棚卸在庫高 】
→期末に販売されずに在庫の製品商品
この金額が次の期では期首棚卸高となります

棚卸し・在庫管理は売上原価に影響するか
大企業などは多くの人・商品がかかわるため
品質不良や盗難などを避けるために日々在庫を
コンピュータ管理しているのが一般的ですが、
中小企業のように社長=会社のオーナーになると
在庫管理は税務申告のため行う事が多いです。
そのためA期首棚卸在庫高=C期末棚卸在庫高なら
当期仕入分や製造した分=売上原価 となりますのでイメージと決算書があうのですが、
A期首棚卸在庫高 > C期末棚卸在庫高では、前年の在庫を今年に販売したわけですから、
こちらの分を今年の売上原価の計算では加味しなくてはなりません。

数字入れて例にしてみると
A 期首棚卸在庫高 400
B 当期商品仕入高 1,000
C 期末棚卸在庫高 100
400+1,000=1,400(前年在庫と今年仕入分)
1,400-100(決算時点在庫)=1,300
(売れた商品原価 = 売上原価)
以外にこの在庫を販売するために使った分 ( 400-100=300 )が、 頭にあるイメージの売上原価と決算書の売上原価にズレを起こしやすいので、 月末に大まかでも在庫管理を行いましょう。在庫管理をしっかりとおこなうことで、
的確な売上原価が分かるようになります。
売上原価がしっかりと分かれば、
売上総利益(粗利)が把握でき、
粗利が把握できれば利益の8割が決まりますので、
経営判断や節税対策が効果的に行えます。
このように在庫管理はとても重要です。

匠税理士事務所の経営支援サービス
匠税理士事務所では品川区や目黒区、世田谷区を
中心に経営支援を行っており
お客様の会社に利益とお金を残せるように
税理士がコンサルティングを行います。
その他にも社長が経営に集中できるように、
会計アウトソーシングや給与計算も提供しております。
所属税理士やサービスはこちらから
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
 担当税理士や提携の専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
担当税理士や提携の専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
期末棚卸・月末在庫など資金需要が多い方の
創業融資サービスはこちらから確認下さい。
【 → 税理士による創業融資 】
在庫を取り扱う業種の会社を作るための
会社設立サービスはこちらから確認下さい。
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
在庫管理などの経営支援や会計経理代行など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で独立開業して会社にする法人成りで
在庫がある業種も対応しております。
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
建設業許可申請はこちらから確認下さい。
【 関連記事: 在庫が資金繰りを圧迫している場合の経営改善 】
【 関連記事: BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 】
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
担当税理士や提携の専門家につきましては、トップページへ移動の上で会社概要からご確認をお願いします。
品川や目黒、世田谷の税理士は匠税理士事務所 ...TOPページへ
◇経営お役立ち情報
執筆者・文責 税理士 水野智史
#棚卸
#在庫
会社設立して起業する前の商標確認と検索方法<K10> (17/09/20)
匠税理士事務所のホームページにご訪問ありがとうございます。
弊所は目黒区や世田谷区、品川区を中心に会社設立など起業支援に力を入れている会計事務所です。
今回は、起業時の商標確認と検索方法についてまとめてみました。
これから会社設立をして起業をお考えの方の多くは、
素晴らしいアイデアや商品、ビジネスモデルをお持ちの方も多いと思います。
それでは後は、商品名や会社名を決めたらすぐにスタート・・・
という前に一つ考えないといけないことがあります。
それは、商標確認です。
商標とは何か?商標確認の重要性
商標(trademark:トレードマーク)とは(1)自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別するためのものです。
(例)会社のブランド、ロゴマーク、商品名、サービス名 等
(2)商品・サービスの提供者は誰か?を示すことができます。
(3)同じ商標が付された商品・サービスは、常に同じ品質を備えていることを示し、
(4)商品・サービスに好印象をもってもらい、利用者の購買意欲を刺激し、
広告宣伝として機能します。
⇒ 商標には、その商標を使用する人の「信用」が蓄積されており、
事業者にとって重要な経営資産です。
商標登録する場合とその検索方法
(1)特許庁に必要事項を記載した願書を提出します。
(郵送・持参・インターネットの利用可)
その際、商標だけでなく、出願する商標をどのような商品やサービスに使用するか明記しなければなりません。
【既に登録済み商標の調査方法は下記にまとめてあります】
(2)上記と同時に、所定の手数料を印紙で特許庁に納付します。
(割印はしません)
(3)審査後、認められると、登録査定という書類が送られてきますので、
所定の期間内に登録料を特許庁に納付します。(※1)
(4)出願した商標が特許庁に登録されます(登録商標)。
(※1)審査の上、登録できないと判断された場合
拒絶理由通知書が送られてきます。
→意見書という形で反論することができます。
また、手続補正書で願書の記載を修正することもできますが、商標を修正することはできません。
上記で反論しても認められない場合は、拒絶査定となり、登録はできません。
→さらに、拒絶査定不服審判をすることもでき、さらに審決取消訴訟という裁判で、商標登録を目指すこともできます。

効力:商標権が発生します。登録した人は、自分の登録した商標を、
出願した商品・サービスの範囲で独占的に使用でき、その効力は日本全国に及びます。
有効期限:登録の日から10年間続き、何回でも更新登録することができます。
具体例
(1)商品「事務用品」 商標「シャープペンシル」
→ 「シヤープペンシル」は、一般的な名称であり、他の商品と区別できないので認められません。
商品「飲料」 商標「シャープペンシル」
→ 「飲料」として使用される「シャープペンシル」は一般的でないため、認められる可能性があります。
(2)商品「飲食物の提供」商標「AAABBBB」(大文字)
商品「飲食物の提供」商標「aaabbbb」(小文字)
→似たような商標の為、認められません。
商標調査・検索方法にはどんな方法があるのか
特許庁が提供している無料のデータベース「特許情報プラットフォーム
J-PlatPat」を利用して、 他人の商標がないかを確認することができます。
→ 関連ページ: 特許庁の特許情報プラットフォーム J-PlatPat
匠税理士事務所の会社設立や商標登録サービス
すべての業種が商標登録の対象となります。
登録していなければ、自分の商標をマネされても文句を言うことができません。
さらに、似たような商標を登録されてしまうと、
自分が使えなくなってしまう可能性もでてきます。
自分が以前から使用していたとしても、登録が先の方が優先されます。
他人の権利を侵害しないため、自分の商標を守るためにも商標登録することをおすすめいたします。
商標登録の専門家は、弁理士となります。
弊所では、弁理士の中でもトップレベルの専門性をもつ弁理士事務所・特許事務所と提携しております。お客様の今後のビジョンに応じて、商標や特許登録などのご相談も承っております。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
合同会社・LLCの損益分配や利益の配当についてK14 (17/09/13)
損益分配とは、合同会社の事業活動により
獲得された利益が各社員に分配されるかに
関するもので、【 配布・割当 】という意味です。
実際に払い戻す【 利益の配当 】とは異なります。利益が生じた年に配当しなくても、
利益剰余金として、留保もできます。反対に、損失が生じた事業年度には、
社員がその損失補てんしなくても、
利益剰余金のマイナスとして認識できます。
利益が計上された場合は各社員の持分が増加し、 損失が計上されたら、各社員の持分が減少します。増減した社員の持分はその【社員の退社】、
または【会社の清算】の時に現実化します。

合同会社・LLCの損益分配の割合
損益分配の割合について定款に定めがない場合、
割合は各社員の出資価額に応じることとなります。
また利益又は損失一方しか割合を定めてないと、
その割合を定められていない損失または利益の分配に共通であるものと推定されます。
この分配の割合は、定款で定めることができます。
 つまり定款で損益分配割合を決められるのが、
合同会社・LLCの最大の特徴です。
つまり定款で損益分配割合を決められるのが、
合同会社・LLCの最大の特徴です。
(株式会社は、原則出資割合に基づきます)
ただし、一部の社員が損失の分配を受けない旨の
定款は有効ですが一部社員が利益を全く受けない
定めは利益を出資者である社員に分配することを
目的とする合資会社の本質に反し認められません。
合同会社・LLCの利益の配当
社員は合同会社に対し、利益配当を求められます。
合同会社は配当を請求する方法など、利益配当に
関する事項を定款で定めることができます。
出資の価額に基づかないで利益配当を行うことも、
社員間で柔軟に取り決めることができる定款自治が認められています。
利益の配当をすることはできません。
会社は社員からの利益配当請求を拒むことができ、
債権者および他の社員のいずれも害することがないようにしています。
期末に欠損額が生じたとき
利益の配当をした時点では利益が出ていても、
業績が予想外に悪く、配当日の属する年度末に
欠損額が生じたときは配当業務を執行した社員と
利益配当を受けた社員が連帯し支払義務を負うことになります。
ただし、その業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明し、
総社員同意で、支払義務は免除されます。

合同会社では定款自治が重要!
定款では、利益の配当をする時期、回数、配当する財産の種類や額など、
総社員の同意により自由に定めることができます。
これは、投資ファンドを合同会社にして活用するときになどに重要となります。
社員がいつでも利益の配当を請求できるのでは、
投資ファンド運営が困難になる恐れがあるからです。
匠税理士事務所の合同会社の会社設立支援
匠税理士事務所は、品川区や目黒区、世田谷区など
東京都の城南エリアを中心に会社設立から創業融資
助成金など起業に関する全てがそろう事務所です。
弊所では経験豊富な40代の税理士やスタッフで
構成される事務所で起業家の方と世代が近く
お客様の視点で効果的な提案をさせて頂きます。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【 →自由が丘の税理士は匠税理士事務所】

◇関連記事
◇個人の起業サービス
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】

◇会社設立サービス
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
◇法人化・法人成りサービス
【 → 東京都で税理士の法人化・法人成り】
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。
【 → 東京都の建設業許可の新規取得・申請代行】
執筆者・分析 税理士水野智史
#合同会社
#LLC
相続での遺言、気を付ける点はどこか (17/09/05)
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第6回 遺産分割協議と相続税の申告
第7回 相続税の税率と税額計算の仕組み
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所は目黒や世田谷、品川を中心に相続税申告や、
相続対策を行っている会計事務所です。
今回は相続でとても重要となる遺言についてまとめてみました。
事業承継でも重要! 遺言の意義、遺言とは何か
オーナー経営者は、会社の後継者には自社株式を中心に、
後継者以外の相続人には、自社株式以外の財産を相続させるなど、
円滑な事業継承を進めるため遺言を作成します。
遺言の作成によって、自らの遺産の配分について
自分の意思を反映させることができるのです。
また、法定相続人でない人や法人は相続権がないため、
遺産を取得することはできませんが、
遺言によりこれらの人に遺産を承継させることもできます。
ただし、遺言は民法で定める方式に従って作成される必要があり、
その方式を満たさないと無効になります。

遺言の方式にはどんな方法があるのか
一般的に「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」の二つの方式で、
遺言は作成されます。
自筆証書遺言とは
遺言書の全文と日付を全て自分で書き、氏名を自署し、押印する方法
長所)遺言の存在・内容を秘密にできる。費用がかからない。
短所)遺言の紛失、偽造、隠匿のおそれがある。無効になる遺言の不備に気付きにくい。
公正証書遺言とは
遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、
遺言者及び証人がその筆記を承認した後、各自これに署名押印する方法
長所)遺言の保管が公証役場であることで、遺言の紛失・偽造・隠匿のおそれがない。
遺言でもできないことがある
遺言の作成によって、自らの遺産の配分について
自分の意思を反映させることができるのが原則ですが、
被相続人(亡くなった方)の財産のうち、
相続人が取得できる最低限の割合が遺留分として保障されています。
これは、被相続人が第三者や特定の相続人に対して全財産を遺贈・贈与した場合に、
被相続人の財産を取得できない相続人が生じるためです。
この場合、被相続人の財産形成に相続人が協力してきたことへ配慮に欠けるという問題や、被相続人の財産を取得できなかった相続人は、生活に支障をきたすおそれがあるという問題が生じます。
このような問題を改善するために遺留分という制度があります。
遺言で全ての財産を特定の方にあげたくても、
遺留分については確保されているのです。
遺留分の詳細につきましては、
以前にこちらのページにまとめておりますので、
こちらよりご確認をお願いします。
【 関連記事 → 相続における遺留分とは、その割合や計算方法 】

匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所は、目黒区の自由が丘にある事務所で、
世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税申告・相続対策サービスを行っている会計事務所です。
相続税は亡くなってからになると節税対策の手法は、
選択肢も効果も限定的になってしまうので、
生前に相続を見越してシミュレーションを行い、
少なくても何かあったときには、遺言(大枠)が決められていて、
その遺言(フレーム)に従って遺産分割・相続税申告を行うのが効果的です。
弊所では、相続税に特化した税理士法人や会計士と提携することで、
一般的な会計事務所では対応できないような大規模案件にも対応することが可能です。
所属税理士や提携の公認会計士・弁護士などの専門家につきましては、
こちらよちトップページへ移動の上、税理士事務所概要にてご確認お願い致します。
相続税についてのご相談がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
五本木・鷹番すぐの税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (17/09/05)
匠税理士事務所HPへ訪問ありがとうございます。
弊所は五本木や鷹番など目黒区を地元に
【起業支援・経営支援】に取り組む事務所です。
【 お客様が安心して本業に集中できる 】ように
税務会計をはじめ、人事労務・法務・知的財産権や
金融機関・各種許認可申請やVISA取得など
【 事業に関連する全分野のプロフェッショナル 】と連携しお客様をサポートしております。
【 匠税理士事務所に相談すれば安心 】と言って頂けるような事務所作りを心掛けてます。
弊所税理士や五本木や鷹番エリアに対応する
提携専門家・確定申告・会計などサービス内容は、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】

五本木・鷹番の会社設立・創業融資・起業支援
五本木や鷹番で会社設立をお考えの方に向けて
会社設立・創業融資など創業相談を行ってます。
・〇月に退職し、起業をしたいので法人設立までの
スケジュールについて話がしたい
・法人設立したいが、料金サポート内容をしりたい
・決算月や株主構成、役員構成などを相談したい
・創業融資も興味あるが、制度全体を知りたい
五本木や鷹番の起業家の方のご相談を承ってます。

実際に会社設立をされる場合には、法人設立登記やその後の各種届出書作成をはじめとして、
全てお任せの経理、経営支援も行ってます。
五本木・鷹番担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

五本木や鷹番で起業される方に向けた会社設立は、こちらからご確認下さい。
【→ 目黒区の会社設立は匠税理士事務所】

日本政策金融公庫と連携した創業融資や資金調達にも対応の会計事務所です。
創業計画書作成支援から面談立ち合いサポート、
五本木や鷹番など目黒区制度融資も対応してます。
【 → 目黒区の創業融資・資金調達 】

五本木や鷹番の創業支援や法人化
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
また、個人で独立開業してから会社設立する
法人化・法人成りも承っております。
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 東京都の税理士による法人化・法人成り】
(税理士は五本木や鷹番など目黒全域対応です)
五本木や鷹番での会計経理や決算確定申告
弊所では東京商工会議所で経営セミナー講師を
担当する税理士が五本木や鷹番など目黒を中心に
コンサルティングで力を入れております。
・利益を残すためにはどのようにしたらよいか。
・利益が出ているはずが、お金がないのは何故か。
・お金が残りやすい経営体質の会社にしたい。
五本木や鷹番の法人様に対する
匠税理士事務所の経営支援サービスや、
税務会計サービスはこちらでご確認をお願いします。
また土地や不動産を売却された際の確定申告や
会計経理や決算の代行、法人化も承ってます。
会社様向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
五本木・鷹番で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

当会計事務所対応エリアは五本木や鷹番など
目黒区が中心となります。
税理士2名・税理士有資格者1名・科目合格者など
スタッフ5名の計10名の会計事務所です。
お気軽にご相談下さい。
会計事務所の求人や採用情報
弊所では随時正社員スタッフ及びパート
アルバイトスタッフ採用求人を行ってます。
欠員が出てからの募集ではなく、
既存メンバーが忙しくならないように
余裕を持った採用計画を立てるためです。
五本木や鷹番など目黒の会計事務所で
の勤務をご検討中の方は、
採用ページをご確認の上、ご応募下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
(五本木・ごほんぎ)や鷹番(たかばん)向けの
匠税理士事務所案内をご覧頂きありがとうございます。
#五本木税理士
#鷹番起業支援
深沢や中町近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (17/09/03)
ホームページにご訪問ありがとうございます。
弊所は、深沢や中町から近くの会計事務所です。
2008年に設立してから、
【起業支援】と【経営支援】の2本を軸に、 会社設立から創業融資・経営コンサルティングに力を入れてきました。
世界4大会計事務所出身の税理士が中心となり、深沢や中町など世田谷地区に強い城南信用金庫、
日本政策金融公庫などの金融機関や、
専門家の連携が充実しているのも特徴の一つです。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の税理士やサービスは、
こちらよりご確認をお願い致します。

深沢や中町で税理士の創業支援や起業支援
【起業支援】と【黒字戦略】 の一環として、
商工会議所や世田谷産業振興公社で
【起業家向け分かりやすい税務会計セミナー】から 【利益とお金を残し,いい会社を作るセミナー】など起業・経営セミナー講師も担当致しております。
幸いなことにこれまでご好評を頂いており、
これら起業支援セミナーで得たノウハウを活用し、
弊所のお客様には出来る限り分かりやすい
会計財務コンサルティングをご提供します。
深沢や中町で起業支援担当の税理士はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

起業支援対応エリア:深沢や中町など世田谷区
会社設立や創業融資など充実の起業支援
深沢や中町など世田谷での起業支援では、
株式会社や合同会社の会社設立代行から、
創業計画書の作成や融資面談の立会、
助成金の申請代行など起業家の幅広いニーズに
対応できるよう提携先の充実に力を入れています。
会社設立の経理や経営支援・税務コンサルティングも経験豊富な税理士やスタッフが多数在籍し、
【 起業に必要なすべてがそろう税理士事務所 】を作っております。
当会計事務所の深沢や中町での起業支援は、
こちらよりご確認お願い致します。
匠税理士事務所の深沢や中町で創業支援は、
こちらよりご確認お願い致します。

深沢や中町の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は深沢や中町など世田谷全域対応)
深沢や中町の経理・会計や確定申告、決算代行
税理士が会計や税務が得意なことは当然ですが、
当会計事務所では、お客様に対して
【利益とお金を残し、良い会社づくり】という理念で経営支援に力を入れております。
財務会計データを活用し、
・売上単価
・外注先や仕入単価
・販売数量
・固定費のどこに問題があるのか、
入金や出金のサイクル・在庫の保有期間の
適正化などの分析を行うことで、
会社の利益面・キャッシュフローなどの
資金面での課題と対応策をご報告致しております。
当会計事務所の経営支援や財務会計、
税務コンサルティングサービスは、
こちらよりご確認お願い致します。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
深沢や中町の方向けの確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
深沢や中町で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

深沢や中町の法人化・会社設立関連情報
深沢・中町など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
深沢や中町で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が深沢や中町で法人化・会社設立したなど
登記の際、対応する行政窓口となります。
深沢や中町近くの税理士事務所や会計事務所の求人採用
匠税理士事務所では、
「お客様の利益と社員の幸福の最大化」を使命に、
共感頂ける方を募集しております。
出来る限り社員の方の話を聞くことで、
【ここ5年間の退職者ゼロ】が最大の特徴です。今後も社員の方が働きやすく・働きがいのある
会計事務所にしていきたいと思います。
深沢・中町など世田谷区の求人や採用情報は、
こちらよりご確認をお願い致します。
深沢(ふかさわ)や中町(なかまち)など世田谷のご近所の方からのご応募をお待ちしております。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
会社設立など起業支援・創業支援や
法人化・法人成りなど会計事務所の対応は
深沢や中町の世田谷など東京都23区全域となります。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#深沢税理士
#深沢会社設立
合同会社を会社設立するときの業務執行社員とは何かK15 (17/08/30)
これから合同会社を会社設立して起業をお考えの方もいらっしゃると思います。
このとき業務執行社員 ≒ 株式会社の取締役(役員)となるわけですが、
合同会社(LLC)が一般的になってきたのは最近ですので、
今回はこの合同会社の業務執行社員についてまとめてみました。
業務執行社員の業務の執行とは何か
業務の執行とは、契約締結等の法律行為、帳簿の記入、従業員の管理、商品の管理等の事実行為が含まれます。
つまりは会社の重要な事項を決めるということを意味します。
合同会社は定款に別段の定めがない限り、合同会社の全社員が業務執行権を有します。
また、合同会社における業務執行者は社員に限られ、社員以外の者を業務執行者とすることはできません。
だたし、法人が社員となる場合は、その法人が選任した個人が職務執行者となり、
合同会社の業務を執行することは可能です。
社員が2人以上の場合には、
合同会社の業務の決定は、社員の過半数をもって行います。
そこで、業務執行社員を定款で定める場合には
定款において、業務執行社員と非業務執行社員に分けることも可能です。
この場合、非業務執行社員は業務執行権を喪失します。
また、定款で業務を執行する社員を1人のみに定めることもできます。
この場合、その者が単独で業務の執行を行うことになります。
実際の現場では、このような会社設計にされる経営者の方も多くいらっしゃいます。
やはり理想は多数決ですが、実際になると物事を決めるのは、
責任を負う代表者ということになるのですから、これも当然かもしれません。

合同会社・LLCの業務執行社員の報酬
合同会社とその社員の関係は委任の関係にあり、原則無報酬ですが、
通常は定款に業務執行社員の報酬について別段の定めを入れて対応します。
個人の業務執行社員には、利益配当として支払うことも可能ですが、
通常は報酬として支払うことが実際の現場では多く見られます。
この場合、利益相反取引となるため、
他の社員の過半数の同意で決めることになります。
ここで合同会社が支払う給与は税務上は役員給与に該当するため、
定期同額給与、事前確定届出給与、またはレアケースですが利益連動給与のいずれかを満たさないと損金算入することができません。
匠税理士事務所の合同会社の会社設立支援サービス
匠税理士事務所では、目黒区や世田谷区、品川区を中心に合同会社や株式会社などの会社設立を承っております。
これから起業される方の将来のビジョン・社員の方とどのような組織を作りたいのか、
出資金は幾らにするかなどしっかりとヒアリングを行いまして、お客様にとって最善の選択となるようにコンサルティングを致します。
会社設立後も経理や給与計算、社会保険などの業務は全て代行させて頂き、本業に集中して起業を成功に導くためのお手伝いを致します。
助成金の申請や日本政策金融公庫と連携した創業融資などの資金調達も行っております。
世田谷や目黒、品川で税理士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
→ 世田谷や目黒、品川の会社設立は匠税理士事務所
◇法人化・法人成りサービス
世田谷区の制度融資・創業融資の税理士は匠税理士事務所 (17/08/23)
世田谷区で会社設立して起業される場合、
【 制度融資 】を検討される方も多いです。
そこで今回は、地元の世田谷区の制度融資の
仕組みにつきまとめました。
なお、既に世田谷の制度融資をご存じで、
計画書作成や面談サポートなど融資サービスについては、
下記からご確認をお願いします。
また、世田谷区の制度融資を知りたい方は、
引き続きこちらにてお読み下さい。
創業融資サービスはこちらを確認下さい。

世田谷区の制度融資の仕組みと創業融資
制度融資の仕組みはシンプルで、
以下一定条件を満たした場合には、
世田谷区など地方自治体で、利子の大部分を
負担してくれるという内容です。
一方で地方自治体は、企業が発展してくれれば、
人材雇用など住民税などの税収が上がったり、
法人都民税など税収が見込めるという相互に
メリットがある仕組みになっています。

また、世田谷区の制度融資あっせん相談と
申込み窓口は、世田谷区産業振興公社、
経営支援係で行ってます。
貸付限度額や貸付期間、金利などの面で
民間金融機関より有利な扱いとなっている反面、
公社相談予約し、週1、概ね4回以上来社が必要です。
世田谷区は、自己資金要件は定められてませんが、
日本政策金融公庫の融資目安などから考え、
自己資金の2倍までが適正額でしょう。【 世田谷区の制度融資の種類 】
【創業資金】限度2,000万円
【利率】2.1%(利用者負担0.3%・区負担1.8%)
【返済期間】7年以内(据置12カ月を含む)
【使い道】運転資金・設備資金

世田谷区の制度融資の流れとその条件・要件
<1>【要件の確認・相談日の予約】
世田谷区産業振興公社へ連絡して、
必要書類や手続きについて説明を受けます。
<2>【金融機関や創業相談員と相談(約4回以上)】
・金融機関に区制度で創業融資あっせんを
申し込む予定を伝え、承諾を受ける必要あり
・創業相談員の継続的な相談を受け、
創業支援融資あっせん申込書・創業計画書作成
・曜日ごとに担当の創業相談員が決まっています。
・相談は、申込者本人以外はできません。
ポイントは、相談を社長様単独で行うことです。また、事前予約が必要な点も確認したい点です。
具体的な資金計画を立て、
融資の必要性が認められるようにしておくこと、
帳簿を整理し、内容を明確することが大切です。
<3>【 融資あっせん書発行・送付 】
創業融資計画書が完成したら、
公社があっせん書類を作成し、
承諾を得た金融機関にあっせん書を送付します。
<4>【金融機関・保証協会の審査融資の可否決定】
金融機関は融資の可否を決定し、通知します。
ここまでに、およそ3カ月を要します。<5>【 融資実行 】
<6>【 審査結果報告 】
金融機関は公社へ可否決定内容を回答
<7>【 利子補給 】
区が利子の一部を補助します。
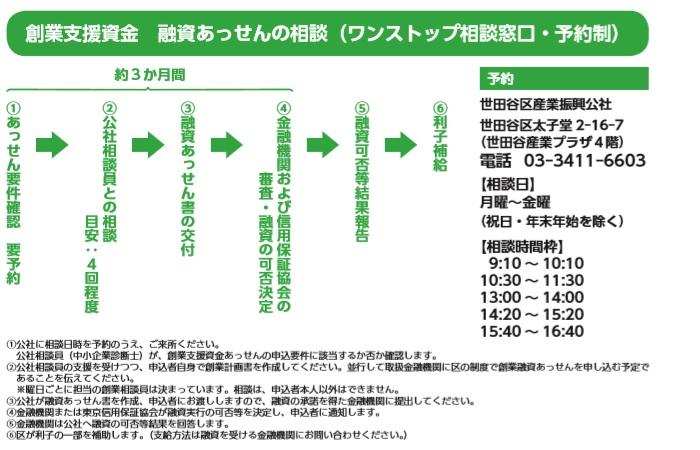
【 世田谷区の制度融資 貸付対象者条件 】
○ 本店(法人)や主たる事業所(個人)を
世田谷区内に設け創業しようとする方、
又は区内に設けて創業後1年未満の方
○ 法人は法人都民税・事業税を滞納していない、
個人は個人事業税を滞納していないこと
○ 住民税を滞納していないこと
○ 東京信用保証協会の保証対象業種であること
→ 定款事業に保証協会の対象業種以外記載しない
例)金融業、遊興娯楽業
〇許認可等が必要な事業は許認可等を受けている
〇融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、
かつ資金と利子の返済能力があること
〇過去2年以内に事業主の経験がないこと
(過去2年内に事業収入・営業・不動産収入がない)
公的融資を受けるためには、
事業計画書などの書類の審査に重点が置かれます。
つまり、制度融資を受けるためには、 融資関係書類の適正な作成がカギとなります。
また自己資金は会社設立をして起業するまでの
準備中で、起業へ熱意を最も評価される所です。
長期にかけてコツコツと貯めてきたのは、
借入金も返せるというように評価されます。

制度融資以外の起業時の資金調達について
世田谷区をはじめ地方自治体の制度融資は、
この一連の作業を全て行わなければなりません。
また、窓口へ行く回数も多いため、
時間も手間もかかってしまいます。
そこで匠税理士事務所では、
起業資金調達をお考えの方に以下の順番勧めます。
1日本政策金融公庫による資金調達 2制度融資による資金調達上記の順番で資金調達をした方がよい理由は、
日本政策金融公庫の新規開業資金については、
要件が公的融資より低く、保証の必要もありません。
また可否判明の期間が2週間なのも魅力です。
つまり手間が少なく、実行まで早いため、 こちらも合わせて検討することをお勧めします。 また日本政策金融公庫創業融資を税理士と一緒に 取り組みポイントを抑えた上で制度融資にご自身で 臨むと効果的であるというのも重要です。匠税理士事務所の創業融資支援サービス
弊所では、起業に強い世界4大会計事務所出身で、
世田谷区産業振興公社で起業セミナー講師を務めた
40代の税理士が、日本政策金融公庫の創業融資など
起業時における資金調達をサポートします。
創業計画書の作成を一緒になって対応し、
面談リハーサル・審査立ち合いも行います。
サービスは、こちらよりご確認お願い致します。

創業融資以外の経営サービスや会計サービス、
担当税理士の詳細などにつきましては、
こちらよりご確認お願い致します。

世田谷区制度融資に対応の会計事務所なら、
匠税理士事務所へお気軽にご相談下さい。
所属税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の税理士は匠税理士事務所 】
世田谷区の創業融資と制度融資お役立ち情報
世田谷区の制度融資を管轄するのは
世田谷区産業振興公社になります。
制度融資に関する各種窓口 【 →世田谷区産業振興公社 】管轄区域:世田谷区
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-16-7
世田谷産業プラザ
制度融資以外の創業融資情報 【 → 日本政策金融公庫 渋谷支店】管轄区域 世田谷区
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町3-2
渋谷サクラステージSAKURAタワー
上記が制度融資以外の創業計画書など
融資対応窓口となります。
税理士担当エリア:世田谷・目黒・品川
執筆者・文責:税理士 水野智史
#世田谷区制度融資
#世田谷区創業融資
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
日本政策金融公庫の融資についてはこちらからご確認下さい。
中目黒・祐天寺など副都心線の税理士・会計事務所の採用求人 (17/08/08)
中目黒・祐天寺など副都心線の方向け匠税理士事務所
採用求人にご訪問ありがとうございます。
【 働きやすさNo1の税理士事務所 】を目指し、
勤務時間・待遇・業務内容・職場雰囲気など
【 社員満足度の最大化 】に取り組んでます。
そのため、事務所運営では、
【いい会計事務所・税理士事務所とは?】を考え、この声に耳を傾けた採用求人、運営をしてます。
働きやすい税理士事務所、いい会計事務所
働きやすい税理士事務所と何か?
いい会計事務所とは何か?
を考える際に、
以前某求人情報特集に掲載されていた
人が辞めてしまう理由を考える事は重要です。
ちなみにこのような上位5位の理由が、
退職の理由7割以上らしいです。
1位 上司の仕事の仕方が気に入らない(23%)
2位 労働時間・環境が不満 (14%)
3位 同僚・先輩・後輩とうまくいかない(13%)
4位 給与が低かった (12%)
5位 仕事内容が面白くなかった (9%)
弊所は、現場第一主義を採用しており、 上司・経営者も現場を重視します。今だれが、どんな仕事をしていて、
その仕事内容はどうか、期限はどうかなど考え、
場合により所長税理士を含めた3人体制で
案件に臨むということもあるように、特定の人に任せるではなくて、
チームで仕事をすることを重視してます。

チームでお客様に最善の仕事の進め方を話し合い、
全員が納得した上で仕事が進むことになります。また労働時間などの職場環境は、
社員の方のプライベートとのバランスを考え、
9時から14時・15時・16時・17時までといった
メンバーそれぞれの勤務時間・働き方を認め、
お互い様・助け合い精神を大事にしています。他の社員の方との人間関係や待遇・仕事内容は、
税理士が現場をよく見ながら2~3か月に
一度個別にミーティングを行い、
・「働きにくいことはないですか?」
・「仕事で他にやってみたい仕事はありますか?」
・「現在の待遇から次の仕事をお任せできると、
このような待遇なりますが、どうでしょうか?」
一方向でなく、相互でコミュニケーションを通じ
事務所運営をしております。
おかげ様で【6年退職者ゼロ】の評価を頂いてます。

中目黒・祐天寺など副都心線の税理士事務所・会計事務所の採用求人
このように匠税理士事務所は、規模でなく
【 社員の満足度 】を追うようにしています。社員満足度が高ければ高いほど、
お客様へのパフォーマンスが上がりますし、
せっかく入所して下さった方と、
【長く楽しく仕事したい】と考えるからです。
したがいまして、人を採用するのは、
誰かが退職したから求人採用をするのではなく、
現在、働いてくださっている社員が
忙しくならないように業務とのバランスを考えて、
【 前倒しで計画的に 】求人採用を行ってます。
結果、【少し暇で、余裕がある位を善し】と考えます。
ちなみに17時以降に残業する社員はいません。中目黒・祐天寺から便利な副都心線にある
目黒区の自由が丘駅2分の税理士事務所ですので、
中目黒・祐天寺など目黒区のご近所の方が多いです。
近くで働きやすい税理士事務所や、
いい会計事務所をお探しの方は、
下記より採用求人の詳細をご確認の上、
ご応募いただければ幸いでございます。

中目黒・祐天寺など副都心線沿線から便利な
匠税理士事務所の税理士やメンバーは、
こちらよりご確認をお願いします。
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

匠税理士事務所のサービスライン全般や
各種活動実績などはこちらからご確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

中目黒・祐天寺など副都心線の会計事務所の勤務を
検討中の方は弊所の求人採用もご検討下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#中目黒税理士事務所求人
#中目黒税理士事務所採用
田園調布や日吉近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (17/08/01)
ご訪問ありがとうございます。
弊所は、田園調布や日吉など東横線を拠点に
世界4大会計事務所出身の税理士が中心となり次のサービスを提供している事務所です。
【1】会社設立や創業融資などの起業支援
【2】個人の方の確定申告や法人化
【3】法人経営者に向けた経営コンサルティング
事務所最大の特徴は、【人材】で、
【高度な専門性】と【技術力】に強みがあります。
所属税理士やサービスは、こちらからご確認下さい。
【 → 起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】

(税理士対応エリア:日吉・田園調布など東横線)
田園調布・日吉の税理士の会社設立・起業支援
匠税理士事務所は、田園調布や日吉など東横線で
会社設立や起業支援に多くの実績がございます。
会社設立の際に大事にしていることは、
1 お客様の将来のビジョンをしっかりと伺うこと 2 将来のビジョンを実現するには どのような会社設立がよいか考えることこの2点に注意しています。
このように日吉や田園調布で起業される方に向け
株主構成や資本金・出資金、役員構成や決算月など
一件一件丁寧に話し合い、
【 匠税理士事務所に会社設立を任せて良かった 】といって頂けるよう努めております。
また30代・40代の税理士やスタッフ、
提携先の会計事務所ですので、
これから会社設立をされる起業家の方に 相談しやすい同世代感も大事にしております。田園調布や日吉で起業支援を担当する
税理士・スタッフの詳細はこちらから
【 → 匠税理士事務所の概要 】

田園調布・日吉など東横線の起業家の方に向けた
匠税理士事務所の会社設立など起業支援は、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 会社設立なら匠税理士事務所 】
田園調布や日吉で創業融資による創業支援
株式会社や合同会社など会社設立とあわせて
創業融資による資金調達を検討されている方に
日吉や田園調布エリア対応の日本政策金融公庫と連携の創業融資による創業支援も行ってます。

創業融資に興味があるが、借りる方がよいか
借りない方がよいのか迷われている方にも
融資のメリットやデメリットをご説明致してます。
また創業計画書を既に作成の方につきましても、
自己資金と融資希望額のバランスや資金の用途
損益計画の整合性等のコンサルティングも行い、
【 融資成功率が9割を超えている 】のが特徴です。田園調布・日吉など東横線で会社設立と一緒に
創業融資も検討している方はご相談下さい。
創業融資による創業支援はこちらから
【 → 創業融資による資金調達 】

田園調布や日吉の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 →創業・起業支援は匠税理士事務所 】
(創業支援は田園調布や日吉なども対応)
田園調布や日吉の確定申告や法人化
匠税理士事務所には個人事業主の確定申告や
法人化に詳しい税理士も在籍しております。
これまで自分で確定申告を行ってきたが、
税金や国民健康保険料が高いので、
効果的な節税を行いたい方や、
これまで個人で事業を行ってきたが、
そろそろ株式会社などにしたいという方に向けて
税務コンサルティングを行う会計事務所です。また事業拡大に伴う経営の相談も承ってます。
田園調布や日吉などの法人経営者の方向けサービスは
こちらからご確認ください。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
田園調布や日吉の方向け経理や会計、確定申告や
法人化など個人サービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
田園調布や日吉で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

日吉や田園調布地区で会社設立されたお客様
会社員を辞めて会社設立し起業を考えた際、
顧問税理士・会計事務所を探していたところ
匠さんのWEBを拝見しお会いして、
人間性に魅力を感じ任せることにしました。
会社設立から融資、会計などHPの通り、
しっかりと対応してくれるので大変助っています。
日吉で会社設立された飲食店様
これまで個人でWEB制作をしていましたが、
消費税が出てくることになり、
こちらの会計事務所に顧問をお願いしました。
会社設立・法人化で社会保険加入も対応してくれ
大変助かりました。
これからもよろしくお願いします。
田園調布で法人化されたWEB制作業様
日吉や田園調布の方向け税理士事務所の求人や採用情報
上記以外のサービスや日吉や田園調布などで
会計事務所の就職をお考えの方に向けた
採用・求人情報につきましては
採用ページより確認をお願いします。
弊所ではお客様の満足度のためには
優秀な人材が不可欠と考えており、
随時募集を行っております。
また、社員の方の働きやすさ・満足度向上に
取り組んでおりここ5年間は退職者がいない
という会計事務所でもあります。
(田園調布・でんえんちょうふ)や(日吉・ひよし)など
東横線沿いにお住いの方で、会計事務所勤務を
ご検討中の方はお気軽にご連絡ください。
田園調布や日吉の法人化・会社設立関連情報
田園調布や日吉の近くの税理士・会計事務所による
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 東京都の税理士による法人化・法人成り】
日吉・田園調布で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記も提携の司法書士が対応致します。
日吉・田園調布近く税理士事務所お役立ち情報
日吉駅・田園調布駅には東急東横線があり、
税務署にもアクセス便利です。
日吉・田園調布で会社設立など起業した場合や、
会社経営をされている場合の税務申告書、
届出書提出先は以下のようになります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 税務申告書、届出書提出先 【 → 神奈川税務署 】管轄区域:神奈川区・港北区(日吉はこちら)
〒222-8550
横浜市港北区大豆戸町528番5
【 → 雪谷税務署 】管轄区域:大田区のうち調布地区(田園調布はこちら)
〒145-8506
大田区雪谷大塚町4番12号
事業税・住民税の申告書、届出書提出先 【 → 神奈川県税事務所 】管轄区域・横浜市鶴見区・神奈川区・港北区
〒221-0824
横浜市神奈川区広台太田町3-8
【 → 品川都税事務所 】管轄区域:大田区・品川区
〒140-8716
品川区広町2-1-36 ※品川区役所 本庁舎・議会棟の2階
住民税の申告書、届出書提出先 【 → 横浜市財政局 】管轄区域:横浜市
〒231-8312
横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
日吉地区の税務相談 【 →東京地方税理士会 神奈川支部 】管轄区域:神奈川区・港北区
〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町547番地の1
日吉の社会保険関連書類の提出や相談先 【 →日本年金機構 港北年金事務所 】〒222-8555
神奈川県横浜市港北区大豆戸町515
上記が日吉や田園調布の方の税務申告や、
会社設立や法人化された際の届出書の提出先、
税務調査を所轄する機関となります。
期限までに税務や決算関連書類の提出を行いましょう。
日吉や田園調布での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#田園調布税理士
#日吉会社設立
相続における遺留分とは、その割合や計算方法 (17/07/21)
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第11回 事業承継とは?事業を継承する際の注意点や種類・やり方
第12回 相続税対策の生前贈与、税率と非課税は?
第13回 相続税の物納とは?相続税が払えなかったらどうする?
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税や事業承継など
税務コンサルティングを行っている会計事務所です。
今回は財産の相続における遺留分について取り上げたいと思います。
そもそも遺留分とは何なのか?
被相続人(亡くなった方)の財産のうち兄弟姉妹以外の相続人が、
最低限取得することができる割合を民法で定めたものを遺留分といいます。
民法で遺留分の制度が設けられているのは、
被相続人の財産のうち相続人が取得できる最低限の割合を遺留分として保障しています。
これは、被相続人が第三者や特定の相続人に対して全財産を遺贈・贈与した場合に、
被相続人の財産を取得できない相続人が生じるためです。
この場合、被相続人の財産形成に相続人が協力してきたことへ配慮に欠けるという問題や、
被相続人の財産を取得できなかった相続人は、
生活に支障をきたすおそれがあるという問題が生じます。
このような問題を改善するために遺留分が制度があります。

兄弟姉妹はたとえ相続人になったとしても遺留分はありません。
従って、兄弟姉妹以外の相続人が遺留分権利者となれます。
遺留分の割合はどれ位なのか?
父母や祖父母などの直系尊属のみが相続人であるときは、
被相続人の財産の3分の1が遺留分権利者全体の遺留分となります。
その他の場合の遺留分は2分の1です。
複数の遺留分権利者が存在している場合には、全体としての遺留分の割合に、
それぞれの法定相続分を乗じたものが、その相続人の遺留分割合となります。
相続人が配偶者と子2人を例にした場合、配偶者の遺留分は1/2×1/2=1/4となり、
子はそれぞれ1/2×1/4=1/8となえります。
遺留分算定の基礎となる財産の計算方法下記の算式により判定します。
1 被相続人の遺産額(相続開始時点の時価)
2 被相続人が生前に贈与した財産額(相続開始時点の時価)
3 債務額
【 1+2-3=遺留分算定の基礎となる財産 】
※被相続人が生前に贈与した財産額については、
贈与を受けた者によりその財産が売却され相続開始時には存在しない場合であっても、
相続開始時に現状のままあるものとみなし、その時価を加算して計算します。
被相続人が生前に贈与した財産額下記の2つが民法により規定されています。
1:相続開始前1年間での贈与財産額
2:相続開始前1年間超の贈与については、遺留分権利者に損害を与えることを認識していた贈与財産
なお、相続人のうちに特別受益を受けた者がいる場合には、その贈与が相続開始1年前に行われたか否かに関わらず、
その特別受益に該当する財産価額が遺留分算定対象となります。
特別受益(民法903条第1項)生計の資本として、または婚姻もしくは養子縁組による贈与を特別受益といいます。
生計の資本としての贈与については、特別な事情が無いかぎり、
相当額の贈与は全てこの特別受益に該当すると考えられています。
従って、実務的には、親(被相続人)から子(相続人)へ贈与した財産の額は、
すべて「被相続人が生前に贈与した財産額」に含まれることとなります。

相続人および遺留分権利者等は、遺留分を確保するための減殺請求ができます。
この場合、被相続人の生前に贈与を受けた者、遺言書により相続分の指定を受けた相続人、遺言で被相続人の財産を取得した者等、遺留分を侵害する者が減殺請求の相手となります。
遺留分を侵害する者に対して意思表示をすれば、書面でも口頭でも遺留分の減殺請求を行うことができます。
一般的には、遺留分を侵害する者に対し、内容証明郵便により通知を行う方法が行われます。
減殺請求権の期限遺留分の減殺請求権には時効が存在します。
具体的には、親が亡くなったときに他の兄弟姉妹に生前贈与や遺贈があり、
自分がその相続により取得した財産の額が遺留分の額に満たなかった場合、
それを認識した日から1年以内に減殺請求を行わなかったときは時効により権利が消滅します。
また、自分に遺留分があることを知らないまま10年が経過した場合にも、時効により権利が消滅します。
このように【遺留分について知らなかった】ということにならないように最低限の知識は必要です。
匠税理士事務所の相続税・事業承継支援サービス
匠税理士事務所では、経験豊富な税理士が、
世田谷や目黒、品川を中心に相続税や事業承継などのサポートを行っております。
相続税については生前贈与などを活用した相続対策から、相続後のトラブルを防止するための遺言作成や、
相続税シミュレーションなどにも対応しております。
大規模な相続案件や事業承継などにつきましては、
提携の相続税専門の税理士や公認会計士と連携して高度なご提案を行うことも可能です。
相続税サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

相続税を担当する税理士や提携の税理士・公認会計士などの詳細につきましては、
こちらよりトップページへ移動の上、税理士事務所概要をご確認下さい。
→ 税理士を世田谷区や目黒区、品川区でお探しなら匠税理士事務所
品川区の制度融資・創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 (17/07/19)
匠税理士事務所は品川区を中心に創業融資など
起業支援に力を入れている会計事務所です。
今回は品川区で会社設立して起業をお考えの方に
起業時の制度融資をまとめました。
品川区の起業家向け資金調達には、
【 1 日本政策金融公庫による創業融資 】 【 2 品川区による制度融資 】の大きく2つが検討ができ、
今回は、【品川区よる制度融資】を掘り下げます。
なお、既に品川区の制度融資はご存じで、
創業計画書や面談など匠税理士事務所の
融資サービスは、下記でご確認を願います。
また、品川の制度融資を知りたい方は、
引き続きこちらをお読み下さい。

税理士対応エリア:品川区など東京都全域
品川区の制度融資や創業融資の資金調達
品川区制度融資あっせんの相談と申し込み窓口は、
品川区商業・ものづくり課 中小企業支援係です。
貸付限度額や貸付期間、金利など民間機関より
かなり有利な扱いとなっている反面、
商工相談員と面談予約し、複数回来所が必要です。
【 つまり手間・時間がかかるのです。 】 創業支援資金【限度額】2,000万円まで
【利率】初創業 本人0.2%内 表面利率1.6%内
【返済期間】10年以内(設備・据置12カ月を含む)
【使い道】運転、設備、運転・設備の併用
【保証料補助率】初めての創業の場合・・全額
品川区の制度融資の流れ<1>金融機関への相談
取扱金融機関へ借入の相談をしてください。
<2>面談予約・あっ旋申込
品川区商業・ものづくり課中小企業支援係で
予約を取り、商工相談員と面談をします。
面談の内容
・創業支援資金あっ旋の申し込み要件の確認
・該当する方は、あっ旋に必要な今後の手続き説明
申込は、税理士・金融機関の代理申請は【不可】。
しかし、以下の方法で、十分に対策は可能です。

商工相談員のアドバイスを受けながら、
申込者自身で創業までの計画を立ててください。
最終的には創業計画書(区指定様式)を含め、
必要書類を提出してください。
商工相談員による確認ができましたら、
取扱金融機関あての紹介状を発行します。
具体的な資金計画を立て制度融資の必要性が
認められるようにしておくこと、
帳簿類を整理し内容を明確することが大切です。
<4>金融機関・信用保証協会の審査と可否決定
紹介状を取扱金融機関へご提出ください。
取扱金融機関で審査を行い、可否が決まります。
なお、信用保証を利用する場合には、
東京信用保証協会による審査も行われます。
(100%保証もしくは80%保証になります)
信用保証協会が審査後、保証可否の報告をします。
<5>審査結果報告金融機関が、申込者、品川区へ可否報告をします。
<6>実行実行後、品川区が申込者へ保証料補助を行います。
※実行後、区から金融機関へ利子補給がされます。
区負担分利子は区から金融機関へ振り込まれます。
※申込者は信用保証協会へ保証料を支払います。
区が信用保証料の全部または一部を補助します。
紹介状発行時、保証料補助制度案内が出されたら
必要事項を記入し、取扱金融機関へ提出。
後日、区から申込者指定口座へ直接振込み。
申込対象○ 初創業は、企業の代表者でない者が、
品川区内創業の場合又は創業し継続5年内の場合
個人事業主として創業予定の方は、
創業に必要な資金総額1/3以上の自己資金が必要
○ 税金滞納してない事(分納は未納されます)
○ 東京信用保証協会の保証対象業種を営むこと
定款目的に保証協会の対象業種以外は記載しない
ポイントのみ記載し、一部は省略しております。

品川区の制度融資や創業融資のポイント
品川の制度融資・日本政策金融公庫の創業融資は、
事業計画書などの書類審査に重点が置かれます。
つまり、制度融資を受けるためには、 創業計画書など関係書類の適正な作成がカギです。品川区の制度融資では、この一連の作業を
全て自分で行わなければなりません。
一方起業では、本業に集中したいというニーズや、
時間がないケースもあるかと思います。
日本政策金融公庫の創業融資も起業する中小企業に手厚い制度です。
利用要件が制度融資より緩く、
面談も1回なので時間もかかりません。
また可否判明の期間が、2週間程も魅力です。
こちらも合わせて検討することをお勧めします。
匠税理士事務所の制度融資・創業融資支援
それでは、品川区で起業をお考えの方に
公庫の創業融資・制度融資どちらがよいかというと
やはり日本政策金融公庫の創業融資がお勧めです。その理由は、大きく分けて2つあります。
まず日本政策金融公庫の創業融資は面談が1回で、
申し込みから実行までの速度が早いことです。起業はスピード感が重要で資金面が後手に回ると、
全てが遅れ始めることになってしまいます。
次に、日本政策金融公庫の創業融資と
品川区の制度融資の両方をご検討される方は、
両方の書式で創業計画書が必要になってきますが、
内容は、【 ほぼ同一 】なので、
まず、日本政策金融公庫の創業計画書を税理士と作成し、
これを基に少しハードルが高い制度融資計画書を
作るようにすると効果的だからです。
匠税理士事務所は、品川区の日本政策金融公庫の
五反田支店と連携し、創業融資サポートのため
創業計画書作成支援や面談対策などを行ってます。
匠税理士事務所の創業融資サービスは、
こちらからご確認をお願いします。

起業時の資金調達以外のご要望につきましても
起業支援や会社設立などご用意しております。
詳細は、こちらからご確認下さい。

匠税理士事務所の担当税理士やサービスは、
下記よりご確認下さい。
【 → 品川区の税理士は匠税理士事務所】

税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー①
( 関連記事:日本政策金融公庫とは )
品川区の創業融資・制度融資お役立ち情報
品川区の制度融資を管轄するのは
品川区地域産業振興課 中小企業支援担当になります。
制度融資に関する各種窓口 【 → 品川区地域産業振興課 】管轄区域:品川区
〒141-0033
東京都品川区西品川1-28-3
制度融資以外の創業融資 【 → 日本政策金融公庫 五反田支店 】管轄区域 品川区
141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13
五反⽥JPビルディング
上記が制度融資以外の創業計画書など
融資対応窓口となります。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#品川区制度融資
#品川区創業融資
代官山すぐの税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (17/07/14)
匠税理士事務所のWEBサイトへご訪問頂きありがとうございます。
弊所は、代官山など東横線エリアで起業支援No1を目指す税理士事務所です。
弊社の強みは 【 起業に必要な全てのサービスがそろう会計事務所 】であることです。
経営やお金、利益など様々な問題についてより相談しやすいように
税理士・司法書士・弁護士・社会保険労務士など専門家・スタッフは全て、
起業家のお客様と同世代である30代・40代で構成されております。
また、お客様の大切な会社を守るため税金や経理だけでなく
法律や人事・労務、著作権などの権利関係、許可申請やビザ取得など
あらゆる各分野で高度な専門性と経験値を併せ持つスペシャリストをそろえ、
代官山で起業されるお客様の幅広いニーズにお応えいたします。
匠税理士事務所の税理士・提携専門家やサービス料金などにつきましてはこちらからご確認下さい。
【 → 起業支援の匠税理士事務所の紹介 】

代官山からアクセス便利な会計事務所
匠税理士事務所は、代官山に電車で5分程という自由が丘駅にあり、
駅からも徒歩2分の場所にあるためお気軽にお立ちより頂くことが可能です。
お客様のお話を伺い、税理士・会計士のみで問題解決が難しいような人事や法務などの問題には、
社会保険や給与計算など人事労務には社会保険労務士が適格なコンサルティングをさせて頂いたり、
契約書など法務については弁護士が各問題ごとに取り組みます。
このようにして税務会計以外でも、お客様が安心して本業に集中できるようにサポート致しております。
税理士による会社設立や創業支援について
代官山エリアの起業家の方でこれから株式会社など会社設計をしたいという方に向けて、
税理士・司法書士が連携してお客様にとってベストな会社設立になるよう資本金や決算月などをコンサルティング致します。
また会社設立とともに資金調達をご検討されている方に向けましては、
代官山エリアに対応した日本政策金融公庫や金融機関と連携した
各創業支援制度を活用した創業融資による資金調達も行っております。
株式会社の会社設立・創業融資などの起業支援サービス詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 会社設立の代行サービス 】
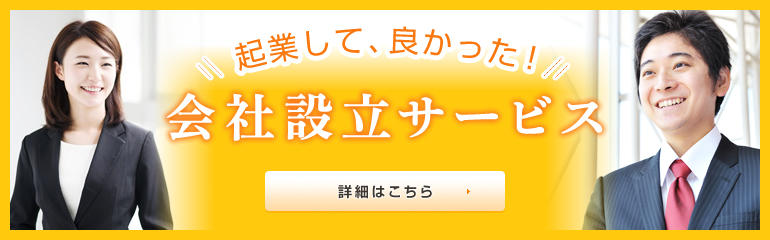
ご希望のお客様には、代官山地域に対応した提携の社会保険労務士と共に助成金の申請代行も承っております。
こちらは完全成功報酬となっておりますので、とりあえず助成金の獲得に挑戦してみたいという
起業家の方に大変ご好評をいただいております。
特に会社設立をして起業するときに人材を雇用したり、社員の研修に力を入れている会社様は
助成金を受けられる場合がございますので、お気軽にご相談下さい。
代官山近くの匠税理士事務所の特徴
匠税理士事務所の税理士は、アパレルやITなど代官山の地域に多い業種をこれまで多く担当しており、
多くのノウハウを有しております。
特にIT業界は進歩・変化が目覚ましいので、
会計税務の知識のアップデートや、IT業界への知識が不可欠です。
また利益率が高いのもこのIT分野の特徴ですので、
獲得された利益をできる限りお金として残せるように節税対策・提案にも力を入れている会計事務所です。
弊所ではこれまでWEB制作会社様・アプリケーションなどソフトウェア開発会社様やインターネット広告代理店様などと多くの取引を担当させて頂きまして、決算の3か月前に税額をシミュレーションし効果的な節税提案を行っておりますので、多くのお客様からご好評をいただいております。
また会社の規模も、会社設立など創業の支援から上場企業の税務申告までの規模に対応しておりますので、
会社規模の成長が早いIT業界のお客様にもしっかりとご対応が可能です。
税務や経理など専門分野についてご安心頂けることは当然ですが、
経営のパートナーとして頂ける税理士事務所であることを心がけています。
代官山で会社設立や創業をご検討中の方で、会社の近くで、
同世代で経営について相談しやすい自社に合った税理士をお探しという方は、お気軽にご相談下さい。
【 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】

代官山の会社経営者向け会計・経営支援サービス
代官山で既に会社を経営されている方につきましては、会計のアウトソーシングを始めてとして、
会計アウトソーシングのデータを活用した財務分析や、経営コンサルティングサービスをご提供しております。
ご要望のお客様には毎月の給与計算や社会保険の手続き業務代行、
社会保険料を削減するためのIT協会健保への加入提案なども行っております。
またIT業界は残業が多いのも特徴ですので、
就業規則などの事前準備や万が一のときの労使トラブルを収めるためこれらのご相談も承っております。
サービスの詳細につきましては、下記よりご確認下さい。
代官山地域のお客様の声
代官山でアパレルの会社を経営しており、
知人に紹介してもらった以前の税理士さんが年配の方で、
コミニュケーションがうまくいかないことが多かったので、
匠税理士事務所さんに相談してみました。
とても物腰がやわらかく、丁寧に説明してくれたので、
お願いして約7年になりますが、ミスもなく会社のために
一生懸命にして下さり、感謝しております。
【 渋谷の代官山 アパレル 株式会社N様】
代官山すぐの会計事務所や税理士事務所の採用求人
代官山にお住いで会計事務所や税理士事務所での勤務をご検討中の方は、
こちらより正社員やアルバイト・パートスタッフの求人や採用情報をご覧いただければ幸いです。
最後までお読み頂き、ありがとうございました。
法人化・法人成りした場合のソフトウェアの引継ぎ (17/07/12)
法人化・法人成りした場合のソフトウェアは、
個人事業から新設会社に引継ぐことになりますが、
ソフトウェアの引継ぎで決めないといけないのが、
1 いくらで引き継ぎか(取得価額はいくらか)
2 どの期間で経費にするか(耐用年数は何年か)
この2点がポイントになります。
そこで今回は、この法人化・法人成りした場合の
ソフトウェア取得価額と耐用年数をどのように
決めるべきかについてまとめてみました。

法人化・法人成りでソフトウェア取得価額はいくらにすべき
個人事業主が法人化・法人成りをして会社設立し、
その資産を会社が引き継ぐ場合、
個人から法人に対する資産の譲渡となり、
その譲渡価額は適正時価によることとなります。
具体的に、資産種類・型式・使用経過年数等を考慮し
市場の見積販売価額、類似物件の売買実例価額等と
比較して価額を決定することとなります。
もっとも、資産の評価は絶対的な基準がなく
困難なことから、有形固定資産に認められている
再取得価額-償却相当額を控除した価額=時価を用いることもやむを得ないと考えられます。

法人化・法人成りソフトウェア耐用年数は何年か
法人化・法人成りした場合に、個人事業から
新設会社にソフトウェアを引継ぐのは、
新設会社にとって他人が使っていたソフトウェアを
中古で買うのと同じ状況になります。
税務上では、中古の減価償却資産につき、
法律上何年で経費化という法定耐用年数を使わず
残存耐用年数を見積もり、その見積耐用年数により
償却計算を行うことも認められています。
また、見積もりは一般的に困難な場合が多いので、
次の算式で算出した年数で、中古資産を経費化する簡便法も認められています。
(A)法定耐用年数の全部を経過
法定年数×0.2
(B)法定耐用年数の一部を経過
→(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
(端数切捨て、2年未満である場合は2年)
実務上、簡便法で経費化が多いのですが、
ソフトウェアは、簡便法を利用できません。
簡便法で耐用年数算出できる資産は限定され、
ソフトウェアはこの対象になってないからです。

中古ソフトウエア耐用年数はどうなるのか
中古ソフトウエア耐用年数で、
簡便法が認められないとなると、
中古ソフトウェア耐用年数はどうなるのでしょうか?
上記の見積法での算出も考えられますが、
ソフトウェアは物理的に残存耐用年数を見積りが困難で、
法定年数によらざるを得ないものと考えられます。
(開発研究用ソフトウェアは別の規定があり。ここでは省略)
このように個人から引き継いだ減価償却資産は、
原則として中古資産に該当するのですが、
中古ソフトウェアは、簡便法で耐用年数計算できないため、
結局のところ新品のソフトウェアと同じように法定耐用年数が償却期間となると考えられます。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区など
東京都で個人事業を株式会社にしたい方に向けて
法人化や法人成り支援を行っております。
法人化した後の社会保険の加入手続きや
給与計算業務、会社設立登記など本業以外は、
全てお任せで、できる限り本業に支障がないよう
法人化をサポートさせて頂きます。
法人化サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
【→ 世田谷区や目黒区、品川区など東京都の法人化・法人成り】

法人化相談会はこちらでご確認をお願いします。
法人化や法人成りについての情報を掲載した
法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
◆上記以外のサービスや担当税理士など
専門家は下記でご確認お願い致します。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

北烏山・南烏山・千歳烏山近く匠税理士事務所・会計事務所 (17/07/07)
匠税理士事務所にご訪問ありがとうございます。
弊所は北烏山・南烏山・千歳烏山など世田谷区で
【起業支援・経営支援】に強い事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士を中心に、会社設立から創業融資などの起業支援や、
経営セミナーなどの講師やコンサルティングが評判です。
もちろん、個人の確定申告や経理代行など
通常の会計事務所で扱う税務会計も対応します。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。

北烏山・南烏山・千歳烏山で会社設立・起業支援
北烏山・南烏山・千歳烏山のお客様でこれから
会社設立をして起業・独立開業をお考えの方に
・社名と本店の場所を決めて頂ければ全て
お任せの株式会社や合同会社など会社設立
・起業時の資金で一部外部借入をご検討中の方に
創業融資支援など起業支援を提供してます。

お客様にとって起業は一生に一度のことですので、
【 匠税理士事務所に頼んで良かった 】といって頂けるような仕事を心掛けております。
起業や独立開業の支援を担当する際は、
税理士以外にも社労士・行政書士・司法書士がチームで
担当しますので税務会計以外も対応が可能です。
【 起業に必要な全てがそろう事務所 】を起業支援のポリシーとしております。
北烏山・南烏山・千歳烏山担当の税理士等はこちら
【→起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】

北烏山・南烏山・千歳烏山の会社設立
株式会社や合同会社の会社設立に伴う資本金や
決算月など基本設計から登記代行、税務署などへの
届出書作成も代行致します。
北烏山・南烏山・千歳烏で会社設立後の
創業融資や助成金・補助金も対応可能です。
起業支援の詳細はこちらから
北烏山・南烏山の創業融資など創業支援
北烏山・南烏山・千歳烏山での創業融資支援では、
起業に強い世界4大会計事務所出身の税理士が、
計画書作成から融資面談前リハーサルも行います。
日本政策金融公庫や自治体制度融資も対応し、
【 融資成功率は9割超 】のトップクラスの実績です。各金融機関と連携した創業融資も行っており、
日本政策金融公庫の上限1,000万円と世田谷区の
制度融資で1,000万円の合計2,000万円を
起業時に調達するという実績も多数ございます。
北烏山・南烏山・千歳烏山対応の金融機関と提携で
スムーズな創業融資で創業支援します。
サービス詳細はWEBで確認下さい。

北烏山・南烏山・千歳烏山の株式会社など
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は北烏山・南烏山・千歳烏山など世田谷対応)
千歳烏山で独立開業支援や法人化・法人成り
北烏山・南烏山・千歳烏山で起業・独立開業する方に
向けた経理会計や経営サポート助成金・補助金など
起業支援サービスの一覧です。
助成金・補助金は創業支援の目的のため成功報酬で
顧問契約無のスポットでの対応も可能です。
北烏山・南烏山・千歳烏山など世田谷区での
サービスの詳細はWEBからご確認下さい。
個人事業で独立開業してから会社設立する
北烏山・南烏山・千歳烏山など世田谷区で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
北烏山・南烏山・千歳烏山の確定申告・経理決算
匠税理士事務所では、北烏山・南烏山・千歳烏山で
個人事業主をされている方の会計や経理青色申告や
これから会社にしたい法人化・法人成りなどや、
自宅や投資マンションなど売却した場合の確定申告
既に会社を経営されている方の決算節税対策など
税務会計サービスも提供しております。
北烏山・南烏山・千歳烏山など世田谷区での
サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
北烏山・南烏山・千歳烏山の方向け経理会計や
確定申告・法人化などサービスはこちらから
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
北烏山・南烏山・千歳烏山で税理士の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

北烏山・南烏山・千歳烏山で税理士の求人採用
北烏山・南烏山・千歳烏山など世田谷区の
税理士事務所や会計事務所の勤務をご検討中の方は
匠税理士事務所の採用情報をご確認下さい。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
北烏山・南烏山・千歳烏山の税理士事務所お役立ち情報
千歳烏山駅には京王線があり、
税務署にもアクセス便利です。
北烏山・南烏山・千歳烏山で事業や、
会社経営をされている方の税務申告書や、
北烏山・南烏山・千歳烏山で会社設立など
起業された方の届出書提出は以下となります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 税務申告書、届出書提出先 【 → 北沢税務署 】管轄区域:世田谷区のうち北部地区
〒156-8555
世田谷区松原6丁目13番10号
【 → 渋谷都税事務所 】管轄区域・渋谷区・目黒区・世田谷区
〒151-8546
渋谷区千駄ヶ谷4-3-15
東京都渋谷合同庁舎4~7階
上記が北烏山・南烏山・千歳烏の税務申告関連や
税務届出書の提出先となります。
北烏山・南烏山・千歳烏山近くのお客様への
会社設立など起業支援・創業支援や、
個人からの法人化・法人成りなどに関する
匠税理士事務所・会計事務所の案内を最後まで
ご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#南烏山税理士 #千歳烏山税理士
上野毛や弦巻すぐの会計事務所は匠税理士事務所 (17/07/03)
匠税理士事務所のWEBサイトへ
ご来訪ありがとうございます。
弊所では、上野毛や弦巻など世田谷エリアを中心に
会社設立などの起業支援や経営コンサルティング、
個人から会社にする法人化を行う会計事務所です。
事務所の方針と致しましては、
【人材にこだわることで、専門性を高め、】 【お客様のお役に立てる税理士事務所であること】をポリシーとしております。
【 匠税理士事務所に頼んで良かった 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の所属税理士やサービスは
こちらで確認お願い致します。

上野毛や弦巻などの会社設立や起業支援
上野毛や弦巻など世田谷区で独立開業し、
株式会社・合同会社を設立される方に向けて
・会社設立に向けて資本金をいくらにすべきか。
・役員や株主はどのようにしたらよいのか。
・会社の基本設計はどんな感じがよいのか、
また融資の必要性についての検討
といった設立に伴う相談会を行っております。
これによりお客様の【 会社設立・起業成功 】をできる限りサポートしたいと考えております。
上野毛や弦巻担当税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

対応エリア:上野毛や弦巻など世田谷区
もちろん、上野毛や弦巻など世田谷で会社設立後の
会計経理や給与計算も代行致します。
詳細はこちらからご確認をお願い致します。
匠税理士事務所の創業融資など創業支援
匠税理士事務所では上野毛や弦巻など世田谷区で
日本政策金融公庫と連携した創業融資など
創業支援にも力を入れております。
上野毛や弦巻での創業融資支援では、
世界4大会計事務所出身の税理士が、創業計画書を社長と一緒になって作成します。
その創業計画書を基に日本政策金融公庫の方との
融資面談にも一緒なって立ち会います。
上野毛や弦巻など世田谷エリアの起業家に向けた
匠税理士事務所の創業融資による創業支援は、
こちらよりご確認をお願いします。

上野毛や弦巻の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は上野毛や弦巻など世田谷全域対応)
上野毛や弦巻の会計経理や確定申告・決算代行
弊所では、上野毛や弦巻など世田谷区で
確定申告や会計税務、経理や決算も承ってます。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
上野毛や弦巻の方向けの確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
上野毛や弦巻で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

上野毛や弦巻での法人化や法人成り支援
個人事業を長年営まれていると、
多くの方が一度は、
『 会社にした方がいいのかな~?』
とお考えになると思います。
そこで今回は、上野毛や弦巻など世田谷エリアで、
個人から会社にする【法人化】【法人成り】で何を考える必要があるかをまとめました。
法人化や法人成りの長所や短所を知る相談会
法人化や法人成りをすれば、
節税が出来て全て得するわけではありません。
法人化や法人成りをすることで、
長所もあれば短所もでてきます。
そのためまずは、法人化をすることで、
どのような点で得をし、どのような点が損か
を知る必要が出てきます。
法人化や法人成りの長所や短所については、
以前にまとめました下記の記事を
ご確認頂けましたら幸いです。
→ 会社にする?個人のまま?法人化のポイント(メリット・デメリット)
お客様ごとに状況も異なりますので、
法人化や法人成りも承っております。
法人化にご興味のある上野毛や弦巻など
世田谷の方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
個人から会社設立前に大事なこと
それでは上記の現在の税制等のみを考えて、
法人化すれば良いかというとそうではありません。
法人化を一度すると、取引関係もありますので、
個人事業へ戻る方はほとんどないです。
そのため一番避けたいのは、
こんなことなら法人化しなければ良かった・・・・
このような事態にならないようにするには、
何が必要かというと、
これからの時代の流れを読み法人化することです。
【税金のみでいえば消費税が一定期間免除される】
だから法人化をしよう・・・
ではなく、
税金は短期的には得をしそうだ、
ただ一方で社会保険はこれから上がりそう・・
社保強制加入になった場合、対応できるか、
また人を雇う際、社会保険負担できるか・
という今後の税制や社会保険制度の流れ、
自分の業界の流れを考えた上での慎重な判断が
法人化にはとても重要です。
上野毛や弦巻での悔いのない法人化を支援します。
匠税理士事務所の法人化・法人成り
上野毛・弦巻など個人から会社設立する世田谷の方に
法人化や法人成り支援サービスをご提供してます。
法人化や法人成りをご検討されている方は、
お気軽にご相談下さい。
法人化・法人成りサービスはこちらから
上野毛や弦巻など世田谷近くの会計事務所や税理士事務所の求人・採用
匠税理士事務所では、上野毛や弦巻など世田谷で
会計事務所への就職や転職をお考えの方に
正社員やパート・アルバイトスタッフの
求人採用を行っております。
人材が事務所の根幹と考えており、
人を大事にすることを第一にしております。
上野毛や弦巻など世田谷向けの求人採用に関する
詳細はこちらからご確認をお願い致します。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
弦巻(つるまき)・上野毛(かみのげ)など
世田谷での会社設立など起業支援・創業支援や
個人で独立開業し法人化・法人成りなどの
匠税理士事務所の案内を最後までご覧頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#上野毛税理士
#弦巻会社設立
日本政策金融公庫の創業融資、実際の流れ (17/07/01)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
第17回 匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に日本政策金融公庫と連携した
創業融資による資金調達を通じて、起業の成功をお手伝いしている会計事務所です。
今回は日本政策金融公庫の創業融資をご検討中の方に向けて、
融資を受けるまでの実際の流れについてまとめてみました。
日本政策金融公庫の創業融資の事前準備
創業融資制度の利用者は、事業を開始するにあたり、
過去1年分のお金の貯め方や、公共料金等の支払いに滞納がないかなどが調べられます。
利用者には計画性が求められ、親から譲り受けたお金や退職金よりも、
毎月の給料からコツコツ貯めたお金の方が高く評価されます。
ここでは、資金をコツコツ貯めた方は、 創業融資で借りたお金をコツコツと返せるというように見るようです。

創業融資を受けるために必要な提出書類
必須書類(融資を受けるために必ず提出が必要な書類)
・借入申込書
・創業計画書
・法人の方は履歴事項全部証明書(謄本)
条件付き提出書類
融資を受ける目的が設備投資である場合など一定の条件の場合に必要な書類
・設備資金借り入れの場合・・・見積書
・担保を希望の場合・・・不動産の登記簿謄本または登記事項証明書
・生活衛生関係の事業を営む場合・・・都道府県知事の推薦書または生活衛生同業組合の振興事業に掛かる資金証明書
借入申し込みの方法
借入申込書の取得
ご自宅の最寄りの日本政策金融公庫を訪ね、借入申込書をもらいます。
日本政策金融公庫の公式ホームページから必須書類をダウンロードすることもできます。
入手した借入申込書に記入して提出することになります。
またホームページのお申込みフォームから直接借入を申し込むこともできます。
いずれの場合も、面談の整合性がとれるよう借入申込書の控は手元に残しておきましょう。
インターネットから申込をした場合、早ければ当日中に折り返しの電話がきます。
ウェブ上でできるのは借入申込書の提出までなので、
電話で創業計画書等の必要書類の確認と借入申込みの内容確認があります。
知らない電話番号からの着信を取らない方は気をつけましょう。
また、ホームページから申し込みしたのであれば、受付確認メールが迷惑フォルダに入っていないか注意しましょう。
創業計画書やその他条件付き提出書類については、郵送ではなく店舗へ持ち込みすることをお勧めします。
面談を受ける際の場慣れが目的です。

日本政策金融公庫の創業融資 借入申込書の記入
借入申込書を記入する段階で、事業にどれくらいの資金が必要なのか、
運転資金は?設備資金は?といったことを具体的な数字として表していきます。
いままでぼんやりしていた事業のイメージを具現化のためにしっかり考えるプロセスでもあるのです。
借入申込をするまでに、事業の看板となる法人名や屋号を決めておきましょう。
また、借入れたお金を何にいくら使うのかを問われます。
具体的には、運転資金であれば、
①商品・材料仕入 ②買掛、手形決済 ③諸経費支払 ④その他、
設備資金であれば①店舗・工場 ②土地 ③機械設備 ④車両 ⑤その他
それぞれ該当するものに○をつけることになります。
申込書には表裏がありますが、(ホームページからダウンロードする時は裏面も刷りだすことを忘れずに)、
新創業融資制度では無担保・無保証人を目指していますから、裏面の記入は必要ありません。
またしばらくは元金の返済を猶予してもらって利息のみを支払う据え置き期間を設定しておくことで、融資により受けた資金をできる限り手元においておくことも可能になります。
こちらについても半年など自分の希望を記載しておきましょう。

匠税理士事務所の創業融資支援サービス
匠税理士事務所では、品川区の五反田にある日本政策金融公庫と連携して創業融資を行っております。
こちらでは主に世田谷や目黒、品川を中心に起業される方に向けて
創業計画書の作成から面談の事前リハーサル・面談の当日立ち合いなどを行っております。
なぜここまで行うかというと、起業時の資金調達の成功は、今後の起業成功に大きくかかわります。
そこで経営者の得意分野である本業への知識に、税理士の専門分野である会計の知識・ノウハウを加えることで、より融資を有利に導きたいという思いからです。
お客様のご協力のおかげ融資実行率9割超なっております。詳細はこちらからご確認下さい。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】はこちら

創業融資以外のサービス内容や税理士・専門家の経歴などにつきましては、こちらよりTOPへ移動の上、会社概要からご確認をお願いします。
合同会社・LLCとは?会社設立のメリットと設立・起業サポート K16 (17/06/27)
合同会社とは平成17年に制定された会社法により、合同会社制度が創設されました。
出資者である社員の全員が出資額を限度とした有限責任制であり、
かつ組合的規律が適用される特徴を有する新しい会社類型です。
創設当初は認知度が低く、株式会社の方が信用度が高いとされ、
それほど活用されていませんでしたが、
近年、その使い勝手の良さのメリットが認識されその設立件数が顕著に増加しています。

株式会社か合同会社か、それとも他の組織で会社設立か迷ったら
【 株式会社との比較 】合同会社の社員と株式会社の株主は、
どちらも有限責任であり、その数に特に制限はありません。
また、株主が取締役となり業務執行を行うのと、
合同会社の社員が業務執行社員となり業務を執行するのは実質は同じです。
しかし、株式会社については、誰でも容易に株主になることができ、
または取引をすることができるように、その利害関係者(株主)の利益を法律によって手厚く保護するため各種規制が多数置かれています。
一方合同会社は、会社の利害関係者の利益を保護する法規制は最低限で、
定款自治によって当事者間で最適な利害状況を自由に設定することが可能になります。
結果、円滑に事業の実施を図ることができるようになります。
代表例が、利益や権限の配分割合を出資額とは関係なく設定することができるというところです。
株式会社では出資割合=権限の割合ですが、合同会社(LLC)ではこれを自由に設定できます。
【 合名会社・合資会社との比較 】近年、知的財産が重要視され、専門的知識やノウハウを持った少数の個性ある出資者が集まり、
自ら経営に参加し定款自治によって柔軟な会社運営を行っているというニーズが高まっています。
原則として、全員一致で定款の変更・その他会社のあり方が決定され、
社員自らが会社の業務執行にあたるという規律が、合同会社、合名会社、合資会社において適用されます。
しかし、合名会社や合資会社の場合、出資社の全員または一部が無限責任を負ってしまうことで、
実際にはあまり活用されていませんでした。
会社法ではこのようなニーズを踏まえ、出資者の有限責任が確保され、
かつ、内部関係について組合的規律が適用される新たな会社類型である合同会社が設立されました。
出資者の有限責任と定款自治による会社運営という点では、
合同会社と有限責任事業組合(以下LLP)は同じです。
相違するのは、法人格の有無、税務上の取り扱い
(合同会社・LLCは法人課税ですが、LLPは法人格がないため事業から生じる損益をその構成員である各組合員に帰属させ所得に課税されます)
合同会社は1人社員が認められるのに対してLLPは複数の組合員が必要である点
合同会社は一部の社員を業務執行社員に定めることができるのに対して、
LLPは全員がなんらかの形で業務の執行に携わる必要がある点、などです。
合同会社にするのか有限責任事業組合にするのかは、適切に判断することが重要です。
合同会社は法人格を有するので、将来株式公開を想定する事業、永続的な事業、安定定期収益が見込める事業が向いています。
一方LLPは、個人や企業の信用を全面に出す事業、
期限を区切ったプロジェクト、ハイリスク・ハイリターンが想定される事業に向いています。

合同会社・LLCでの会社設立のメリット活用例
【メリット活用例 その1】株式会社の場合、株主平等原則に基づき、出資割合に応じて利益を分配するのが原則ですが、
合同会社については、利益の分配を出資者間で自由に取り決めることができます。
優れた技術を開発したベンチャー企業が事業化するにあたり多額の資金が必要となったとき、
大企業との間で合同会社を共同出資により設立することがあります。
ベンチャー企業の技術(知的財産)を評価して、
出資割合の少ないベンチャー企業に対して出資割合に応じないで、
より多くの利益分配されるよう両社が定款に定めて柔軟にとり決めることができるのです。
【メリット活用例 その2】大企業の子会社や外資系企業の日本子会社などで、
親会社の意向や方針により運営され、かつ上場による資金調達の必要がないときに、
合同会社を設立するケースが増えつつあります。
設立にコストがかからず、意思決定のスピードが高まり、
組織運営が柔軟に行われることが認識されてきました。
【メリット活用例 その3】
ファイナンス関連で合同会社が多く活用されています。
その一番の理由は合同会社には会社更生法の適用がない点です。
資金の貸手は貸付に際して担保設定を行いますが、会社更生法の適用があると、
担保権は更生担保権になり回収が困難となるので、資金提供を躊躇されることが想定されます。
また、大規模な資金調達により負債総額が200億円以上になった場合、
株式会社であれば会社法上の大会社になり、会計監査法人の設置等によう多額のコストが発生してしまいますが、
合同会社(LLC)であればその懸念はありません。
【メリット活用例 その4】
小企業においても合同会社が活用されつつあります。
株式会社の場合、少数派株主が株式総会で取締役から排除されると、
会社の経営から締め出されることになります。
いわゆるスクィーズアウトです。
しかし、合同会社では原則として、
社員全員が業務を執行する権限をもつので、スクィーズアウトが生じにくいのです。

匠税理士事務所の合同会社・LLCの会社設立サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に合同会社・LLCの会社設立を承っております。
会社の設立から創業融資による資金調達、助成金の申請代行や会計税務や経営コンサルティングまで 【 起業に必要な全てがそろう会計事務所 】です。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
匠税理士事務所の合同会社・LLCの会社設立サービスの詳細はこちらからご確認をお願いします。
◇法人化・法人成りサービス
商工会議所世田谷・目黒・品川支部と連携したマル経融資 (17/06/21)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー①
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区の企業様や個人事業主様を支援する会計事務所です。
そのため、世田谷・目黒・品川地域の東京商工会議所様と連携を強め、
マル経融資による資金面でのサポートや経営セミナーなどに取り組んでおります。
マル経融資制度とはどんな融資なのか
マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の方々をバックアップするため、東京商工会議所の推薦により、無担保・保証人不要・低金利で融資を申し込める国(日本政策金融公庫)の公的融資制度です。
こちらは起業家向けの融資制度というよりは、
既に会社経営をなさっている方に向けた融資です。

マル経融資制度の融資条件はどうなのか
【融資限度額】
2,000万円
担保/保証人不要です
(信用保証協会の保証も不要)
→通常の金融機関融資では、保証協会の保証が求められますので、保証料がかかりますが、こちらは必要ございません。
【返済期間】
運転資金7年以内
設備資金10年以内
【融資対象】
以下のすべての要件を満たす方
1・従業員20人以下(宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の法人・個人事業主
2・商工会議所の経営・金融指導を受けて事業改善に取り組んでいる
3・最近1年以上、同一会議所の地区内で事業を行っている
4・商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる
5・税金(所得税、法人税、事業税、住民税)を完納している
【マル経融資制度での融資利率】
1.11%(平成29年4月12日現在)
金利が通常の金融機関より低いのは、商工会議所での経営指導というコンサルティングが行われるため、
融資を行う日本政策金融公庫からすればリスクが下がる分は、金利を下げましょうという理由のためです。
ちなみに融資利率は金融情勢により変わることがありますので、詳しくはお近くの支部へお問合せください。
中央区、港区、品川区、大田区、世田谷区、中野区、板橋区、練馬区、江東区、墨田区、足立区、葛飾区については、一定の条件で区より支払利息の一部補助が受けられます。

東京商工会議所での融資、資金使途はどうなのか
【運転資金】
仕入資金
掛金・手形決済資金
給与・ボーナスの支払い 諸経費等の支払い
【設備資金】
店舗・工場改装
営業車両購入
機械・設備・什器等の購入
※
この融資限度額、返済期間の取り扱いは、平成30年3月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります。
マル経融資制度での必要書類
【法人の方の場合】
前期・前々期の決算書および確定申告書
決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の残高試算表
法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)
【個人事業主の方】
前年・前々年の決算書(または収支内訳書)および確定申告書
所得税・事業税・住民税の領収書または納税証明書
見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)
匠税理士事務所の経営サポート・資金調達サービス
匠税理士事務所は、世田谷・目黒・品川地域の東京商工会議所様と経営セミナーなどでの取り組みを通じて連携を強め、
マル経融資制度や経営コンサルティングを通じて世田谷区や目黒区、品川区の企業様・個人事業主様の経営支援に力をいれている会計事務所です。
【ご参考:これまでの経営セミナーの取り組み】
法人向けの経営支援サービスにつきましては、こちらよりご確認をお願いします。
これから起業をお考えの方には、マル経融資制度より日本政策金融公庫様と連携した 創業融資制度が有効ですので、こちらにも対応しております。
世田谷区や目黒区、品川区での会社設立など起業をお考えの方は、
これらの地域を管轄する品川区五反田にあります日本政策金融公庫五反田支店様とも
連携しておりますのでお気軽にご連絡ください。
→ 目黒区や品川区、世田谷区の創業融資や起業の資金調達は匠税理士事務所

起業時の資金調達以外にも起業支援や会社設立なども承っております。

匠税理士事務所の税理士やスタッフの略歴・提携専門家などの詳細は会社概要からご確認をお願いします。
法人化や法人成りをしたら経費が増えて節税対策? (17/05/30)
匠税理士事務所は、世田谷や目黒、品川など東京23区を中心に
個人事業から株式会社にする法人化を支援している会計事務所です。
今回は、法人化をするかご検討中の個人事業主の方に向けて、【 法人化や法人成りしたら経費が増えて節税になるのか 】についてまとめました。
法人化や法人成りしたら経費はどうなるのか
決算日の設定が可能になり、節税対策が打ちやすくなるメリット
個人事業主は決算(締め)は12月31日となります。
10月~12月が閑散期の事業はこちらでもよいのですが、 この時期が忙しいと、この10月から12月に上がった利益に節税対策を打つ時間がなく、 税金がいつも多くなってしまうということが起こりえます。
そこで法人化をし会社の定款に記載すれば、事業の忙しくない時期に決算日を自由に設定することができます。
結果として、忙しい時期に獲得した利益に対して、
閑散期に節税対策をしっかりと行えるということが可能になります。
結果、利益が出てすぐに必要な節税対策をうつというより、
じっくりと時間をとり節税対策を行う方が、内容的にも金額的にもいい経費の使い方になります。

出張手当の支給
出張時の交通費や宿泊費は個人も法人も経費にできますが、
この他、法人は旅費規定を作成し金額を明記することにで出張手当を経費とすることができます。
生命保険の掛金を経費にできる
個人事業主の生命保険料は最高12万円の生命保険料控除という所得控除しかありません。
これに対して、法人の社長に対する保険は、一定の要件と満たした保険に加入すれば、
保険の種類によってはその保険料の一部を経費として扱うことができます。
そして、会社が死亡保険金を受け取ったら一定の死亡退職金が支給できます。
※ただし、この退職金の一部は個人の相続税の課税対象となります。
(相続税でも非課税枠など特例がございます)
退職金を経費にできる
給料に給与所得控除があるように、退職金にも退職所得控除という収入から差し引ける特別な控除があります。
退職所得は給与所得より有利に計算されますから、
退職金をうまく活用することで税金の支払総額を抑えることができます。
会社側も退職金を支払うと経費として認められます。

経費の範囲拡大
個人事業では、家計と事業の分離という観点から、経費として認められる部分が会社に比べ狭くなっております。
法人化することにより、要件を満たせば
・自宅の家賃を受け取ったり
・一定の要件を満たした健康診断について、経費としたり
・ご親族への給与の支給も、個人事業よりは支給の要件が緩やか
といった経費上のメリットもあります。
匠税理士事務所の法人化や法人成り支援サービス
上記では法人化した場合の経費面でのメリットを取り上げましたが、
社会保険の強制加入などデメリットも多くございます。
匠税理士事務所では、これまで世田谷区や目黒区、品川区を中心に法人化を支援させて頂きました。
現在の事業内容やこれからのビジョンを伺って、法人化意思決定のご相談も承っております。
法人化や法人成りの相談会サービス
【 法人化・法人成りに必要な全てがそろう税理士事務所 】をコンセプトに、匠税理士事務所では税務顧問契約をご検討中のお客様に向け法人化や法人成りのご相談を承っております。

ご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
法人化や法人成り支援サービス
◆法人化・法人成りをご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。
【 → 世田谷・目黒・品川など東京での法人化・法人成り 】◆法人化や法人成りについての情報を掲載した情報館のバックナンバーはこちらです。
◆法人成り以外のサービスや料金などにつきましては、こちらからご確認をお願い致します。
【 → 世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】
会社設立の資本金は多すぎても少なすぎもダメK17 (17/05/24)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
起業をお手伝いさせて頂く際に、
【資本金は幾らにしたらいいでしょうか?】
このようなご相談を頂くことがございますので
今回はこちらについてまとめてみました。
そもそも資本金とは何なのか
そもそも起業の際の資本金は、設立にかかる初期費用と一定期間の運転資金と設備資金の合計額というとイメージがしやすいかもしれません。
一定期間というのはどのくらいで売上が立つか、
売上代金(売掛金)回収にどの位期間を要するのか
仕入代金の支払いサイトや在庫の量や販売までの
期間などさまざまな角度から検討しますが、
商売を行う上で必要な3か月から半年分のお金は
用意したいところです。
資本金以外に事業が軌道にのるまでの期間の生活に
必要な資金も確保しておく必要があります。

資本金はいくらがいいのか、資本金を決めるときのポイント
資本金を決めるときにとても重要なことは、
多角的な視点で考えることです。
大きく分けると資本金を決めるにあたっては、
以下の4つのポイントがあります。
1 税金面で資本金を決めるポイント
資本金が1,000万未満の場合、
原則として設立事業年度と翌事業年は消費税を納めなくてもよいことになってます。
(ただし例外あり今回は省略)
また、法人税においても、資本金が1,000万円以下である場合に
利益にかかわらず納めなくてはならない法人住民税の均等割が7万円なのに対して、
1,000万円超になると18万円へと増加します。
このように税金だけ考えると資本金は少ない方が、得なことが多いですね。
2 創業融資など資金調達面ではどうなのか
創業融資はその名の通り
会社を始めたばかりの人が使える融資制度です。
この創業融資は、事業全体に要する資金の1/10から1/2の資本金を準備しているかどうかを
要件としている場合があります。
また、一般的な新創業融資制度では、
自己資金の2倍が融資の目安となります。
【 関連記事 】
つまり創業融資など資金調達は資本金は多ければ多い方が、貸す側としても安心なので得なようです。
一方で資本金が多すぎるとそもそも融資は必要なのかという方向に話が向かいかねませんので、こちらも注意が必要です。
3 得意先開拓で、信用に問題はないか
株式会社や合同会社については、
誰でも法務局で会社概要を入手することができ、
その資本金額を知ることができます。
会社法改正により、1円から会社を設立することができるようになりましたが、
まだまだ資本金が会社の信用度を図る基準となっていることは否定できません。
新規取引の際に謄本を取り寄せて資本金が極端に少ない場合、
財務的に不安定で、信用力が弱い会社とみられる可能性があります。
卸売り業などで仕入れを1か月後など信用取引(掛取引)するには、
資本金が1,000万円あるような会社以外は付き合わないという場合もあるようです。
4 各種許認可の取得で資本金がネックにも・・・
許認可によっては、自己資本金額が要件になっている場合もございます。
許認可を受けられずに、
事業がスタートできないということがないように事前に確認しておきましょう。
【 資本金制限がある代表的な業種の例 】
旅行業・・・・・・・・300~3,000万円
一般建築業・・・・・・500万円
優良職業紹介事業・・・500万円
一般労働者派遣業・・・2,000万円×事業所数

匠税理士事務所の会社設立支援サービス
これからのビジョンをお伺いした上で、
上記のポイントや、業界特有の論点、
これまでのノウハウを用いまして、
・資本金は幾らにされた方がよろしいか
・会社の役員構成や決算時期はいつ頃がよろしいかなどをご提案致しております。
会社設立後の経理や経営支援のみならず、助成金の申請代行から創業融資による資金調達サポートなど起業に伴う全てがそろう税理士事務所・会計事務所を心がけております。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
起業や創業の味方!日本政策金融公庫とはどんな組織 (17/05/19)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
第13回
【 日本政策金融公庫、名前は聞いたことがあるけど、どこにある銀行? 】
このように思われるのも無理はないと思います。
日本政策金融公庫は、国が出資して作った組織で、
創業・起業など実績がないため民間金融機関から融資を受けることが難しい新規開業を目指す個人や法人に、
国の政策のもと、経済の発展や地域の活性化を目的として融資を行ってくれる政府系金融機関です。
そのため、通常の銀行などのように預金業務は行っておらず、貸出のみを積極的に行っているため、
ATMなどがなく名前は聞いたことがあるけど・・・・
ということが多いようです。
組織の存在理由が他の金融機関と異なるため、
新しい事業を始める人や中小企業にとっては非常に利用勝手のよいプランが豊富に用意されています。

日本政策金融公庫の業務概要
日本政策金融公庫の前身は次の政府系金融機関です。
・国民生活金融公庫
・農林漁業金融公庫
・中小企業金融公庫
・国際協力銀行
その業務内容は前身を引き継いだもので、
「国民生活事業」「中小企業事業」「農林水産事業」「危機対応等円滑業務」の4つに大きく分れてます。
このうち、国民生活事業の概要は以下の通りです。(平成27年度実績)
・融資先の約9割が従業員数9人以下、4割が個人事業主
・融資先数は88万企業で、1先あたり平均融資残高689万円
・創業前および創業後1年以内の方への融資件数は26,465件
・創業融資により9万5千人の雇用を創出
・税務申告を2期終えていない方へ無担保・無保証人で融資する「新創業融資制度」の融資実績は、21,007先
このように、国民生活事業では創業支援に力を入れており、
起業を目指す人々の力強い味方であり、創業後もお世話になる可能性の高い金融機関なのです。

創業支援に関する融資制度
【新規開業資金】
対象者・・・ 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
融資限度額・・7,200万円(うち運転資金4,800万円)
融資期間・・・設備資金20年以内(据置期間2年以内) 運転資金7年以内(据置期間2年以内)
【女性、若者/シニア起業家支援資金】
対象者・・・ 女性または35歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方
融資限度額・・7,200万円(うち運転資金4,800万円)
融資期間・・・設備資金20年以内(据置期間2年以内) 運転資金7年以内(据置期間2年以内)
【再挑戦支援資金】
対象者・・・ 廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
融資限度額・・7,200万円(うち運転資金4,800万円)
融資期間・・・設備資金20年以内(据置期間2年以内) 運転資金7年以内(据置期間2年以内)
【新事業活動促進資金】
対象者・・・ 経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方
融資限度額・・7,200万円(うち運転資金4,800万円)
融資期間・・・設備資金20年以内(据置期間2年以内) 運転資金7年以内(据置期間2年以内)
【中小企業経営力強化資金】
対象者・・・ 新事業分野の開拓のために事業計画を策定し、
外部専門家(認定経営革新等支援機関)の指導や助言を受けている方
融資限度額・・7,200万円(うち運転資金4,800万円)
融資期間・・・設備資金20年以内(据置期間2年以内) 運転資金7年以内(据置期間2年以内)
実際の創業融資の状況はどうなのか?
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都の起業支援をサポートしておりますが、
実際、創業融資の実行割合や一件当たりの融資金額について、
日本政策金融公庫様の起業家への資金面でのサポートは手厚いといえます。
やはり、国がバックにたって起業を支えるという姿勢の表れですね。
一方で新規創業では1,000万円が一つの上限になることが多いので、 上記の制度の上限一杯まで融資してもらえるという事業計画では厳しいかもしれません。もちろん、返済実績を重ねていき事業が拡大していけば、限度額が2,000万などドンドン増えていくのも事実です。
その他の、創業融資のお役立ち情報(バックナンバー)をご覧になりたい方は、こちらです。
創業融資の情報館 バックナンバー

匠税理士事務所の創業融資サポートサービス
匠税理士事務所では日本政策金融公庫の品川区にある五反田支店様と連携して、世田谷区や目黒区、品川区での起業をサポートしております。
創業計画書の作成から当日の面談立ち合いまでしっかりとサポート致しますので、安心してご相談下さい。
創業融資サポートサービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。
【 → 目黒区や品川区、世田谷区の創業融資や起業の資金調達は匠税理士事務所 】

起業支援サービス一覧
会社設立サービス...これから会社を作るお客様向けの会社の設立・経理や税金、経営のサポートサービス。
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
給与計算サービス...給与計算の代行や、社会保険の加入手続き、人事労務のサポートサービス。
助成金サービス...正社員化や社員教育についての助成金代行とコンサルティングサービス。
資金調達以外の会社設立や助成金などの起業支援サービスや、経営支援サービスの詳細につきましては、TOPへ移動の上ご確認をお願いします。
親族外への事業承継はどんなやり方や方法があるの? (17/05/11)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>親族外への事業承継
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第6回 遺産分割協議と相続税の申告
第7回 相続税の税率と税額計算の仕組み
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。
弊所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に地域密着の会計事務所です。
今回は、ご高齢の経営者の方で、
【自分もいい歳だし、そろそろ事業を他の人に任せたい。】このような思いで事業承継をご検討される方に向けて、
事業承継をするときには、
どのようなやり方があるのかについて簡単にまとめてみました。
事業承継の種類にはどんなものがあるの?

①現オーナー経営者の子どもや兄弟姉妹などの親族が後継者となる【 親族内承継 】
②オーナー経営者の親族に後継者として相応しい人物が居ない場合や、
親族以外で事業を承継してほしいという人物がいた場合に、
自社内の親族以外の役員または従業員が後継者となる【 親族外承継(従業員等に対するもの)】
③オーナー経営者の親族や自社の従業員に事業を承継する適当な後継者が居ない場合に、
会社そのものを売り買いする【 親族外承継(M&A) 】 の3種類があります。
M&Aによる親族外承継にはどのようなやり方があるの?

オーナー経営者の親族や自社内に事業を承継する候補がいない場合において、
会社の事業を存続させ、従業員の雇用を維持し取引先の仕事を確保するため、
あるいは経営者自身の老後の生活資金を得るために事業承継の選択肢としてM&Aを行うケースが増えています。
この場合のM&Aの代表的な手法としては株式譲渡と事業譲渡があります。
事業承継の手法である株式譲渡とはオーナー経営者が会社の株式をすべて買い手に譲渡し、
その対価として金銭を取得する手法です。
事業譲渡とは何か、そのメリットは
売り手の会社がその事業の全部または一部を他の会社に譲渡する契約を結び、
事業売却の対価として買い手側の会社から金銭を取得する手法です。
売り手側の会社に簿外債務(連帯保証債務、公租公課の追徴金・延滞金など)の存在が懸念される場合に、
会社そのものをM&Aしてしまうとこれらを引き継ぐことになるので、
あくまで欲しい事業部分のみを売買したいときに利用される手法です。
その他の親族外への事業承継手法
【 吸収合併 】
吸収合併とは、合併により消滅する会社の権利義務のすべてを合併後存続する会社に承継させることをいいます。オーナー経営者が合併後存続する会社(買い手となる会社)の株式を取得することにより手続きを行います。
【 株式交換 】
株式交換とは、自社株式と他社株式とを交換することで、その他社を自社の100%子会社とすることをいいます。事業承継の手法として行う場合、売り手側の会社は買い手側の会社の100%子会社となります。オーナー経営者は会社売却の対価として買い手側の会社の株式を取得することになります。
【 吸収分割 】
吸収分割とは、会社がその事業に関して持つ権利義務の全部または一部を分割したのちに既存の会社に承継させることをいいます。
匠税理士事務所の世田谷や目黒、品川での事業承継サービス
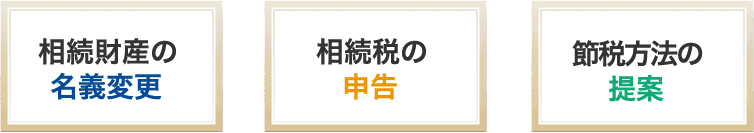
匠税理士事務所は世田谷区や目黒区、品川区のお客様を中心に事業承継に関する税務コンサルティングを行っています。
規模の大きな事業承継につきましては提携している事業承継専門の税理士・公認会計士と連携して対応致しておりますので、会社の状況に応じて最適なストラクチャーの検討、提案を行うことも可能です。
事業承継の準備として、生前贈与などを活用のご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
所属税理士や提携先の専門家につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
→ 自由が丘の税理士は匠税理士事務所|世田谷区や目黒区,品川区対応
事業承継以外の経営支援サービスなどについては、
TOPページへ移動の上、ご確認お願い致します。
会計事務所のインターンやインターンシップ採用求人 (17/05/10)
税理士事務所や会計事務所で将来働くのか、
大手上場企業で働くのか考えている。
このような大学生や専門学校生など学生の方もいらっしゃると思います。
現在は好景気で就職しやすい状況なので、多くの学生は安定している大手企業に就職される方が多いのですが、
このような景気の中で国家資格をとってでも税理士事務所や会計事務所で将来の就職を検討されるのは、
大きく2つの理由があるからではないでしょうか。
1 税理士や会計士になれば組織の一部ではなく、個人の能力で純粋に評価される 2 不景気などになっても資格などスキルがあると生き残れるいずれも個を磨くことで、社会から評価されるということになるわけですが、
これは良い点もあれば厳しい点もあります。

税理士事務所や会計事務所のインターンや就職の良い点
お客様には、〇〇株式会社さんではなく、
〇〇さんと個人名で言われることが多いですが、
これは会社という看板の前に税理士や会計士として、
どれだけお客様の役に立てるかということが求められるということです。
お客様の役に立つには、
1人間的に魅力【マインド】が必要であり、
2お客様の問題や悩みを解決できる技術力【スキル・テクニック】
の両面が求められます。
こうした両面を実務や試験勉強・自主学習を通じて磨くことになるわけですので、
20代は遊びより自己研鑽が多くなります。
こうした過程をえて個人の能力は高まり、30代に入ると税理士や会計士としてお客様に
評価して頂けるようになります。
このように厳しい道のりですが、お客様の評価が全てで、 学閥や縁故などもないという点ではフェアな業界だと思います。人工知能・AIの発展で税理士・会計士の仕事がなくなるといわれることもありますが、
お客様は単純に会計・税務の代行をしてほしいわけではなく、
自分の問題を一緒になって解決して欲しいというのがニーズですので、最後は人間性が重要。
医師の仕事をロボットが全てやることはできないように、
税理士・会計士もスキルとマインドを磨き、お客様の問題に取り組むことでその必要性は残るものと考えます。
会社員になって、
・部長や課長のポストが人あふれててあかない・・・・
・会社がM&Aに失敗して、業績が危うくリストラを始めた・・・・
このような外的な環境に左右されることなく、
【自分の努力次第で、お客様は正当に評価して下さる】のが、
最大の魅力かもしれません。

税理士事務所や会計事務所のインターンシップや就職でよくない所
税理士事務所や会計事務所のインターンシップや就職をお考えの方で、
税理士事務所や会計事務所はブラック体質ではないのか?
このようにお考えの方もいらっしゃると思います。
仕事がチーム化されていなかったりして、個人に全て担当させる事務所では、
残業時間が多かったりもするようです。
また、残業代が支給されない・給与が低いなど待遇面でも問題があるところも多いようですが、
これは経営者である税理士・会計士に利益配分感覚に問題があるのかもしれません。
【参考ページ:ブラックな税理士事務所や会計事務所の見極め方】
匠税理士事務所のインターンやインターンシップ採用・求人情報
匠税理士事務所では、インターンやインターンシップ採用を通じて、
大学生や専門学校生など学生の方の採用を行っております。
仕事は全てチームで担当しますので、繁忙期を通じて残業は一切ございません。
また、利益配分を重視しておりますので、アルバイトスタッフにも残業や有給制度があり、
時給などの待遇も他の税理士事務所や会計事務所より高い設定になっております。
求人面では、【 働きやすさNo1の税理士事務所 】を使命に、
職場環境・待遇面の改善を随時行っており、
結果として【 ここ5年間で退職者ゼロ 】という評価を頂いております。
インターンやインターンシップ採用では、1日5時間で週3日からの勤務が可能です。
・時給は1,100円~ (交通費は全額支給)
・データ入力と書類の整理など
・応募資格は、税理士試験簿記論及び財務諸表論合格済みの方(学部は不問)
・勤務地 目黒区自由が丘1-4-10-404
インターンシップ終了後に、勤務を検討される方については、
こちらより採用求人情報をご確認下さい。
またインターンシップをご検討中の方は下記より応募方法をご確認ください。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の匠税理士事務所・会計事務所の求人採用

また所属税理士やスタッフなど匠税理士事務所の概要については下記よりTOPへ移動の上ご確認ください。
人材採用や求人面でも株式会社にする法人化や法人成りは効果あり (17/05/08)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
今回は法人化と採用の関係性について記載します。
労働人口の減少などに伴い人手不足と騒がれてしばらく経ちましたが、この傾向は続きそうです。
こうした環境下で人材採用や求人活動を行ってもなかなかいい人がとれない、
このように悩まれる経営者の方も多いと思います。
そこで今回は、個人事業主の形で事業をされている方に向け、個人から会社にする法人化・法人成りが採用活動や求人に与える影響をまとめました。

株式会社などにする法人化や法人成りが採用や求人に与える効果とは
『 安心・安定を求め、就職活動求職する人が多い 』
日本人は特にこの傾向があり、昔から公務員は
就職活動では根強い人気です。
現代では、生活の安心や安定を求めて、
個人事業主形態の下に勤務するより、
低収入でも株式会社などの会社の「正社員」として働きたいと思っている人が多くなっています。
また、「社会保険」を条件に求職・就職活動をしている人も少なくありません。

個人事業主の方は、健康保険を市区町村が管轄している「国民健康保険」でまかない、
年金は「国民年金」のみに加入されているケースがほとんどです。
個人事業主の場合は、原則常時5名以上を雇い入れている一部の業種に限り、
社会保険加入義務があるにすぎないからです。
逆をいうと特に社会保険への加入が義務付けられているわけではないため、
積極的に個人事業で社会保険に加入しているという方はまれです。
また、個人事業の場合、従業員は社会保険へ加入できるものの、事業主本人は「対象外」です。
こうした理由から、人件費が増えてしまう社会保険への加入を行わない事業主が多い傾向があります。 これは経営者側の理由であり、勤務する側からは、【社会保険加入を望む】のが本音かもしれません。
一方、会社の場合は、たとえ社長1名の会社でも社会保険への加入が義務づけられています。
結果、経営者側が社会保険への加入を望もうと望まなないも関係なく加入を余儀なくされます。
これは勤務する側としては、要望と一致することになります。
こうした理由から、「会社組織はないところは、社会保険に入っていない」という固定概念を、
求職者の多くが持っているので、ハローワーク等での求人募集では、会社の方が有利に社員を集められる傾向があります。

優秀な人材を採用するためには、会社であることは重要
『 特に大企業からの転職者はシビア 』
大きな企業で働いていた方は、福利厚生制度、有給休暇、残業手当など、
中小企業では当たり前ではない権利が、当たり前に利用できる環境に慣れてます。
(大企業で働いていた=優秀でないのですが、大企業経験者は比較的どの会社も採用したがる傾向があるのも事実です。)
このような環境で勤務してきた人を含め、職を探している人のほとんどが求めるものは、
【好給与・私生活充実休暇・地位やりがい】です。

これらすべてを用意することは難しいにしても、
どれを重視するかという選択を経営者側が行うのは重要です。
その際に会社の形をしていると、優秀な人が応募してくる可能性が少し高くなります。
その理由として社会保険は原則完備されてますし、
会社組織にしているため、労働基準法に準じていると考えられるからです。
【好給与・私生活充実休暇・地位やりがい】といった
労働条件がほぼ同じなら、やはり最後はしっかりとしてそうな組織で働きたいというのが、働く側の気持ちでしょう。面接まで話が進めば、経営者の人柄や仕事内容にほれて、優秀な人材が入社してくるでしょう。
個人より会社に優秀な人が集まるのは事実です。
匠税理士事務所の法人化や法人成りサービス
匠税理士事務所では目黒区や品川区、世田谷区を中心に法人化や法人成りを行う会計事務所です。
株式会社や合同会社の会社設立や、会社設立後の経理や税務手続きの代行、
社会保険の加入手続きや給与計算、各種許認可申請や融資による資金調達など
【 法人化に伴う全てそろう事務所 】です。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

匠税理士事務所の所属税理士や提携専門家などの詳細につきましては、こちらです。
【 → 目黒区自由が丘の匠税理士事務所 】
◆法人化相談会は 法人化・法人成り相談会 からご確認をお願い致します。
◆法人化や法人成りのメリットやデメリットはこちらです。
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】◆法人化や法人成り以外のサービスはTOPページからお願い致します。
【 → 世田谷区の税理士は匠税理士事務所 】
◆法人化や法人成りの法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
執筆者・文責:税理士 水野智史
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
法人化や法人成りを行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
法人化・法人成りのタイミング、売上・年商の目安ラインは? (17/04/29)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は法人化・法人成り支援を行う事務所です。
3月に確定申告が終わって、
個人事業を行われている方同士で会うと、
【 事業も大きくなり、そろそろ会社しようか・】 【 消費税負担も重いし会社にしようかなぁ・】このように個人事業を行われている方同士で、
確定申告が終わった後に
法人化や法人成りのタイミングや目安につき
お話になられることもあるかと思います。
そこで今回は、この個人事業を株式会社にした場合の法人化・法人成りについて節税など何が特に有利になるのか、どれくらいの規模になったら、いつのタイミングで検討すべきかをまとめてみました。

個人事業を法人化するのは年収・売上がいくら?どのタイミング
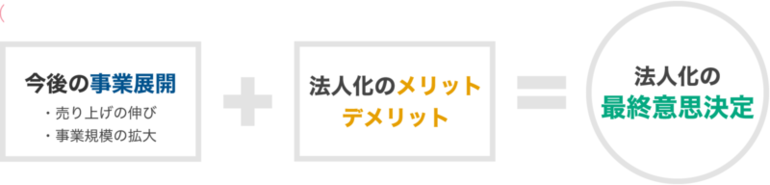
【 個人事業を株式会社にする法人化・法人成りは、年収・年商幾らから検討時期ですか? 】
このようなご質問を頂く機会がございます。
タイミングを考える際は、お客様の事業がどれだけの人員を必要とされる事業なのか、
現在の利益状況と個人の税額はどれくらいなのかを伺うようにしております。
その理由は、年商1,000万円を超えたことによる
消費税の節税効果は、最長で2年。
つまり限りがある一時的なものです。
一方、社会保険などの負担増は会社に
社員さんがいる限り継続して生じます。

消費税免税効果のみを狙い法人成りをすると、
免税期間が終わり消費税節税効果がなくなると、
社会保険の負担増のみ残ってしまったので、
法人成りしなければ良かった・・・・
ということになりかねません。
そこで、
1 法人化で毎期継続的に節税できそうな金額 (個人の利益と税額の状況をもとに試算) 2 法人化で発生する社会保険強制加入など継続的なコスト増1 > 2 であれば、継続的に法人化のメリットがあるというわけで、ご提案を致します。
会社にするタイミングは年収・売上が幾らでなく、
税金や社会保険の面では・個人の利益と税金が増えてきたこと
・人員があまりいらないので社会保険など加入によりコストが増加しないといった視点に、
【 法人化・法人成りで新規得意先が増える 】などの経営面での判断を加えたタイミングで
決断するとよい結果につながります。
つまり【 長期的・総合的視点が重要 】です。

株式会社や合同会社など会社にするタイミングは
これから事業が拡大し、年商や売上が伸びる中で、
上記の社会保険増加等のデメリットと、
新規得意先増・人材採用等メリット+節税メリット
を総合的に考えたうえで、
今後の時流を考え、【 間違いないタイミング 】と感じたときともいうことができます。

それでは、法人化したときのメリットやデメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか。
個人事業を株式会社にする法人成り、税金面での節税メリットとは

法人化して会社にすると税率が低くなる?
株式会社や合同会社など会社設立をすると、
代表取締役社長といえども、税法上では会社から給料をもらうサラリーマンになります。
所得税の計算上、サラリーマンの所得金額は収入金額から給与所得控除を引いて求めます。
この給与所得控除は無条件で所得から差し引くことができる概算の経費のイメージです。
そうなると、実際にかかった経費は
会社の利益・所得から差し引くことができ、
その上、実際に支払いがなくても給料の一定割合を給与所得控除として個人所得から追加的に差し引くことができるので、社長個人の所得金額は低くなり、かかる税金も安くなります。
所得税が年収が多くなれば税率も上がる累進課税なのに対して、
法人税はほぼ一定ですから、所得が大きくなればなるほど個人事業の場合の事業主の所得税と、
法人化した場合の会社の税金と社長の所得税の合計額の差額は大きくなり節税効果が出てきます。
【 会社の税金の計算構造 】
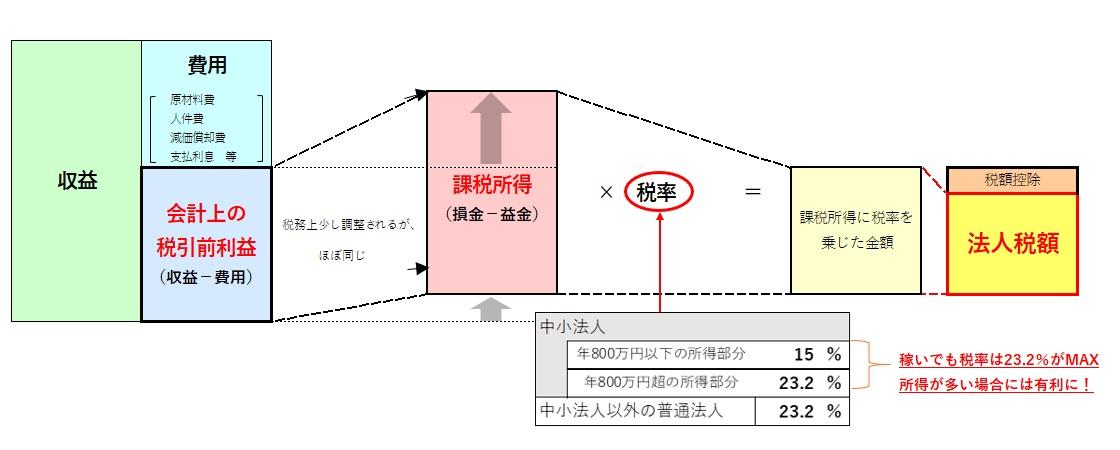
【 個人事業の税金の計算構造 】
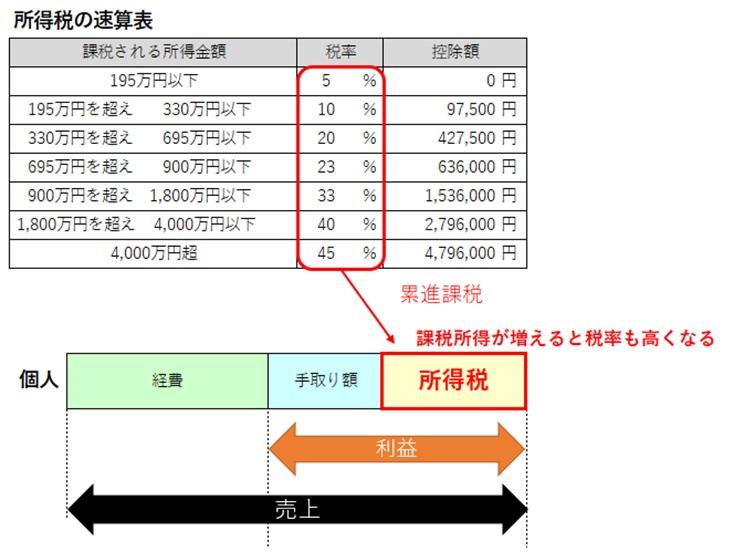
また、サラリーマンになることで、
ほとんどの業種の個人事業主にかかっていた個人事業税(原則5%)の適用がなくなります。
会社には事業税や地方特別税が課税されますが、
自分の給与をとって会社に所得が残らなければこれらの税金は0円です。
※ただし、役員報酬は原則事業年度の途中で変更することはできません。
会社の利益が思った以上に出そうなので役員報酬を上げてしまったりすると、
上げた分は会社の経費として認められず会社で税金がかかる上に、
個人が給料を受け取ったことは変わらないので個人の所得税や住民税の課税も受けてしまうことになるので注意しましょう。
家族への給与を上げることで世帯の税金が安くなる
所得税は収入が高い人ほど税金が高くなる
累進課税の仕組みです。
ですから、労働面でも精神面でも不可欠な助けとなる家族や親族に適正な給料を支払うことで、
事業主だけが給料を多くする場合と比べ、世帯の税金の合計額は低くなり節税することが可能です。
個人事業主で青色申告を行っている方は、
専従者に給料を支払うとき、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。
この届出書に記載した給料以上を支払っても必要経費にはなりませんが、
法人化すれば、この届出は不要となります。
そのため、次の年の給料を増やしたり、
株主や役員ではない親族へ賞与を支給したりすることができるようになります。
つまり届出を出すタイミングを考えなくてよく、会社の方が、親族へ給料を経費として計上できる自由度が高くなるのです。
配偶者控除や扶養控除の適用がある
サラリーマンの所得税の計算は、収入金額から給与所得控除を引いた所得金額からさらに
「所得から差し引かれる金額」を引いて課税所得を計算します。
「所得から差し引かれる金額」の中の「配偶者控除」や「扶養者控除」については、個人業を営んでいる方の青色専従者でその年に一度でも給料をもらっている人や、
白色申告での専従者の方は、所得に関係なくこれらの対象とはなりません。
一方、会社から給料をもらう立場になると、配偶者や扶養家族は、仕事に専従していても
配偶者控除や扶養控除の対象から外れません。
ですから、所得基準(103万円以下)を満たせば、
配偶者控除や扶養控除の最低38万円を社長の所得から差し引くことができます。
【 ※個人事業主には、配偶者の収入が103万円を超え141万円未満の場合適用される配偶者特別控除の適用もありません。 】
平成30年1月より配偶者控除の適用できる年収要件が現行の103万円以下から150万円以下に引き上げられます。
また、配偶者特別控除も150万円超から201万円まで控除額が段階的に減ることになり、
現行の配偶者特別控除を拡大する形で行うこととなります。(但し、納税者本人の所得制限あり)
給与以外のその他メリット
【消費税の免税タイミング】
消費税は、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、
消費者から預かった消費税があってもその納税が免除されます。
会社設立後の第一期と第二期のタイミングではそもそも前々事業年度がなく、
このうち資本金が1,000万円未満である会社には消費税が免除され、大きな節税効果をもたらします。
ただし第二期の消費税判定タイミングでは、
第一期の半年間の売上または給与支払額が1,000円超える場合に例外があります。
また、第一期の半年間の売上または給与支払額が1,000円超えそうな場合にも対応策がありますので、
詳細はこちらからご確認をお願い致します。。
【赤字の繰越控除の期間が長くなる】
事業者が赤字となってしまった場合、その赤字を翌年度以降に持ち越して、
黒字になった事業年度(会計期間)の所得と相殺してあげましょうという制度がありますが、
個人事業主の持ち越しの期間が3年なのに対して、
株式会社や合同会社など会社にして青色申告をしている事業者は9年(平成29年4月1日以降に開始する事業年度に生じた欠損金については10年)に延びます。
匠税理士事務所の法人化タイミング相談会・法人成り支援
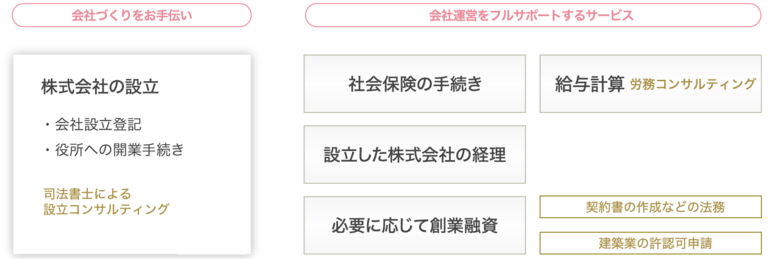
匠税理士事務所は、世田谷や目黒、品川など東京で個人事業を株式会社に合同会社にする
法人化のタイミングや目安のご相談を通じて法人成りのお手伝いを行っている会計事務所です。
・これまで確定申告を自分でやってきたが、法人成りのタイミングを検討している。
・法人化の売上や年商の目安やそのタイミングや流れについて一度専門家の話を聞いてみたい。
このような方からのご相談をお待ちしております。
株式会社の設立、社会保険手続きや給与計算、設立した後の経理、創業融資まで法人成りに必要な全てをサポートします。
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
法人化のタイミングや目安相談会の詳細はこちらからご確認をお願い致します。

法人化タイミングや目安等の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
タイミングや目安の無料相談会でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
サービス
【1】世田谷や目黒、品川での法人化や法人成りは匠税理士事務所 の詳細はこちら
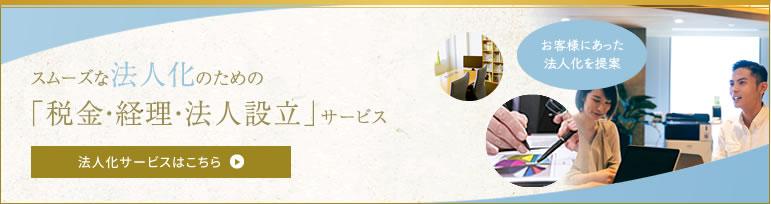
◆法人化のタイミングや目安以外に法人成りについての情報を掲載した法人成り情報館のバックナンバーはこちらです。
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
担当税理士や提携の専門家につきましては、こちらよりTOPへ移動の上でご確認をお願いします。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
補足:法人化のタイミングや目安で検討すべき法人成りには上記以外にいくつかの長所・短所がありますが、
説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
法人化や法人成りを行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
会社設立で会社名・会社の名前である商号の決め方は?K22 (17/04/25)
匠税理士事務所のWEBサイトへご訪問ありがとうございます。
弊所は、世田谷区や目黒区や品川区を中心に会社設立や創業融資など起業支援に力を入れている会計事務所です。
弊所では起業に関するお手伝いをする中で、
これから株式会社や合同会社など会社設立をして起業したいう方からご相談を頂いた際に、
最低限以下の2つを決めて頂くようにお願いをいたします。
1 会社名(商号=会社の名前) 2 本店所在地【関連記事:会社設立など起業時に事務所物件や会社物件を決めるポイント】
資本金などは、お客様からヒアリングをさせて頂ければ、自己資金と税務上優遇額のバランスなどですぐに決まることが多いのですが、上記2点は中々すぐに決まりにくい事項なので事前にじっくりと考えて頂きます。
もちろん、一度決めたら変えられない事項ではないのですが、
これらの変更は登記事項になりますので登記料ももったいないですし、
何より得意先にご迷惑をかけてしまうので、変えるものもなかなか大変です。

会社名(商号=会社の名前)を決めるときのポイント
商号とは会社名です。事業コンセプトや将来のビジョンを年頭におき、
自分だけでなく協力者の想いのつまった会社名を考えましょう。
取引先に覚えてもらいやすいかというマーケティング面や、
その名前でドメイン取得可能か、という点まで考慮するとよいでしょう。
長すぎるとかっこがよくても、覚えてもらえません。
すぐに覚えてもらえて、仕事を任せても安心というようなイメージがわくとベストです。商号・会社名の決定のルール
使用できる文字の種類
ひらがな・カタカナ・漢字のほか、アルファベットやアラビア数字、「&」「’」「,」「‐」「.」「・」
使用できない文字の種類
読み方が統一していない文字 「@」「!」「?」、ローマ数字「ⅰ」「ⅱ」
会社形態を表す語を入れる
株式会社、合同会社等会社の種類を表す語を商号の頭か末尾につけなければなりません。
前につけるか後につけるかは、見栄えや言いやすさで決めましょう。
特殊業種のみに使用できる語句がある
銀行・信託・農業協同組合・保険等、実際にこれらの業種を行う会社のみ使用できます。
会社の部門を表す語句は使用できない
支店、支部、支社、事業部など、会社の一部門を表す語句は使用できません。
同一住所で同一商号は使用できない
同一住所で同一商号の会社を登記することはできません。※注
※注:同一商号の調査
以前は、同じ地域に似たような会社の名前がすでに存在していると、
社名を思いどおりにつけられませんでした。
しかし、平成18年の会社法改正にともない、同一住所で同一会社名でなければ問題なしとなりました。
とはいっても、著名な会社と同一または類似の商号の使用は不正競争防止法で禁止されています。
たとえ著名でなくても、同業者の商号と同一または類似の商号を用いることは、
消費者の混乱をまねくとして禁止されています。
ときには他社から訴えられることもあるので事前に調査して回避した方がよいでしょう。
類似商号は、法務局の登記所に設置されている専用端末で検索するか、
インターネットのオンライン登記情報検索サービスを利用して調査することができます。
・会社のルールである定款に、どのようなことを盛り込むべきか。
→関連記事:会社設立時の定款に記載する目的や会社名を決めるポイントとは
・役員構成はどのようにしたら、トラブルがすくないか。
→関連記事:会社設立時の役員(取締役)・株主などパートナー選びは慎重に

匠税理士事務所の会社設立・起業支援サービス
匠税理士事務所では、これから株式会社や合同会社など会社設立をして起業したいう方に
ご要望をしっかりと伺って、お客様が作りたい会社ができるよう
一件一件、お客様のご要望に沿った会社設立のコンサルティングと代行を致しております。
会社設立に必要な事項を説明し、お客様のご要望と各法律上のポイントを説明致します。
こうしたヒアリングをもとに、法務・登記の専門家である提携の司法書士が登記を代行させて頂きますので、
お客様のお手間をできる限り最小限に抑えます。◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
税理士 目黒区、世田谷区や品川区の会計事務所匠税理士事務所TOPへ ...TOPページへ
また、株式会社や合同会社など会社設立をした後の社会保険の加入手続きや、経理の代行、助成金を検討したい場合のコンサルティングも承っております。
会社設立など起業時に事務所物件や会社物件を決めるポイントK18 (17/04/19)
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に起業支援を行っている会計事務所です。
今回は、会社設立などこれから起業をお考えの方に向けて、
事務所物件や会社物件を決める際のポイントについてまとめてみました。
事務所物件を借りる場合のポイント
どこに事務所や会社の本店を置くのかは、集客や企業イメージに大きな影響をあたえます。
以下のチェックポイントを考慮しながら検討しましょう。
ただし業種によってどのポイントを優先するかは異なってくるので注意しましょう。
【 会社物件選びのチェックポイント 】
・交通アクセスの利便性はよいか ・家賃は予算内におさまっているか
→ 起業して生き残ることが最優先、固定費は出来る限り抑えるのが重要です。
一方で事業が拡大した場合にも当面はこの間取りで対応可能かどうかも検証しましょう。
・顧客ターゲット層の人口は多いか→地域ごとに特色があり、各地域を管轄する行政機関も様々な取り組みを行っています。
自社のお客様が多い地域を拠点とすると交流会等人脈を作りやすいというメリットもございます。
・近隣に同業の競合店はないか飲食店や美容業など商圏が狭い業種は特に注意が必要です。
・電力供給量は十分か→ IT業などPCを多く利用される方は、作業に大きなブレーキがかからないよう特に注意です。 ・携帯電話の電波が届きやすいか、またインターネット環境は整っているか
(データ転送量が多いIT業の場合には、回線を入替えることが可能かどうかも検証しましょう。)
候補となる物件を見つけたら、
必ず実際に現地周辺を歩いて、人の流れや動線、周囲の環境などを確認しましょう。
しっかりと見極めて契約を検討しましょう。

事務所物件や会社物件をシェアオフィスにする場合
自宅とは別に事務所を借りることがメジャーな方法ですが、
敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用や毎月の家賃を自己資金でまかなうのはかなりの負担となります。
最近では、多くの事業者が共同でフロアを利用するシェアオフィスの形態も広まっています。
事務所経費をあまりかけず、
安価で一等地などにきれいなオフィスを持つことができます。
椅子や机など購入する必要がなく、
電話対応サービスなどを利用できることもあります。
社会保険や雇用保険の加入時に障壁となる可能性があります。
また、契約で決められた回線使用料やコピー代等の付帯費用も入れると、
結果的に割高になる可能性もあるので注意しましょう。

バーチャルオフィスを事務所物件や会社物件にする場合
ワークスペースを設けずに住所と会議室の利用権だけを借り受ける
バーチャルオフィスの形態も台頭してきました。
非常に安価な賃料で、一等地に住所を設定でき、
電話対応サービスなどを利用できることが多く、自宅住所を公開する必要がありません。
上記シェアオフィスのデメリットがあるほか、バーチャルオフィスという名前の通り、
実在性に疑問を持たれることもあるので、
創業融資の借入審査に通らない可能性もあります。
年々規制が厳しくなっているため、バーチャルオフィスを選択する際には十分な検討が必要です。
共同事務所の形式で事務所運営をする場合
同じ事業または補い合うような事業を営む事業者が共同で事務所を開けば、集客力アップの効果を期待でき、家賃や光熱費などを節約できます。
ただし、費用について不公平感が出ないよう負担基準を明確にしたり、応接室等共用部分の使用規定を細かく定めたりしておかないと、
共同事務所のパートナーともめる原因となります。
間借りを検討する場合
知人や取引先のデスクを借り、そこで仕事をするのが間借りと呼ばれる形態です。
前職の社長や親戚が応援してくれる場合等、親しい間柄でよくみられるケースです。
この場合転貸にならないか大家さんによく確認しておきましょう。
初期費用や賃料が無料もしくは安価でよいのですが、他者が借りているオフィスのため、レイアウトの設計や会議室の使用などに自由度がなく、貸主に気を遣うのが難点です。
匠税理士事務所の会社設立や創業融資などの起業支援サービス
匠税理士事務所は、株式会社・合同会社の会社設立の代行や、創業融資などの資金調達といった起業支援に力をいれている会計事務所です。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
これから世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区で起業をお考えの方で、会社設立や創業融資などをご要望の方はお気軽にお問い合わせください。
日本政策金融公庫の創業融資とは?成功のため6つのポイント (17/04/15)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
第14回 日本政策金融公庫とは、日本政府が100%出資の政府系金融機関です。
こうしたことから、日本政策金融公庫の創業融資は税金を使った公的な融資と考えられ、
新しい産業を生み、育てることを政策的に行うという目的を持っています。
このような目的・背景があるので、普通の金融機関ではあまり積極的ではない起業支援についても、日本政策金融公庫では積極的に起業家への融資に取り組んでいます。
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を管轄とされている品川区の五反田にある
日本政策金融公庫の五反田支店様と連携して世田谷や目黒、品川などご近所での創業融資・会社設立など
起業支援に力を入れている会計事務所です。
今回は日本政策金融公庫の創業融資をご検討中の方に向けて、
日本政策金融公庫の創業融資とは、どのような制度でそのポイントについてまとめてみました。
日本政策金融公庫の創業融資はどんな特徴があるのか

日本政策金融公の創業融資の特徴は、何よりも融資が行われるまでのスピードです。
融資実行までのスピードが早いことで、この融資制度を利用すれば、
物件取得や事業開始などの起業準備に関わる資金調達を素早くおこなうことができるため、
ビジネスチャンスを逃さずに進むことができます。
これは起業家にとっては、とてもありがたいですね。
ただし、金融機関からみるとリスクの高い融資でもあります。
起業間もない実績のない会社への創業融資ですから、
貸したお金が返ってこないということも十分に想定されます。
こうしたことから、他の金融機関では、創業融資は積極的に行われず、行う場合には、
ほとんどの場合に、信用保証協会の保証付き融資となるわけで、時間がかかります。
信用保証協会を活用した創業融資と資金調達【← 関連記事 】
一方で日本政策金融公庫は、起業案件を多く担当され、独自のノウハウをもっているため、創業融資の実行までのスピードは、TOPレベルの早さです!
日本政策金融公庫の創業融資を成功させる6つのポイント

日本政策金融公庫の創業融資は、実行まで早いのが特徴ではありますが、
1項目でも審査基準をクリアできなければ審査はとおらないことを意識しましょう。
また、一度審査に落ちてしまうと、同じプラン、切り口での再挑戦は不可能です。
日本政策金融公庫の創業融資を成功させる下記6つのポイントを押さえて、
完全な準備をしてから申し込みましょう。
1 融資の申込準備
完璧な理論武装を行い、専門家の税理士や会計士に事前に相談し、不明点、不安点をなくしておく。
2 起業前のお金の使い方に注意
起業前1年間の通帳を提出し、水道光熱費や通信費、税金の滞納がないかチェックされる。
コンビニなどでの現金払いの場合は、控えを保管しておく。
3 資金の受け入れに注意
個人的に贈与を受ける場合は、自己資金としてカウントしてもらうため、証拠の残る振込にする。
また他社から出資を受ける場合、金額や影響が大きすぎると創業と認められない場合があるので注意する。
4 金融機関から信頼のある税理士や会計士の紹介
経営や資金繰りに強い税理士や会計士が顧問につく予定であると、信頼度が上がり有利となります。税理士や会計士以外の士業でも創業融資のコンサルティングを行っていることもありますが、会計・税務・経営の専門家である税理士や会計士からの日本政策金融公庫への推薦がほとんどです。
5 創業融資面談
日本政策金融公庫の場合、申込から一週間以内に面談審査が行われます。
面談では、信頼できる人物かどうか、経営者として資質に問題がないかをみられます。
・好印象のために
信頼感の高い服装で。必ずスーツで臨むこと。
・嘘をつかない
相手はプロと心得て、矛盾のないよう。
・自信をもって
根拠を示し、明確な説明を。
・わかりやすく
受け答えは、結論から簡潔に。
・熱意と覚悟をアピール
何がなんでも軌道に乗せるという熱意と確実に返済するという覚悟をアピール。
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)などの融資審査・面談のポイント【← 関連記事 】
6 完璧な創業計画・事業計画特に売上がきちんと上がることの客観的な根拠を用意。
取引先の発注書や契約書などがあると格段に有利となる。
創業融資で最重要の完璧な創業計画・事業計画とは

創業計画・事業計画とは、つまるところ、
【 自社はどのような会社で、何のために、幾らお金が必要で、いくら貸してほしいのか、そして借りたお金はどのようにして返していくのか 】を説明する資料です。
これを【会社概要】・【必要な資金と調達方法】・【当面の損益予定】というように表現します。
【会社概要】
①取扱い・サービス欄この欄には商品内容のみではなく、別紙で写真入りの説明をするなどのアピールをすることがお勧めです。
→ 日本政策金融公庫では、多くの融資案件を手掛けられていますので、より分かりやすくイメージしてもらうための資料作りは重要です。
:セールスポイントはなんですか?
この欄には商品構成を記入するのも重要ですが、仕入れに関する優位性やこれまで培ってきた販売技術や
イベント開催などの強みをセールスポイントとすることが重要です。
→ ここでは、他社との差別化ができていて、しっかりとした競争力がこの会社にあるか見極めるというわけですから、できる限り自社の強みをしっかりと伝えたいですね。
②取引先・取引条件等欄:販売先・仕入先・外注先
審査の際に重視される欄です。契約書・注文書など手元にある書類は必ず提出して下さい。
個人情報の取り扱いには注意しながら、可能な範囲で顧客リストを見せることも有効なアピールです。
なお創業準備と並行して新規の顧客開拓をしている場合には顧客開拓進捗表などの作成がおすすめです。
また、仕入先や外注先などの中に大手企業があると審査に有利に働く場合があります。
:従業員等・人件費の支払い
事業内容や売上予測と比較して適正な従業員数かを確認される欄です。
従業員数と人件費との整合性には十分な注意が必要です。 ここでポイントなのは、入金や支払いのサイクルなどがや上記スタッフ数構成が、
下記の【必要な資金と調達方法】・【当面の損益予定】につながってくるところです。
論理的に矛盾がないかをしっかりと検証するようにしましょう。
事業計画書の表で、【必要な資金と調達方法】は以下のように記載します。
右側:事業に必要なお金をどうやって集めたのか? (自己資金額・借入額など)
左側:そのお金を事業の何に使うのか? (設備や運転資金の項目と金額)
という内容で作られています。
この時、右側の合計金額と左側の合計金額は必ず一致させることが必要です。
:設備資金欄
この欄には、今回の事業で購入予定の設備の名称と金額を記入します。
設備とは:減価償却できる資産です。内装費や店舗を賃貸した場合の保証金・敷金なども含まれます。
:運転資金・合計欄
この欄には商品の仕入れ、経費の支払いなど設備資金以外のものを記入します。
融資対象となるのは目安として運転資金の2~3か月分です。
見積書等が用意しにくい場合には各項目で自分が予測する金額を計算し、内訳を欄外や別紙に記載します。
その他の、創業融資のお役立ち情報(バックナンバー)をご覧になりたい方は、こちらです。
創業融資の情報館 バックナンバー
匠税理士事務所の創業融資や会社設立など起業支援サービス
匠税理士事務所では世田谷区や目黒区、品川区を中心に、品川区の日本政策金融公庫五反田支店と連携して創業融資コンサルティングを行っております。
自己資金と必要資金のバランスを伺い、どのような資金調達がベストかというコンサルティングや、創業計画書の作成サポート、融資面談の事前リハーサルや日本政策金融公庫の面談立合を行っております。
創業融資支援サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
経営革新等支援機関の詳細 中小企業の財務・経営を支援する経営革新等支援機関 へ。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
また世田谷区や目黒区、品川区で株式会社や合同会社など会社設立をお考えの方に向けて、会社設立の代行や設立後の経理・経営のサポートを行っております。
世田谷や目黒、品川で会社設立に強い税理士 をお探しの方はお気軽にご相談下さい。
起業支援サービス以外の経営コンサルティングや会計アウトソーシングサービスの詳細、担当税理士のプロフィールなどにつきましては、こちらよりTOPへ移動の上でご確認をお願いします。
その他の起業支援サービス一覧
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
給与計算サービス...給与計算の代行や、社会保険の加入手続き、人事労務のサポートサービス。
助成金サービス...正社員化や社員教育についての助成金代行とコンサルティングサービス。
資産移転など事業承継へ法人化や法人成りの活用 (17/04/12)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化の活用
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に株式会社の会社設立などへの法人化を通じて
資産の移転や事業承継対策などのコンサルティングを行っております。
今回は、会社にすることで個人資産にどのようなメリットがあるかについてまとめてみました。
個人資産が守られる法人化や法人成りのメリット

個人事業主の場合には、個人の負債も事業から生じた負債も法的には同じくくりです。
しかし、法人化・法人成りして会社を作った場合、商品の仕入れ費用や借金で支払いが滞っても、
それは会社の責任で、役員個人にその責任は及びません。
株主も同様、出資した範囲内での責任にとどまるので、形式的には個人に返済義務は生じません。
(ただし、連帯保証がついた場合は除きます。)
不動産の賃貸借や金融機関からの借り入れは、
社長個人の連帯保証を条件に会社として契約させられることがほとんどです。
このようなケースでは、個人事業主のままでも、
法人化・法人成りしたとしても個人としての返済義務は同じです。
つまりは、個人資産と会社資産を切り分けるために、連帯保証が一つのポイントになるのです。また、法人化・法人成りすると、
個人名義で借りていた借金は会社名義に変更するよう金融機関から促されますが、
税務調査では、この借入の返済が、しっかりと手続きをしておこないと、
社長への賞与とみなされる可能性があるので要注意です。
事業継承のための相続対策としての法人化や法人成り

個人事業を営む場合、事業主が死亡すると、
プライベート用の預金口座も事業用の預金口座も個人名義であればすべて凍結されてしまいます。
遺産分割が決定されるまで通帳からお金を引き出すことができないのです。
凍結された預金へは、得意先からの入金も仕入先への支払いもできなくなります。
そして商売上の契約条項もすべて引き継いだ人の名義で再度契約し直さなければならないため、
大変な手間がかかります。
これに対し、会社の財産は会社に所有権があるので、
預金口座も凍結されず入金や支払いが滞ることはありません。
会社の代表者を決定し登記すればよく、契約などは代表者の変更だけで済みます。
相続に関しては、個人事業主の場合には、
事業用であろうとプライベートであろうと保有しているすべての財産が相続の対象となりますが、
会社を保有している方の場合は、プライベートな財産のほかは、会社の株式のみが対象です。
では、株式の評価はどのようにされるのでしょうか。
比較的小さな会社の場合は、会社の資産と負債を亡くなられた時の時価によって
計算した差引純資産額をもって評価する純資産価額方式を、
大きな会社の場合は、
自分たちの業種と同じ商売をしている上場企業の株価を参考に評価する類似業種比準方式を、
中くらいの会社は純資産価額方式と類似業種比準方式を併用して株価を評価します。
純資産価額方式の場合は相続税対策として、純資産が低くなるような施策を行うことも可能です。
純資産価額方式と類似業種比準方式では、後者のほうが評価額が低くなる傾向があります。
生命保険に関して、個人契約の場合500万円を超えた保険金は相続税の対象となります。
一方会社で契約し、会社が受取人になっている保険金はそもそも相続税の対象とはなりません。
保険金が支払われるとき、
過去9年間(H29年4月以降開始の事業年度では10年間)の赤字がある場合には、
その分だけ保険金収入と相殺することもできるのです。
つまり税金がほとんどかからないこともあり得るのです。
また、会社が受け取った保険金を死亡退職金として遺族へ支給することができます。
この死亡退職金は個人の保険金と同じく、同居人一人当たり500万円までが非課税です。
これらをまとめると、会社の財産の方が、
いろいろと節税の方法が多いので便利ということです。
事業の売買が容易であるメリット

事業主に後継者がいない場合や、違う事業を始めたい場合など、
事業を売却するケースがあります。
企業価値は会計上の純資産だけではなく、売上高や将来性、
創立からの年数や地域でのシェア、商品のブランド価値など多面的、総合的に判断します。
個人事業では、事業主自身が商売そのものであることが多いのに対し、
会社は社長の個人的技術や手腕を卓越し、集団としての価値を評価されます。
この集団としての価値を売買できるところに会社のメリットがあります。
個人事業を買い取った場合には、新規に事業を起こすのと同じ労力が必要となりますが、
会社の売買は発行している株式の売買により、
容易に事業自体を引き継ぐことができるのです。
→ こうした理由からM&Aを行うのは、ほとんど会社組織というわけで、
事業承継においてM&Aの手法も選択肢に加わるのが会社形態のメリットです。
【 関連記事: 事業承継とは?事業を継承する際の注意点や種類・やり方 】
会社にすると得られる信用のメリット
会社にすることで、信用を得ることができるのが大きなメリットです。
初めて取引をする相手からは、個人事業主であるより、
会社であることの方が信用を得やすいといえるでしょう。
なぜ信用されるのか、それは「登記」されているからです。
つまり、だれもがいつでも会社の重要事項を閲覧でき、居場所を確認することができるからです。
大手企業は保守的ですからリスクをとることを嫌がる傾向があり、
個人事業主とは仕事をしないところもあります。
金融機関から借入れをする際や、返済する必要のない助成金を獲得する際にも、
この信用により有利に話を進めることができます。
また、求人面でも、個人事業よりも会社の方が福利厚生面で安心感を与え、
優秀な人材を確保しやすくなります。
【 関連記事: 会社にする?個人のまま? 法人化ポイント(メリット・デメリット) 】
匠税理士事務所の法人化・法人成りサービス
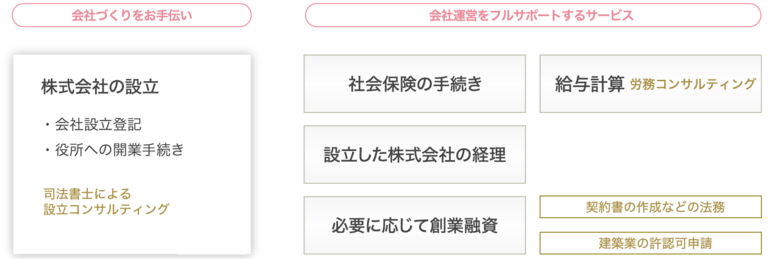
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に法人化や法人成りの支援を行っております。
会社を設立して事業用財産の移転を行うなど法人化や法人成りのサービス詳細は、こちらよりご確認をお願いします。
法人化相談会の詳細はこちらからご確認をお願い致します。

法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
◆法人化や法人成りについての情報を掲載した法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
法人化以外のサービス詳細や所属税理士・提携専門家などにつきましては、こちらです。
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、
説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
事業承継とは?事業を継承する際の注意点や種類・やり方 (17/04/08)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>事業承継とは
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第11回 事業承継とは?事業を継承する際の注意点や種類・やり方
第12回 相続税対策の生前贈与、税率と非課税は?
第13回 相続税の物納とは?相続税が払えなかったらどうする?
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
事業承継は少し前から新聞などで取り上げられるようになり、
会社を経営されている方にとって気になる事項の一つだと思います。
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に
事業承継に特化した公認会計士・弁護士などと提携し事業承継対策を行っております。
今回はこの事業承継の意味や、事業を次世代に継承する際にどのようなことに、
注意をしてどのような種類が事業承継にはあるのかについてまとめてみました。
事業承継とは何なのか

事業承継とは、会社の経営者が経営者としての地位や、
株式・不動産など事業を継承する上で必要な資産を後継者に引き継ぐことです。
中小企業にとって経営者が、
誰を後継者として事業を引き継いでいくのかは重要なテーマとなります。
事業承継は経営者にとって最後の大仕事となる重要な事項ですが、
どの企業でもいつかは必ず訪れる問題であり、できるだけ早いタイミングから準備を行っていくことで、
現経営者と次世代の経営者の並走期間・準備期間が長くなり、
会社のいいところ・悪いところ・生き残る道がしっかりと見えるようになりますので、
できるだけ早いタイミングからの準備が事業承継を成功させるための近道となります。
事業承継にはどのような種類があるのか

事業承継には
① 親族内承継
現オーナー経営者の子どもや、兄弟姉妹などの親族が後継者となる「親族内承継」
② 親族外承継 (従業員等に対するもの)
オーナー経営者の親族に後継者として相応しい人物が居ない場合や、親族以外で事業を承継してほしいという人物がいた場合に自社内の親族以外の役員または従業員が後継者となる「親族外承継(従業員等に対するもの)」
③ 親族外承継 (いわゆるM&A)
オーナー経営者の親族や自社の従業員に事業を承継する適当な後継者がいない場合に、
会社そのものを売り買いする「親族外承継(M&A)」 の大きく分けて3種類があります。
事業承継を行う上での留意点

事業承継を行う上では後継者となる人物の了承を早めに得て、
後継者として教育をしていくことが重要となります。
事業承継を円滑に進めるため、オーナー経営者自身が自社の状況を正確に判断し、
後継者が経営判断を誤ることが無いようその情報を伝える必要があります。
ただし、経営はいかに場数をくぐってきたかということが重要ですので、
理屈の説明ではなく、現経営者と次世代の経営者の並走を通じて、
このような局面では、どのように次世代は対応するのかを見極めて、
現経営者ならどう対応するか、その理由と過去の経験を説明するという実戦的な準備期間が長いことが重要です。
最終的には、次世代の経営者 = 現経営者 という判断の精度・速度になった際に、
本格的に退くというのがよろしいのではないでしょうか。
親族内承継における注意点

オーナー経営者の親族を後継者とする場合には下記の点に注意が必要です。
①関係者の理解を得ること
早いタイミング候補となっている親族に後継者として指名したい旨を知らせ、
本人の了承を得ることが必要となります。
特に後継者候補が複数いる場合には早期に指名をすることが重要です。
また、親族間での争いが起きないようにするためにも、併せて非後継者候補である親族に配慮が必要となります。
事業承継は取引先や金融機関などの利害関係者にとっても大きな影響を及ぼします。
円滑に承継を実行するには、予め事業承継計画を作成するなど利害関係者の理解を得る必要があります。
さらに会社内部の役員・従業員に対しても配慮が必要です。
古参の社員などは「先代の時代から働いてきた」という自負や、
後継者候補を幼いころから知っていることで、まだ子供だと思っていた人間が自分の上に立つ
ということに複雑な感情を抱く可能性もあります。
人材の確保が難しい背景はあるかもしれませんが、
事業承継のタイミングでベテラン社員にも引退をしてもらう事を検討する必要も出てきます。
あるいは、現経営陣と次世代経営陣候補の並走を検討してもよろしいかと思います。
これは自社のおかれている人的資源や、ライバル企業との力関係を考え、慎重に判断を行いましょう。
②後継者候補に必要な知識を学ばせ、教育及び実務を通じて経験を積ませること
事業承継に備えて、後継者を一人前の経営者として育成していくことが必要です。
なるべく早い段階から教育や実務の経験を積ませることが大切になります。
社内で行う研修は後継者を法人内の各部門で現場の状況を学ばせ、
将来的に必要になる現場感覚を備えさせることなどがあります。
また、部門責任者などの地位につけて現場を任せることで、
成功した場合には社内の従業員や社外の利益関係者からの信頼を得る効果があります。
社外で行う教育には自社ではなく通常の一般企業で勤務させることや外部のセミナーへ参加させることなどが挙げられます。
社会人経験を積ませることで社会の常識を身につけさせることができ、
将来経営者になったときにその経験及び人脈を経営に活かすことができるというメリットがあります。
③財産の分配について配慮すること
オーナー経営者の財産の分配については後継者への経営権の集中と後継者以外の相続人の遺留分の確保が必要となります。
親族外承継(従業員等)を行う場合には株式取得資金の確保と、
個人保証の問題を解決することに留意をする必要があります。
後継者には自社株式(最低でも議決権総数の50%超、議決権総数の2/3以上が望ましい)を集中させ、
後継者以外の相続人との問題を回避させることが重要です。
これらは民法と税法がからむ内容なので、早期より対策の検討が必要です。
親族外承継(従業員等)における留意点

親族外承継(従業員等)を行う場合には株式取得資金の確保と個人保証の問題を解決することに留意をする必要があります。
① 株式取得金の確保
経営権を握るために必要な株式を取得するために必要な資金を後継者が用意することが必要となります。
企業によっては株価が高くなり、その資金の調達が困難になる場合もあります。
解決策として、その会社の資産などを担保として金融機関から資金を調達することや、経営承継円滑法の活用などが挙げられます。
②個人保証の引継ぎ
オーナー経営者が会社経営から離れる以上、後継者が会社の保証人となることが求められることがあります。この場合、個人保証の引継ぎについて後継者の理解を得ることが必要です。
また、親族内承継と同様に利害関係者の理解を得ること及び経営を行うための教育・養成を行うことが重要です。一般的に企業内承継の場合、親族内の承継よりも関係者の理解を得ることに時間がかかる傾向にあります。
事業承継対策サービス
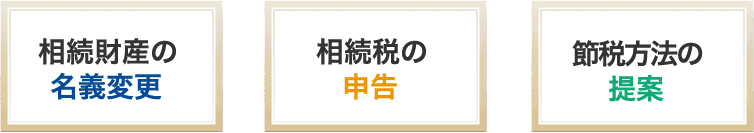
匠税理士事務所では、事業承継や生前贈与対策などに特化した公認会計士や弁護士などと提携して事業承継対策サービスをご提供しております。
現在の自社株式の評価はどれくらいなのか、
事業を継承する候補者は決まっているが、どのような財産をどのような時期に移転するのかなど
段取りについて相談をしたいというご相談を承っております。
生前贈与対策や相続税の申告・事前シミュレーションはこちらから
匠税理士事務所の事務所概要はこちらよりご確認をお願いします。
【 税理士対応エリア:目黒区や品川区、世田谷区など東京都23区全域 】
事業承継以外の経営支援サービスなどにつきましては、
こちらよりTOPへ移動の上で、各サービスをご確認いただけますと幸いです。
必見!創業融資成功のための4つのポイント (17/03/29)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
第18回 匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に
これまで資金調達・創業融資を通じて起業家の方を支援してきました。
今回はこうした起業支援の中で、
創業融資のポイントについてまとめてみました。
創業融資成功のポイント1:融資依頼額は適正か
(必要額)―(自己資金)=(融資依頼額)となるため、金融機関に相談に行く前に必要額の見積もりが必要です。
必要額としては、事業を始めるために最初に必要な経費(設備資金)と
自分の給与・人件費・家賃・通信費などの必要な経費(運転資金)があり、
すでに支払ったものも必要額に組み入れることで融資依頼額を増やすことができます。
また、運転資金には上記必要経費の他に、
研修費・調査費・ホームページ費用など営業活動をスムーズにするため戦略的に投資する資金も含めるのがポイントです。
金融機関への説得力を高めるため見積もりが取れるものは取り、
計画書上では運転資金に組み入れます。
こうして必要額と自己資金が決まり、融資依頼額が決まるのですが、融資依頼額はどれ位が適正なのでしょうか?
融資依頼額は、昔は一般的に自己資金の2倍が一つの目安でした。現在は、自己資金要件が緩和されましたが、やはり貸す側の本音は1,000万円借りたいなら500万円は自己資金を用意してほしいというのが、本音だともとれますし、
実際の現場でも自己資金の約2倍が融資成功例に多いように感じます。
またご新規で融資を日本政策金融公庫に申し込む場合には、1,000万円が一般的に上限となりますので、こちらも踏まえていくらの融資を申し込むか考えることが重要です。
創業融資成功のポイント2:自己資金はいくらになるか
「自己資金」について注意すべき点
無担保・無保証人で借りられる日本政策金融公庫や信用保証協会の制度では、自己資金が重視されます。
例えば、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」にある自己資金の要件としては
創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金があること(付随条件あり)とされています。
ここで注意すべき点は、自己資金であると認めてもらうために
その調達方法を裏付ける通帳などの資料が必要であること、
一時的に借りたお金で自己資金を水増しできないよう、
まとまった資金がある場合はその裏付け(資産を売却した場合はその証明書など)が求められること、
住宅ローンなどの借入金がある場合には自己資金から差し引かれることです。
このポイント1とポイント2の必要資金と自己資金とのバランスを考えて、
融資依頼額が適正かどうかが判断されるわけです。
自己資金が少ない場合には、必要資金を一部縮小して小さく事業が始められないかを
検討することも重要になります。
それでも自己資金が足りない場合には、何とか自己資金として認めてもらえるものがないかを考えるのも有効です。
また、自分で考えていた自己資金と金融機関が考える自己資金が違っていたため、
融資がうまくいかなかったということがないように注意が必要です。
創業融資成功のポイント3:借りたお金はこう返す、を証明する事業計画書の書き方
金融機関に提出する申請書類とは別に、
さらに事業内容を詳しく説明するために作成するものが事業計画書です。
提出は任意ですが、規定の書式では事業に対する熱意が伝わりにくいため、
融資を受けやすくするためにも作成することをおすすめします。
事業計画書の内容としては以下のようなものを盛り込むことができます。
・創業の動機、事業の将来性
・事業経験
・取扱商品・サービス
・顧客ターゲットや顧客ニーズ
・売上計画
・固定費計画
・損益計画
この事業計画書の目的は金融機関を納得させてより、
スムーズに融資を受けられるようにすることです。
事業経験から活かせるものや同業者との差別化を図れる優位性などは事業の今後の可能性をアピールするものとなります。
ここでのポイントは、夢物語ではなく、固い数字であり、一つ一つの数字がしっかりとした根拠に基づいていることです。数字が固く、根拠に基づいていればいるほど、
金融機関はこの会社はしっかりと収益を上げて、返済できそうだという印象になってきます。
創業融資成功のポイント4:融資の面談準備は万全か
ポイント1から3は、いずれも書類の準備が全てですが、
金融機関も大きなお金を出すことになるわけですから、
【 貸したお金が無事に返ってくるか 】 これが命題であり、
この命題を無事に達成できるかを、書類と面談で確かめるわけです。
創業融資では、
【何とかしてお金を借りたい】というのではなく、
金融機関の担当者の方に、
【 しっかりと返せますから、ご安心ください。 】ということを伝えるのがポイントです。このように考えると、服装はどのような服装が良いのか、
無理に大きく見せる必要ないなど大事なことが見えてきます。
匠税理士事務所の創業融資・会社設立など起業支援サービス
匠税理士事務所では、
世田谷区や目黒区、品川区を中心に創業融資による資金調達支援を行っております。
創業計画書の作成サポートや、融資面談の対策や当日の立ち合いなどを通じて、
お客様の資金調達と起業成功を支援しております。
サービスの詳細につきましては、こちらからご確認をお願いします。
創業融資と同時に会社設立をお考えの方につきましては、
会社設立前に資本金や株主構成・比率などをコンサルティングや、
会社設立の手続き代行も承っております。
会社設立サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
→ 目黒や品川、世田谷の会社設立は匠税理士事務所
匠税理士事務所は今後も起業に必要な全てがそろう会計事務所を目指して、
サービスの充実・人員の増加充実に努めます。
所属税理士のプロフィールなどにつきましては、こちらよりご確認をお願いします。
→ 目黒区や世田谷区、品川区の税理士は匠税理士事務所
個人事業から会社設立する法人化で、大変なことやデメリット (17/03/25)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化のデメリット
法人化で気を付けるべきことは?
匠税理士事務所では、世田谷や品川、目黒を中心に個人事業から会社設立を行う法人化をサポートしております。
今回は、
個人事業から会社設立する法人化で、大変なことは何ですか?という
お客様からのご質問に対する回答をまとめてみました。
事業資金使用の自由度がなくなること

個人事業であれば、プライベートな支出について、
経費にはできないものの、事業主勘定を使い自由にお金が引き出せます。
つまり通帳にあるお金 = 自分のお金というわけです。
しかし会社となると、
通帳にあるお金 = 会社のお金ということになりますので、
いかに社長といえども、役員給与として決定した毎月一定の金額と諸経費の精算以外は、原則としてお金を引き出すことはできず、こうした役員給与として決定した毎月一定の金額と諸経費の精算以外の引出は、経費として認められないどころか、社長への貸付金として計上されてしまいます。
この場合、注意しないといけないのは、利息が発生するということです。
返済しないと、役員賞与として社長個人に所得税や住民税が課税されるのです。
この場合の金利は、原則として平成26年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は1.9%が適用されます。
( 借入の年度により基準金利が異なるので注意が必要です。 )
ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、
その借入利率を基準として計算します。
つまり会社という第三者から自分(社長)にお金を貸して、金利が発生するイメージです。
また、社長に対する貸付金があると金融機関からの借入れが難しくなります。
銀行借入れをプライベートに使われてしまうと判断されかねないからです。
もちろん、個人事業主であっても融資・借入で調達したお金を個人の私生活で使うと、
事業主貸という勘定に残りますので同じように融資を受けることは難しくなりますが・・・・
プライベートと仕事の線引きもしっかりと行わなければなりません。
会社の経費はすべて売上を目的とした投資ですから、個人使用分の費用は一切計上できません。
会社設立でオーナーと経営者が異なるということも・・・

会社の中で一番決定権を持つのは、オーナーである株主です。
株主の集まりを株主総会とよび、
会社の重要事項の決定には決議が必要です。
そしてその過程は、議事録として残さなければなりません。
会社の住所、目的、役員等重要な変更があった場合の登記にはこの議事録が必要です。
個人事業主の場合には、株式という持ち分概念がありませんので、
個人事業主 = 事業のオーナーということになりますが、
株式会社の場合は、
社長 = 株主の会社もあれば、
社長 ≠ 株主という会社もあります。
つまり所有と経営が分離しているのが、会社というわけで、
こうしたことから会社には、以下のような機関があるのです。
会社の機関の種類と役割
株主総会
会社の大本を決定する最高意思決定機関。資本の増減、決算の承認、取締役や監査役の選任など。
取締役会
株主総会で決まった大枠の範囲内の実務業務を決定する機関。代表取締役の選任や営業方針、人事案件などの業務の詳細を決定する。
監査役
数字の監査を行う機関。取締役の業務監査も行う。
会社設立・法人化時の手続きが面倒であること

会社設立して法人化をするためには以下の関係各所へさまざまな書類を提出し手続きしなければなりません。
【 1:登記関係手続 】
公証役場・・・・・・・・・・・・・・・・定款の認証
登記所(法務局)・・・・・・・・・・・・設立登記申請書、代表印の登録
【 2:税務関係手続 】
税務署(個人として)・・・・・・・・・・個人事業の開廃業等届出書、所得税の青色申告の取りやめ届出書、事業廃止届出書
税務署(会社として)・・・・・・・・・・法人設立届出書、青色申告の承認申請書
都道府県や市区町村の税務課(会社)・・・法人設立届出書 【 3:社会保険関係手続 】
都道府県や市区町村の税務課(個人)・・・健康保険等喪失証明書
年金事務所・・・・・・・・・・・・・・・健康保険、厚生年金保険新規適用届
労働基準監督署・・・・・・・・・・・・・労働保険保険関係成立届
ハローワーク・・・・・・・・・・・・・・雇用保険適用事業所設置届
【 4:許可関係手続 】
その他公的な機関・・・・・・・・・・・・保健所、警察署、都道府県出先機関などへの営業許可関係の手続きや建築業の許可申請手続きなど
【 その他の名義変更手続きなど 】
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・賃貸している店舗の契約者変更、金融機関の預金口座開設、代表印の作成・登録、借入金やリース債務の継承、得意先仕入先などへ会社にしたことの連絡
こうしてみると、かなりの手続きが必要になりますね。
匠税理士事務所は、世田谷区や品川区、目黒区を中心に会社設立・法人化支援を行っております。
こうした手続きのうち、1から4の全てを代行させていただきますので、
会社設立・法人化でお客様のお手間は、ご本人様以外できない名義変更手続きのみとなります。
会社をたたむ際の面倒な作業
個人事業主でしたら、失敗して商売をやめるときは、
最後の年の収入に関する確定申告をすれば済みます。
しかし、会社を万が一失敗させると、その結末はとても大変です。
法律に従い、会社の解散を通知・公告し、解散日から2か月以内に税務署へ解散確定申告をします。
そして残っている財産を清算し、残余財産を確定させると、
再び税務署へ清算確定申告を、法務局へ清算結了の登記をしなければなりません。
会社を清算するときに、帳簿上の資本以上に財産が残っていると、
これが課税されてしまうのもデメリットです。
破産や民事再生となるとさらに面倒です。
現実的には解散のみ行うとか、
何もしないで休眠会社として名前だけ残しておくケースがよく見受けられます。
また転職したにもかかわらず、
会社として借りた借金を返済するためだけに存在し、
税務申告しない会社もたくさんありますが、
法人格が残っている間は法人住民税の均等割といって、
赤字でも課税され納税義務は発生しますので申告が必要となります。
つまりこれから事業がドンドン大きくなりそうだ、
大きくしていきたいという方は会社設立を行う法人化がお勧めですし、
縮小が予想される方は個人のままがよいかもしれません。
匠税理士事務所の会社設立・法人化支援サービス
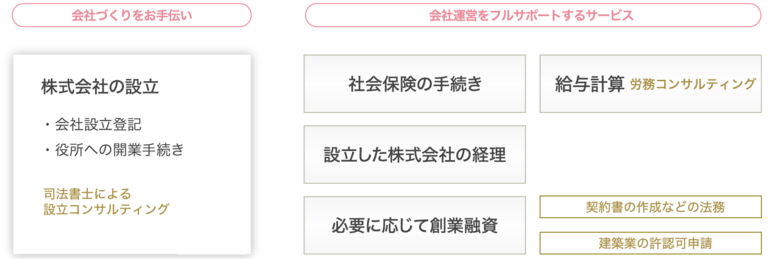
現在の個人事業の規模が大きくなってきたので、
合同会社などの会社設立を行いたいという方に向けて、会社設立を行う場合のメリット・デメリットをご説明させていただき、実際にお客様の確定申告書を拝見して会社設立した方が有利なのかどうかをコンサルティング致します。
その後に会社設立を行う場合には、各種手続きの代行からご要望があれば融資による資金調達も承っております
法人化相談会の詳細はこちらからご確認をお願い致します。

法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
税理士事務所の会社設立・法人化支援サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
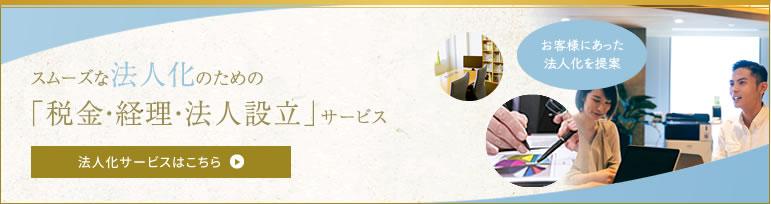
◆法人化や法人成りについての情報を掲載した法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
法人化や法人成りをした後のサービス
個人事業から会社にした後の会社設立後の経理や給与計算・創業融資などをサポートする会社設立サービスの詳細はこちらからご確認ください。
【1】目黒区や品川区、世田谷区での会社設立サービス
匠税理士事務所の税理士対応地域は、世田谷区・目黒区・品川区など東京都23区となっておりますが、他地域のお客様のご要望も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
税理士の詳細や司法書士、社会保険労務士など各種手続きを担当する専門家につきましては、
TOPページからご確認をお願いします。
→ 目黒、品川や世田谷の税理士は匠税理士事務所
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、
説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
ブラックな税理士事務所や会計事務所の見極め方 (17/03/23)
これから税理士事務所や会計事務所に勤務を
お考えの方で就職・転職するに際して、
【ブラックな】税理士事務所・会計事務所で
働きたいという方はいないと思います。ブラックな事務所というと、
1 仕事量が多くて、残業が多い
2 給料が低い
3 所長のパワハラ
一言で言えば、【 きつい 】事務所です。
ブラック見極めのコツは、このようになるでしょう。
このうち、2の給料が低いは面接や入所前に
条件提示があり、条件が合わなければ他社に
移ることも選択肢としてあげられます。
ブラックな税理士事務所の雰囲気の見極め
また、上記3のパワハラは税理士事務所や
税理士法人・会計事務所に入所する前に、
面接や会社説明会などで会社の雰囲気など
よく見ると何となくわかりますが、
【 何か質問はありますか? 】と聞かれた際に、
【最近どれくらいの方を採用され、 どれくらいの方が現在も勤務されてますか?】と逆に聞いてみるのもよいかもしれません。
人材を大切にしている事務所は、
人がそもそも辞めませんから、
すんなりと答えてくれます。
一方離職率の高い事務所は、困るかもしれません。今は売り手市場の状態なので、
面接で聞きたいことをしっかりと聞いて、
ベストな税理士事務所を選びしましょう。

残業が多い事務所の見極め方
残業が多いかどうかは、正直入所してみないと
わからないというところもありますが、
応募するか迷っている事務所の営業時間が
9時~17時とすると、17時~18時くらいで
人の出入り・事務所に電気がいつまでついてるか
見てみるのも、一つの手です。
電気が早く消えるなら、チームで仕事し、
仕事量が各人ごとに管理されてます。
仕事が早くないから残業をしているという
考えもあるかもしれませんが、
こちらもチームで対応している場合には、 他の人間でカバーすべきでしょう。このように面倒かもしれませんが、
これから長年働く場所を選ぶわけですから、
2~3日の労を惜しまないことで、
いい事務所を選べる確率は高くなります。

税理士事務所、ブラックでないでしょうか
匠税理士事務所は、仕事はチームで対応し、
残業は繁忙期を通じて一切ございません。また全員が気持ちよく働けるように、
正社員・パートスタッフともに有休が付与され、
給与も他社に比べ高めになるように設定してます。学校行事など私生活のときには、
【お互い様・助け合いの精神】を大切にし、 ワークライフバランスを重視の事務所です。こうした方針のもと、
【 ここ5年間で退職者はゼロ 】
というのが何よりの評価と考えてます。
また面接時、実際に勤務しているスタッフと
話をしてもらいますので、
所長のみではなく現場の声も聞いて頂き、
お互いに良い選択となるように心がけております。
匠税理士事務所でのご勤務をご検討中の方は、
こちらより詳細のご確認をお願いします。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の税理士事務所・会計事務所の求人採用情報
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や在籍スタッフ詳細は、
こちらからご確認をお願いします。


執筆者・文責 税理士水野智史
#税理士事務所求人 #会計事務所採用
相続税対策の生前贈与、税率と非課税は? (17/03/21)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>生前贈与、税率と非課税
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第11回 事業承継とは?事業を継承する際の注意点や種類・やり方
第12回 相続税対策の生前贈与、税率と非課税は?
第13回 相続税の物納とは?相続税が払えなかったらどうする?
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。
弊所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に贈与を活用した相続税対策や贈与税・相続税の申告を承っております。
今回は相続税対策のうち、生前贈与についてまとめてみました。
相続税対策として、
相続が発生する前である生前に次の世代へ財産を贈与する生前贈与は効果的です。
この基本的な考え方は、
1 相続税と贈与税の税率の差を利用すること
2 贈与税の基礎控除(税金がかからない金額)の活用
3 財産の価値が将来上がっていくものを早めに渡す
といったことです。
今回はこの中でも、
1 相続税と贈与税の税率の差を利用すること
2 贈与税の非課税の金額の活用 を取り上げます。
贈与税の計算と税率(暦年課税)と非課税について

贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与によりもらった財産の価額の合計額が課税対象となります。
贈与税の基礎控除(税金がかからない金額)は、受贈者1人あたり110万円です。
1年間に贈与によりもらった財産の価額の合計額から110万円を控除し、
その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税を活用した節税対策では、やはり無計画の一括移転ではなく、
長期間よく検討してこの110万円の非課税枠を利用したりすることで、財産移転を行います。
贈与税の税率は以下の通りです。
【一般贈与財産用】 (一般税率) :特例贈与財産用」に該当しない場合
例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など
基礎控除後の課税価格 / 税率 / 控除額
200万円以下 / 10% / ‐
300万円以下 / 15% / 10万円
400万円以下 / 20% / 25万円
600万円以下 / 30% / 65万円
1,000万円以下 / 40% /125万円
1,500万円以下 / 45% /175万円
3,000万円以下 / 50% /250万円
3,000万円超 / 55% /400万円
【特例贈与財産用】(特例税率)
直系尊属(祖父母や父母など)から、
その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用
基礎控除後の課税価格/税率 /控除額
200万円以下 / 10% / ‐
400万円以下 / 15% / 10万円
600万円以下 / 20% / 30万円
1,000万円以下 / 30% / 90万円
1,500万円以下 / 40% / 190万円
3,000万円以下 / 45% / 265万円
4,500万円以下 / 50% / 415万円
4,500万円超 /55% / 640万円
それでは贈与税と比較すべき相続税の税率はどうでしょうか?
相続税の税率につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
匠税理士事務所の生前贈与を活用した相続税対策・事業承継サービス
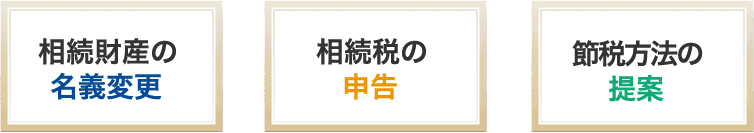
匠税理士事務所では世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続が発生する前に財産を次世代に円滑に移転させるための相続税対策・事業承継サービスを提供しております。
・相続が発生する前に最終的にどのような資産をどの方に移転させるのか、
・その場合には税務上どのような取り扱いになり、どれくらい税額がでるのか、
・他に有効な提案はないか など
資産家の方の財産を効果的に次世代に移転できるようにコンサルティング致します。
匠税理士事務所の生前贈与を活用した相続税対策・事業承継サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
相続税対策や贈与税の申告以外のサービスラインや、
税理士のプロフィール・提携先の公認会計士や司法書士など専門家の詳細につきましては、
こちらより移動の上、会社概要からご確認をお願いします。
→ 目黒・品川・世田谷の税理士事務所は匠税理士事務所へ
キャリア形成促進助成金の受給額と受給可能な事業主≪J3≫ (17/03/06)
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に
助成金申請に専門特化した社会保険労務士と連携して助成金申請代行を承ってます。
今回はこの助成金うち、キャリア形成促進助成金の受給額と受給可能な事業主についてまとめました。
キャリア形成促進助成金の受給額
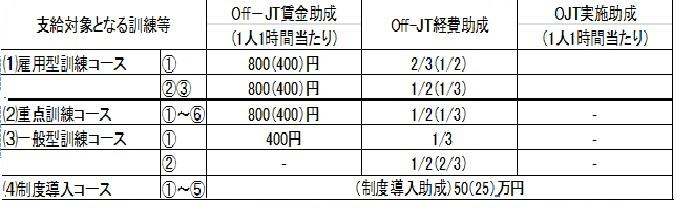
( )は大企業の助成額
Off-JT・・通常の業務を離れて行う職業訓練
OJT・・・適格な指導者の下、労働者に仕事をさせながら行う職業訓練
1 賃金助成(1人1コースあたり)・・・1,200時間
(認定職業訓練、専門実践教育訓練は1,600時間)
2 OJT実施助成(1人1コースあたり)
雇用型訓練コース①②・・476,000円(中小企業以外272,000円)
雇用型訓練コース③・・・268,000円(中小企業以外153,000円)
3 経費助成の限度額(1人当たり)
雇用型訓練コース
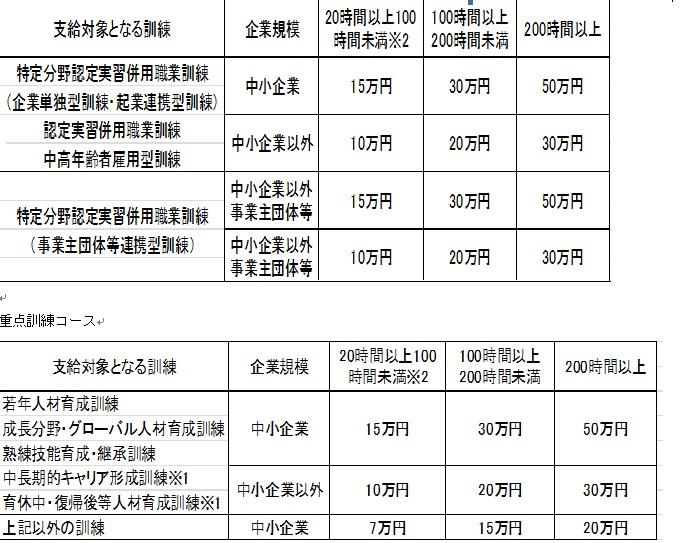
※1育休中・復帰後等人材育成訓練のうち、育児休業中の訓練等については、
企業規模に応じて、中小企業の場合は30万円、中小企業以外の場合は20万円、
中長期的キャリア形成訓練のうち訓練の実施方法が通信制として講座指定された訓練等については、
企業規模に応じて、中小企業の場合は50万円、中小企業以外の場合は30万円とし、
訓練時間に応じた限度額は設けず。
※2育休中・復帰後等人材育成訓練については、10時間以上100時間未満
4 1事業所の支給額
1事業所が1年度に受給できる助成額の上限・・・500万円
(認定実習併用職業訓練と認定職業訓練は、1,000万円に拡大
助成金の受給可能な事業主様とは
助成金を受給できる事業主は以下の要件をすべて満たす方となります。・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
(支給または不支給の決定のための審査に必要な書類当を整備・保管し、その提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること。)(管轄労働局等の実地調査を受け入れること)
・申請期間内に申請を行うこと
助成金を受給できない事業主(以下の要件のいずれかに該当する方)
・不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、
あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主。
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(これらの営業を行っていても、接待業務に従事しない労働者の雇入れに係る助成金については認められる場合がある)
・暴力団関係事業主
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
・助成金の不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主
【 関連記事 :キャリア形成促進助成金 その制度概要とは 】
匠税理士事務所の助成金申請代行
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区の会社様など事業主様を対象に
社会保険労務士と連携して助成金申請の代行やコンサルティングを行っております。
・助成金について興味があるのが難しそう。。。
・何となく自社が当てはまる気がするので、一度話を聞いてみたい。
・あまり手間をかけられないが、助成金を受けたい。
このような場合には、助成金に詳しい社会保険労務士がコンサルティングさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
◇助成金サービス
◇TOPページ
→ 目黒や品川、世田谷の税理士は匠税理士事務所
注:平成29年3月時点の情報で記載しております。判断は自己責任でお願いします。
創業融資、起業時に借入をするか、しないか迷ったら (17/02/28)
・これから会社設立をして起業しようと考えているが、
自己資金は貯めたので、創業融資なしでも何とかなりそうだ。
・会社を何年か経営していて、今まで無借金経営なので、
当面借入をしなくてもよいが、大型案件が増えてきたので外注さんや仕入でお金が必要になるかも・・
このようにお金がどうしても必要でない方でも、
少し創業融資・借入を受けた方がよいか気になるという方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、創業融資や借入を受けるかどうかを迷った場合についてまとめてみました。
借入を躊躇するよくある理由と融資を受けるメリット
①借り方が分からない創業融資・借入で必要な書類は、意外に少なく特に創業融資は、過去の売上実績を問われないので、
独立・開業時は一番借りやすく、融資を受けるチャンスでもあります。
融資の準備のため時間をあまりとれないという方は、
税理士など専門家に相談してみるのも良いかもしれません。
②利息がもったいない今は資金があるので借り入れは不要という場合もありますが、
利息=将来借りるための投資と考えて支払うことも有用です。
初回融資の場合申請した全額が借り入れできないことがありますが、
一度返済実績を作っておくと借りられる金額が増えていくので、
将来的に少し大きめの借り入れ需要が起こったときに役に立ちます。
現在の金利は1%から2%ほどですので、借入に1,000万円融資を受けたとしても、
年間で10万円から20万円の利息となります。この利息以上に利益を出せるかどうかを考えてみると、
良い判断ができるかもしれません。
③返せるかどうか不安「借りたから返さなくてはならない不安」と「手元資金が少ないため有効策を打てない不安」、
同じ不安なら事業を進めるための不安をとる方がよいでしょう。
ただ、1,000万円を借りるということは、
返済期間の間に1,000万円以上の利益を出さなければならないことを意味しますから、
短期間の無理な返済期間や将来利益を出せるあてがないの借入をすることは、
会社にとってマイナスになる場合が多いです。
匠税理士事務所の創業融資や事業借入支援サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に創業融資や事業借入の支援を行っております。
品川区にございます日本政策金融公庫の五反田支店や各種金融機関・信用金庫などと連携しておりますので、
お客様の幅広いニーズにお応えすることが可能です。
創業融資や借入支援のサービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
→ 目黒区や品川区、世田谷区の創業融資や起業の資金調達は匠税理士事務所
株式会社や合同会社などの会社設立支援サービス
また、株式会社や合同会社などの会社設立も同時に検討されている方に向けて、
会社設立のコンサルティングから会社設立の登記の代行など起業支援サービスもご用意しております。
サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
→ 会社設立を世田谷区や目黒区、品川区で行うなら匠税理士事務所
会社設立や創業融資など起業支援以外の税理士によるサービスにつきましては、
こちらよりTOPページへ移動の上でご確認をお願いします。
匠税理士事務所では、会計事務所とこれまでお付き合いのない方が、
お気軽にご相談ができるように心掛けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所
法人化・法人成りした場合の個人事業の届出手続 (17/02/21)
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区で
法人化・法人成りをお手伝いしております。
法人化や法人成りは、株式会社や合同会社などを
作ることになるので会社設立に伴う届出の作成や
提出ばかりに意識が集中しがちですが、
忘れていけないのは、会社設立と同時に個人事業を廃業することになるということです。
【 関連記事:法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き 】
例えば、令和〇年3月1日で会社設立をして、
個人事業を廃業する場合には、
令和〇年1月1日から令和〇年2月28日までの所得は
個人のものなのでこちらについて確定申告と同時に
3月1日~所得は法人で、個人は廃業になります。
そのため、個人事業の廃業届が必要なのです。
またこれと同時に個人の廃業が決まるのですから、
それ以降の個人事業所得もなくなるということで、
前年の所得を軸に計算した予定納税の減額という
手続きも出てくることになります。
それでは、この予定納税とは何なのかについて
まとめてみました。
予定納税とはなにか、どんな制度か

その年の5月15日現在において確定している
前年の所得金額・税額などを基に計算した金額
(予定納税基準額)が > 15万円以上である場合、
その年の所得税及び復興特別所得税の一部を
あらかじめ納付するという制度があります。
この制度を予定納税といいます。予定納税基準額の計算方法と申告
予定納税基準額は次の(1)又は(2)になります。
(1)次のいずれにも該当する人は、前年の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。) がないこと。
ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
→(1)に当てはまる方が、ほとんどです。
(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる
課税配当所得等の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。
また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額及び当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
上記(1) 又は (2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。
予定納税額は、所轄の税務署長から原則としてその年の6月15日までに、書面で通知されます。

予定納税の納付額及び納付期間
予定納税は予定納税基準額の3分の1の金額を、
第1期分として7月1日から7月31日までに
第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
予定納税の減額申請とは
その年の6月30日の状況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額より
少なくなる人は7月15日までに所轄の税務署長に
「予定納税額の減額申請書」を提出し承認されれば予定納税額は減額されます。
なお、第2期分予定納税額の減額申請は
【 11月15日まで 】です。
(この場合には、10月31日の現況において判断することになります。)。
法人化・法人成り廃業に伴う予定納税減額申請で
7月・11月の税金を減額し、事業投下することで
ビジネスチャンスを広がることも可能です。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援
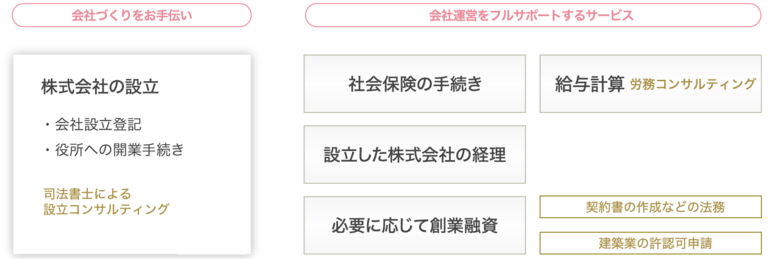
弊所では、法人化に伴う最終年度の確定申告や
上記届出書の作成代行、株式会社や合同会社など会社設立の登記や各種届出書作成手続代行、
会社設立後の社会保険の加入手続きなど
起業に必要な各種手続きを承っております。
会社設立後の経理や給与計算、税金の申告や融資による経営支援も充実しておりますので、
お客様は会社名の決定や取引先への連絡など最小のお手間になるような体制をご用意しています。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

法人化サービス下記よりご覧ください。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
→ 世田谷区・目黒区・品川区など東京での法人化・法人成り支援
(法人化の税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域)
→ 法人化相談会の詳細は 法人化無料相談会 からご確認をお願い致します。
担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
法人化・法人成りに伴う税理士の
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
法人化と同時に資金調達も行う
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
法人化後の会計経理や決算、確定申告など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

◆法人化や法人成りについての情報を掲載した法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
◆担当税理士の詳細や会社設立を担当する司法書士などの詳細につきましては、 以下のリンクよりTOPへ移動の、税理士事務所概要よりご確認をお願い申し上げます。
法人化でお困りの方・会計事務所をお探しの方は、お気軽にご相談下さい。
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、
説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事はお知らせの免責事項をご確認下さい。
執筆者・文責 税理士水野智史
#法人化個人廃業
#法人化予定納税
相続税を分割で支払う延納とは?相続税の支払い (17/02/13)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税の延納とは
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第11回 事業承継とは?事業を継承する際の注意点や種類・やり方
第12回 相続税対策の生前贈与、税率と非課税は?
第13回 相続税の物納とは?相続税が払えなかったらどうする?
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所のホームページにご訪問頂きましてありがとうございます。
弊所は、30代の税理士や提携専門家が、
世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税などの税務コンサルティングを行う会計事務所です。
今回は相続税のうち、その納付・支払方法の中でも、
延納についてまとめてみました。
相続税における延納とは何か

相続税の納付方法は、
相続税の納付期限は申告書の提出期限と同じ、
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。相続税の納税は金銭での一括納付が原則です。
しかし、相続税額が10万円を超え、
金銭で納付することが困難である場合には、納付方法の特例として、
相続税を分割で支払う「延納」という方法が認められています。
延納期間中は利子税の納付が必要となります。
相続税で延納が認められる要件

次に掲げる全ての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で一括納付することが困難であること。
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、
延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
なお、相続又は遺贈により取得した財産に限らず、
相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。
①国債及び地方債
②社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの
③土地
④建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの
⑤鉄道財団、工場財団など
⑥税務署長が確実と認める保証人の保証
延納に伴う担保提供関係書類の提出期限
納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に
担保提供関係書類を添付して提出する必要があります。
ただし、延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、
担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出することにより、1回につき3か月を限度として、
最長6か月まで担保提供関係書類の提出期限を延長することができます。
延納の許可までの審査期間
延納申請書が提出された場合、税務署長は、その延納申請に係る要件の調査結果に基づいて、
延納申請期限から3か月以内に許可又は却下を行います。
なお、延納担保などの状況によっては、
許可又は却下までの期間を最長で6か月まで延長する場合があります。
【 関連記事:相続税を物で納める場合にはこちら 】
匠税理士事務所の相続税コンサルティング・申告サービス
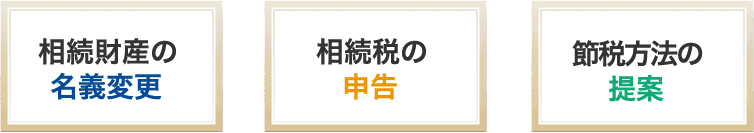
匠税理士事務所では、相続が発生した後の税務申告の代行から、相続が発生する前の相続税対策などの税務コンサルティングを承っております。
財産の内容や財産金額大きいなど複雑な案件につきましても、相続税に特化した税理士・公認会計士と連携しておりますので、しっかりとご対応させていただきます。
相続税コンサルティング・相続税申告サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
→ 世田谷区や目黒区、品川区の相続税コンサルティング・税務申告サービス
【税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
税理士の専門分野や提携専門家の詳細につきましては、こちらよりTOPページへ移動の上、会社概要のご確認をお願いします。
創業融資とは何か、売上目標はどう立てる (17/02/07)
匠税理士事務所では、
世田谷区や目黒区、品川区を中心に起業支援を行っております。
起業支援や起業セミナー講師を通じて、起業家の方から頂くご相談の多くが、
起業時における資金の問題です。
この資金の解決策の一つとして挙がるのが、創業融資です。
そこで今回は、この創業融資について記載しました。
創業融資とは何か、どのようなものがある?
【 創業融資とは、簡単にいうと起業時における借入です。】
この借入というとメガバンクや信金などの金融機関からの借入が浮かびますが、
起業時においてこうした金融機関が直接融資をしてくれることは、
不動産などの担保があるなど余程のことがない限り、なかなかあり得ません。
それでは創業融資=起業時における借入 は、
どこから行えばよいのかということになりますが、
1・・日本政策金融公庫(国が運営する中小企業を支援する金融機関)
2・・自治体と信用保証協会、金融機関が協力して資金を貸し出す制度融資
この2つが主なものとなります。
いずれも起業時における資金サポートを目的としておりますので、
起業については理解があり、融資にも積極的です。
このような理由から創業融資は、日本政策金融公庫 又は 制度融資が主流になります。
両者の違いにつきましても、まとめてみましたので、こちらからご確認をお願いします。
【 関連記事: 創業期の資金調達 日本政策金融公庫と制度融資の違い 】
創業融資で売上目標を立てるにあたっての注意点
創業融資の申請準備をする前に、
まず決めておきたいのが売上目標金額です。
なぜなら、目標金額が具体的になると資金繰り計画の見通しが立ちやすく、
しっかりとした売上目標の設定は融資に大変有利になるためです。
創業融資で売上目標を設定するために必要なポイントは以下の3つです。
①具体的であること
目標の根拠として「数字」と「固有名詞」が入っていること。
例えば、「○カ月以内に新規顧客○件(○万円)を開拓するため○○さん、に1週間に一度メールや電話でコンタクトをとる」など。あるいは受注が確定していることを示す資料などがあると尚可。
②測定可能であること
進捗状況を確認するために数字での測定が可能であること。例えば1カ月の目標を立てているのであれば最初の期間での達成額と目標の額を比較し、もし達成していなければ戦略を見直すなど具体的な行動に移すことができます。
③達成可能であること
あまりにも簡単な目標ではなく、また逆に高すぎる目標ではなく「少し背伸びをすれば達成可能」くらいの目標であること。またその設定が適切であるかどうか定期的にチェックするようにすることも必要です。
つまり融資の審査担当者が、
【 上席の方に報告しやすいようにしっかりとした根拠資料に基づいた売上 】であることが求められます。
また売上が決まってしまえば、経費は自分で削減することができますので、比較的簡単に決まります。
このような理由から創業融資における事業計画書では、売上金額とその根拠が重点的に確認されることになるのです。
【 関連記事 】
匠税理士事務所の創業融資・資金調達支援サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に創業融資をサポートしております。
事業計画書の作成サポートから当日の融資面談立ち合いまで独自のサービスやノウハウを駆使することで、起業時の資金調達を支援しております。
匠税理士事務所の創業融資・資金調達支援サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をいただければ幸いです。
創業融資以外に助成金についても資金調達の一環として、
ご検討中の方につきまして助成金の申請代行サービスも行っておりますので、
こちらよりご確認をお願いします
起業以外の経営支援サービスや税理士・提携銀行など匠税理士事務所の詳細につきましては、
こちらよりTOPへ移動の上で、ご確認お願い致します。
→ 税理士を世田谷区、品川区でお探しの方は匠税理士事務所TOPへ
三年以内既卒者等の採用定着に伴う奨励金(助成金)≪J4≫ (17/01/31)
匠税理士事務所では、
品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に助成金の申請代行やコンサルティングを行っております。
今回は助成金のうち、 三年以内既卒者等の採用定着に伴う奨励金(助成金)についてまとめてみました。
三年以内既卒者等の採用定着のための助成金・奨励金概要
学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、
既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、
採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金・助成金制度があります。
(平成28年2月10日から平成31年3月31日までに募集等を行い、
平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。)
【 奨励金・助成金の対象者 】
以下の学校等を卒業または中退した者で、
これまで通常の労働者として同一の事業主に引き続き12か月以上雇用されたことがない者
①学校(小学校および幼稚園を除く)、専修学校、各種学校、外国の教育施設の卒業者、または中退者
②公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練の修了者、または中退者
【奨励金の支給額】
事業主が、対象者を雇入れて一定の要件を満たした場合に、
企業区分、対象者及び定着期間に応じて下表の支給額を支給します。
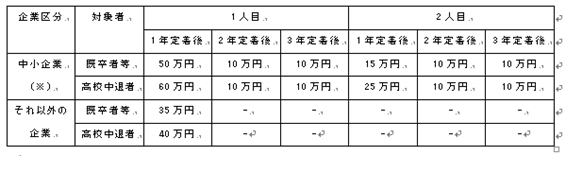
(※)中小企業に該当するかどうかは業種ごとに定められた資本金もしくは出資の総額、
または常時雇用する労働者数により判定します。(詳細は厚生労働省HPを参照)
若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
奨励金・助成金の支給要件
三年以内既卒者等の採用定着に伴う奨励金・助成金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。
<既卒者等コース>
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
<高校中退者コース>
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと
※1 学校(小学校及び幼稚園を除く)等に在学する者で、卒業若しくは修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人または学校卒業見込者等および学校等の卒業者・中退者であることを条件とした求人。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
【奨励金の不支給要件】
・対象者の雇入れを行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう。以下同じ)の対象者を雇用した事業主
・基準期間(対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年6か月を経過する日までの期間をいう)に、当該雇入れに係る事業所の雇用保険被保険者を事業主都合により離職させた事業主
など奨励金不支給となる要件がありますので申請前に詳細を確認する必要があります。
奨励金(助成金)支給申請の流れ
(1)新卒求人の申込みまたは募集
↓
(2)採用選考
↓
(3)対象者の雇入れ
↓
(4)第1期支給申請
↓1年間定着後
(5)第2期支給申請
↓1年間定着後
(6)第3期支給申請
(1)新卒求人の申込みまたは募集
新卒求人の申込みまたは募集を行う際、以下の書類を労働局に 提出してください。 ①当該求人・募集に係る求人票または募集要項等 ②当該求人・募集前3年度間の新卒者を対象とした求人票また は募集要項等 ※ここで提出いただいた資料については、支給申請時の提出は必要ありません。
(4)第1期支給申請
支給要件を確認するため、支給申請書とあわせて以下の書類等を労働局に提出してください。 ①対象労働者との労働契約について確認できる書類またはその写し ②対象労働者の卒業や退学の事実およびその時期が確認できる書類 ③対象労働者の支給対象期中の出勤状況が確認できる書類★ ④対象労働者に対して支給対象期中(下欄参照)に支払われるべき賃金について支払ったことが確認できる書類★ ⑤ユースエール認定企業の場合、認定通知書の写し ⑥誓約書 ⑦その他
奨励金の要件を確認するために必要となる書類★
※第2期、第3期の支給申請時にも、★の書類及び前期の支給決定通知書を提出していただきます。
【支給対象期について】
■ 助成金は、支給対象期(※)ごとに、最大3回に分けて支給します。
■ 支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークで行ってください。
■ 支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。申請期限を過ぎると 奨励金を受給できなくなりますのでご注意ください。
※ 支給対象期は、当該雇入れの日から起算して12か月ごとに区切った期間です。
【その他の助成金関連情報】
匠税理士事務所の助成金の申請代行サービス
匠税理士事務所では、助成金の申請代行を承っております。
助成金を活用してみたいが、実際に要件を満たしているか不安な方や、
助成金の申請の手間をあまりかけたくないので代行を検討しているという方に向けて、 助成金を専門とする社会保険労務士と連携して、 世田谷や目黒、品川など東京都23区を中心に助成金受給のコンサルティングを行っております。
サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
◇助成金サービス
所属税理士などの会計事務所の詳細は、こちらです。
◇TOPページ
世田谷や目黒、品川の税理士は匠税理士事務所
法人化や法人成りの無料相談会を税理士が実施中 (17/01/17)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化や法人成りの相談会
個人事業から会社にすることを、
法人化・法人成りといいます。
匠税理士事務所は法人化ご検討中のお客様の
相談を伺い法人化したほうが有利なのか、
どんな長所短所かなどの相談会を実施してます。
法人成りして会社を設立した場合、
場合により会社にしなかった方が有利なこともあり注意と専門家へ事前相談が重要です。
法人化・法人成りの相談会について

法人化の無料相談会では、
どのラインから法人化を検討すべきか
自社の場合どのような点に注意をしながら
会社にするべきかなどのご相談を承っております。
実際に法人化を担当する税理士が、
相談会を担当致しますので
・自社の場合の法人化の目安・疑問解決
・どんな会計事務所でどんな人材がいるのか
・料金や実際の流れはどのようになるのか
など様々なご要望にお応えできるかと思います。
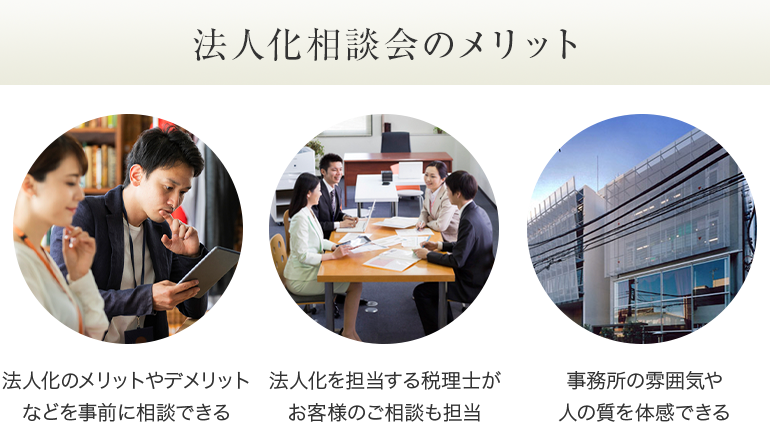
法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
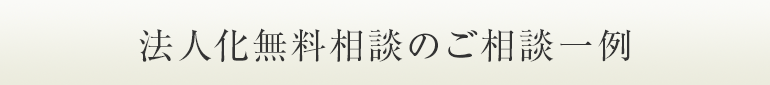

法人化や法人成りの短所や欠点、デメリットとは
(1)株式会社や合同会社などの会社設立費用はどのくらいか
個人事業の場合には設立費用は発生しませんが、会社を設立する場合には設立費用が発生します。
設立費用は資本金等の額によって金額は変わりますが、主に登記費用として20から30万円くらいが一般的のようです。
(株式会社の場合は登録免許税が約20万円・司法書士報酬が約5万円)
こちらはもちろん創立費など会社の経費となります。
※お客様のご要望がございましたら司法書士や許可申請の行政書士の紹介のみも行っております。
(2)税理士費用はどの程度を想定したら良いか
個人事業の青色申告は特殊な申告を除きご自身で行うことも可能な場合が多いですが、 法人の税務申告はご自身では難しく税理士に依頼することが多くなると思われます。
税理士報酬は、会計事務所によって異なります。
1.料金面で安いところを探すのか
2.サービスや人の質で探すのか
お客様の大切にしている考えに沿った税理士事務所を探されると良いと思います。
税理士費用以上に節税の提案などがあれば、これらの費用はメリットになります。
(3)赤字でも税金がかかるのか。法人住民税均等割
法人の場合は、赤字であっても法人住民税均等割という税金が最低7万円課税されます。
これは資本金の額と従業員数に応じて課税されます。
均等割を想定して資本金を決めることも重要です。
(4)役員報酬の変更について
税務上の役員報酬については、会計期間開始の日から3カ月以内に定めた金額を次の定時株主総会まで原則として変更することができません。
つまり、期の途中に役員報酬を増額しても、税金の計算上一部は経費と認められません。
また、個人のときのようにお金の引き出しを自由にすることはできず、 原則役員給与以外の引き出しは色々な制約が出てきます。
(5)社会保険料の負担
個人事業主は国民健康保険料と国民年金保険料を納付します。
会社を設立して役員報酬を受け取る場合には、社会保険の加入が強制となり社会保険料を支払うことになります。
その場合の保険料は会社負担と個人負担を合わせて給与の25%くらいになります。
一般的には個人事業主よりも会社が支払う社会保険料(会社負担と個人負担を合わせた金額)の方が多くなります。
なお、法人化での社会保険加入はメリットもありますので、詳細は下記よりご確認ください。
→ 法人化・法人成りでの社会保険加入によるメリットとデメリット
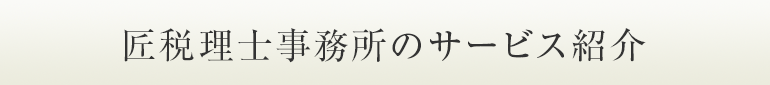
匠税理士事務所の法人化・法人成りサービス

匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区など東京都で、
個人事業を株式会社や合同会社にしたいという方のご相談を承っております。
税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
★法人化・法人成りのサービスは、こちらです。
【 → 世田谷、品川、目黒で法人化・法人成りサービス 】
★法人化や法人成りについての情報を掲載した法人化情報館のバックナンバーはこちらです。
★在籍の税理士・提携司法書士など会計事務所の詳細は、TOPから「会社概要」へ移動の上、ご確認をお願い致します。
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、
説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
法人化や法人成りを行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
相続税の物納とは?相続税が払えなかったらどうする? (17/01/10)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税の物納とは
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第11回 事業承継とは?事業を継承する際の注意点や種類・やり方
第12回 相続税対策の生前贈与、税率と非課税は?
第13回 相続税の物納とは?相続税が払えなかったらどうする?
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所では、世田谷や目黒、品川を中心に税務コンサルティングや経営支援を行っております。
今回は土地や建物など不動産などで大きな資産を相続された方で、
相続税の納付が難しい場合の物納についてまとめてみました。
相続税における物納とは何か

相続税を延納によっても金銭で納付することが困難な場合にに限り、
その納付を困難とする金額を限度として
一定の相続財産による物納が認められています。
つまり財産を用いることで、相続税という税金を払うという制度です。
しかし、どのような場合でも物納が認められるわけではありません。
物納が認められるためには、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
相続税における物納の要件とは
(1) 相続税を金銭で一括納付することが困難であり、
かつ延納によっても金銭で納付することが困難であること
(2) 物納する財産は、相続により取得した財産のうち、国内にある以下の財産であること
第1順位 国債、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債および株式、ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券
第3順位 動産
(3) 物納する財産は、国が管理または処分するのに適したものであること
(4) 物納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに、
物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。
相続で物納を活用するメリット
物納財産は、原則として相続税の課税価格の計算の基礎となった
相続税評価額により国が引き取ります。
よって「物納財産の評価額>実勢価格」の場合には、
売却による現金納付よりも有利となります。
また、財産を売却した場合とは異なり、
物納による相続税納付分には譲渡所得税が課されません。
相続開始の日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合に
譲渡所得税が軽減される制度を利用することも可能であるため、
売却が有利か物納が有利か判断する必要があります。
【 関連記事:相続税を分割で納める場合にはこちら 】
匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス
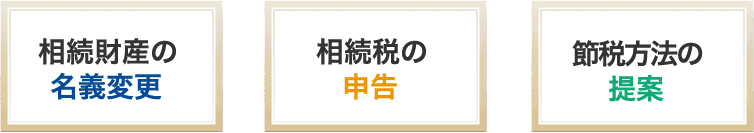
匠税理士事務所では、相続が発生した後の相続税の申告から、相続が発生する前の相続対策のコンサルティングにつき、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に承っております。
サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
【税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
相続税以外のサービスや所属税理士・提携会計士などの専門家詳細につきましては、
こちらよりTOPへ移動の上、会社概要からご確認を頂けましたら幸いです。
起業時に借入や創業融資の利用は必要か (17/01/03)
匠税理士事務所では、
品川区の五反田にある日本政策金融公庫や、
各種金融機関と連携して世田谷や目黒、品川を中心に創業融資の支援を行っております。
この創業融資に関するご相談の中で、
【 創業時に借り入れはしたほうがよいでしょうか? 】
このようなご相談を起業家の方からよくいただきますので、
今回はこちらについて記載しました。
起業時の借入・創業融資の目的
【 創業時に借り入れはしたほうがよいでしょうか? 】
このように思われる起業家の方の場合には、
必要資金を自己資金で調達されていて、
事業を進めることができるという方が多いので、
【 万が一の場合に備えが必要ですか 】 と伺うようにしております。
この回答で備えが必要・ゆとりが欲しいということであれば、
やはり創業時の借入・融資は活用すべきということになります。
その理由は、
①借入・融資を受けやすい
担保も保証人も不要の融資制度があります。
また、過去の売上実績を問われない独立・開業時は一番借りやすく、
融資を受けるチャンスでもあります。
事業を始めてしばらく経つと実績が重視された融資になってしまいます。
②利息がもったいない
今は資金があるので借り入れは不要という場合もありますが、
利息=将来借りるための投資と考えて支払うことも有用です。
初回融資の場合、申請した全額が借り入れできないことがありますが、
一度返済実績を作っておくと借りられる金額が増えていくので
将来的に少し大きめの借り入れ需要が起こったときに役に立ちます。
また金利は約1%から2%ほどになり、経費にもなりますので、
お金があることで得られるビジネスチャンスや、安心と比べて利息は大きな金額にはなりません。
③返せるかどうか不安
「借りたから返さなくてはならない不安」と
「手元資金が少ないため有効策を打てない不安」、
同じ不安なら事業を進めるための不安をとる方がよいでしょう。
融資の承認がおりたということは、
つまり事業計画の有効性を金融機関が認めたということなのですから、
返済するあてを作るための事業計画を練って自信をもって遂行していけばよいのです。
匠税理士事務所の創業融資・起業支援サービス
匠税理士事務所では、
世田谷や目黒、品川を中心に創業融資の支援を行っております。
・借り入れが必要かどうか
・どれくらいの金額の創業融資が必要か
・事業計画書など必要な書類はどのようなものがあるのか
このようなご質問・ご相談に対応した融資コンサルティングサービスをおこなっております。
お客様のご協力のおかげ融資実行率9割超なっております。詳細はこちらからご確認下さい。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】はこちら

株式会社や合同会社などの会社設立サービス
これから株式会社や合同会社を設立を融資と一緒に検討しているので、
詳細なスケジュールなどについて相談したいといった会社設立のご相談もあわせて、
承っております。
株式会社や合同会社などの会社設立サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認ください。
【税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
創業融資や会社設立など起業支援以外の経営コンサルティングサービスや、
税理士のプロフィールなどにつきましては、こちらよりご確認ください。
世田谷区や目黒区、品川区での建設業許可の新規取得や申請代行 (16/12/24)
弊所は、世田谷や品川に近い目黒区自由が丘駅2分の建設業に強い会計事務所です。
そのため、目黒区・世田谷区や品川区で建設業や、建築業で起業される会社様を中心に
建設業許可新規取得や申請代行の相談を頂きます。
税理士事務所との顧問契約がなくても、
建設業許可新規取得の申請代行・更新手続・業種追加などのみ でもご相談いただけます。
新規取得申請をご要望の方は
こちらを確認下さい。【↓】
建設業許可の新規取得・申請代行はこちら
【→東京都の建設業許可の新規取得・申請代行は匠税理士事務所】

一般建設業許可新規取得の関連情報は
こちらから確認を願います。
【 関連記事:土木や解体工事など一般建設業許可業種・資格登録要件とは 】
特定建設業許可の新規資格取得の関連はこちら
【 関連記事:特定建設業許可の資格取得まで建設建築業界で成功するには 】

また、経営セミナーで講師を務める世界4大会計事務所出身の税理士が在籍しており、
建設業に向けた経営支援に力をいれております。
建設業に必要な全てある事務所をスローガンに、
建設業許可の申請以外の資金調達や社会保険加入、補助金や助成金のご相談、
税務会計など経理全体や経営相談も承ってます。
詳細につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【 関連記事:建設業や建築業に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所 】

世田谷区や目黒区、品川区の建設業許可更新手続・業種追加の代行
許可更新手続では、毎期必ず行う必要ある決算変更届の提出を税務会計の専門家の税理士と建設業に特化した行政書士と連携して対応します。
したがいまして、許可の手続きに伴うお客様のお手間を減らし、許可の新規取得や更新業種追加の時間を減らせます。

建設業許可の有効期限の一本化
複数工事業種の建設業許可をお持ちの会社様で、
許可の有効期限が異なる場合には、先に有効期限が満了となる工事業種の5年更新のタイミングで、
他の工事業種の建設業許可の更新も同時に行うことが可能です。
建設業許可更新の際の東京都や神奈川県の更新手数料は5万円ですので、
許可の有効期間が工事業種によって異なりますと、
それぞれの工事業種の5年更新のタイミングで、更新手数料5万円が生じてしまいます。
このような場合には、建設業許可の有効期間を一本化してしまった方が、
更新費用を節約することが可能になります。
世田谷区や目黒区、品川区などで複数工事業種の建設業許可をお持ちの会社様で、
お困りの方には建設業特化の行政書士が初回は無料でコンサルティングさせて頂きます。
建設業許可の更新手続き
・申請報酬 52,500円
・法定費用 50,000円
上記の法定費用は建設業許可申請を行う際に、
国や都道府県等に納める税金等で、
それぞれの手続きごとに決まっています。
建設業許可の更新手続き サービス内容
(1) 建設業許可の申請書類一式の作成
(2) 証明書類(必要書類)の代理取得
(3) 建設業許可要件その他に関するご相談
(4) 申請代理
(5) 許可期限等 手続き時期のお知らせ
※許可の有効期限を管理させて頂き、ご要望に応じてご提案させていただくことも可能です。

【税理士・行政書士対応地域:世田谷や目黒、品川など東京都23区全域の建築業や建設業】
目黒区の匠税理士事務所の経営支援サービス
匠税理士事務所では、建設業許可の新規・更新の申請代行以外にも、
会社の黒字化のための経営コンサルティングや、
資金繰りの改善のためのキャッシュフロー経営支援など
経営支援に力を入れている会計事務所です。
世田谷区や目黒区、品川区を中心とした
経営支援サービスの詳細はこちらよりご確認ください。

世田谷区や目黒区、品川区を中心とした会社設立・法人化支援
これから建設業の株式会社を設立したい、
これまで個人でやってきた事業を株式会社に法人化したいというお客様にむけて、
匠税理士事務所では、司法書士と連携して株式会社の設立代行・法人化も承っております。
会社設立・法人化支援のサービス詳細はこちらよりご確認ください。
会社設立や法人化につきましては、
世田谷、目黒、品川を中心に東京都全域に対応致しております。
また所属税理士や司法書士など提携専門家の詳細につきましては、
TOPページに移動の上、会社概要よりご確認ください。
→ 目黒、品川や世田谷の税理士は匠税理士事務所
世田谷や目黒、品川での建設業許可の新規取得や申請代行につき
最後まで御覧頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#目黒区建設業許可新規取得
#品川区建設業許可申請代行
キャリア形成促進助成金と助成金申請代行≪J5≫ (16/12/21)
匠税理士事務所では、助成金に詳しい社会保険労務士と連携し
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に助成金の申請代行などのコンサルティングを承っております。
今回は各種助成金制度のうち、キャリア形成促進助成金についてまとめました。
キャリア形成促進助成金とは
職業訓練などを実施する事業主等に対して、労働者のキャリア形成を効果的に促進するために、
訓練経費や訓練中の賃金を助成する制度です。
原則として、正社員に対するする訓練で、一定時間数の実施要件のもと、賃金や費用を助成します。
人材育成を重視する事業主であれば、業種を問わず受給可能性が極めて高い制度です。
キャリア形成促進助成金の制度の活用が向いている事業の例
・IT企業(又はIT企業に進出予定の企業)
・生命科学等のライフサイエンス系の研究開発業
・運送業、旅客業
・農業、林業、水産業
・スポーツジム、スイミングスクール等の健康増進施設の運営
・人材の定着に悩む医療機関、介護事業者
・OJTにより営業マンを育成する会社
・エステシャン、美容師等の技術習得のためのインターン期間が長い業種
・職人、技能工、コンサルティング、士業の業界等のスキルや専門性の習得に時間を要する業界
・新卒一括採用を行う業界で、6カ月以上の研修期間を設ける会社
・海外進出をおこなう企業(既に海外進出をおこなっている企業)
・国の指定する成長分野に進出予定の企業
・上記の他、長期間にわたる技能(スキル)や専門知識の習得が不可欠な業種
キャリア形成促進助成金の支給対象となる訓練と対象企業
雇用型訓練コース
①特定分野認定実習併用職業訓練
(建設業、製造業、情報通信業が実施する厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練)
②認定実習併用職業訓練
(厚生労働大臣の認定を受けたOJT付訓練 原則として新入社員研修を想定した制度)
③中高年齢者雇用型訓練
(中高年齢新規雇用者等を対象としたOJT付訓練)
重点訓練コース
≪中小企業以外・中小企業≫
①若年人材育成訓練(雇用締結後5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練)
②熟練技能育成・継承訓練(熟練技能者の指導力強化、技能継承のための訓練、認定職業訓練)
③成長分野等人材育成訓練(医療・介護・福祉・IT・ライフサイエンス・バイオ、環境、建設、運輸、農林水産、健康、医療関係の製造業、フィットネスクラブ等の健康増進施設や健康授業等をおこなう事業等、の事業主が対象となる従業員におこなう訓練)
④グローバル人材育成訓練(海外進出にかかる人材のための訓練)
⑤中長期的キャリア形成訓練(厚生労働大臣が指定した専門・実践的な教育訓練講座)
⑥育休中・復帰後等人材育成訓練(育児休業中の訓練、復帰後、再就職後の能力アップの訓練)
一般型訓練コース
①教育訓練・職業能力評価制度
(従業員に対する教育訓練か職業能力評価を、ジョブカードを活用し計画的に行う制度)
②セルフ・キャリアドック制度
(一定の要件を満たしたセルフ・キャリアドック制度を導入し実施した場合に助成)
③技能検定合格報奨金制度
(技能検定に合格した従業員に奨励金を支給する制度を導入し、適用した場合に助成)
④教育訓練休暇等制度
(教育訓練休暇制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、適用した場合に助成)
⑤社内検定制度(社内検定制度を導入し、実施した場合に助成)
<お役立ち情報 助成額と助成金の支給対象事業者はこちら>
→ 【関連記事】キャリア形成促進助成金の受給額と受給可能な事業主
<お役立ち情報 その他の助成金情報はこちら>
→ 【関連記事】キャリアアップ助成金とは?助成金の申請代行
匠税理士事務所の助成金申請サポートコンサルティング
匠税理士事務所では、人事労務の専門家である社会保険労務士と連携して、各種助成金の申請代行を承っております。
助成金申請サポートサービスは、こちら。
◇助成金サービス
→ 助成金の申請代行・コンサルティングサービス
助成金以外のサービスや所属税理士につきましては、こちら
◇TOPページ
→ 目黒、品川や世田谷の税理士は匠税理士事務所
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区の起業や経営支援に力を入れている会計事務所です。
最終更新日:平成28年12月21日
会社設立時の定款作成 事業目的や会社名を決めるポイント21 (16/12/13)
K21
目黒区の匠税理士事務所では、品川区や目黒区、世田谷区を中心に株式会社や合同会社の会社設立サポートや、創業融資や助成金の申請代行などの資金調達を通じて起業支援に力を入れている会計事務所です。
今回は株式会社や合同会社の会社設立において、必ず作成しなければならない定款(会社のルール)に記載する事業目的・会社名を決める際のポイントについてまとめました。
会社設立に必要な定款とは何か
定款とは何なのか、定款作成のポイントについて記載します。
会社設立に必要な定款とは、会社の基本的なルールを決めたものです。
株式会社の場合、定款について公証人の認証を受けるため、記載ミスがあっても認証後の修正は認められません。
そのため、慎重に作成を進めていかなければなりません。
会社設立時の定款の記載事項
会社設立時の定款の絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、必ず記載しなければならない項目で、これらが漏れているものは定款として無効です。
記載事項と記載例
① 商号
→「当会社は、○○株式会社とする。」
② 事業目的
→「当会社は次の事業を営むことを目的とする。
近い将来だけではなく、将来やりたい事業までを視野にいれて定めておくのがポイントです。
③ 本店所在地
→「当会社は本店を○県○市に置く」
④ 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
→「当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○万円とする。」
⑤ 発起人または社員の氏名、または名称および住所
→「発起人の氏名、住所および発起人が設立に際して引き受けた株式数は、次の通りである。
住所 名前 株数」
⑥ 社員全員が有限責任である旨
→「当会社の社員の全部を有限責任社員とする。」(合同会社のみ記載)
⑦ 発行可能株式総数
→「当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする」(株式会社のみ記載)
◇事業目的を決める際の注意点
事業目的は定款に必ず記載しなければならない事項で、その書き方はある程度決まっています。
最初はかしこまった言葉ではなく、自分の言葉でやりたいことを書いてみることをお勧めします。
書いてみて、ある程度まとまってきたら、最終的に認められるかどうかは管轄法務局の登記官の判断によるところも大きいので、法務局に足を運ぶか、司法書士などの登記の専門家に相談するのがよいでしょう。
特に建築業や派遣事業など許認可事業の場合、決まった表現・文言がなければ認可を受けられないという場合もあります。
事業目的は、設立後すぐに営むわけではなく、将来予定している事業も入れておくと、定款変更などで再度登記を行うなど手間・手続きが省けます。
ただし、予定もない事業を数多く記載すると、
いったいこの会社は何をしているのかと、取引先や出資者、金融機関から疑問をもたれ、
銀行口座がなかなか開設できないなどスムーズに取引が行われないことになりかねませんので注意が必要です。
会社設立時の定款の相対的記載事項
会社設立時の定款の相対的記載事項とは、定款に定めないと効力が生じない項目です。
記載事項と記載例
① 現物出資
→「当会社の設立に際しての現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産、その価格およびこれに対して割り当てる設立時発行株式の数は次のとおりとする。
② 株式の譲渡制限に関する定め
→「当会社の株式を譲渡により取得するには、株式総会の承認を受けなければならない。」
③ 株券発行の定め
→「当会社の発行する株式については、株券を発行する」
④ 役員の任期の伸長
→「取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする」
会社設立時の任意的記載事項
会社設立時の任意的記載事項とは、記載がなくても定款が無効になるわけではなく、
また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではない項目です。
記載事項と記載例
① 英語の社名
② 総会の開催時期
③ 役員の員数
④ 事業年度
会社設立時の会社名を決める際の注意点
会社の名前は、何をしている会社なのか、どういうポリシーの会社なのかが一目でわかるのが理想的です。
<関連記事: 会社設立で会社名・会社の名前である商号の決め方は? >
会社法の施行で、同じ住所でなければ、既に存在する会社と同一の社名をつけることができるようになりましたが、
「不正の目的をもって他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用してはならない」とも決められています。
また、商標登録された有名ブランド名を社名とすると、商標権の侵害の問題が生じ、差し止め請求を受けたり、
損害賠償の請求対象になったりするかもしれません。
上記のような問題を回避するために、会社名を決めたら、法務局で念のために商号調査簿を閲覧し調査してみましょう。
<関連記事: 会社設立して起業する前の商標確認と検索方法 >
匠税理士事務所の会社設立代行・起業支援サービス
匠税理士事務所では、定款決定におけるコンサルティングや、
資本金はいくらがいいか、決算時期はいつがいいかといった会社設立に伴うご相談
司法書士と連携した株式会社や合同会社の設立代行を承っております。
これから株式会社や合同会社の会社設立をご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
税理士 目黒区、世田谷区や品川区の会計事務所匠税理士事務所TOPへ ...TOPページへ
最終更新日:平成28年12月13日
相続時精算課税制度と相続税対策 (16/12/07)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続時精算課税制度と相続税対策
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所では、相続税申告・相続対策などの税務コンサルティングサービスを行っております。
相続税対策の一環として、相続時精算課税制度も選択肢としあがってきますので、今回は相続時精算課税制度についてまとめてみました。
相続時精算課税制度とは

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、
財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合には、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に
一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、
その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税(※補足)へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、
相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
このように、相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。
【補足※暦年課税について】
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から
基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
(この場合、贈与税の申告は不要です。)
相続時精算課税の適用について

相続時精算課税の適用対象者
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者で、贈与者の推定相続人である子又は孫とされています。
相続時精算課税の適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
相続時精算課税における税額計算
①贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、
相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、
複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者が、
相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、
その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、
贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注)
相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
②相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、
それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、
相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
制度の適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子又は孫)は、
その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
相続時精算課税は、受贈者(子又は孫)が贈与者(父母又は祖父母)ごとに選択できますが、
いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
匠税理士事務所の相続税対策・税務コンサルティングサービス
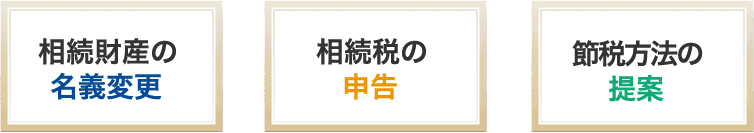
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税申告や、事業承継対策・相続税対策を承っております。サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成28年12月7日
世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所
相続した土地・不動産の相続税評価はどう行うか (16/11/22)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続した土地・不動産の相続税評価
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所では、目黒区や品川区、世田谷区を中心に相続税申告や相続税対策など税務コンサルティングサービスを行っております。
相続税や贈与税、事業承継などで財産評価を行う場合に、金額も大きく税額に影響する財産として土地が挙げられます。
そこで今回は、不動産のうちで土地を>相続税した場合の評価についてまとめてみました。
相続税や贈与税における宅地(土地)の評価方法

相続税や贈与税における宅地の評価については、その利用形態ごとに状況を斟酌して評価を行うように定められています。
(1)自用地
自用地とは、所有者の自由になる、土地に他の権利や制限がない宅地をいいます。
評価しようとする宅地が自用地の場合は、路線価方式または倍率方式により
評価した金額そのものがその宅地の評価額となります。
関連記事
(2)借地権
借地権とは、家屋の所有を目的として賃借している宅地に関する権利をいいます。
借地人は土地の所有者ではありませんが、借地権は借地借家法によって強く保護される権利であり、
財産価値を有することから
借地権も相続税や贈与税の課税対象になります。
借地権の価額は、借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に借地権割合を乗じて求めます。
この借地権割合は、借地事情が似ている地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表に表示されています。
評価額=自用地としての価額×借地権割合
(3)貸宅地
貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいいます。
貸宅地は借地人の家屋の敷地であるため、自用地と比べて著しくその土地の利用が制限されます。
そこで、貸宅地の評価額は自用地評価額から借地権相当額を控除した金額となります。
この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、
次の算式の借地権割合を20%として計算します。
評価額=自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合
(4)貸家建付地
貸家建付地とは、貸家の目的とされている宅地、すなわち、所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
この場合、貸家には借家人やテナントが入居しているため、その土地の利用が制限され、
また、借家人やテナントに立ち退いてもらう場合には立退料が必要になることも考えられます。
そこで、貸家建付地の評価も自用地評価額から一定の評価減を行います。
評価額=自用地としての価額-(自用地とした場合の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(5)私道
私道には、
①公共の用に供するもの
例えば、通抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合
②専ら特定の者の通行の用に供するもの
例えば、袋小路のような場合があります。
そのうち、
①に該当するものは、その私道の価額は評価しないことになっています。
②に該当する私道の価額は、
その宅地が私道でないものとして路線価方式又は倍率方式によって評価した価額の30%相当額で評価します。
評価額=自用地としての価額×30%
相続した土地・不動産の相続税評価の特例

【小規模宅地等の特例】
相続財産のうち、
その相続の開始の直前において居住または事業の用に供されていた宅地等がある場合に、その宅地の評価額の一定割合を減額することができる特例があります。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
相続税には、この他にも様々な評価の特例がございます。
特例を活用することで税額を大きく下げることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の相続税申告・相続対策コンサルティング
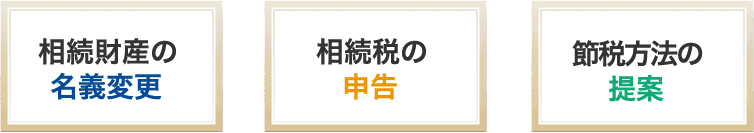
匠税理士事務所では、相続が発生した場合の相続税申告から、相続が発生する前の相続対策コンサルティング・事業承継サービスをご提供しております。
世田谷区や目黒区、品川区など東京都で相続税に関するご相談がございましたら、お気軽にご相談下さい。
コンサルティングサービスの詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
品川の税理士は匠税理士事務所
キャリアアップ助成金 (処遇改善コース)≪J2≫ (16/11/14)
匠税理士事務所では、助成金に特化した社会保険労務士と連携して、
世田谷や目黒、品川を中心に起業支援や経営支援を行っております。
今回は、キャリアアップ助成金のうち 「処遇改善コース」 についてまとめました。
<キャリアアップ助成金 制度全体の説明は こちら>
【関連記事: キャリアアップ助成金とは?助成金の申請代行 の解説 】
キャリアアップ助成金の処遇改善コースとは
キャリアアップ助成金の処遇改善コースでは、
有期契約労働者に次のいずれかの取組を行った場合に支払われます。
①すべて又は一部の基本給の賃金テーブルを改定し、2%以上増額させた場合
対象労働者の賃金テーブル等を改定した後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して
2か月以内に申請する必要があります。
②正規雇用労働者と共通の処遇制度を導入・適用した場合
対象労働者延べ4人以上に健康診断を実施した日の翌日から起算して2か月以内/
対象労働者の賃金テーブル共通化後、
当該賃金テーブル等の適用後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請する必要があります。
③週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し社会保険を適用した場合
短時間労働者の週所定労働時間延長後6か月分の賃金を
支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請する必要があります。
キャリアアップ助成金による助成額(※中小企業以外は下記よりも助成額が少なくなります)
①賃金テーブル改定
【すべての有期労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合】
対象労働者が1人~3人:10万円 4人~6人:20万円 7人~10人:30万円 11人~100人:1人当たり3万円
【一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
対象労働者が1人~3人:5万円 4人~6人:10万円 7人~10人:15万円 11人~100人:1人当たり1.5万円
②共通処遇推進制度
・法定外の健康診断制度を新たに規定し4人以上実施:1事業所当たり40万円
・共通の賃金テーブルの導入・適用:1事業所当たり60万円
③短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長
1人当たり20万円
匠税理士事務所の助成金申請代行サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に助成金の申請代行を行っております。
◇助成金サービス
◇TOPページ
最終更新日:平成28年11月14日
相続税における葬式費用はどうなるのか (16/10/19)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税における葬式費用
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
ホームページへのご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所は目黒区の自由が丘にある会計事務所です。
弊所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都を拠点に30代の税理士やスタッフが税務や経営コンサルティングサービスをご提供しております。
今回は相続税の税務申告における葬式費用は、どのように取り扱うのかについてまとめてみました。
相続財産から除ける葬式費用とは

相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を課税財産から差し引くことができます。
相続税の課税財産から差し引く葬式費用は、通常次のようなものです。
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
・葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(お通夜など)
・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
相続税計算で控除できない葬式費用

次のような費用は、
遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。
・初七日や四十九日の法要などのためにかかった費用
・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
税務申告後の税務調査でトラブルにならないように注意しましょう。
匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス
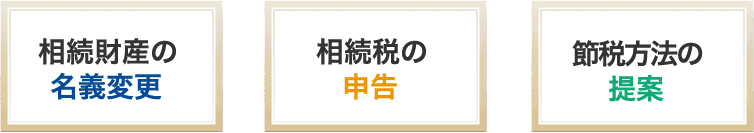
匠税理士事務所では、相続が発生した後の税務申告から名義変更・各種登記などの諸手続きを様々な分野の専門家と連携して承っております。
相続税申告から生前の相続対策コンサルティングをご要望のお客様は、お気軽にご相談下さい。
サービス詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
◆ 目黒区、品川区や世田谷区の相続税申告に強い税理士は匠税理士事務所
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成28年10月18日
世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所
キャリアアップ助成金 (正社員化・人材育成コース) ≪J1≫ (16/10/14)
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に助成金の申請代行や会社設立など
起業支援・経営支援に力を入れている会計事務所です。
今回はキャリアアップ助成金のうち、正社員化コースと人材育成コースについてまとめてみました。
キャリアアップ助成金における正社員化コースとは
制度の概要
就業規則または労働協約その他これに準じるものに規定した制度に基づき、
有期契約労働者等を正規雇用労働者・多様な正社員等に
転換または直接雇用した場合に支払われます。
転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して
2か月以内に支給申請する必要があります。
助成額(※中小企業以外は下記よりも助成額が少なくなる)
①有期雇用→正規雇用:1人当たり60万円
②有期雇用→無期雇用:1人当たり30万円
③無期雇用→正規雇用:1人当たり30万円
※派遣労働者を正規雇用で直接雇用する場合、1人あたり30万円加算
※母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は①10万円②③5万円加算
キャリアアップ助成金におけるとは人材育成コース
制度の概要
有期契約労働者を対象に正規雇用労働者等に転換、又は処遇を改善することを目指して
以下の職業訓練を実施した場合に支払われます。
職業訓練計画実施期間の終了した日の翌日から2か月以内に
支給申請書を管轄労働局へ提出してください。
①一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練を含む)
②有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
③中長期的なキャリア形成訓練(Off-JT)
助成額(※中小企業以外は下記よりも助成額が少なくなる)
※1事業所あたりの限度額は1年度500万円
【Off-JTの支給額】
・賃金助成:800円/1人1時間
・経費助成:一般職業訓練・有期実習型訓練・育児休業中訓練→最大30万円
中長期キャリア形成訓練(有期実習型訓練後に正規雇用等に転換された場合)→最大50万円
【OJT(有期実習型訓練)分の支給額】
・実施助成:800円/1人1時間
【関連記事:キャリアアップ助成金とは? 制度全体の内容について 】
キャリアアップ助成金など助成金の申請代行
匠税理士事務所では、目黒区や世田谷区や品川区を中心に、起業家の方や既に会社経営をされている方に向けて
助成金の申請代行サービスを提供しております。
助成金の申請や各種コンサルティングにつきましては、
助成金に特化した社会保険労務士と連携して、お客様のご要望にお応えします。
◇助成金サービス
◇TOPページ
最終更新日:平成28年10月14日
株式会社の設立には、いくら用意すべき? (16/10/11)
匠税理士事務所は、
品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に
株式会社の会社設立や創業時の資金調達を支援している会計事務所です。
今回は、株式会社の会社設立など起業をお考えの方から
頂くご相談である【 株式会社の設立には、いくら用意すべき? 】
についてまとめてみました。
株式会社など会社設立の必要資金はいくら?
従来は最低資本金制度のもと、
株式会社の設立には1,000万円必要でしたが、
会社法施行により、この規制が撤廃されました。
そのため資本金が1円でも会社が設立できます。
しかし、このような会社は登記こそできますが、
事業を行うにはかなり無理があります。
【 時折、最近できたと思っていたお店屋さんが、
すぐに閉店していた ということはないでしょうか? 】
色々な理由があると思いますが、閉店の理由はやはり資金不足が多いようです。
立が上がりに時間がかかってもいいように、必要な資金を注意深く算定し、十分に確保しましょう。
必要資金 = 運転資金 + 設備資金 + 生活資金
運転資金・・・事業が軌道に乗るまでの6カ月~1年の間の固定費と変動費の合計額
固定費:売上高に関係なく発生する費用。人件費や家賃など。
変動費:売上高に比例して変動する費用。仕入れや販売諸経費など。
(関連記事: 運転資金と設備資金の違い )
設備資金・・・機械や車など会社の事業運営に必要な設備のための資金
生活資金・・・6カ月~1年間の事業主の生活に必要な資金
起業資金の調達方法には、どんな方法があるのか
必要資金を調達するには、
大きく分けて次の方法が考えられます。
① 自己資金
② スポンサー
③ 金融機関からの借り入れ
④ 出資受入
⑤ 親戚や友人からの借り入れ
資金調達が可能かどうかは、事業主のもつ資産や信用力・人脈によって大きく変わってきます。
必要資金の全額が調達できない場合でも、
親戚や友人を拝みたおして借り入れすることは避けましょう。
こうした借り入れは返済が滞りがちになり、
大事な信用を失ってしまいますし、
場合によっては贈与税の対象となる可能性も出てきます。
また、必要資金が不足のまま事業を開始すると、
本来の営業活動が疎かになり、事業運営に行き詰まります。
調達した資金の範囲内で運営できるよう事業計画を再検討するのがよいでしょう。
資本金とは? いくら用意すべきか
資本金の額は会社の信用に影響することですから、
必要資金相当額は資本金としておいた方がいいでしょう。
事業をするにあたり、借入金とともに資本金も活動資金として使うことができます。
資本金が多い方がゆとりをもって経営に取り組むことができるのです。
ただし、無計画に大きな資本金で会社を設立するのも問題です。
資本金が1,000万円を超えると都道府県民税や市町村民税に影響します。
消費税の課税事業者の判定の観点からも、
設立時の資本金の額は最大でも1,000万円未満がいいでしょう。
( 関連記事: 会社設立と会社の資本金、1円の株式会社の問題点 )
匠税理士事務所の会社設立・創業融資支援サービス
匠税理士事務所では、
品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に会社設立・創業融資支援を行っております。
会社設立の際には、30代の税理士・司法書士が、
お客様のご要望お伺いし、会社設立をしっかりとサポートさせて頂きます。
また株式会社の会社設立後に、
創業融資や助成金などの資金調達をご要望のお客様には、
日本政策金融公庫や各種金融機関、助成金を専門とする社会保険労務士と連携し、
ご要望にお応えしております。
品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心とする
会社設立や創業融資などのサービス詳細につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
最終更新日:平成28年10月11日
会社設立などの起業支援以外の経営支援や税務コンサルティングサービス、
担当税理士や専門家につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
信用保証協会を活用した創業融資と資金調達 (16/10/05)
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に
これまで多くの起業のお手伝いをさせて頂きました。
その際に創業者の方々が一番お悩みになることは、
開業資金の調達です。
創業資金は、「自己資金+融資」で調達することがセオリーです。
しかし金融機関からのプロパー融資については、
ある程度の実績がないと可能性は著しく低いと思われます。
そこでまずは起業をお考えの方は、日本政策金融公庫の融資制度を利用するか、
もしくは、自治体の融資制度などで実績を重ねましょう。
関連記事→創業融資を申し込むために必要な書類(日本政策金融公庫) へのリンク
これら2種類の融資制度のうち、
自治体の融資制度は、信用保証協会の債務保証が下りて初めて
金融機関からの融資が実行されます。
そこでは今回は信用保証協会とその制度についてご紹介します。
信用保証協会とは何か
信用保証協会とは、これから創業される中小・零細企業者が金融機関から融資を受ける際に、
保証人になってくれる公的機関のようなものです。
この信用保証協会の債務保証を利用して、
民間金融機関から融資をうけることのできる制度を総じて
「保証付き融資」「マル保」「信保」と呼ばれています。
自治体が絡むとこれらを一般的に
「自治体融資」「自治体制度融資」「制度融資」などといいます。
信用保証制度のしくみ
信用保証協会は、創業者や中小事業者が何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合に、
債務者に代わって銀行に「代位弁済」します。
金融機関にとっては大変ありがたい制度なのです。
ただし、これはあくまでも一時的な立替払いですから、
その後信用保証協会は代位弁済したものについて取り立てを行うことになります。
そのため、日本政策金融公庫の融資は通常は、
公庫担当者との面談が一度で済みますが、
金融機関と保証協会の融資の場合には、
金融機関との面談と保証協会との面談の2度あることが
ほとんどです。
保証協会を利用可能な事業者とは
原則として、中小企業信用保険法に定める中小企業者(一定の規模以下の事業者)が対象です。
また、商工業のほとんどの業種で利用できますが、
農林漁業、風俗関連営業、金融業、宗教法人、非営利団体、その他協会において不適当と認める業種については利用できません。
しかしながら、信用保証協会によって多少見解が異なるケースもあるので、
詳しくは地元の信用保証協会のWEBサイトでご確認ください。
所在地や業歴については、原則として住所及び営業の本拠地が所轄の都道府県にあり、
一般的には、同一事業を同一場所で1年以上営んでいることが条件だとされています。
創業枠等については、開業前、または1年未満でも対象となります。
信用保証額について
無担保保証限度額・・・8,000万円
普通保証限度額・・・・2億円 (組合は4億円)
信用保証は、保証限度額以内なら複数に渡り利用が可能なので、
制度上は2億8,000万円(組合は4億8,000万円)まで利用できるということです。
しかしながら、この限度額とは別に、
自治体制度融資などについては融資要項等でそれぞれ融資限度額が決まっています。
これから創業したい、創業して間もない方への自治体創業融資の限度額は、
東京都の場合2,500万円ですから、信用保証限度額は2,500万円ということになります。
信用保証料とは
信用保証料とは、
信用保証協会が金融機関に対して中小企業者の保証をすることへの対価として支払うものです。
信用保証料は、中小企業信用保険の信用保険料や、代位弁済に伴う損失の補てんや、経費等、制度運営上必要な経費に充当されています。
信用保証料は、借入金額・保証料率、借入期間、返済方法により算出します。
匠税理士事務所の起業支援サービス
匠税理士事務所は、
30代の税理士を中心に起業支援に力を入れている会計事務所です。
品川区にある日本政策金融公庫の五反田支店様や各金融機関様と提携し、
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区の起業に伴う資金調達を支援しております。
創業計画書や融資面談の対策など創業融資支援サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
→ 目黒区や品川区、世田谷区の創業融資や起業の資金調達は匠税理士事務所
創業に伴う資金調達以外にも会社設立やその後の経理・経営支援も承っております。
会社設立支援サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
更新日:平成28年10月5日
起業支援以外の経営コンサルティングサービスなどのサービスラインや、
所属税理士の詳細などにつきましては、下記よりTOPへ移動の上、
ご確認を頂けましたら幸いです。
路線価方式や倍率方式など土地評価と相続税 (16/09/23)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>路線価方式や倍率方式
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
匠税理士事務所のホームページにご訪問ありがとうございます。
弊所は世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に税務コンサルティングに力を入れている会計事務所です。
今回は相続税や贈与税を計算するときに、
相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価する必要がありますので、土地の主な評価について説明します。
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
そして土地の評価方法には、大きくわけて路線価方式と倍率方式があります。
関連記事
◆ 相続した土地・不動産の相続税評価はどうやる?土地評価における路線価方式とは

路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の
1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価は、毎年7月にその年1月1日時点の価額として国税庁より公表されます。
路線価方式における土地の価額は、
路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、
その土地の面積を乗じて計算します。
<路線価を基とした評価額の計算例>
正面路線価(300千円)×奥行価格補正率(1.00)×面積(180平方メートル)=評価(54,000千円)
土地評価における倍率方式とは

倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
固定資産税評価額は都税事務所、市区役所又は町村役場で確認することができます。
また、評価倍率は路線価図とともに毎年公表されます。
匠税理士事務所の相続税申告・税務コンサルティングサービス
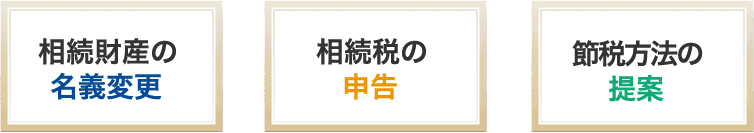
匠税理士事務所では、相続税に関する税務申告から生前贈与対策など相続税対策、事業承継対策など税務コンサルティングを行っております。
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に、司法書士・弁護士・資産税に特化した公認会計士と連携して、お客様のお悩みを解決できるようにしております。
相続対策サービスや税務申告サービスにつきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成28年9月23日
相続税以外のサービスや税理士・スタッフの経歴などにつきましては下記よりTOPページへ移動の上でご確認を頂けましたら幸いです。
出張に伴う日当や旅費、出張手当を活用した節税対策は旅費規程が必要!! (16/09/21)
匠税理士事務所は世田谷区や目黒区、品川区など
東京都23区を中心に起業や経営支援、
税務コンサルティングに力を入れる会計事務所です。
今回は、会社設立など起業される方、
法人化をしたい方、既に会社経営されてる方など
会社形態で事業を行われている方に向けて
旅費規程・出張規定を活用した出張に伴う日当や旅費、出張手当の節税対策をまとめました。

旅費規程が必要な出張に伴う日当・出張手当と節税対策とは?
出張手当とは、出張した役員・従業員に対して
会社から支給する手当で、出張の際に実費として
支出する交通費・宿泊費以外に支出する手当です。
個人事業主の場合、出張の際に生じる交通費や
宿泊費の実費は必要経費となりますが、
出張手当や日当を必要経費にできません。
一方、法人成り・法人化して会社設立した場合や、
既に会社を経営されていて出張が多い会社の方は
出張費用の実費が必要経費となるのはもちろん、
会社が社長に対して出張手当や
日当を支払ったものについても
必要経費(損金)とすることが可能になります。
また、消費税法上の取扱いは
交通費や宿泊費と同様に
課税仕入れとして仕入税額控除ができます。
更に出張手当を受け取る側の社長・従業員も
出張手当は所得税・住民税がかからず節税となり
社会保険料対象とならないメリットがあります。

旅費規程・出張規定作成で何に気をつけるべき
メリットばかりに思える出張手当や日当ですが、
出張手当等が社会通念上不相当に高額である場合、
非課税所得とならず給与課税となるため注意です。
会社が出張した役員・従業員に対して
出張手当や日当を支給するためには、
【旅費規程や出張規程】を作成して出張者の役職や
出張距離に応じた手当を定める必要があります。
そして税務調査の際には、この旅費規程や
出張規定が社会通念上相当である旨を
統計値などを活用して説明する必要が出てきます。
◆旅費・出張手当の取扱い◆
【 個人事業 】
出張で必要な交通費や宿泊費実費が必要経費となる
【 法人 】
規程・社会通念上内で支給の出張手当・日当は損金
匠税理士事務所 税務コンサルティング
匠税理士事務所では世田谷区や目黒区、品川区など
東京都23区を中心に税理士による税務コンサルティングや
節税対策をご提供しております。
出張手当や日当を支給するための
【旅費規程】・【出張規程】作成や、
慶弔見舞金の規定作成など会社の規定を活用した税務コンサルティングに力を入れる事務所です。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
出張時の車両設備など起業資金調達で
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
出張が多い業種も対応する規定作成から
会社設立までのサービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人事業主で独立開業し会社にする
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

税務調査対応はこちらで確認下さい。
個人事業を株式会社や合同会社にして節税する
法人化を検討中の方はこちらから
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】
執筆者・文責 税理士水野智史
#出張日当 #出張手当 #旅費規程
創業融資では何に気をつけるべき?融資担当者の視点から (16/09/12)
サービス起業>創業融資支援サービス>創業融資では何に気をつけるべき
創業融資のサービスやお役立ち情報はこちら
創業融資サービス 世田谷・目黒・品川に対応
第11回 匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心にこれまで日本政策金融公庫をはじめ、各金融機関と連携して多くの創業融資を支援させて頂きました。
そこで今回は、創業融資を受ける場合に、何に気をつけるべきなのか?についてまとめてみました。
創業融資の場合、融資担当者は何に注意しているか

世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区での創業融資では、融資担当者は「人物」「将来性」「確実性」などに大きくウェイトを置いています。そのため、次の点に注意が必要です。
創業者の場合
① 事業に必要な経営能力があるか?:経営能力の有無
・創業の動機
・事業の経験
・事業に対する考え方
:事業計画の妥当性
・収支予測の組み立て方
・収支予測の見通しについての考え方
②本当に売り上げが立てられる計画となっているのか?
その計画が事業として継続できるものかどうかは非常に重要です。
商売として成立する(=継続的に売り上げ・利益が出る)ためには事業の仕組みがしっかりしていることが必要です。
:事業の仕組みの裏付けには下記からなる事業計画の妥当性を要します。
・収支計画
・資金繰り
・財務的根拠
※融資対策上、「販売先」と「販売予定」の確保がポイントアップにつながります。
③返済が滞りなく行える計画となっているか?
売上以上に原価や経費がかかってしまうと、返済に支障が出る可能性があります。
そのため、収入・支出・利益のバランスが重視されます。
具体的に、利益が捻出できるかどうかは次の算定式で計算されます。
a (税引き後利益 + 減価償却費 - 個人事業の場合には生活費 ) > b(返済額)
aの部分が返済の引き当て分と判断されます。
a>bであるとき、融資の見込みありと判断されます。
④数字は根拠をもって作られているか?
事業計画書に記載する数字は「裏付けがあるもの」であり、
「実行が可能なもの」でなければなりません。
例えば、事業用の設備や事務所備品などは金額の根拠として
見積書やインターネットの価格カタログ等を準備することがその根拠となります。
※融資対策上、今後1年間の予想収支である「創業後の見込み欄」の記入のみでなく
各月ごとの予想収支である「月次収支予定表」を添付することで、
計画がより具体的で明確となります。
その他の創業融資のお役立情報バックナンバーは創業融資の情報館 バックナンバー へ。
匠税理士事務所の創業融資支援サービス
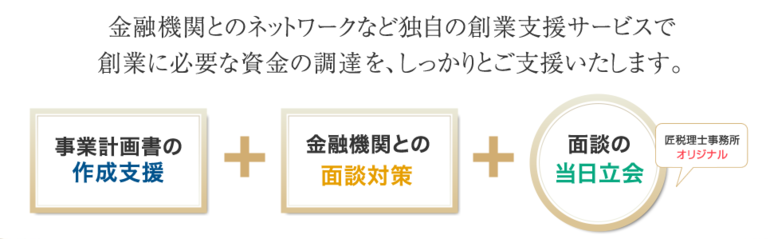
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に創業融資などの資金調達支援を通じて起業をサポートしております。
・創業計画書の作成をしたいが、よく分からないので相談したい
・自己資金と融資による調達可能額のイメージをしりたい
・本業に集中して起業したいので、経理や資金回りをサポートして欲しい
このようなご相談を承っております。
匠税理士事務所の創業融資支援サービスにつきましては、下記よりご確認を頂けましたら幸いです。
創業融資支援サービス
創業融資のお役立情報バックナンバーは
創業融資の情報館 バックナンバー へ。
記事については免責事項をご確認下さい。
匠税理士事務所の会社設立サービス
起業を検討中の方に向けて、会社設立専門の司法書士と連携して、創業融資以外にも会社設立の代行から経営支援も承っております。詳細につきましては、こちらよりご確認をお願い申します。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
起業支援サービス一覧
給与計算サービス...給与計算の代行や、社会保険の加入手続き、人事労務のサポートサービス。
助成金サービス...正社員化や社員教育についての助成金代行とコンサルティングサービス。
法人のお客様向けサービス...黒字戦略や財務強化などのオリジナルサービスのご紹介
【税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区】
最終更新日:平成28年9月12日
起業以外のサービスラインや所属税理士の紹介は、以下のTOPページよりご確認を頂けましたら幸いです。
会社設立にはどんな印鑑が必要?K12 (16/09/07)
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心にこれまで多くの会社設立を支援させて頂きました。
その中でよく頂くご相談の一つに、【会社設立をしたら、どんな印鑑が必要ですか?】
というご相談がございました。
そこで今回は会社設立後に一般的に必要となる法人の印鑑について記載します。
企業の実印である代表者印 (法人実印)
代表者印 (法人実印)とは、会社が法人登記を行なった法務局に登録がされた印鑑のことを指します。
代表取締役や代表社員が契約書等重要な書類に押印することから、代表者印と呼ばれています。
代表者印(法人実印)を押印するということは
すなわち会社の意思決定を示すこと。したがって、全ての会社に必要なはんこであり、大切に保管されている最重要な印鑑でもあります。
≪使用例≫
・登録申請書・委任状
・金銭消費貸借契約書
・不動産売買契約書や担保物件の設定契約書
・連帯保証をする際の契約書
・そのほか取引先・役所など相手方から特に要求された場合
代表者印を法務局に登録すると、印鑑カードの交付を受けることができます。
このカードは「印鑑証明書」の交付の際に窓口に提示する必要があります。
代表者が変更した場合、この代表者印を引き継ぎます。
代々受け継がれていくため、個人名は入らないのが通常です。
金融機関との取引に必要な法人銀行印
法人銀行印は銀行口座を開設する際に、金融機関に登録を行う印鑑のことを指します。
企業以外、私達が日常的にお金を振り込んだり引き出したりする際に使用している銀行印と基本的な使い方の違いはありません。
会社の大切なお金を預かる金融機関に届け出る印鑑なだけあって、実印と同様に厳重な管理が必要な印鑑の1つでもあります。
基本的に銀行印と通帳があれば窓口において預金が引き出せるため、管理を徹底することが求められます。
銀行印は金融機関のルールに合っていればどのようなはんこでも登録が可能なため、代表者印(法人実印)を銀行印として登録することも可能です。
しかし、セキュリティの面から考えて銀行印は新しく専用の印鑑を作成することが推奨されています。
日常的に使用される角印
角印は、見積書や請求書など日常業務に使用されているはんこです。
横長で長方形が多く採用されており、日常的に使用される会社の認印のこと多くの人が角印と読んでいるようです。
人によっては、社印や社判などと呼んでいます。
見積書や請求書などはもちろん押印の必要な書類ですが、実印を押すほどではありません。
かといって銀行印を日常的に使用するのも安全面から控えるべきです。
このような状況の中で角印は簡単で便利なはんことして多くの企業で重宝されているのです。
このような理由から、起業された方の多くは上記の3つの印鑑を作られる方が多いです。
匠税理士事務所の会社設立サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に会社設立の手続きから創業融資などの資金調達など起業支援を行っております。
会社設立後の経理や経営支援も行っておりますので、お客様が安心して本業に集中できるようにお手伝いしております。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
母子家庭の方を雇用した場合の助成金≪J6≫ (16/08/31)
母子家庭の母の方を雇用された場合には、
特定就職困難者雇用開発助成金を検討することができます。
特定就職困難者雇用開発助成金とは高齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、
これらの方の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
母子家庭の母等も助成金の対象労働者となっています。
<助成金の対象者
母子家庭の母等に該当する求職者であり、
かつ紹介を受けた日において雇用保険被保険者でない者(失業等の状態にある者)
【 雇入れの条件 】
対象労働者を次の(1)(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
【 注意点 】
対象労働者が、以下に該当する場合には助成金の支給対象外となりますので注意が必要です。
・雇い入れ日の前日から過去3年間に雇入れ事業主に雇用されたことがあった場合
・紹介を受ける前から雇用の内定があった場合
・雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族である場合
また、雇入れ事業主が、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過するまでの日の間に
雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇したことがある場合は支給対象外となる、
など事業主側にも条件があります。
他にも支給対象外となるケースがありますので、申請の際には要件を確認したうえで行う必要があります。
助成金の支給額
対象労働者の雇入れに係る日から起算して1年間を対象とし、
6か月ごとに2期に区分して支給されます。
短時間労働者以外:60万円(中小企業以外は50万円)…30万円(25万円)×2期
短時間労働者 :40万円(中小企業以外は30万円)…20万円(15万円)×2期
ただし、支給対象期ごとの支給額は、
支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合(※)や所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、
支給額が減額されます。
(※)支給対象期の初日から1か月以内に離職した場合には支給されません。
【 受給手続き 】
本助成金を受給しようとする事業主は、
支給対象期ごとに、それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に
支給申請書に必要な書類を添えて管轄の労働局へ支給申請してください。
本助成金の詳しい内容、最新情報については厚生労働省のホームページを参照してください。
また、要件や手続き等の詳細についての問い合わせは最寄りの労働局またはハローワークで受け付けています。
匠税理士事務所の助成金の申請代行サービス
匠税理士事務所では、起業や雇用に伴う助成金の申請代行サービスを提供しております。
提携の社会保険労務士と連携して、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を 中心に助成金の申請代行を承っております。
助成金の申請代行サービスの詳細は、こちらよりご確認ください。
◇助成金サービス
対応地域【 世田谷区や目黒区,品川区など東京都23区対応】
その他のサービス、所属税理士・提携社会保険労務士は、こちらよりご確認ください。
◇TOPページ
最終更新日:平成28年8月31日
相続税の税率と税額計算の仕組み (16/08/26)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税の税率と税額計算
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第6回 遺産分割協議と相続税の申告
第7回 相続税の税率と税額計算の仕組み
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に
直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を
民法に定める相続分により按分した額に税率を乗じます。
この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに
用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算に当たっては、
法定相続分により按分した法定相続分に応ずる取得金額を
下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
相続税の税率は、各相続人が取得する金額が多いほど税率も高くなる、
超過累進税率という仕組みになっています。
改正前と改正後の相続税の税率

<「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」が平成27年1月1日以後の場合>
法定相続分に応ずる取得金額/税率/控除額
・1,000万円以下 /10% /-
・3,000万円以下 /15% /50万円
・5,000万円以下 /20% /200万円
・1億円以下 /30% /700万円
・2億円以下 /40% /1,700万円
・3億円以下 /45% /2,700万円
・6億円以下 /50% /4,200万円
・6億円超 /55% /7,200万円
<「相続の開始の日(被相続人の死亡の日)」が平成26年12月31日までの場合>
法定相続分に応ずる取得金額/税率/控除額
1,000万円以下 /10% /-
3,000万円以下 /15% /50万円
5,000万円以下 /20% /200万円
1億円以下 /30% /700万円
3億円以下 /40% /1,700万円
3億円超 /50% /4,700万円
法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
【 相続税対策としては、相続前に財産を移転する生前贈与も効果的です。 】
生前贈与の場合の贈与税率の仕組みと計算方法などはこちらから。
匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス
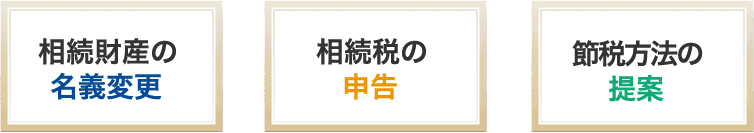
世田谷区や目黒区、品川区など東京都を中心に相続税申告・相続対策サービスをご提供しております。
相続が発生した後の有効な遺産分割のご提案から相続が発生する前の贈与を活用した相続税対策までを承っております。複雑な案件は業界最高峰の相続税に特化した税理士と提携して対応できるような体制をご用意しております。相続に伴う名義変更などもお任せ下さい。
相続税申告・相続対策サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成28年8月26日
相続税申告以外のサービスラインにつきましては、こちらです。
法人化や法人成りによる慶弔見舞金規定の作成と節税対策 (16/08/18)
法人化や法人成りをご検討中の方は、
消費税の免税期間や、法人税率と所得税の税率差などについて
節税対策に魅力を感じていらっしゃる方も多いと思います。
【関連記事】
→ 会社にする?個人のまま? 法人化ポイント(メリット・デメリット)へ
今回は、法人化や法人成りに伴うメリットである
慶弔見舞金規定の活用と節税対策について記載しました。
慶弔見舞金等に関する個人事業と法人の課税関係
個人事業主の場合、業務に直接関係のない親族の冠婚葬祭等に対して
金品を支給しても、その支出は個人的なものとされ
必要経費とすることができません。
一方、法人成りして会社を設立した場合には、
「福利厚生規程」や「慶弔規程」を作成することにより、
その規程に従って役員・従業員に支給する慶弔見舞金(結婚祝・出産祝や見舞金)は、
社会通念上の範囲内の額であれば
福利厚生費として経費処理することができます。
慶弔見舞金を受け取る側の社長や従業員側では、
所得税・住民税非課税、社会保険料の対象外となり節税対策となります。
この慶弔見舞金は役員・従業員本人だけではなく
役員・従業員の家族に対する支給も含まれます。
「福利厚生規程」や「慶弔規程」において、
役職や勤務年数に応じた社会通念上の相当額を支給金額として
設定し基準を定めておくことが
課税当局とのトラブルを回避することにつながります。
慶弔見舞金等の税法上の取扱い
個人事業では、業務遂行上直接必要な慶弔見舞金は必要経費となります。
法人では、各社内規程に則り、
社会通念上の範囲内で慶弔見舞金が交際費や福利厚生費になります。
ここでのポイントは、こうした社内規定を作る際に、
1・・世の中の同業他社と比較して社会通念上、
適正な金額であることを立証できる資料を用意したうえで、規定を作成すること。
2・・規定にしたがって支給している などといったことが挙げられます。
【関連記事】
→ 出張に伴う日当や旅費、出張手当の活用に旅費規程が必要!?へ
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス
匠税理士事務所では、法人化に伴う個人事業の廃止に伴う確定申告から
会社設立後の経理代行、会社設立手続き、慶弔規定などの作成など
法人化や法人成りに伴うすべてや節税対策を支援しております。
法人化や法人成りをご検討中の方は、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
税理士の対応地域は、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域となります。
最終更新日:平成28年8月18日
上記以外のサービス内容につきましては、
以下よりTOPページへ移動の上でご確認をお願いします。
キャリアアップ助成金とは?助成金の申請代行≪J7≫ (16/08/08)
キャリアアップ助成金の内容
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の方の
企業内でのキャリアアップ等を促進するため、
これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
助成金は次の3つのコースに分けられます。
1.正社員化コース
有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成するコース
2.人材育成コース
有期契約労働者等に対する職業訓練を助成するコース
【関連記事:キャリアアップ助成金(正社員化コース・人材育成コース)の解説 】
3.処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金テーブルの改善、健康診断制度の導入、賃金テーブルの共通化、
短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成するコース
【関連記事:キャリアアップ助成金(処遇改善コース)の解説 】
キャリアアップ助成金の支給対象事業主
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の
受給資格の認定を受けた事業主であること
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
・支給申請時点において、対象労働者について、事業主都合による解雇をしていない
(天災、その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、
または 労働者の責めに帰すべき理由により解雇した場合を除く)事業主であること
キャリアアップ計画とは
有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、
今後のおおまかな取り組みイメージ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組み)を
あらかじめ記載するものです。
・3年以上5年以内の計画期間を定める
・「キャリアアップ管理者」を決める
・「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って、おおまかな取り組みの全体の流れを決める
・ 計画対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う取り組みなどを記載する
・ 計画の対象となる有期契約労働者や無期雇用労働者の意見が反映されるよう、
労働組合な どの労働者の代表から意見を聴く
匠税理士事務所の助成金申請代行サービス
匠税理士事務所では、これから起業をお考えの方、既に会社の経営をされていらっしゃる方にむけ、
助成金の申請代行サービスを提供しております。
助成金に詳しい社会保険労務士と連携し、助成金に関するコンサルティングを行っております。
助成金の申請代行サービスは、こちらよりご確認ください。
◇助成金サービス
上記以外のサービスや、所属税理士はこちらよりご確認ください。
◇TOPページ
→ 世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所
【税理士の対応地域:世田谷区・目黒区・品川区など東京都23区全域】
最終更新日:平成28年8月8日
株式会社での会社設立の注意点やポイント (16/08/02)
そもそも会社設立をする場合に
どのような種類があるのでしょうか?
会社の種類は、大きく分けて
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。
一番設立数の多い株式会社は、
設立費用が他の3種類での会社設立よりかかりますが、
社会的信用度が高い、引先拡大のチャンスが大きくなる、
銀行融資が受けやすい、よりよい人材を集めやすいなどのメリットがあります。
そのためどの形態で会社設立をされるかお悩みの場合には、
株式会社を設立されることをお勧めします。
株式会社設立の注意点やポイント
≪取締役について≫
株式会社は、会社法施行後、
最小取締役1人で株式会社はつくれるようになりました。
取締役が1人のときは、その者が代表取締役となります。
役員の任期は原則2年ですが、定款に定めれば10年まで伸ばせます。
取締役が3人以上いるときは取締役会を設置することができます。
取締役の選任・退任は謄本に履歴が残りますので、
任期を長くして中途で退任の場合には、任期途中の退任が形に残ってしまいます。
社長一人で株式会社を設立される場合には、
任期は最長の10年間をお勧めしますが、
ご友人などと会社設立される場合には、
任期を短めにしておくことをお勧めします。
≪株主総会について≫
株式会社は決算が終わってから
通常3カ月以内に毎年株主総会を開かなければなりません。
多くの中小企業では、
決算から2か月以内が税務申告期限となりますので、
こちらの期限に合わせて2か月以内に開催するのが一般的です。
関連記事
しかし上場企業の場合には、
監査などの関係から決算の確定に時間がかかることが多く、
決算から3か月目に株主総会を開催したりします。
このような場合には、
税務署や都税事務所などの所轄官公庁に予め申告期限の延長を行い、
税額の見込計算・納付を2か月以内に済ませ、
株主総会で決算が確定する3か月目に税務申告を行うという流れとなります。
このとき、取締役会を設置していない場合、
招集手続き等が簡単になります。
≪機関設計について≫
株式会社の機関設計には、
それぞれ設立する会社に適したものを選択しましょう。
機関設計の大原則は、株主総会と取締役を設置することです。
また、取締役が3名以上いるときは取締役会を設置するかどうかを選択できます。
身内だけの小規模な会社では、
経営上の意思決定を迅速に行えるので設置しない場合がほとんどです。
一方、経営方針をしっかり話合いたい場合や、
対外的にしっかりとした会社という印象を与えたい場合には取締役会を設置します。
また、株主に同族関係者以外が含まれる等会社が複雑になってくると、
所有と経営を分けるため、取締役会を設置します。
この場合、監査役または会計参与を選任する必要があります。
株式会社での会社設立、実際はどうなのでしょうか
会社設立の理論的な話は上記の通りですが、
実際には出来る限りシンプルな役員構成・株主構成をお勧めしております。
なぜなら、最初の内は役員・株主間で仲がいい場合でも、
何らかの理由で不仲になるときが出てきます。
その際に出資に係るお金や、
会社での経営における実行権が絡んでくると、
より事が複雑になってしまうからです。
しばらくはシンプルな形で経営をしていき、
軌道にのってきたら、提携の形を模索したりする方法をお勧めしております。
匠税理士事務所の会社設立・起業支援サービス
匠税理士事務所では、
・資本金は幾らにした方がよいのか
・役員や株主構成での注意点
・今後の経理の進め方
・入金と支払のサイクルを決める際のポイント
など法務面・税務面・経理面・経営面の多角的な視点で、
お客様の会社設立をサポートしております。
匠税理士事務所の会社設立サービス詳細につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
最終更新日:平成28年8月2日
【税理士の対応地域:目黒区・品川区・世田谷区など東京都23区全域】
会社設立以外の経営支援などのサービスや、
各種アウトソーシングサービスにつきましては、
以下よりTOPページへ移動の上で、ご確認を頂けましたら幸いです。
法人化・法人成りによる退職金を活用した節税対策 (16/07/27)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化退職金の活用
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
法人化・法人成りによる退職金制度の活用によるメリット

個人事業の場合には、事業主は何十年勤務しても退職金を受け取ることができません。
事業主ご本人だけではなく、事業専従者として勤務する妻や子供などの家族従業者に退職金を支給したとしても必要経費にはなりません。
一方、法人成りして会社を設立した場合には、
将来自分が役員等を退任した時には、会社から退職金を受け取ることが可能になります。
家族が役員や従業員である場合には、
その家族が退職する際には会社から退職金を支給することができるのはもちろん、
社長であるご自分の役員退任の際に退職金を支給することができます。
退職金の税務上の取扱い

個人事業・・・自己または事業専従者に対する退職金の支給は必要経費にならない
法人・・・・・退職金規程に則り、社会通念上の範囲内で退職金として損金になる
退職金を受け取る個人側においては、
退職所得の計算の際に勤務年数に応じて一定の控除を受けられる他、
税率をかける前に1/2を乗じるので実質的な税率は半分になり、
分離課税であるため他の所得と合算する必要がないという税制上の優遇措置を受けることができます。
退職所得控除とは?
退職所得の金額は次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
上記計算式における退職所得控除額は勤務年数に応じて以下のように計算します。
勤務年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円× A(80万円に満たない場合は、80万円)
20年超 800万円+70万円×( A-20年)
個人事業から法人成りして会社を設立した場合において、
個人事業当時から引き続き勤務している従業員が退職する場合に支払う退職金の計算上、
適用される勤務年数は個人事業当時の勤務期間を通算することができます。
ただし、退職給与規程等に個人事業当時からの期間を含めた勤続期間を
基礎として退職金を計算する旨が定められていることが必要です。
また、青色事業専従者であった者の場合は、
会社設立の日から退職するまでの期間が勤続年数となるため
個人事業当時の勤務期間を通算することができないので注意が必要です。
(所得税法施行令第69条第1項、所得税基本通達30-10)
小規模企業共済制度を活用した退職金と節税
退職金に近い制度として小規模企業共済制度があります。
この制度は個人事業者や一定の会社役員が加入する制度で、
廃業時や役員退任時に積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができます(加入条件あり)。
共済金の受け取り方法にはいくつか選択肢がありますが、
一括で受け取る場合は退職所得扱いとなります。
共済金掛金は月額1,000円から70,000円であり最大で年額84万円となります。
この掛金は必要経費とはなりませんが、その年に支払った掛金の全額が所得金額から控除されます。
一定の要件を満たせば、法人成り後も引き続き会社役員として加入し続けることも可能です。
会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス
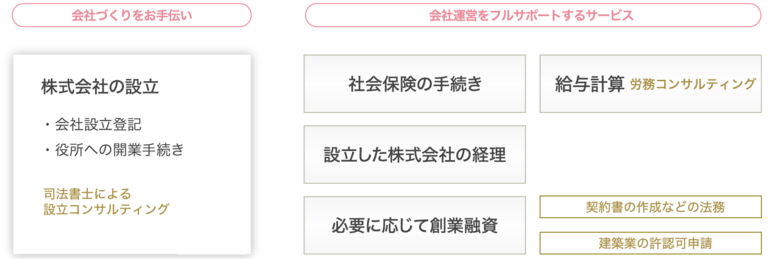
匠税理士事務所では、退職金を活用した節税対策や、法人化・法人成りに伴うお客様の様々なニーズにお応えしております。
・会社にした方がいいか悩んでいる
・会社にしたいが手続きが大変そう・・・
このようなお客様の少しでもお役に立てれば幸いです。
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
【1】世田谷や目黒,品川など東京都での法人化・法人成りサービス の詳細はこちら
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
税理士対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域
最終更新日:平成28年7月27日
東京都 税理士の匠税理士事務所HPへ
建設業や建築の独立開業に何が必要か?やり方・方法とは (16/07/22)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
今回は、建設業や建築の独立開業に何が必要か
独立開業するためのやり方・方法をまとめました。
弊所では建設業や建築関連のお客様が多いため、
【 独立開業 】を多くお手伝いしております。
建設業や建築で独立開業される方で、
業界が未経験という方はほとんどおらず、
前職で設備工事・防水工事・内装工事・解体など
【 様々な専門分野 】をお持ちです。
独立開業後は、この技術・ノウハウを売る事になるため
販売するものは、既に決まっています。
それでは他に建設業や建築で独立開業で
何が必要になるのかというと
大きく分けて2つを決めればよいのです。
1 事業を行う箱(組織)を決める個人で行うか 又は 会社で行うか
2 資金調達をするのかしないのか自己資金のみで行うのか、借り入れするか?
これらを決めてしまえば、書類作成などは
専門家の代行で完結できます。
以外に簡単ですね。
建設業や建築の独立開業は個人・会社どちらがよいか
個人事業主か会社で独立開業かでは、
以下のメリット・デメリットを考えて判断すべきです。
個人事業主は、・会社のように設立費用がかからない
・自分でソフトなどでできる簡単な帳簿で対応可能
というメリットがありますが、
・会社に比べ信用力が低く借入・求人に適さない
・利益が出たら節税手法が狭いデメリットがあります。
 一方で株式会社・合同会社など会社は、
一方で株式会社・合同会社など会社は、
・信用力があり借入・求人では有利
・利益が出た時、節税手法が広いメリットがありますが、
・登録免許税など設立費用の約25万がかかる
・帳簿が複雑で自分で難しいデメリットがあります。
個人事業主 と 株式会社・合同会社など会社は、
メリットやデメリットが表裏一体で、
最初はそんなに売上がたたないかもしれないし、 いつまでやるか分からない場合には、 個人事業主の方がおすすめです。 逆に、最初から前職のお客様などとの案件が 既に決まっている場合や借入・求人も 積極的に行う場合には、 株式会社・合同会社など会社がおすすめです。
これらはどちらが良いというわけでなく、
経営観や人生観の問題ですので、
独立開業される方の今後のビジョンに
あわせて決めるべきです。
ただ会社員の給与は、自分が会社に貢献した売上の
おおよそ3割程が世の中の目安となりますが、独立開業後は、売上から経費を差し引いた利益が
【 自分の儲け 】となります。
やり方次第では、無限に稼げるという点は、
やはり独立開業の大きな魅力です。
建設業や建築の独立開業、創業融資は必要か?
事業を行う箱(組織)を決めたら、
後はこれらを実現する資金の調達が必要です。
借入は嫌なので自己資金のみで事業するのも
一つの立派な考え方ですが、
資金が最初からある程度確保出来ていれば、
材料や機械・車や外注人材で制約を受けずに
仕事のオファーがあれば受注できるため
独立開業時は借入の活用をお勧めしております。案件を資金の制限無しに請けられれば、
各案件でしっかりと利益確保することで、
お金がたまりやすいことを意味します。

金利は2%ほどですので、建設業・建築工事で
それ以上に利益を上げればよいというわけですし、
必要なければ使わずにおけばよいわけで
入金遅れの時には精神安定剤にもなります。
それでは建設業や建築の独立開業の資金調達は
どんな方法・どこがおすすめかといいますと、
1 日本政策金融公庫の創業融資 2 各自治体の制度融資これらがおすすめです。
なぜなら、建設業や建築の独立開業はリスクがあり、
通常の銀行などの金融機関は担保などがなければ、融資対応しませんが、
上記2つは、国と自治体ですので経済活性化など
公的な目的を有しているため、
建設業や建築の独立開業などのリスクも
加味して考えてくれるからです。
匠税理士事務所の創業融資は、
こちらからご確認をお願いします。

建設業や建築の独立開業支援サービス
建設業や建築は一件の工事金額が大きいため、 販売力と施工力次第で1年目で億の売上も可能な 非常に【 夢 】のある事業です。一方で受注から納品までの期間が長く材料や
外注費の立替金額が大きくなったり、
現場での事故や工期遅れなど納品まで
トラブルが生じやすいという
ハイリスク・ハイリターンな性格も有します。匠税理士事務所では建設業や建築の独立開業が
成功するよう日本政策金融公庫や金融機関と
連携して建設業・建築業の資金調達を支援します。
【世界4大会計事務所出身税理士】が計画書作成、融資面談の立ち合いまで支援することで
【融資成功率は9割】を超えております。
また、事故やトラブルは、人事労務の専門家の社労士や
弁護士とチームで対応致します。
税務会計以外の助成金・補助金も対応しており、
【独立開業に必要な全てがそろう事務所】です。
建設業・建築業に強い匠税理士事務所詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
建設業・建築業向け会社設立や補助金・助成金など
起業サービス一覧はこちらから
【→ 起業のお客様サービス一覧】

建設業・建築業担当の税理士・提携専門家は、
こちらからご確認をお願いします。

建設業や建築の独立開業に何が必要か?やり方・方法とは
についての御案内を最後までお読み頂きありがとうございました。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
相続税がかからない財産とは (16/07/21)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税がかからない財産
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第1回 相続時精算課税制度と相続税対策
第2回 相続した土地・不動産の相続税評価
第3回 相続税における葬式費用
第5回 相続税がかからない財産
第6回~10回はこちら 相続税バックナンバー6-10
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 相続税申告・相続対策サービス
相続税の計算においては、原則として相続等により取得した財産は、すべて課税の対象となります。
しかし、その中でも社会通念上相続税の対象とすることが適当でないものについては相続財産から除くこととされています。
相続税がかからない財産には何があるのか

相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
(1)仏壇、仏具、墓地など
日常礼拝の用に供する上記などのものは相続財産から除かれます。
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや、
商品として所有しているものは相続税がかかります。
(2)死亡保険金のうち非課税限度額までの金額
被相続人の死亡によって取得した死亡保険金のうち、
被相続人が保険料を負担していた分は相続税の対象となりますが、
このうち、下記の非課税限度額までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
(3)死亡退職金、功労金のうち非課税限度額までの金額
被相続人の死亡により受け取った退職手当金、功労金などで、
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは相続税の対象となりますが、
このうち下記の非課税限度額までの金額は相続税の対象から差し引くことができます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
なお、被相続人の死亡後3年経過した後に支給が確定した退職金などは、
受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。
(4)弔慰金のうち非課税限度額までの金額
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、
葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
しかし、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、
実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
上記以外の部分については、下記の金額までを弔慰金等に相当する金額とし、
その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき・・・被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき・・・被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
※普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
(5)国、地方公共団体等へ寄付した一定の要件を満たす財産
相続や遺贈によって財産を取得した人が、
その財産を相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や
公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附した場合には、その財産は相続税の対象となりません。
匠税理士事務所の相続税申告・相続対策サービス
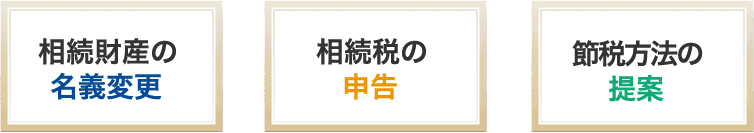
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域を中心に相続が発生した後の相続税申告や、将来の相続を想定した相続対策サービスをご提供しております。
相続税申告・相続対策をご要望の方は、下記よりサービスの詳細をご覧ください。
匠税理士事務所の相続税支援サービス
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
<税理士の相続税申告対応地域:世田谷・目黒・品川など東京都全域>
相続税以外のサービスや、
所属税理士のプロフィールなどにつきましては、
以下よりTOPページにご確認の上で、ご確認を頂けましたら幸いです。
目黒区の制度融資・創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 (16/07/14)
目黒区制度融資による起業資金の調達を支援する
自由が丘の匠税理士事務所の税理士水野です。
これから創業したい方で、重要なことは、
やはり【起業時のお金】の準備です。
全額自己資金で起業される方は一部で、
多くの方は、創業融資を利用されます。
そこで、今回は目黒区で起業される方に向け
創業融資のうち主要な資金調達方法の
【1 目黒区の制度融資】【2 日本政策金融公庫の創業融資】を記載します。
両者を比較し、【メリット・デメリット】を把握し、
どちらがよいのか、又は 両方同時に活用かを
検討するとよろしいかもしれません。
既に目黒区の制度融資をご存じで、
計画書作成や面談サポートなど融資サービスについては、
下記よりご確認をお願いします。
目黒区制度融資を知りたい方は以下をご覧下さい。
制度融資や創業融資サービスはこちら

目黒区の制度融資と創業融資の資金調達

目黒区の制度融資は、以下のような制度です。
目黒区の創業支援の制度融資【 限度額 】
運転・設備資金共に原則、1,000万円(一部例外あり)
【 利率 】
1.8%以内(目黒区の補助1.5% 本人負担0.3%内)
【 返済期間 】
7年以内 (設備9年以内)
制度融資の対象目黒区に主たる事業所
(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置き、
創業する方(創業後1年未満を含む)が対象。
次の(1)から(3)の全要件を満たし、A 又は Bのいずれに該当すること
(1)融資に係る事業以外には事業を営んでいない
(2)住民税を滞納していないこと
(3)原則、事業に必要な許認可を受けている
A 融資申込時に事業を営んでおらず、
融資希望額と同額以上の自己資金・計画を有し、
個人は2か月以内・法人は3か月以内、
特定創業は6か月以内に創業できること
(設立登記後1年未満で事業開始してない法人含む)
B 融資申込時に事業を営んでいるが、
事業開始から1年未満であること
ただし、法人は会社設立登記日から1年未満なこと

目黒区の制度融資の申し込みと流れ
目黒区の融資あっせんの相談と申し込み
目黒区の融資あっせんの相談と申し込みの窓口は、
商工相談所(目黒区総合庁舎1階)で行ってます。
貸付限度額や貸付期間、金利などの面で
民間金融機関より有利な扱いとなっている反面、
商工相談所(目黒区総合庁舎1階)へ相談予約をし、
2回の来所が必要となります。目黒区の制度融資の流れ
<1> 目黒区総合庁舎1階に事前予約の上、
相談に行く必要があります。
ここで目黒区の商工相談所(目黒区総合庁舎1階)にて、融資の面談がされます。
1 相談カ-ドを作成(事業内容、融資希望額等)
2 面接(資格の確認、利用制度の決定等)
3 申込書の配布、必要書類の説明
また、事前予約が必要な点も確認しておきたいです。
<2>商工相談所(目黒区総合庁舎1階)へ申込・審査
必要な書類が揃ったら、事前予約をして、
商工相談所(目黒区総合庁舎1階)へ事前予約の上、
提出と審査に行く必要があります。
一部の特別貸付については、
中小企業診断士の企業診断があります。
役所において、いったん審査が入りますので、
面談・書類作成をしっかりしておくことに加え
目黒区の融資についての但し書きも、
しっかり頭に入れておきましょう。
また、資金計画を立て、制度融資の必要性が
認められるようにしておきましょう。
<3>金融機関への融資申し込み
目黒区役所側での審査が終わると、
金融機関へのあっせん書が出されます。
この書類を社長様で斡旋先金融機関に提出します。
ここで、金融機関の審査や、場合によっては
信用保証協会の審査が行われます。
目黒区制度融資の仕組みは、以下の通りです。
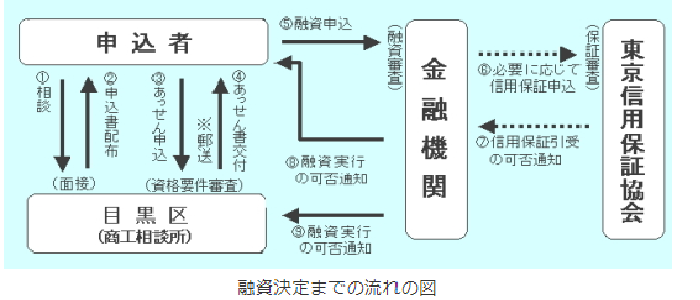
この公的融資を受けるためには、
事業計画書などの書類の審査に重点が置かれます。
つまり、公的融資を受けるためには、
融資関係書類の適正な作成がカギとなります。
それでは、目黒区の制度融資と日本政策金融公庫の 創業融資のどちらを優先し検討すべきでしょう? 弊所は、日本政策金融公庫の創業融資の優先を 起業時の資金調達では、お勧めしています。それは、次の理由に起因します。
日本政策金融公庫の創業融資メリット
日本政策金融公庫の創業融資の最大のメリット、 それは、断然に早く、手間が少ないことです。これまで目黒区で起業される方の資金調達を
数多く支援してきましたが、
申込から3週間から1か月程で資金調達できます。
【 実行の早さ最大の理由は、面談が一回なこと。 】日本政策金融公庫の面談は、
目黒区の制度融資に比べて回数が少ないため、
融資実行までの期間が断然に早いです。
また、日本政策金融公庫の創業融資で利用する
創業計画書と制度融資で利用する創業計画書は、
作成の上でのポイントは同じです。
したがって、創業融資で利用した計画書の軸を
目黒区の制度融資で利用することも可能です。
 いずれの融資も上限額が一般的に1,000万円です。
これ以上の金額が必要な場合には、
創業融資・目黒区制度融資を同時に申し込むことも、
一つの選択肢としてあがってきます。
いずれの融資も上限額が一般的に1,000万円です。
これ以上の金額が必要な場合には、
創業融資・目黒区制度融資を同時に申し込むことも、
一つの選択肢としてあがってきます。
税理士の創業融資や目黒区の制度融資支援
匠税理士事務所は、目黒区で起業される方に、
資金調達の必要性やチャネルの検討から、
創業計画書の作成など資金調達を支援します。
東京商工会議所や各機関経営・起業セミナー講師の 世界4大会計事務所出身の税理士が在籍しており、 創業計画書作成では高度な専門性を発揮します。また、日本政策金融公庫と提携してますので、
弊所のお客様は、特別に匠税理士事務所にて
融資の審査面談を受けることも可能です。
制度融資に対応のみずほ銀行や城南信用金庫など
各種金融機関とも提携しておりますので、
制度融資による資金調達もサポート致してます。
サービスの詳細は、下記よりご確認をお願いします。

所属税理士や融資以外のサービスは、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の税理士 匠税理士事務所 】

(融資情報は随時更新されます。最新情報は各行政機関で確認下さい。)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
日本政策金融公庫の創業融資につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
目黒区の創業融資・制度融資お役立ち情報
目黒区の制度融資を管轄するのは
目黒区商工相談所になります。
制度融資に関する各種窓口 【 → 目黒区商工相談所 】管轄区域:目黒区
〒153-8573
東京都目黒区上目黒2丁目19−15
制度融資以外の創業融資 【 → 日本政策金融公庫 五反田支店】管轄区域 目黒区
〒141-0031
東京都品川区西五反田8-4-13
五反⽥JPビルディング
上記が制度融資以外の創業計画書など
融資対応窓口となります。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#目黒区制度融資
#目黒区創業融資
法人化・法人成りと個人財産・事業資産の引継 (16/07/01)
起業の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化・法人成りと個人財産・事業資産の引継
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
個人事業主から法人成りして会社を設立した場合、
初年度会計期間が1年に満たないことはあります。
今回は、会計期間が1年に満たない場合の
会社設立初年度の減価償却の計算方法や、
個人事業主時代から利用していた事業用資産を
法人に引き継いだ場合について記載しました。
法人化後の会社設立初年度の減価償却資産

個人事業者から引き継いだ減価償却資産
減価償却費の計算に使用する償却率は、
1年使用していることを前提としているため、
設立初年度の会計期間が1年に満たない場合は、
事業供用した月数分に対応する償却率を計算する
という特別な対応が必要となります。
≪計算式≫
定額法又は定率法の償却率×(その年度の月数/12)
◆中古資産の耐用年数について
個人事業者から引き継いだ減価償却資産は、
いわゆる中古資産に該当します。
中古資産を取得までの経過年数が判明していれば、
耐用年数を再計算することができます。
※ただし、その中古資産を事業供用するために
支出した資本的支出(大改造)額が、取得価額50%を
超える場合以下は適用できないので注意です。

≪法定耐用年数の全部を経過したもの≫
法定耐用年数×20%が中古の耐用年数です。
≪法定耐用年数の一部を経過したもの≫
(法定耐用年数-経過年数)+ 経過年数×20% が中古資産の耐用年数となります。
(計算例)
法定年数30年で取得まで10年経過の減価償却資産
(30年―10年)+10年×20%=22年
◆法人成りをした会社設立初年度の期中に新たに取得した減価償却資産
会社設立初年度の期中に新たに取得した
減価償却資産につきましては、
事業供用月以後の月数分の償却費計算が必要です。
このように会計期間が1年に満たない場合の
会社設立初年度の減価償却や、
個人事業主時代から利用していた事業用資産を
法人に引き継いだ場合は、税務上多くの論点に
ご注意の上、申告しましょう。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援
匠税理士事務所は世田谷区や目黒区、品川区など
東京23区を中心に個人事業主から株式会社にする
法人化・法人成りの支援に力をいれております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)とは
法人化・法人成りのための手続や、会社にした後の経理代行、税務申告や給与計算などご要望の方は
以下よりサービス詳細をご覧下さい。
>法人化・法人成りのための手続や、会社にした後の経理代行、税務申告や給与計算
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
【税理士対応地域:世田谷や目黒、品川など東京23区全域】
執筆者・文責 税理士 水野智史
#法人化個人財産 #法人化事業資産の引継
会社設立後の社会保険・労働保険(労災・雇用保険)の加入手続き(義務や必要書類)≪p13≫ (16/06/16)
匠税理士事務所では品川区や目黒区、世田谷区など東京都23区を中心に会社設立や創業融資などの起業支援に力を入れている会計事務所です。
会社設立をご検討中の方が、税金と同じ位気にされる事項として社会保険の加入がございます。
会社設立後に人を雇用すると、社会保険や雇用保険への加入が必要になってきます。
そこで今回は、社会保険や雇用保険への加入義務や各保険の必要書類とその提出先についてまとめました。
会社設立後の社会保険・労働保険(労災・雇用保険)の加入
そもそも社会保険とは何なのか
社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「労災保険」「雇用保険」の5つの制度で構成される保障制度です。
実務では、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」を社会保険
「労災保険」「雇用保険」を労働保険といいます。
1・・病気やケガをしたときの医療保険である健康保険
2・・介護が必要な時に介護サービスを受けられる介護保険
3・・老後の年金制度である厚生年金保険
4・・労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷したときの労災保険
5・・労働者が失業した場合や育児・介護のために休業したときの雇用保険です。
社会保険の加入については、加入の義務がある「強制適用事業所」とそれ以外の事業所があります。
「強制適用事業所」に該当する場合は、被保険者となる従業員を必ず社会保険に加入させなければなりません。
(注)強制適用事業所→被保険者1人以上の法人事業所、または常時5人以上を雇用している個人事業所です。
社会保険 会社設立後に社会保険事務所へ提出する書類
社会保険の保険料はどのように計算されるのか?
社会保険の保険料は、最初は給与に各種手当、通勤費、昼食費などを含めた標準報酬月額に一定の保険料率をかけて計算します。
その後は、毎年4、5、6月の3カ月の報酬の平均をベースに決定されます。
なお、保険料は会社と従業員が2分の1ずつ負担します。
会社設立後の社会保険の加入手続き
健康保険と厚生年金保険は、社会保険事務所で手続きをします。
法人であれば従業員の人数にかかわらず強制適用です。
したがって、会社設立後は必ず社会保険への加入手続きが必要になります。
①健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・・・資格取得日から原則5日以内に持参もしくは郵送で提出します。
②健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
→事実発生から5日以内
正社員は必ず社会保険に加入します。
パートタイマーは一日の労働時間と1カ月の労働日数が、おおむね社員の3/4を超で加入義務があります。
加入する役員や従業員の氏名等を記載するこの届出書には基礎年金番号が必要で、年金手帳で確認します。
年金手帳を紛失している場合には紛失届を提出して再発行の手続きもしましょう。
③健康保険被扶養者(異動)届
→従業員に家族がいる場合は②とともに5日以内に提出する。
添付書類、提示する書類は各ケースや社会保険事務所によって多少異なります。
社会保険上の被扶養者として認められる家族や親族は、被保険者とその配偶者の第3親等まで、
もしくは事実婚など同一生計の事実がある人です。
被保険者の直系の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫は、
被保険者の収入によって生計維持していれば、同居しているかどうかは問われません。
75歳以上の高齢者は「後期高齢者医療制度」の被保険者となり、社会保険の扶養対象とはなりません。
これらの要件を満たし、かつ1年間の収入が130万円未満の者です。
④国民年金第3号被保険者資格取得届
厚生年金に加入している役員や従業員の配偶者で20歳以上60歳未満の者が被扶養者となる場合、
その配偶者は国民年金第3号被保険者とよばれ、
国民年金の保険料を納めなくてよいことになっています。
この期間は保険料を納付したものとして将来の年金受給額が計算されます。
国民年金第3号被保険者となるためには、上記③に加え、
国民年金第3号被保険者資格取得届を提出しなければなりません。
④保険料口座振替依頼書
思わぬ納付漏れを防いだり、
納付手続きの手間を省いたりするために口座振替が便利です。
ただし資金繰りに不安があるときは、この申出書を提出せず、
当面は納付書による現金納付をしてもかまいません。
会社設立後の社会保険の加入における上記①②には、登記事項証明書の原本や、
出勤簿またはタイムカード、賃金台帳、年金手帳、
役員報酬決定の臨時株主総会議事録のコピー(役員が加入する場合)等の添付書類が必要となります。
添付書類は管轄の年金事務所によって多少異なるので、提出する前に確認をとるとよいでしょう。
≪その他注意点≫
・社会保険料率はひんぱんに(毎年9月)に改定されます。
・40歳以上65歳未満の従業員には介護保険料が加算されます。
・社会保険に加入していないと、将来従業員から本来うけられたはずの社会保険の給付を会社が支払うよう損害賠償請求されるリスクがあります。
労働保険(労災保険や雇用保険)の加入手続き
労働保険とは、労災保険や雇用保険を総称したもので、 労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、 業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり成立手続が義務付けられています。
そのため、スタッフを雇う場合には、事業主は、労働保険(労災保険や雇用保険)の成立手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労災加入 会社設立後に労働基準監督署へ提出する書類
労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また、病気になった場合や不幸にもお亡くなりになった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行う機能を果たす保険です。
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
会社設立をして従業員を雇ったら、労災保険についての届出書を所轄の労働基準監督署へ提出します。
労災保険は、正社員のほか、パートタイマー、アルバイト、外国人労働者、 従業員と同様に業務に従事する一定の役員が対象となります。
労災保険は従業員の賃金と業種に応じて保険料を計算し、労災保険料は全額会社負担です。
①保険関係成立届
・・・保険関係成立日から原則10日以内
②労働保険概算保険料申告書
・・・保険関係成立日から原則50日以内に届出て保険料を納付
雇用保険 ハローワークに提出する書類
雇用保険は、労働者が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、また、自ら教育訓練を受けた場合に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。
雇用保険は労災保険とともに、原則的に加入が義務付けられています。
雇用保険の対象者は労災保険の対象と少し異なり、以下の人は対象となりません。
・ 週20時間未満労働の人
・ 4カ月以内の期間を予定して働く人
・ 昼間の学生(アルバイト)
・ 臨時内職的に雇用される人
保険料は、事業内容によって区分されており、会社と従業員が一定の比率で負担します。
① 雇用保険適用事業所設置届
・・・保険関係成立日から原則10以内
② 雇用保険被保険者資格取得届
・・・被保険者となった日の属する月の翌月10日まで
匠税理士事務所の社会保険・雇用保険加入手続サービス
匠税理士事務所では、社会保険・労働保険を専門とする専属の社会保険労務士が、労働保険(労災保険や雇用保険)に関する加入手続きの代行を承っております。
社会保険・雇用保険加入手続は、初回の加入のための手続きと、毎年の申告手続きが必要です。
お客様に出来る限り、本業に集中して頂けるように労働保険(労災保険や雇用保険)の加入手続きや、毎年の申告手続きの代行をを全て代行させて頂きます。
また給与計算手続きの代行も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
就業規則など各種規定の作成サービス
・労使間でのルールとなる会社の就業規則を作成し、
労使トラブルにならないようにしたい。
・会社の規模が大きくなってきたので、就業規則を作成しなければならない。
このような理由で就業規則作成をご検討の会社様は、就業規則作成も承っております。
◇トップページ
品川区の税理士は匠税理士事務所TOPへ
【税理士・社会保険労務士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域】
◇専門家の詳細
自由が丘の税理士 匠税理士事務所の提携先一覧
お客様満足を高めるため、随時提携先の充実をし、お客様のご要望に即した最適な専門家が担当します。
遺産分割協議と相続税の申告 (16/06/10)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>遺産分割協議と相続税の申告
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第6回 遺産分割協議と相続税の申告
第7回 相続税の税率と税額計算の仕組み
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
遺産分割とは、被相続人(亡くなった人)が持っていた財産を
各相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人)に分ける手続きをいいます。
遺産分割のやり方としては、
大きく指定分割、協議分割、審判分割の3種類があります。
遺産分割のやり方と相続税の対策

(1)指定分割
指定分割は、被相続人が遺言書でその分割内容等を指定し、それに従って分割する方法です。
(2)協議分割
協議分割とは、相続人全員で遺産の分割について協議をし、
相続人全員の合意により遺産分割する方法です。
この場合、相続人のうち1人でも、
遺産分割協議に参加しない者がいる場合には遺産分割協議は成立しません。
なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、
その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。
この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
(3)審判分割
(2)の方法で協議が成立しない場合には、
家庭裁判所の審判により分割します。
期限までに分割できなかったときは、
民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。
出来る限り、相続人同士が円満でいることで、
全体の税額が少なくなるような分割が可能になります。
ただ、実際にこれまで家を束ねていた方に相続が発生すると兄弟同士が不仲になって、
意見がまとまらなかったりすることもよくあります。
このようなことにならないように、
生前にしっかりとした話し合いを行って、
大まかな方向性を決めておくことが重要です。
遺産分割の具体的な方法について

(1)現物分割
現物分割とは、遺産そのものを分割する方法です。
(例)子Aは自宅建物と自宅敷地を相続、子Bは預貯金を相続といった方法です。
(2)代償分割
代償分割とは、遺産の分割に当たって
共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、
その現物を取得した人が、
他の共同相続人などに対して債務を負担する(自分の財産を渡す)方法です。
現物分割が難しい場合に行われる方法です。
(例)子Cは5000万円の自宅建物をを相続し、子Cから子Dに現金2500万円を渡す
→子C、子Dともに実質2500万円ずつ財産を取得するといった方法です。
(3)換価分割
遺産を売却した上で、その売却代金を分割する方法です。
世田谷区や目黒区、品川区を中心とする匠税理士事務所
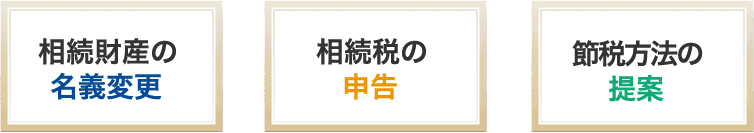
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区を中心に相続税や事業承継を支援しております。
相続税の申告だけではなく、提携先と連携することで、相続に伴う登記や生前のコンサルティングサービスも承っております。
世田谷区や目黒区、品川区の相続税・事業承継支援サービス
匠税理士事務所の事務所概要や所属スタッフ、提携している会計士や司法書士などにつきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成28年6月10日
相続税以外のサービスラインや、経営お役立ち情報、セミナー情報はこちら。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
法人化すると赤字の繰越期間が長くなる! (16/06/03)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化と赤字の繰越期
法人化についてのお役立ち情報
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
第10回 法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要か
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】全回 法人化バックナンバー
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
個人事業において1年間の事業活動で赤字・損失(純損失)を出した場合、
その純損失は翌年以後3年間繰り越すことができます。
一方、法人がその事業年度で、税務上の損失(欠損金)を計上した場合には、
翌年以後9年間繰り越すことができます。
法人の赤字の繰越期間は、平成27年度税制改正により
平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じる欠損金の繰越期間は10年に延長されます。
このように個人と法人では、赤字の繰越期間が大きく異なります。
個人事業と法人の欠損金(赤字)の繰越控除制度の活用

繰越欠損金制度とは、税務上の赤字(欠損金)が出た場合に、
翌期以降の所得金額の計算上損金の額に算入できる制度です。
法人は継続して事業を営んでいることを前提としているため、
利益が生じた事業年度についてだけ課税する原則を貫くと、税負担が過重となることを考慮して設けられているものです。
多額の赤字となった場合、
個人事業では繰り越せる期間が3年間という短い期間のため
過去の損失のすべてを控除できない可能性もありますが、
法人の場合は損失を控除しきれないリスクは、かなり少なくなると思われます。
このように長期的な事業展開が予測できる事業で、
当面赤字が続くがしばらくすると黒字転換することが見込まれる場合には、
法人化を行い、赤字を会社に計上するのもの戦略の一つかもしれません。
赤字・欠損金の繰越のためには何が必要か?
欠損金の繰越控除をするためには、『 青色申告の承認申請書 』を所定の期間までに提出して、青色申告の承認を受ける必要があります。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、
その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても繰越控除の規程が適用されます。
中小企業と大企業の繰越欠損金(赤字)の扱いの違い
法人の繰越欠損金の損金算入は、資本金1億円以下の一般的な中小法人の場合は、
繰越欠損金の範囲内であれば100%控除することができますが、
資本金1億円超の会社などの場合には控除限度額があります。
<税改正に伴う補足情報>
資本金1億円以下 ・・ 9年(※1)間の課税所得から控除できる
資本金1億円超・・・・・9年(※1)間の課税所得から控除できる課税所得の80%(※2)
(※1)平成29年4月1日以後に開始する事業年度については10年
(※2)平成27年4月1日~平成29年3月31日に開始する事業年度については65%
平成29年4月1日以後に開始する事業年度については50%
匠税理士事務所の法人化支援サービス
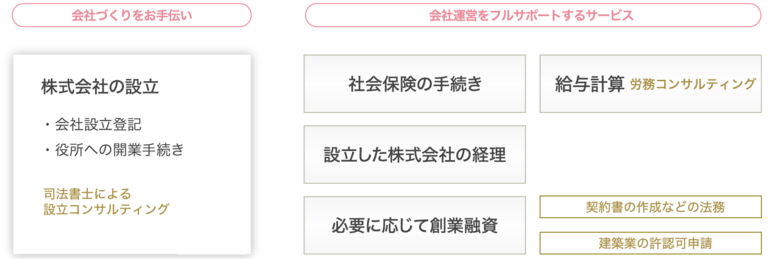
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に
法人化・法人なりをご検討中のお客さまに向けて、
法人化・法人なりのメリット・デメリットをご説明差し上げたり、
会社設立をする際のポイントなどのコンサルティングサービスをご提供しております。
税理士による法人化・法人なりのサービスの詳細
【1】世田谷区や目黒区、品川区など東京都での法人化支援 の詳細はこちら
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成28年6月3日
< 税理士による対応地域:世田谷や目黒、品川など東京都全域 >
世田谷区の税理士なら匠税理士事務所へ
相続税とは、基礎控除などの計算方法と申告 (16/05/20)
匠税理士事務所TOP >サービス個人>相続税申告・相続対策の税理士事務所>相続税の計算方法と申告
相続税や相続対策についてのお役立ち情報
第6回 遺産分割協議と相続税の申告
第7回 相続税の税率と税額計算の仕組み
第1~5回はこちら 相続税バックナンバー1-5
第11回~15回はこちら 相続税バックナンバー11-15
相続税支援サービスはこちら 世田谷区や目黒区,品川区での相続税申告・相続対策サービス
相続が身近な方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。
そこで今回は、相続が起きた場合に出てくる相続税とは何なのか、
どのように計算をして、
いつまでに申告・納付をしなければならないかについてまとめてみました。
相続税とは? 基礎控除などの計算方法

相続税とは財産を相続した場合にかかる税金です。
どのような場合に発生するのかというと、
亡くなった人(被相続人といいます)から、
1 相続や遺贈などにより取得した財産(遺産総額といいます)の合計額(下記※2) が、
2 基礎控除額(下記※1) を超える場合に、
原則として、相続税が生じてきます。
【 ここでは、説明のため各種控除軽減などは省略します。 】
具体的には、相続税は、相続や遺贈によって
取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により
取得した財産の価額の合計額
(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が
基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)
に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、
その期限は、被相続人(亡くなった人)の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
※1 相続税における基礎控除額とは
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
法定相続人には養子も含まれますが、
相続税の計算上、法定相続人の数に算入できる養子の数は制限されています。
また、相続人のうち、相続を放棄した人がいる場合であっても、
基礎控除額を計算する際は法定相続人の数に含めます。
課税価格の合計額が基礎控除額より少ない場合には相続税はかかりません。
※2 遺産総額の計算方法
① 遺産総額+相続時精算課税の適用を受ける財産の価額
↓
② ①-(債務+葬式費用+非課税財産)=遺産額
相続税の申告書の提出先と申告期限と納期

被相続人の死亡の時における住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出します。
財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありませんので注意が必要です。
申告期限までに申告しても、
税金を期限までに納めなかったときは、
利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、
比較的に大きな税額になることが一般的です。
相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、
物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、
申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
匠税理士事務所の相続税対策・相続税の申告サービス
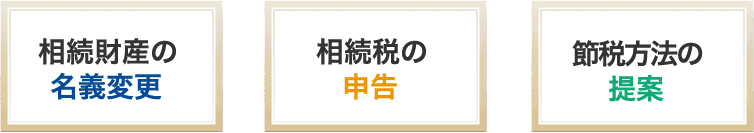
匠税理士事務所では、相続税対策や相続税に関する税務申告をサポートしております。
・相続が起きたので、税務申告を任せたい
・相続が起きる前に事前のシミュレーションを通じて相続税対策をしたい
このようなご要望にお応え致します。
相続税対策・相続申告サービスはこちら
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成28年5月20日
税理士の対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域
相続税対策や相続に関する税務申告以外のサービスラインや、
所属税理士の略歴などにつきましては、下記にてTOPへ移動の上、ご確認を頂けましたら幸いです。
世田谷 税理士 の匠税理士事務所 TOPページへ
法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買 (16/05/13)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化や法人成りの財産売買
法人化についてのお役立ち情報
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
第10回 法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要か
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】全回 法人化バックナンバー
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
個人で営む事業を株式会社に組織変更することを
【法人化】又は【法人成り】といいます。
これまで、法人化又は法人成りについては、
何度か記事にまとめてみましたが、
今回は、法人化又は法人成りに伴う譲渡所得につき
記載したいと思います。
これまでの記事まとめ
会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)
法人化又は法人成りに伴う譲渡(財産売買)とは?
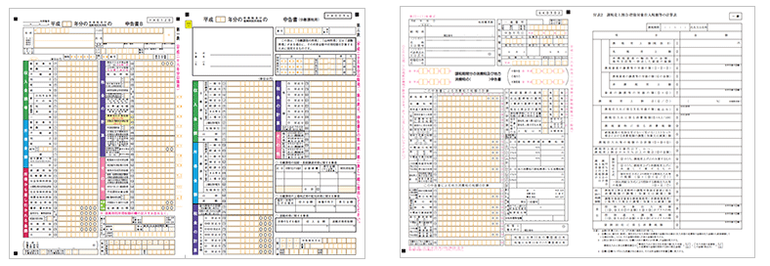
個人から会社にする法人化・法人成りを行うと、
多くの方で個人事業に使っていた財産の譲渡
個人から会社への引き継ぎが発生します。
ここで財産の売買や譲渡・引継ぎというと、
中々ピンとこないのですが、
個人事業主から全くの他人(新しく設立する会社)に
これまで使っていた財産を売買すると考えるとより
イメージが涌きやすいかもしれません。
それでは法人化や法人成りに伴う個人と法人での
財産売買取引はどのようなものなのでしょうか。
法人化や法人成りに伴う資産売却に関する所得税の考え方
個人事業でこれまで利用していた財産を、
その時価を上回る価格で法人に引き継いだ場合、
譲渡益について所得税を納めます。
例えると個人財産で90円しかない価値のものを
新しく設立する会社に100円で売ると、
100-90=10円の売却益(譲渡益)が生じます。
この譲渡益に対して税金がかかるということです。

個人の財産を会社に売る場合には、
原則、個人の税金を定めている所得税法で
税金を考えます。
所得税法では、資産を引き継ぐ形態、
またその資産の種類により、
所得区分が異なりますので注意しましょう。
1 現物出資、売却または贈与の場合
① 棚卸資産(原材料・仕掛品・製品・半製品・商品)
→ 事業所得
②土地・その上に存する権利・建物・付属設備・構築物
→ 土地建物等の譲渡所得(分離課税)
③ ②以外の有形固定資産
(車両・機械装置・工具器具備品等)・無形固定資産
→ 譲渡所得(総合課税)
④ その他の資産
(ゴルフ会員権・1個30万円超の貴金属・書画骨董品等)
→ 譲渡所得(総合課税)
(1個30万円以下貴金属・書画骨董品)→非課税
⑤ 30万円未満で資産計上しなかった減価償却資
→譲渡所得(総合課税)

2 賃貸の場合
個人所有の事業資産を法人に賃貸した場合は、
賃貸料収入に関し所得税申告義務が生じます。
① 不動産(土地、建物、付属設備及び構築物等)
船舶、航空機の貸付による賃貸料
→ 不動産所得
② ①以外(動産、工業所有権、採石権、鉱業権等)の貸付による賃貸料
→ 雑所得
法人化や法人成りに伴う個人と法人での財産売買に対する消費税の取扱

(1) 課税対象取引
対価を得て行われる法人への資産の引き継ぎや、債務を伴う資産の贈与や現物出資は、消費税の課税対象取引となり、消費税の申告が必要です。
(2) 非課税取引
課税対象取引のうち、以下の資産の引き継ぎに関しては非課税取引として消費税は発生しません。
① 土地、および土地の上に存する権利
土地と建物を一括して譲渡する場合、建物部分は課税対象取引となります。
② 有価証券(預金、貸付金、売掛金等の金銭債権を含む)
③ 支払手段(現金、小切手、約束手形)
④ 物品切手(商品券、図書券、プリペードカード等
⑤ 社会福祉事業又は更生保護事業等としての資産、身体障害者物品
⑥ 土地の貸付
⑦ 住宅の貸付
社宅等居住用建物の貸付は非課税取引ですが、事業用建物の貸付は課税対象取引となります。
東京都で匠税理士事務所の法人化・法人成り
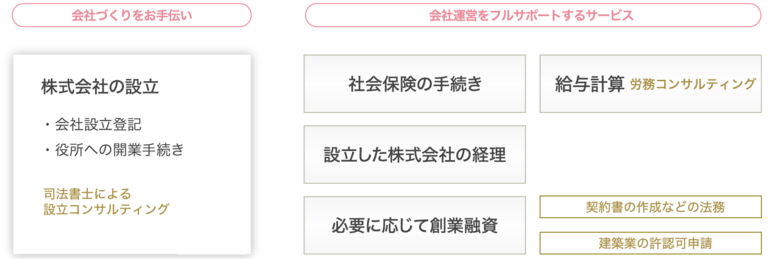
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区など
東京都23区を中心に法人化・法人成りを承ってます。
弊所では法人化・法人成りがお客様にとって、
有効か否かをご判断頂くために、
メリット・デメリットを丁寧にご説明し、
お客様に最善の法人化・法人成りを心掛けてます。所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
法人化と同時に資金調達も可能です。
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
株式会社や合同会社などを設立する
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
個人と法人での財産売買などの確定申告や
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事はお知らせの免責事項をご確認下さい。
税理士対応地域:世田谷や目黒・品川など東京都23区
執筆者・文責 税理士 水野智史
#法人化譲渡
#法人化財産売買
会社設立時の販売計画など事業計画の重要性K19 (16/04/27)
会社設立し実際に起業するとなると、やはり不安はつきものです。
この不安を拭い去るためには、計画を立てて、着実に実行していくことがとても有効です。
そこで今回は、会社設立し実際に起業した際の事業計画のうち、重要な販売計画・仕入計画・経費計画についてまとめてみました。
会社設立・起業後に最重要である販売計画とは
企業は世の中の役に立つことで、売上獲得します。
企業が生き残こるためには、売上がもっとも重要です。
この売上の見通しをたてたものが、≪販売計画≫となります。
このように販売計画はとても重要ですので、
会社設立が決まったら、まず販売計画を立てましょう。
事業を行う上での前提条件・5W1Hを綿密に検討することが必要です。
① WHO・・・・ 従業員の有無や人数の決定
② WHOM・・・顧客ターゲットを明確に

③ WHAT・・・ 取扱商品、サービスの決定
④ HOW・・・・ 販売方法の選択 店舗を持つのか、
インターネットを活用するのか等
⑤ WHERE・・事業を行う場所の決定
⑥ WHEN・・・営業時間の決定
前提条件が決まれば、売上予測も立てやすくなります。
その際、実際の顧客の購買行動は、
不確定であることを考慮するとともに、
事業主の自己商品への過大評価にも注意しましょう。
売上予測は業種により算定方法が異なります。
① 店舗売り割合の大きい販売業(スーパーなど)
・・・1㎡あたりの売上高×売場面積
② 飲食業、理・美容業などのサービス業
・・・客単価×席数×回転率
③ 労働集約型の業種
(人手に頼る業務の割合が大きい業種、自動車販売業・化粧品販売業・ビル清掃)
・・・従業員1人あたりの売上高×従業員数
④ 資本集約型の業種
(設備が直接売上に結び付く機械化の進んだ業種、部品加工業・印刷業・運送業等)
・・・設備の生産能力×設備数
※㎡あたりの売上高や従業員1人あたりの売上高などは中小企業庁や国民生活金融公庫が統計を公表していますので、ご参考にされるとよいかもしれません。
事業計画を立てる上での仕入計画とは何か
【利は元にあり】と、松下幸之助さんがおっしゃっているように、
仕入は事業の根幹をなすとても重要な要素です。
そのため販売計画が決まったら、次は仕入計画を策定しましょう。
<仕入先の選定>
・・・必要な時期に適正な数量を安価で安定的に供給してくれる仕入先を決めます。
扱う商品によっては、供給の安定性やセンスの良さに重点を置きましょう。
<仕入れの条件>
・・・現金払いか掛け払いか、手形の支払サイトなどの条件を決定します。
事業経営上では、出(経費)を制する経費計画が重要
売上から仕入を差し引いた粗利を幾ら確保できていたとしても、経費が多ければ事業は赤字となり、会社にお金がなくなってしまいます。
そのため事業を経営する上で、出を制することが重要になり、≪経費計画≫が必要になってきます。
一般的には、仕入れ計画の次は経費計画を立てる方が多いです。
経費は次の2種類に分けて予測します。
【 固定費 】
・・・売上高の変動に関係なく、毎月一定額発生する費用。家賃や人件費など。
【 変動費 】
・・・売上高にともない発生額が毎月異なる費用。 仕入れや外注費、販売諸経費など。
販売計画に経費計画を組み合わせて利益の見通しをします。
それにより、事業主の生活維持や借金の返済ができれば、とりあえずOKです。
匠税理士事務所の会社設立や起業支援サービス
会社設立をし、起業をする際には事業計画が重要になります。
その理由は経営をしていく上で重要であることと、創業融資などでも金融機関が自社を評価する際に活用されるというためです。
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に、会社設立の登記などの手続きから、
起業時の資金調達のための創業融資、起業後の経理や経営支援など起業に必要な全てをサポートしております。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
世田谷区や品川区、目黒区の会計事務所は匠税理士事務所 ...TOPページへ
世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区で、起業のため税理士をお探しの方は、お気軽にご相談下さい。
最終更新日:平成28年4月27日
法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要か (16/04/22)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化退職金の活用
法人化についてのお役立ち情報
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
第10回 法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要か
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】第11~15回 法人化バックナンバー11-15
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
法人化・法人成りを行うということは、個人事業を廃業し、新しく会社を設立するということになります。
つまり、廃業の届出を個人で提出する必要が出てくるとともに、会社では開設の届出が必要になります。
そこで今回は、法人化・法人成りによる開業廃業にはどんな届出が必要かについてまとめてみました。
【これまでの記事のまとめはこちら】
会社にする?個人のまま?法人化ポイント(メリット・デメリット)
個人事業廃業に必要な税務上の届出書
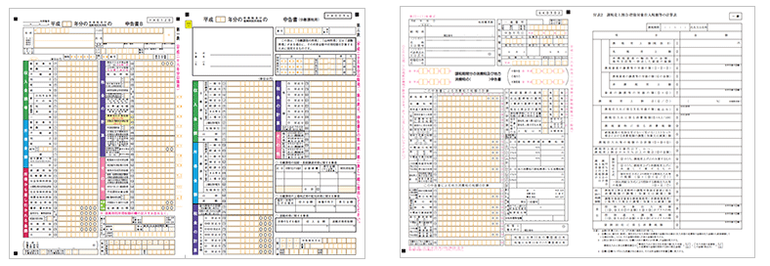
法人化や法人成りに伴う個人事業の廃業の際には、 以下の届出書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。
1 個人事業の廃業等届出書
個人の事業所得、不動産所得、山林所得が生じる事業を廃業した場合
廃業をした日から1か月以内に個人事業の廃業等届出書を提出しなければなりません。
書式はこちらより入手可能です。
→ 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|申告所得税関係|国税庁 へのリンク
2 所得税の青色申告の取りやめ届出書
青色申告の承認を受けていた個人事業者が、
青色申告書による申告をやめようとする場合にはやめようとする年の翌年3月15日まで
所得税の青色申告の取りやめ届出書を提出しましょう。
3 事業廃止届出書
消費税を支払っていた課税事業者が事業を廃業した場合には、
事業廃止後速やかに事業廃止届出書を提出するようにしましょう。
4 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書
所得税及び復興特別所得税の予定納税義務のある事業者は、
事業廃止に伴って、
予定納税額の減額を申請を検討することができます。
第1・2期分の減額申請については、
その年の7/1~7/15、第2期分のみの減額申請は、
その年の11/1~11/15までに申請してください。
5 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与を支払っていた個人事業者が
事業を廃業した場合には、
廃業をした日から1か月以内に
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を提出しましょう。
法人化・法人成りによる会社設立にはどんな税務上の届出書が必要
法人化・法人成りによる会社設立では、普通に株式会社を設立する場合と同様の税務上の届出書が必要となります。
こちらにつきましては、以前に記事にまとめました以下をご参照頂けましたら幸いです。
税務上の廃業設立届出以外に法人化や法人成りで検討すべき届出
税務上の届出以外に法人化や法人成りで検討すべき届出には、一般的にいかのようなものが考えられます。
・会社設立による社会保険への加入が義務付けられますので、
社会保険の加入手続きが必要になります。
・建築業などの許認可が必要な場合には、許認可申請も必要になります。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス
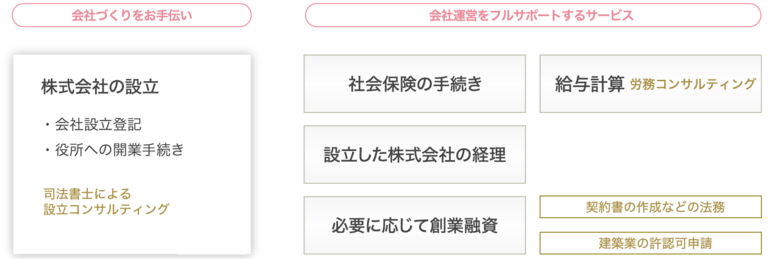
匠税理士事務所では、法人化・法人成りに伴う税務上の届出作成から、
各種専門家と連携して社会保険の加入手続き・建築業の許認可申請などをサポートしております。
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
また設立手続きのみにとどまらず、
設立後の経理や経営のサポート、資金調達が必要な場合には、
各種金融機関と連携した融資コンサルティングも行っております。
補足:法人化・法人成りでは上記の他にもいくつかの長所・短所がありますが、説明の都合上省略させて頂いておりますことをご了承下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
税理士の対応地域は、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区となります。
最終更新日:平成28年4月22日
東京都 税理士の匠税理士事務所HP TOPへ移動します。
株式会社や合同会社で会社を作る|会社設立の情報館 バックナンバー② (16/04/07)
株式会社などの会社設立は、ビジネスモデルや、必要資金・資金調達の方法、
本店所在地や役員構成などの重要事項を決めて、司法書士などの専門家に登記を依頼します。
会社設立の重要事項以外に、必要になってくることはどのようなことがあるのでしょうか。
目次
会社設立に伴って準備すべき事務的な作業
会社設立に伴う金融機関での法人口座の開設
会社設立登記が完了した後に行うことになります。
会社の売上は原則、会社の口座に入金されなければなりません。
会社設立後にすぐに売上が見込まれる方は、得意先に迷惑をおかけしないためにも、口座開設をしたい金融機関に問い合わせ、
・どのような書類が必要なのか、・口座開設がされるまでには、どれ位の期間が必要になるのかを確認しておくことをお勧めします。
【 関連記事:会社設立・法人設立後の銀行口座開設はどの銀行がいい? 】
株式会社など法人設立の案内状
会社設立をしたことを、これまでの仕事でお世話になった方々に、お知らせできるように事前に準備しておくと、
会社設立して事業にプラスになることも多くございます。
事前にレイアウト文章などを考えておき、いつでも発送できるようにしておくことをお勧めします。
会社の印鑑である法人代表印などを作る
会社の場合は大きく以下の3つの印鑑が必要になります。
① 代表者印
法務局に登録される、いわば会社の実印です。
会社設立の登記申請書の添付書類に押印するため、遅くとも会社設立の登記申請までには必ず用意が必要です。
代表取締役が変更した場合、基本的に代表者印を引き継ぎますから、個人名は入らないのが普通です。
② 銀行印
代表者印をそのまま銀行印として用いることも可能ですが、万が一代表者印を紛失してしまった場合には、
登記と口座の両方の面で悪用されるおそれがあるので、別々のものを製作したほうがよいでしょう。
③ 角印
請求書や見積書など日常業務の書類に押印する印鑑です。
補足
会社設立登記の添付書類として出資者や役員個人の印鑑証明書も必要となります。
会社設立においては発行後3ヶ月以内のもののみ有効です。早めに取得しておきましょう。
株式会社や合同会社で会社を作る|会社設立の情報館 バックナンバー②
その他の会社設立にあたっての情報は下記に、これまでのノウハウを活用した起業の情報をまとめております。お役に立てば幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
→ 株式会社を作るにはどうすればよいのか?会社設立までの流れ...
→ 会社設立後に一般的に必要となる法人の印鑑について記載します。...
→ 起業したいと思うのですが、何をすればいいですか...
→ 損益分配とは、合同会社の事業活動により獲得された利益がどのように各社員に分配...
→ 合同会社の業務執行社員についてまとめてみました。...
→ その使い勝手の良さのメリットが認識されその設立件数が顕著に増加しています。...
→ 資本金は幾らいくらにしたらいいでしょうか...
→ 事務所物件や会社物件を決める際のポイントについてまとめてみました...
→ 販売計画・仕入計画・経費計画についてまとめてみました...
→ 本店として登記する場所をどこにすべきかについて記載しました...
匠税理士事務所では、会社設立や創業融資などの起業支援サービスをご用意しております。
会社設立に伴う出資額や株主役員構成の打ち合わせ、その後の会社設立登記の代行や、
経理・社会保険の加入手続きの代行など起業に必要な全てをサポート致します。
起業支援に強い会計事務所をお探しの方は、匠税理士事務所にご相談下さい。
◇TOPページはこちら→
目黒 税理士 なら匠税理士事務所 TOPページへ
不動前や戸越銀座付近の税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (16/04/02)
弊所サイトへご訪問ありがとうございます。
弊所は大井町線・目黒線不動前や戸越銀座などで
【経営支援・起業支援】で実績ある事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に税理士・職員計10名が30~40代であり、
同世代の社長様の創業支援に実績がございます。
【人の質・専門家の質】でお客様に満足頂き、 【品川No1の事務所】を目指す税理士事務所です。 【 匠税理士事務所に頼んで良かった 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
所属税理士やサービスはこちらから
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

不動前・戸越銀座の税理士の会社設立・起業支援
弊所ではこれまで品川の不動前や戸越銀座で
会社設立や起業支援を多く担当しました。
特に品川での起業支援や経営支援では、
東京商工会議所品川支部様で経営セミナー講師を担当しその他公的機関創業支援セミナー講師も担当してます。
不動前や戸越銀座起業支援担当の税理士は、
こちらからご確認をお願いします。
【→匠税理士事務所の概要】
 不動前や戸越銀座の株式会社・合同会社の法人設立
不動前や戸越銀座の株式会社・合同会社の法人設立
また、法人設立など起業をされる方に対して
品川の金融機関と連携して、
不動前や戸越銀座の創業融資も対応しますので
法人設立から創業融資、助成金の申請代行、
各種許認可申請など起業に関するすべてのサービスを用意してます。
不動前や戸越銀座など品川エリアでの税理士の
会社設立サービスはこちらからご覧ください。

不動前・戸越銀座の創業融資による創業支援
日本政策金融公庫や制度融資など創業融資税理士による創業計画書の作成サポートや
創業融資における金融機関との面談対策など
創業時の資金調達のノウハウも充実しております。
不動前や戸越銀座など品川で会社設立される方の
創業融資による創業支援詳細はこちらから

不動前や戸越銀座などで創業する場合の
品川区による制度融資にも対応
【 → 品川区の制度融資サポート 】
不動前や戸越銀座の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は不動前や戸越銀座など品川全域対応)
不動前や戸越銀座の経理・確定申告・決算代行
弊所は、不動前・越銀座など品川エリアを中心に
企業様向け経営コンサルティングに力を入れてます。
これまで中小企業のコンサルティングを15年以上の
専門性と、会計データを基にした経営支援で
関与先の黒字率9割超を実現しております。 また会社が伸びた後も上場企業を数多く担当した
また会社が伸びた後も上場企業を数多く担当した
経験豊富な税理士が所属しておりますので、
税務面のコンサルティングも充実しております。
不動前や戸越銀座など品川エリアの企業様の経営や
税務会計のご相談はお気軽にご連絡下さい。
会計や経理、決算をアウトソーシング
経営支援はこちらからご覧ください。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
不動前や戸越銀座の方向けの確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
不動前・戸越銀座で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

会計事務所まで不動前・戸越銀座のアクセス
不動前や戸越銀座から会計事務所までの
乗り換え情報などにつきましては、
アクセスよりyahoo乗り換えなどで確認下さい。
戸越銀座・不動前で会社設立・法人化された声
個人事業を戸越銀座で5年ほど行ってきましたが、
売上が増えて、人を雇うことや得意先からの
要望もあってこちらの会計事務所さんに
法人化をすることになりました。
不動前のにいる同業の知り合いが
水野税理士さんにお願いしていたので
紹介してもらって法人化の相談をさせてもらい
お願いすることにしました。
法人設立以外にもその後の税務や会計など
いろんな手続きも対応してくれ助かりました。
品川戸越銀座・不動前付近で法人化の小売業A様
不動前や戸越銀座など品川エリア近くで
税理士事務所や会計事務所をお探しの方は、
弊所の税務会計正社員スタッフ
アルバイトスタッフに関する採用をご覧ください。
不動前・戸越銀座など品川区の会計事務所の採用求人はこちら
不動前・戸越銀座の税理士事務所お役立ち情報
不動前駅・戸越銀座駅には目黒線・大井町線があり、
税務署にもアクセス便利です。
不動前・戸越銀座で会社設立など起業した場合や、
会社経営をされている場合の税務申告書、
届出書提出先は以下のようになります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 税務申告書、届出書提出先 【 → 品川税務署 】管轄区域:品川地区 (不動前はこちら)
〒108-8622
港区高輪3丁目13番22号
【 → 荏原税務署 】管轄区域:荏原地区 (戸越銀座はこちら)
〒142-8540
品川区中延1丁目1番5号
事業税・住民税の申告書、届出書提出先 【 → 品川税事務所 】管轄区域: 品川区・大田区
〒140-8716
品川区広町2-1-36 ※品川区役所 本庁舎・議会棟の2階
上記が不動前や戸越銀座の税務申告関連や
各種届出書の提出先となります。
期限までに決算関連書類の提出を行いましょう。
最後までご覧頂きありがとうございました。
不動前(ふどうまえ)・戸越銀座(とごしぎんざ)で
会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#不動前税理士
#戸越銀座税理士
法人化や法人成りの手続きや確定申告 (16/04/01)
起業と黒字化の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化や法人成りの手続きや確定申告
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
個人事業主の方には、
確定申告後の年々の税額の増加や、得意先からの要請などで法人化や法人成りをお考えになる方も多いと思います。
そこで今回は、法人化や法人成りの手続きの中でも、
法人化・法人成りをした場合の個人事業の廃業日や、個人事業主としての最終年度の所得計算における確定申告のポイントをまとめてみました。
法人化・法人成りした場合の廃業日の考え方やポイント

法人化・法人成りした場合には、
廃業日つまりどこからどこまでが個人の計算でどこからどこからが新しく作る会社の計算になるのでしょうか
一般的には、次のような考え方で区分するとよいでしょう。
原則的な課税期間(利益の計算期間)の考え方
【個人事業者の所得税の課税期間】
1月1日から廃業した日まで
※ 個人事業の申告期限と納期は3月15日のままです。
【法人設立第1期】
設立した日からその事業年度終了の日まで
※ 法人の申告期限と納期は事業年度終了の日から原則2か月以内です。
それでは、個人事業を廃業した日についてはどのように考えるのでしょうか?
個人事業を廃業した日の考え方
・ 個人事業の棚卸資産をすべて設立した法人が引き継ぐ場合・・・【 廃業した日=設立した日 】
・ 個人事業の棚卸資産をすべて引き継がなかった場合・・・・・・・・・【 廃業した日≠設立した日 】
引き継がなかった棚卸資産を全て売却・廃棄するまで、個人事業も設立した法人と共に継続されていることになります。
廃業する日は、事務手続きも含めて事前にスケジュールをきちんと立てたうえで決定しましょう!
廃業する日の混乱は、
税金の計算ももちろんですが、取引先へご迷惑をおかけすることにもなりかねませんので、段取りよく行いましょう!
法人化・法人成りした場合の収入や経費など確定申告の注意点やポイント

税金の計算上も、同じように個人の収入や経費にする部分と
法人の収入や経費にする部分の決まりがあります。
個人事業の最終年度の総収入金額
廃業した日の属する年の総収入金額とは、
その年の1月1日から廃業した日までの収入金額をいいます。
現金を受け取っていなくても、
売り上げた(納品やサービス完了した)のが廃業した日の前であれば、
その売り上げを廃業した日の属する年の総収入金額に含めます。
収入の入れ忘れは、税務調査で指摘の多い事項です。
しっかり確認をして漏れのないようにしましょう!
個人事業の最終年度の必要経費
廃業した日の属する年の1月1日から廃業した日までに生じたものを、
原則として必要経費とします。(特例などもございますが、ここでは省略致します。)
特に廃業年度の経費については、
特別な処理が必要になりますので、注意しましょう。
① 貸倒引当金
売掛金の回収不能等、将来の損失に備えて見積もり計上するものですから、
個人事業を廃業するのであれば、必要経費に算入することはできません。
② 貸倒損失
個人事業を廃業した後に生じた貸倒損失については、
廃業しなければその年の必要経費にすることができたものであれば、
廃業した日の属する年又はその前年の必要経費にすることができます。
更正の請求も可能です。
その他、減価償却費や事業税などはとても特殊な計算が必要です。
税務調査では、誤って経費に入れてしまったなどの指摘が多いほか
経費に入れられるものを、入れ忘れてしまうようなミスも多くあるため
注意が必要です。
特に事業用資産の売却では、譲渡所得という特殊論点があります。
この計算誤りや、消費税の納付漏れも目立つ事項なので気を付けましょう。
匠税理士事務所の税理士による法人化や法人成りサービス
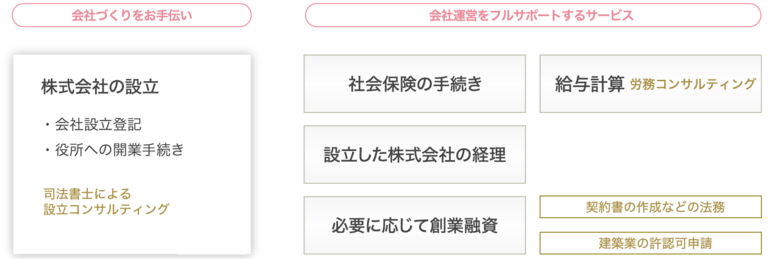
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区を中心に法人化や法人成りのお手伝いをしております。
・会社にした方がよいのか、個人のままでよいのか・・
・法人化のメリット・デメリットについて知りたい など
法人化や法人成りについてのご相談がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
法人化のサービス
個人事業から株式会社にするための法人化についてのサービスは下記よりご確認下さい。
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
【1】法人化・法人成り支援サービス の詳細はこちら
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
※経営のお役立ち情報
※起業のお役立ち情報
※世田谷の税理士なら匠税理士事務所まで
法人化や法人成りの目安やライン等の相談会 (16/03/18)
起業と黒字化の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化や法人成りの目安等のご相談承っております!
個人事業主の方で、確定申告が終わると、
【 そろそろ会社にした方がよいのだろうか・・・? 】
【 消費税率UPもあるし、消費税免税について一度話を聞いてみたい 】
このように法人化や法人成りでお悩みの方も多いのではないでしょうか。
匠税理士事務所では、 このような個人事業主の方に向けて、
【 法人化や法人成の目安やラインの相談会 】を行っております。
法人化・法人成りの無料相談会

法人化・法人成りの相談会では、
法人化・法人成りのいいところと悪いところの両方をお伝えしております。
それは、お客様の事業にとって法人化・法人成りは、とても大きな出来事であるため、
【 法人化や法人成りがベストな結果になるように心がけているからです。 】
また、税理士が出来る限り、お客様の事業の内容を把握した上で、
よいご提案が差し上げられるように実際に確定申告書・決算書を拝見し、
綿密な将来のビジョンをお伺いした上で、コンサルティングをさせて頂いております。
法人化の目安・ラインとは? どれ位の規模で会社にするのか?

【 法人化の目安は年商どれ位の規模でしょうか? 】
というご質問を頂くことも多くございますが、
これは税率だけで判断するとあまり望ましくない結果になることが多いので、
必ず将来の展望・法人化することにより取引ができる得意先の見込みなどをお伺いします。
一般的に消費税免税の観点から年商1,000万円を超えたあたりから、
法人化をご検討される方が多くいらっしゃるのは事実ですが、
人を多く要する業種なのかどうか等で、【 社会保険料UPのデメリット VS 節税額 】を考えると結果は変わります!
やはりお客様お一人お一人のビジョンに照らし合わせて、数字をまじえて検討するのが、
一番よい結果につながると考えます。
法人化のメリット・デメリットについては、担当税理士がわかりやすくまとめた人気お役立ち情報がございますので、
ご興味のある方はこちらよりご確認を頂けましたら幸いです。

匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービス
匠税理士事務所では、個人事業の廃業に伴う最終申告や各種届出、
法人化のための会社設立に伴う各種手続きなど法人化・法人成りを承っております。
会社設立後の社会保険の加入手続きや給与計算、会計経理の代行から資金調達などの創業融資にも対応しております。
匠税理士事務所の法人化・法人成り支援サービスにつきましては、下記より詳細をご確認頂けましたら幸いです。
法人化のサービス
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
【1】法人化・法人成り支援サービス の詳細はこちら
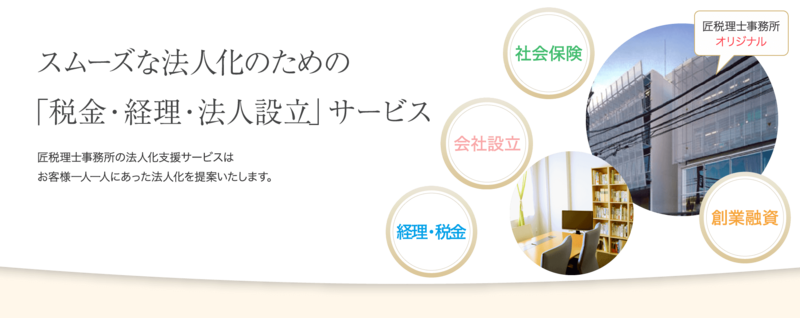

法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
※経営のお役立ち情報
※起業のお役立ち情報
※税理士 目黒 匠税理士事務所まで
目黒区中央町の税理士・会計事務所は匠税理士事務所へ (16/03/14)
匠税理士事務所は中央町近くの会計事務所です。
弊所は、【 高い専門性と高度な技術力 】を有する
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に、 司法書士・社労士・弁護士のチームで対応します。40代の税理士が中心のため、
お客様は30代や40代の方が多く、
【起業支援】や【事業承継】が得意な事務所です。
結果、会社設立や創業融資などの起業支援や、
黒字化のため利益戦略会議・キャッシュストック経営など
【起業】と【黒字戦略】にノウハウがございます。
匠税理士事務所に所属する専門家や
サービスは下記でご確認をお願いします。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】

中央町の会社設立や創業融資・起業支援
匠税理士事務所では、
中央町など目黒区でこれから会社設立をし
起業したい方に向け会社設立サポートを行ってます。
会社設立後に会計経理の代行から
利益を出すための経営支援に対応致します。
中央町を担当する税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

中央町など目黒区で株式会社の会社設立等
起業支援サービスはこちらでご確認下さい。
また、会社設立と同時に独立開業など起業資金を
用意するための創業融資にも対応しております。
中央町など目黒区に対応する信用金庫や、
日本政策金融公庫など金融機関と提携してます。
制度融資などにも対応しておりますので、
ご興味のある方はこちらで確認をお願いします。
【 → 創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】

中央町の会計経理決算・確定申告など創業支援
匠税理士事務所は、中央町など目黒区での
創業支援として会計経理決算・確定申告代行や、
補助金・助成金の申請などを行ってます。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
中央町など目黒区地元密着の匠税理士事務所
弊所は中央町など目黒区の地元のお客様に
ご支持頂ける会計事務所を目指しております。
そのため、起業支援以外にも、会計や経理の代行、
確定申告などにも対応しております。
10人程の規模であるため、
直接ご対応が困難な状況の際には、
出来る限り提携先をご案内するなどで
少しでもお役に立てるように心掛けてます。
助成金や補助金などの申請代行や、
事業承継に伴う譲渡、給与計算などの業務も
ご相談頂けます。
匠税理士事務所のサービスにつきましては、
こちらよりご確認下さい。
会社様向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
目黒区中央町で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

会計事務所対応エリア:中央町など目黒区全域
中央町の法人化・会社設立関連情報
中央町など目黒区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 目黒区など東京都の法人化・法人成り】
法人化・会社設立に伴う商業法人登記は
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 渋谷出張所 】管轄区域 目黒区
〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号
(渋谷地方合同庁舎)
上記が中央町で法人化・会社設立など
登記の際、対応する行政窓口となります。
税理士の対応地域は、中央町(ちゅうおうちょう)など
目黒区など東京都23区全域となります。
正社員やパートスタッフ採用求人はこちら
目黒区中央町の会社設立などの起業支援・創業支援や
法人化・法人成りなどは匠税理士事務所へご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#中央町税理士
#中央町法人化
アプリケーション開発など市場販売目的のソフトウエアのIT会計税務 (16/03/11)
スマートフォンの普及によって、アプリケーション開発を事業とされている会社も増えてきました。
このアプリケーションをアップルなどに公開し、
ダウンロードしたユーザーに対して料金を頂く事業を行った場合には、
税務上はどのように取り扱われるのでしょうか?
今回は、市場販売目的のソフトウエアの制作費についてまとめます。
◇市場販売目的のソフトウエアについて
・製品マスター(複写可能な完成品)を制作し、これを複写したものを販売するソフトウェア
・不特定多数のユーザー向けに開発したソフトウェアの販売やライセンス販売(ライセンスの使用を許諾し使用料を得る契約)するソフトウェア
初回の製品マスター開発までのコストはどのような取扱?
会計上は、ソフトウェア制作過程において、構想・企画、設計、プログラミングを経て、
最初に製品化された製品マスターの完成までが研究開発費になります。
最初の製品マスターは、製品として機能するものではありませんから、研究開発費は発生した時点の費用として処理します。
製品マスターの完成時点は、具体的には次の2点によって判断することになります。
①製品性を判断できる程度のプロトタイプが完成していること
②プロトタイプを制作しない場合は、製品として販売するための重要な機能が完成しており、
かつ、重要な不具合を解消していること
税務上も、研究開発費等に係る会計基準と合わせるのが妥当と考えます。
製品マスター開発後の制作費はどう扱う?

最初に製品化された製品マスターができた後、
試用・テスト、追加機能の開発、機能強化が行われ、
完成した製品マスターができるまでの製造費用は、
ソフトウェア(無形固定資産)として資産計上します。
【 ソフトウェア計上した場合の減価償却 】
上記無形固定資産に計上したソフトウェアは、税務上、定額法減価償却が求められ、
この減価償却費を通じて損金に計上していきます。
ソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて次のとおりです。
「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」→3年
◇減価償却について
減価償却は見込販売数量に基づく方法や、見込販売収益に基づく方法に合理的根拠があり、納税地の所轄税務署長の承認を受けることができた場合にはその方法により計算することもできます。
しかし、実務上はやはり定額法で、減価償却を進めるのが一般的です。
臨時減価償却について
会計上は見込販売数量や見込販売収益に基づき減価償却をしていて、
当初の見込みより著しい減少が見込まれる場合は、
そのソフトウェアの経済価値が著しく陳腐化したものと考えられるため、
その減少部分について一時の費用又は損失として処理する必要があります。
しかし税務上は臨時的な償却が無条件に認められていないため、損金算入することは難しいといえます。
匠税理士事務所のIT企業サポートサービス
匠税理士事務所では、IT分野でこれから起業をお考えの方にむけた会社設立や創業融資、
既にIT分野で会社を経営されている方に向けた経営サポートや、各種アウトソーシングサービスを提供しております。
◇IT事業を経営されているお客様向けサービスページ
◇IT経営のノウハウ 関連記事
IT関連事業の経営者様に向けた税務や経営お役立ち情報を更新してます。
最終更新日:平成28年3月11日
IT事業以外の方に向けたサービスラインや、所属税理士・税理士事務所の所在地などにつきましては、下記よりTOPページからご確認をお願いします。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
【匠税理士事務所 対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域】
会社設立のノウハウ集|会社設立の情報館 バックナンバー③ (16/03/05)
匠税理士事務所では、定款作成のサポートから会社設立の登記サポートまで会社設立に必要な手続を税務面・法務面から、税理士と司法書士がしっかりとサポートします。
また会社設立以外の資金調達や創業融資のご相談、会社設立後の経理や給与計算のアウトソーシングまで起業に必要な全てをご用意しております。
社長様の大切な会社に、より多くの利益と お金残すお手伝いをしたいをすることを使命と考え
黒字戦略のための利益戦略会議やキャッシュストック経営など独自のサービスでお客様の利益とお金を守ることに専門特化した会計事務所税です。
是非一度、私たちのサービスをご体験下さい。
【対応地域:目黒区や世田谷区、品川区など東京都全域】
会社設立のノウハウ集|会社設立の情報館 バックナンバー③
その他の会社設立にあたっての情報は下記に、これまでのノウハウを活用した起業の情報をまとめております。お役に立てば幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
→ 定款(会社のルール)に記載する事業目的・会社名を決める際のポイント...
→ 会社名(商号=会社の名前)を決めるときのポイント...
→ 元々、粗利の低い商品を作り、得意先や販路、市場での情報収集が完了した段階で...
→ 実際に脱サラ起業や開業をして成功するには、何か必要なのでしょうか?...
→ 社長さまに最も行って頂きたいことは営業です。...
→ 思わず来店したくなるような看板や店舗の外観はとても強力な宣伝効果があります。...
→ 会社を設立する際に、仲の良い人や前職の先輩などと一緒に起業されるという方も多いと思います。...
→ 会社設立・法人設立した場合に 「どの銀行に口座開設すればよいのか」 について...
→ ...
→ ...
起業支援に強い会計事務所をお探しの方は、匠税理士事務所にご相談下さい。
◇TOPページはこちら→
目黒 会計事務所 なら匠税理士事務所 TOPページへ
ソフトウェア開発の費用~原価計算~プロジェクト管理 (16/02/26)
IT業界における収益計上などのポイントについて、
以前まとめましたが、今回は費用の会計上のポイントをまとめてみました。
ソフトウェア開発などIT業における費用の分類と管理方法
ソフトウェア開発において重要となるのは、
その仕事にいくらかかって、売り上げがいくら、粗利はいくらなのかです。
人件費の高いIT業では、プロジェクト管理ができているか否かで、採用計画や粗利が大きく変化します。
不採算を作らないためにも、進捗と原価を管理して、
いくら投入しているのか把握しながら仕事をすすめることが大切です。
進捗を計算するために、原価計算を行います。
ソフトウェア開発に伴うプロジェクト管理
ソフトウェア開発は人工作業によるものですから、人件費の集計が一番のポイントになります。
人件費のほかには、サーバーやソフトウェアの利用料といった経費も対象です。
部門には、制作部門、開発部門、間接部門などがありますが、それぞれの企業に合わせて設定します。
会社の規模が10人くらいであれば、部門に振り分けない方法の方が管理がしやすいかもしれません。
継続できないような細かすぎる作業は、混乱を招きますので、初めはおおまかな部分でよいのかと思います。
直接労務費は作業報告書などに基づき各制作担当者がプロジェクトの制作に
直接従事した作業時間に見合う部分を配賦します。
直接要した経費は、配分の必要があれば配分しましょう。
間接費については、プロジェクトに直接関連付けできないので、
作業時間等の合理的な配賦基準を設定し配賦します。
継続できないような細かすぎる作業は、混乱を招きますので、初めはおおまかな部分でよいのかと思います。

◇ソフトウェアなどの開発に伴う原価差異はどう扱うべきか?
原価計算を効率的に行うために、事前に金額を見積もる予定原価や標準原価を使うことがあります。
これらの価格と実際にかかった費用との差額は原価差異として、原則的には売上原価として処理します。
見積もりが不適当で、原価差異が多額になってしまった場合に、例外として売上原価と棚卸資産に配分します。
システム開発などIT業で原価計算をするために
原価計算するためには、以下のことに留意して内部統制することが必要となります。
ソフトウェア開発は受注確定前から開始することもあることから、どの時点からプロジェクト設定するのかも検討しましょう。
この作業を事前にしっかりとしておかないと、どの案件に関する経費かが区分できなくなってしまう恐れが出てきます。
作業時間は、各人が報告後、上司の承認を得る必要があります。
あまり複雑にしすぎると、報告書が形骸かしてしまうので、
出来る限りシンプルに、内容がわかりやすい報告書であることが重要です。
実際に発生した費用の差異を分析することも大切です。
この分析を経営管理上役立てるとともに、
工事進行基準の進捗度の計算や赤字受注の処理に必要な情報となります。
ソフトウェア開発などは、
長期間に及ぶことが多く、かつ多くの人間がかかわるため、
しっかりと管理しておかないと、コストが多額にのぼってしまうこともよくあります。
しっかりと予算とコストの検証をおこなって、対応していくことが利益確保にはとても重要です。

IT業に強い 匠税理士事務所の概要紹介
匠税理士事務所では、IT業界の会計税務に詳しい税理士が所属しておりますので、
会計や税務を通じて、お客様に付加価値の高い専門サービスをご提供致します。
また各種公的機関で経営セミナー講師を担当するなど経営支援に定評がございますので、
IT業界で税理士をお探しの方は、下記より事務所概要をご確認頂けましたら幸いです。

IT業のお客様向けサービスの紹介
IT業界でこれから会社設立を検討されている方につきましては、会社設立の代行からその後の経理アウトソーシングや、起業の資金調達を支援しております。
目黒区という土地柄、IT事業を経営されているお客様とのお付き合いが多く、IT業の税務や経営コンサルティングの事例が豊富です。 IT事業は、日々変化を遂げている事業のため、ある程度の若さと経験値が大切かと考えております。IT分野で事業をされている方で税理士変更をご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。
◇IT事業を経営されているお客様向けサービスページ
◇IT経営のノウハウ 関連記事
IT関連事業の経営者様に向けた税務や経営お役立ち情報を更新してます。
最終更新日:平成28年2月26日
株式会社を作るには? 会社設立の流れ K11 (16/02/20)
K11 株式会社を作るにはどうすればよいのか。会社設立までの流れについてまとめております。
株式会社を作るのはなぜか?
一般的に、利益が多ければ多いほど税金は会社のほうが有利になっていきます。
所得税は超過累進税率で所得が多いほど税率が上がりますが、法人税は2種類の税率しかないからです。
<関連記事: 株式会社を作ったら、税金はいつ、いくら支払う?>また、会社からもらう給与については給与所得控除が使えますし、一定要件を満たす生命保険料が法人の経費になります。
税金面以外にも、会社の方が社会的信用度は高く、
取引先拡大のチャンスが大きくなる、銀行融資が受けやすい、
よりよい人材を集めやすいなどのメリットがあります。
個人事業でスタートし、事業が軌道に乗ってから会社設立する法人成りという方法もありますが、
名刺や看板、銀行口座を替えたり許認可を取ったり、法人化の手続費用などを考えると、
最初から会社にしておいた方がよかったということもございます。
<関連記事: 会社にする?個人のまま? 法人化ポイント(メリット・デメリット) >
株式会社の会社設立までの流れ
1 商号を決め、法務局で商号調査をする
会社の商号が決まると、<同じ名前の会社が同一の住所に存在しないか確認します。
会社の名前が商標登録されたものかどうかも調べたほうがよいでしょう。
商標権の侵害となると商標の使用差し止めや損害賠償の請求対象になるかもしれません。
2 個人の印鑑登録を済ませ会社の実印を作る
<関連記事: 会社設立にはどんな印鑑が必要? >
3 定款を作成する
定款とは会社の運営に関するルールのようなものです。
必ず記載しなければならない事項や、記載しなければその定めの効力を生じない事項などがあるので注意しましょう。
また、書き方にもルールがあるので、一般的な慣行に従うのがよいでしょう。
4 定款の認証
定款の認証は本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が取り扱います。
定款3通、発起人の印鑑証明各1通、定款認証時欠席する発起人の委任状、
4万円の収入印紙、公証人の定款認証手数料5万円、発起人の実印、以上を持参しましょう。
(司法書士などの専門家を利用するとこれらの費用が電子定款となるので削減できます)
5 資本金の払い込み
定款の認証が終わり次第資本金の払い込みをします。
振込みがされた口座の通帳コピーと会社代表者の証明書を添付して登記申請することになります。
金銭以外の出資を現物出資といいますが、それが500万円を超えると検査役による現物出資財産の調査が必要となります。
現物出資は調査に時間を要するので、多額の現物出資はお勧めできません。
6 登記申請をする
本店の所在地を管轄する法務局の登記申請窓口に申請書および添付書類一式を提出します。
郵送による申請も可能ですが慣れていない人は窓口で申請するほうが確実です。
建築業の許認可申請など必要な場合は許認可を取る
許認可制度とは、国などが衛生面や、建築業の許認可申請など技術面で一定の水準以上に保つため、事業者について資格制限を行っているものです。
国の介入が少ない順に「届出」「許可」「認可」「免許」があります。
要件を満たしていないと営業できない場合があるので、しっかりと調査、準備しましょう。
費用がかかりますが、専門家に相談し申請の代行をお願いすると安心です。
◇建設業許可申請サービス
世田谷区や目黒区、品川区など東京都での会社設立サービス
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区など東京都を中心にこれまで多くの会社設立を支援させて頂きました。
会社設立の代行から起業時の資金調達、起業後の経理代行から経営支援まで起業に必要な全てをご用意しております。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
税理士 目黒区世田谷区や品川区の匠税理士事務所TOPへ ...TOPページへ
会社設立の本店登記場所はどこがいい?本店所在地の決め方K20 (16/02/05)
これから起業をご検討される方で、会社設立を予定されている方もいらっしゃると思います。
今回は本店として登記する場所をどこにすべきかについて記載しました。
【関連記事:会社設立時の役員(取締役)・株主などパートナー選びは慎重に】
会社設立の際の本店登記はどこがいい?
会社設立をこれまで数多く担当させて頂きまして、
本店の登記場所として、
ご相談を頂くのは大きく以下のようなケースが多いです。
1 ご自宅又はご実家などの一軒家
2 現在賃貸借契約を結ばれて利用されているマンションなど
3 登記の名義だけを貸してもらえるバーチャルオフィス
それでは、上記それぞれの場所を本店として登記した場合には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
ご自宅又はご実家などの一軒家を会社設立時に本店登記した場合
ご自宅又はご実家などの一軒家を、会社設立時に本店として登記した場合の最大のメリットは、
引越しなどが考えられにくいので、本店を移すということがあまりなく、
余計な登記のための諸費用が発生しないことが挙げられます。
逆にデメリットとしましては、本店が自宅になるので、
会社設立後に、リース会社や保険会社税理士事務所・会計事務所や、社会保険労務士事務所等から大量のDMが送られてきてしまうことです。
賃貸借契約を結ばれているマンションなどを本店とする場合
賃貸借契約を結ばれているマンションなどを本店とする場合のメリットは、登記には部屋番号を載せないようにして、
表札に会社名を書かないとDMなどが配達されにくくなることもあるようです。
デメリットは、
引越しなどがある度に余計な登記のための諸費用が生じてしまうこと、
所轄官公庁へ異動届出書を提出する必要が出てしまうことが挙げられます。
登記の名義だけを貸してもらえるバーチャルオフィスを本店にする場合
登記の名義だけを貸してもらえるバーチャルオフィスを本店とする場合のメリットは、
上記の賃貸借契約を結ばれているマンションなどを本店とする場合と同様に、
登記には部屋番号を載せないようにして、表札に会社名を書かないとDMなどが配達されにくくなることや、
有名な場所にオフィスがあるように見えるので、事業規模が大きな会社に見せることもできます。
デメリットしては、
取引相手などが調査をすれば、バーチャルオフィスであることが分かるので、
逆に会社の実在性を疑われたり、金融機関によっては、バーチャルオフィスが本店の場合は、
法人の口座開設を断られるケースもあるようです。
匠税理士事務所の会社設立・起業支援サービス
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区など東京都中心に、多くの会社設立をお手伝いさせて頂きました。
会社設立の代行や経理のサポート、創業融資のコンサルティングといった起業支援サービスの充実はもとより、
・法人口座開設のためスピーディに対応してくれる金融機関を紹介して欲しい。
・会社設立と同時に許認可を取得したい
などのような起業家の様々なニーズにお応えできるような提携先の充実も心掛けております。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス
→ 世田谷区や目黒区、品川区での創業融資支援サービス

◇会社設立サービス
→ 世田谷区や品川区など東京都での会社設立の代行サービス
◇法人化・法人成りサービス
最終更新日:平成28年2月5日
IT税務では受託開発の売上計上、いつあげる? (16/01/29)
IT事業を営まれている方の多くで受託開発で
システム・ソフトウェアを制作されている方が多いです。
IT業界で受託開発の【 システム・ソフトウェア制作 】を
税務会計で一般的に【 受注制作ソフトウェア 】と呼び、
受注制作ソフトウェアでは、売上計上方法は
大きく分けて以下の2つになります。
受注制作ソフトウェア(受託開発)の売上計上
受注制作ソフトウェアに関する売上の計上方法には
【 完成基準 と 進行基準 】の二つがあります。進行基準とは、制作の進行途上において、
進捗部分に成果の確実性が認められるときには
工事進行基準を適用し、それが認められない場合、
完成基準により成果物の提供が完了した時に、
【 一度に、売上および売上原価 】を計上します。

では、工事進行基準とは、売上をどのように、
いつ計上するのでしょうか。
売上の工事進行基準とはどんなもの?
【 工事進行基準の適用要件 】
工事進行基準適用には、次の要件があります。
・解約の可能性が低い、または解約されても
進捗部分には対価の支払いがある。
・完成させる能力がある、また環境が整っている。
・対価が契約で定められている。
・毎決算期ごとに収益総額、原価総額及び
進捗の見直しがおこなわれる。
<計算方法>
収益総額に進捗度を乗じて計算します。
進捗度とは、受注したソフトウェアの原価総額の
見積りに対し決算日までに制作した部分に対する
原価が占める割合です。
ただし工事契約基準において合理的であれば
直接作業時間比率法などその他方法も認めらます。
【 法人税法上の取り扱いはどうなるの? 】
平成20年度の税制改正により、制作期間が
1年以上で請負額10億以上受注制作ソフトウェアは
工事進行基準が、【 強制適用 】されます。
また損失が見込まれるものについても
進行基準が認められます。
【 受託開発売上の実務上の取扱い 】
工期が概ね3ヶ月のもの、工事規模が小さいものは
実務上、工事完成基準が採用されています。
工事完成基準のポイントは、
ずばり、【 売上と費用が対応している 】こと。売上が翌期に上がるのに費用のみ当期ではなく、
この場合は在庫で費用を翌期に繰り越すことで、
売上と費用を対応させるかが重要となります。

ITで特殊な契約がある場合の売上計上時期
【 分割検収条件契約 】
ひとつのソフトウェア開発プロジェクトを
幾つかのフェーズに分けて契約を締結し、
フェーズ単位で検収を行う場合には、
以下要件を満たせばフェーズ単位で売上計上できます。
・フェーズが顧客に価値ある成果物提供である。
・対価が確実に請求されること、
また対価が適切な区分で分割されていること
【 複合契約 】
ソフトウェアの提供に加え、
以下のような異なる種類のサービスを一体で
販売する契約を複合契約といいますが、
この場合サービスごとに金額を把握できる場合は
それぞれ収益計上する必要があります。
例えば、
・保守サービスが含まれる契約
保守期間にわたり収益認識する。
・アップグレードサービスのある契約
ユーザーの利便性を高め、顧客を抱え込み、
新製品へ買い替え促進も図れる。
アップグレードできる期間で収益認識する。
・ハードウェアと合わせて販売される契約
ソフトウェアとハードウェアが区分できる場合、
それぞれ提供が完了した時点で収益認識するが、
有機一体で区分不可能な場合は、
ともに提供が完了した時点で収益認識する。

◇IT経営のノウハウ 関連記事
IT関連事業の経営者様に向けた税務や経営お役立ち情報を更新してます。
匠税理士事務所のIT業界向け経営支援
匠税理士事務所は、IT業界に詳しい税理士による
経営支援や起業支援を行っております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

既に会社を経営されている方に向けては、
税務コンサルティングサービスをご用意してます。
これからIT業界で会社を設立し起業したい方や、
会社設立され間もない方で創業融資検討中の方に
会社設立や創業融資支援をご用意しております。
詳細につきましては、こちらよりご確認下さい。
◇IT事業を経営されているお客様向けサービス
所属税理士や提携専門先はこちらから
◇匠税理士事務所について
担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
IT税務に強い税理士による株式会社など
会社設立サービスはこちらから
IT受託開発のための資金調達を支援する
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
ITで起業・創業された方の会計経理代行など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
ITで独立開業し、個人から会社にするための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
【対応地域】
世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域
IT業界での経営や起業につきましては、
お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#IT税務 #IT売上
システム開発やソフトウェア開発などのIT会計 (16/01/22)
今回は、システム開発やソフトウェア開発などのIT企業が、会計や税務で留意することをまとめてみました。
システム開発やソフトウェア開発などの企業には、
ハードウェアやソフトウェア、コンサルティング等のサービスをまとめて提供する会社もございます。
こうしたIT企業の会計税務の処理をするときには、
それぞれをどのように把握して処理するかに留意しなけばなりません。
システム開発やソフトウェア開発などIT業界の会計は複雑なので要注意
特に、システム開発やソフトウェアの会計処理が問題となりますが、
システム開発・ソフトウェア開発などの会計処理では大きく次の2種類に分類されます。
1、受注制作のソフトウェア
まず顧客からこのようなシステム・ソフトウェアを作りたいという受注を受けます。
その要望、予算、業種に合うようにシステム・ソフトウェアが制作され販売されます。
いわゆるオーダーメイドのシステム・ソフトウェアですから、

金額が高くなることも少なくありません。
また、販売管理や購買管理などのシステムは
大型化する傾向にあります。
契約形態は、基本的に請負契約です。
形式的に名称が違っても、
実質的な内容により判断します。
IT業界では受託開発とも言われますが、
つまるところ、開発完了後に、得意先である委託者に納品する形態の取引をいいます。
2、市場販売目的ソフトウェア
上記のように顧客からの個別受注ではなく、
システム開発・ソフトウェア開発企業がマーケティングすることにより
市場のニーズを把握して独自にソフトウェアを開発・販売します。
こちらは薄利多売が目的で、汎用性のある機能を多く有しています。
CD-ROM等のパッケージやオンラインによるダウンロード販売に加え、
サーバーやアプリケーションソフトを
顧客にレンタルする企業(ASP)によるサービスの提供など、
最近では商品の提供形態も広がっています。
上記の受注制作のソフトウェアと大きく異なるところは、
所有権を開発者がもち、ユーザーはこれをダウンロードなどを通じて利用するところにあります。
なぜ、受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアに分けるのか?
会計や税務では【 なぜ、受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアに分けるのか? 】
受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアでは、
受注制作のソフトウェアでは、得意先である開発委託者に納品することで売上が計上されますが、
市場販売目的ソフトウェアでは、ユーザーがダウンロードなどをすることで、売上が計上されます。
このように受注制作のソフトウェアと市場販売目的ソフトウェアでは、
売上が上がる時期が、比較的短期間であがる受注制作のソフトウェアと、
売上が比較的長期間であがる市場販売目的ソフトウェアでは、
開発のための経費もそれぞれに合わせる必要があるという趣旨から、取扱が大きく分かれます。
このようにシステム・ソフトウェア開発といっても、
その形態により売上や経費の計上時期は大きく異なるのです。
IT業界向けの税務・経営のノウハウ お役立ち情報
IT事業における税務についてのお役立ち情報を記載しております。
記事にかんするご質問はご遠慮ください。お知らせをご確認いただき判断は自己責任でお願いします。
◇IT経営のノウハウ 関連記事
IT関連事業の経営者様に向けた税務や経営お役立ち情報を更新してます。
IT業界に強い税理士が所属している匠税理士事務所のサービス紹介
匠税理士事務所では、これまで受注制作のソフトウェアや、ダウンロード形式の市場販売目的ソフトウェアをはじめ、大手メディア配信会社やPCメーカーなどの税務申告を担当していたIT業界での経験が豊富な税理士が所属しております。
ソフトウェア開発などIT業界に強い税理士・会計事務所をお探しの方は、お気軽にご相談下さい。
◇IT事業を経営されているお客様向けサービスページ
所属税理士や提携専門先は、こちらよりご確認下さい。
◇匠税理士事務所について
自由が丘の会計事務所なら匠税理士事務所...会社概要
世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所...TOPページへ
最終更新日:平成28年1月22日
建設業や建築業に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (16/01/15)
建設業・建築業に強い匠税理士事務所サイトへ
ご訪問ありがとうございます。
建設業許可で定められてる工事業種は全29業種、
2種類の「一式工事」と、27種類の「専門工事」が定められています。
この建設業や建築業の最大の特徴は、
【 利益が大きいが、リスクも大きい 】ことです。
【経営】利益を確保する売価・原価の設定が難しい
【資金】外注・材料など立替で、資金繰りが難しい
【労務】現場事故などで社員とトラブルが生じる
【受注】許可取得更新ができないと受注困難になる

私たち専門家は、各専門性を発揮することで、
【リスク】を取り除き、【利益】を最大化します。
お客様の利益の最大化は、誰が担当になり、【 経営のパートナー 】になるかが重要と考えます。
規模を追うと人の質が低下して、
大きなご迷惑をお掛けすることになりますので、
【 人材の質・サービスの質 】にこだわります。
弊所では、お客様窓口を経験10年以上で
税理士有資格者に限定しており、
世界4大事務所出身で経営セミナーの講師を務める税理士が担当します。また労災など労務専門社労士、建設業許認可専門の行政書士、法務専門の弁護士など業界トップレベルの
【各分野専門家が、一つになりお客様を支援する】 これが私たちの最大の強みです。また、上場企業を担当していた税理士が所属し、
規模も年商2,000万~7億と幅広く対応可能です。
利益をお金として残す! 建設業や建築業が専門の税理士が担当
建設業や建築業は、取引金額が大きいため、
利益が残る仕組みを作ることが重要です。
取引で扱う金額が大きいため、
人件費や家賃などの固定費が膨らんでしまい、
売上は大きいが、利益が残らない事が起きがちです。
また、建設業や建築業の経営課題で、資金繰りの問題が最も多く見受けられます。
これは、取引が大きいため
外注や材料仕入など大きな金額が先払いとなり
入金は納品後、納品までの工期が長く
入金まで時間がかかるなどの理由により
一時的に資金繰りが困難なためです。
特に会社が成長する時期は注意が必要となります。
【理想は利益率が高く、資金繰りが良い】ですが
これは急には出来ません。
儲かって、利益がお金として残るという会社を地道に築いていく以外道はありません。
匠税理士事務所では、以下のような解決策を毎月の会計数字を確認した上で提案します。
【 解決策 1 】入金・支払の時期サイクルを見直す
【 解決策 2 】売上・外注単価見直しで利益率向上
【 解決策 3 】工期が長い案件の一部前金の検討
【 解決策 4 】高利率又は入金が早い得意先に再編
【 解決策 5 】低利率で長期間の融資・借入の検討
ここでポイントなのは、【 お金がない=融資 】と安易に考えないことです。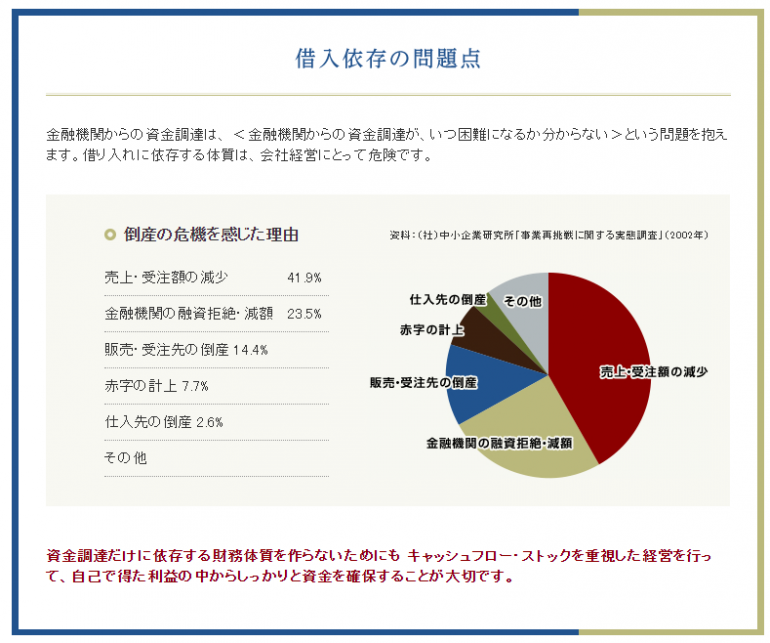
赤字の場合も同様で、
なぜ赤字なのか【 固定費 と 粗利 】どちらに問題があるか把握することが重要です。なぜ資金不足か、赤字かを考えないと、穴が開いた袋に水をいれるということになりかねません。
経営結果である数字も視野に入れ、資金不足の原因を考え、解決策を検討、実行する事が大切です。
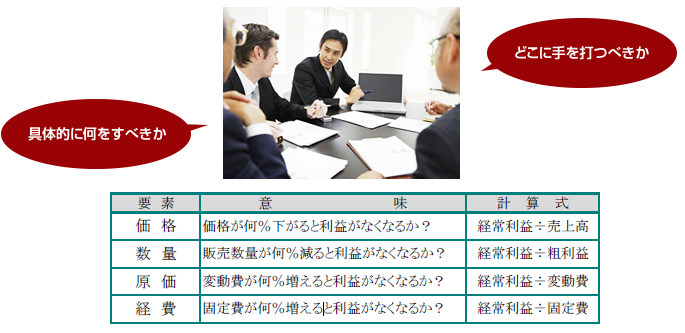
儲かる仕組み(高利益率の体制)を作り、
お金がたまるサイクルを作る取り組みの中で、
一時的な不足を融資対応するのがあるべき姿です。
建設業に詳しい税理士の法人様向けサービス
建設業や建築業向けの利益やお金の経営支援
弊所では、経営セミナー講師を務める
世界4大会計事務所で大手ゼネコン担当税理士が在籍し効果的な【経営支援】・【節税対策】を提案します。
匠税理士事務所の全サービスラインや料金などは
こちらからご確認をお願い致します。
【 → 起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】

担当する税理士や提携専門家はこちらから
【 → 匠税理士事務所の概要 】

法人様向けサービスはこちらをご確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
建設業の許認可申請サービス
建設業には、【 建築工事、土木一式工事、舗装工事、とび・土木工事、大工工事、左官工事、石工事、タイル、れんが、ブロック、屋根、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ、板金、ガラス、熱絶縁工事、さく井工事、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体工事 他全29種 】の分野で許可申請と更新が必要です。
仕事を行うに際して、
資金調達や物件・設備・人材の確保と同じく
大切な事項で許可認可の取得や更新があります。
建設業許認可専門の行政書士の申請代行
この建築業や建設業許可申請の取得は一見、
自分でもできそうですが実際やると複雑です。
匠税理士事務所では、建設業の許認可申請に特化した専門の行政書士と提携し
お客様の許可申請をサポート致します。
建築業や建設業許可申請の専門家である
行政書士に許可申請を任せるメリットは
【充実したノウハウで建築業など許認可がとれやすい】
【許可取得のスケジューリングを行ってもらえること】
【自分でやる手間が省け仕事に集中できること】
などがあります。
東京都・神奈川県の建設業の許可申請はこちら↓
建設業許可が取得可能か 無料相談実施中です
許可申請につきましては、専属の行政書士が
「建設業許可が取得可か」無料コンサルティングします。建設業許可を取得できない場合も、
なぜ取得できないのか、どれ位の期間
どうすれば取得できるかなど見直しを提案します。
弊所では、建設業に特化した行政書士と連携して、
東京都知事許可申請から国土交通大臣許可申請や
一般許可から特定許可まで対応してます。
お客様のご要望・今後の事業展開を伺った上で
最善の提案をすることも可能です。
税務顧問契約なしで、東京都や神奈川県での建設業許認可申請代行のみも可能です。
これまでの豊富な経験とノウハウを活かし、他では難しかった案件にもしっかりと対応しております。
東京都や神奈川県全域対応の建設業許可申請
建設業 新規申請(知事・一般)
・申請報酬 126,000円~
・法定費用 90,000円
新規申請(大臣・一般)
・申請報酬 147,000円~
・法定費用 150,000円
申請内容・案件で個別見積もりになりますので
お気軽にご相談ください。
上記法定費用は、建設業許可申請を行う際の国や都道府県等に納める税金等で手続で決まってます。
更新手続きや業種追加も対応し、更新に必要な会計書類も匠税理士事務所が行政書士と連携し東京都や神奈川県全域に対応致します。
◇一般建設業許可
◇特定建設業許可
◇入札に必須の経営事項審査(経審)
行政書士対応地域は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都・神奈川県全域となります。
建築業に多い労災事故など労務専門の社会保険労務士に給与計算
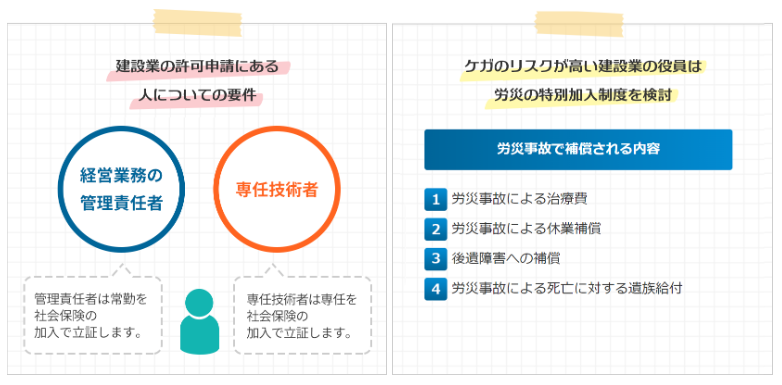
建設業や建築業は他のお仕事に比べると極めて
労働中の事故である労災が多いお仕事です。
そのため、対応を誤るとトラブルになりかねません。そこで労災への加入や雇用の際の契約書締結、
損害保険といった保険がとても重要になります。
また訴訟などに発展しそうな場合には、
弁護士も交えた対応が必要になってきます。
その他にも建設業の許可申請に
必要な社会保険の手続きもお任せください。
匠税理士事務所では、社会保険や労働保険は専門家である社会保険労務士や弁護士と提携することで、お客様のお手間を最小限にしながら
会社を守る体制をご用意致しております。
◇サービス

税務会計以外にも外国人労働者の方の永住権や
VISA対応などの行政書士とも提携しております。
お気軽にご相談ください。
会社設立の際の許可申請は、許可申請・税務届出・社会保険手続きが必要です。
税理士のみでこれを全て行うと速度は1/3、
チームですと3倍速で行えるため、
匠税理士事務所では、建築業許可申請分野の専門家である行政書士と税理士・社労士が、
お客様専属チームを編成し、
丁寧・迅速に対応致します。
詳細はこちらからご確認下さい。
建設業や建築業の会社設立・創業融資サービス
<税理士・会計事務所の対応地域>
世田谷区・目黒区・品川区など東京都23区・神奈川県
建設業・建築業向け資金調達サービスも用意してます。
◇建設業や建築業の資金繰り・融資による資金調達
◇事務所概要
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇お役立ち情報
建設業や建築業の経営ノウハウを掲載しております。
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区など中心とする自由が丘にある会計事務所で、
建築や建設業の税務会計に強い税理士事務所です。
解体工事や屋根、屋根、清掃、ガラス工事など
幅広い業種に対応可能。
会計事務所の対応エリア:世田谷区や目黒区・品川区・大田区など東京都全域と川崎市や横浜市など神奈川県
執筆者・文責:税理士 水野智史
#建設業税理士
ECサイト事業者などIT業の収益計上 (15/12/25)
起業セミナーの講師を担当させて頂いた際に、
セミナー受講者の方で、ECサイト事業で起業を検討中の方から
IT業の収益計上時期についてご質問を頂くことが多いので、
今回はECサイト事業者などの収益計上について記載しました。
モール型ECサイト事業者などIT業の収益計上
【ECサイトへの出店料について】
Eコマースサイト事業者は、出店料を受け取ることにより、
サイトに出店者の店舗・商品の情報を掲載し、
サイトの利便性及び集客力を向上させ、
出店者の販売機会拡大に努める義務を負っているといえます。
ですから、モール型Eコマースサイト事業者は、
出店者から出店料を受け取った時点では、
役務提供が完了しているとはいえず、
出店期間にわたり役務提供の進捗に応じて、
収益認識を行う処理が適切といえます。
具体的には、出店料を月額定額で毎月徴収している場合は、
その発生時に収益として計上しますが、
ある一定期間の出店料を前払いで徴収している場合は、
出店期間にわたり期間按分して収益計上するのが適切と考えます。
マージン料・オークション料などの収益計上について
Eコマースサイトの出店者・オークション参加者は、
サイト内で出店者・オークション参加者の商品の販売契約が成約した時に、
販売高に応じて一定の成果報酬手数料をEコマースサイト事業者へ支払う契約が結ばれます。
この場合、Eコマースサイト事業者は、店舗・商品の情報を掲載し、
インターネットユーザーからの申し込みがあった場合出店者サイトへ送客し、
受けた注文の情報を出店者・オークション参加者へ渡すという
役務提供をすでに行っているわけですから、
成約した時点で収益認識することが適切であるといえます。
匠税理士事務所のECサイト事業者などIT業向けサービス
匠税理士事務所では、
ECサイト事業者などIT業の方の起業や経営の支援をしております。
これから起業をお考えの方は、
こちらよりサービスの詳細をご確認を頂けましたら幸いです。
既に会社を経営されている方は、
こちらよりサービスの詳細をご確認を頂けましたら幸いです。
IT関連お役立ち情報ページ
会社設立の関連情報
IT業界の税務会計の特殊論点などの記事
最終更新日:平成27年12月25日
上記以外のお役立ち情報や料金などの詳細につきましては、
以下リンクにてTOPへ移動の上で、ご確認をお願いします。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
創業期の資金調達 日本政策金融公庫と制度融資の違い (15/12/05)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
起業・独立・開業など創業期の資金調達

起業資金はどのように調達すれば良いでしょうか。
一般的な起業資金の調達方法は
これらの方法が考えられます。
(補助金やベンチャーキャピタル出資は省略します。)
日本の大多数の中小企業では、
①自己資金と⑤事業の儲けから捻出できる資金以外の不足資金は、④金融機関から調達しているのが現状です。
②両親からの借り入れについては、
事業が万が一上手くいかなかったかったときの
最終手段として残しておき、
③友人や取引先などからの借り入れは、
将来のトラブルを充分に考慮する必要があります。

経営ではお金は生命線であり、どんなに優秀な商品や人材でもお金がなければ倒産します。
そのため経営者に融資の知識は、必須となります。
創業期もお付き合いできる銀行・金融機関を確認しましょう。
創業期にはどの銀行や金融機関が良いのか
A社の社長様は、起業後、不安的な資金繰りを安定させるため、
以前から給与振込口座として使っていた銀行に融資の話を聞きに行きました。

社長さま 「会社を作って融資を受けたいのですが...」
融資担当者 「融資をご希望ですね。お話を伺いますのでこちらの書類を書いてください。」
言われたとおりに書類を書くと
融資担当者 「不動産担保があれば話は別ですが、
起業時の融資は、こちらでは現在お取扱いがございません。」
と銀行に断れてしまいました。
起業したばかりの会社は実績がなく、信用力が低いため、しっかりとした融資の知識をもって、融資に臨む必要があります。
創業融資の基礎知識 その1
一部の銀行では、
「融資の取引実績」や「起業後3年以上経過」など融資の取引条件を持っています。
起業したばかりの会社は、この銀行の取引の条件にマッチしないことが多く、
大部分は取引実績のない創業期に融資を受けることは難しくなっています。
つまり創業期は、通常の法人の融資ではなく創業期専門の融資制度を利用します。
創業融資の基礎知識 その2
創業期の融資は一般的なものとして
![]() 日本政策金融公庫の融資
日本政策金融公庫の融資
![]() 東京都などの自治体が行っている制度融資があります。
東京都などの自治体が行っている制度融資があります。
この制度について理解を深めて、創業融資を利用してみましょう。
日本政策金融公庫って何?
日本政策金融公庫のメリット
![]() 100%政府出資の政府系金融機関です。
100%政府出資の政府系金融機関です。

政府系金融機関は、企業の育成目的から金融面での支援を行い、経済を活性化することを目的としているため、創業期の会社にとっては、有利な貸し出し条件を持っています。無担保無保証の融資制度など独自の商品があります。
※無担保...担保となる不動産などがなくても融資を受けられること
※無保証...保証人をたてなくても融資を受けられること
創業期の味方、制度融資って何?
制度融資は?

制度融資とは、自治体と信用保証協会、金融機関が協力して資金を貸し出す融資です。
①自治体などが金融機関に貸し出し用のお金を預け②信用保証協会が、実績がない・信用力がないなどの理由で
融資が通りにくい中小企業の代わりに保証人となることによって
③民間金融機関から融資を受けることができるものです。
制度融資のメリットとデメリット
制度融資には、利用にあたっては次のような利点と注意点があります。
《 利 点 》![]() 特定の制度には、利息や保証料の補助を行っているものもある。
特定の制度には、利息や保証料の補助を行っているものもある。![]() 普段自分が利用している金融機関を窓口とすることができる。
普段自分が利用している金融機関を窓口とすることができる。
《 問題点 》![]() 通常の金利以外に、保証人になってもらうための保証料の負担が発生します。
通常の金利以外に、保証人になってもらうための保証料の負担が発生します。![]() 制度融資の条件に一致する必要があります。
制度融資の条件に一致する必要があります。![]() 経営指導を受けなければならないなど手続きや手間がかかるケースがあります。
経営指導を受けなければならないなど手続きや手間がかかるケースがあります。
①目黒区へ来所(1回目)のうえ相談し
②来所し(2回目)申し込みを行います。(一部の借り入れでは中小企業診断士の企業診断が必要)。
③あっせん書に必要書類を添えて、取扱金融機関に融資の申し込み
④金融機関では、申込者の経営内容等を審査し、信用保証協会に信用保証を依頼
⑤金融機関(及び信用保証協会)の審査を経て、融資が実行
創業融資は日本政策金融公庫・制度融資?
日本政策金融公庫の融資を利用するのか、
制度融資を利用するのか
それぞれのメリットやデメリットを知って、最終的に判断すべきです。
起業や開業支援サービスのご紹介
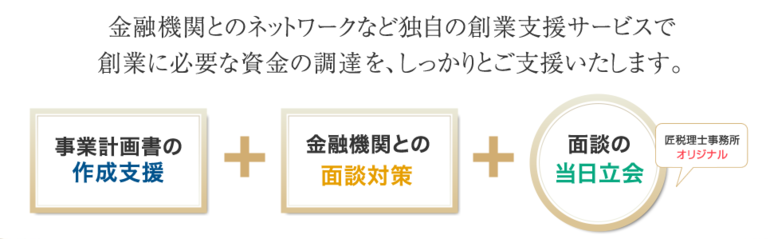
匠税理士事務所では、各制度融資に対応している地域密着の信用金庫、
日本政策金融公庫など政府系金融機関と連携した創業融資支援サービスをご用意しております。
創業融資につきましては、匠税理士事務所までご相談ください。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら

起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

その他の創業融資のお役立ち情報(バックナンバー)をご覧になりたい方は、こちらです。
創業融資の情報館 バックナンバー
記事については免責事項をご確認下さい。
創業・起業・会社設立などのスタートアップサービス
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
給与計算や社会保険サービス...毎月の給与計算や社会保険の新規加入・人事労務サービス。
税理士 東京都 TOPページ ...匠税理士事務所TOPページへ
世田谷区、目黒区、品川区などの東京都や川崎市・横浜市など神奈川県など全域で
創業融資などの資金調達を行う匠税理士事務所へお気軽にご相談下さい。
日吉・田園調布・新丸子の税理士事務所・会計事務所の採用求人 (15/11/15)
日吉や田園調布、新丸子などの方に向けた
弊所採用求人を御覧頂きありがとうございます。
税理士試験を受験される方で、大原・TACで
勉強されていらっしゃる方も多いと思います。
また、子育て中の方など私生活でお忙しい方も
いらっしゃると思います。
当会計事務所は、専門学校で税理士になるため
一生懸命に勉強されている方や、
子育て中の方も活躍できる事務所環境です。
代表税理士も社員も全員が子育て中ですので、
【繁忙期も残業ゼロ・給与水準も最高レベル】と働きやすさNo1会計事務所を目指してます。
試験や私生活と実務経験・仕事の両立をお考えで、
これから一緒に成長して下さる方を募集します。
日吉・田園調布・新丸子の税理士事務所の採用求人
・試験に受かりたいが、仕事もしたい。
・実務経験を積みたいが、勉強もしたい。
・子育てしながら、キャリアも継続したい。
このようなお悩み・ご要望をお持ちのの方も
多いのではないでしょうか。
かくいう弊所の税理士である宮崎も働きながら、
5科目合格をしましたので、働きながら資格を取る
難しさは十分に理解しております。
また、子育てしながら働く大変さも十分に
日々実感しております。
そこで、仕事をしながら私生活が充実できる環境を
作りたいという思いから、
大原受験生支援・子育て支援の求人採用を
(キャリアアップ制度)を作りました。
実際にこの制度で税理士講座の出席率は100%、
しっかりと勉強できると好評を頂いてます。
また、実務の経験・能力も付いてきます。
大原受験生向け求人採用情報の詳細は、
こちらよりご確認をお願いいたします。

日吉・田園調布・新丸子近く会計事務所の求人
日吉・田園調布・新丸子近く事務所で就職したく、
正社員・パートスタッフ求人情報を探している方で、
・残業が多く公私充実のため転職を考えている。
・社員を大事にする会計事務所に移りたい。
・同世代の勢いのある税理士事務所で働きたい。
このような方向け採用制度を用意してます。
正社員・パートスタッフ募集中の匠税理士事務所採用求人
匠税理士事務所は、どんな会計事務所なのか、
社員にはどのような人間がいるのか、
税理士はどんなキャリアなのか?
このようなご質問につきましては、
下記のをご確認頂けましたら幸いです。
日吉・田園調布・新丸子などお近くにお住まいの
皆様からのご応募をお待ちしております。
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

弊所は日吉・田園調布・新丸子から便利な
東横線エリアを拠点とする会計事務所で
会社設立・創業融資など起業に力を入れてます。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 田園調布や日吉近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所】

日吉や田園調布、新丸子近くの会計事務所の勤務を
検討中の方は弊所の求人採用もご検討下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#田園調布税理士事務所採用
#日吉税理士事務所採用
大井町・五反田など池上線の税理士・会計事務所の採用求人 (15/11/14)
大井町・五反田など池上線沿線の方に向けた
弊所採用求人を御覧頂きありがとうございます。
弊所は、2008年3月に設立の成長中の事務所で、
事務所を盛り上げて下さる人材を募集しており、
大井町・五反田など池上線など品川エリアで【働きやすさNO1】を目指してます。
そのため、金銭・時間的な充実が重要と考え
【 品川トップクラスの給与水準で、残業ゼロ 】の会計事務所となっています。
現在税理士試験を受験中の方には、
大原簿記専門学校やTACなどがある水道橋や、
横浜、新宿、池袋もアクセスが便利です。

大井町・五反田など池上線の税理士事務所の採用
匠税理士事務所は、人材が財産です。
そのため、 【 社員幸福の最大化 】を追及します。
1 公私が充実出来る勤務時間→【繁忙期残業ゼロ】
2 働きやすい職場環境 →【6年 退職者ゼロ】
3 出来る限りよい待遇 →【地域トップの待遇】
を中心に努め、入社して頂いた人材に出来る限り、
【長く楽しく】働いて頂けるように努めてます。
そのため、求人や採用に伴う選考では、
資格や学歴のみで物事を判断するのでなく、
その方のこれまでの経験・人間性・能力を
重視した人材選考・採用を行っております。

大井町・五反田など池上線の会計事務所の求人
正社員やパート・アルバイトスタッフなど
採用求人状況は、以下でご確認下さい。
匠税理士事務所では、残業がなく、
できる限り働きやすい会計事務所を目指します。
そのため、一人当たりの仕事量を少なくし、
負担を減らすため人材を前倒しで採用しています。
これはお客様お一人・お一人を大切にしたいため、
少し暇な位が丁寧にご対応できるので、
ちょうどいいという考えにもつながり、
【社員幸福度・お客様満足の最大化】が目標です。
今後も1年を通し、随時求人採用活動を行い、
いい人がいらっしゃれば、
是非一緒に働かせて頂きたいと考えております。
大井町・五反田など池上線の採用求人状況は、
随時更新しております。
皆様からのご応募を心よりお待ちしております。
大井町・五反田など池上線近く匠税理士事務所
・これからどんな人と一緒に働くことになるのか?
・駅からのアクセスは?
という方は、以下のリンクで
匠税理士事務所の事務所概要へ移動して下さい。
弊所の所属税理士やスタッフがご覧いただけます。
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】

大井町・五反田など池上線での弊所への位置は、
アクセスページでご確認ください。
匠税理士事務所サービスラインは
こちらからご確認下さい。
【 → 品川区の税理士は匠税理士事務所】

大井町・五反田など池上線の税理士・会計事務所の
採用求人に関する記事を最後までご覧頂き、
ありがとうございました。
皆様からのご応募お待ちしております。
大井町・五反田など池上線の会計事務所の勤務を
検討中の方は弊所の求人採用もご検討下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#大井町税理士事務所採用
#五反田税理士事務所採用
財務分析・経営分析セミナー (15/11/13)
大田区の東京商工会議所様で
財務分析・経営分析セミナーの講師を担当させて頂きました。
当日は約60人の方にご参加頂き、
最後までとても熱心に受講して頂きました。
決算書をほとんどの方がご持参頂き、
電卓を用いられて財務分析・経営分析を大変熱心に行われていたのが、
とても印象的でした。
ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。
また東京商工会議所 大田支部の皆さま、
当日までのご準備、色々とありがとうございました。
これからも少しでも多くの方に、
より参考となる経営セミナーをお届けできるように努めて参ります。
財務分析・経営分析セミナーの様子
当日のセミナーの様子です。

約2時間、 最後までご清聴頂ましてありがとうございました。
匠税理士事務所が担当する経営セミナー情報
匠税理士事務所では、
経営セミナーを通じて経営支援を行っております。
財務分析・経営分析セミナー以外にも、
様々なセミナーを担当しておりますので、
ご興味のある方は、下記よりご確認を頂けましたら幸いです。
財務分析・経営分析セミナー以外の経営サポートや、
各種サービスラインなどにつきましては、下記よりご確認を頂けましたら幸いです。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
ソフトウェア販売などIT業界の売上・収益ポイント (15/11/07)
今回は、IT業界で起業された方や会社を既に経営されている方で新しくソフトウェア販売を開始したいというご相談に対して税務会計上のポイントをまとめました。
お客様から依頼されて納品するようなソフトウェア販売について
お客様から依頼されて納品するようなソフトウェアについては、
基本的には、お客様に依頼されたソフトウェアを納品・引渡をした際に売上(収益)を計上することになります。
ここでいう引渡しがあった日は、出荷日、検収日、購入者の使用収益可能日、検針日等も考えられますが、
契約内容に応じて合理的であると認められる日のうち、法人が継続して収益を計上をしている日とされます。
市場販売目的ソフトウェアをダウンロードさせて販売する場合の収益計上時期について
上記で記載しましたお客様から依頼されて納品するようなソフトウェアのように
税務上、棚卸資産の販売による収益は、
その引渡しがあった日の属する事業年度の収益・益金の額に算入することとされています。
ソフトウェアの販売は、一般的にCD-ROM等をいったん販売代理店に提供し、
販売代理店からユーザーに出荷します。
会計処理上は、ユーザーがそのソフトウェアの利用可能となった時点で
収益を計上することになるので、それぞれのユーザーの利用可能日を把握する必要があります。
そこで、ユーザーにライセンスキーを取得してもらうのです。
ライセンスキーは、ソフトウェア企業が管理し、
直接ユーザーに送り、その利用可能日を把握するという方法がとられています。
インターネットでのダウンロード販売の売上はいつになる?
最近は、ソフトウェアの販売方法も多様化し、<インターネットからダウンロードするケースも多く見られるようになりました。
このような場合、料金を入金された際に、ライセンスキーを発行し、ユーザーが利用可能な状況になるので、
この段階で収益を計上する形式が一般的です。
【 まとめ 】
ソフトウェアの販売については、その販売形態に従い収益認識日を決定することが重要です。
いずれもインターネットビジネスはすごしスピードで変化しているため、
税務会計の取扱と実際のビジネス内容を照らし合わせて収益計上について検証することが重要です。
IT業界の方に向けた匠税理士事務所のサービス紹介
弊所では、毎年公的機関で、経営セミナーの講師を担当させて頂いたり独自の経営支援サービスを開発するなど経営支援に力を入れております。
・経営支援に強い税理士を探している。
・事業内容をしっかりと理解してくれて、経営相談しやすい会計事務所を探している。
このようなお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談下さい。
◇IT事業を経営されているお客様向けサービスページ
所属税理士や提携専門先は、こちらよりご確認下さい。
◇匠税理士事務所について
自由が丘の会計事務所なら匠税理士事務所...会社概要
世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所...TOPページへ
最終更新日:平成27年12月19日
世田谷・目黒・品川の法人向け節税対策 (15/10/30)
匠税理士事務所では、
世田谷区や目黒区、品川区など地元地域を中心に
法人の節税対策サービスをご提供しております。
法人向け節税対策の流れ
法人向けの節税対策にあたり、最も重要なのは
税金の対象となる当期の利益が幾ら程になるのかを
しっかりと予測することです。
匠税理士事務所では、
現時点での経営状況を的確に把握した上で、
社長様から今後の見通しを入念にヒアリングし、
独自開発のシステムを基に、
税金の対象となる当期の利益が幾ら程になるのかを予測します。
これによりどれくらいの節税対策が必要になるのか、
またその手段としてはどのようなものが適切なのかを社長様と一緒になって考え、
最適なものをお選び頂きます。
節税対策と会社資金のバランス
節税対策は大事な利益をお金として残すためには重要ですが、
過度な節税は会社資金のバランスを崩し、経営を不安定にしてしまいます。
そこで、
1 お金を出さずに税金が減る節税対策
2 お金を出さずに税金を先送りする節税対策
3 お金を出して、税金が減る節税対策
4 お金を出して、税金を先送りする節税対策
これらの中から、どれが会社にとって最善かを
会社資金のバランスを加味して考えます。
場合によっては、節税対策を実施せずに、
税金を普通に納付した方が会社の経営にとっては良いケースもありますので、
会社様にとっての最善策は何かを一緒になって検討します。
匠税理士事務所の節税対策を担当する税理士
弊所では、実務経験が15年以上の経験豊富な税理士が
お客様の会社の税金を丁寧にシミュレーションし、
最善のご提案を致します。
節税対策を担当する税理士の詳細につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
世田谷区や目黒区、品川区などの対応地域
匠税理士事務所の節税サービスは、
世田谷区や目黒区、品川区などを中心に対応しておりますが、
上記以外の東京23区や神奈川県の川崎市・横浜市にも対応可能です。
節税対策にご興味のある会社様は、
お気軽にご相談下さい。
最終更新日
平成27年10月30日
節税サービス以外の経営支援サービスなどにつきましては、
下記よりトップページへ移動の上でご確認をお願いします。
税理士 東京都の匠税理士事務所HPへ
若手の税理士や会計士をお探しの方へ (15/10/26)
現在会社を経営されている方 又は これから起業を考えている方で、
税理士や会計士 を探しているが、
『 色々と相談しやすい同世代の方がいいな~。 』
このように思われていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
匠税理士事務所は、
税理士や税務会計スタッフが全て30代・40代で構成されており、
同世代の経営者の方や起業家の方にご支持を頂いている会計事務所です。
税理士の実務経験年数は10年以上で、
起業支援の実績や上場企業の税務会計まで幅広いニーズに対応可能な
ノウハウを有しております。
→ 自由が丘の税理士 匠税理士事務所の概要
30代や40代の若手の経営者や起業家の方に支持されている税理士事務所
弊所の特徴と致しましては、
ほとんどのお客様が30代や40代の若手の経営者や
起業家であるという特徴がございます。
起業支援をご要望のお客様には、
会社設立から創業融資、起業後の経理や経営のサポートを
同世代の税務会計スタッフが担当させて頂き、
ご好評を頂いております。
起業支援の詳細につきましては、
こちらよりご確認下さい。
また会社を継がれた2代目の社長様から経営の相談が出来る
同世代の税理士がいいということで、ご依頼を頂くことも多くございます。
弊所では、経営支援の独自サービス開発や、
東京商工会議所などの各機関にて経営セミナーの講師を担当させて頂くなど
経営支援に力を入れております。
経営支援の詳細につきましては、こちらよりご確認下さい。
若手の税理士や会計士以外にも社会保険労務士・弁護士・司法書士も対応
会社の問題を税務会計以外でもサポートさせて頂くため、
給与計算や就業規則作成など人事問題は、
社会保険労務士をご紹介させて頂き、
契約書の作成や法務問題などの対応には、
弁護士をご紹介させて頂くことも可能です。
匠税理士事務所では、
30代・40代の同世代の経営者様・起業家の方のお力になりたいため、
提携専門家も全て30代・40代で構成されております。
会社の経営問題やそれ以外などのご相談がございましたら、
お気軽にご連絡下さい。
世田谷区や目黒区、品川区を中心に東京都23区全域対応
弊所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に
東京都23区全域に対応している会計事務所です。
出来る限りお客様のご要望に沿えるよう、
遠方の方のご要望も承っております。
お気軽にご相談下さい。
最終更新日:平成27年10月26日
各種サービス内容や、料金等につきましては、
下記よりTOPへ移動の上でご確認下さい。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
法人化・法人成りとは?|法人化の情報館 バックナンバー② (15/10/25)
毎年確定申告が近づくと、そろそろ会社にした方がいいのだろうか。
このようにお考えになる個人事業主の方も多いと思います。
この個人事業で経営していた事業を、株式会社や合同会社などの会社にすることを、
【 法人化 】 又は 【 法人成り 】 といいます。
一般的には、個人で事業をされて4年目頃に年商1,000万円を超えたのを
きっかけに消費税の節税メリットから法人化を検討される方も多いようです。
匠税理士事務所の法人化支援サービスは下記のリンク先よりご確認ください。
法人化支援サービス はこちら
法人化・法人成りは、得か損か
そこで法人化・法人成りは得か損かという話になるのですが、これは営まれている事業内容や規模によっても変わってきます。
ここでポイントなのは、メリットやデメリットを総合的に判断して、法人化や法人成りを考えることが重要です。
関連記事: 会社にする?個人のまま? 法人化のポイント(メリット・デメリット)
法人化するのは大変なのか?
結論から言うと、法人化すること自体は、そんなに大変ではありません。
主に金融機関へ法人口座の開設を行ったり、会社を設立したり、得意先への連絡や個人事業の廃止の申告などで時間や手間がかかりますが、官公庁などへの手続きは一般的に税理士などの専門家が担当致しますので、【 こんなに楽なんだったら、もっと早く法人化しておけばよかった 】 というお声をよく頂いたりもします。
一方で、会社から個人に戻す時には、一般的には事業が縮小したようなイメージを残すなどプラスの印象とは言い難いため、法人化の基本的な知識をつけてからの実行をお勧めします。
法人化(法人成り)の情報館 バックナンバー②
これまでのノウハウを活用した法人化(法人成りの)情報館をまとめております。お役に立てば幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
法人化無料相談会について
個人事業を株式会社にする法人化に関するお悩みなどは、中小企業や個人事業主を専門とする会計事務所匠税理士事務所にお任せください!
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。

法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
匠税理士事務所の法人化サービス
弊所では、お客様に法人化や法人成りをする上で事業内容を詳しくお伺いした上で、
どのようなメリットやデメリットがあるのかを打ち合わせで説明させて頂きます。
この打ち合わせを踏まえまして、法人化の手続や会社設立、その後の経理や経営支援をお手伝いしております。
詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
最終更新日:令和1年5月25日
退職金規定・旅費規程など社内規定作成について (15/10/21)
このようなお悩みはございませんか?
・自分で会社を経営しているが、
自分が会社を辞める際にはどれほどの退職金が会社から出せるのだろうか・・・
・仕事上出張が多いが、手当などは出せないのだろうか・・・
こんな疑問をお持ちの経営者の方もいらっしゃると思います。
退職金規定・旅費規程など社内規定作成はなぜ必要か?
退職金や出張手当などの各種手当は、
結論からいうと税法の要件に適合する社内規定がしっかりと整備されており、
これらに基づいていれば支給することも可能です。
逆に税法の要件に適合する退職金規定などの社内規定や旅費規程がなければ、
これらの支給は難しくなります。
退職金規定などの社内規定や旅費規程の作成
将来の税務調査に備えてしっかりとした会社にしたいという方は、
これらの社内規定の作成に力を入れられても良いかもしれません。
税務上ポイントになるのは、世の中の相場と比較して適正か否か。
これが退職金規定などの社内規定や旅費規程の作成では、重要になります。
匠税理士事務所では、多数の統計資料を用意しており、
これらに基づき各種規定の作成代行を承っておりますので、
ご興味のある方はお気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の事務所概要
退職金規定などの社内規定や旅費規程の作成は、
しっかりとした知識と経験がある税理士が担当致します。
匠税理士事務所の事務所概要につきましては、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
→ 自由が丘の税理士 匠税理士事務所の概要
最終更新日:平成27年10月21日
退職金規定などの社内規定や旅費規程の作成以外の
サービスラインは下記よりご確認をお願いします。
税理士 目黒の匠税理士事務所HPへ
社内研修や勉強会の講師や講演の依頼 (15/10/16)
匠税理士事務所では、
これまで数多くのセミナーや講演の講師を担当させて頂きました。
これらの経験やノウハウを活かした
社内研修や勉強会の講師や講演の依頼を承っております。
このような社内研修や勉強会の講師・講演を担当致しました。
・会社の経理部の方に向けた経理スキルアップ講座
・経営幹部候補の方に向けた試算表や決算書の読み方講座
・経営幹部の方に向けた利益とお金を残すための経営講座
・人事問題や労務問題への事前対策講座
上記以外の内容の社内研修や勉強会の講師も承っております。
また税務・会計以外にも人事や労務などの
社内研修や勉強会をご要望のお客様には、
提携の専門家をご紹介差し上げることも可能ですので、
お気軽にご相談下さい。
社内研修や勉強会を担当させて頂く講師について
社内研修や勉強会を担当させて頂く講師は、
弊所の税理士 水野となります。
これまでのセミナー実績等につきましては、
下記よりご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所の概要や提携専門家につきましては、
下記よりご確認をお願致します。
→ 自由が丘の税理士匠税理士事務所 概要
(一部、ホームページに記載していない提携専門家の方もございますので、
お客様のご要望に応じて最善の専門家をご紹介致します。)
(対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域及び神奈川県)
最終更新日:平成27年10月17日
社内研修や勉強会の講師依頼以外に
匠税理士事務所の所属税理士やスタッフ・サービスラインなどにつきましては、
下記よりご確認をお願いします。
税理士 東京都の匠税理士事務所HP TOPへ移動します。
本店移転登記や増資、役員変更などの登記手続 (15/10/02)
本店移転登記や増資手続、役員変更などの各種登記手続を
ご自分で行うのは中々大変です。
そこで匠税理士事務所では、
世田谷区や目黒区、品川区を中心に提携の司法書士事務所による
本店移転登記や増資、役員変更などの登記手続を承っております。
登記を担当する提携司法書士について
登記業務は司法書士が専門となります。
提携の司法書士は、
登記業務の経験年数が10年以上ございますので、
各種登記業務にも対応可能です。
本店移転登記や増資、役員変更などがございましたら、
お客様はご希望の内容と登記希望日をご教示頂けましたら、
司法書士がしっかりと対応させて頂きます。
各種登記料金について (本店移転登記や増資、役員変更など)
役員変更 20,000円~
本店移転登記 30,000円~
増資 50,000円~
その他登記事項変更 20,000円~
上記以外の各種登記にも対応しておりますので、
お気軽にご相談下さい。
会社設立の登記から経理・経営支援サービス
株式会社を設立したい方には、
登記手続きから経理や経営支援までをサポートする
会社設立の登記から経理・経営支援サービスをご用意しております。
サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
→ 品川区や世田谷区など東京での会社設立 サービス
匠税理士事務所について
自由が丘の匠税理士事務所では、
中小企業の経営支援から起業支援に力を入れております。
提携先の専門家や所属税理士・スタッフにつきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域・川崎市・横浜市
最終更新日:平成27年10月2日
登記サービス以外の各種情報やサービス内容は、
下記よりトップページにて移動の上でご確認をお願いします。
東京都 税理士の匠税理士事務所HPへ
東急東横線や大井町線の税理士・会計事務所 (15/09/19)
ご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所は、東急東横線や大井町線の沿線
自由が丘駅から徒歩2分の会計事務所です。
平成20年に設立し東急東横線や大井町線を中心に、
【起業支援・経営支援】に力を入れてきました。
会計事務所の特徴としては、
【人材の質・サービスの品質】にこだわることで お客様の黒字率が約9割であることです。匠税理士事務所の税理士・会計スタッフ・提携先
サービスラインは、こちらで確認をお願いします。
【→ 起業と黒字戦略の匠税理士事務所】

東急東横線・大井町線の会社設立や起業支援
東急東横線や大井町線などの地域を中心に
会社設立のご要望がある起業家の方には、
起業支援の経験豊富な40代税理士が会社設立から
資金調達など創業融資も全て支援します。
起業後の会計なども全てお任せ頂き、
起業支援で本業への専念を通じ、成功へ導きます。「会社設立は大変そう。」ですが、
会社名と本店の場所のみ決めて頂ければ その他事項は税理士と相談し決めて頂けます。東急東横線や大井町線で起業支援を
担当する税理士や専門家はこちらから
【 → 匠税理士事務所の概要 】

匠税理士事務所の起業に強い税理士による
会社設立の代行からその後の会計・起業支援は、
こちらよりご確認をお願いします。
東横線で創業融資による創業支援に強い会計事務所
株式会社や合同会社を作って起業する際に、
同時に進めておくと効果的なのが、
東急東横線や大井町線など東京都の制度融資や
日本政策金融公庫創業融資による創業支援です。
会社を設立して間もない場合、会社実績ではなく、
社長の実績(職歴や自己資金などの貯金)や
今後の見込・事業計画を基に融資可否が決まります。
しかし、普通に会社で一生懸命働かれてきた方、 自己資金をためてきた方にとっては、 創業融資は、決して難しいことではありません。弊所税理士は今後の見込みである事業計画を
社長様と一緒になって作成し、
提携先である日本政策金融公庫の五反田支店様や
金融機関と連携し創業支援します。
会社設立の創業融資による創業支援はこちらから
【 → 創業融資・資金調達支援サービス 】

東急東横線や大井町線の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
(税理士は東急東横線や大井町線の全域対応)
【助成金の申請代行も対応している税理士事務所】会社設立など起業時は人材を雇用するため、
各種助成金を獲得するチャンスでもあります。
助成金は条件さえ満たせば、
比較的獲得することが難しくありません。そのため、弊所では大井町線や東急東横線沿線に
対応する助成金に特化した社会保険労務士が、
お客様の会社の状況をヒアリングした上で、
助成金に関するコンサルティングを行います。
報酬は成果報酬となっておりますので、万が一の場合も安心しご利用いただけます。
その他にも助成金の申請サポートなど起業に関する
あらゆるサービスをご用意しております。
会計や経理、確定申告の代行や法人化も対応
匠税理士事務所は、会社に利益とお金が残るように
会計データを活用した経営支援に力を入れてます。
東急東横線や大井町線沿線の会社様で、
経営に強い税理士・会計事務所をお探しの方は、
こちらよりサービスをご覧頂けましたら幸いです。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
東横・大井町線で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

東急東横線や大井町線の会社設立・起業・法人化セミナー
匠税理士事務所は、東急東横線や大井町線沿線で
会社設立や創業融資などの起業・独立開業支援や
経営支援や法人化セミナーも開催しております。
当会計事務所の税理士が講師のセミナーに
ご興味のある方は、是非ご参加下さい。
品川の大井町で会社設立されたお客様
会社員を10年し以前から会社設立に興味があり、
自宅で会社設立して起業の兼ね合いから、
東横線や大井町線沿線の会計事務所を探してました。
大井町で行われた会社設立セミナーに参加したところ水野税理士の話が分かりやすく、
相談しやすそうだったのでこちらの会計事務所にお願いしました。
税務や会計のことは全然分からなかったのですが、
全てお任せできるので大変助かりました。
また創業時の融資でも大変お世話になりました。
今後も宜しくお願いします。
【品川大井町の会社設立 株式会社WY様】
東横線や大井町線の法人化・会社設立関連情報
東横線・大井町線の沿線などで個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 東京都での法人化・法人成り】
東横線・大井町線で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記も提携の司法書士が対応し、
届出書は、当会計事務所の税理士が代行致します。
東横線の税理士や会計事務所の採用求人
匠税理士事務所では、
事業拡大のため税務会計部門のパートスタッフ、
アルバイトスタッフ・正社員を募集してます。
東急東横線(とうきゅうとうよこせん)や
大井町線(おおいまちせん)沿線の税理士事務所や
会計事務所での勤務をご検討中の方は、
こちらより詳細をご確認頂けましたら幸いです。
【 → 大井町線の税理士・会計事務所の採用求人】
税理士の対応エリアは、東急東横線の沿線や
大井町など品川や世田谷、目黒です。
大井町駅からのアクセスも便利です。
会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成り以外に経理や会計、確定申告なども承っております。
お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#東横線税理士
#東横線会社設立
生命保険を活用した節税対策と節税提案 (15/09/17)
匠税理士事務所では、
世田谷区や目黒区、品川区など東京都を中心に
お客様の会社に利益とお金を残すためのお手伝いをしております。
利益を出すと当然ですが、税金は発生します。
この税金への対策として、
出来る限り会社にお金を残すために
生命保険を活用した節税対策が出てきます。
生命保険を活用した節税対策の注意点
生命保険を活用した節税対策の注意点は、
幾つかございますが、主なものとしては以下の注意点ではないでしょうか。
・短期解約になって、結果として損をするような財務的に無理な内容でないか。
・出口である保険金や解約返戻金が入金されるときの税金への対応が
しっかりと考えられているか ということです。
営業マンの提案でドンドン加入してしまって、
節税をしていたつもりが、解約時に思わぬ税額が生じてしまったり、
保険料で会社の資金バランスが崩れてしまうなどということが無いように注意が必要です。
法人で加入する生命保険には、主にどのような種類があるか
法人が加入する生命保険で主に検討されるのは、
全額が損金となる定期保険 又 は1/2のみ損金となる長期平準定期保険です。
それでは、定期保険とは税務上どのようなものなのでしょうか。
定期保険の取扱い
定期保険は、養老保険と異なり満期返戻金や配当金がないことから、
その支払保険料については、原則として、資産に計上することを要せず、
その支払時に支払保険料、福利厚生費又は給与として損金の額に算入することとされています。
(法人税基本通達9-3-5)。
それでは定期保険と違って、
1/2のみ経費になる長期平準定期保険とはどのようなものなのでしょうか。
長期平準定期保険の取り扱い
長期平準定期保険とは、
1 その保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超え、
2 当該保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超えるものをいいます。
税務上なぜ長期平準定期保険と区別する必要があるのか?
定期保険といっても、保険期間が非常に長期に設定されている場合には、
年を経るに従い事故発生率が高くなるため、本来は保険料は年を経るに従って高額になりますが、
実際の支払保険料は、その長期の保険期間にわたって平準化して算定されることから、
保険期間の前半において支払う保険料の中に相当多額の前払保険料が含まれることとなります。
このため、例えば、保険期間の前半に中途解約をしたような場合は、
支払保険料の相当部分が解約返戻金として契約者に支払われることになり、
支払保険料を支払時に損金算入することに課税上の問題が生じます。
そこで、このような問題を是正するため、
一定の要件を満たす長期平準定期保険の保険料については、
保険期間の60%に相当する期間に支払う保険料の2分の1相当額を
前払保険料等として資産計上することとされています。
匠税理士事務所の保険を活用した節税提案
弊所では決算3か月前に利益の状況を
独自のシミュレーションシステムを活用して予測し、
節税対策の効果と会社の財務バランスを踏まえて、
提携のファイナンシャルプランナーを交えて、
特定の保険会社の商品ではなく、
最善の保険をお客様ご自身でお選び頂くようにしております。
このようにすることで、
1. 保障という保険本来の機能
2. 節税対策の効果
3. 財務面でのバランス
4. 最終的にお金として残るにはどうすればよいか
の多角的な視点からより良いご提案ができればと考えております。
・苦労して獲得した利益をしっかりとお金として会社に残し、
安定した経営を実現したいという方や、
・退職金の準備も視野に入れた生命保険の活用を検討されている方
がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。
→ 自由が丘の税理士 匠税理士事務所 事務所概要
対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都全域・神奈川県
最終更新日:平成27年10月14日
上記の節税対策以外の経営支援サービスなどにつきましては
下記のトップページからご確認を頂けましたら幸いです。
税理士 東京都の匠税理士事務所HPへ
自由が丘や中目黒の給与計算・社会保険の加入手続き (15/08/28)
匠税理士事務所では、
給与計算・社会保険を専門とする専属の社会保険労務士が
自由が丘や中目黒を中心に給与計算の代行や、
社会保険の加入手続きを承っております。
給与計算は、所得税や住民税などの税金や
社会保険の知識を要するため複雑な一方で、
社員の方との信頼関係からミスや遅れがあってはいけないとても重要な作業です。
弊所では、この給与計算・社会保険の加入手続きにもしっかりと対応し、
お客様が本業に集中できる経営環境づくりをサポート致します。
自由が丘・中目黒の会社様向け給与計算・社会保険加入手続きサービス
自由が丘や中目黒で、
既に会社を経営されていらっしゃる方に向けて、
給与計算や社会保険の手続きを代行させて頂く、
給与計算・社会保険サービスをご用意しております。
これから会社を設立したいという方には、
給与制度のコンサルティング、社会保険の加入手続きも
行っております。
給与計算・社会保険サービスの詳細につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
( 税務会計の顧問契約なしで、 給与計算・社会保険サービスのみでもご利用頂けます。 )
→ 目黒区での給与計算サービス
就業規則や人事労務問題にもしっかりと対応
会社のルールである就業規則を作成し、
労使トラブルを事前に予防したり、
勤務体系・賃金体系のコンサルティングや、
人事労務問題の対応など給与計算のみではなく、
労務コンサルティングも行っております。
労務コンサルティングを担当する社会保険労務士、
弁護士などの専門家につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
→ 自由が丘の匠税理士事務所の提携先概要
今後もお客様満足度を高めるため、
地元である自由が丘や中目黒を中心に、
提携先やサービスをドンドン充実させていけるように努めております。
自由が丘で給与計算サービスをご利用中のお客様の声
会社のスタッフが増えてきたので、
職場で給与計算をするのが、スタッフの目が気になり
そろそろ限界かな~と思っていた時に、
給与計算のアウトソーシングを提案して頂き、
お願することにしました。
毎月15日頃になると憂鬱だったのですが、
その作業もなくなり、大変助かっています。
これからも宜しくお願いします。
自由が丘 飲食店Y様
中目黒で社会保険の加入手続きサービスをご利用中のお客様の声
社会保険の加入の必要性ついてしり、
自社ではどう手続きすればよいか困っていたため、相談してみました。
社会保険労務士の先生がとても丁寧に説明して下さり、
社会保険の制度や内容をよく理解できました。
社会保険の加入手続きも全て代行して下さったので、
大変助かりました。
これからも毎年の社会保険の手続きをお願いします。
中目黒 サービス業 T様
最終更新日:平成27年9月9日
給与計算や社会保険加入手続き以外のサービスについて
匠税理士事務所の経営お役立ち情報や、
給与計算や社会保険以外のサービスラインにつきましては、
下記よりご確認をお願いします。
東京都 税理士 の匠税理士事務所HPへ
最後までお読み頂きましてありがとうございました。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
最終更新日:平成27年9月10日
会社を作るには?会社設立で知っておきたいポイントK7 (15/08/21)
匠税理士事務所は、世田谷区や目黒区、品川区を中心に会社設立や法人設立などの起業支援に専門特化した会計事務所です。
会社ができるまでの基本知識を身につけて必要事項を決めていけば、きちんと会社はつくれます。
起業の成功は準備をしっかりできるかにかかっています。
まずはどのような会社を作りたいのか、その上で、資本金、役員と決めていきましょう。
つくりたい会社のイメージをつくる
会社を作る際には、まず、どのような組織形態で起業するかを決めなければなりません。
起業をされる際に、皆さま悩まれるのが、株式会社などの会社設立か、個人事業で進めるかという比較です。
会社設立?それとも個人事業者?
新たに起業する方はまず会社を設立するか、個人事業としてはじめるか悩むと思います。
会社設立のメリット、デメリットを理解して、自分のケースについてはどちらが有利になるのか専門家である税理士に相談しておくとよいでしょう。
株式会社で設立するメリット
①税金面
一般的に、利益が多ければ多いほど税金は会社のほうが有利になっていきます。
所得税は超過累進税率で所得が多いほど税率が上がりますが、法人税は2種類の税率しかないからです。
所得に応じて税率のあがる所得税と異なり、基本的に税率が一定のため、ある程度所得が見込めるようになると節税にもなります。
②経費面
個人事業主は自分に給与を支払えませんが、会社は役員報酬を支給でき、それを経費できることもメリットです。会社からもらう給与については給与所得控除が使えます。
一定要件を満たす生命保険料が法人の経費になります。生命保険や退職金などの節税策は個人事業主と比べると豊富といえます。
③信用面
税金面以外にも、会社の方が社会的信用度は高く、取引先拡大のチャンスが大きくなる、銀行融資が受けやすい、よりよい人材を集めやすいなどのメリットがあります。大手企業と取引したりする際には、株式会社である必要があったり、求人など人の雇用の際にも有利に働きます。
個人事業でスタートし、事業が軌道に乗ってから会社設立する法人成りという方法もありますが、名刺や看板を替えたり許認可を取るなど専門家や税理士に支払ったりする費用を考えると、売上がある程度見込まれる場合には、最初から会社にしておいた方がよさそうです。
<関連記事:個人事業主で起業か、会社設立(株式会社)か。 >
株式会社で設立するデメリット
設立時、手続きに費用がかかり、会計や税務申告など、複雑な手続きを要します。
株式会社で設立するデメリット主なデメリットの一例です。
- 設立の費用が必要となる
- 役員の任期がある
- 赤字でも法人住民税(均等割)を納税しなければならない
①設立の費用が必要となる
株式会社を設立するためには費用が必要です。
- ☆法務局への登記手続きに登記手数料や印紙税
- ☆専門家費用
定款用収入印紙代 40,000円(電子定款割引あり)
定款の認証費用 30,000円〜(資本金変動あり)
登録免許税 150,000円〜(資本金変動あり)
依頼しようとする専門家の個別見積もりとなります。
専門知識を持つ専門家に設立を代行してもらうと、報酬の支払いが必要です。
設立費用が安くい「合同会社」を選択する方もおられます。
②役員の任期がある
株式会社の役員には、任期があり任期が満了すると、株主総会の場で役員を選び直します。その後を登記しなければなりません。
役員登記は、登記に必要な書類や手数料が発生します。株式会社の任期は最長で10年にしておくとコストを抑えることができるでしょう。
③赤字でも法人住民税(均等割)を納税しなければならない
個人は、利益がない年は、所得税が発生しません。
法人の場合は、赤字でも、法人住民税の均等割を払う必要があります。
均等割は、法人の規模によって、例えば23区の場合は、70,000円~を支払うこととなっています。
会社設立のポイント 会社の種類
現在設立できるのは、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つです。
合資会社と合名会社は個人事業主が集まって会社として組織化するようなイメージです。
株式会社の設立に要する費用は最低約20万円、合同会社で約6万円です。
合同会社はランニングコストが安く、利益配分や経営の自由度が高いのですが、
まだまだ日本では周知度が低く、信用度やイメージなどで株式会社にはかないません。
ある程度お金に余裕があるならば、株式会社にしておくのがよいでしょう。
会社を設立するときの事業のコンセプトを決める
会社設立するにはまず自分の持っている武器は何かを考え、強みを活かせる分野を絞り込みます。
そして、それを行うのにふさわしい立地と、
早く売上をあげるための集客アプローチ(手段)も検討しておきましょう。
集客アプローチ例
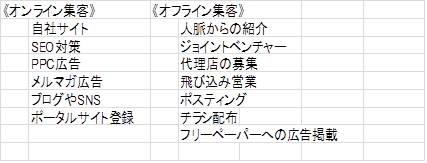
事業プランが決まったら、競合他社を分析し、差別化や付加価値をつけることも大事です。
会社設立・法人設立までの流れ
会社設立・法人設立では、最初に商号を決めることが出てきます。
今後ずっと付き合っていく会社名ですから、慎重に決めましょう。
商号は、法務局で商号調査をすることをお勧めします。同じ名前の会社が同一の住所に存在しないか確認するということです。
会社の名前が商標登録されたものかどうかも調べたほうがよいでしょう。商標権の侵害となると商標の使用差し止めや損害賠償の請求対象になる可能性があるためです。
社名が決まると書類を作成する上で必要な、個人の印鑑登録と会社の実印を作る必要が出てきます。
(関連記事:会社設立にはどんな印鑑が必要? )
会社のルールである定款を作成する
定款とは会社の運営に関するルールのようなものです。
必ず記載しなければならない事項や、記載しなければその定めの効力を生じない事項などがあるので注意しましょう。また、書き方にもルールがあるので、一般的な慣行に従うのがよいでしょう。

定款の認証
定款の認証は、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局所属の公証人が取り扱います。
定款3通、発起人の印鑑証明各1通、定款認証時欠席する発起人の委任状、4万円の収入印紙、公証人の定款認証手数料5万円、発起人の実印、以上を持参しましょう。
資本金の払い込みについて
定款の認証が終わり次第資本金の払い込みをします。>振込みがされた口座の通帳コピーと会社代表者の証明書を添付して登記申請することになります。
金銭以外の出資を現物出資といいますが、それが500万円を超えると検査役による現物出資財産の調査が必要となります。
検査役費用は100万円ほどかかる上、数ヶ月の時間を要するので、多額の現物出資はお勧めできません。
そして出資金が払い込まれたことを、取締役、監査役が調査し、登記申請をすることになります。
登記について
会社設立の登記申請をするためには、本店の所在地を管轄する法務局の登記申請窓口に申請書および添付書類一式を提出します。郵送による申請も可能ですが、慣れていない人は窓口で申請するほうが確実です。
登記申請のための書類に記載事項の不備があったり、不足があったりしたときなど窓口なら丁寧に教えて頂けるからです。申請には、登記申請書、別紙(OCR用紙)、印鑑届書のほか、以下の書類を添付しなければなりません。
・認証を受けた定款
・発起人の決定書・・・本店の所在場所および払い込む金融機関を記載する。
・就任承諾書・・・設立時取締役、設立時監査役全員の承諾書が必要。
・選定書・・・取締役会設置会社が代表取締役を選ぶ場合に必要。
・設立時代表取締役の就任承諾書・・・代表取締役を選ぶ場合に必要。
・印鑑証明書・・・設立時取締役全員(取締役会設置会社は代表取締役)の個人の印鑑証明書。
・出資の払い込みを証明する書面・・・証明書と銀行通帳のコピー。
・資本金の額の計上に関する証明書
(関連記事:会社設立と会社の資本金、1円の株式会社の問題点)
登記が終了したら、法務局で登記事項証明書を取得しましょう。税務署、市役所、社会保険事務所などに提出するため登記事項証明書が必要になります。銀行などでの口座開設、オフィスを賃貸するための契約の際に必要となることが多いので、何部か多めに履歴事項全部証明書を発行しておくことをお勧めします。
必要な場合許認可を取る
許認可制度とは国などが衛生面や技術面などを一定の水準以上に保つため、事業者について資格制限を行っているものです。
国の介入が少ない順に「届出」「許可」「認可」「免許」があります。
要件を満たしていないと営業できない場合があるので、しっかりと調査、準備しましょう。費用がかかりますが、専門家に相談し申請の代行をお願いすると安心です。
(関連記事:建築業など各種許認可申請)
会社設立後に税務署などへ提出する書類について
会社を設立したら、所定の書類を税務署に提出します。書類には必ず提出しなければならないものと、任意に提出すればよいものがあり、中には期限が定められているものもあるので注意しましょう。
(関連記事:法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き)
匠税理士事務所の起業・会社設立支援サービス
匠税理士事務所は、提携の司法書士と連携し会社設立など登記申請手続の代行手続や法人設立後の会計のアウトソーシングや給与計算・社会保険手続の代行、創業時の資金調達まで起業に必要な全てをサポートしております。
起業支援を担当する税理士は、40代で同世代の起業家の方から大変好評を頂いております。匠税理士の起業支援サービスにつきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
◇関連記事
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
◇その他の起業支援サービス
◇個人の起業サービス
青年会議所(JC)での経営セミナー・講演会 (15/07/31)
匠税理士事務所のセミナー実績のページをご覧いただきましてありがとうございます。
青年会議所さま(JC)の例会にて、講演会講師を担当させて頂きました。
当日は台風で大変な天候にもかかわらず、約30名の方にご参加頂きました。
約2時間の経営に関する講演会でしたが、最後までご清聴頂きました。
経営セミナー実績 青年会議所様
青年会議所さま(JC)において、中小企業の経営者さまを対象とした、経営セミナーの「基礎コース」を開催し、定員の30名の方にご参加いただきました。
本セミナーでは、情報提供の後、実際に課題の解決・改善ができるよう、実践も含めた内容となっており、2時間でしっかりと分かることを目標に設定し講演させていただきました。
現場において明日からでも具体的な活動として、実践できるようセミナーを作らせていただきました。
青年会議所(JC)でのセミナーの様子
青年会議所(JC)でのセミナーの様子につき、当日の写真を掲載させて頂きます。
経営の勉強に熱心な方が多く、懇親会にご招待して頂くなど、
とても親切で温かい方々に感動しました!
青年会議所(JC)の皆さま、講演会開催まで色々とありがとうございました。
心より感謝致します。
いただきました感想の一部をご紹介させていただきます!
講演内容はもちろんのこと、メンバーの出席率も非常に良く充実した例会にすることができました。本当にありがとうございます! などのご意見をいただきました
その他のセミナー実績や開催中のセミナー
匠税理士事務所の税理士が、講師を務めさせて頂く講演会やセミナーなどの予定につきましては、
下記の経営ビジネスセミナー・経営講座情報よりご確認いただけます。
経営や起業に関する講演会やセミナー講師をお探しの方へ
匠税理士事務所では、経営や起業に関する講演会やセミナーなどの講師を承っております。
これまでの講演会やセミナーの実績、講師料金の目安などにつきましては、
下記より起業セミナーや経営セミナーの講師依頼・講演依頼の詳細をご確認頂けましたら幸いです。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談下さい。
今後も皆様により良いセミナー・講演会をお届けできるように事務所全体で取り組んで参ります。
匠税理士事務所の所属スタッフやその他の情報につきましては、
下記よりTOPページへ移動の上、ご確認をお願いします。
自由が丘での法人設立や法人化は自由ヶ丘の匠税理士事務所 (15/07/24)
ご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所は、自由が丘駅徒歩2分の場所にある
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に【法人設立】・【法人化】の支援に力を入れる
2008年設立の税理士事務所です。
株式会社や合同会社などの法人設立には、
・1 起業で新たに法人を設立する場合
・2 個人事業から法人に変更する場合
がございます。

いずれの法人設立もお客様の人生において
とても大きな出来事ですので、
【 匠税理士事務所に任せて良かった。 】とって頂けるように
法人設立・法人化経験豊富な税理士と司法書士が
コンサルティングをさせて頂きます。
匠税理士事務所の所属税理士やサービスは、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

自由が丘で起業したい方に向けた法人設立
自由が丘で起業したい方に向けた法人設立では、
・将来的にどのような事業展開をされていきたいか
・株主構成や資本金は幾らにされるのか
・創業融資をご検討されるのか、
その場合は幾ら必要になるのか
など法人設立を成功させるための必要事項を、
しっかりとヒアリングさせて頂きます。
お客様のご要望に対して、
税務的にも法務的にも問題ないかを検証した上で、
ベストな法人設立をご提案致します。
担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。

法人設立サービスはこちらを確認下さい。
自由が丘で法人化や法人成りの代行サービス
個人事業をされていて法人化を検討される方は
節税や取引先から要望の場合が多いのですが、
法人化は、税務等の手続き的にも難しく、
更に得意先への法人化に伴うご案内や、
事業口座を変更する必要があるなど大変です。
【 法人化したが、メリットを感じない・・・ 】とならないためにも、税金だけではなく、
社会保険なども考えて検討を行う必要があります。
匠税理士事務所では、
これまで数多くの法人化・法人成りに伴う
コンサルティングを行ってきましたので、
お客様にベストな提案を行うことが可能です。
サービス詳細はこちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区での法人化・法人成り】
建設業や建築業の法人成り相談会
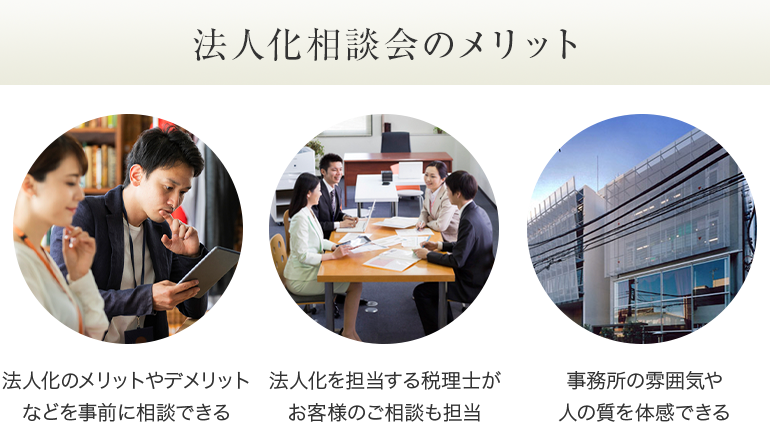

法人化・法人成り無料相談会のご予約は、
お手数ではございますが下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にて
ご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、
ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様と打ち合わせ後削除し、勧誘連絡等一切致しません。
無料相談では回答できない事もございます。
自由が丘での法人設立や法人化以外のサービスや、
弊所からのお役立ち情報などにつきましては、
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 →法人のお客様向けサービス一覧 】
【 →起業家のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 →個人事業のお客様サービス 】
執筆者・文責:税理士 水野智史
給与計算・社会保険の代行 (15/07/17)
匠税理士事務所では、
給与計算や社会保険の代行サービスを提供しております。
税務・会計の顧問は、付き合いがあるので変えられない。
今のままの税理士事務所を利用したままで、
給与計算や社会保険の手続き代行のみ任せたい。
このようなご要望をお持ちの方にも、
税務会計の顧問契約なしで、給与計算・社会保険の代行のみお引きけもしております。
お気軽にご相談下さい。
給与計算・社会保険の代行サービスを利用するメリット
社会保険については、これからマイナンバーが導入され、
かなり厳しくチェックされていくことになることが予想されます。
給与計算や社会保険の代行サービスでは、
専属の社会保険労務士が、お客様の手をわずらわせることなく、
社会保険や給与計算を全て代行しますので、
本業に安心して集中できることが可能になります。
人事や労務の問題もご相談下さい
給与計算や社会保険の代行サービスをご利用されている会社様で、
従業員と労使トラブルになってしまった場合にも、
社会保険労務士や弁護士がしっかりとフォローする体制を御用しております。
また、労使トラブルにならないように
事前に就業規則を作成し、労務問題になっても会社をしっかりと守るための
コンサルティングもご提供しております。
匠税理士事務所の給与計算・社会保険サービス
給与計算・社会保険の代行サービスについて
ご興味のある方につきましては、
下記より詳細をご確認頂けましたら幸いです。
ご不明な点などございましたら、
お気軽にご相談下さい。
最終更新日:平成27年7月17日
給与計算や社会保険以外の税務や会計のサービスライン、
経営支援サービスなどは、下記よりTOPページに移動の上、ご確認をお願いします。
世田谷 税理士の匠税理士事務所HPへ
保証人がいない、保証人なしでの融資は受けられる? (15/07/10)
サービス起業>創業融資支援サービス>保証人なしの融資
創業融資のサービスやお役立ち情報はこちら
創業融資サービス 世田谷・目黒・品川に対応
第8回 起業後、設立をしたばかりの会社は、
業績がなく、お金を借りる際の信用が低くなります。
そのため不動産の担保などがあれば別ですが、
一般的には金融機関での融資が難しくなります。例えば、個人で家を買うときには、購入する家や
土地を担保として住宅ローンを組みますね。
同じように事業のお金を借りる際にも
不動産などの担保や保証人を立てなければ
お金を借りることは、難しいのが現状です。

借り入れなどのお世話になる金融機関を決めて、
預金の実績や、借り入れの実績を重ねることで
一定の条件に達した際に保証人なしの借り入れを
検討してもらえるようになるのが一般的です。
保証人が立てられないと、融資は利用できないのでしょうか?
これから起業や独立開業したいが、
事情があって、保証人を立てられない場合には
どうしたら良いのかをまとめてみます。
ぜひ、参考にしてください。

~保証人を立てられないときには、こんな制度があります~
保証人を立てられないときには、
大きくわけ次の二つを検討してみます。
まず、【 第一に 】
日本政策金融公庫の保証人なしでも利用できる
融資の利用を検討してみることです。
【二第二に 】、
国や地方公共団体の制度融資を検討することです。
国は、ベンチャー支援するためにお金の面についていろいろな政策を打ち出しています。
一つは、普通の金融機関では融資が難しいような
起業間もない経営実績のない会社の融資を検討する
専門の金融機関をつくることです。
これが日本政策金融公庫です。
次に、信用保証協会が保証人になることで
一般の金融機関から融資を受けられるようにする【 自治体連携型の制度融資 】です。
いずれの場合にも、経営の実績がないため
事業計画書の内容や金融機関等との面談によって
融資ができるかどうかが判断されます。
そのため事業計画書の作成は重要なのです。
弊所では世界4大会計事務所出身の税理士が
資金調達をサポートしており、
成功率90%超の地域トップレベルの実績です。所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

その他の、創業融資のお役立ち情報(バックナンバー)をご覧になりたい方は、こちらです。
創業融資の情報館 バックナンバー
匠税理士事務所の創業融資支援サービス
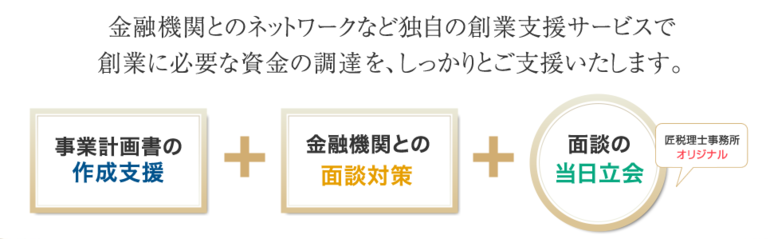
匠税理士事務所では、融資がはじめてで
何から手を付ければ良いか分からない
お客様のご要望にお応えします!
ぜひ、私たちのサービスをご体験ください!
創業融資支援サービス
創業融資お役立ち情報のバックナンバーは、創業融資の情報館 バックナンバー へ。
経営革新等支援機関の詳細はこちら 、中小企業の財務を支援する経営革新等支援機関 へ。
記事はお知らせの免責事項をご確認下さい。
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
これから会社を作って起業する方への
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
保証人なしでも融資で資金調達など可能な
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
経営支援や節税対策など税理士による
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で起業創業して会社に変更する
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

執筆者・文責 税理士 水野智史
#保証人なし借入 #借入保証人
目黒区での経営セミナー (15/06/26)
匠税理士事務所の税理士 水野が、
目黒区の東京商工会議所様にて経営セミナーの講師を担当致しました。
セミナー当日は、50名の定員までお申し込みを頂き、
皆様、2時間の経営セミナーを最後まで集中して聞いて下さり、
白熱した雰囲気でした。
ご参加頂いた経営者の皆様、
お忙しい中、最後までお付き合い頂きましてありがとうございました。
今後も受講者の皆さまの少しでもお役にたてるように、
より良いセミナーを届けていけるよう努めてまります。
また、開催まで色々とご協力頂きました東京商工会議所目黒支部の皆様、
ご協力ありがとうございました。
目黒区での経営セミナーの雰囲気

目黒区での経営セミナーの開催予定
匠税理士事務所では、今後も地元目黒区で、
経営者の皆様の少しでもお役に立てるような
経営セミナーやビジネスセミナーを開催していきたいと考えております。
目黒区での今後の開催予定の経営セミナーやビジネスセミナー、
過去に担当させて頂きました経営セミナーの詳細につきましては、
下記よりご確認を頂けましたら幸いです。
経営セミナーの講師・講演会の講師のご依頼をご検討中の方へ
匠税理士事務所に
経営セミナーやビジネスセミナーの講師・講演会の講師のご依頼を
ご検討して頂ける方につきましては、
下記よりご確認を頂きまして、ご連絡を頂けましたら幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
講演内容や講演料などにつきましても、
できる限り主催者様のご要望に沿いたいと思いますので、
お気軽にご相談下さい。
上記以外の所属税理士や事務所スタッフ、
経営お役立ち情報につきましては、下記よりTOPページへ移動の上、
ご確認をお願いします。
税理士 目黒区なら匠税理士事務所HPへ
起業に必要な開業資金の計算方法と事業計画や創業融資の関係 (15/06/23)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
第3回 匠税理士事務所HPにご訪問ありがとうございます。
起業する場合、会社員の時に、お金を準備する必要があります。いくら資金準備し起業すべきでしょうか。
起業まで資金準備を、簡単なステップで説明すると
ステップ1
起業に必要な資金を計算し、ステップ2
自分の貯金でまかなえそうなお金を計算しステップ3
残りの資金を融資してもらうための準備をするこのようなステップで開業資金を準備していきます。
(関連記事: 起業・開業の貯金はいくらまで貯める、用意するべき? )
今回は、これらの開業資金の計算方法について紹介します。
起業に必要な開業資金の計算方法とは?

起業をするために必要な資金幾らでしょうか。
分かりやすくするためこの資金を種類ごとに分類して考えてみましょう。
大きく分類すると
①起業の時だけに必要な資金
②起業後の会社を運営する際の、経営安定化に必要な資金
この2つが通常必要な開業資金です。
①②は、会社立ち上げ時に、この開業資金がなればスタートできないわけです。
起業するときには、もう一つ考えておかなければならないことがあります。
それは、事業が軌道に乗るまで耐えられる体力となる資金です。
単純にいえば
会社が赤字の間、持ち応えるための
③会社運営の資金
④当面の生活費
ということになります。
①②は、起業のために使う開業資金です。
③④は、いざというときのために貯金として用意したい資金です。
この③④を視野に入れず起業をしてしまうと
資金がなくなって倒産ということが起こってしまうため注意が必要です。
次に個々のお金の計算方法をみましょう。
起業時・創業時だけ必要なお金の計算方法

実際に会社を作るために必要資金は、どんなお店を作るか決定し見積り等で計算することになります。
ここでは、会社員時代の経験を活かし
必要な設備や機器をピックアップしながら一つ一つ業者さんと価格を決定していきます。
ビジネスプランがどれだけ具体的にできているかどうかと、会社員時代の経験値が非常に重要になります。
開業資金の主な例として
A 事務所や店舗を設けるための初期費用
B 商品や材料などを揃えるための費用
C 会社を作るための費用
D オープンの販売促進に使う費用
などがあります。
会社員時代と全く異なる業種で起業してしまうとこの見積りや必要な機材が分からず苦労してしまうことがあります。
業界での豊富な経験を活かしたり、経験が不足する場合には、業界の研究を充分に重ねましょう!
起業後の会社運営・経営の安定化に必要な資金

事業は思いのほかお金がかかるといったご意見が多いのは、
この経営の安定化のために必要な資金が
頭の計算から漏れているケースが多いからです。
商売では、商品を先に仕入れたり、業者さんへのお支払を行って、
その商品やサービスが売れ、お金が入ります。
その間には、当然、家賃や会社を維持するお金が必要となります。
売れたお金が入ってくるよりも先に仕入れや外注、経費といった支払いがたくさん発生するのです。
売れたお金が入ってくるまでの間に会社を安全に運営していくためには、経営の安定化のお金が必要となるのです。
ビジネスプランと照らし、売り上げのお金が入るまでの間持ちこたえるお金を計算しましょう!
安全に起業するための保険となる資金
続いて赤字の間、持ち応えるための資金も重要です。
つまりは、③事業運営の資金・④当面の生活費です。
この2つは、社長様が事業を何ヶ月で軌道に乗せられるかどうか、
生活レベルがどの程度かによって変わります。
ポイントはこの③④のお金がどれだけあるかどうかが実は非常に重要です。
この余裕資金がないと、経営者は資金に振りまわれて正常な判断が出来なくなってしまいます。
また、生活資金が減少し続けると、家族にも迷惑をかけてしまいます。
悲観的に想定し、必要な開業資金を貯蓄しましょう!
最後に、創業融資を検討してもらえるお金は
①起業の時だけに必要な資金
②起業後の事業運営する際の、経営の安定化のために必要な資金
となります。
つまり、いざという時の個人の貯蓄がある程度でき、
起業に必要な①②の資金を試算してから、
どれだけを貯蓄で、どれだけを創業融資でといった流れで
開業資金の問題をクリアにしていきます!
創業融資など未経験分野に関しては、その道のプロに相談することも大切です。
日本政策金融公庫の創業融資支援サービス
匠税理士事務所は、日本政策金融公庫提携の会計事務所・経営革新等支援機関として中小企業の財務や経営のサポートを行っております。創業融資については、私共にお任せください!

創業融資と共に株式会社設立などをご検討されている方は、こちらをご確認下さい。

創業融資のお役立情報バックナンバーは
創業融資の情報館 バックナンバー へ。
記事については免責事項をご確認下さい。
起業や開業支援の一覧
会社設立の代行...これから会社を作るお客様向けの会社の設立・経理や税金、経営のサポート。
税理士の創業支援...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポート
給与計算...給与計算の代行や、社会保険の加入手続き、人事労務のサポート
助成金...正社員化や社員教育についての助成金代行とコンサルティング
開業資金や日本政策金融公庫の創業融資に関する記事を最後までご覧頂きましてありがとうございました。
税理士の対応エリア:世田谷区や目黒区、品川区など東京23区
目黒区の匠会計事務所TOPへ
資金調達は起業で一番大切。金融公庫の創業融資を活用すべき (15/06/18)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
第1回 これから起業をしようと思っており、本業(営業や製造、生産)に関することは自信があるが
本業以外のことは心配ということはないでしょうか。
起業後は、どんなことに苦労するのでしょうか?
既に起業された方の声からこれから準備すべき点は何なのか一緒にみていきましょう!
起業時に苦労したこと 資金調達が最も多い悩み

起業家の主な資金調達先となる日本政策金融公庫の調査によると(3点複数回答可)
これから起業される方が苦労したこと
第一位は、資金繰り・資金調達 47.7%
第二位は、顧客・販路の開拓 45.6%
第三位は、財務・税務・法務知識の不足 33.8%
となります。
第一位は、お金の問題、資金調達です。
起業される方は、会社員時代に管理職であった方が最も多いという結果があります。
つまり、会社員時代に、
本業に関するノウハウや経験を積み
自信がついた時に起業という流れが一番多いのです。
会社員時代には、
どんな商品を作って(企画)、作り(生産)、どう売るか(販売)が中心となります。
しかし経営者となると
商品の企画・生産・販売の段階のお金の問題をクリア、
そのため、お金をまわしていけるかどうか
お金が無くなったらどうなってしまうのだろうということが不安の第一位となります。
(関連記事: 起業・開業の貯金はいくらまで貯める、用意するべき? )
創業した後の、現在の苦労は・・・

それでは創業したのちには、どんな問題が苦労があるのでしょうか。
第一位は、顧客・販路の開拓 44.2%
第二位は、資金繰り・資金調達 39.7%
第三位は、従業員の確保 28.1%
ここで着目すべき点は
起業した後も、お金の問題が、第二位にあります!
起業後に、会社が上手くいかないからでしょうか?
これには、こんな理由があります。
思ったよりも事業にはお金がかかる。
これが要因の一つです。

商売では、商品を先に仕入れたり、
業者さんへのお支払を行って、
その商品やサービスが売れ、お金が入ります。
その間には、当然、家賃や会社を維持するお金が必要となります。
売れたお金が入ってくるよりも先に
仕入れや外注、経費という支払が発生するのです。
売上が伸びれば伸びるほど、
成長過程ではたくさんのお金を必要とします。
これが起業後、社長の苦労に資金繰りがある原因です。
(関連記事:売上が伸びているのに資金不足なのは・・ )
起業成功は資金問題を解決できるかどうか
ここで注目すべき点は
第三位にあった
財務・税務・法務知識の不足がなくなっていることです。
多くの社長さまは、起業後に税理士と契約をします。
そのため財務や税務、法務に関する知識の不足が苦労からなくなるわけです。
しかし、お金の問題だけ、なぜ残るのでしょうか?
税理士にもいろいろな得意・不得意があります。
一般の税理士事務所は、融資・資金調達は、社長様任せになる事がほとんどです。
そのため社長様は、資金問題について
相談相手がいない...
もっと事業を大きくしたいのに資金調達でブレーキがかかる...という悩みを抱えてしまうのです。
このことから分かるようにこれから起業しようとするときには経理や税金だけではなく、
お金など資金調達や、経営の問題にもしっかりと対応できる税理士を選ぶことが大切です!

起業や開業時の資金調達支援のご紹介
匠税理士事務所では、日本政策金融公庫等の金融機関と連携し、起業や開業に必要な資金調達をサポートしております。
これから起業されるお客様向けの、融資支援サービスはこちらとなります。
日本政策金融公庫の創業融資支援
創業融資のお役立情報バックナンバーは
創業融資の情報館 バックナンバー へ。
記事については免責事項をご確認下さい。
起業支援サービス一覧
会社設立...これから会社を作るお客様向けの会社の設立・経理や税金、経営支援。
創業支援...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポート。
給与計算...給与計算の代行や、社会保険の加入手続き、人事労務の代行。
助成金の代行...正社員化や社員教育についての助成金代行とコンサルティング
法人のお客様向けサービス...黒字戦略や財務強化のご紹介
起業時の資金調達に関する記事を最後までご覧頂きありがとうございました。
創業計画書の書き方・記載について (15/05/29)
以前にも創業計画書の書き方について記載致しましたが、
今回は創業計画書の中でも、
取扱い・サービス欄と取引先・取引条件等の欄について
その書き方の説明をしたいと思います。
(参考:創業計画書の作成ポイント)
創業計画書 取扱い・サービス欄の書き方
【お取扱いの商品・サービスを具体的にお書き下さい】
この創業計画書 取扱い・サービス欄には、
商品内容のみではなく、別紙で写真入りの説明をするなどのアピールをすることがお勧めです。
【セールスポイントはなんですか?】
この欄には商品構成を記入するのも重要ですが、
仕入れに関する優位性やこれまで培ってきた販売技術や
イベント開催などの強みをセールスポイントとすることが重要です。
創業計画書の取引先・取引条件等欄の書き方
【販売先・仕入先・外注先】
審査の際に重視される欄です。
契約書・注文書など手元にある書類は必ず提出して下さい。
個人情報の取り扱いには注意しながら、
可能な範囲で顧客リストを見せることも有効なアピールです。
なお創業準備と並行して、
新規の顧客開拓をしている場合には顧客開拓進捗表などの作成がおすすめです。
また、仕入先や外注先などの中に大手企業があると
審査に有利に働く場合があります。
【従業員等・人件費の支払い】
事業内容や売上予測と比較して適正な従業員数かを確認される欄です。
従業員数と人件費との整合性には十分な注意が必要です。
創業計画書の作成支援
匠税理士事務所では、
起業時の資金調達を支援しております。
そのため創業計画書の作成でお困りの方をサポートするサービスをご用意しております。
詳細につきましては、下記よりご確認をお願いします。
→ 創業融資支援サービス
最終更新日:平成27年5月29日
上記以外の起業お役立ち情報は、
下記よりトップページに移動の上、
ご確認下さい。
品川区での経営セミナー (15/05/23)
匠税理士事務所では、
経営支援を通じて、地元地域の活性化に少しでもお役にたてればと考えております。
その一環として、
東京商工会議所の品川支部様にて経営セミナーの講師を
匠税理士事務所の税理士 水野 智史が担当させて頂きました。
当日は、3月という決算など年度末の会社様が多いにもかかわらず、
定員70名までの申し込みを頂き、
とても熱心に受講して下さった方が多かったのが印象的でした。
セミナーをご提供出来るように努めて参ります。
品川区での経営セミナー当日

品川区での今後の経営セミナー予定
匠税理士事務所では、品川区や目黒区など地元でのセミナー開催を今後も積極的に開催していきたいと考えております。 経営セミナーの開催状況につきましては、随時ホームページへ掲載していきたいと思いますので、ご興味のある経営者の方は、お気軽にお申し込み下さい。→ 経営ビジネスセミナー・経営講座情報匠税理士事務所の概要についてはこちらから
弊所では、品川区などを中心に独自の経営支援サービスをご用意し、経営支援などに力を入れている30代のメンバーが中心の税理士事務所です。 所属税理士やスタッフ・提携先など事務所の詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。→ 自由が丘の税理士 匠税理士事務所設備投資を決算対策で行う際のポイント (15/05/22)
決算前になり利益がでそうなので、
そろそろ設備も古くなってきたし、買い替えたいので経費にならないかと
聞かれることがあります。
決算対策での設備投資、ポイントは金額
事業に関係するものなので、最終的には全額費用となるのですが、
問題はその時期です。
100万円利益が出そうだから、100万円設備を買う。
これで利益0という具合にはいかないのです。
 税法には耐用年数が各資産ごとに決められていて、
税法には耐用年数が各資産ごとに決められていて、
今回買おうとする資産は、
例えばサーバー用以外のパソコンであれば、
4年で使い切るのが妥当という具合に
決まっているのです。
このように定められているので、
100万 ÷ 4年 = 25万円
(期中の購入ならさらに月数按分されます)のみが、今年の費用となります。
(ここでは分かりやすくするため、定額法での説明となっています。)
もちろん、途中で壊れて処分をした場合には、
除却ということで全額費用となりますし、
1つの資産の取得価額が30万円未満のものについては、
一時に費用化できるという特例(合計額300万円が限度)もありますが、
原則は上記のように考えます。
また決算対策での設備投資を行う場合には、
税額から取得価額の一定割合を控除するという税額控除を検討するのも有効です。
税額控除は、毎年改正がありますので、
(国税庁の設備投資の税額控除)など国税庁のサイトで
時折、確認するようにしましょう。
利益を予測した上で、早期に行うのが節税対策のポイント
節税対策は、利益を的確に予測したうえで
決算前の対策はできるだけ早目に、かつ資金繰り、
翌期の事業戦略もよく考えて行わないと
設備を買って資金・税金も出てしまうという
二重な痛手になりますので注意が必要です。
匠税理士事務所では、
決算前に利益を予測し、
税額のシミュレーションを行っております。
弊所のサービスラインは、下記よりご確認をお願いします。
上記以外のサービスラインなどにつきましては、
下記よりトップページへ移動の上、ご確認をお願いします。
最終更新日:平成27年5月22日
業種や事業内容、代表者など創業融資の注意点 (15/05/09)
匠税理士事務所では、
起業時に必要な資金調達や創業融資を通じて、起業支援に力を入れています。
今回は、より多くの方の起業時の資金調達のお役に立てるように
創業融資を受ける際に支障が出やすい事項についてまとめてみました。
融資を受けることができない業種・受けにくい業種はあるの?
金融業・遊興娯楽業などを行う方は、
原則として公的創業融資制度を利用することができません。
特に金融関連の事業については、細心の注意が必要です。
事業を行う本人ではなく、配偶者を社長にしての創業融資申請は可能ですか?
原則は事業を行う本人が、代表者として申請する必要があり、
名前だけ借りるという場合は、認めらません。
その配偶者が事業に実際に参加することが大前提となります。

業種特性として女性社長のほうが、
イメージ戦略を立てやすいネイルサロンなどの業種といった
よほどの事がない限りは、
本人以外を代表者にして創業融資を獲得するのは困難です。
過去に事業をされていて、
融資の返済が遅れたなどの事情があり、
ご自身で融資を受けるのは難しいので、
何とか奥さんを社長にして融資を検討できないかという場合でも、
事前照会や面談などで確認が行われますので、
やはりご自身が代表者となり、創業融資の申請をすべきです。
匠税理士事務所の創業支援サービス
弊所では、起業時の資金調達を通じて、
起業の成功を支援するため創業融資に力を入れており、
これまで数多くの実績がございます。
創業計画書の作成や融資制度全般について相談をしたいという
起業家の方がいらっしゃいましたら、
下記より創業融資支援サービスをご確認頂けましたら幸いです。
→ 目黒や品川、世田谷など東京都での創業融資や起業の資金調達
創業融資以外にも会社設立や起業後の経理・経営支援を承っております。
サービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。
最終更新日:平成27年5月9日
匠税理士事務所の所属スタッフやアクセス、
その他のお役立ち情報は下記よりTOPページ移動の上、ご確認を頂けましたら幸いです。
世田谷区 税理士 弊社HPはこちらへ
売上や仕入の経理処理ではどこに気を付ける? (15/04/25)
ご自身で経理をやられている方にとって、
慣れない会計ソフトでの入力は中々大変な作業だと思います。
特に、売上や仕入の経理処理は、損益に与える影響が大きいのと同様に、
税務調査でも重点的に確認されるので、とても重要。
そこで今回は、売上や仕入の経理処理ではどこに気を付けるべきかについて記載しました。
売上や仕入は特に重要な勘定科目
売上や仕入は勘定科目はシンプルですが、
取引先が多数にのぼると計上漏れが、
一番の注意点となります。
これが漏れていれば、
損益に大きな影響があり、税金にも影響するので、
税務調査では、ここが重点的に確認されます。
また経営の面でも、
商品の仕入・売上は会社の業務のメインであり重要。
売上を期日に回収できないと
資金ショートの可能性が大きくなり、
買掛金の支払いが滞ると会社の信用にもかかわってっくるので
正しく計上し管理されなければなりません。
仕入・売上を会計処理して計上する際のポイント
売上の計上基準
売上の計上基準についての詳細は、
以前に記載しました下記よりご確認をお願いします。
仕入の計上時期
一定期間の取引を集計して請求されることが多く、
請求書より当該期間の仕入合計額で仕訳・入力する。
ポイントは、商品の納品がいつかということ。
支払い時の経費ではなく、納品されたのがいつかがポイントです。
支払方法のチェックポイント
振込の場合は、振込手数料を受取人側で負担する場合は、
その手数料金額を差し引いた金額を振り込むが、
この取引の仕訳計上の際、買掛金満額を借方に計上することで、
買掛金残高が合わなくなるので注意!
また、買掛金や経費を総合振込の場合には、
総合振込依頼書にて科目をチェックします。
支払手形の(将来一定時点を支払日とする証券)場合は、
仕入時 → 仕入/買掛金
手形振り出し時 → 買掛金/支払手形
手形期日 → 支払手形/当座預金など
そして、月末には買掛金とともに
支払手形や当座預金の残高を試算表で
確認することが重要です。
匠税理士事務所の経理支援サービス
弊所では、お客様が本業に集中できるように、
経理や会計のアウトソーシング、給与計算や社会保険などのアウトソーシングを承っております。
これから起業をお考えの方や起業され間もない方は、
下記より起業支援サービスの詳細をご確認下さい。
→ 起業支援サービス
既に会社を経営されている方につきましては、
こちらより各種アウトソーシングサービスや経営支援サービスをご確認頂けましたら幸いです。
最終更新日:平成27年4月25日
その他のサ―ビズラインや事務所に関する情報は、
以下のリンクよりTOPページへ移動の上、ご確認をお願いします。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
創業計画書で必要な資金と調達方法はどう書くの? (15/04/16)
創業計画書の記載項目で重要箇所の一つとして、
起業するための必要な資金とその調達方法の欄があります。
そこで今回は、
創業計画書の作成における必要な資金と
その調達方法について記載します。
創業計画書の表は
右側:事業に必要なお金をどうやって集めたのか?
(自己資金額・借入額など)
左側:そのお金を事業の何に使うのか?
(設備や運転資金の項目と金額)
という内容で構成されています。
この時、右側の合計金額と、
左側の合計金額は必ず一致させることが必要です。
起業に必要なお金の書き方について
<設備資金の欄>
この欄には、
今回の事業で購入予定の設備の名称と金額を記入します。
ここでいう設備とは、減価償却できる資産です。
内装費・店舗を賃貸した場合の保証金・敷金等も含まれます。
見積書等が用意しにくい場合には
各項目で自分が予測する金額を計算し、
内訳などを別紙に記入するのも一手です。
<運転資金の欄>
この欄には商品の仕入れ、経費の支払いなど
設備資金以外のものを記入します。
融資対象となるのは目安として運転資金の2~3か月分です。
 運転資金の計算でおかしがちなミスに、
運転資金の計算でおかしがちなミスに、
個人事業の方の給与があります。
個人事業の場合、
事業主の給料は経費として計上はできません。
(この欄の人件費として記入できないことに注意して下さい)
法人の場合には役員給与として計上することができます。
運転資金・設備資金でのポイントは、
しっかりと資料を用いてどのような目的で、
幾ら必要なのかを理路整然と説明できることです。
(関連記事: 運転資金とは何か、設備資金との違い )
創業計画書における資金の調達方法の書き方について
上記のようにして、お金が何に幾ら必要かを記入した上で、
その資金をどのようにして調達するのかを記載します。
大体はご自身で貯金された自己資金の金額と、
融資による借入希望額を記載することになります。
ここでのポイントは、
1 自己資金の金額と借入希望額の金額が妥当であること
2 自己資金を用意するまでのプロセスがしっかりとしていること
という大きく分けて2つがポイントになります。
関連記事:
( 創業融資の審査のポイント )
匠税理士事務所の創業融資・起業支援サービスのご紹介
匠税理士事務所では、
創業計画書の作成支援から面談のリハーサル・当日の面談立ち合いなど
起業に伴う資金調達のサポートを行っております。
創業融資をご検討中の方は、
下記より詳細をご確認頂けましたら幸いです。
その他、会社設立や起業後の経理や経営支援も行っております。
起業支援サービスの詳細につきましては、
下記よりご確認下さい。
→ 起業支援サービス
最終更新日:平成27年4月16日
匠税理士事務所の所在地やその他の事務所情報などにつきましては、
下記よりTOPページへ移動し、ご確認をお願いします。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
武蔵小杉や元住吉の税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (15/03/26)
ホームページへご来訪ありがとうございます。
弊所は武蔵小杉や元住吉など東急東横線の沿線で
【 起業支援と経営支援 】が評判の会計事務所で、
【 経営に必要な全てがそろう税理士事務所 】をコンセプトに弁護士・社労士・司法書士・行政書士が
チームを編成し給与計算・助成金・法務もサポートします。
世界4大会計事務所出身の税理士の経営支援では
社長様と一緒に黒字化支援・資金調達・節税対策や
【お金がたまる仕組み作り】など多角的な提案で、
お客様の会社の利益・資金の最大化を行います。
所属税理士やサービスはこちらで確認下さい。
【 →起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】

武蔵小杉・元住吉の税理士の会社設立・起業支援
武蔵小杉や元住吉で会社設立されるお客様に
起業支援セミナー講師を務める40代税理士と、
川崎市の提携司法書士がご要望を伺い、
会社設立時の役員構成や株主構成をどうすべきか
資本金や決算月はどうすべきかを話し合います。
お客様にとっては一生に一度の大事な起業ですので【 匠税理士事務所に任せて良かった 】といって
頂けるよう会社設立を丁寧に取り組みます。

【 お客様との信頼関係 】が最重要と考えており、
提携先は全て10年以上お仕事をしている専門家で チーム編成し、お客様の成功のため起業支援します。武蔵小杉の起業支援を担当する税理士は、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

武蔵小杉や元住吉など東横線沿線の会社設立では、
お客様は会社名と本店所在地をお決め頂ければ
【後はお任せ】というスムーズな会社設立を行い、
本業に集中して頂ける環境作りに努めます。
起業支援はこちらでご確認下さい。

武蔵小杉や元住吉の創業融資による創業支援
株式会社や合同会社の会社設立後の資金調達のため
創業融資をご検討されている方には、
武蔵小杉や元住吉エリア対応の日本政策金融公庫や
各金融機関と連携した創業融資も行ってます。
創業融資による創業支援では、
計画書作成を税理士がお客様と一緒になって行い、
融資面談前のリハーサルも行います。

また金融機関担当の方の面談も匠税理士事務所で
税理士立ち合いのもとに行えるという
弊所の独自の創業支援をご用意致しております。
武蔵小杉や元住吉でもトップクラスの融資実績があり 【 成功率は9割を超える実績 】がございます。起業したいが自己資金の一部を外部調達したい。
このような方はお気軽にご相談下さい。
【→ 創業融資による資金調達支援 】

(武蔵小杉や元住吉地区の制度融資も対応します)
桜新町や玉堤の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
(創業支援は、武蔵小杉や元住吉など対応)
武蔵小杉や元住吉近く匠税理士事務所の特徴
匠税理士事務所の最大の特徴は、人の質です。事務所とお客様の付き合いは結婚と似ています。
起業から事業をやめられるまでのお付き合いを
考えると長ければ20年以上にもなります。
弊所の平均関与年数は、【 10年以上 】となり、
多くのお客様に長い間ご利用頂いております。
弊所ではお客様のお役に立ちご利用頂くには、
決めた約束は必ず守る人間性と、お客様課題を
解決する専門性が大切と考えておりますので、
優秀な人材・提携先が不可欠と考えております。そのため、社内スタッフをはじめ、
提携先の専門家の充実には力を入れております。
今後も武蔵小杉や元住吉など東横線沿線での
経営支援No1税理士事務所・会計事務所を目指し税理士・スタッフ・提携先充実に取り組んで参ります。
法人経営者向け経営支援や税務会計サービスはこちら
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

武蔵小杉や元住吉の確定申告・会計経理の代行
武蔵小杉や元住吉にお住いの方に向け
以下の税務申告サービスを提供致しております。
・個人事業主の方の会計や確定申告代行
・相続税の申告や相続対策
・会計経理代行や給与計算、社会保険手続き
・土地や家、武蔵小杉のタワーマンション売買
賃貸収入に伴う確定申告
・建設業などの各種許認可申請や更新手続き
・契約書作成や各種慶弔規定の作成など
・外国の方のためのVISA申請代行
武蔵小杉の方向け経理や会計、確定申告や
青色決算サービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
武蔵小杉や元住吉で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

武蔵小杉や元住吉での法人化・法人成り
会社設立や起業支援以外にも、
個人事業で事業を行っていたけれども
株式会社や合同会社にする法人化も対応してます。武蔵小杉や元住吉で事業をされていて、
法人化・法人成りに興味があるので
話を聞いてみたいという方には、
法人化した場合のメリット・デメリットを
分かりやすく説明する相談会も行っております。
お気軽にご相談下さい。
武蔵小杉や元住吉で匠税理士事務所の
法人化サービスは、こちらからご確認下さい。
【 → 法人化・法人成りサービス 】
助成金や補助金申請にも対応の会計事務所
こちらの創業融資以外にも武蔵小杉や元住吉で
起業される方の資金調達の選択肢として、
助成金・補助金申請での資金調達も選択肢です。弊所では助成金申請に特化した社会保険労務士と
武蔵小杉対応の起業専門税理士が連携し
助成金の申請代行も承っております。
起業時に人を雇う場合には助成金の要件を
満たすこともございますので、
創業融資・助成金申請などお気軽に相談下さい。
こちらより確認を頂けましたら幸いです。
【→ 起業のお客様 サービス一覧 】

武蔵小杉近くの税理士事務所求人採用
武蔵小杉や元住吉以外の方への
東横線の方に向けた紹介につきましては、
こちらよりご確認下さい。
→東横線の税理士・会計事務所は匠税理士事務所
その他の法人設立以外の情報や
(武蔵小杉・むさしこすぎ)、
(元住吉・もとすみよし)の方に向けた
匠税理士事務所の求人や採用などに
つきましては採用情報をご確認下さい。
働きやすさ重視を追求しておりますので、
【平均在職年数が6年以上】の事務所です。
お客様にも社員の方にも長期間お付き合い頂ける事務所づくりを心掛けております。
詳細につきましては採用情報をご確認下さい。
【 → 武蔵小杉など東横線・目黒線の税理士・会計事務所の採用求人】
武蔵小杉近くの税理士事務所お役立ち情報
武蔵小杉とは、武蔵小杉駅の周辺名称で、
神奈川県の川崎市中原区になります。
武蔵小杉で会社設立など起業した場合や、
会社経営をされている場合の税務申告書、
届出書提出先は以下のようになります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 武蔵小杉の方の税務申告書、届出書提出先 【 → 川崎北税務署 】管轄区域・中原区・高津区・宮前区
〒210-8606
川崎市川崎区榎町3番18号
東京国税局業務センター川崎南分室
(川崎北税務署)
事業税・住民税の申告書、届出書提出先 【 → 高津県税事務所 】管轄区域・川崎市中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区
〒213-8515
川崎市高津区溝口1-6-12
リンクス溝の口 2階
住民税などの申告書、届出書提出先 【 →川崎市役所 】〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
社会保険関連書類の提出や相談先 【 →日本年金機構 高津年金事務所 】〒213-8567
神奈川県川崎市高津区久本1-3-2
上記が武蔵小杉の方の税務申告や社会保険の
届出書の提出先・税務調査所轄となります。
期限までに決算関連書類の提出を行いましょう。
最後までお読み頂きありがとうございました。
武蔵小杉や元住吉で会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い税理士・会計事務所をお探しの方は
匠税理士事務所へお気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
令和6年10月13日更新
#武蔵小杉税理士
#武蔵小杉会社設立
創業融資の審査のポイント (15/03/21)
創業融資を担当する金融機関の担当者は、
融資の審査において、
「人間性」 「将来性」 「確実性」 に大きなウェイトを置いています。
したがって、融資の審査ではこれらをしっかりと担当者に伝えられるかが、
創業融資の成否に大きく影響してきます。
創業融資の審査では、次の点に注意が必要です。
①事業に必要な経営能力があるか?
経営能力の有無
・創業の動機
・これから始める事業での経験
・事業に対する考え方
事業計画の妥当性
・収支予測の組み立て方
・収支予測の見通しについての考え方
②本当に売り上げが立てられる計画となっているのか?
その計画が事業として継続できるものかどうかは非常に重要です。
商売として成立する(=継続的に売り上げ・利益が出る)ためには、
事業の仕組みがしっかりしていることが必要です。
事業の仕組みの裏付けには
下記からなる事業計画の妥当性を要しま す。
す。
・収支計画
・資金繰り
・財務的根拠
※融資対策上、「販売先」と「販売予定」の確保が
ポイントアップにつながります。
そのため、販売先については、
根拠資料を個別に用意する等の重点を置き、
融資担当者に安心して融資ができる先であることを
伝えることが重要になります。
③返済が滞りなく行える計画となっているか?
売上以上に原価や経費がかかってしまうと、
返済に支障が出る可能性があります。
そのため、収入・支出・利益のバランスが重視されます。
具体的に、利益が捻出できるかどうかは次の算定式で計算されます。
a(税引き後利益+減価償却費-個人事業の場合には生活費) > b(返済額)
aの部分が返済の引き当て分と判断されます。
a>bであるとき、融資の見込みありと判断されます。
創業計画の時点で、a<bになると思われてしまうと、
融資の実行は難しくなりますので、
必ず返済ができるということを固い数字で、証明することが重要になります。
④創業計画書の数字は根拠をもって作られているか?
創業計画書に記載する数字は「裏付けがあるもの」であり、
「実行が可能なもの」でなければなりません。
例えば、事業用の設備や事務所備品などは金額の根拠として
見積書やインターネットの価格カタログ等を準備することがその根拠となります。
ここでもやはりポイントになるのは、
 金融機関で審査をする際に、
金融機関で審査をする際に、
書類を基に行うということに配慮して、
創業計画書の数字は、
何らかの書類に根拠づいた
しっかりとしたものであることがポイントになります。
このように、
創業融資では、「人物」 「将来性」 「確実性」 をしっかりと金融機関の担当者に説明することで、
融資をしてもしっかりと返済できる相手先であることを伝えることがポイントになります。
匠税理士事務所の創業融資支援サービス
匠税理士事務所では、日本政策金融公庫をはじめ、各種金融機関と連携することで、起業時の資金調達を支援しております。
創業計画書の作成など創業融資に関するサービスは、下記よりご確認をお願いします。
目黒区、品川区や世田谷区など東京都23区での創業融資や資金調達支援サービス
株式会社や合同会社など会社設立も承っております。
匠税理士事務所の会社設立の代行サービスはこちらから
創業時の資金調達など起業を支援するためのセミナーも開催中
匠税理士事務所では、起業時の資金調達や経営に関するポイントをお伝えするためのセミナーも開催しております。
創業セミナーの詳細やサービスライン、
会社情報につきましては、下記よりご確認をお願いします。
世田谷区 税理士事務所 の匠税理士事務所HPTOPページへ移動します。
最終更新日:平成27年3月21日
開業や起業の際の自己資金はどこまで認められるか (15/03/13)
日本政策金融公庫などで創業融資を検討したいのですが、
開業や起業の際の自己資金にはどこまでが認められるのでしょうか?
このように思われている起業家の方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、開業や起業の際の自己資金について記載したいと思います。
開業や起業の際の自己資金として扱われるもの
開業や起業の際の自己資金として扱われるものとしては、

・会社員時代などに起業のために貯蓄してきたお金
・車などを売却したお金
・既に事業のための保証金や機械などに利用したお金
がございます。
車や機械なども結局は、
地道に働いて貯めたお金で買ったものですから、
ポイントは、
いずれも地道に蓄えてきたというプロセスです。
つまり、
【 しっかりとお金を貯めれる 】 = 【 お金を返せる 】
とつながることです。
逆に自己資金として扱われにくいものには、
どのようなものがあるのでしょうか?
創業融資などで自己資金として認められにくいもの
創業融資では、
次のお金は中々、自己資金として認められにくいです。
・ノンバンクなどから借りてきたお金
・親などから贈与されたお金
・第三者から借りてきたお金
これらは、いずれも地道に貯めてきたものではなく、
ただそこにたまたまお金があるという状態です。
これでは、
【 しっかり貯めれない 】 = 【 貸しても返ってくるのか危うい 】
ということになるため、
中々自己資金としては認められません。
創業融資では、自己資金の金額とプロセスが重要
創業融資では、自己資金の金額とプロセスが、
その人の起業にかける熱意をあらわします。
融資担当者も、一回の面談で大金を貸すわけですから、
【 論より証拠 】 というわけで、
これまでの自己資金という実績を重視します。
将来は起業をしたいとお考えの方は、
自己資金をしっかりと準備することが重要です。
(関連記事:起業や開業のための貯金はいくらまで貯める、用意するべき?)
匠税理士事務所の創業融資支援サービス
弊所ではこれまで数多くの起業資金調達のお手伝いをして参りました。
これから起業・開業をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
サービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。
→ 品川区や世田谷区、目黒区など23区での創業融資や資金調達支援
匠税理士事務所の起業支援サービス一覧や特徴はこちらからご確認下さい。
→ 起業支援サービス
最終更新日:平成27年3月13日
上記以外のスタッフ紹介や、
経営に関するお役立ち情報につきましては、
下記よりトップページへ移動の上、ご確認をお願いします。
世田谷 税理士 の匠税理士事務所HPへ
荏原や豊町の税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (15/03/07)
ご来訪ありがとうございます。
弊所は荏原や豊町など品川区を中心に
お客様に支持される事務所を心掛けています。そのため、規模は追わず、
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に、お客様のお役に立つことが出来る
【人材の質 と サービスの質】を追求しており、【高度な専門性】と【技術力】を用いて、
関与先の黒字率は90%を超えています。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の所属税理士や、
業務内容・料金はこちらでご確認下さい。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

荏原や豊町で税理士の会社設立・起業支援
匠税理士事務所には、
40代の起業支援セミナー講師が在籍し、 東京商工会議所など各機関で多く公演します。そのため会社設立のご相談や起業に関する
ご依頼を多く頂いております。
こうした起業支援のお仕事を通じて、
会社設立に伴う手続きはもちろんですが、
起業後に儲かって、お金が残る仕組み作りに豊富なノウハウがございます。
経理や会計、給与計算の代行や
税務申告、決算にも対応しておりますので、
お客様は本業に集中していただけます。
荏原や豊町起業支援担当の税理士はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

荏原や豊町などで株式会社の会社設立など
税理士による起業支援は、こちらを確認下さい。
荏原や豊町での創業融資による創業支援
独立開業など創業支援で多くご相談を頂くのが、
会社設立時の資金のご相談です。
運転資金は多ければ多い方が、
経営の安全度は増加しますので、
起業される方には創業融資をご提案しております。
品川区の日本政策金融公庫や各種金融機関とは、
綿密に連携しております。
また金融機関OBも顧問に在籍しており、
品川区での融資実績はトップレベルで、 成功率は90%を超えております。荏原・豊町など品川区で会社設立時の創業融資による
独立開業や創業支援はこちらを確認下さい。
【→ 品川区の創業融資・資金調達】

荏原や豊町の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(創業支援は、荏原や豊町など品川全域対応)
荏原や豊町の確定申告や決算代行も対応
荏原や豊町で事業を既にされている方で
経理や会計のアウトソーシング、
税務申告や決算代行の要望にも対応してます。
また建設業許可申請や社会保険手続き、
VISA取得や法務など会計事務所以外の要望も
行政書士や社会保険労務士と連携し対応してます。
経営に必要な全てがある事務所 を軸に今後も荏原や豊町など品川区エリア対応の提携先の充実に努めて参ります。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
荏原や豊町の方向け確定申告や経理の代行
法人化など個人サービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
荏原や豊町で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

荏原や豊町の会社設立・法人化登記情報
品川区の荏原・豊町で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
荏原や豊町など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が荏原や豊町で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
今後もご要望に応じて随時サービス内容の増加、
提携先の拡充に努めて参ります。
また当会計事務所では正社員やパートスタッフを
募集しています。
荏原や豊町など品川区で会計事務所勤務を
ご検討中の方は、弊所採用をご覧ください。
(荏原・えばら)や(豊町・ゆたかちょう)など
品川区近くで税理士や会計事務所をお探しの方に
向けた匠税理士事務所の案内ページを最後までご覧頂き感謝致します。
荏原や豊町など品川区で会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い会計事務所をお探しならお気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#荏原税理士
#荏原会社設立
会社設立時の役員(取締役)・株主などパートナー選びは慎重に (15/02/20)
会社設立時には、資本金を幾らにするかと同じ位悩む事項に役員構成をどのようにするかが挙げられます。
会社を設立する際に、仲の良い人や前職の先輩などと一緒に起業されるという方も多いと思います。
このようなときに気をつけるべきことが幾つかありますが、今回はその中でも創業融資や資金調達面での影響と会社設立時に役員構成を考える際のポイントをまとめました。
会社設立時の役員などパートナー選びが創業融資にブレーキをかけることも・・
【会社設立時に自分が社長で、友人に役員(取締役)になってもらい、
役員給与などなくても時折、経営の相談ができればいいな~。】
このような考えで、役員になってもらうと、
意外なところに落とし穴があることもあります。
というのは、その役員の方が<去に金融機関とリスケジュールや、
返済不能などトラブルを起こした方だと、
金融機関は会社自体をそのように判断してくる可能性が高まります。
友人には、こうした事を話していないケースもありますので、
思わぬところでトラブルにならないように取締役など役員を外部から入れる場合は、
特に慎重に検討する必要があります。
起業時は、役員・株主は1人か家族のみの経営がベスト
上記のことから、起業時は役員や株主は社長のみの会社か、社長と奥様のみ役員での会社設立をお勧めします。
これは上記の創業融資の点からもそうですが、
役員や株主をできる限り少数にすることで、重要なことを判断する際の意思決定もスムーズになったり、
喧嘩別れにより会社が空中分解してしまうことも避けられます。
役員の種類にはどのようなものがある?
株式会社の役員には、取締役、監査役、会計参与の3種類がありますが、取締役だけで起業するケースが圧倒的に増えました。
監査役や会計参与はある程度会社が大きくなってから検討しましょう。
取締役が3名以上の場合は取締役会を設置できますが、小規模な会社であればその設置はまれです。
起業間もないときは、経営のスピードが大切。
役員の数が多ければ多いほど議論が増え、決定に時間がかかるため、起業間もないときは、出来るだけ少人数の役員構成がよいでしょう。
役員の義務と責任とは その任期は
役員は会社の業務を執行する際に故意または重大な過失によって第三者に損害を与えた場合、それを賠償する責任を負います。
そのほか、兼業を禁止する競業避止義務や、役員が自社と取引する場合に問題となる利益相反取引などにおいて責任を問われます。
これらをどうしても行う場合には、株主総会などでこれらを承認する旨を決議しておくことが必要です。
役員の不祥事などで、会社が損害を被った場合に、株主が会社を代表して役員を訴えることができます。
小規模な会社であっても出資者としての株主の利益をおろそかにしてはいけません。
役員の決定と任期
起業では多くの場合、発起人がそのまま取締役となり、発起人が複数の場合は通常その中から代表取締役を一名決定することになります。
ただし、外部から選ぶこともできます。
株式会社の役員の任期は、定款に特に定めがなければ2年(監査役は4年)です。
そして定款で定めれば最長10年まで延ばすことも可能です。
特にこだわりがなければ、登記費用を抑えることができるので、最長にする場合も多く見受けられます。
登記をほっておくと罰金もありますので、この点からも出来る限り長めの任期が良いかもしれません。
会社設立・創業融資などの起業支援サービス
匠税理士事務所では、
・会社設立のために資本金を幾らにするべきか。
・株主構成をどうするべきか。
・会社を設立した後の入金・支払いのサイトについてどうすべきか
など会社設立やその後の経営についても、しっかりとサポートしております。サービスの詳細につきましては、下記よりご確認下さい。
◇関連記事
起業家の方向けのお役立ち情報を集約した匠税理士事務所の起業塾はこちらから
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス
→起業時の資金調達を支援するための創業融資サービスをご用意しております。

◇会社設立サービス
会社設立をご検討中の方には、設立手続や経理や経営サービスをご用意しております。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
◇法人化・法人成りサービス
匠税理士事務所では、金融機関と提携して、創業時の資金調達や事業計画書の作成サポートを行っております。
起業や創業、開業については、匠税理士事務所へご相談下さい。
IT業の会社設立・創業融資・起業や独立開業は匠税理士事務所 (15/02/06)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は世界4大会計事務所出身の税理士を軸に IT業の会社設立など起業支援に強い事務所です。・IT業界で独立開業して成功できるでしょうか?
・起業したらどんな流れになるのでしょうか?
起業セミナーでこのようなご相談を頂きます。
今回はIT業界での起業・創業につきまとめました。
IT業の会社設立・起業成功は創業融資が重要
IT業界は、利益率が高いという特徴がある一方で、着手から納品までの期間が長期になることが多く、
その間の外注費や人件費などの経費が先行の支払で出るため、売上代金が回収されるまで
一時的に資金が厳しくなるという特性があります。また、納品時に仕様や作業範囲等を巡りトラブルになった場合、入金が更に遅れる事も起こりえます。
起業後しばらくすれば、この問題も蓄えや、
弁護士の対応等で的確に対応できますが、
独立開業後は蓄えも不足し、ノウハウも少なく、
【 リスクに弱い状態 】になっています。
この時期に日本政策金融公庫の創業融資による資金調達をお勧めします。
日本政策金融公庫は財務省が出資する起業や
中小企業の経営を支援する金融機関であり、
特に、創業時の起業資金の融資には積極的です。
利率は2%程で1,000万を創業融資で調達しても
年20万円程です。必要なければ手をつけずにおいて
おけば良いわけで、売上確保に時間を要した場合も
5年返済なら、【時間を稼ぐ】ことが出来ます。もちろん、最初から案件があれば
利息以上に、稼げばいいというわけです。
成功する方は、このお金の使い方が上手です。大型案件で外注先を活用、無事納品まで仕上げる。
一時的に立て替え払いで支払いは出ますが、
仕切った後は、しっかりとお金が増える。
このサイクルをしっかりと回されます。

東京都や川崎市・横浜市・神奈川県の創業融資
創業融資ではこれまでの経歴と社長と事業の将来性に対して融資が行われます。
数年経営し融資を受けると決算書を基に融資が行われることになります。
創業時と数年後、借りやすいのは【 創業時 】。それは将来性を軸にプレゼンが可能だからです。

ただ創業融資はIT業の特殊性を計画書に取り込み、
融資面談で金融機関担当者に伝えないと中々成功につなげるのが難しいというのも事実です。
匠税理士事務所では、日本政策金融公庫や
各種金融機関と連携した制度融資を活用して、
起業時の資金調達でIT起業をサポートします。
東京都や川崎市・横浜市など神奈川県の創業融資で
トップクラスの実績がございます。
そして税理士の豊富な経験とノウハウの活用、
お客様のご協力で【融資実行率9割超】です。
詳細はこちらからご確認下さい。

IT業創業融資は東京都・川崎・横浜・神奈川県対応
IT業界に強い税理士による会社設立サポート
IT業界は利益率が高いため、会社設立すぐに大きな利益が出る場合も多くございます。
そのため将来の配分等でトラブルにならないよう
株主構成を社長様と一緒になって検討したり、
売上が1,000万円を超えても消費税免税になるよう
【資本金・給与設定】を慎重に行う必要があります。また、会社設立後の会計や経理の流れ作りや、
お金がたまる様な入金と出金のサイクルなど
会社設立後の初期設定がとても重要です。
匠税理士事務所では、
世界4大会計事務所を出身のIT業界に強い税理士が会社設立時の基本設計から事業が軌道に乗るまでの会計などにつき丁寧にサポート致します。
会社設立サービスはこちらよりご確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の会社設立 】

IT業会社設立は東京都・川崎・横浜・神奈川県対応
【匠税理士事務所で担当させて頂いたIT業】・アプリケーション開発
・システム開発
・ECサイトの運営
・ゲーム製作
・WEB製作
・ITサポート会社
・大手メディア配信会社
・映画製作会社
・IT広告会社 など
IT企業に必要な全てがそろう会計事務所です
経営セミナー講師の税理士がIT業を担当し
変化の早い事業を【税務・経営】両面で支援します。
残業など労務問題、就業規則や助成金申請も
社会保険労務士事務所と連携し対応します。
起業時にIT導入補助金・小規模持続化補助金
返還不要型の補助金制度を活用したい
補助金専門家の中小企業診断士が対応します。
著作権・商標権など権利・契約書など法務関係
外国人プログラマー採用のビザ取得も可能です。
【 IT業に必要な全てサポートする事務所 】です。◇ 匠税理士事務所の概要 ◇
匠税理士事務所の所属税理士や専門家は、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

匠税理士事務所のサービスラインは、
こちらからご確認をお願いします。

IT会社設立・創業融資など税理士対応エリア:東京都や川崎市・横浜市など神奈川県全域
◇サービス紹介
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇その他のサービス
→税理士変更をご検討のお客様
→個人事業主又は法人化をご検討のお客様
IT会社設立・創業融資など会計事務所の対応エリア:
東京都や川崎市・横浜市など神奈川県全域
IT業で会社設立、創業融資など起業成功の流れ
IT業で会社設立、起業して成功されている方には、【 前倒しで起業に取り組み、修正が早い 】
という特徴があります。
例えば会社を辞めて、会社設立して起業する時に、
普通であれば、
【1】 会社を辞める【2】 資金調達のため創業融資など準備をする
【3】 IT会社設立する(事業の箱を用意する)
【4】 営業を始める
【5】 売上を確保していき、軌道にのせる
という流れとなります。
一方で起業して成功する方の場合には、
【1】 資金調達のため創業融資などの準備をする
【2】 IT会社設立する(事業の箱を用意する)
【3】 営業を始める
【4】 会社を辞める【5】 売上を確保していき、軌道にのせる
このような流れとなります。
もちろん、在籍している会社の就業規則によりできることは一部制約があるかもしれませんが、
成功される後者の場合には、会社を辞めるまでに、大体の場合、準備が完了しています。例えば、創業融資はどこで、いくら程借りれるか?その必要書類の準備が済んでおり、
会社設立後にはどれくらい売上が立ちそうか等が、会社を辞める前にすでに分かっています。
ある程度借りれそうなら、社員を最初から雇って、オフィスを借りるという攻めの戦略を採用します。
逆に想定より借りれないなら、最初は必要最小限。最悪、起業時期を延ばす修正をかけます。
だから、成功の確率が上がります。 【 会社設立から起業して事業開始までの流れ 】
【 会社設立から起業して事業開始までの流れ 】
例えば、現在会社に勤務され、【5月起業を考え、8/10退職、9月から稼働 】を例に説明します。
⓵ 5月に税理士と打ち合わせ
会社名、本店の場所、資本金など新会社の設計決定
【 → 同時に創業計画書作成と必要資料用意 】
② 1週間程で司法書士にて⓵の設計書で登記手続
③ 登記申請から2~3週間で謄本入手
④ 【 謄本入手と同時に創業融資の申込 】と銀行口座の開設・税務署等の届出書
⑤ 勤務先の退社後に社会保険の変更手続
→ 2~3週間で新設法人の保険証入手
⑥ ⑤の後、すぐに事業開始
IT業での独立開業して開始までのスケジュールは、上記の流れとなります。
何だか自分で全てやると頭が痛くなりそうですが、専門家チームを活用すると、
1時間半打ち合わせに参加して、社名など最低限の事を決めて頂ければ、後はお任せとなります。このスケジュールを表にしますと下記になります。
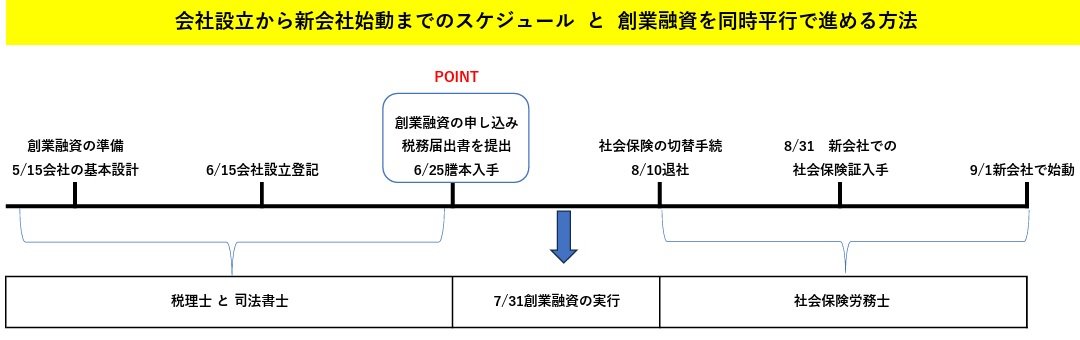
(官公庁の混雑具合で、多少前後します。また下記表は余裕をもったスケジュールになっています。)
このように起業成功に、前倒しの準備は重要です。
この準備の中でも、お金の用意は特に重要です。具体的に、上記スケジュール表では、設立登記前に創業計画書等を作成、
会社設立登記が完了後すぐ創業融資を申込むという会社設立・創業融資の同時進行がポイントです。当然ですが、早めに申し込めば早めに融資の金額がどれだけになるのか分かります。
そしてこの融資金額が早くわかることで、ビジネスの拡大・縮小の判断が迅速に行えます。
このスピード感が独立開業の成功に重要なのです。
IT事業に関する経営・会社設立・起業情報
IT業界特有論点を中心に税務会計・起業等に
関するお役立ち情報を掲載しております。
it関連情報・会社設立情報は更新しております。
◇IT経営・会社設立ノウハウ記事
IT関連事業の経営者に向け税務経営情報を更新中。
・デザイナーやコーディング(コーダー)などIT業の源泉所得税の計算方法・納付書の書き方
・アプリケーション開発など市場販売目的ソフトウエアのIT税務
ITに強い税理士による会社設立をご検討中の方は、匠税理士事務所にご相談下さい。
IT会社設立・創業融資など税理士対応エリア:東京都や川崎市・横浜市など神奈川県全域
免責事項
掲載情報に基づいて利用者が下した判断および起こした行動によりいかなる結果が発生した場合においても、匠税理士事務所はその責を負いません。 また、当サイト内のコンテンツは法令に改正が入った際などにおいても、最新の法令への変更は行いません。当サイトのコンテンツの情報を利用し起こりうる損害その他一切の影響や利用者の皆様に発生する損害について、匠税理士事務所はその責を負いませんのであらかじめご了承ください。
執筆者・文責:税理士 水野智史
起業時の自己資金はどのくらいまで用意すべきか (15/01/30)
『 将来的に起業をしたいと考えている方にとって、
自己資金をどれくらいまで用意するべきか。 』
これは現在勤務している会社を
辞める時期にもかかわりますので大きな問題です。
そこで今回は、起業時の自己資金について
どれ位まで用意した方がよいのかをまとめてみました。
必要資金のうち、外部からどれだけ調達できるかがポイント
自己資金をどれくらいまで用意するべきか = 必要資金のうち外部からいからまで調達できるか
このように読みかえることで、
自己資金が幾ら必要になるかが分かります。
起業家の資金調達は、
大きく分けて行政機関を活用した制度融資と、
日本政策金融公庫による創業融資の2つに分けられます。
このうち、行政機関を活用した制度融資は、
各行政機関によっても異なりますが、
自己資金と同額までが融資対象になります。
つまり必要資金の半分は自己資金で用意する必要が出てきます。
(関連記事:制度融資とは?目黒区や世田谷区、品川区の融資制度)
一方の日本政策金融公庫による創業融資では、
自己資金の2倍が融資の限度となりますので、
必要資金の1/3は自己資金で用意する必要が出てきます。
それでは自己資金は幾ら必要になるのでしょうか
融資の制度によって上限が異なるものの、
起業後の立ち上がりには少し時間がかかるのが一般的ですので、
やはり最低必要資金の半分は用意したいところです。
自己資金をできるだけ多く用意できれば、
それだけ金融機関にいかに自分が起業に本気であるのかを
アピールすることが可能になります。
『起業成功のためには、自己資金をしっかりと用意すること』
この地道な努力が重要です。
起業時の資金調達支援サービス
匠税理士事務所では、起業支援に力を入れております。
そのため起業されるお客様に必要なサービスは全てご用意しております。
【資金調達支援】
各種行政機関の制度融資や日本政策金融公庫の創業融資など
起業時の資金調達支援に力を入れております。
サービスの詳細はこちらよりご確認下さい。
目黒区や品川区、世田谷区など23区での創業融資や起業の資金調達
【経理や給与計算、経営支援】
その他の会社設立の代行や起業の経理・経営支援サービスは
こちらからご確認下さい。
最終更新日:平成27年1月30日
起業支援以外の匠税理士事務所サービスや
事務所情報は、こちらよりご確認下さい。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
建設業や建築業の情報館 バックナンバー② 経営支援専門の会計事務所 (15/01/23)
匠税理士事務所では、経営サポート・経営支援に力を入れております。
利益とお金を残して会社を元気にする独自のサービスラインを用意しております。

【 このようなご希望やお悩みはございませんか 】
・会社を伸ばして行きたいので、経営の相談相手を探している。
・利益やキャッシュの視点から会社の課題を知りたい。
・目標利益を出したい。
・キャッシュが安定した経営をしたい。
このようなご希望のある会社様は、ご相談下さい。
◇サービスページ
◇法人のお客様
◇個人のお客様
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇建設業の許可申請
建設業や建築業の経営お役立ち情報TOPICS 目次

これまでのノウハウを活用した建設業や建築業の経営情報をまとめております。お役に立てば幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
◇バックナンバー①はこちらです。
→ ...2024年から建設業界・建築業界でも残業時間規制がかかるなど人手不足の問題はより深刻化することが予想されます。
→ 1件請負金額が500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の大規模案件受注が可能になることです。...
→ 時間外労働の上限規制に備えるためにも業務効率の見直しや人材の配置などの改善など対策が必要になります。...
→ 国土交通省が建設キャリアアップシステム・CCUS制度を始めてます。...
→ ...
経営を取り巻く様々な問題に対応できるように、人事労務の専門家や、法務の専門家など経営に関連する幅広いニーズにお応えできる体制をご用意しております。提携先の専門家や事務所の詳細につきましては、下記よりご確認をお願いします。今後もお客様の満足度向上のため、優れた提携先やスタッフを追加していく予定です。
◇会社概要はこちら→自由が丘の匠税理士事務所と提携先の紹介
上記以外の事務所情報・アクセスなどは、下記よりTOPページへ移動の上、ご確認をお願いします。
◇TOPページはこちら→世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所
創業計画書はどんな書類が必要?その書き方は (15/01/09)
・創業計画書にはどんな書類が必要でしょうか?
・計画書の書き方を教えて下さい。
このようなご相談を起業セミナーなどで
受講者の方から頂くことがあります。
そこで今回は、創業計画書はどんな書類が必要なのか
またその書き方のポイントについてまとめてみました。
創業計画書にはどんな書類が必要?
起業の資金調達では、
大きく分けて制度融資と日本政策金融公庫による創業融資の二つがあることは以前記載しました。
(関連記事:制度融資はどの銀行がいい?日本政策金融公庫の創業融資との違い)
この制度融資と日本政策金融公庫の創業融資では、
創業計画書のテンプレートが異なるのですが、
多少の形式が変わっても、ポイントは同じです。
融資成功を分けるのは、
【 借りたお金を利益からしっかりと返すことを証明できるか 】 ということです。
つまり必ず利益を上げられるか → 売上を確保できるか という構図になります。
ですので、頭で考えた数字だけの
理屈くさい創業計画書が求められるのではなく、
見積書や受注書など売上の数字の根拠がしっかりとある
現実的な創業計画書が重要になります。
これらの書類で具体的な得意先や売上を説明出来れば、
金融機関などの融資担当者は、
稟議書で上司に説明もしやすくなり、
融資成功につながりやすくなります。
これは、貸す側の気持ちになると分かりますが、
『 論より証拠 』 ということですね。
というわけで、
創業計画書はその書類そのものと同じ位、
売上に関する見積書など根拠書類が重要になります。
創業計画書はどうやって書くのか?
創業計画書は、起業をしなければまず書くことがない書類です。
そのため慣れていないので当たり前です。
しかし、融資のチャンスは数少ないため、
重要な書類でもあります。
そこで創業計画書の書き方について記載してみました。
詳細はこちらよりご確認下さい。
匠税理士事務所の創業支援サービス
匠税理士事務所では、
起業時の資金調達支援に力を入れております。
サービスの詳細はこちらから
会社設立やその後の経理や経営支援についてはこちらからご確認下さい。
匠税理士事務所の起業支援サービスの特徴
事務所スタッフや提携先などのサービス以外の情報は
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所TOPへ移動の上、
ご確認をお願いします。
最終更新日:平成27年1月9日
独立開業や起業のための借入や資金調達はいつ行うべきか (15/01/02)
独立開業や起業のために必要な資金を
何とか自分で用意することが出来たので、
とりあえず自己資金で始めてみよう。
このように考えられて起業をされる方も多いと思います。
そこで今回は、独立開業や起業をされる方に向けて
借入や資金調達について起業時に検討する重要性について説明したいと思います。
独立開業や起業のための借入や資金調達のタイミングはいつがいいか?
独立開業や起業をされた際に、成功を考えてスタートしたものの、
中々軌道に乗らず、最初は苦労するということがあります。
そのような際に自己資金が減ってしまい、
お金が厳しいので融資を検討するという流れになると、
金融機関は、赤字の事業に融資を積極的に行いませんので、
資金調達は難しくなってしまいます。
起業してすぐに借入や資金調達を検討するメリット
上記に対して、起業してすぐに借入や資金調達を検討するメリットは、
今後の事業の展望は、
事業計画書でしっかりと説明をすれることができれば、
実際の事業の実績は問われません。
また、自己資金も豊富な状態での申し込みになるので、
金融機関の融資の際には成功率は高まることが多いです。
また金利も年間1~2%程ですので、
損益には大きな影響がなく、
事業が軌道に乗って不要であれば、
返済してしまうという選択肢もあがります。
匠税理士事務所の創業融資・資金調達支援サービス
匠税理士事務所では、
起業時の資金調達を支援し、起業の成功をお手伝いするために、
日本政策金融公庫や各行政機関の制度融資に対応する金融機関と連携して
創業融資・資金調達サービスを提供しております。
匠税理士事務所の起業支援サービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。
目黒や品川、世田谷など23区の創業融資や起業の資金調達 はこちら
最終更新日:平成27年1月2日
その他の匠税理士事務所の事務所概要や料金などは
下記よりご確認をお願いします。
世田谷区 税理士 のHPTOPへ
運転資金とは何か、設備資金との違い (14/12/26)
これから起業をお考えの方で、
起業時に融資を検討される方も多いと思います。
日本政策金融公庫や金融機関からの借り入れでは、
その使い途として、主に設備資金と運転資金に分けられます。
それではこれらの設備資金と運転資金、
どのような内容で、融資ではどのように扱われるのでしょうか?
設備資金とは何か、設備資金目的の融資
設備資金とは、事務所の保証金や内装工事代金、PCやデスクなどを
購入するために必要な資金をいいます。
設備資金は、その内訳が分かる見積書などを用いて、
何に幾ら必要なのか融資担当者に説明することが容易なので、
運転資金と比較して、融資を受けやすい傾向があり、
返済期間も運転資金と比較して長期間の借入となる場合が多いです。
運転資金とは何か、運転資金目的の融資
運転資金とは、設備資金以外の資金をいいます。
つまり、人件費や家賃、電気代など会社を維持するための資金です。
運転資金は、設備資金と異なり、
資金の使い途の根拠資料となる見積書がないので、
融資では設備資金に比べて、厳しく審査され、
返済期間も比較的短期間になりがちです。
【参考】
実際の融資制度をご覧頂くと、返済期間の長短が明らかです。
目黒区や世田谷区、品川区の制度融資 を実際に見てみる
設備資金と運転資金、どちらで借りた方が有利なのか?
結論から言えば、
 設備資金を創業融資で調達し、
設備資金を創業融資で調達し、
自己資金は運転資金に充てるのが効果的です。
したがって、事務所の保証金や内装費など
比較的金額が大きくなりがちで、
見積書など使い途をしっかり証明できる場合は、
設備資金で融資を申し込み、
自己資金は運転資金に充てるいう方法が効果的です。
匠税理士事務所の創業融資・起業支援サービス
匠税理士事務所では、
起業支援に力をいれており、
これまで数多くの創業融資や資金調達を支援してきました。
創業計画書の作成や、創業融資についてお悩みの方は、
お気軽にご相談下さい。
創業融資支援サービスはこちらから
最終更新日:平成26年12月26日
その他のサービスラインや事務所情報は、
下記よりTOPページにてご確認をお願いします。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
会社設立・法人設立後の銀行口座開設はどの銀行がいい? (14/12/19)
会社設立・法人設立をされた後、すぐに行うべきことの一つに銀行口座の開設があります。
この銀行口座の開設は、今後の会社経営においてはとても重要です。
そこで今回は、会社設立・法人設立した場合に 「どの銀行に口座開設すればよいのか」 について簡単にまとめてみました。
会社設立・法人設立後の口座開設は、今後の事業運営に合わせて決めること
銀行での口座開設に臨む前に、今後自分はどのような事業を行っていくのかを、考えてみます。
金融機関ごとの強みが、自社にとって最も機能するような選択を行うことが大切です。
それでは、金融機関ごとの特徴として、どのようなものがあるのでしょうか。
口座開設する前に知っておくべき、銀行など金融機関ごとの特徴
1 メガバンクなどの都市銀行
東京三菱UFJやみずほ銀行、三井住友銀行などメガバンクの強みは、スケールメリット、事業規模です。
法人であれば、移転することもありますので支店がどこにでもあるということのメリットはとても大きいです。
日本全国はもとより、海外にまで対応できるところも大きな強みとなります。
高額な融資にも対応できることも強みとなります。
ただ、リスクを避け、保守的なところがあるため、法人口座開設の審査が厳しく時間がかかります。
また、融資には、企業規模や実績が求められ、創業時の融資にはあまり積極的ではありません。
2 信用金庫
地域密着型のため、都市銀行のようなスケールメリットはないものの、
面倒見がよく、融資にも積極的で、会社の経営状況に応じて、経営状況の悪いときにも経営者の相談に応じてくれることが多いという特徴があります。
設立間もない会社や小規模な会社にも親身に相談に乗ってくれるのも良い点です。
ただしスケールメリットが得られにくいため特定の地域以外にも会社の規模を広げる場合、最寄りに支店がないなども支障が出てくるため法人口座として信用金庫を選ぶ際には注意が必要です。
3 ゆうちょ銀行
郵便局の店舗を活用した広い支店網が魅力となります。
ただ融資はほとんどやっていないのがデメリットです。
4 ネット銀行
手数料の安さが最大のメリットです。
しかし店舗がほとんどなく、銀行に窓口等での対面による相談ができないのがデメリットになります。
大手銀行と組み合わせると便利に活用できます。
会社を作ったら、最低2つの銀行口座を作ることをお勧めします。
会社設立を行い、会社を経営されていると、
1 売上を伸ばしていくことと、
2 資金を調達していくことが必要となります。
そのため、
1 自社の事業で売上を伸ばしていくには、
どの銀行で口座を開設した方がよいのかという判断が求めらます。
全国展開の店舗なら大手銀行、地域展開限定であれば都市銀行や信用金庫、ネットショップならネット銀行、ゆうちょ銀行といったイメージです。
2 資金を調達していくには、
創業間もない頃は、信用金庫がお勧めです。
もちろん、信用金庫の融資以外にも資金調達の方法はありますが、選択肢が増えるという点では、やはり信用金庫で口座開設を行っておくのがよいのではないでしょうか。
匠税理士事務所の会社設立などの起業支援サービス
匠税理士事務所では、2008年に事務所を設立してから一貫して、起業支援に専門特化してきました。
会社設立や創業融資など起業に関する幅広いご相談にお応えできる万全な体制をご用意しております。法人の口座開設や創業融資などで提携金融機関を紹介することも可能ですので、お気軽にご相談下さい。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス
→ 世田谷区や目黒区、品川区での創業融資支援サービス

◇会社設立サービス
→ 世田谷区や品川区など東京都での会社設立の代行サービス
◇法人化・法人成りサービス
最終更新日:平成26年12月19日
制度融資とは?目黒区や世田谷区、品川区の融資制度 (14/12/12)
創業時の資金調達のための借入として、
大きく分けて日本政策金融公庫による創業融資と、
都道府県や市区町村などの自治体が主体となる制度融資がございます。
今回は制度融資のうち、目黒区と世田谷区の制度融資をご紹介致します。
なお平成26年12月時点の情報ですので、
最新の情報につきましては各行政機関にてご確認下さい。
目黒区の制度融資:中小企業創業支援資金融資
(創業融資)
運転資金・設備資金として1,000万円
(返済期間)
運転資金7年(据置1年を含む)
設備資金 9年(据置1年を含む)
目黒区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置いて
中小企業を初めて創業しようとする事業者(創業後1年未満を含む)を対象とした融資です。
(融資要件)
次の1.又は2.に該当し、3.及び4.の要件を満たすこと

1. 融資申込時に事業を営んでおらず、
融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、
個人は2か月以内、法人は3か月以内に創業できること
(設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む)
2. 融資申込時に事業を営んでいるが、
事業開始(売上発生等客観的に事業開始が確認できる日)から
1年未満であること
ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること
3. 原則として事業に必要な許認可を受けていること
4. 住民税を滞納していないこと
世田谷区の制度融資:創業支援資金
(創業融資)
運転資金・設備資金 2000万円以内
(返済期間)
7年以内(据置期間12ヶ月を含む)
(融資要件)
次の(1)~(6)の要件を満たしている方。
1当初より世田谷区内に主たる事業所(法人の場合は主たる事業所及び本店登記所在地)を設け、
創業すること。あるいは、世田谷区内で創業後1年未満であること。
※主たる事業所とは、売上高が半数以上を占める事業所のことです。
※本店登記と事務所が区内にあっても、
売上を生ずる主たる事業所の実体が区外にある場合は対象になりません。
※事業実態の確認のため、事業所の訪問を行い、あっせんの可否を決定する場合があります。
※1年以内に区外で創業した後に世田谷区内に移転した場合は対象になりません。
2東京信用保証協会の保証対象業種で創業すること。
3申込日までに申込者が、
申告・納付すべき特別区(市町村)民税及び事業税★を完納していること。
★個人事業主は個人事業税、法人は法人都民税・法人事業税。
4過去2年以内に、法人・個人を問わず事業主の経験がないこと。
※課税証明書・納税証明書等に事業収入・不動産収入・営業収入等が計上される方は、
ご利用できません。
5借入希望額に見合った自己資金があること。
※自己資金とは、自分で完全に処分可能な現金・預金等のうち、
創業のために利用する資金をいいます。
親族や友人等からの借入金は、返済を予定するかぎり自己資金には該当しません。
6既に支払い済みの代金を区の融資で充当するものではないこと(既に支払い済みの購入代金は、
区の融資対象から除きます)。
品川区の制度融資:創業支援資金
(創業融資)
運転資金 1,000万円まで
設備資金(運転資金の併用) 1,500万円まで
(返済期間)
運転資金 7年以内 (据置期間12ヶ月を含む)
設備資金 10年以内(据置期間12ヶ月を含む)
(申込対象者)
A 品川区で中小企業を創業しようとする方で、他の企業の代表者でない方
B 企業の代表者で、当該企業の他に品川区に中小企業を創業しようとする方
C 品川区内に創業して5年以内の中小企業者
制度融資や日本政策金融公庫による創業融資・資金調達を支援してます
制度融資を活用するには、
各市区町村によってその内容も上記のように大きく変わりますので、
地域ごとの内容を理解していることも重要です。
匠税理士事務所では、
これまで世田谷区・目黒区・品川区などを中心に
数多くの起業支援の一環として、
制度融資や日本政策金融公庫による資金調達を支援してきました。
制度融資や日本政策金融公庫などを活用したサービスラインにつきましては、
下記よりご確認をお願いします。
その他匠税理士事務所の起業支援サービス一覧とその特徴については、
こちらよりご確認をお願いします。
ご希望の方には、
制度融資に対応している金融機関のご紹介も行っております。
お気軽にご相談下さい。
最終更新日:平成26年12月26日
その他の事務所情報につきましては、
下記よりTOPからご確認をお願いします。
税理士 東京都 の匠税理士事務所HPへ
利益とお金を残して会社を元気にしたい経営者の方へ (14/11/30)
匠税理士事務所では、
利益とお金を残して会社を元気にしたい経営者の方を支援しております。
利益を残したい経営者を支援する利益戦略会議
【お客様の黒字率100%を目標にしております。】
そのため、利益を残すことを出来る限り、
シンプルに分かりやすく説明することで、
利益を残すためには、
経営者の方に何が求められていて
どのように行動することが必要なのかを分かりやすく
毎月のミーティングで話合います。
・会社の課題を明らかにしたい。
・一緒になって会社の経営を
考える参謀・パートナーを探している
・会社を良くしたい。
このような方に最適なサービスラインです。
詳細はこちらから
お金を残すためにはどうすれば良いか、そんな経営者をお手伝いします。
【 儲かっているはずなのに、お金がない・・・ 】
会社を経営されていると、
こんな不思議なことが普通に起きてきます。
そこで匠税理士事務所では、
お金をしっかりと残すためには、
お客様の会社のどこに問題があるのかについて、
キャッシュフロー・キャッシュストックの考え方を軸にした
独自のサービスラインをご用意しております。
詳細はこちらよりご確認下さい。
匠税理士事務所では、
利益をお金をお客様の会社に残すことをお手伝いすることで、
お客様の会社の発展をお手伝いしております。
上記サービスライン以外のサービスや事務所の情報につきましては、
下記よりトップページにてご確認をお願いします。
起業・黒字戦略の匠税理士事務所|世田谷区や目黒区 品川区の税理士
最終更新日:平成26年11月30日
税理士事務所・会計事務所経験者のパートスタッフ・アルバイトスタッフ募集中 (14/11/21)
匠税理士事務所では、
税理士事務所・会計事務所での勤務経験者で、
パートスタッフ・アルバイトスタッフとして勤務して頂ける方を募集しております。
パートスタッフ・アルバイトスタッフ募集・採用要項
今回のパートスタッフ・アルバイトスタッフの募集・採用要項としましては、
現在のスタッフとのバランスを加味して40歳までの女性の方で、
税理士事務所での勤務経験が3年以上の方を募集しております。
内部での会計処理業務がメインとなり、
 外部業務は一切ございません。
外部業務は一切ございません。
勤務時間につきましても、
ご要望に出来る限り沿いたいと考えておりますので、
ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
(お子様がいらっしゃるなどのため、週3日で
9時から15時の勤務もご相談下さい。)
求人・採用に関する詳細な情報はこちらから
匠税理士事務所の事務所概要
弊所は全スタッフが30代の若くて、元気のある事務所です。
明るい雰囲気で、全員で助け合うことを大切にしております。
残業は一切ございません。
定時で集中して働きたいという方に向いている事務所です。
事務所の概要はこちらよりご確認下さい。
→ 自由が丘の匠税理士事務所 概要
税理士試験を受験中の方へ
税理士試験受験中の方は、
支援するためのこちらの勤務制度も御検討下さい。
その他のサービスラインなど各種情報につきましては、
目黒 税理士 匠税理士事務所TOPへ移動の上、ご確認をお願いします。
最終更新日:平成26年11月21日
中小企業の資金調達の方法とは (14/09/04)

経営者にとって、資金調達はとても大切な仕事の一つです。
資金調達には、様々な方法があります。
このうち、中小企業の資金調達として挙げられる方法・各方法の注意点などについてまとめております。
少しでもお役にたてれば幸いです。
中小企業の資金調達とは?
中小企業は、上場企業と異なり株式の発行による資金の調達や、社債の発行による資金の調達といった手段は、現実的にはほとんど使用することができません。
それでは、中小企業が資金調達をする方法としてどのような方法があるでしょうか。
銀行からの借り入れ
いわゆる融資です。もっとも現実的な手段です。
金融機関(保証協会)は、資金を借り入れる理由が合理的であるかどうか、貸した資金をきちんと返済できるかどうかなどその会社の業績やお金の流れ・管理方法がどのようになっているかの企業実態を調査し融資をするか否かを決定します。
会社の業績が早期の段階で正しくできており、資金計画に基づいて不足資金や不足時期をきちんと示すことが大切です。
また借りた資金をどのように使用して、どう返済するのかを示すため事業計画書の作成も大切となります。
金融機関に、お金に関して、しっかりとした会社と理解していただくためにも業績・資金管理・事業計画が重要です。
ノンバンクなどからの融資
高金利であるため経営を圧迫するケースがあるため、金利に注意を払う必要があります。
返済期間が短期間であり、借りては、返すといったことを繰り返す傾向があるため手軽という理由での借り入れには注意が必要です。
スピードや審査にはメリットがありますが、事業用資金としては少額で、ケースによっては銀行融資の審査に影響がある可能性もあります。
「ノンバンク」とは、その名の通り「バンク(銀行)」ではない金融機関を指します。
消費者金融、クレジットカード会社、信販会社、事業金融会社、リース会社 等が具体例です。
これに対し金融機関とは、銀行や信用金庫、信用組合をいいます。
補助金・助成金による資金調達
補助金の目的にそった事業を行い、一定の申請書などを提出することにより資金を調達する方法です。
補助金も助成金も"国や地方公共団体から事業者に対して支給されるお金"で、原則返済不要です。
補助金は、経済産業省管轄、一般的にはモノに対する補助で、1事業者に支払われる金額が大きいですが、助成金よりも審査が厳しいです。
助成金=厚生労働省管轄でヒトに対する助成がメインです。
補助金目的の事業が終了し、その後に入金がされるため、予定していた補助金が通らないと、ビジネスが破綻してしまうことがある点の注意が必要です。
製造業や特殊な技術開発、産学連携に向いた資金調達方法です。
◇サービス
投資家やベンチャーキャピタルからの資金調達
会社のビジネスモデルなどに賛同する企業やファンドなどから資金を調達する方法です。
出資の割合によっては、投資家やベンチャーキャピタルが経営に参画してくる可能性がでてくるため注意が必要です。
資金を注入してもらった後に会社が大きく儲かった際に、投資分の買い戻しがどうなるかなども重要なポイントです。
銀行融資との違いは、銀行からの融資は「借入」のため返済義務が生じ、ベンチャーキャピタルからの出資は「資本」のため、返済義務は発生しません。
ベンチャーキャピタルからの出資を受けることと引き換えに、自社の株を譲渡するケースが多く、経営における発言権や議決権に影響が出る可能性があります。
また、ベンチャーキャピタルは、リターンを求めるため、成果が出せない場合は、投資から撤退することもあります。
役員からの資金の投入
最後に、緊急時の資金調達として、役員からの資金の投入があります。
経営者は、会社が好調なときほど、会社の緊急時に備えて、会社・役員個人共に緊急時の資金を貯蓄しておくことが重要です。
そのうえで、資金計画に基づいて資金が不足する時期を早期に発見し、資金調達を行うことが大切となります。
資金調達の中には、好ましくないものもあり、長い目で見ると会社の経営を余計に危うくするものもございます。
資金調達の際には慎重に吟味しましょう。
匠税理士事務所のキャッシュストック経営のためのサービス
匠税理士事務所は、税務や会計だけではなく、財務や経営といった中小企業の経営を支援するサービスを展開しております。経営強化に取り組む中小企業様は、ご相談ください。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
建設業や建築業の経営お役立ち情報館 バックナンバー (14/08/30)
匠税理士事務所は、建設業や建築業の経営支援に強い会計事務所です。
こちらは、建設業や建築業の経営についてまとめたもののバックナンバーとなります。
◇サービスページ
◇法人のお客様
◇個人のお客様
◇相談会
建設業や建築業で独立・開業をお考えの方に向けた相談会を開催しております。
◇建設業の許可申請
建設業や建築業の経営お役立ち情報TOPICS 目次

これまでのノウハウを活用した建設業や建築業の経営情報をまとめております。お役に立てば幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
◇バックナンバー②はこちらです。
→ 材料の確保には、お金が必要ですし、人材の確保は更に難しく、お金と働きやすい環境が必要です。...
→ 税務調査で対象とされやすい10種類の事業のうち3事業があがっています。...
→ 建設業・建築業の粗利率(売上総利益率)の平均は、概ね20%です。...
→ 建設業や建築業のお客様の最大の悩みは資金繰りがもっとも多い...
→ 入札の形式で一番多いのは、やはり一般競争入札です。...
→ 入札には大きく分けて、一般競争と指名競争があります。...
→ 入札に参加しようとする建設業者は、それぞれの許可業種に応じて経審を受けなくては...
→ 建設業や建築業の源泉所得税の計算方法・納付に関係しそうなのは、...
→ 事業的に成功してくると、特定建設業許可が視野に入ってきます。...
→ 営業利益(本業の利益)の最大化に最も重要な要素である請負金額・受注額など売価の最大化について...
◇TOPページはこちら→世田谷区や目黒区 品川区の税理士は起業・黒字戦略の匠税理士事務所
営業キャッシュフローを確保し、フリーキャッシュフローを生み出す (14/08/23)
会社を経営されていく上で、利益と同様に注意すべき項目として資金、
すなわちキャッシュフローが挙げられます。
資産や負債の状況を表すのが貸借対照表、売上や原価・利益を表すのが損益計算書です。
キャッシュ・フロー計算書は、どのような理由でどれだけのお金が入ってきたのか
のような理由でどれだけのお金が出ていったのかを表したものです。
キャッシュ・フロー計算書は、現金の流れを把握することができます。
会社を経営されている方で、資金繰り表を作成されている会社は多いと思います。しかしキャッシュフロー計算書を作成されている会社は、まだまだ少ないのが現状です。
キャッシュフロー計算書とは
「キャッシュフロー計算書は、何故重要か?」
「キャッシュフロー計算書とは、何なのか?」
一言で表現すると、キャッシュフロー計算書は、会社のお金の流れを理解し、
何故お金が増減したのかを理解するために重要であるといえます。
このキャッシュフロー計算書を駆使することで、
キャッシュフローが良くなるようには、どうすれば良いか考える習慣がつき、
債権の回収速度や支払のタイミング、在庫の調整などに気を付け、お金が残りやすい会社を作ることが可能になります。
損益計算書上で利益が出ていても、実際にキャッシュが同額増加しているかというと利益=お金とはならないのが経営の難しさです。
資産と負債のバランス良し、利益のバランス良しの視点にキャッシュフロー(お金の流れよし)の視点を加えなければなりません。
そのために必要なのがキャッシュフロー計算書です。
ここでは、キャッシュフロー計算書の読み方ではなく、どんなことに気を付けて経営していればキャッシュフローが良くなるかを説明致します。
営業キャッシュフロー・フリーキャッシュフローの重要性
このキャッシュフローの中でも営業キャッシュフローは特に重要です。
営業キャッシュフローがプラスであることは、すなわち本業から資金を増やせていることを意味します。
逆にこれがマイナスだと、本業で資金を減らしてしまっていることになります。
キャッシュフローを経営に取り入れてみたい場合には、まず営業キャッシュフローから始めてみることをおすすめします。
営業キャッシュフローの改善の打ち手
→売上代金は、できるだけ早期回収できるよう取引のスタート時によくよく検討すべきです。
新規の取引先には、早期回収が可能な契約条件を提示する
既存の取引先には、前金、中間金、最終金など設定し、回収条件の見直しを交渉するなどの働きかけが大切です。
売上代金の未回収分とならないよう大きな受注の時こそ、回収を一番に考えた取引をすべきです。
赤字は、当然キャシュが減ります。
赤字は絶対にいけません。
利益を増やすには、売上の増加、粗利率の向上、原価のメス入れが重要です。
在庫は、お金が寝た状態となり、材料や商品のロスや廃棄の原因となります。
適正在庫を持つようにし、多少高くても、在庫を作らない仕入れも大切です。
仕入れや外注費の支払いは、少しだけ先延ばしにすると、キャッシュ・フローの改善につながります。
少なくても売上代金を回収してから、仕入代金を支払わなければなりません。
この交渉ができない会社様とは、資金的に余裕がないとお付き合いが難しいため、上限金額を設定してお取り引きしなければなりません。
このようにして営業活動によるキャッシュフローがプラスで、この営業活動により得たキャッシュフローより
事業のために投資にまわしたキャッシュフローを差し引いたフリーキャッシュフローが、プラスであれば、
自由に使える資金があり、借入金の返済や預金増やすことができるので、
営業活動によるキャッシュフロー・フリーキャッシュフローは多ければ多いほど資金的には楽になります。
キャッシュフロー経営を行うことで、強い会社を作る
キャッシュフローを重んじる経営を行われている会社は、つぶれにくい強い体質になります。
それは、赤字でも会社はつぶれませんが、お金が無くなれば会社はつぶれます。
キャッシュフロー計算書を重視した経営を行えば、必然的にキャッシュフローは、良くなっていきますので、つぶれにくい体質になっていきます。
経営者は会社の利益とともに、会社のキャッシュフローにも、絶えず注意を払わなければなりません。
匠税理士事務所では、キャッシュフローをコンサルティングに取り込むことで、
会社の経営に、【 利益 と キャッシュフロー】 の視点を持って頂けるようにサポートしております。
キャッシュフローを支援に取り入れたコンサルティング
匠税理士事務所では、キャッシュフロー経営を支援するため、様々資料を活用したコンサルティングを行っております。
このようにお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
会計事務のアルバイト・パートスタッフさんを募集しています。 (14/08/08)
匠税理士事務所では、
会計事務に関する業務のお手伝いをしていただける
アルバイト・パートスタッフさんを募集しております。
アルバイト・パートスタッフさんに関する募集要項
今回の会計事務のアルバイト・パートスタッフさんの募集では、
以下の2つの形式の募集となっております。
・税理士試験を受験されている方で、社会人経験のある方を対象とした募集
→ 税理士事務所や会計事務所のアルバイト・パートスタッフの求人・採用情報
・税理士事務所での勤務経験がある方を対象とした募集
→ パート・アルバイト求人・採用 (会計事務所での総務スタッフ)

詳細につきましては
上記のリンクからご確認を頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所までのアクセスや所属税理士について
弊所は、自由が丘駅より徒歩2分の場所にある会計事務所で、
30代の若手を中心とした事務所です。
一緒になって成長して頂ける方からの募集を
スタッフ一同、心よりお待ちしております。
匠税理士事務所までのアクセスや所属税理士に関する詳細は、
下記のリンクよりご確認を頂けましたら幸いです。
採用担当:水野
その他の事務所に関する情報につきましては、
下記よりTOPページへ移動の上で、ご確認をお願いします。
最終更新日:平成26年8月8日
財務分析を通じた会社の課題把握と解決支援 (14/08/02)
匠税理士事務所では、
財務分析を通じて、会社の経営を支援しております。
財務分析は、このような場合に効果的です。
・会社の規模が大きくなってきて、会社の状況を正確につかむことが難しくなってきた。
・メーカーなど複雑な事業を経営しており、会社の状況をつかみにくい。
・会社を承継したばかりで、会社の状況や課題をつかみたい。
資金面など安全性に対する財務分析の効果
財務分析を実施することで、
売掛債権・仕入債務・在庫の課題が浮き彫りになってくるため、
会社の資金面での安全性を保つためには、
どの課題に、どのようにアプローチすべきかが
明らかになってきます。
それと同時に、
会社のお金の増減のこれまでの経緯を
キャッシュフロー計算書を通じて解析し、
お金が増減したのは、
どのような理由なのかを把握するとともに、
お金が残りやすい会社になるには、
どうすればよいのかを検討します。
利益面など収益性に対する財務分析の効果
次に、会社の収益面・利益面での
財務分析の効果の一つとして、
会社の売上がどのような形で、
経費に使われ、最終的に利益として残るかのプロセスの検証や、
各工程の同業他社との比較を通じて、
利益を残すには、
どこをどのように改善すべきかを検証します。
また、
赤字の会社は主にどこに手を打てば、
黒字にできるのか、
黒字の会社は、どうしたら赤字になってしまうのか
など具体的な提案を行っております。
匠税理士事務所の財務分析の特徴
匠税理士事務所の財務分析は、
分析をするのが課題ではなく、
分析した結果、
課題の把握と、解決策の提案、実行を目的としており、
そのため、より実践的な形を採用しております。
他の会計事務所をご利用の方で、
財務分析のみを利用して頂くことも可能ですので、
お気軽にご相談下さい。
財務分析のお役立ち情報
最終更新日:平成26年8月7日
財務分析以外のサービスの詳細は、
下記よりトップページからご確認下さい。
目黒区 税理士 なら匠税理士事務所TOPへ
八雲・池尻大橋近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/07/26)
匠税理士事務所HPの閲覧ありがとうございます。
弊所は、八雲・池尻大橋近くの会計事務所です。
40代の税理士が2名所属し、他の会計スタッフも
全員が30~40代の社員10名の事務所で、
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 【 起業支援と経営サポート】に定評があります。提携先の弁護士や弁理士、公認会計士も充実し、
総合力で目黒No1の会計事務所を目指してます。匠税理士事務所の税理士やサービスは
こちらでご確認をお願い致します。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】

八雲や池尻大橋の会社設立など起業支援
弊所では八雲や池尻大橋などに近い目黒区で
株式会社など会社設立される起業家の方に向け、
司法書士事務所と連携し登記手続を行います。

また、目黒区制度融資に対応可能の城南信用金庫や
西武信用金庫、メガバンクなどの金融機関や
八雲や池尻大橋などの目黒ブロックを担当する
日本政策金融公庫との連携などで
起業時の資金調達を創業融資でサポートします。
匠税理士事務所の八雲や池尻大橋など目黒区の
会社設立・起業支援サービスはこちらをご確認下さい。
八雲・池尻大橋を担当する税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

八雲や池尻大橋での株式会社・合同会社などの
会社設立手続き、会社を作った後の経理サポートや
起業支援サービスはこちらから。
【 → 目黒区での会社設立支援 】
八雲や池尻大橋の創業融資など創業支援
八雲や池尻大橋で会社設立など起業資金調達や、
創業融資支援も承っております。
創業計画書の作成や融資面談の対策や
当日の面談立会までしっかりとサポートします。
【 → 目黒区での創業融資支援 】

会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は八雲・池尻大橋など目黒全域対応です)
八雲・池尻大橋など目黒区での経営支援
当会計事務所は、八雲や池尻大橋など目黒区の
会社様に向けた経営支援サービスとして、
・会計アウトソーシング
・月次経営支援コンサルティング
・経営計画の作成と運用の支援を行っております。
これらのサービスを中心として、
お客様全社を黒字・増収増益にできるように、
日々サービスと知識の研鑽を行っております。
八雲や池尻大橋などの会社様に向けた
当会計事務所の会計や経営支援サービスは、
こちらよりご確認下さい。
会社様向けサービスはこちらをご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けた会計や経理、確定申告や
法人化などのサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
八雲・池尻大橋で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

匠税理士事務所の所属税理士の紹介
弊所では人材こそお客様へのサービスの原点と
考えております。
今後も八雲や池尻大橋など目黒エリアの会社様の
お役に立てるよう提携先や会計スタッフの充実を
目指して事務所を運営していく所存です。
所属税理士やサービス内容や料金、
会計スタッフの求人や採用情報は、
下記よりご確認をお願いします。
【 → 東京都目黒区の会計事務所の求人・採用は匠税理士事務所】
八雲や池尻大橋で税理士・会計事務所をお探しなら
目黒の匠税理士事務所へご相談下さい。
弊所ではお客様のために一生懸命になってくださる
税務会計スタッフの求人採用も行っております。
目黒地域の会計事務所への勤務をご検討中の方は
求人ページをご確認下さい。
八雲・池尻大橋の会社設立・法人化登記情報
目黒区八雲・池尻大橋で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
八雲・池尻大橋など目黒区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 渋谷出張所 】管轄区域 目黒区
〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号
(渋谷地方合同庁舎)
上記が八雲・池尻大橋で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
(八雲・やぐも)や(池尻大橋・いけじりおおはし)の
会社設立などの起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどされる方や、
会社経営者様に向けた事務所紹介につき
お読みいただきありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#八雲会社設立
#池尻会社設立
キャッシュフロー計算書と資金繰り表の作成目的の違い (14/07/20)
匠税理士事務所は、利益戦略とキャッシュストック経営のお手伝いに専門特化した会計事務所です。
【 儲かっているはず、利益が出ているはずなのに、会社にお金がない 】
このようなご相談を多くいただくことがあります。
そこで、儲かって、お金が残る会社作りに必要なキャッシュフロー(CF)についてまとめました。
資金繰り表を作っているから、キャッシュフロー計算書はいらないのでは
このようにお考えの方もいらっしゃると思いますので
両者の作成目的の違いについても記載致します。
キャッシュフロー計算書と資金繰り表の違い
★キャッシュフロー(Cash Flow)計算書
現金の流れをキャッシュフロー(cash flow)といいます。
どのような理由でいくらのお金が入ってきて、
どのような理由でいくらのお金が出ていったのかを表し
お金の流れを明らかにして、資金繰りをよくし、会社にお金が残るようにすることができます。
儲かっているのに、お金がないは、
まさに「 どのような理由でいくらのお金が出ていったのか 」お金の流れの悪い部分を見つける
キャッシュフロー計算書の守備範囲となります。
★資金繰り表
一方、資金繰り表は、目先数カ月の入金と支払いの予定表です。
一定期間先の将来にわたって、会社の資金が不足しないか検証し、
資金の先を読むための資料となります。
★両者の関係
キャッシュフロー(Cash Flow)計算書で、お金の入り<お金の支払いとなれば当然いつかは資金が不足します。
資金繰り表では、例えば向こう半年間の入金と支払いの予定表をつくるわけですが
上記「 いつかは資金が不足します 」が具体的にいつ不足するのかが分かります。
またキャッシュフロー計算書は、現状のお金の状態ですから
例えば大型案件の受注など将来については守備範囲から外れ
この将来は資金繰り表がまさに守備範囲となるわけです。
このようにキャッシュフロー計算書と資金繰り表は、お互いに補完し合うような関係にあり、
それぞれ作成することで、かなりの効果が企業にもたらされます。
◇関連記事
キャッシュフロー計算書の見方と活用方法
【 儲かっているはず、利益が出ているはずなのに、お金が会社にない 】
という会社様は、利益の視点に加えて
お金の流れを重視するという視点を加えるとよいと思います。
キャッシュフロー計算書の目的が、お金の流れを理解し、
何故お金が増減したのかを把握することを主たる目的としていますから
お金を増やす経営のためには知っておきたい知識となります。
★キャッシュフロー計算書の見方
キャッシュフローは、以下の3つの分けます。
それぞれ、どの区分に原因があり、お金が増減したのかを把握することが重要になります。
① 営業活動によるキャッシュフロー
商品やサービスを販売することにより得られた現金の動きを示した部分です。
こちらは本業によりどれだけお金が増減したかを示しますので、きわめて重要な部分です。
したがって、最も重視すべき区分となります。
◇関連記事
こちらについては過去に関連記事にまとめたものをご確認ください。
② 投資活動によるキャッシュフロー
投資活動のお金の流れを示し、
土地や建物、その他の資産の売買により生じたお金の動きを示した部分となります。
投資活動ですので、余剰資金か借入かが資金の源泉となるわけですが
投資した資金をいつまでに回収できるか・いつ換金化するかという考えを持つことが大切です。
特に注意が必要なのは、有価証券など時価が変動しやすい投資資産
土地や会員権など換金化しにくいものは、本業でお金がしっかり稼げていないと非常に危険です。
社員全員の努力の結晶ともいえる努力結果の"儲かったお金"の使い道ですので、投資は慎重に行いたいものです。
③ 財務活動によるキャッシュフロー
通常の会社様であれば、金融機関などからの融資の借り入れや返済によるお金の流れを示した部分となります。
企業が成長するためには、借り入れによる資金調達が時には必要となります。
と同時にこの資金は、返済が必要になるわけです。
大型案件の受注のための資金調達であれば、一時的にショートする資金の確保のため、不足時期を過ぎ、使用しないでおけばお金の流れは悪くなりません。
問題となるのは、借り入れをしたお金で上記投資活動を行って新規事業がうまくいかなかったケース
赤字補填資金として借り入れをしたケース
借りたお金が人件費や経費で消えてしまう、実質赤字補填資金となってしまったケース
これらの場合には、返済である財務活動によるキャッシュフローが後々重くのしかかります。
お金がある優良企業のキャッシュフローはどうなる?
優良企業は ①営業キャッシュフローがプラスです。
とにもかくにも、これが大前提です。
大切なのは、本業で現金を稼ぐ力を表す①営業キャッシュフローが、必ずプラスでなければならないということです。
ここがマイナスでは、次第に会社のお金が減少していくことになりますので、お金の流れを変える対策が必要になってきます。
( 関連記事:営業キャッシュフローを確保し、フリーキャッシュフローを生み出す! )
設備投資がない会社様は、基本的に資金繰り表のみで経営可能です。
それは上記営業活動のキャッシュフローの改善しか方法がないため、まずは本業で頑張ることが第一のため
キャッシュフロー計算書は一年に一度チェックすれば充分でしょう。
キャッシュフロー計算書による経営が必要となるのは、過去の借入金の返済がある会社様に向いています。
具体的には、設備投資資金が多く必要となる事業
大型の機械装置を入れる必要がある製造業のお客様や、大型バスや大型トラックなど運送業など初期投資が大きい会社様です。
必然的に、先に借り入れをおこし、資金の返済が後々必要となるためキャッシュフロー計算書を意識した経営が必要となります。
キャッシュフロー経営と資金繰り表の作成支援
匠税理士事務所では、キャッシュフロー経営を支援するためのコンサルティングや資金繰り表の作成をサポートしております。
このようにお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
目黒区 税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
八幡山や千歳台近く税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/07/12)
匠税理士事務所へご来訪ありがとうございます。
弊所は八幡山や千歳台など世田谷区で起業を
お考えの方や、現在事業を経営されている方に
会社設立や創業融資などの起業支援や、
経営コンサルティング・節税対策を提供する事務所です。
【人の質・サービスの質】にこだわることで、
お客様のお困りごとやニーズに対応できるよう
心掛けております。
また、世界4大会計事務所出身税理士が在籍し、 【高度な専門性・高い技術力】に定評があります。八幡山や千歳台など世田谷近くで会計事務所を
お探しなら匠税理士事務所もご検討下さい。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。

八幡山や千歳台の会社設立や起業支援
これから株式会社や合同会社などを設立し、
独立開業や起業をお考えの方に向けて
会社設立の代行など起業支援を提供します。
お客様は会社名・本店の場所のみお決め頂ければ
税理士が資本金や定款などの基本設計致します。

初回1時間ほど会社設立の打ち合わせに参加頂き
税理士・司法書士が書類を作成いたしますので、
書類をご確認頂きイメージと合っていれば
そのまま登記・会社が出来るという流れです。
お客様の一生に一度の起業が成功するように専門家がチームを編成し、起業支援します。
八幡山や千歳台担当税理士・専門家はこちら
【→起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】

八幡山や千歳台など世田谷区で株式会社や
合同会社の会社設立など起業支援はこちら
八幡山や千歳台の創業融資など創業支援
これから独立開業や起業をされる方で、
車両などの設備資金や内装工事費など初期費用を
金融機関から創業融資(借入)で調達したい方に、
創業計画書作成から融資面談立ち合いまで全て
お任せの創業融資による創業支援を提供します。
政府系日本政策金融公庫による創業融資に加え
世田谷区などの制度融資にも対応する城南信用金庫
や各種メガバンクと連携し万全の体制を用意します。
これまで【融資成功率は90%超】という業界で
トップレベルの創業支援実績がございます。
八幡山や千歳台など世田谷区で会社設立時の
創業融資詳細はこちらからご確認ください。

八幡山や千歳台で会社設立や独立開業後の
会計経理や決算・確定申告代行、節税対策から
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は八幡山や千歳台など世田谷全域対応)
八幡山や千歳台の会計経理・確定申告決算
八幡山や千歳台で会社を経営されている方には
税務会計のアウトソーシングや給与計算代行、
節税対策などの税務コンサルティングもご用意してます。
会社に利益とお金が残る仕組み作りや、
社長が本業に集中できる環境作りをサポートします。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
また、現在個人事業を営まれている方や、
自宅や投資不動産を売却された方、賃貸中の方には
確定申告の代行サービスもご用意しております。
八幡山や千歳台の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
八幡山や千歳台で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

八幡山や千歳台の補助金・助成金申請代行
八幡山や千歳台で地形をされている方で
お気軽にご相談下さい。
経験豊富な提携社労士・中小企業診断士が、
初回は無料のコンサルティングを通じて
活用・獲得ができそうな制度を提案致します。
会社設立時の助成金・補助金はこちらから
【 → 起業のお客様 サービス一覧 】
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
八幡山・千歳台近くの税理士事務所お役立ち情報
八幡山駅・千歳船橋駅には京王線・小田急線があり、
税務署にもアクセス便利です。
八幡山・千歳台で会社設立など起業した場合や、
会社経営をされている場合の税務申告書、
届出書提出先は以下になります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 税務申告書、届出書提出先 【 → 北沢税務署 】管轄区域:世田谷区のうち北部地区
〒156-8555
世田谷区松原6丁目13番10号
【 → 渋谷都税事務所 】管轄区域・渋谷区・目黒区・世田谷区
〒151-8546
渋谷区千駄ヶ谷4-3-15
東京都渋谷合同庁舎4~7階
上記が八幡山や千歳台で会社設立や法人化の届出書や
税務申告関連の書類提出先となります。
期限までに決算関連書類の提出を行いましょう。
八幡山・千歳台の法人化・会社設立の登記
八幡山・千歳台など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
八幡山や千歳台などでの法人化や法人成り、
会社設立に伴う商業法人登記に関しましては
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が八幡山や千歳台で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
八幡山や千歳台など世田谷区の方に向けた
会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成り、起業支援など
匠税理士事務所の御案内を最後までご確認頂き
ありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#八幡山税理士
#千歳台税理士
会計を活用した効果的な予算管理コンサルティング (14/07/05)
匠税理士事務所では、毎月の会計データを活用し、予算管理を行いたい経営者の方を支援するためのコンサルティングを行っております。
予算管理の重要性
会社の規模が比較的小さいうちは、前年対比で経営判断を行うのが一般的ですが、
事業規模が大きくなると、これを予算とし、その目標を会社で一丸となって目指します。
この予算、達成させるためには、作成しただけではなく、その後の効果的な運用がポイントになります。
予算と実績を管理し、運用することは大切
年間の予算を作成された方は、これを必ず毎月の予算に落とし込み、更にこの毎月の予算と実際の経営結果を比較するように習慣づけるようにしましょう。
これにより早いうちに、打ち手が正しかったのか、誤っていたのかが、
分かるようになるので、軌道修正も早期に行うことができ、決算の前に様々な方法を考え実践することができるようになります。
結果として、決算もいい結果になるという良いサイクルが生れます。
経理には、毎月の製造や販売、営業の成果を社長に知らせ、社長が正しく意思決定を行えるための資料を作るというとても大切な役割があります。
予算と実績の管理を行う際の大前提としては、毎月の経理が現場の現状を適正に表せるように設計する必要があります。
例えば、売り上げが2月に上がる案件の原価は、2月に原価が上がるようにしないと粗利が正しく出なくなります。
・仕事が忙しくて、経理や記帳などが置き去りになってしまっている。
・経理担当者が辞めてしまって、その後、なかなか経理が安定化しない。
経理がしっかりと安定化しないと、毎月どれだけ利益が上がっているのか分からず、予算と実勢の比較をしても意味のないものとなってしまいます。
これは当たり前のことですが、とても大切なことです。
忙しいのに利益が出ていない・・・・
忙しいのに赤字・・・
何故だか手元にお金が無い・・・
このようなことは放っておくと、問題が複雑化していきます。
こうした課題も早期発見、早期対応で黒字体質・安定した資金繰りに変えやすくなります。
予算の管理と同時に毎月の業績を正しく早期に出すことに合わせて取り組む必要があります。
◇会計アウトソーシングサービス
匠税理士事務所の予算・実績比較による経営コンサルティング
匠税理士事務所では、経営計画の作成を通じて、経営者の方が、予算という前向きな目標を掲げ、その目標を無事達成できるように毎月の経営資料と比較した上で、達成のために何がポイントになるのかについて、経営コンサルティングを行っております。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
世田谷区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
試算表や決算書を読みこなす勉強会 経営者ビジネスセミナー (14/06/14)
匠税理士事務所は、経営者様を利益とお金の視点からご支援するためのセミナーやコンサルティングに専門特化しております。
これまで15年以上にわたって、会社の経営支援に携わり実績を積み上げてきた税理士が、
経営改善のポイントを、ビジネスセミナーを通じてお伝えします。
こちらのセミナーでは、
会社を経営されていると、試算表や決算書などを読みこなす必要が出てきますが、
本業以外のことは何となく苦手・・・
このような社長様に向けた試算表や決算書を読みこなす勉強会となります。
匠税理士事務所の試算表や決算書を読みこなすための勉強会
試算表や決算書などの読み方や、会社を経営していく上で必要な財務指数を勉強会を通じて説明しております。
◇このような方にお勧めです。
・会社を将来継ぐことをお考えの方で、経営に必要な数字を理解したい方
・現在会社を経営しているが、感覚に頼った経営になっている方
(他の税理士事務所をご利用の中の方でも、お気軽にご参加下さい。)
◇決算書の読み方や業績管理 過去に取り上げたテーマ
p10 仕入債務回転率と仕入債務回転期間
p12 総資産回転率・総資本回転率とは
勉強会を担当する講師について
試算表や決算書を読みこなすための勉強会につきましては、匠税理士事務所の税理士水野智史が講師を務めさせて頂きます。講師プロフィールにつきましては、こちらよりご確認下さい。
◇講師プロフィール
決算書読みこなし勉強会の開催日と開催場所
この経営ビジネスセミナーでは、 経営者様のお役にたてるよう実践的・実用的であることを第一にしております。
セミナーを通じ、自社に持ち帰りすぐに役に立つこと、経営が改善されることを目的としています。
そのため受講していただく方のニーズにより、専門家と連携することもあります。
◇セミナー概要
現在、ご予約がうまっておりお引き受けができません。
【開催日】
毎月 第三金曜日 18:30から20:00
【定員】
4名(定員となり次第、締め切らせて頂きます。)
【参加費用】
10,000円
【持ち物・服装】
筆記用具・ノート・電卓。服装は自由です。ラフな格好でかまいません。
【主催・お問い合わせ】
匠税理士事務所
TEL : 03-6272-4704
平日 9:00 ~ 17:00
メール お問い合わせフォーム
【場所】
匠税理士事務所セミナールーム
東京都目黒区自由が丘1-4-10 カランタ1966 404
アクセス:
・東急東横線、大井町線/ 「自由が丘」駅より徒歩2分
・東急目黒線/「奥沢」駅より徒歩5分
匠税理士事務所 セミナー情報
◇セミナー情報
その他の匠税理士事務所に関する情報につきましては、TOPページよりご確認をお願いします。
→ 世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ
緑が丘や洗足近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/05/24)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は緑が丘や洗足近くにある会計事務所で、
【 起業支援と経営支援 】に力を入れる事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士を中心に 【人の質】や【サービスの質】にこだわり、 高度な専門性を武器にお客様のお役に立てる税理士を使命としております。
所属税理士やサービスにつきましては
こちらよりご確認をお願い致します。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】

緑が丘や洗足の会社設立など起業支援
緑が丘や洗足など目黒区で起業される方に対し
目黒区の行政機関を利用した制度融資や
日本政策金融公庫の創業融資の起業支援など
目黒区を対象エリアとする金融機関からの融資など
起業時に必要な資金調達をサポートしております。
また目黒区で会社を設立される場合には、
税理士・司法書士によるコンサルティングで
法務・税務でも起業支援で成功へ導きます。
緑が丘や洗足担当の税理士・専門家はこちらから
【 → 匠税理士事務所の概要 】

当会計事務所の緑が丘や洗足近くでの
会社設立サービスは、こちらで確認下さい。
【 → 目黒区での会社設立支援 】
緑が丘や洗足の創業融資など創業支援
匠税理士事務所では創業時の資金調達も行います。
緑が丘や洗足の創業融資を利用した資金調達は
こちらからご確認下さい。
【 → 目黒区の創業融資・資金調達】

会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は緑が丘や洗足など目黒全域対応です)
緑が丘や洗足の経営支援・法人化
匠税理士事務所では、全関与先を黒字にすることを
目標に会社の数字面・社長からのヒアリングを
基にした経営コンサルティングに力を入れてます。
・経営につき相談できる会計事務所を探している。
・コミュニケーションがとれる税理士がいい
・コンサルティングに強い会計事務所がいい。
緑が丘や洗足など目黒区の会社様で、
上記ご要望がございましたらお気軽に相談下さい。
緑が丘や洗足の近くの税理士・会計事務所による
個人事業主で独立開業から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 東京都の税理士による法人化・法人成り】
目黒区の匠税理士事務所の特徴
匠税理士事務所は、
人の質・提携先の質にこだわることで、
お客様へのサービス品質にこだわります。
品質を通じてお客様利益の最大化を心がけており、
【 目黒区の顧客満足NO1 】の会計事務所
を目指しております。
会計や経理、給与計算や社保手続き代行や
決算・確定申告などの税務申告をはじめ、
個人から会社にする法人化にも対応してます。
詳細はこちらよりご確認下さい。
会社様向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
緑が丘や洗足で個人の方向け確定申告や、
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
緑が丘・洗足で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

緑が丘や洗足での会計事務所の求人採用情報
緑が丘や洗足など目黒区の税理士事務所や
会計事務所の正社員・パートスタッフにつき
求人・採用情報をお探しの方は下記を
ご確認の上、連絡を頂けましたら幸いです。
【 → 東京都目黒区の会計事務所の求人・採用は匠税理士事務所】
上記以外の経営お役立ち情報や会計・給与計算などのサービスラインにつきましては、
上記よりTOPへ移動の上、ご確認をお願いします。
緑が丘(みどりがおか)や洗足(せんぞく)近くで
会社設立や起業支援に強い税理士や会計事務所を
お探しならお気軽にお問い合わせください。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#緑が丘税理士事務所
#洗足法人化
桜新町や玉堤近くの税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (14/05/10)
ご訪問ありがとうございます。
弊所は桜新町や玉堤など世田谷区を中心に
【経営支援】と【起業支援】に強い事務所です。お客様との信頼関係を大切にし、
長くご利用頂けるよう丁寧な対応を心掛けており、
お付き合いの平均が10年以上という事務所です。 世界4大会計事務所出身の税理士が所属し経営セミナーや起業セミナーで講師を務めており、
【高度な専門性】と【技術力】も評判です。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】
そんな事務所であり続けたいと努めております。
所属税理士やサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

桜新町や玉堤での会社設立や起業支援
桜新町や玉堤で会社設立し起業される方に向け
会社設計や設立登記から会計経理、
給与計算代行・経営サポートで起業支援します。
匠税理士事務所では、司法書士・社労士や
弁護士など専門家がチームで対応しますので 起業に必要な全てがそろう事務所となり、決算・確定申告など会計業務以外も対応できます。
桜新町・玉堤の起業支援を担当する税理士や、
提携専門家はこちらからご確認下さい。
【→匠税理士事務所の概要】

起業支援対応:桜新町・玉堤など世田谷区
また経理代行から経営支援まで含めた
会社設立サービスの具体的な内容は、
こちらにてご確認をお願いします。
桜新町や玉堤の創業融資による創業支援
匠税理士事務所では、桜新町や玉堤で
これから起業される方に向けて、
日本政策金融公庫や金融機関と連携した
創業融資による資金調達にも対応してます。
創業計画書作成から融資面談立会いという 独自のサービス内容に加えて、桜新町や玉堤の幅広い業種に対応可能です。
銀行のOBも在籍しておりますので、 資金調達では桜新町や玉堤など世田谷で トップクラスの実績がございます。融資成功率は9割を超え、桜新町や玉堤で
多くのお客様にご支持頂いております。
桜新町や玉堤で会社設立時の創業融資は、
こちらからご確認下さい。

桜新町や玉堤の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は桜新町や玉堤など世田谷全域対応)
桜新町や玉堤の会計経理や確定申告・青色決算
会社設立や創業融資など起業支援以外の
確定申告や決算代行、法人化や法人成り
など税務サービスもございます。
桜新町や玉堤など世田谷区に対応してますので、
お気軽にご相談下さい。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
桜新町や玉堤の方向け確定申告や経理代行
法人化・青色決算サービスはこちらから
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
桜新町や玉堤で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

桜新町や玉堤の法人化・会社設立関連情報
桜新町・玉堤など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
桜新町や玉堤での法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が桜新町や玉堤で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
桜新町や玉堤の会計事務所の求人採用
匠税理士事務所では、
桜新町や玉堤など世田谷近くで
正社員又はパートスタッフとして勤務を
検討中の方は匠税理士事務所採用を確認下さい。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
(桜新町・さくらしんまち)・(玉堤・たまづつみ)など
世田谷区のお客様に向けた会社設立など起業支援・創業支援や
個人からの法人化・法人成りなど匠税理士事務所案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#桜新町税理士事務所
#桜新町会社設立
南大井や東大井近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/05/03)
ホームページへのご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所では、品川の南大井や東大井近くで
【 経営支援・起業支援 】に力を入れてます。
当事務所の方針と致しましては、
【人材の質 ・ 提携先の質】にこだわることで、 南大井や東大井など品川地域の経営支援・起業支援No1の会計事務所を目指してます。品川の日本政策金融公庫や城南信用金庫など
城南エリアに強い金融機関と連携してますので、
資金調達の実績も豊富にございます。
所属税理士や社員・提携先やサービス内容は、
こちらよりご確認をお願い致します。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

南大井や東大井で税理士による起業支援
弊所では、【お客様の黒字率100%】を目指して経営分析を通じたコンサルティングや、
会計アウトソーシングなどにより社長様が
本業に集中できる環境づくりに力を入れています。
・会社が大きくなり、様々な問題が生じてきた・・
・長期的な視点で、経営に取り組んでいきたい・・
・会社を継いだばかりで相談相手が欲しい・・
東大井や南大井で会社を経営されている方で、
このようなお悩みをお持ちの会社様に対して、
経営コンサルティングを行ってます。
会計アウトソーシング・税務や起業支援など
各サービスはこちらよりご確認下さい。
南大井や東大井担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

会社設立や創業融資など起業支援は
こちらからご確認下さい。
【→ 起業のお客様向けサービス】
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
南大井・東大井で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

南大井や東大井で会社設立など創業支援
弊所では、関与先の黒字化支援と共に、
会社設立や創業融資など起業支援に力を入れており
起業コンサルティング経験20年以上の40代の税理士がお客様にとって大事な起業を全力で支援します。
南大井や東大井で会社設立や創業融資などの
創業支援をご検討されている方はご相談下さい。
会社設立など創業支援はこちらから
南大井や東大井で創業融資の資金調達
匠税理士事務所は金融機関と連携した
創業融資による資金調達も対応しています。
創業計画書の作成や融資に関するサポート、
創業融資など資金調達はこちらよりご確認下さい。
南大井や東大井など品川地域で会社設立など
創業される方に行政融資制度も対応します。

南大井や東大井の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は南大井や東大井など品川全域対応)
南大井や東大井近く匠税理士事務所
弊所では、お客様サービスの向上を目指して、
提携先開拓やスタッフ研鑽に取り組んでおります。
東大井や南大井など品川エリアに対応する会計や
経営以外の人事労務や法務も専門家と連携し
対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。
詳細は、会社概要をご参照ください。
南大井や東大井の法人化・法人成り
南大井や東大井など品川区で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 品川区など東京都の法人化・法人成り】
法人化対応エリア:南大井や東大井など品川区全域
東大井・南大井で法人化されたお客様
自宅と会社が品川の南大井にあるので、
品川で法人化に強い税理士を探していたところ、
セミナーで話を伺いお願いしました。
法人化セミナーがとても分かりやすかったので、
節税対策も相談できることが決め手でした。
実際にお願いしてみると
自分の会社の課題や改善策を
分かりやすく説明してくださるので、
大変助かっています。
品川区南大井メーカー株式会社Y様 法人化

南大井や東大井など品川で税理士事務所や会計事務所の求人採用
南大井や東大井など品川区でお役に立てるよう
業務拡大に伴いスタッフを募集しております。
南大井(みなみおおい)や東大井(ひがしおおい)
など品川で税理士事務所や会計事務所の求人や
採用情報をお探しの方は下記をご確認の上、
ご連絡を頂けましたら幸いです。
その他の南大井や東大井地域の方への
匠税理士事務所サービス・お役立ち情報や
会社設立など創業支援・起業支援や、
法人化・法人成り等は上記より確認をお願いします。
南大井や東大井など品川エリアで
当会計事務所紹介を御覧頂き感謝致します。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#大井税理士
#大井法人化
赤堤や豪徳寺近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/05/01)
匠税理士事務所へ来訪ありがとうござます。
弊所は30代と40代を中心とした税理士事務所で
税務会計から給与計算・社会保険・許可申請など
【 事業経営に必要な全てがそろう事務所 】です。 【世界4大会計事務所出身税理士】が対応するため、税額控除や税務調査など高難度も対応可能です。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
赤堤や豪徳寺など世田谷近くで会計事務所を
お探しの方はお気軽にご相談下さい。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

赤堤や豪徳寺での会社設立など起業支援
匠税理士事務所は、30代と40代が中心なため
起業されるお客様が多いという特徴もございます。
同世代の経営者の方から頂くご相談は、
会計経営以外にも多岐に渡ります。
税務や会計以外の住宅購入に伴うローンの考え方や
退職時における退職金の積み立てのプランニングなど
FP業務のご相談にも対応しております。
もちろん、会社設立や起業の経理など起業支援で、
赤堤や豪徳寺など世田谷エリアトップの実績があり、 融資成功率は9割を超えています。赤堤や豪徳寺担当の税理士・専門家はこちら
【→匠税理士事務所の概要】

当会計事務所の会社設立・起業支援は、
こちらにてご確認をお願いします。
(起業支援対応:赤堤や豪徳寺など世田谷区)
赤堤や豪徳寺の創業融資による創業支援
赤堤や豪徳寺で起業・独立・開業をお考えの方は、
まず最初に創業融資で資金調達を検討すべきです。
創業当初は、売上が安定的に上がりにくく、
また資金調達は、創業時の成功率が高いからです。創業して2年ほど経つと決算書(結果)で
融資の判断が行われるのに対して、創業時は将来性に対して判断が行われるためです。
匠税理士事務所は、これまで創業融資などの
創業支援で多くの実績がございますので、
創業計画書作成から面談立会いまでサポートします。
赤堤や豪徳寺の会社設立時の創業融資による
創業支援はこちらでご確認をお願いします。

赤堤や豪徳寺の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(創業支援は赤堤や豪徳寺など世田谷全域)
決算確定申告など税務や会計経理代行も対応
赤堤や豪徳寺など世田谷エリアの会社様に向け
当会計事務所は、決算確定申告代行も承ります。
またこれまで赤堤や豪徳寺で個人事業主で
青色決算書などの確定申告をしてきたが、
株式会社や合同会社など会社にするための
法人化や法人成りにも対応可能です。
税務業務や会計や経理代行に関しまして、
ご要望がございましたらお気軽にご相談下さい。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
赤堤や豪徳寺の方向けの確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
赤堤や豪徳寺で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

赤堤(あかつつみ)や豪徳寺(ごうとくじ)など
世田谷エリアの会社様に向けた
匠税理士事務所の案内ページにつき
ご確認ありがとうございました。
確定申告の提出先は、赤堤や豪徳寺など
世田谷北部エリアは北沢税務署となりますが、
経理代行や自宅やマンション売却に伴う
確定申告もお気軽にお問い合わせください。
赤堤や豪徳寺の法人化・会社設立登記情報
赤堤・豪徳寺など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
赤堤や豪徳寺で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらで手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が赤堤や豪徳寺で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
赤堤や豪徳寺での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#赤堤税理士
#豪徳寺会社設立
仕入債務回転率と仕入債務回転期間 (14/04/26)
会社の財務状態の安全性を分析する上で、
・売掛金などの売上債権
・在庫などの棚卸資産
・買掛金などの仕入債務に関する項目が大きく分けてあります。
今回はこの買掛金などの仕入債務に関する項目を中心とした
仕入債務回転率と、仕入債務回転期間の計算方法を取りあげます。
仕入債務回転率の計算方法や計算式
仕入債務回転率とは、
買掛金などの仕入債務と、商品の仕入高との関係を見る指標であり、
仕入債務には、通常買掛金と支払手形が主なものとしてあげられます。
これらを用いた分析指標である仕入債務回転率を
算式に表現すると、以下のようになります。
仕入債務回転率 = 売上原価 ÷ 仕入債務
この仕入債務回転率が高くなると、
商品の仕入に伴う買掛金や支払手形などの仕入債務に対して
現預金などの支払期間が短くなっていることを意味します。
このような場合には、商品などの仕入先から何かしらの理由で
決済条件の短縮化や現金決済を要求されていたり、
これらの条件が悪い仕入先との商取引が開始されたことなどから
資金繰りが悪化していることが考えられます。
仕入債務回転期間の計算方法や計算式
仕入債務回転期間とは、仕入債務回転率の逆数で求められる安全性分析の指標の一つです。
この仕入債務回転期間は、次の算式で表現することができます。
仕入債務回転期間(日) = 仕入債務 ÷ 売上原価 × 365
(今回はイメージしやすくするため、日数の算式を掲載しております。)
仕入債務回転率と仕入債務回転期間などの財務分析のポイント
仕入債務回転率と仕入債務回転期間にあたっては、1年間のみの仕入債務などで計算すると
経営判断を誤る恐れがあることから過去2~3年の分析を行うことが重要です。
これにより全体としての傾向を抑えることができ、適切な改善策を講じることが可能になります。
◇商品の仕入債務以外の企業の経営分析に関する情報は、こちらからご確認下さい。
決算書の見方や各種ポイントについて記載しております。
→ 貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)など会社の財務諸表の読み方や見方
・売上債権の回収状況に関する安全性分析については、こちらからご確認下さい。
・棚卸資産の状況をを通じた安全性分析については、こちらからご確認下さい。
・その他の経営お役立ち情報については、こちらからご確認下さい。
財務分析や経営分析を活用した経営コンサルティング
匠税理士事務所では、財務分析や経営分析を活用した企業の経営コンサルティングに力を入れております。
財務分析や経営分析にご興味がある経営者の方は、お気軽にご相談下さい。
◇コンサルティングサービス
上記以外のサービスラインや、所属税理士、その他の事務所情報は下記より世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ移動の上、ご確認をお願いします。
中延や旗の台近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/04/20)
ご訪問ありがとうございます。
弊所は、2008年に設立した10名の事務所で
【世界4大会計事務所出身の税理士】を中心に 【 起業支援 】と【 経営支援 】を通じてお客様のお役に立つことにより、
品川No1の会計事務所を目指しております。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
代表税理士・社員も30代・40代で構成され、
同世代のお客様が多いのが特徴の一つです。
所属税理士やサービスなどは、
こちらよりご確認をお願い致します。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

中延や旗の台で税理士の会社設立・起業支援
弊所は30代~40代の同世代のお客様が多く、
会社設立や創業融資など起業支援を柱としてます。
会社設立は、お客様の一生の中で
とても大きな出来事ですので、
この会社設立後の起業支援で成功に導けるよう経験豊富な税理士が全力でサポート致します。
中延や旗の台で起業支援担当の税理士はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

中延や旗の台など品川区での会社設立詳細は、
こちらからご確認下さい。
税理士対応エリア:中延や旗の台など品川区全域
中延や旗の台で創業融資による創業支援
中延や旗の台で会社設立して起業される方で
起業時に創業融資を検討中の方には、
品川区五反田の日本政策金融公庫と提携し
中延や旗の台の起業の資金調達もサポートします。
事業計画書の作成や融資面談対策などで
お困りの方などもお気軽にご相談下さい。
中延や旗の台など品川区で会社設立時に
創業融資による創業支援を検討中の方はこちら

(注)日本政策金融公庫以外にも各種金融機関と
連携した制度融資にも対応致しております。
中延や旗の台の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は中延や旗の台など品川全域対応)
中延や旗の台の確定申告・決算や会計経理代行
匠税理士事務所ではサービスのもう一つの柱に
会社様の黒字化支援を置いています。
弊所では、お客様の黒字率100%を目標に掲げ、 コンサルティングスキルの研鑽とお客様の経営改善に力を入れております。
中延や旗の台の会社様で、経営コンサルティング・経営計画作成をはじめとした経営支援や
会計アウトソーシングや給与計算・社会保険代行の
ご相談はお気軽にご連絡下さい。
また、個人事業主の方が株式会社や合同会社に
組織変更をする法人化・法人成りも対応します。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
旗の台・中延で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

旗の台や中延から匠税理士事務所へアクセス
中延や旗の台から匠税理士事務所へお越し方は、
路線情報などアクセスページでご確認下さい。
大井町線で自由が丘駅でお降り頂くか、
お車でお越し頂く場合には、近くのコインパーキングを
ご利用頂くと便利です。
旗の台で会社設立されたお客様の声
品川区旗の台で会社設立する際に、
融資にも強く全て任せられる税理士さんを探してました。
ちょうど1年前ほどに起業した先輩から、
匠税理士の話をきいてお願いしました。
経理や税金以外にも、
社会保険や給与計算なども対応して下さるので
感謝しています。
これからも宜しくお願い申します。
<品川の旗の台で会社設立 株式会社I様>
中延で税理士により法人化されたお客様の声
会社がある中延近くの品川区から行きやすい
会計事務所をさがしていたところ、
ホームページをみてこちらに法人化を
お願いすることにしました。
かれこれ8年になりますが、ミスが一切なく
いつも緊張感をもって仕事してくれるので、
とても信頼できる会計事務所さんです。
これからもお願いします。
<中延で法人化された株式会社Y様>

その他の中延や旗の台など品川区でのサービスや
会計税務のお役立ち情報は、
上記よりでご確認をお願いします。
中延(なかのぶ)や旗の台(はたのだい)など
品川の会社設立・起業支援、法人化・法人成りに強い
会計計事務所をお探しならお気軽にご相談下さい。
品川区の会計事務所の採用求人はこちらから
中延や旗の台での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#旗の台税理士
#中延税理士事務所
棚卸商品など在庫回転期間、在庫回転率の計算式と計算方法 (14/04/18)
会社を経営されている方にとって、在庫は経営にとても大きな影響を与えます。
会社規模が大きくなってくると、この在庫管理も大変になってきます。
棚卸商品などの管理と在庫回転期間、在庫回転率について
在庫管理を怠ると、現金が在庫になったまま、
現金化されないのを放置することになるため、
最終的には資金繰りが悪化し、会社の安全性が損なわれてしまいます。
そこで在庫状況を全体的に把握するため在庫回転期間、在庫回転率といった
在庫による安全性分析が効果的です。
在庫回転期間・棚卸回転期間とは何か、その計算式と計算方法

在庫回転期間・棚卸回転期間とは、
商品を仕入れてから、どのくらいの日数で販売できるのかを把握する分析指標です。
棚卸回転期間・在庫回転期間は、一般的に期間が短いほど商品を仕入れてから
在庫となっている期間が短く、よく売れていることになります。
逆に在庫回転期間が伸びてきた場合には、
在庫過剰や、デッドストック(売れ残り)があるのではないかと疑う必要が出てきます。
この在庫回転期間を把握するための算式は以下のとおりです。
(今回はイメージをしやすくするため、日数にて説明します。)
在庫回転期間(日数) = 棚卸資産 ÷ 売上原価 × 365
在庫回転率・棚卸回転率とは何か、その計算式と計算方法
在庫回転率、棚卸資産回転率とは、
棚卸資産(在庫)を効率的に売上に結びつけているかを把握するための指標です。
これを算式に表現すると
棚卸資産回転率 = 売上原価 ÷ 棚卸資産 となります。
在庫回転期間、在庫回転率の分析のポイント
在庫回転期間、在庫回転率については、
季節変動などで在庫が一時的に多くなる業種などの場合には、
ある一時点のみの分析では、正しく経営判断ができなくなりますので、
長期間の指数の平均値を利用する必要が出てきます。
このように財務分析は、一時点のみをとらえるのではなく、
その企業の傾向がどのような傾向なのかをとらえ、
その傾向に応じて対策を講じていくことが重要です。
◇在庫以外の企業の経営分析に関する情報はこちらからご確認下さい
決算書の見方や各種ポイントについて記載しております。
→ 貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)など会社の財務諸表の読み方や見方
売上債権の回収状況に関する安全性分析については、こちらからご確認下さい。
仕入債務の状況をを通じた安全性分析については、こちらからご確認下さい。
★その他の経営お役立ち情報については、こちらからご確認下さい。
匠税理士事務所では各種財務分析や経営分析を活用した経営コンサルティングを行っております。サービスの詳細はこちらよりご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
その他のサービスラインや、事務所概要につきましては、TOPページに移動の上、ご確認下さい。
世田谷の税理士 匠税理士事務所TOPページへ移動します。
最終更新日:平成26年4月26日
売掛金などの売上債権回転率・売上債権回転期間の計算式 (14/04/05)
会社が伸びて規模が大きくなってきた場合には、
全体を把握する方法として財務分析が有効です。
そこで今回は、貸借対照表など財務諸表を活用した安全性分析のうち、
売上に関する債権分析を取り上げます。
商売は売り上げを上げて完了ではなく、資金の回収までしっかりと行って、
次の商売に再投資するというサイクルが重要です。
そこでこの売上債権回転率や売上債権回転期間を活用して、
この回収がどのように推移しているのかを把握し、
異常がないかを随時確認していくことが重要となります。
経営ではこの売掛金・仕入代金・在庫期間のバランス感覚がとても大事です。
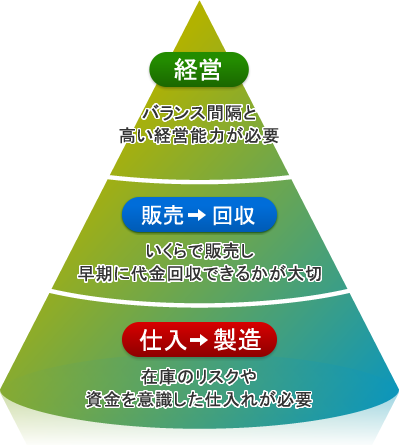
売上債権回転率と売上債権回転期間とは
売上債権回転率と売上債権回転期間とは、
売上債権の回収がどれほど効率的に行われているかを見る指標です。
これらの数字を見ることで、債権の回収状況全体を把握することができ、
各指標に異常が生じた場合には、その原因解明を行い、
迅速に対応していくことが重要です。
売上債権回転期間の計算式や計算方法
売上債権回転期間とは、商品を販売してから売掛金などの売上債権を回収するまでに
かかる期間を月数または日数で示した指標です。
そのため売上債権回転期間は、その期間が短ければ短いほど
現金化が早いことを意味するため、優良ということになり、
企業の安全性は高いと考えることができます。
売上債権回転期間の算式は以下のとおりです。
月数で示すものと日数で示すものがありますが、ここでは日数の算式を記載します。
売上債権回転期間 = 売上債権 ÷ 売上高 × 365日
売上債権回転率の計算式と計算方法
売上債権回転率は、売上債権の回収がどれほど効率的に行われているかを見る指標であり、
大きいほど効率よく資金が循環していると言えます。
売上債権回転率 = 売上高 ÷ 売上債権

貸借対照表を活用した安全性分析のポイント
貸借対照表を活用した安全性分析のポイントは、指標の趨勢を見極め、
分析結果を行動に移して経営改善をしていくことです。
つまり、1期だけなどある一時点のみをとらえるのではなく、
2~3期を通して趨勢を見たり、各時点の平均値を用いるなど
全体としての流れを把握し、
売上債権回転期間が、長くなってきているのであれば、
その原因を現場レベルで確認し、的確に対策を打っていくことで、
お金が残りやすい企業体質になっていきます。
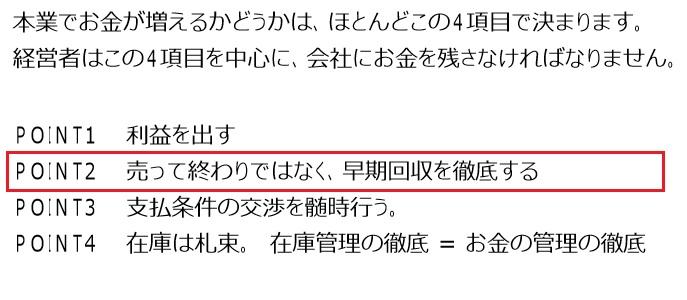
◇経営お役立ち情報
売上債権回転率・売上債権回転期間以外にも仕入債務や在庫などの見地からの安全性の検証も有効です。関連記事はこちらからご確認下さい。
★決算書の見方や各種ポイントについて記載しております。
→ 貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)など会社の財務諸表の読み方や見方
★在庫状況を通じた安全性分析については、こちらからご確認下さい。
★仕入債務の状況をを通じた安全性分析については、こちらからご確認下さい。
★その他の経営お役立ち情報については、こちらからご確認下さい。
匠税理士事務所では、各種財務分析や経営分析を活用した経営コンサルティングを行っております。サービスの詳細はこちらよりご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
その他のサービスラインや、事務所概要につきましては、下記リンクからTOPページに移動の上、ご確認下さい。
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
目黒区の税理士なら匠税理士事務所...TOPページへ
最終更新日:平成29年4月26日
西品川や南品川近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/03/21)
匠税理士事務所に訪問頂きありがとうございます。
弊所は、40代の税理士やスタッフを中心とする
【起業支援】・【経営支援】に力を入れる事務所で
お客様のお役に立てるように 【人の質・サービスの質】が特徴の会計事務所です。匠税理士事務所の税理士やサービスは
こちらからご確認をお願い致します。

対応地域:西品川や南品川など品川エリア全域
西品川・南品川で税理士の会社設立・起業支援
西品川や南品川で会社設立をご検討中の方に
司法書士と連携した法務コンサルティングを通じて
会社設立後にトラブルが起きないような
会社ルールの定款作りをサポートしてます。
また会社設立後には、税務署など各行政機関への
届出書作成や会計アウトソーシング、
税理士による起業支援も力を入れてます。
西品川や南品川担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

会社設立や会計経理・起業支援の詳細は、
こちらからご確認をお願い致します。
西品川や南品川の創業融資による創業支援
匠税理士事務所は、西品川や南品川での
創業計画書の作成サポートや融資面談立会など
創業融資による創業支援も充実しています。
西品川や南品川など起業資金調達のため
創業融資をご検討中の方は、品川の五反田にある
日本政策金融公庫とも提携しておりますので、
創業融資支援も可能です。お気軽にご相談下さい。
【 → 品川区の創業融資・資金調達】

西品川や南品川などでの起業をお考えの方で、
品川区の制度融資をご要望の方には
制度融資にも対応しております城南信用金庫など
各種金融機関とも提携しておりますので、
ご要望をお聞かせいただければ幸いです。
【→品川区の制度融資と創業融資 】
西品川や南品川の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は西品川や南品川など品川全域対応)
西品川や南品川の確定申告・会計経理代行
上記起業支援以外にも、会計経理代行などの
各種アウトソーシングサービスをはじめ、
会社の経営を支援するための経営分析や
財務分析コンサルティングも充実してます。
また西品川や南品川など品川の個人の方に向け
確定申告代行や会社にする法人化・法人成りなど
税務コンサルティングも行います。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
西品川・南品川で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

匠税理士事務所までのアクセス
西品川や南品川など品川から匠税理士事務所までの
各種鉄道情報や地図はアクセスよりご確認下さい。
近くには時間極駐車場もございますので
お車でのご来訪も便利です。
西品川や南品川の会社設立・法人化登記情報
品川区の西品川・南品川で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
西品川や南品川など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が西品川や南品川で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
西品川や南品川で税理士事務所・会計事務所の求人採用
西品川や南品川など品川エリア近くで、
税理士事務所・会計事務所の求人情報や採用情報をお探しの方に向けた
匠税理士事務所の求人や採用情報のご紹介です。
詳細はこちらよりご確認下さい。
上記以外の業務内容や料金は、
上記よりご確認下さい。
西品川(にししながわ)や南品川(みなみしながわ)
品川区以外のお客様のご相談も承っております。
お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧くださりありがとうございました。
西品川や南品川など品川区で会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い会計事務所をお探しならご相談ください。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#西品川税理士
#南品川会社設立
玉川台や玉川田園調布近くの匠税理士事務所・会計事務所 (14/03/18)
玉川台や玉川田園調布、東玉川からすぐの
匠税理士事務所へご来訪ありがとうございます。
弊所は世界4大会計事務所出身の税理士と、フィナンシャルプランナー、社労士、弁護士、
中小企業診断士等が連携して
【会社に利益とお金を残す事】を使命としてます。また、確定申告や決算のみで終わりではなく、
会計経理データを活用した経営支援を行います。
【 匠税理士事務所に任せて良かった 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の税理士やサービスは
こちらからご確認下さい。

玉川台や玉川田園調布、東玉川の会社設立や起業支援
玉川台や玉川田園調布、東玉川など
世田谷区でこれから法人設立をしたいという方に
社名から本店所在地・役員などの定款作成から
税務署等官庁への届出書作成など全て対応します。
お客様は打ち合わせに参加頂くのみで、書類の作成の必要はございません。

お決め頂いた事項を司法書士にて登記し、
届出は税理士が対応します。
また社会保険の変更や加入手続きも
社会保険労務士が対応しますので、
事業に集中できるようになっております。玉川台・玉川田園調布・東玉川担当税理士等はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

玉川台や玉川田園調布・東玉川など世田谷区での
会社設立はこちらからご確認下さい。
(対応エリア:玉川台・玉川田園調布・東玉川など世田谷)
玉川台や玉川田園調布、東玉川の創業融資など創業支援
また会社設立と同時に起業資金の確保を
ご検討されている方は、
玉川台や玉川田園調布・東玉川エリアに
対応する金融機関とも連携しております。
創業融資支援につきましては、
こちらからご確認をお願いします。

玉川台や玉川田園調布・東玉川で株式会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は玉川台や玉川田園調布・東玉川対応)
確定申告や会計経理決算にも対応の匠税理士
・玉川台や玉川田園調布、東玉川で自宅や
マンションを売却されたり、事業に伴う
確定申告の代行を検討している。
・個人事業の法人化や法人成りを検討中。
・インボイス対応で会計事務所を探している。
このような税務会計に関するご相談にも
対応しております。
玉川台や玉川田園調布・東玉川で税理士事務所を
お探しの方はお気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所のサービスはこちらをご確認下さい。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
玉川台・玉川田園調布・東玉川の確定申告・経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
玉川台や玉川田園調布、東玉川で税理士の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

玉川台や玉川田園調布、東玉川の法人化・会社設立関連情報
玉川台や玉川田園調布、東玉川など世田谷区で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
玉川台や玉川田園調布、東玉川で法人化・会社設立の
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が玉川台や玉川田園調布、東玉川で法人化や、
会社設立など登記の際、対応する行政窓口となります。
玉川台や玉川田園調布、東玉川の税理士の採用
玉川台や玉川田園調布、東玉川など世田谷区に
お住まいで近くの会計事務所や税理士事務所での
勤務を検討中の方は採用情報を確認下さい。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
玉川田園調布(たまがわでんえんちょうふ)
玉川台((たまがわだい)・東玉川(ひがしたまがわ)など
世田谷のお客様向け会社設立や法人化・法人成りなど匠税理士事務所の案内ページを
最後までご閲覧下さりありがとうございます。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#玉川税理士
#玉川田園調会社設立
会社設立や許認可申請など業務提携をご検討頂ける行政書士の方へ (14/03/15)
匠税理士事務所では、
起業に伴う会社設立の申請や、
各種許認可の申請などの業務を
共に取り組んで頂ける行政書士の先生を探しております。
匠税理士事務所が提携行政書士の先生に求めること
匠税理士事務所では、
「 お客様の利益の最大化 」
を使命としており、
この使命に賛同して頂ける行政書士の先生を募集しております。
私達と一緒に
お仕事をして頂ける行政書士事務所の先生は、
以下のURLにて詳細をご確認の上、
ご連絡を頂ければ幸いです。
ご不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡下さい。
事務所概要と所属税理士のご紹介
匠税理士事務所は、
目黒区の自由が丘にある税理士事務所で、
起業と経営コンサルティングに力を入れている事務所です。
弊所の概要やアクセスにつきましては、
こちらからご確認下さい。
その他の各種サービスラインや、
料金体系などの情報に関しましては、
下記よりTOPページに移動の上、ご確認をお願いします。
世田谷区 税理士 弊社HPはこちらへ
最終更新日:平成26年3月15日
目黒区駒場東大前の税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/03/14)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は、目黒区駒場東大前近くの会計事務所で、
【 1 会社設立・創業融資などの起業支援 】 【 2 経営コンサルティング 】に力をいれておりまして、
世界4大会計事務所出身の税理士を中心とした 【高度な専門性】と【高い技術力】が強みです。もちろん、経理代行や確定申告など税理士事務所の
一般業務にも対応しております。
所属税理士やサポート内容などにつきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

目黒区駒場東大前の会社設立や起業支援
駒場東大前など目黒区で株式会社などを設立し
起業される起業家の方に向けて、
会社の役員構成から資本金など基本事項立案から、
実際の登記に至るまでサポート致しております。
お客様とは一度事務所で打ち合わせをすれば、
会社設立が可能です。
会社設立後の経理代行と税務申告や経営支援、
助成金や補助金対応も可能になっており、
【 起業に必要な全てがそろう事務所です。 】担当する税理士や専門家はこちらから
【 →匠税理士事務所の概要 】

駒場東大前など目黒区での会社設立サポートは、
こちらからご確認下さい。
また、起業家にとって資金調達は最優先事項ですが
弊所では目黒区の制度融資や日本政策金融公庫の
創業融資も対応しています。
創業計画書の立案作成支援や、
金融機関審査立会いを通し起業資金確保します。
金融機関出身のOBが顧問に在籍してますので、目黒区での融資成功実績が豊富にございいます。
駒場東大前など目黒区での創業融資の資金調達は、
こちらからご確認下さい。

起業と黒字戦略に強い匠税理士事務所
弊所は、駒場東大前など目黒区で
起業支援や黒字戦略に力を入れております。
また、会計や経理の代行、給与計算アウトソーシングや
確定申告・事業承継など税務業務も対応してます。
事業を行う社長様の広い相談に応えれるように、
行政書士、社労士、弁理士など提携も充実してます。
駒場東大前など目黒地域の方への
匠税理士事務所の案内につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
駒場東大前で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

駒場東大前(こまばとうだいまえ)の目黒区など
東京都23区全域が税理士の対応地域となります。
また駒場東大前から近くの会計事務所で正社員や
パートスタッフ勤務をご検討中の方は、
弊所サイトの採用情報をご確認ください。
皆様からのご応募をお待ちしております。
【 → 東京都目黒区の会計事務所の求人・採用は匠税理士事務所】
執筆者・文責:税理士 水野智史
桜上水・上北沢近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/03/14)
世田谷区の桜上水や上北沢近くの匠税理士事務所へ
ご訪問ありがとうございます。
弊所は世界4大会計事務所出身の税理士を軸に、会計経理データを活用した財務分析と
会社の黒字化を行うコンサルティング、
事業承継や税額控除などの【高度税務】や、
専門性を活かした節税が評判の会計事務所です。もちろん、税務調査もしっかりと対応しますので、
結果、お客様とのお付き合いは平均10年以上です。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
世田谷区の桜上水や上北沢近くで、
経営支援・節税対策に強い会計事務所をお探しなら
匠税理士事務所にご相談下さい。
税理士や提供業務につきましては
こちらからご確認をお願いします。

桜上水や上北沢で会社設立や創業支援
匠税理士事務所では、株式会社設立の代行から
起業時の資金調達のための創業融資、
会社設立後の会計や経理のサポートも承ってます。
会社設立や創業融資など起業支援実績では、
桜上水や上北沢など世田谷でトップレベルです。

そのため、金融機関の審査面談を弊所で実施し、
税理士が面談に同席できる特典もございます。
結果として、融資成功率は9割を超えており、多くの起業家の方にご支持いただいております。
桜上水・上北沢担当の税理士や専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

桜上水や上北沢で創業融資など起業支援
匠税理士事務所の桜上水や上北沢の起業支援、
会社設立後の会計経理・決算代行など創業支援は、
こちらからご確認をお願い致します。
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
桜上水や上北沢など世田谷区での会社設立サービスは、
こちらからご確認をお願いします。
また桜上水や上北沢などの各種金融機関とも
提携した制度融資や政策金融公庫の創業融資など
2つのチャネルからの調達が可能です。
匠税理士事務所が提供する桜上水や上北沢など
世田谷区の創業支援はこちらで確認下さい。

創業支援対応エリア:桜上水・上北沢など世田谷区
確定申告や経理決算・法人化代行もお任せ
弊所は、桜上水や上北沢での
会社設立や創業融資など起業支援以外の
確定申告や経理決算の代行も充実しております。
お客様は書類を送るだけであとはお任せという
事業に専念できる体制づくりを支援しております。また、桜上水や上北沢で個人事業を行われて、
規模が大きくなってきたため法人化・法人成りを
検討されている場合も対応可能です。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
桜上水や上北沢の方向け確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
桜上水や上北沢で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

また助成金や補助金など税務会計以外の相談も
社会保険労務士や中小企業診断士など専門家と
提携した起業支援・創業支援も対応可能です。
桜上水・上北沢の方に向けた>助成金・補助金など
起業支援・創業支援はこちらからご確認下さい。
【 → 補助金や助成金とは?補助金申請書の作成代行と助成金申請 】
社長様のお役に立てる税理士事務所づくりに今後も注力していきたいと思います。
桜上水や上北沢の法人化・会社設立登記情報
桜上水・上北沢など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
桜上水や上北沢で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が桜上水や上北沢で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
桜上水・上北沢近くの税理士事務所の採用
桜上水や上北沢近くで会計事務所勤務を
ご検討中の方は、弊所採用情報をご覧下さい。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
桜上水(さくらじょうすい)や
上北沢(かみきたざわ)など世田谷区の
お客様に向けた会社設立など創業支援・起業支援や
法人化・法人成りに関する匠税理士事務所のご案内を
最後までご確認頂き誠にありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#上北沢税理士
#上北沢会社設立
上大崎や大崎駅近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/03/12)
匠税理士事務所サイトにご訪問ありがとうございます。
弊所は、大崎駅や上大崎など品川のお客様に向けた
【起業支援と経営支援】に力を入れる事務所です。
【世界4大会計事務所出身の税理士】を中心に 【お客様の起業成功】【会社の成長】のお手伝いで 品川エリアでNo1を目指しています。そのためには、優秀な人材と高度な専門性を有する提携先の充実が重要と考えており、
【人の質・サービスの質】にこだわるという想いで 匠税理士事務所という社名に致しました。所属税理士の詳細や提携の専門家、サービスは、
こちらよりご確認をお願いします。

大崎駅・上大崎で税理士の会社設立・起業支援
匠税理士事務所では、2008年に設立してから、
会社設立して起業したいというお客様に、
会社の役員・資本金などの基本設計から入金や、
支払サイクル設定、利益を出すポイントや、
経理方法の勉強会などを通じて会社設立と
その後の起業支援で成功をお手伝いします。

また、【 起業に必要なすべてがそろう税理士事務所 】をスローガンに、
起業に伴い資金調達のご要望があるお客様には、
日本政策金融公庫五反田支店様と連携し
多くの創業融資で起業支援してきました。
大崎駅・上大崎エリア担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

・大崎駅・上大崎などで株式会社を設立したい。
・大崎駅や上大崎など品川で起業したいが、
創業融資を検討している。
このようなご要望で会計事務所をお探しの方は、
お気軽にご相談下さい。
上大崎や大崎駅対応の株式会社の会社設立や
その後の経理や経営支援サービスはこちら

大崎駅・上大崎で創業融資による創業支援
【 品川区の制度融資にも対応しています 】日本政策金融公庫様以外にも、
大崎駅・上大崎など品川を中心とする信用金庫様や
各種金融機関様とも提携してますので、
会社設立の資金調達につきお気軽にご相談下さい。
また、制度融資にも対応可能です。
品川区で創業融資による創業支援はこちらから
ご要望がある場合には、社会保険手続き代行や
給与計算など起業付随する業務も承ってます。

大崎駅・上大崎の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は大崎駅・上大崎など品川全域対応)
上大崎や大崎の会計経理や確定申告・決算代行
大崎駅や上大崎など品川区のお客様に向け
会計のデータを財務分析という形で活用し、
会社の問題把握を行い、この問題点を
改善する経営支援に力を入れております。
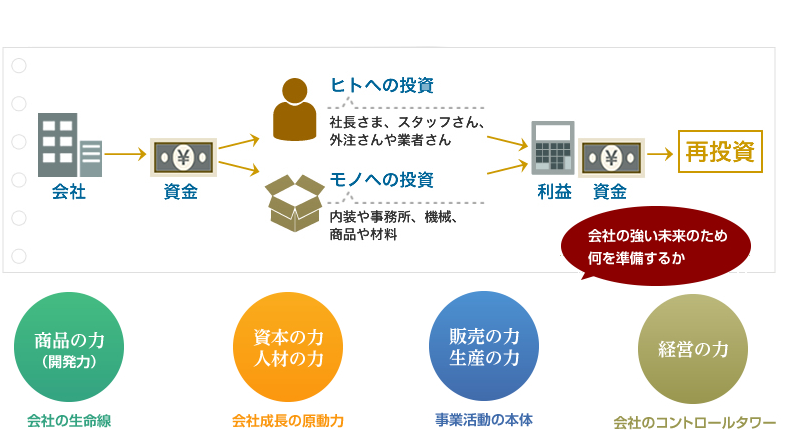
利益率分析や対応策の検討、資金繰り
融資コンサルティングなど状況に応じ
コンサルティング内容を細かくアレンジしております。
また利益とお金がたまるようにするための
利益戦略会議やキャッシュストック経営など
独自サービスもございます。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
上大崎や大崎駅の方向け確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
上大崎・大崎で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

上大崎・大崎駅で税理士による法人化・法人成り
最初は小さく始めるため個人事業で起業したが、
事業が大きくなってきたので
株式会社など会社にしたいという方に向けて
法人化サービスも提供致しております。
上大崎など品川区で個人から会社設立する
法人化は、こちらでご確認をお願いします。
【 → 品川区の法人化・法人成り 】
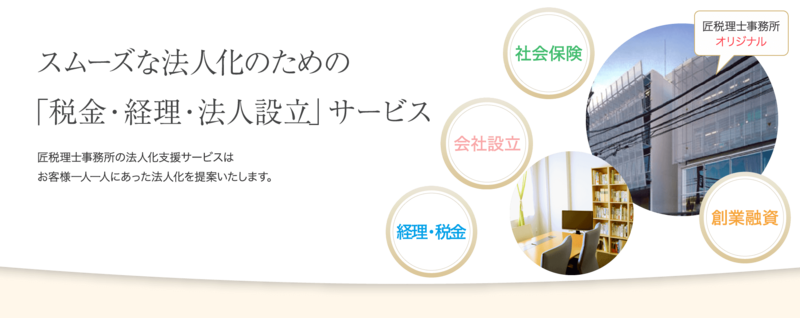
大崎や上大崎から弊所へお越しのお客様へ
大崎や上大崎など品川エリアから弊所の路線情報、
地図などはアクセスページでご確認下さい。
上大崎で法人化された広告代理店様の声
広告代理店を10年程前からやっており、
当時の税理士さんがITに詳しくないため、
業界の税務会計に詳しい税理士さんで
法人化に強い方を上大崎近くで探してた時、
業者さんからの紹介で知りました。
実際にお願いしてみると、
とても丁寧に教えてくれて、
税務調査でもまったく指摘を受けず、
大変助かりました。
これからもよろしくお願いします。
【品川区上大崎の広告代理店 法人化株式会社T様】
大崎でリフォームの会社設立されたお客様の声
リフォームの会社に15年程前から勤務していて、
大崎駅近くで会社設立し起業しました。
最初は大崎駅近くにある自宅で開業を考えたので、
できる限りお任せするところはお任せして、
売上確保に集中したいと考えました。
会計処理の代行から事業へのアドバイス
節税提案まで助かっています。
トラブルでは弁護士を紹介して下さり満足です。
今後も宜しくお願い致します。
【大崎駅のリフォーム会社設立 A様】
上大崎や大崎駅の会社設立・法人化登記情報
品川区の上大崎や大崎駅で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
上大崎や大崎駅など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が上大崎や大崎駅で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
大崎駅や上大崎などの近所で求人や採用情報
大崎や上大崎など品川区近くの税理士事務所を
お探しの方で一緒になって事務所を盛り上げて
下さるスタッフを募集しております。
詳細は採用情報からご確認下さい。
大崎駅や上大崎など品川区の方に向けサービスや料金体系のご紹介は、
上記からTOPページに移動の上、ご確認下さい。
上大崎(かみおおさき)・大崎駅(おおさきえき)近く
にある会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い会計事務所です。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#上大崎税理士
#大崎会社設立
代沢や下北沢近くの税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (14/03/01)
匠税理士事務所に訪問頂きありがとうございます。
弊所は、代沢や下北沢など世田谷区で
世界4大会計事務所出身の40代税理士を軸に【 起業支援・経営支援 】に力を入れる事務所です。
事務所の特徴と致しましては、
【 人の質・サービスの質 】へのこだわりで、 高度な専門性を駆使して、お客様黒字率を100%にすることを使命としております。匠税理士事務所の税理士経歴・サービスは、
こちらよりご確認をお願い致します。
【 →世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

下北沢・代沢の税理士の会社設立や起業支援
匠税理士事務所は、世田谷区の産業振興公社などで
起業創業セミナー講師を歴任し、
これらの活動を通じ世田谷区で会社設立など
起業支援を数多くサポートしてきました。

このノウハウを活かし下北沢・代沢など世田谷区で
会社設立をご検討されている方や、
創業融資などをご検討されている方には、
日本政策金融公庫と連携して資金調達を行います。
代沢・下北沢担当の税理士や専門家は
こちらをご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

匠税理士事務所の代沢や下北沢など世田谷区で
会社設立・起業支援サービスはこちらから
【 → 世田谷区での会社設立の代行 】
下北沢・代沢の創業融資による創業支援
匠税理士事務所の代沢や下北沢など
世田谷区で会社設立時の創業融資による
創業支援をご検討中の方は、
創業融資支援サービスをご確認下さい。

代沢や下北沢の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は代沢や下北沢など世田谷全域対応)
経営支援や会計・経理アウトソーシング
匠税理士事務所では、経理・決算・確定申告代行から
これらの会計財務データを活用した
会社の経営支援に注力してます。
40代の世界4大会計事務所出身の税理士が、経営コンサルティングを通じて
会社の利益拡大に貢献できるように尽力し、
会計のアウトソーシングニーズがある会社には、
会計のアウトソーシングサービスも提供してます。
土地など不動産を売却された方の確定申告や
個人から会社にする法人化もご相談下さい。
代沢や下北沢の方へのサービスはこちらを確認下さい。
法人の会社様向けサービス
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向けサービス
【 → 個人のお客様サービス一覧 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
代沢・下北沢で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】
弊所では、起業支援と経営支援を通じて、
満足度世田谷区NO1の会計事務所を目指します。
代沢・下北沢の方からお問い合わせお待ちしてます。

弊所は、正社員やアルバイトスタッフ、
パートスタッフも募集しております。
採用求人の詳細はこちらでご確認下さい。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
代沢や下北沢から匠税理士事務所のアクセス
代沢や下北沢から弊所までの地図や
電車情報などアクセスにつきましては、
上記より会計事務所概要からご確認ください。
お車でお越しの方は、コインパーキングも
近くにございますのでご利用ください。
代沢や下北沢の法人化・会社設立関連情報
代沢・下北沢など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
代沢・下北沢で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が代沢・下北沢で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
代沢や下北沢での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#下北沢税理士
#下北沢会社設立
社会保険労務士による就業規則作成などの労務コンサルティング≪p8≫ (14/02/27)
匠税理士事務所では、提携の経験豊富な社会保険労務士と共に、
就業規則など各種社内規定の作成など人事労務のコンサルティングにも力を入れております。
就業規則など社内規定作成による労務コンサルティング
・ 人が増えてきて、統率が取れなくなってきた。
・ 問題のある社員がいるが、何とかしたい。
・ 会社のルールをそろそろ作りたい
・ 就業規則を作らないといけない規模になった。

このように人員が増えてくると
会社を適切に経営していく上で、
労務管理が必要になってきます。
正しい労務管理をするためには、
しっかりとした就業規則などの社内規則が必要です。
そこで匠税理士事務所では、
人を活用し経営成績が伸びるように
提携の社会保険労務士と共に
就業規則などの作成など
労務コンサルティングサービスを提供しております。
勤怠管理と給与計算アウトソーシング
就業規則に基づき、
社員がしっかりと勤務してくれているかなどの勤怠管理や、
これらを給与に反映して会社の競争力を高めるなど
就業規則や勤怠管理を反映した
給与計算アウトソーシングサービスも行っております。
社会保険労務士による社会保険などの各種手続きの代行にも
対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の提供する給与計算サービスの詳細は
こちらからご確認下さい。
また労使トラブルに発展してしまって場合には、
社会保険労務士や人事労務問題に詳しい弁護士が対応致します。
≪p8≫匠税理士事務所の事務所概要や、提携社会保険労務士・弁護士のプロフィールはこちらから
→ 自由が丘の税理士は匠税理士事務所・社会保険労務士について
人事労務サービス以外のサービス
人事労務のコンサルティングや給与計算以外にも、
会社の会計アウトソーシングや経営支援サービスもご提供しております。
詳細はこちらからご覧下さい。
上記以外の各種サービス、料金などは、
下記よりTOPページにてご確認下さい。
◇バックナンバーはこちら→
最終更新日:平成27年9月7日
契約書の作成や契約内容の確認などの企業法務サービス (14/02/21)
匠税理士事務所では、企業に法務部などを持たない中小企業のお客様を
契約に関するトラブルなど法務面のリスクからお守りするため
企業法務サービスを弁護士事務所と連携し提供しております。
◇目次
1.社長様と会社との間で必要になる契約書(税理士)
2.会社と取引先様との間で必要になる契約書(弁護士)
1.社長様と会社との間で必要になる契約書(税理士)

中小企業や個人事業主のお客様にとって、「 契約書は無縁 」 と思われがちですが、そうではありません。
以下のような場合には、きちんとした契約書がないと、後々思わぬ不利益を被ることがございます。
お心当たりのある方は、一度契約書の作成を検討されてもよろしいかもしれません。
会社と社長との間の契約書作成が必要になるケース(税理士)
【 自分が経営している会社からお金を借りたが、契約書を一切作成していないケース 】
税務調査の際に賞与として認定されるリスクが残りますので、
①きちんと契約書を作成した上で、返済予定表を作成し、
②他人からお金を借りるのと同じような環境を作ることで、
税務調査官から思わぬ誤解を受けないように注意しましょう。
◇関連記事
【 自分の自宅の一部を会社に貸し付けているが、契約書を作成していないケース 】
取引の事実そのものを否認されないように、
①毎年の確定申告と家賃の受け渡しはもちろん必要ですが、
②他人に不動産を賃貸するのと同様に、自分の会社との不動産の賃貸借に関する契約書も結んでおきましょう。
◇関連記事
◇匠税理士事務所の契約書作成サービス
匠税理士事務所では、税務顧問契約を頂いておりますお客様の契約書作成もサポート致します。
税務調査でトラブルとならないよう適正な家賃や利率を設定し、契約書を作成致します。
2.会社と取引先との間で必要になる契約書(弁護士)

商取引をこれまでの口約束などで何となく進めていても、
企業間の関係は良いときばかりではなく、悪くなることもあります。
そのような場合に、言った言わないという問題にならないためにも、
重要な内容は契約書を作成しておくことが重要です。
しかし、契約書は法律上のポイントなどを加味していなければ、
特に一回当たりの金額が大きい取引などは思いもよらないトラブルにもつながりかねません。
そこで重要な商取引は、取引ごとに法務面のプロフェッショナルである弁護士による契約書作成が有効です。
◇関連記事
→契約書とは何か?その書き方や作り方、効果とは...契約書とは何か?その書き方や作り方、効果について
弁護士による契約書の作成やレビューのサービス内容と料金
・得意先から契約書が送られてきて、印鑑を押すように言われたが、
重要な取引で金額も大きいので誰かに相談したい・・・・
・ これまで取引の実績がない会社との契約なので、
問題なく取引を行っていけるか心配だ。
・ レベニューシェアの契約を考えているが、
うまくいったときにケンカ・トラブルにならないか心配だ・・・
・ ライセンス利用料の契約が、現時点では双方納得しているが、
将来利用料を簡単に上げられるようだと事業が安定しないので何とかしたい。
このような想いを経営者なら一度は経験したことがあると思います。
そのような場合にも、企業法務のプロフェッショナルである弁護士が契約内容を確認し、
アドバイスする契約書レビューサービスを提供しております。
また、自社の条件を盛り込んだ契約書を作りたいという契約書の作成サービスも行っております。
トラブルになってしまうと当事者間の話し合いが反って好ましくない方向に向かってしまうことがあります。
そのような時には、作成しておいた契約書をもとに弁護士を交えてお話をすることが有意義です。
◇契約書の作成やレビュー料金
料金は契約書のボリュームにもよりますが、3万円~10万円程になります。
大きな商取引に際して、万全を期したいという方にお勧めです。契約書の作成やレビューなど企業法務サービスを担当する弁護士の詳細
匠税理士事務所では、
契約書の作成や、契約内容のレビューなど企業法務サービスを
経験豊富な弁護士と連携して提供しております。
契約書の作成はもちろんですが、
には、弁護士が手続きや提案など問題の解決にむかってお客様をお手伝い致します。
※法務トラブルをめぐる弁護士費用は、個別お見積りとなります。
◇事務所の概要や、法務を担当する弁護士のプロフィールはこちらとなります。

東品川や北品川すぐの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/02/13)
ホームページへご訪問頂きありがとうございます。
弊所は東品川や北品川で会社設立など起業支援と
経営支援に力を入れている会計事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸とした【 高度な専門性 と 独自の経営支援サービス 】
が強みの税理士事務所です。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
所属税理士や税務会計スタッフの詳細、
サービスや料金はこちらでご確認下さい。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所 】

東品川・北品川で税理士の会社設立・起業支援
匠税理士事務所では、品川全体に対応する
日本政策金融公庫の五反田支店と連携をとり
多くの創業融資で起業支援をしてきました。
会社設立・起業後の最重要課題は、
生き残ることで、そのために資金調達は不可欠です。
匠税理士事務所では会社設立と創業融資で
品川でトップレベルの起業支援実績があり、 融資の成功率は9割を超えています。東品川や北品川など品川エリアで会社を設立し、
起業に必要な資金の一部について、
創業融資制度による起業支援を利用したい方は、
お気軽にご相談下さい。
東品川や北品川担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

東品川や北品川など品川区で株式会社など
会社設立による起業支援はこちらから
東品川や北品川で創業融資による創業支援
起業家の方に向け創業融資による起業資金の調達を
東品川や北品川でサポートしてます。
創業計画書作成や融資面談の立会など
普通の税理士事務所では行わないところまで
手厚いサポートが特徴です。
起業時資金調達サービスはこちらで確認下さい。
ご希望の方には、城南信用金庫と連携した
会社設立時の品川制度融資も承ってます。

東品川や北品川の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は東品川や北品川など品川全域対応)
東品川や北品川での会計代行や経営支援
東品川や北品川など品川エリアで既に事業を
経営されている方に向けて、
会計のアウトソーシングやアウトソーシングで
得られたデータを活用した経営コンサルティングを
提供しております。
経営セミナー講師を務める税理士が担当し、
関与先様の黒字率は94%となっております。・経理担当者が辞めて、会計代行を検討中
・会社を大きくしたいが、経営支援してほしい
・利益率の改善など黒字化したい。
東品川や北品川で上記のご希望をお持ちの方は、
お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の経営支援サービスはこちらから
【→法人のお客様向けサービス】

東品川や北品川の確定申告や決算・経理会計
東品川や北品川で個人事業をされている方に向け
青色申告や確定申告、決算の代行から
会計や経理のアウトソーシングを承ってます。
事業が大きくなってきたので税理士に任せたい方や
株式会社にする法人化にも対応しております。
匠税理士事務所の個人の方向けサービスはこちらから
【 → 個人のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
東品川・北品川で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】
東品川や北品川など品川地域から
匠税理士事務所までのアクセスにつきましては、
アクセスページをご利用ください。
近隣にはコインパーキングもございまして、
コインパーキングの情報はアクセスページにございますのでご活用いただければ幸いです。
東品川や北品川の会社設立・法人化登記情報
品川区の東品川・北品川で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
東品川や北品川など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が東品川や北品川で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
東品川や北品川近くの税理士事務所や会計事務所での就職をご検討中の方へ
匠税理士事務所は、正社員スタッフ、
アルバイトスタッフを募集しております。
北品川(きたしながわ)・東品川(ひがししながわ)
品川近く税理士・会計事務所で就職を検討中の方は
下記より詳細を確認の上、ご応募下さい。
その他の匠税理士の法人化や法人成りなど
業務内容や会社設立の料金や質問は
上記よりTOPページにてご確認下さい。
東品川や北品川など品川区の方への会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りの当会計事務所紹介を確認頂き感謝致します。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#北品川税理士事務所
#東品川会社設立
業務提携・事業提携を募集中。商標登録に強い弁理士、特許事務所の方へ (14/02/08)
匠税理士事務所では
商標登録や各種特許登録に強い弁理士の先生、
特許事務所の方などとの業務提携・事業提携を募集中しております。
匠税理士事務所が業務提携先・事業提携先に求めること
匠税理士事務所が、
業務提携先・事業提携先の
弁理士の先生や特許事務所の方に求めることは、
商標登録や各種特許登録を通じた
「 お客様の利益の最大化 」 です。
この理念に共感して頂ける弁理士の先生や特許事務所の方との
お仕事を通じて、弊所のお客様に喜んで頂ける環境作りを目指しています。
商標登録や各種特許登録など弁理士先生や特許事務所の方に依頼する業務
具体的な業務内容としましては、
アパレル事業の方の商標登録や、
IT事業に関する特許登録など
お客様のビジネスで生じてくる権利関係への対応となります。
上記の商標登録や特許業務などを
サポートして下さる弁理士、特許事務所の先生は、
下記リンクURLにて内容をご確認の上、
ご連絡を頂けましたら幸いです。
→ 匠税理士事務所との業務提携や事業提携の募集・応募について
ご検討の程、宜しくお願いします。
匠税理士事務所の事務所概要
匠税理士事務所の事務所概要や、
自由が丘駅から事務所までのアクセスなどにつきましては、
下記のリンクよりご確認をお願いします。
所属税理士のプロフィールはこちらからご確認下さい。
その他の各種業務内容や料金体系など
上記以外の情報につきましては、
下記のリンクでトップページへ移動しますので、
こちらからご確認をお願いします。
→世田谷区 税理士の匠税理士事務所HPへ
最終更新日:平成26年2月8日
西五反田や東五反田近くの匠税理士事務所・会計事務所 (14/02/02)
匠税理士事務所への訪問ありがとうございます。
弊所では、西五反田や東五反田の会社設立など
【創業支援】や【経営支援】に力を入れてます。
創業支援と経営支援でお客様のお役に立つために 【人材・提携先の充実 】が重要と考えており、 税理士・社労士・弁護士などの質に強みがあります。匠税理士事務所・提携先の専門家や
サービス一覧などの事務所概要につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

西五反田や東五反田の会社設立や起業支援
西五反田や東五反田など品川で起業される方に、
40代の税理士が提携している司法書士と共に、
法務コンサルティングも交えた会社設立サポートや、
日本政策金融公庫の品川区の五反田支店と連携し、
創業融資による起業資金調達をサポートします。
会社設立・創業融資など起業支援では、
品川地域でトップクラスの実績を有しており、弊所独自のサービスも多数ございます。
西五反田や東五反田担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

匠税理士事務所の西五反田や東五反田での
起業支援サービスはこちらでご確認下さい。

西五反田・東五反田の創業融資による創業支援
【会社設立など起業時は資金調達チャンス】その理由は、経営してしばらくすると金融機関は、
実績である決算書を軸に融資の判断を行います。
創業してすぐに結果を出すことは難しいのですが、
創業時は決算書がありませんので、
これからの事業展開を創業計画書でしっかりと
説明できれば融資を獲得しやすいのが現状です。

匠税理士事務所では西五反田や東五反田など
品川区で創業計画書作成サポートから、
金融機関との審査面接の立ち合いなど
独自の創業融資による創業支援を展開し、
日本政策金融公庫の五反田支店様や
各種金融機関と連携しており、
創業融資による創業支援で多くノウハウを有します。
会社設立後の創業融資による創業支援は、
こちらからご確認お願い致します。
西五反田や東五反田など品川全域の会社設立に対応

西五反田や東五反田の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は西五反田や東五反田など品川全域対応)
西五反田や東五反田などの会社の経営支援
匠税理士事務所の最大の特徴は、
経営支援でお客様の約9割が黒字ということです。 この黒字率を100%にすることを使命として、 財務・経営コンサルティングに力をいれてます。・利益率の改善をしたいので、
会計など相談できる相手を探している。
・五反田など品川に近い会計事務所を探している。
・会社の規模が大きくなってきたが、
何か統率できる方法がないか考えている。
・黒字にしたい。
・経営について話が分かる税理士がいい。
など事業を改善するためのパートナーを五反田など
品川でお探しの方は、お気軽にご相談下さい。
経理や会計アウトソーシングや経営支援は
こちらからサービスをご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
西五反田や東五反田の方向け確定申告・経理代行
法人化など個人サービスはこちらから。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
西五反田や東五反田で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

会社設立や法人化・法人成り・コンサルティングを担当する
税理士のプロフィールはこちらから
西五反田や東五反田からのアクセス
西五反田や東五反田から匠税理士事務所へ
ご来訪頂く場合、東急池上線・東急東横線を
ご利用頂き旗の台の乗り換えが便利です。
電車での時間は約20分ほどで、
自由が丘駅から2分アクセス便利な会計事務所です。
日本政策金融公庫五反田支店で融資の声
西五反田で会社設立して起業する上で
機械や仕入などかなりの初期費用が必要でした。
融資支援をしてくれる同世代税理士を探していて
匠税理士事務所にお世話になることになりました。
会社設立後の創業融資の創業計画書作成も
一緒になって丁寧に教えてくれて、
面談当日のリハーサルや面談にも一緒に
立ちあってくれてとても頼もしかったです。
無事満額実行して頂くことができて、
大変感謝しております。
これからもよろしくお願いします。
<西五反田卸売業で会社設立 株式会社M様>

法人設立や創業融資以外のサービス内容や、
各種料金、西五反田や東五反田からの匠税理士事務所へ
アクセスはアクセスページで確認下さい。
西五反田や東五反田の会社設立・法人化登記情報
品川区の西五反田・東五反田で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
西五反田や東五反田など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が西五反田や東五反田で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
西五反田や東五反田の税理士事務所の求人採用情報
西五反田(にしごたんだ)・東五反田(ひがしごたんだ)近く
会計事務所の求人や採用情報をお探しの方は、
下記ページより匠税理士事務所の
求人・採用情報をご確認下さい。
西五反田や東五反田など品川エリアにお住いの
皆様からのご応募をお待ちしております。
西五反田や東五反田エリアは品川税務署の管轄となります。
確定申告の相談に行く時間がないので任せたい
という方もお気軽にお問い合わせください。
西五反田や東五反田など会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い会計事務所をお探しならお気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#東五反田税理士
#東五反田会社設立
法人設立や会社設立が専門の司法書士事務所との業務提携募集 (14/02/01)
匠税理士事務所では、
起業に伴う法人設立、会社設立業務に共に取り組んで頂ける
司法書士事務所との提携先を募集しております。
業務提携先の司法書士事務所に求めること
提携司法書士事務所の先生に求めることは、
会社設立などや会社の各種登記で、
「 お客様の利益を最大化できること 」 です。
この理念に賛同いただける司法書士の先生からの
ご連絡をお待ちしております。
業務提携後の流れ
業務提携に関して、
双方の合意となりましたら、
お客様よりご要望を頂き次第、
お客様にとって最善と思われる司法書士の先生に
各種会社の登記に関する業務を
お願いすることになります。
匠税理士事務所に
お力をお貸し頂ける司法書士事務所の先生は、
以下のURLをご確認の上、ご連絡を頂ければ幸いです。
ご検討の程、宜しくお願いします。
匠税理士事務所のサービス内容などにつきましては、
下記のリンクよりTOPページへ移動しますので、
こちらからご確認下さい。
世田谷区 税理士 弊社HPはこちらへ
匠税理士事務所との業務提携や事業提携の募集・応募について (14/02/01)
匠税理士事務所では、
業務提携や事業提携をご検討頂ける
以下の事務所や企業様を募集しております。
業務提携や事業提携の募集や応募をしている事業
匠税理士事務所では、
お客様への一層のサービス向上のため、
下記の業務につき、
業務提携や事業提携を検討しております。
・給与計算や社会保険手続、就業規則作成をご担当して頂ける社会保険労務士の先生
(詳細:給与計算や就業規則を担当する社会保険労務士の業務提携募集)
・会社に関する各種登記業務を担当して頂ける司法書士の先生
・会社設立や各種許認可申請を担当して頂ける行政書士の先生
(詳細:会社設立や許認可申請など業務提携をご検討頂ける行政書士の方へ)
・補助金申請代行の中小企業診断士・行政書士の先生
(詳細:補助金申請代行の中小企業診断士・行政書士との提携募集)
・商標権や特許権などを担当して頂ける弁理士の先生
(詳細:業務提携・事業提携を募集中。商標登録に強い弁理士、特許事務所の方へ)
・会社の融資や起業時の創業融資を担当して頂ける金融機関の方
(詳細:銀行や信用金庫など金融機関との業務提携先を募集中 )
業務提携先や事業提携先に求めること
私たちが、
業務提携先や事業提携先に求めることは、
「 お客様の利益の最大化に貢献できること 」 です。
この理念に共感して頂ける方は、
匠税理士事務所の
税理士水野宛にご連絡をお願いします。
(電話番号:03-6272-4704)
メールの場合には、takumi-info@takumi-tax.jp へ
メールをお願いします。
その他の業務や事業に関する提携について
上記の業務や事業以外にも、
お客様のお役に立てる業務や事業がございましたら、
上記の連絡先へご連絡を頂けましたら幸いです。
ご連絡をお待ちしております。
匠税理士事務所のサービスラインなどにつきましては、
下記のリンクよりTOPページにてご確認下さい。
世田谷 税理士は匠税理士事務所
最終更新日:平成27年10月1日
経営理念(ビジョン)など会社理念や企業理念を作りたい方へ (14/01/31)
KK3 経営理念を作りたいとは思うのですが、やはり会社として経営理念(ビジョン)は、ないといけないものでしょうか?
このようなご質問を頂きました。
経営理念(ビジョン)を作るのは、大事ですが考えすぎは禁物です。
経営理念は確かに大事です。
しかし、そう簡単には作れるものではなく、経営理念を作ることは、とても大変なことです。
なぜなら、会社の今後の数年又は数十年先の中心となるものを、1日や2日で作れるはずがないのです。
お客様と向き合って、頂いた感謝の言葉やお叱りの言葉など、会社としての色々な経験を通じて、
今後どのようなお客様に、どのような商品又はサービスで
お役に立つ会社を目指すかという方向性(ビジョン)が決まるものです。
一方で、株主が他にいて株主総会がある会社様や、投資会社が入っている会社様を除いて
社長様=株主で従業員さんが50人以下の会社様であれば
意外と起業時の精神がそのままビジョンになるケースも多いです。
お勤めからなぜ、会社を立ち上げたのか。
自分の仕事上、絶対譲れないポリシーが何かを考えると初期の段階ではビジョンが定めやすいように思います、
ビジョンだけで数枚のページにわたるようなものを作ってしまうと、自分の考えが中心になった計画になってしまい あまり良い計画とはなりません。
一度、これだけは譲れないものを短い言葉で箇条書きにしてみて、実務の中であっているものは残し、間違っているものは躊躇なく消す作業を繰り返し、月日をかけて決めていくことも可能なのです。
会社理念や企業理念など経営理念を作るのは社歴何年頃が多い?
会社理念や企業理念など本格的に経営理念を作られる会社は、
社歴として10年目かの会社が多いように思います。
やはり、実際のお客様の声に勝るものはなく、このお客様の声を踏まえて、
本物の経営理念(ビジョン)が出来上がっていくので、
これだけ長い年月を要するのではないでしょうか。
ご自身と社員様の会社なのですから、素敵な言葉ではなくても良いですし、違ったら変えていけば良いのです。
<経営理念(ビジョン)がない、起業間もない会社はどうすべきか
起業間もないときは、お客様が少ない場合が一般的ですので、なかなか最初はお声を頂く機会も少なくなります。
そのため、具体的な経営理念(ビジョン)を作るのは社歴が長い会社に比べて難しくなります。

そのような場合には、「 人類に貢献する 」 など
漠然とした理念を掲げるのではなく、
商売の原理原則である
「 お客様のご要望を満たす会社になる。 」
これだけでも良いと思います。
このような姿勢で取り組んでいる限り、お客様から愛される会社になりますし、
そのような会社は生き残ります。
そしてお客様から様々なお声を頂くことで、より具体的な経営理念(ビジョン)になっていきます。
・採用しようとする人材は、お客様のご要望を満たせるか
・売れないということは、お客様のご要望を満たせていない、何が改善点なのか
・お客様のご要望を満たせ、売価が最大化されたものは何か
これだけでも立派なビジョンなのです。
経営理念は、本やセミナーの中にはありません。
御社のお客様のありがとうの中に眠っているのです。現場主義で、よく自社を見るとその中に答えがあります。
経営理念(ビジョン)がなければ、会社が傾くのではなく
どんな経営理念(ビジョン)を持っていればお客様のご要望にもっと応えられるか
会社が変な方向へ行かないように初心忘るべからずのために持つ指針のようなものです。
経営理念や経営計画作成を支援するコンサルティングサービス
匠税理士事務所では、これまで数多くの会社様の経営理念作成や経営計画作成を支援してきました。
経営理念(ビジョン)や経営計画を作成にご興味のある方は、お気軽にご相談下さい。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
東京都の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
目黒本町や都立大学近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/01/26)
匠税理士事務所へご来訪ありがとうございます。
弊所は平成20年3月に設立し、
都立大学・目黒本町という目黒区を拠点に
【起業支援と経営支援】に力を入れる事務所で、
都立大学や目黒本町など目黒のお客様が多く、 【人の質】・【専門性】が高い税理士事務所です。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
弊所の税理士や提携先・サービスなどは、
こちらからご確認下さい。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

目黒本町や都立大学の会社設立など起業支援
弊所は代表税理士が40代ということもあり、
同世代の若いお客様が多くいらっしゃいまして、
会社設立など創業支援に力を入れてます。
【起業に必要な全てそろう税理士事務所】を軸に、目黒本町や都立大学で会社設立の代行、
その後の会計・経理のアウトソーシングや、
決算書の作成、税務申告書作成をはじめとして、
創業後に必要な資金を調達する創業融資や
給与計算・社会保険の加入手続きも行っております。

また助成金の申請代行や契約書作成の法務サポートや、
官公庁の許認可申請や特許商標の登録、
申請対応等も承っております。
目黒本町や都立大学担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

目黒本町・都立大学の起業家向け会社設立代行や
会計・給与計算はこちらをご確認下さい。
【 → 目黒区での会社設立サービス 】

目黒本町・都立大学の創業融資など創業支援
【創業融資の資金調達で独立開業を創業支援】会社設立時に創業融資を検討される方には、
自己資金と必要資金のバランスを伺って、
融資可能額の検証や資金調達先の選定など
コンサルティングも承っております。日本政策金融公庫や目黒本町や都立大学など目黒が
地元の城南信用金庫など金融機関と提携してます。
サービスの詳細につきましては、
こちらからご確認をお願いします。
【 目黒での創業融資や起業の資金調達 】

会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
<税理士は目黒本町・都立大学など目黒全域対応>
目黒本町や都立大学近く法人向け経営支援
お客様の黒字率100%実現をミッションとして、 都立大学や目黒本町など目黒エリアを拠点に 経営コンサルティングに力を入れております。従来の会計事務所のサービスである
会計アウトソーシング、経理や給与計算代行や
決算や確定申告、法人化なども承ってますが、
アウトソーシングで得られた会計データを活用し、
経営改善のための提案を行っております。
経営者向け支援・法人化等の税務コンサルティングはこちらをご確認下さい。
会社様向けサービスはこちらからご確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧】
目黒本町や都立大学の方向け個人サービスはこちらから
【 → 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
目黒本町・都立大学で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

目黒本町・都立大学から会計事務所アクセス
目黒本町や都立大学の最寄駅からのアクセスは、
上記にございます弊所の事務所概要ページより
ご確認頂けましたら幸いです。
最寄駅は目黒の自由が丘駅で、
駅より徒歩2分の場所にある会計事務所です。
目黒本町や都立大学の近くで会計事務所や税理士事務所の求人・採用情報をお探しの方へ
業務拡大に際しまして正社員スタッフと
パートスタッフを募集しております。
目黒本町や都立大学にお住いの方で興味のある方は
下記をご確認の上、お気軽にお申込み下さい。
都立大学や目黒本町など目黒地域のお客様に向けたその他の確定申告などの業務内容、
会社設立や法人化・法人成りなど各サービスに伴う料金は
上記リンクよりトップページにてご確認下さい。
目黒本町(めぐろほんちょう)や都立大学(とりつだいがく)の方に
向けたご案内につき最後までご確認頂きまして
ありがとうございました。
目黒本町や都立大学の会社設立・法人化登記情報
目黒区の目黒本町や都立大学で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
目黒本町・都立大学など目黒区で個人から会社設立する
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 渋谷出張所 】管轄区域 目黒区
〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号
(渋谷地方合同庁舎)
上記が目黒本町や都立大学で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
会社設立など起業支援・創業支援や
法人化・法人成りなどの御案内を最後まで
お読みいただきありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
令和6年10月12日更新
#都立大学税理士
#都立大学会社設立
尾山台・九品仏近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/01/20)
匠税理士事務所のホームページへ
ご訪問ありがとうございます。
弊所は尾山台・九品仏など世田谷地域から
アクセス便利な税理士事務所で
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 【経営支援で世田谷No1】を目指しております。また会社設立に伴う起業支援から、
海外展開する上場企業の税務会計に対応可能です。
これらの経験やノウハウを活用して、 幅広いお客様のニーズにお応えできる 会計事務所という特徴がございます。 【 匠税理士事務所に頼んで良かった 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
弊所の税理士や税務会計のスタッフなど詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

これまで税理士が対応させて頂いた業種
・ IT(ホームページ制作やシステム開発など)
・ メーカー(PCメーカー・薬品・洋服)
・ 広告代理店
・ 飲食店
・ 各種サービス業
・ 卸売
・ 小売業(インターネット通信版売含む)
・ 建設業など
尾山台や九品仏の会社設立など起業支援
弊所は世田谷の産業振興公社にて、
起業家向けセミナーの講師を担当し、
これまで世田谷の尾山台や九品仏での会社設立や
創業融資などの起業支援を行ってきました。
起業に必要な全てがそろう事務所を起業支援のポリシーとしております。
尾山台や九品仏担当の税理士・専門家はこちら
【→匠税理士事務所の概要】

起業支援対応エリア:尾山台・九品仏など世田谷区
尾山台や九品仏など世田谷で会社設立を検討中で、
会社設立代行、会計決算アウトソーシングをご希望の方は、
下記会社設立サービスをご確認下さい。
【→ 世田谷区での会社設立代行】
尾山台や九品仏の創業融資による創業支援
また、世田谷エリアで起業資金調達のための
創業融資による創業支援につきましては、
下記で弊所サービスを確認頂けましたら幸いです。
尾山台・九品仏に対応の金融機関をご紹介します。
【→ 世田谷の創業融資・資金調達 】

尾山台・九品仏の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は尾山台・九品仏など世田谷全域対応)

尾山台・九品仏で会社設立のみの相談も承ってます。
お気軽にお問い合わせください。
尾山台や九品仏の経理・確定申告や法人化
匠税理士事務所では、会社の会計や決算業務、
税務申告のアウトソーシングサービス、
利益拡大の経営コンサルティングに力を入れてます。
尾山台や九品仏会社様に向けた
財務会計や節税対策・経営支援サービスは、
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
尾山台・九品仏の方向けの確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
尾山台・九品仏で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

尾山台や九品仏など世田谷区で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
尾山台や九品仏から匠税理士事務所への地図
尾山台や九品仏から弊所へご来所される場合には、
大井町線の自由が丘駅からアクセスが便利です。
自由が丘駅から弊所への地図につきましては、
事務所概要ページにございます事務所への
アクセスをご確認下さい。
尾山台や九品仏など世田谷で税理士事務所の求人や採用情報をお探しの方
尾山台や九品仏など世田谷地域で、
税理士事務所の求人や採用情報をお探しの方は、
匠税理士事務所の求人採用情報を確認下さい。
匠税理士事務所は世田谷エリアNo1の働きやすい
会計事務所を目指しております。
九品仏や尾山台など世田谷地域の方からの
ご応募をお待ちしております。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
尾山台(おやまだい)九品仏(くほんぶつ)近くで
税理士や会計事務所をお探しの方に向けた
匠税理士事務所の紹介ページを
ご確認頂きありがとうございました。尾山台や九品仏での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどはお気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#九品仏税理士
#尾山台税理士事務所
銀行や信用金庫など金融機関との業務提携先を募集中 (14/01/18)
匠税理士事務所では、
お客様の満足度の一層の向上を目指しております。
そのため、
お客様の事業に、
全力で取り組んで頂ける銀行や信用金庫など
金融機関の方との業務提携を募集しております。
信用金庫や銀行など金融機関の方などと提携したい業務について
金融機関、銀行関係者の方などに
ご協力頂きたい業務内容としましては、
以下の通りです。
< 起業支援業務 >
・ 創業時における法人の新規口座開設
・ 起業した法人に対する創業融資(制度融資など)
< 起業以外の法人向け支援業務 >
・ 弊所の関与先に対する融資支援
・ 他金融機関からの借り換えのサポート
・ 住宅ローンのサポート
上記以外にも、
お客様からのご要望がございましたら、
臨機応変にご対応頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所との提携をご検討頂ける信用金庫、銀行など金融機関のの方へ
匠税理士事務所との上記業務の提携について
ご検討頂ける金融機関、銀行関係者の方は、
下記のリンクより詳細をご確認頂きました上で、
匠税理士事務所の
税理士水野宛にご連絡をお願いします。
(電話番号:03-6272-4704)
メールの場合には、takumi-info@takumi-tax.jp へ
メールをお願いします。
目黒区の自由が丘にある匠税理士事務所の事務所概要について
匠税理士事務所は、
目黒区の自由が丘に2008年に
設立された税理士事務所です。
弊所は、
関与先の黒字率100%を目指して、
経営コンサルティングに力を入れており、
現在関与先の約9割が黒字経営 という特徴があります。
今後もこの黒字率が100%になるように
お客様への経営コンサルティングに注力することを
事務所の使命としております。
匠税理士事務所の所属税理士のご紹介
弊所に所属している税理士の詳細につきましては、
下記よりご確認下さい。
今後もお客様の満足度向上のため、
随時税理士など有資格者の増員を検討しておりますので、
追加され次第、更新させて頂きます。
事務所のサービスラインや概要などにつきましては、
以下のリンクよりトップページへ移動の上、
ご確認をお願いします。
→ 世田谷区や目黒区、品川区など東京都の税理士は匠税理士事務所
最終更新日:平成26年2月8日
武蔵小山・西小山近く税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (14/01/04)
匠税理士事務所HPに訪問ありがとうございます。
弊所は、世界4大会計事務所出身の税理士を中心に女性税理士・税理士有資格者など計10名の事務所で、
【 起業支援 や 経営支援 】に強みがあります。起業支援や経営支援の一環として、
東京商工会議所品川支部で経営セミナー講師を
商工会議所本部で起業セミナー講師を担当しました。
【豊富な経験】と【高度な専門性】を活用し、
お客様のお役に立てるように努めており、
起業支援・経営支援で品川地域NO1を目指します。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の所属税理士やスタッフ、
サービス概要はこちらでご確認をお願いします。

(税理士対応:武蔵小山・西小山など品川区全域)
武蔵小山・西小山・小山台で会社設立・起業支援
弊所は、会社設立のための方向性の確認から、
会社ルールである定款作成、司法書士と連携し登記など
会社設立代行サービスをご提供しております。
【 お客様は社名を考えるだけで後はお任せ 】をコンセプトにし、
【 創業に必要な全てがそろう会計事務所 】を心掛けております。
また、会社設立後の経理はもちろん、
武蔵小山や西小山、小山台など品川区を担当する
日本政策金融公庫の五反田支店と連携して
創業融資コンサルティングも行っております。
武蔵小山・西小山担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

武蔵小山・西小山での株式会社の会社設立など
具体的な会社設立などの起業支援サービスの詳細は
こちらからご確認をお願いします。
【→品川区での会社設立の代行】

武蔵小山・西小山・小山台の創業融資・創業支援
品川区でこれから起業をお考えの方に向けて、
創業計画書の作成や融資面談対策も行います。
品川区の制度融資を受けたい方には、
城南信用金庫など連携してますので、
武蔵小山や西小山、小山台など品川エリアの
お客様の創業支援を致しております。
詳細はこちらからご確認をお願いします。

武蔵小山や西小山、小山台の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(創業支援は武蔵小山や西小山、小山台など品川対応)
武蔵小山や西小山、小山台の税理士の経営支援
弊所では会計のアウトソーシングサービスを通じて
整理した会計データという事実に基づいた
経営コンサルティングに力を入れております。
会計のデータを税務申告や金融機関への
決算など融資提出書類だけに終わらせず、
会計データを利用して効果的な経営をしたい
経営者の方を支援しており、
【お客様の黒字率100%を目標としております。】武蔵小山や西小山、小山台で経営支援を
担当する税理士・提携専門家などはこちらから
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
武蔵小山・西小山で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

武蔵小山で会社設立された客様の声
起業前に会社設立セミナーに参加し、感じがよく、
色々と相談にのってくれそうだったので、
武蔵小山の商店街の喫茶店で一度お話を聞いて
頂いて税務顧問契約をお願いしました。
経理や税金もしっかりと対応してくれて、
会社のことで色々と相談にものって
もらって大変助かっています。
これからも宜しくお願いします。
(武蔵小山サービス業 会社設立A様)
西小山で税理士による法人化の会社様の声
西小山の会社近くで税理士を探してたところ、
匠税理士事務所さんを見つけてさっそく話を
聞いてみました。
会社の利益・お金を貯めるためには、
自社は何をすべきなのか
とても分かりやすく説明して下さったので、
お願いすることにしました。
経営の相談にものってくれるので満足してます。
(西小山IT関連 法人化の株式会社K様)
その他の武蔵小山・西小山など品川区での業務内容や各種報酬などにつきましては、
上記よりトップページにてご確認下さい。
武蔵小山・西小山の会社設立・法人化登記情報
品川区の武蔵小山・西小山で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
武蔵小山・西小山など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が武蔵小山・西小山で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
武蔵小山・西小山や小山台近くの税理士事務所の求人採用
武蔵小山や西小山、小山台近くで、
税理士事務所の求人や採用情報をお探しの方は、
下記の求人・採用情報の詳細をご確認下さい。
西小山や武蔵小山、小山台など品川エリアの方からの
ご応募をお待ちしております。
武蔵小山(むさしこやま)・西小山(にしこやま)や
小山台(こやまだい)近くで税理士・会計事務所を
お探しの方にむけた匠税理士事務所の紹介ページを
ご確認頂きありがとうございました。
武蔵小山、西小山、小山台で会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りを要望の方はお気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#武蔵小山税理士事務所
#西小山税理士事務所
創業融資のお役立ち情報バックナンバー<2> (14/01/01)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー①
会社設立後の創業融資についてのお役立ち情報バックナンバー
これから創業融資をご利用しようと考えているお客様に向けた情報を発信しているページです。
バックナンバー①に入りきらかったものを掲載しております。
こちらは 創業融資のお役立ち情報バックナンバー<2> です。
記事に関しましては免責事項をご確認ください。
記事に関するご質問や無断掲載などはご遠慮いただけましたら幸いです。
第15回 起業や開業に必要なお金の確保と資金調達先にはどこがあるか
第16回 世田谷区の制度融資の仕組みと創業融資
第17回 日本政策金融公庫の創業融資、実際の流れ
第18回 必見!創業融資成功のための4つのポイント
第19回 品川区の制度融資の内容や仕組みと創業融資
第20回 商工会議所世田谷・目黒・品川支部と連携したマル経融資
記事については免責事項をご確認下さい。
匠税理士事務所の創業融資や会社設立サービス
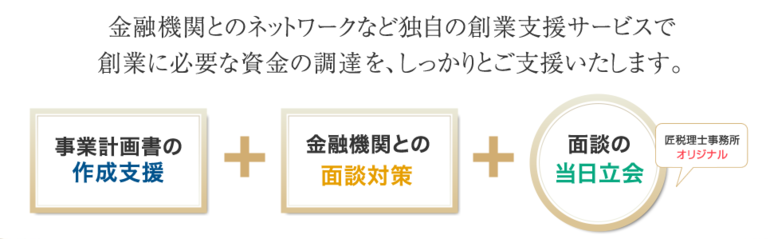
匠税理士事務所では、創業における今後の展開をヒアリングさせて頂き、そこから事業計画書の作成サポートや、金融機関との融資における面談の事前練習と、金融機関担当者との面談当日の立会いなどまでサポートする創業融資支援サービスをご用意しております。
創業融資支援サービス
起業支援サービス一覧
また、創業融資と一緒に会社設立をご検討されている場合には、会社の設立と会社設立後の経理も丸ごとバックアップする会社設立代行サービスをご用意しております。会社設立代行サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
世田谷・目黒・品川の会社設立の代行...会社を作るお客様向けの設立・経理や税金、経営のサービス。
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
給与計算サービス...給与計算の代行や、社会保険の加入手続き、人事労務のサポートサービス。
助成金サービス...正社員化や社員教育についての助成金代行とコンサルティングサービス。
法人のお客様向けサービス...黒字戦略や財務強化などのオリジナルサービスのご紹介
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。皆さまからのご連絡をお待ちしております。
世田谷 税理士 をお探しなら匠税理士事務所へご相談下さい。
上馬や下馬近くで会計事務所や税理士をお探しの方へ (13/12/27)
匠税理士事務所のWEBサイトへ
ご訪問頂きましてありがとうございます。
弊所は目黒と世田谷の中間地点に位置するため、
上馬や下馬などの世田谷や目黒の会社様を
多く担当させて頂いております。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に税理士科目合格者4名、FP3名の計10名の事務所で、
【起業支援】・【経営支援】が評判の事務所です。
人の質やサービスの質にこだわることで、 【お客様満足度の最大化】を目指しております。
匠税理士事務所の税理士やスタッフ、サービスは、
こちらからご確認下さい。

上馬や下馬で税理士の会社設立や起業支援
弊所税理士は世田谷の産業振興公社が主催する起業家支援セミナーの税務部門の講師を担当し
これまで多く上馬や下馬など世田谷で
起業される方の会社設立を支援してきました。
そのため、上馬や下馬など世田谷での会社設立や
創業融資など起業支援に多数実績があります。
また、起業後の会計や税務申告代行など
起業支援のサービスが豊富です。
上馬や下馬で会社設立や起業をご検討中で、
起業支援をご要望の方は、ご相談下さい。
担当税理士や事務所概要はこちらを確認下さい。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

上馬や下馬など世田谷区で株式会社など
匠税理士事務所の会社設立代行による
起業支援はこちらにてご確認下さい。
【→世田谷区での会社設立サービス 】
上馬や下馬の創業融資による創業支援
上馬や下馬で会社設立以外にも創業融資や、
起業後の会計・経営支援につきましては、
下記よりご確認をお願いします。
上馬や下馬に対応の信用金庫や日本政策金融公庫と
連携した創業融資はこちらを確認下さい。

上馬や下馬の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は上馬や下馬など世田谷全域対応)
上馬や下馬の会社の会計・経営支援・法人化
既に会社を経営されていらっしゃる方には、
会計や経理のアウトソーシングや、
これらアウトソーシングを通じて得られた会計情報を
活用した経営コンサルティングも提供してます。
また 個人事業主から株式会社にするための
法人化・法人成もご提供しております。
サービス詳細は下記よりご確認下さい。
弊所では、これらの専門性と人材のサービス力や
提携先の充実を通じて上馬や下馬など
世田谷のお客様より一層支持される
【 満足度NO1の会計事務所を目指します。】法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
上馬や下馬で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】
上馬や下馬など世田谷区で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】

上馬や下馬から匠税理士事務所のアクセス
上馬/下馬から弊所へ電車でいらっしゃる場合は、
上記の事務所概要ページにございます乗換検索を
ご利用されると便利です。
また、お車でご来所される場合には、
事務所近くコインパーキングの利用が便利です。
コインパーキングの一覧や上馬や下馬から事務所へ
のアクセスこちらでご確認をお願い致します。
【 → 匠税理士へのアクセス 】
上馬や下馬の求人や採用情報をお探しの方へ
上馬や下馬の求人や採用情報をお探しの方は、
アクセスが便利な弊所も是非ご検討下さい。
弊所の採用情報をご覧頂きまして、
ご連絡を頂けましたら幸いです。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
皆様からのご応募をお待ちしております。
上馬や下馬での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#下馬税理士
#下馬起業支援
品川区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人 (13/12/23)
匠税理士事務所の品川区の方に向けた
求人採用情報をご覧頂きありがとうございます。
今回の採用求人は、会計税務を担当して頂ける
正社員・パート・アルバイトスタッフを募集します。
品川区の正社員・パートアルバイト求人採用
匠税理士事務所の特徴と致しましては、
起業支援や経営コンサルティングに定評があり、
上昇志向の品川区のお客様が多いのが特徴です。
私たちは、お客様の成長ニーズに応えるため
サービスや能力向上の研鑽に注力しています。
また、全員が30代・40代で、現状に満足せず、
今後も絶えずサービスラインを増やし、
お客様と一緒に拡大していきたいと考えてます。
今回の品川区のエリアに向けた求人採用では、将来の幹部候補の正社員やパートスタッフを募集します。
詳細はこちらからご確認をお願いします。

匠税理士事務所の求人採用情報の詳細
弊所では、お客様の利益に貢献し、
「お客様の黒字率100%を目指しております。」
この結果として、
【 お客様利益 の最大化 】 と 【 社員の幸福 の最大化 】を目指します。この使命を達成するためには、
優秀な社員の方の力が不可欠ですので、
一緒になって頑張って下さる方を、
今回の採用・求人では求めています。
給与など待遇は、品川区でトップレベルの水準でここ【 6年間の退職者はゼロ 】です。
正社員スタッフやパートスタッフ、
アルバイトスタッフを募集してますので、
待遇などの諸条件につきましては、
下記採用・求人ページでご確認下さい。
利益還元や働きやすさを大切にしますので、 残業がなく、勉強や子育てなど私生活が充実します。働きやすさNo1の税理士事務所を目指した
事務所づくりの取り組みを今も続けており、
【 ここ6年間の退職者ゼロ 】が最大の特徴です。
また今後もスタッフの方の働きやすさを求め、
より良い環境作りに努めております。
品川区など近所ので採用求人情報をお探しで、
税理士事務所や会計事務所で勤務を検討中の方から
ご応募をお待ちしております。
【 →会計事務所の求人や採用、就職・転職は匠税理士事務所へ 】

こんな税理士がいる会計事務所です。
匠税理士事務所には、BIG4出身の税理士や
コンサルティングファーム、金融機関出身者など
様々なメンバーが活躍しています。
色んなキャリア、様々な方が活躍する会計事務所で
人が残って、育つ環境が強みの税理士事務所です。
【 百聞は一見にしかず。 】というこで、
こちらの事務所概要をご覧頂けましたら幸いです。
【 →起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】

品川区から匠税理士事務所のアクセス
匠税理士事務所は品川区へのアクセスも
大変便利な位置にございますし、
東横線や大井町線、目黒線・多摩川線など
通勤にも便利な場所にある会計事務所です。
現在勤務して頂いているスタッフの方も
品川区近くにお住いの方もいらっしゃいます。
弊所へ品川区からアクセスにつきましては、
下記ページ乗換路線情報でご確認下さい。
【 → 匠税理士事務所へのアクセス 】

採用求人にある品川区近く匠税理士事務所とは
この品川区エリアの方に向けた採用求人にある
匠税理士事務所とはどんな事務所なのか?
サービスライン全体やセミナー活動情報は、
下記のリンクでTOPページに移動しますので、
TOPページよりご確認ください。
所属税理士やサービスはこちらから
【 → 品川区の税理士は匠税理士事務所】

何かご不明な点がございましたら、
お気軽にご連絡下さい。
品川エリアの方に向けた求人や採用情報を最後まで
ご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#品川区税理士事務所求人
#品川区会計事務所求人
会社、法人や自営業の税金や税務と、その節税対策や方法とは (13/12/14)
会社、法人の経営をされている自営業の方にとって、
とても大変な思いをしてようやく確保した利益に、
約3割から4割の税金がかかってくる・・・・・・
確かに頭の痛い問題ですね。
この税金とうまく付き合って、
会社や法人を経営していくにはどうすればよいのでしょうか?
会社、法人の税金や税務とその正しい節税対策や方法とは
会社、法人の正しい節税対策や方法とは、
ずばり税法という法律に従って正しい節税対策を行うことです。
ここで税法という法律に従わず、
誤った節税対策や節税の方法をとってしまうと、
その後の税務調査で、
本来納めるべき税金に
ペナルティーの税金が生じてしまい、
余計に税額が増えてしまったり、
税務署から疑わしい会社であるという目で見られてしまい、
税務調査の頻度が増加してしまいます。
(関連記事: 税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象となる会社の決め方 )
(関連記事: 株式会社の税金はいつ、いくら支払う? )
(関連記事: 税務調査で一番怖い税金とは・・・・ )
それでは、
税法という法律に従って正しい節税対策とは、
簡単に言うと何なのでしょうか?

それはずばり、
税法というルールに定めている方法で、
課税所得(利益とほぼ同じ)を計算して
申告・納付を行うことです。
そのため、節税対策には様々な方法があります。
しかし、税額に大きな影響を与えることができる節税対策は、
かなり限られてきます。
節税対策のポイントは、
この数ある有効な打ち手の中から、
会社の利益状況に応じて最善の方法を選択することにあります。
誤った会社、法人の節税対策は、会社をピンチにする
先に述べたとおり、
節税対策は会社の利益状況を適切に読むことがポイントです。
例を挙げると、
100しか利益が出そうにない会社に対して、
200の節税対策をしてしまう、
すると税金は出なくても、
会社は大赤字になり、
資金繰りが圧迫してしまったり、
融資で不利になってしまったりということも起こります。
また、節税対策の中には、
会社全体での利益のバランスを加味したうえで、
経費とした金額が、
適正な金額か否かを判断してくる事項もありますので、
過度な節税対策は、
将来の税務調査で思わぬトラブルを引き起こします。
匠税理士事務所が提案する会社・法人向けの節税対策
匠税理士事務所では、
決算3か月前に会社・法人様に対し、
独自で開発したシステムを利用して利益を予測したうえで、
納税額の予測を実施し、効果的な節税対策を提案するという
納税シミュレーションを行っています。
この手法は、
株主配当を早期に計算する必要がある上場企業などが行っている
税金見込計算や税効果会計の検証などを行う ( tax accrual )の考え方を取り入れたものです。
【 以前の事務所では税額の通知が決算後に行われ、急に資金が必要となり困った。 】
【 全く節税対策をしてくれないので困っている・・・ 】
という経営者様からこの納税シミュレーションは、
大変ご好評を頂いております。
黒字で節税対策に困っている会社様、法人様や自営業者の方は、
お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所の事務所概要やサービスはこちらから
その他の経営お役立ち情報はこちらから
料金や事務所所在地などはこちらからご確認下さい。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
黒字倒産とは何か、どうやって防ぐのか? (13/12/11)
経営者の方は、黒字倒産という言葉を耳にしたことがあると思います。
それではこの黒字倒産は何故起きるのでしょうか?
事例を踏まえた黒字倒産の説明
倒産とは、お金がなくなって事業が立ち行かなくなることをことをいいます。
逆を言えば、会社は赤字でも外部から借入金などで資金調達できれば倒産しません。
それではなぜ黒字倒産が起きるのでしょうか。

2億円の商品を販売し、この仕入が1億円なら1億円の利益が出ます。
当然、黒字ですね。
そしてこの販売代金2億円が入金されるのが1年後、
仕入の支払いが、この入金前にきてしまって支払えない・・・・
他からの資金調達もできないようなら、
決算書では黒字でも倒産してしまいます。
つまり決算書上は、販売(納品)時点で利益を認識するのに対して、
入金はその後になってしまうというのがポイントです。
実際にはこの利益に対して約3割の税金も課されますので更に大変です。
黒字倒産をどうやって防ぐか(予防策は)
この黒字倒産の予防策にも色々とありますが、
「 入金は早く、支払は遅く。 」 を心掛けることが原則です。
それでは具体的にはどのようにして、黒字倒産を防げばよいのでしょうか。
1 入金のサイクルと支払のサイクルをできる限り同じにするように交渉する。
→ これらは売上先や仕入先との交渉になるので、なかなか厳しいかもしれませんが、
この厳しい交渉は社長の重要な仕事です。
2 大口の案件の場合には、前金で材料分など一部を入金してもらう。
→ これは大口の案件になる場合、当然として材料など仕入も大きくなります。
そのため、材料代など一部を前金で頂いておくことで、一時的な資金繰りの悪化を防げます。
3 資金が固定化してしまうような固定資産への投資へ慎重に検討する
→ 機械など設備投資をしてしまうと、多額のお金が一時的に出ていきます。
これに対して機械などの設備を利用して上がる利益は一時的には入ってきませんので、
大口の固定資産への設備投資は慎重に行いましょう。
設備投資による内製化の前に、外注を検討するのも有効です。
(関連記事 外注と内製化、どちらが会社にとって有利か )
4 売掛債権などが回収不能にならないように債権管理を徹底する。
→ 売掛債権などの回収不能は、
少しずつ改善した資金繰りを一瞬で悪化させます。
得意先の選定や、債権管理は徹底するようにしましょう。
(関連記事 与信管理のための企業情報で利益剰余金の調査は重要 )
5 最低6か月先までの資金繰り表を作る。
→ 会社を経営していく上では、
最低は6か月先の資金繰りは読んでいないといけません。
簡単なもので良いので、
半年先の資金繰り表を作成するようにしましょう。
(関連記事 中小企業と資金繰り対策(資金繰り表の作成) )
また、資金繰りは会社の生命線ですので、
経理担当者などに丸投げではなく、
経営者自身がしっかりと理解していないといけません。
黒字で、かつ資金繰りの良い会社を目指すには
黒字で、かつ資金繰りの良い会社が本当の優良な会社です。
それには上記のように資金繰りが良くなるような仕組みを作ること、
最低月商の2~3か月は余裕資金を会社に留保できるように努めること、
上手に借り入れをりようすること、
などが重要です。
黒字倒産を予防する匠税理士事務所のサービスとその他のお役立ち情報
上記で記載しました黒字倒産を防ぐため、匠税理士事務所では、中小企業の経営支援に力を入れております。
匠税理士事務所による会社経営者の方への経営支援サービスはこちらからご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
品川の税理士は匠税理士事務所へ...TOPページへ
中目黒や学芸大学近くの税理士や会計事務所 (13/12/09)
中目黒や学芸大学など目黒が拠点の匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。
弊所は、中目黒や学芸大学すぐの会計事務所で、
平成20年設立から目黒区を地元にしてきました。
税理士も全員30~40代のためお客様も中目黒や、学芸大学で同世代の方が多くいらっしゃいます。
事務所の特徴と致しましては、
【 世界4大会計事務所出身の税理士 】を中心に 【人の質】と【サービスの質】にこだわり、 【起業支援・経営支援】で目黒No1を目指してます。そこで、お客様のお役に立つためには、
【人材の質】と【高度な専門性】が最重要と考え、
優秀な人材と提携先充実に取り組んで参りました。
匠税理士事務所の所属税理士や専門家・サービスは、
こちらよりご確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

中目黒や学芸大学の会社設立や起業支援
匠税理士事務所は40代税理士が2名所属しており、
行政機関主催の起業塾のセミナー講師や、
東京商工会議所本部で経営指導員向け講師など
会社設立・起業支援で高い専門性がございます。【 同世代の税理士がいい 】というご支持も頂き
これまで中目黒や学芸大学で会社設立など起業支援を数多く担当しました。
中目黒や学芸大学で株式会社・合同会社の会社設立や創業融資などで税理士・会計士をお探しの方は
こちらからをご確認下さい。
中目黒や学芸大学を担当する税理士や
会計事務所の概要はこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の匠税理士事務所の概要 】

会社設立や経理・経営支援はこちらを確認下さい。

会社設立後間もない方、起業につきお悩みの方に、
起業に必要な全てをご用意致しております。
中目黒や学芸大学の会社設立後の経理・会計など
起業支援や創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】

創業するに際して資金調達を検討されている方に、
中目黒や学芸大学など対応の日本政策金融公庫など
金融機関と連携し起業に伴う資金調達・創業融資も対応致しています。
創業支援詳細は、こちらからご確認下さい。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資は匠税理士 】
中目黒や学芸大学近くの税理士事務所
当会計事務所は【お客様の黒字率100%】を目標に
公的機関経営セミナー講師などでノウハウ蓄積や、経営支援のための独自サービスを用意してます。
中目黒や学芸大学の法人様に向けた会計や決算、
税務や経営コンサルティングにつきましても、
世界4大会計事務所出身の税理士も所属しており
事業拡大後も安心して任せられると
中目黒の多くの法人様に好評を頂いております。
資本金1億円以上の法人にも対応可能です。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】

中目黒駅近くの確定申告や会計経理や決算・法人化の代行
匠税理士事務所は、起業支援や創業支援や
経営セミナーなど講師を東京商工会議所の
目黒支部様などで担当させて頂いております。
中目黒や学芸大学で個人事業をされている方の
事業の経営相談や確定申告代行、
会計経理や決算の代行から法人化につき
ご相談がございましたらお気軽にご下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
中目黒・学芸大学で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

中目黒駅や学芸大学駅から、
匠税理士事務所までのアクセスは
東急東横線で5分程になります。
最寄駅である自由が丘駅からの場所は、
サイドバーの会社概要ページに移動します。
こちらからご確認下さい。
また中目黒からお車でご来所の方には、
事務所近くにコインパーキングもございます。
中目黒での会社設立と創業支援の声
10年勤めていた会社を退職し、
中目黒で株式会社の会社設立をしました。
匠税理士の水野先生とは、会社設立前に
起業支援・創業支援セミナーを通じ知り合い、
これまで営業部だったこともあり、
お金や会計のことは全く知識がなかったため、
この事務所なら会社の力になってくれると考えて
匠税理士さんにお願いすることにしました。
会計やお金のことは完全にお任せしているので、
売上確保に専念出来て大変助かっています。
これからは、売上確保と合わせて
利益確保に力を入れなければいけませんので、
ご指導の程、よろしくお願いします。
中目黒会社設立 サービス業 T様
中目黒や学芸大学の会社設立・法人化登記情報
中目黒・学芸大学など目黒区で個人から
会社設立する法人化・法人成りはこちらから
中目黒や学芸大学など目黒区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 渋谷出張所 】管轄区域 目黒区
〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号
(渋谷地方合同庁舎)
上記が中目黒や学芸大学で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
中目黒駅・学芸大学近く税理士事務所お役立ち情報
中目黒駅や学芸大学近くには、
目黒区全域を管轄する目黒税務署がございます。
目黒税務署は中目黒駅や学芸大学から
アクセス便利な祐天寺駅より、
徒歩5分の場所にございます。
会社設立後の源泉所得税や各種税金の納付書が
必要な方や申告書などの用紙が必要な方は、
こちらでご相談にのって頂くことも可能です。
→ 目黒税務署 へのリンク
中目黒や学芸大学の税務申告書、届出書提出先 【 → 目黒税務署 】
管轄区域:目黒区
〒153-8633
目黒区中目黒5丁目27番16号
事業税・住民税の申告書、届出書提出先 【 → 渋谷都税事務所 】管轄区域・渋谷区・目黒区・世田谷区
〒151-8546
渋谷区千駄ヶ谷4-3-15
東京都渋谷合同庁舎4~7階
住民税などの申告書、届出書提出先上記が中目黒や学芸大学の税務申告や
会社設立時の税務届出書の提出先です。
期限までに決算関連書類の提出を行いましょう。
目黒区で会計事務所の採用や求人情報をお探しの方へ
中目黒や学芸大学など目黒で会計事務所の求人情報や採用情報をお探しの方は、
詳細を下記でご確認頂けましたら幸いです。
匠税理士事務所では、中目黒や学芸大学など
目黒エリアにお住いの皆様からのご応募を
心よりお待ちしております。
最後までお読み頂きありがとうございました。
(中目黒・なかめぐろ)や(学芸大学・がくげいだいがく)など
目黒区以外の会社設立など起業支援や創業支援、
法人化・法人成り等のお客様も対応してます。
ご不明な点などがございましたら
お気軽にご連絡下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#中目黒税理士 #中目黒税理士事務所
決算書の見方や読み方が分かるということ (13/12/08)
会社を経営していく上で、
決算書の見方や読み方をしっかりと理解しているということは、
とても重要です。
それは何故でしょうか?
決算書の見方や読み方が分かることで得られるもの
決算書の見方や読み方が分かることで、
得られるものは沢山ありますが、
その中でも代表的なものは以下の3つと考えます。
1 会社の現状を客観的に把握できる。
→ 数字は自社の問題点を正直に教えてくれます。
売上総利益率(粗利率)が下がっていれば、
商売の本業そのものの立て直しが急務であり、
販売管理費が膨れてきていれば、
無駄な経費が増えてきているということが分かるなど、
決算書の各指標は会社の長所と短所を正直に教えてくれます。
2 経営が変わり、社内が変わる
→ 数字に基づいた経営を行うことで、
問題への取り組みが的確に行えるので
業績改善を即座に行えます。
感覚に頼った経営では、何が問題なのか、
その打ち手は何が最善なのかが
見えなくなってしまいます。
また、数字に基づいて評価することで、
社内の評価が公平になったり、
社内での目標達成の度合いなどを明確に把握できるようになり、
実績を上げる人間が評価されるという本来あるべき姿になり、
社内の活性化にも役立ちます。
3 利害関係者(金融機関や取引先)との交渉力が向上する
→ 銀行担当者や新規の得意先に自社の業績を
社長自ら説明できる会社と、何も説明できない社長、
どちらが利害関係者(金融機関や取引先)からの信頼を
得られるかは言うまでもありません。
「 数字に強くて、経営能力がある社長 」 と見なされれば、
銀行の利率や新規得意先からの有利な条件の引出に当然有利となります。
決算書の見方や読み方を理解する上で必要な知識とは
それでは決算書の見方や読み方を理解する上で必要な知識は何でしょうか?
簿記などが必要なのでは・・・・
と思われるかもしれませんが、
簿記はあくまで帳簿を付ける際のルールですので、
このルールを経営者が自ら理解する必要まではないと思います。
それよりもむしろ、
経営者には全体としての決算書への理解が求められ、
決算書(貸借対照表と損益計算書)の見るべきポイントを抑えていることが重要です。
つまり全体として決算書を理解できていれば、
経営判断や利害関係者への説明は十分に可能です。
貸借対照表や損益計算書など会社の決算書の読み方や見方
それでは貸借対照表や損益計算書など
決算書の読み方や見方のポイントについて下記で記載してみました。
少しでもお役にたてると幸いです。
その他のサービスなどについてはこちらからご確認下さい。
目黒区の税理士は匠税理士事務所へ TOPページへ戻る
その他の経営お役立ち情報はこちらからご覧ください。
※経営コンサルティング お役立ち情報
最終更新日: 平成25年12月8日
三軒茶屋駅近くの税理士や会計事務所なら匠税理士事務所 (13/12/07)
ホームページへご訪問頂きありがとうございます。
匠税理士事務所は、三軒茶屋駅など世田谷地域で、
【起業支援 と 経営支援】を展開する会計事務所で、
世田谷産業振興公社主催の創業セミナー講師を担当する
世界4大会計事務所出身40代税理士が担当者になり 起業から上場企業まで広く対応可能な事務所です。また、人事労務の専門家である社会保険労務士、
法務は契約書作成や訴訟対応まで弁護士が対応し、
チームを編成する10名の税理士事務所です。
【個】にチーム力を加えた【総合力】でサポート、あらゆるご相談に対応できる体制を用意してます。
所得税理士やサービスなど概要はこちらから

三軒茶屋で会社設立・創業支援に強い税理士
匠税理士事務所の会社設立サービスでは、
お客様と税理士、司法書士の専門家が打合わせ後、
お客様に最適な会社設立のご提案を行います。
三軒茶屋など世田谷地域に対応の社会保険労務士・弁護士・行政書士による人事労務・法務という
創業に必要な全てのサービスをご用意しています。三軒茶屋など世田谷でこれから起業される方や、
起業して間もない方向け創業支援サービス一覧や
起業支援担当税理士・提携専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要】
会社設立後の経理・決算など起業支援や
創業融資など創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】

三軒茶屋など世田谷での株式会社や合同会社の会社設立をご検討中の方につきましては、
株式会社の会社設立サービスはこちらから
(会社設立対応エリア:三軒茶屋など世田谷区)
【 → 世田谷区での会社設立 】

三軒茶屋での創業融資など起業支援
匠税理士事務所は、三軒茶屋などの世田谷のエリアでこれから会社設立をお考えの方に向けて、
信用金庫や日本政策金融公庫など金融機関と連携し創業融資支援を行っており、
融資成功率は9割超と世田谷でもトップレベルです。
・創業融資に興味があるが、利率はどれ位で
返済期間はどれ位なのか一度話を聞いてみたい。
・自己資金と必要資金は適正かどうか、
銀行から見た判断を知りたい。
・創業融資を受けた方がよいか相談したい。
・三軒茶屋などで起業するが世田谷区の制度融資と
公庫融資の組み合わせを相談したい。
幅広い創業融資に対応しノウハウがございます。また創業計画書の作成支援から匠税理士事務所での
創業融資面接の立ち合いといった三軒茶屋の法人に
向けた独自のサポートをご用意しております。
【→ 世田谷の創業融資や資金調達支援】

経理代行や決算確定申告など税務サービス
会社設立や創業融資以外のサービスとしましては、
書類を送るだけで会計や経理、決算代行させて頂き
その後の業績報告や経営相談も行っております。
三軒茶屋の法人様に向けた
会計や経理、決算をアウトソーシングも対応してます。
また三軒茶屋で会社設立・創業融資の起業支援や
会計を活用したコンサルに力を入れてきました。
弊所税理士は実務15年以上の経験を有し、 上場企業税務会計担当の実績もございます。これらの経験・ノウハウを活かして、
【 世田谷の顧客満足No1 】の会計事務所を目指しております。
法人の経営者様向けサービスはこちらをご覧下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けサービスはこちらをご覧下さい。
【→ 個人のお客様向けサービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
三軒茶屋で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

三軒茶屋など世田谷エリアの会社設立や会計など
お客様からのご相談をお待ちしております。
三軒茶屋駅からの会計事務所へのアクセス
三軒茶屋駅から会計事務所までの乗り換え情報や、
自由が丘駅から弊所までの地図につきましては、
上記より会社概要ページに移動しますので、
ページ下部にございますyahoo乗り換え情報や、
グーグルマップなどにて三軒茶屋からアクセスなどご確認頂けましたら幸いです。
三軒茶屋地域で会計事務所の求人や、
採用情報をお探しの方は採用求人情報を
ご確認の上、お申し込み下さい。
【 → 三軒茶屋の税理士・会計事務所の採用求人】
会社設立などの起業支援・創業支援や法人化など
匠税理士事務所で活躍して下さる方からの
ご応募お待ちしております。
三軒茶屋近くの税理士事務所お役立ち情報
三軒茶屋を管轄する税務署は、
世田谷税務署になります。
三軒茶屋で会社設立など起業、
会社経営をされている方の税務申告書、
届出書提出先は以下の様になります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 税務申告書、届出書提出先 【 → 世田谷税務署 】管轄区域:世田谷区のうち中央部地区
〒154-8523
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎3階・4階
【 → 渋谷都税事務所 】管轄区域・渋谷区・目黒区・世田谷区
〒151-8546
渋谷区千駄ヶ谷4-3-15
東京都渋谷合同庁舎4~7階
上記が三軒茶屋などの会社設立届出書や
税務申告関連や届出書の提出先となります。
三軒茶屋の法人化・会社設立の登記情報
三軒茶屋など世田谷区で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
三軒茶屋など世田谷区での法人化や、
会社設立に伴う商業法人登記は
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が三軒茶屋で法人化・会社設立など
登記対応の行政窓口となります。
会社設立や創業融資などの起業支援や創業支援が
得意な税理士が在籍しており、
対応エリアは、三軒茶屋(さんげんぢゃや)など
世田谷区など東京全域の会計事務所です。

執筆者・文責:税理士 水野智史
#三軒茶屋税理士
#三軒茶屋会社設立
与信管理や信用調査のための企業情報で利益剰余金の調査は重要 (13/12/05)
・新規取引の依頼を頂いたが、
取引金額が大きいし、入金されるまでの期間が長い・・・・・
新規で取引をするための調査ではどこを見ればよいのだろう?
・業界で得意先の色んな噂を耳にするが、
与信管理の際に決算書のどこを見ると分かりやすい?
経営者の方でこのような悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。
それでは与信調査でどこを調べると効率的でしょうか?
利益剰余金は与信管理や信用調査では重要な企業情報

新規で取引する際に、相手先の決算書を確認するということもあります。
その際に色んな勘定科目がありますので、見るべきポイントは沢山あります。
例えば当期純利益。
これがマイナス、つまり赤字だと好ましくないのは当然ですが、
これがプラス、つまり黒字なら良いのでしょうか。
そうではありません。
前期以前は大赤字で、黒字なのかもしれません。
そこで資本の部にある利益剰余金という指標を確認すべきです。
利益剰余金は、会社を設立してからこれまでの獲得した利益の累計だからです。
したがって与信管理や与信調査の際に利益剰余金があれば、
会社を設立してこれまで累積で見て黒字経営をしている堅実な会社であることが分かります。
逆にここが大赤字だと、これまであまり経営が、
うまくいっていない会社ではないかと注意してみることが重要です。
利益剰余金は操作されにくい項目(マイナスの利益剰余金は要注意)
与信管理や与信調査の際に、注意したいのは粉飾決算ですが、
この利益剰余金は、会社を設立してからこれまでの累積であるため、
特定期間粉飾をして黒字にされていても、
継続的な赤字会社の場合には、この利益剰余金はマイナスになりがちです。
そのため利益剰余金は、与信調査や与信管理で有効な企業情報の一つとなるのです。
もちろん、与信調査・与信管理には様々な数字を利用すべきですが、
利益剰余金を確認することはとても効果的です。
利益剰余金など財務情報を活用した経営支援サービス
匠税理士事務所では会社の財務分析などを活用した経営コンサルティングに力を入れております。経営相談やコンサルティングをご希望の方はお気軽にご相談下さい。匠税理士事務所のコンサルティングサービスにつきましては、下記よりご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
東京都の税理士なら匠税理士事務所...TOPページへ
その他の決算書の読み方のポイントについては、こちらからご確認下さい。
◇経営お役立ち情報
多角化経営・多角化企業それとも集中化戦略? (13/11/28)
・多角化して失敗した・・・
・本業以外には手を出さない。
こうした言葉は経営者の方でしたらよく耳にされると思います。
それではどちらが正解なのでしょうか?
集中化戦略の長所・短所について
この集中化戦略の長所は、資金や人材などの経営資源を一点に集中することで、
その一点だけでは、小が大を破ることができるということがあります。
例えば、大手のデパートに行けば、
大手は資本など資源が豊富ですので、どのジャンルの品物も大体のものは揃ってしまいます。
これに対して、小さな個人商店がスーパーを経営し、
あらゆるジャンルを取り扱えば、どのジャンルも品種などで手薄となり、
結果として大手デパートに敗れてしまいます。
しかし小さな個人商店が、デパートにあまり置いていないような子供のおもちゃに特化した場合、
個人商店の方が、子供のおもちゃというジャンルでは、
大手デパートを上回るため、大手に勝つことも可能となります。
しかし集中化戦略の短所は、
子供のおもちゃというジャンル自体に少子化などの問題が生じ、
全体として右肩下がりになった場合には、一緒になって業績が悪化してしまい、
立て直しが難しいという弱点もあります。
つまり集中化戦略は、環境変化に対応しにくいというリスクが残ってしまうのが短所です。
多角化経営・多角化企業の長所・短所について
それでは集中化戦略ではなく、多角化経営・多角化企業にした場合、
つまり上記の例でいう大型デパートにはどのような長所・短所があるのでしょうか?
長所しては、
ある分野の売上が低迷してきて、逆に他の分野が伸びてきた場合は、
伸びてきた分野に投資を集中させ、低迷している分野は撤退を検討するなど
多角化戦略は、環境変化のリスクに対して、柔軟な対応ができることが長所として挙げられます。
短所としては、多角化していけばしていくほど
事業全体の管理が難しくなり、集中化して一部を攻められると弱いという側面があります。
それでは、集中化と多角はどのように選択すべきでしょうか。
会社の規模に応じた集中化と多角化の選択
会社の規模が小さいうちは、何もかも手を付けると、規模の大きいところに敗れてしまいますので、
会社が小さいうちは、事業を集中化して収益力を高めておき、
会社に体力がつけ、一つ一つ新たな事業をしっかりと作り上げていくというのが王道です。
そして多角のポイントは、
集中化して積み上げてきた事業に関係のある事業を、
新たに始めることで、事業全体としての強みを増していくところにあります。
これまで営んできた事業と全く関係のない事業などでの不用意な多角化は、
好調な事業の足を引っ張る要因にもなりますので、事業の多角化については、慎重に検討しましょう。
匠税理士事務所では、お客様の黒字率100%を目指して、会社の経営コンサルティングに力を入れております。経営相談やコンサルティングをご希望の方は、お気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所のコンサルティングサービスにつきましては、下記よりご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
東京都の税理士なら匠税理士事務所...TOPページへ
武蔵小杉など東横線・目黒線の税理士・会計事務所の採用求人 (13/11/26)
匠税理士事務所の武蔵小杉など東横線や、
目黒線の採用求人をご覧頂きありがとうございます。
弊所は拡大のため会計税務部門の正社員スタッフ、
税務パートアルバイトスタッフを募集してます。
武蔵小杉など東横線・目黒線の会計事務所の採用求人
匠税理士事務所は、武蔵小杉など東横線・目黒線から
アクセスが便利な会計事務所です。
弊所の特徴は、所長も含め全社員が30代~40代で
成長意欲と能力が高い社員が多いのが特徴です。
得意分野も強みもそれぞれ異なり、
起業支援から大企業の税務コンサルティングまで
幅広く対応し、サービス内容は日々進化します。
また、仕事と私生活・勉強とのバランスを加味し、 残業はなく、働きやすさを心掛ける会計事務所です。そんな私たちと一緒に切磋琢磨して
税務会計のプロフェッショナルを目指しませんか。
武蔵小杉など東横線・目黒線近くの税理士事務所や
会計事務所をお探しなら、下記をご覧ください。

武蔵小杉など東横線の匠税理士事務所の採用求人
今回の求人採用は、一体性を重視するため、
現在のスタッフと同世代の方を募集の対象とし、
正社員とパートアルバイトスタッフ採用求人を行ってます。
担当して頂く業務内容は、内勤での業務となり、
主に会計や税務を担当して頂くことになります。
(外勤業務や残業は、一切ございません。)
今回の武蔵小杉など東横線・目黒線の方に向けた
採用と求人に関する詳細なお仕事の内容や、
待遇は下記のページよりご確認をお願いします。
なお、給料水準は、武蔵小杉など東横線・目黒線で 【 最高水準のレベル 】になっております。
税理士試験を応援の勤務時間調整や試験休暇や、
武蔵小杉など東横線・目黒線沿線の一部専門学校の
受講料割引制度も充実してます。
また、これまで社員の満足度を重視し、
パートアルバイトスタッフ有給制度や賞与制度、
正社員スタッフ残業ゼロ化を通して、
【 ここ6年間で退職ゼロ 】が最大の特徴です。
これからもチームで仕事をする仕組みづくりや、
給与体系、職場の環境づくりなどを通して、
【 働きやすさNo1の税理士事務所・会計事務所 】を目指します。武蔵小杉など東横線・目黒線の近くの税理士や、
会計事務所での勤務をご検討中の方は、
是非一度ご確認を頂けましたら幸いです。
【 → 会計事務所の求人・採用は匠税理士事務所】

東急東横線自由が丘駅より徒歩2分の場所にあり、
武蔵小杉など東横線・目黒線のアクセス便利ですので、
採用・求人情報をご覧の上、ご応募下さい。
東横線・目黒線の匠税理士事務所の求人採用
オフィスは、デザイナービルの綺麗なオフィスで、
遅くとも【18時には必ず全員が退社】します。
残業をしないように仕事を全体で管理し、
スタッフの方が働きやすい環境に努めており、
プリンタは各人ごとに設置されてます。
デスクも1.5人分の広さで最新のPCなど完備です。
(また、残業のない仕事量も特徴です。)
武蔵小杉など東横線・目黒線からのアクセスや、
所属税理士やスタッフはこちらから確認下さい。
【→ 自由が丘の税理士は匠税理士事務所】

武蔵小杉など東横線・目黒線の皆様からの
ご応募をお待ちしております。
採用・求人情報を最後までご覧くださり
ありがとうございました。
武蔵小杉の方へ匠税理士事務所のご紹介
匠税理士事務所では武蔵小杉エリアで
起業支援や経営支援に取り組んでおります。
武蔵小杉エリアの方に向けた匠税理士事務所の
紹介ページはこちらからご確認下さい。

武蔵小杉など東横線・目黒線の沿線の会計事務所で
勤務を検討中の方は弊所の採用求人もご検討下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#武蔵小杉税理士事務所採用
#東横線税理士事務所採用
短期経営計画書と中期経営計画書の作り方や立て方 (13/11/24)
KK1 会社から組織への変革を行い経営を行う上で経営者にとって、
短期経営計画書や中期経営計画書を作成することは、とても重要な仕事です。
自分の会社の成長に必要な利益を得て自分の描く組織を作り上げるために
・真のお客さまは誰なのか
・真の商品は何なのか
・どんな人材を採用して、どんな事業を行うのか
・何を通じてお客さまに利益をもたらすのか
これらが定まらなければ会社の永続的な成長・存続はありません。
これらに必要な、
短期経営計画書と中期経営計画書の作り方や立て方について記載します。
短期経営計画書と中期経営計画書とは何か?
会社には経営理念というビジョンがあります。
このビジョンをどう実現していくのかを表現したものが、経営計画書となります。
したがって、これらの経営計画を立てる前にビジョン(経営理念)という会社の根幹を考えるが必要あります。
(参考:経営理念と経営計画を作りたい方へ )

短期経営計画書は、この経営理念や方針にしたがって
1年先を見通して、会社をどうするのかという短期的な計画という位置づけで、
1年先を見通した数字ですので、その精度は比較的高い数字となります。
一方で中期経営計画書とは、5年程先を見通したものをいいます。
この経営計画では、
『 5年後に自社をどのようにしたいのか 』
というイメージを実現するためのプロセスを、
各年度ごとに表現したものになります。
中期経営計画書において重要となるのは、
これから先自社の製品やサービスがどのように変化するのか、
その変化にどう対応していくのか
自社の中心となる人材の育成雇用は今後どのように変わっていくのか
大切なことは、計画を作るための数字ではありません。
また目標や希望をきれいに並べるものでもありません。
今後自社に訪れるであろう脅威を事前に予測し、そのための準備を日々積み重ねていくものと捉えると物事が良くみえるようになります。
どんな人材を採用していくのかの採用予定、設備の購入予定などおおまかな経営の方向性を決めてあるかないのかでは全く違ったものとなります。
例えば、今後自社のサービスを提供する人材の確保が難しくなると想定されれば
機械化やAIの導入により安価に提供できるようになるサービスと
難しい環境のなか採用する人材でどのような高付加価値なサービスを提供するのか考え、売価が最大化できる方法を探さなくてはいけません。
経営計画の立て方
経営計画を立てる際に、
1 最終的に獲得したい利益を決め、
2 予想される人件費や家賃などの経費を決め、
3 1 + 2 =必要な売上総利益(粗利) が求められるので、
これを売上総利益率(粗利率)で割り戻せば、
必要な最終利益を確保するための売上が決まってきます。
(補足:売上総利益(粗利)の意味についてはこちらからご確認下さい。)
自社が成し遂げたい目標利益を決定し、経費は予想するのが簡単ですので、
この2つの要素を固定してしまえば、後は達成しなければならない売上総利益率(粗利率)が決まるというわけです。
この必要な売上総利益を決定するために自社の商品や得意先、市場を踏まえて細かな戦略に落とし込んで行くことになります。
借入金の返済が多い会社様や、人材の多い会社様では必要な利益は会社存続にMASTなためこのような方法で経営計画を立てる必要があります。
経営計画の作成支援サービス
短期経営計画書や中期経営計画書について作成を検討されている方に向けたコンサルティングも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
東京都の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
脱サラ、開業して成功、独立して失敗の分かれ目 起業と貯金(資金) (13/11/22)
・いつかは起業して成功したい・・・
・将来は必ず独立したい!
ノウハウや営業力・技術力をお持ちの方でこのように
思われてる方も多いのではないでしょうか。
脱サラ起業・開業で成功するために必要な事
それでは脱サラ起業や開業をし成功するには、
何が必要なのでしょうか?
必ず必要なのは、【 成功する準備 】です。
実際に起業して成功していく方は、
綿密に準備をされている方がほとんどです。
それでは成功にどんな準備が必要でしょうか。
起業や独立をして失敗しないための準備
起業や独立の準備にも色々とありますが、
最低限以下の準備が必要となります。
1 得意先を獲得できる営業力(人間的な魅力)
→お客様を獲得しないと事業は軌道に乗りません。
会社員の頃と大きく異なるのは、仕事を自分で獲得してくるということです。
これが起業して1年目の大きな壁となってきます。
2 将来他社との競争の中でも勝ち残って、
収益を確保できるような技術力や商品力
→ 高収益モデルの事業を実現するための技術や
商品の開発は、一朝一夕にはできません。
こうした技術力などは会社員時代のうちに、
出来る限り高めておき、起業して厳しい競争でも
耐え抜けるようにしておくのが理想的です。
3 事業が軌道に乗るまでのゆとりを持った資金
→起業に必要な資金の最低半分は、自分で調達するという姿勢でなければ、金融機関などの融資を
受けられる可能性は低くなります。

起業には、いくら貯金すれば良いでしょうか?
このようなご質問をよく頂きます。
業種によりますが、必要資金の1/3又は1/2を
自己資金で用意される方が多いです。
(自己資金は多ければ多いほうがよいです。)
最初の自己資金をまったく用意せずに、
借入ですべて対応しようとすると、
毎月の返済額が多額になり、あっという間に
資金不足で事業を止める事態に陥ります。
起業当初は想定していたように、
集客がうまくいかないことが多いので、
この際に自己資金が豊富であれば
集客のための改善策を多く選択肢から選べます。

しかし、自己資金がなければ選択肢も限られて、
トラブルなどからの立て直しも困難となります。
一度、開業すると、事業を継続するのか、
廃業するのかのどちらかになります。
起業するからには事業を継続させ、
伸ばしたいという方がほとんどだと思いますので
綿密な創業計画から必要な資金を算定し、
必要資金に対して一部融資を受けたとしても、
余裕をもった自己資金で起業するのが適切です。
創業計画や自己資金を用意せず、見切り発車での起業にならないようにしましょう。
成功度合いと起業の準備の度合いは比例する
この他にも準備は、しっかりとしていれば、
準備しているほど良いのは言うまでもありませんが
起業の成功を大きく左右する事項を中心的に取り上げてみました。起業して成功したいという方は、成功できるためのしっかりとした準備を行いましょう。
何とかなるといった見切り発車は禁物です。
成功と失敗の分かれ目は、この準備の度合いにあるといえます。
匠税理士事務所の起業を成功させる支援
匠税理士事務所では、起業家支援に力を入れており
【起業に必要な全てがそろう事務所です。】起業成功を後押しするための会社設立のサポートや
起業後の経理アウトソーシングなど起業支援サービスや
所属税理士や料金などはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】
起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

(関連記事: 30代、40代、50代で起業するために必要な準備)
(関連記事: 社長の営業能力が起業後は重要です。 )
(関連記事: 売上総利益・粗利を決める売価決定の重要性 )
(関連記事: 起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき? )
◇関連記事
起業家の方向けのお役立ち情報を集約した匠税理士事務所の起業塾はこちらから
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス
→起業時の資金調達を支援するための創業融資サービスをご用意しております。

◇会社設立サービス
会社設立をご検討中の方には、設立手続や経理や経営サービスをご用意しております。
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
税理士 目黒区、世田谷区や品川区の会計事務所匠税理士事務所TOPへ ...TOPページへ
匠税理士事務所では、金融機関と提携して、創業時の資金調達や事業計画書の作成サポートを行っております。
起業や創業、開業については、匠税理士事務所へご相談下さい。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
会社の経営理念(ビジョン)と経営計画を作ることの効果 (13/11/19)
KK2
このように会社の経営理念(ビジョン)と経営計画の作成に取り組む時期は、会社によってそれぞれです。
この会社の経営理念(ビジョン)と経営計画は、
これらがあるか、ないかで 会社のリスクに対する対応力を大きく変えます。
それは何故でしょうか?
会社の経営理念(ビジョン)と経営計画を作ることの効果
会社の経営理念(ビジョン)と経営計画を作るためには、一般的には、最低3~4か月はかかります。
そしてこの期間、社長は会社の将来を必死になって考えます。
その結果、今後自社を取り巻く環境がどのように変わるか、
そしてその環境の中で、自社はどう生き残っていくかを考えるきっかけとなります。
会社の経営理念(ビジョン)と経営計画を作成した後に、とるべき方法や考え方が変わったという声をよく耳にするのは、
このように必死になって自社の将来を考えるという、
会社の経営理念(ビジョン)と、経営計画作成がもたらす最大の効果です。
具体的には、会社の経営理念(ビジョン)と、経営計画が無い場合は、
目先の一手二手を打つような経営だったのが、<会社の経営理念(ビジョン)と経営計画がある場合には、
最低3年先を見た経営に変わってきて、これに合わせて結果も変わってきます。
特に長いスパンで取り組むべきカテゴリーについては計画があるとないとでは、全く違う判断をすることがあります。
この他にも社員への意思疎通、金融機関への協力要請の際に、重要な根拠資料となるなどの効果もあります。
このように会社の経営理念(ビジョン)と経営計画を作成するのには、
相当な労力と時間を要しますが、必ず回収できます。
経営理念(ビジョン)と経営計画を作成することをお勧めします。
会社の経営理念・ビジョンと経営計画の作り方
それでは会社の経営理念や経営計画は、どのように作るべきなのでしょうか?
経営理念(会社としてのビジョン)を作成した上で、
その後に短期経営計画(1年先を見通した経営計画)を作成し、
中長期経営計画(3~10年先を見通した経営計画)を作成するという流れをお勧めしています。
(関連記事:短期経営計画書と中期経営計画書の作り方や立て方)
経営理念(会社としてのビジョン)は、きれいな言葉である必要はありません。
自分の仕事上、譲れないポリシーをそのまま短い言葉で現す程度でよく、記載しすぎはかえって計画を違う方向に曲げてしまうこともありますので注意が必要です。
会社の経営理念や経営計画を作るのは、社長の仕事です。
会社の経営理念や経営計画は、簡単に作成できることではありません。
会社の経営理念と経営計画は、常務や部長などが作成するものではなく、
会社の最高責任者である社長が自ら作成すべきです。
なぜなら、「 将来会社をこうしたい! こんな会社を作りたい! 」 という
全社員を引っ張っていけるような旗(経営理念と経営計画)を
作れるのは、社長以外にいないからです。
(関連記事:経営者の仕事とは何か、社長に求められるものとは)
経営計画の作成支援サービス
短期経営計画書や中期経営計画書について作成を検討されている方に向けたコンサルティングも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
東京都の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
2013 起業家支援セミナー (せたがや創業塾) (13/11/08)
匠税理士事務所では起業家を支援しています。
その一環として、
平成25年11月15日に
世田谷区産業振興公社で、
今年もせたがや創業塾の起業セミナーを
弊所の税理士水野が担当させて頂きました。
(会場の最寄駅は三軒茶屋駅でした。)
内容は、創業時における税務知識についてでした。
具体的には
起業するときは、個人事業がいいのか、
会社がいいのかという組織形態の選択のポイントと、
個人で起業した場合の税務上の注意点や、
会社で起業した場合の注意点などを19時から21時までお伝えしました。
例年、受講生の方の熱意は素晴らしく、
無事盛況となっているセミナーですが、
今年も参加者のほとんどの方から
質問を頂けるなど大変盛況となりました。
来年も企画しておりますので、
起業をお考えの方は是非ご参加下さい。
また、匠税理士事務所が、
世田谷や目黒、品川などお近くで起業される方を支援することに
注力しております。
匠税理士事務所主催のセミナー最新情報は、
こちらからご確認下さい。
↓
その他の講師のご依頼などはこちらからご確認下さい。
その他弊所の具体的な起業や創業支援サービスの内容につきましては
下記よりご確認をお願いします。
起業に伴う会社設立の代行サービスはこちらから
起業後の経理や決算などを支援するサービスはこちらから
その他のサービスラインなどは下記よりTOPページからご確認下さい。
品川区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
最終更新日:平成25年11月22日
上用賀や用賀近所の税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (13/11/08)
匠税理士事務所サイトへ来訪ありがとうございます。
弊所は2008年に事務所設立以来、上用賀や用賀など世田谷のお客様が多くいらっしゃいます。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に高度な専門性と高い技術力を活かした
【起業支援】・【経営支援】に定評があります。税務会計や節税対策、決算・確定申告も対応し、
用賀など世田谷のお客様に多く利用頂いてます。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
所属税理士やサービスにつきましては、
こちらよりご確認下さい。

(税理士対応地域は用賀や上用賀など世田谷)
用賀や上用賀で税理士の会社設立・起業支援
用賀や上用賀など世田谷区で
会社設立をして起業されるお客様に対しては、
・資本金はどれ位にした方がよいのか。
・決算月はいつなら節税対策しやすいのか
・役員や株主構成を決めるポイントはどこか
・用賀や上用賀など金融機関はどこがいい?
など起業に伴うご相談にもご対応しております。

税理士が会社設立後も、経理体制構築から
全てお任せの経理アウトソーシングサービスや、
人事労務の専門家である社会保険労務士を交えた
給与計算や社会保険手続きの代行、
弁護士と連携した契約書などの作成サポート、
建築業の許認可申請、外国人の方の就労ビザなど
【 起業家の方が本業に集中できる環境づくり 】お手伝いするサービスを行っております。
上用賀や用賀で起業支援担当の税理士はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

起業支援対応エリア:上用賀や用賀など世田谷区
用賀や上用賀で創業融資による創業支援
匠税理士事務所では、創業支援に力をいれており、
【創業に必要な全てがそろう会計事務所】です。当会計事務所の会社設立・創業融資など起業家向け
サービスはこちらからご確認をお願いします。
上用賀や用賀などでの会社設立と同時に
起業時の資金調達など創業融資はこちら

用賀・上用賀の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は用賀・上用賀など世田谷全域対応)
用賀・上用賀の経理会計や確定申告・決算代行
用賀や上用賀で会社経営されている方に対しては、
・会社の経理アウトソーシング
・税理士による黒字支援コンサルティング
・株式会社や合同会社へ法人化・法人成り支援
・上場企業など大規模会社にも対応できる税理士の
高度な税務会計コンサルティング
・社会保険労務士を交えた労務コンサルティング
・弁護士などを交えたM&Aサービス
などを税理士が丁寧に行います。

また、会計事務所のサービスを超えたニーズも
提携ラインで対応しております。
今後もスタッフの質やサービスの質の向上に努め、
用賀や上用賀のお客様のお役に立つことで、
【世田谷地域満足度No1の会計事務所】を目指して行きたいと思います。
税理士による会社様向け財務経営支援や
会計サービスはこちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
上用賀や用賀の方向けの確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
上用賀・用賀で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

用賀で会社設立されたお客様の声
長年の夢だった用賀で小売業の会社設立をしました。
税理士の水野先生とは世田谷のセミナーを通じ。
知り合い人間性に共感して顧問を依頼しました。
会計サポートから事業についての相談にも
税理士さんが親身になってくれるので、
うちの会社にはなくてはならない存在です。
今後ともよろしくお願いします。
世田谷 用賀の小売業L様
上用賀の法人化・法人成りのお客様の声
これまで用賀にある他の会計事務所の
税理士にお願いしてきましたが、
税務調査で多くの追加の税金が出てしまい
こちらにお願いすることにしました。
これまでの節税対策では、
リスクの説明が一切なかったのですが、
こちら会計事務所の税理士さんは、
医療法人への法人化・法人成りも
分かりやすく説明をしてくれて満足してます。
世田谷区 上用賀のクリニックK様
用賀や上用賀から匠税理士事務所のアクセス
用賀駅から自由が丘駅までのアクセスは、
上記リンクのアクセスページでご確認下さい。
税理士が執筆する会計や起業、
コンサルティングお役立ち情報はこちらから
※黒字経営コンサルティングへ移動します。
当会計事務所の税理士対応エリアは、
用賀(ようが)や上用賀(かみようが)など
世田谷など東京都23区全域となります。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 用賀近くの税理士・会計事務所の採用求人】
用賀近く会計事務所のお役立ち情報
用賀駅は、東京都世田谷区用賀2-39にあり
東急田園都市線があります。
用賀で会社設立など起業した場合や、
会社経営をされている場合の税務申告書、
届出書提出先は以下のようになります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 税務申告書、届出書提出先→玉川税務署
管轄区域:世田谷区のうち用賀など玉川地区
〒158-8601
世田谷区玉川2丁目1番7号
事業税・住民税の申告書、届出書提出先→渋谷税事務所
管轄区域・世田谷区・目黒区・渋谷区
〒151-8546
渋谷区千駄ヶ谷4-3-15
東京都渋谷合同庁舎4~7階
社会保険関連書類の提出や相談先 【 →日本年金機構 世田谷年金事務所 】〒154-8512
東京都世田谷区世田谷1-30-12
上記が上用賀や用賀の方の税務申告や社会保険の
届出書の提出先・税務調査所轄となります。
期限までに決算関連書類の提出を行いましょう。
上用賀や用賀の法人化・会社設立関連情報
上用賀・用賀など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
用賀で法人化・会社設立に伴う商業法人登記は
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が法人化・会社設立など登記の際、
対応する行政窓口となります。
上用賀や用賀での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#用賀税理士
#用賀税理士事務所
#用賀会社設立
外注と内製化、どちらが会社にとって有利か (13/11/06)
会社の規模が一定に達すると、
組織をどう作るかという問題が発生します。
現在の流れは、事業一部をアウトソーシングする
外注利用のビジネスモデルの企業が増える一方、
仕事が増え、外注費が膨らんできたので
社内で製造(内製化)した方が良いのか、
迷っているというご相談も多くいただきます。
このような問題には、次のような考えが有効です。
今後の事業の見通しはどのようになりますか?
その理由としては、この質問に対する回答が、
【 内製化 か 外注 】の判断につながるからです。

外注にする場合のメリットやデメリット
外注の場合、外部取引先と請負契約になりますので
外部取引先の利益も製造コストにのることで、
短期的には原価率が上昇することになります。
ただ、仕事があるときは外注して、
仕事が減少してきた場合には、
外注委託量を調整できるメリットがあるため
内製化のように固定費が増加しません。
こうした点から現代のように、
事業環境が早いスピードで変化することで、
事業の見通しを立てにくい場合には、外注利用は、有効な選択肢となります。
また、外注した場合には製造のための設備を、
自社で用意する必要がないため、
資金を用意する必要がないメリットもあります。
優秀な人材の採用が難しい中小企業にとって
スキルや専門性の高い人材に仕事を依頼し
高品質・画期的な業務を行ってもらえることも
外注利用のメリットの一つです。

それでは内製化のメリットは何でしょうか。
内製化(自社で製造)した場合のメリットやデメリット
内製化メリットは、外部の利益を加味する必要がなく、
製造コストを下げられるメリットがあります。
また、外注した場合には外注先が他社の案件で、
手一杯で受けてもらえないリスクもありますが、
内製化では、このリスクを管理できます。
それでは中小企業にとって外注と内製化、
どちらが有利なのでしょうか?
中小企業における外注と内製化のポイント
外注を利用する場合は、自社の資金や人材などの
資源を固定化させる必要がないことや、
外部から取引先への委託量も調整が可能なため
仕事量で臨機応変に対応できる利点があります。
したがって、
事業の先行きが読み切れない場合には、
外注で対応する方が、成功する確率は上がります。

逆に先行きが長期に見渡せるような場合で、
事業にあったスキルの人材確保が可能な場合は、
内製化も検討すべきことになります。
このように外注か、内製化かを判断する上で、
【経営者の先見性】が最大のポイントになります。
多額の借入を行って、莫大な設備投資をした後に、
ブームが去り衰退局面に入ることもありえます。
目先の判断で利益率が良いから内製化をしないよう
長期的な視点を持って慎重に取り組みましょう。
中長期的な視点で考えても、
問題ないというようであれば、
事業経営は利益の最大化が重要ですので、
【内製化】に踏み切るのがよいでしょう。
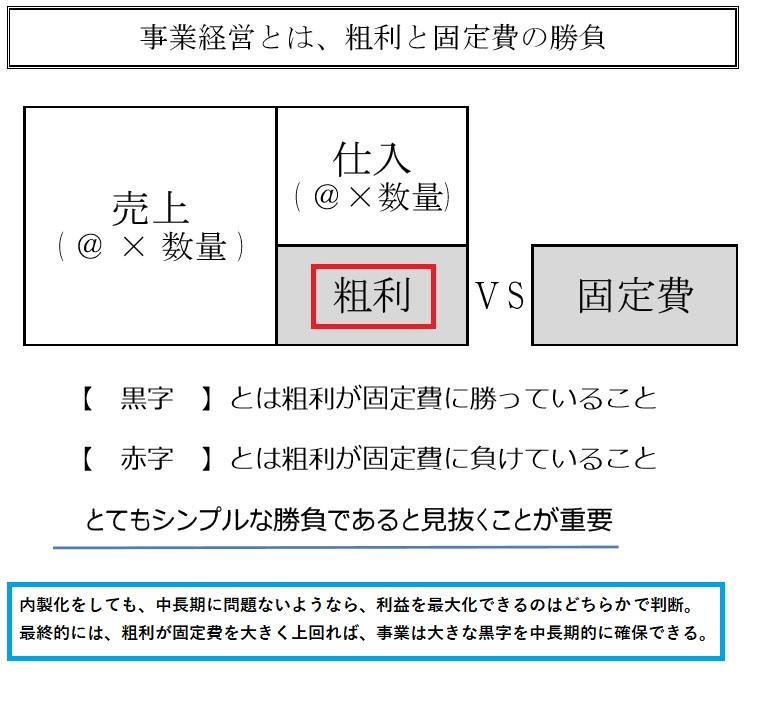
外注化や内製化の長所や短所を踏まえた経営コンサルティング
匠税理士事務所では、経営者が内製化や外注化を
検討される際に適切な判断ができるように数字を
交えた経営コンサルティングを行っております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
内製化のための設備資金など
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
株式会社を設立して起業するなど
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
外注と内製化どちらが会社にとって有利かなど
経営支援や会計経理の代行など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人から会社へ組織変更するための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

上記外にも経営お役立ち情報を収録してます。
◇経営お役立ち情報
弊所が提供する会計のアウトソーシングや、コンサルティングサービスにつきましては下記よりご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
執筆者・文責 税理士水野智史
#外注メリット
#外注デメリット
一か月単位の変形労働時間制≪p12≫ (13/11/05)
労働基準法では、労働者の労働時間を一日8時間 一週間40時間までとしています。
これを法定労働時間といい、法定労働時間を超えて仕事をさせるには36協定を結び割り増し賃金を支払う必要があります。
36 協定で定める延長時間について
36 協定で定める延長時間は、
最も長い場合でも、次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。
1 週 間 15 時間
2 週 間 27 時間
4 週 間 43 時間
1 箇 月 45 時間
2 箇 月 81 時間
3 箇 月 120 時間
1 年 間 360 時間

しかし、事業の内容例えば
医療や介護機関、
タクシーなどの運送業、
警備などの業種については
月初や月末に業務が集中することがあります。
このような業種には変形労働時間制を活用します。
ここでは1か月単位の変形労働時間制について説明をします。
1か月単位の変形労働時間制について
1か月以内の一定期間を平均して
一週間あたりの労働時間が
法定労働時間(原則40時間)を超えない定めをした場合
↓
特定の週に40時間を超えて
又は特定の日に8時間を超えて労働させても良いという制度です。
≪変形労働時間制を採用したときの割り増し賃金の計算について≫
1か月単位の変形労働時間制のpoint
1. 就業規則で変形労働時間制の採用をする旨定めて
就業規則届を所轄労働基準監督署長に提出する
2.労使協定を締結し労働基準監督署に届け出る
3.変形期間を1か月以内の期間とする、変形期間の始期を定める
4.一か月以内の一定期間を平均し一週間当たりの労働時間が
法定労働時間(原則40時間)を 超えない範囲内
5.労使協定又は就業規則により、変形期間の各日各週の労働時間を
あらかじめ具体的に定めておく必要があります。(始業、終業)
匠税理士事務所では、
経験豊富な社会保険労務士と提携することにより、
人事労務面のコンサルティングにも対応しております。
サービスの詳細はこちらからご覧下さい。
※目黒区や世田谷区、品川区での給与計算や社会保険、労務コンサルティング
◇バックナンバーはこちら→
その他のお役立ち情報はこちらから
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:25.11.5
世田谷区 税理士事務所なら匠税理士事務所TOPへ
販売戦略は重要!自社販売か、代理店等の委託販売か? (13/11/03)
会社は事業をしている上で、
商品を売るか、サービスを提供するかで付加価値を生み出し、これによって利益を上げていきます。
そのため、事業である以上は、
商品又はサービスをお客様に販売するということが必要になります。
その際に、販売戦略は、大きく二つの分かれ道があります。
一つは自社販売。
もう一つは販売代理店などを通じた他社による販売。
それではこの二つの販売戦略、どのような違いがあるのでしょうか?
自社販売は中小企業には不可欠
自社で商品を売る最大のメリットは何でしょうか?
それは自社の商品については、誰よりも知識があり、
その商品やサービスの良さを、
より多くのお客様にお伝えしたいという誰にも負けない熱意があることです。
これは当たり前のように思われることですが、
販売代理店など他社に販売を委託した場合、
他社は自社以外からも販売の委託を受けている場合の方が多いので、
自社製品についての知識も自社販売に比べ低くなりますし、その販売意欲も下がるのが当然です。
こうしたことから放っておいても売れるような一流ブランドなどはさておき、
中小企業の場合には、自社販売に注力した方が、成功する確率は高くなります。
販売代理店などの委託販売のメリットは?

販売代理店や問屋などを利用した場合には、手数料などは生じますが、
その得意先など販売網を利用することができる
という最大のメリットがあります。
一方で、販売代理店や問屋における他者との力関係により、
あまり販売に注力してもらえなかったり、
消費者に直接商品を販売するわけではないので、
消費者の声を直接聞く機会が減ることになり、
商品開発などのチャンスを失ってしまうというデメリットもあります。
中小企業がとるべき販売戦略とは
もちろん各業種によって違いもありますが、
上記のような自社販売と、
他社を用いた販売の長所と短所を加味すると、
中小企業の経営者は、市場における消費者から自社の認知度が高まるまでは、
自社販売に注力し、商品開発による改善で顧客からの支持率を高めるとともに、
高利益率の確保に努め、市場において確固たる地位を築いた段階で、
自社販売を継続しながら、
他社による販売を交えていくという販売戦略が一つの成功の型になると考えます。
匠税理士事務所では、経営支援を通じてお客様の黒字率100%を目指すため、会計を通じて現場主義のコンサルティングに力を入れております。サービスの詳細はこちらから
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
二子玉川近くの税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (13/11/02)
二子玉川すぐの匠税理士事務所のホームページに
ご訪問ありがとうございます。
弊所は二子玉川からアクセス便利な位置にあり、
これまで多くのお客様の会社設立・起業支援や
経営支援を担当させて頂きまして、
世界4大会計事務所出身の税理士による高度税務や経営コンサルティングに定評がある事務所です。また、給与計算など人事労務の専門家の社労士や、契約書など法務専門家の弁護士と連携し、経営に必要な全てがそろう事務所という想いのもと
【世田谷地域で顧客満足No1の税理士事務所】を目指しております。
そのために、人の質・サービスの質が重要と考え、
税理士・会計スタッフの【 質 】にこだわります。

匠税理士事務所の税理士やサービス・提携専門家はこちらでご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

二子玉川で税理士による会社設立・起業支援
所属税理士が30代や40代ということもあり
二子玉川など世田谷で起業される同世代パートナーを
求める起業家の方から支援されています。
世田谷区の産業振興公社で起業塾講師を担当し、会社設立など起業支援ノウハウが充実しており、
起業時の資金調達・創業融資も多数の実績があり
【 起業に必要な全てがそろう事務所です。】二子玉川などに対応の専門家等はこちらより
ご確認を頂けましたら幸いです。
起業支援担当の税理士・事務所概要はこちら↓
【 → 匠税理士事務所の概要 】

匠税理士事務所の会社設立や創業融資
起業後の経理や経営などの創業支援はこちら↓
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
二子玉川の創業融資・会社設立など創業支援
二子玉川にアクセスが便利であることから、
二子玉川の会社設立を多く担当させて頂いてます。
これから起業をお考えの方で、会社設立手続きや、
その後の会社の経理決算などを任せる会計事務所を
お探しの方は下記起業支援サービスをご覧下さい。
経済産業省 関東財務局で認定経営支援機関認可も受けており、様々な制度のコンサルティングも可能です。
会社設立など起業支援や経営支援を通じ
お客様の黒字率100%を使命とし、
これからも二子玉川など世田谷エリアの
お客様にお役にたてるように努めております。
株式会社・合同会社などの会社設立や
起業支援や創業支援はこちらでご確認下さい。

また二子玉川など担当する日本政策金融公庫や
城南信用金庫・メガバンクなど金融機関と連携し、
起業資金の調達である創業融資では、
融資成功率90%超世田谷トップレベルの実績です。
当会計事務所の会社設立後の資金調達として
創業計画作成など創業融資はこちらから↓
【 → 世田谷区の創業融資による資金調達 】

経営支援に強い会計事務所・税理士事務所
独自の経営支援サービスが特徴です
二子玉川など世田谷区エリアを中心として
お客様の黒字化支援で経営支援に力を入れており、
90%以上のお客様が、黒字経営を実現されている税理士事務所です。
また税理士は、東京商工会議所・青年会議所などで
経営セミナーの講師を数多く担当するなど
経営支援のノウハウに定評があり、
少し変わった独自商品を取り揃えてます。
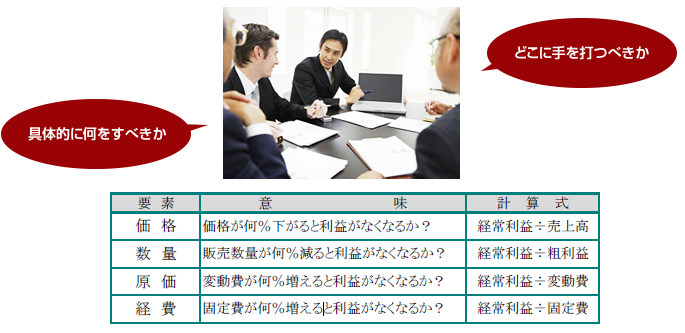
こだわりの人材の質・サービスの質
上場企業を担当していた税理士が2名所属しその他にも経験豊富な税務会計スタッフがおります。
事業拡大後もしっかりと対応可能です。
また、人事労務に強い弁護士、社会保険労務士など
各分野のエキスパートが、二子玉川など
世田谷地区のお客様の事業をサポートします。
IT企業などの方には、
ソフトウェア特許に対応可能な弁理士・特許事務所と
連携してますので、様々なニーズ対応できます。
詳細はこちらよりご確認をお願い致します。
法人経営者向けのサービスはこちら
【 → 法人のお客様向けサービス】
個人の方への経理会計や決算確定申告、
法人化のサービスはこちら
【 → 個人事業のお客様サービス】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
二子玉川で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

当会計事務所で起業支援した二子玉川の方
昨年、二子玉川の自宅を本店に起業し、
会社設立するため税理士を探してたのですが、
知人から匠税理士事務所を紹介してもらい
こちらの会計事務所に起業支援をお願いました。
経理の初心者の私にていねいに説明して下さり
経理も全てお任せの状態でしたが、
会社設立後の決算も迎えれました。
来年は人を雇う予定なので、
また色々とお世話になると思いますが、
これからも宜しくお願いします。
(世田谷 二子玉川:会社設立A様)

二子玉川近くの税理士事務所お役立ち情報
世田谷区の二子玉川近くには、
世田谷玉川地域管轄の玉川税務署が
二子玉川ライズ様や高島屋様の近くにあります。
こちらは、田園都市線や大井町線でアクセス便利な二子玉川駅徒歩5分の場所にある税務署で、
各種税金に関するご相談や税務申告書の用紙や
源泉所得税の納付用紙などを提供頂けますので、
ご利用になられる方は、
以下で所在地など確認を頂けましたら幸いです。
→ 玉川税務署 へのリンク

等々力の税金お役立ち情報
世田谷区の二子玉川駅近くには、
二子玉川総合支所・等々力出張所がございます。
こちらでは住民税の納税証明や印鑑証明書、
住民票の交付など各種行政サービスを
受けることができるので大変便利です。
二子玉川の法人化・会社設立関連情報
二子玉川など世田谷区で法人化・法人成りは
こちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
法人化・会社設立に伴う商業法人登記は
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が二子玉川で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
二子玉川近くの会計事務所の求人・採用情報
二子玉川近くで
会計事務所の求人や採用情報をお探しの方で、
お客様のために一生懸命になって頂ける方は、
ページ上部にございます採用情報より、
詳細をご確認の上、ご連絡頂けましたら幸いです。
現在、正社員スタッフ・パートスタッフ
アルバイトの方を募集しております。
二子玉川以外の方も是非ご応募下さい。
匠税理士事務所は世田谷で
働きやすさNO1の税理士事務所を目指してます。
お気軽にお問い合わせください。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 二子玉川の税理士・会計事務所の採用求人】
二子玉川で会社設立後の起業支援・創業支援や
法人化・法人成りなど匠税理士事務所の案内を
最後までご覧下さりありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#二子玉川税理士
#二子玉川会社設立
売上総利益・粗利を決める売価決定の重要性 (13/10/31)
売上総利益(粗利)について考えることは重要
ヒト・モノ・カネの経営資源を活用して
事業を拡大させるためには、その原資となる利益が重要となります。
売上が毎年上昇傾向にある企業であっても
利益が上昇しない企業は< 忙しいが、儲からない > といった悩みを抱えます。
必要な利益を確保して、経営を行うために
コストカットなどの支出面の見直しは、よく取りあげられる論点です。
しかし、これは短期的な解決策であり
長期的には、売上についての解決策、
すなわち売上総利益(粗利)について解決策を検討してみることが重要です。
( 補足:売上総利益や粗利についての意味などは下記の参考記事をご確認下さい。 )
売価と売上総利益(粗利)との関係について
そもそも売価とは、どのように設定すべきなのでしょうか。
この設定は、経営者にとって最も難しいもので、かつ重要なことではないでしょうか。
利益は当たり前ですが売上から原価を差し引いた残りで計算されます。
売価は原価と利益の合計となります。
原価は、交渉などによる多少の変化はあるものの基本的に必要な仕入れコストは、ほぼ変化がありません。
つまり、売価の決定は、顧客の満足度のバランスを加味しながら
自分の会社の利益をいくら乗せるかということが>ポイントとなるわけです。
これこそが経営の重要な点です。
高付加価値が会社を成長させる

会社を安定して存続させ、成長させるためには、
この利益は、会社の維持に必要な人件費、家賃などのコストまで
視野に入れた設定にしなければなりません。
このコストをまかなえるような設定にするためには
高付加価値な商品やサービスである必要があります。
高付加価値な商品や差別化されたサービスを常に研究し、
これによって得られる利益で新たな利益の獲得のための準備を
常に継続して行うことで会社の規模は徐々に多くなっていきます。
コストを削るという視点も重要ですが
原価に、高い利益を付加して売るためには、どうしたら良いかという視点を
経営者が絶えず持ち続けることで、会社が成長するのではないでしょうか。
会社経営を支援するサービス
匠税理士事務所は、経営支援を通じてお客様の黒字率100%を目指します。経営についてお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
◇会社経営者の方を支援するためのコンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
伸びている会社には、なぜ経営計画があるのか<短期・中期経営計画書の策定> (13/10/28)
KK3 会社を経営している方で、順調に業績を伸ばされている方は、そのほとんどが経営計画をお持ちです。
経営計画の役割とは
経営計画は、経営者自身がその作成の際に、会社の今後を取り巻く環境を予測し、
現状の再確認と将来について考えるという役割があります。
一方で、経営者が将来どのように会社を経営していくのかを
全社員に対して意思表示するという役割もあります。
このような経営計画を作らないということは、現状や将来について経営者しっかりと考える機会を一つ失うことになりますし、
また会社の規模が小さいうちはまだ良いのですが、会社が大きくなってくると
会社全体に経営者の考えが伝えることが難しくなり、各自が経営者の意図をくみ取ることができないで、
現場が混乱するという事態につながります。
経営計画は今後会社がどのようになっていくのか、地図としての役割を果たしますので、
会社の規模が大きくなってくればくるほど、その重要性は増していきます。
ただ、まず始めは自分の地図でもよいと考えております。
自分の地図から、中心人物への地図、社員の地図などそれぞれ順を追っていけば良いのです。
成長企業に経営計画がある理由
会社を伸ばされている経営者の多くは、1年後の短期経営計画と、
3~5年後の中期計画を少なくても作成されていることが多く、この計画を現状の差異を随時分析し、経営課題に取り組まれています。
このような姿勢が現状を良しとしせず、絶えず挑戦するという経営姿勢につながり、会社の成長につながるのです。
経営計画は作成してみると、意外に簡単です。
また、これがあるか、ないかで融機関などからの印象も大きく異なります。
中期経営計画書の前に短期経営計画書は作成されましたか。
匠税理士事務所では、中期経営計画書を作成される前に、
これまで短期経営計画書を作成されていらしたかを確認させて頂くようにしております。

なぜなら中期経営計画は非常に策定するのに
難易度が高く、かつその後の運用も難しいものです。
これまで短期経営計画を作成されていない場合には、
短期経営計画を作成された方が有効だからです。
短期計画を作ることで、
目の前の問題と、将来の問題を意識できるようになり、
最終的には中期経営計画書に辿り着けます。
経営計画をまだ作成されていない方は、まずは1年間の短期経営計画から挑戦されてみてはいかがでしょうか。
◇経営計画 関連記事
経営計画の作成支援サービス
匠税理士事務所では、会社様の短期経営計画や中期経営計画の作成支援を行っております。また、これらの経営計画が作成のみでは終わることがないように、その後の実績との比較検証をサポートしております。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
品川区の税理士匠税理士事務所 ...TOPページへ
東京都の経営コンサルタントによる経営コンサルティング (13/10/25)
弊所では、
経営コンサルタントや各種分野の専門家が、
それぞれの能力を発揮することで、
お客様の黒字化支援・経営コンサルティングに力を入れております。
東京都の経営コンサルタントについて
経営コンサルタントというと
色々なイメージがあるかと思います。
その中で私たちは、
現場主義の経営コンサルティングを
提供する経営コンサルタントであるという信念をもって
コンサルティング業務に当たっております。

私たちは、
会計の専門家という立場から
会社の現状を社長と一緒になって共有できる立場にあり、
かつ、
これまで15年以上にわたって
数多くの経営者にとってのパートナーとして
経営コンサルティングに
取り組んできたという実績を
もっている経営コンサルタントが
所属している東京都の事務所です。
こうした専門能力やこれまでのノウハウを活かして、
一件でも多くの経営改善のお役に立てるよう努めています。
経営コンサルティングについて
私たちは、これまで下記のような数多くの会社様の
経営コンサルティングをさせて頂きました。
このようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談下さい。
< 今までご相談を頂いた内容 >
・現在は赤字経営だが、黒字経営にどうしてもしていきたい。
・自分の目標としている黒字にまでは、まだまだ届かない。
・会社の社長になったばかりで、そもそも黒字経営にどうしたらなるのか分からない。
・会社が大きくなってきて、どこに問題があるのか分からない。
・利益が出ているが、何故かお金が残らない・・・
・経営に一緒になって取り組んでいく相談役を求めている・・・・

このようなお悩みをお持ちの経営者の方は
お気軽にご相談下さい。
この他、人事などのコンサルティングにも
対応できる専門家も在籍しております。
経営コンサルティングサービスや経営コンサルタントのご紹介
弊所のコンサルタントによる
東京都や神奈川の会社様を対象にした
具体的なコンサルティングサービスにつきましては、
下記よりご確認下さい。
→ 経営コンサルタント・税理士など専門家の紹介 はこちらからご確認下さい。
会社の経営を支援する経営コンサルティングサービスの詳細
→ 法人向け経営支援サービスの一覧 はこちらからご確認下さい。
<東京都や神奈川県が経営コンサルティングの対応地域となります。>
弊所の経営コンサルティングサービスにつきましては、
東京都又は神奈川県の会社様のみに提供させて頂いております。
経済産業省より認定支援機関としての認可も受けておりますので、
経営支援のための各種制度を利用した経営コンサルティングを
実施することも可能です。
<経営のお役立ち情報はこちらから>
ここでは、経営者の方に向けた経営お役立ち情報を記載しております。
経営に関するお役立ち情報は、
今後も随時更新していきますので、
お気軽にご覧ください。
≪p3≫ 儲かって、お金が残る会社にするには
≪p4≫ 粗利を決める売価決定の重要性
≪p5≫ 販売戦略は重要!自社販売か、代理店等の委託販売か?
≪p6≫ 外注と内製化、どちらが会社にとって有利か
≪p7≫ 経営理念と経営計画を作りたい方へ
≪p10≫ 黒字倒産とは何か、どうやって防ぐのか?
≪w≫ その他のコンサルティング情報
最終更新日:平成26年12月6日
その他のご相談につきましても承っております。
サービスの詳細につきましては、
下記よりTOPページからご確認下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
年末調整とは?年調のやり方や源泉徴収票の作成方法と作成代行≪p11≫ (13/10/22)
秋になると年末調整の資料として、税務署や生命保険・損害保険会社から
個人事業主や会社宛てに年末調整のご案内や保険料の控除証明が届き始める季節です。
そもそも、年末調整とは何なのでしょうか? (こんな感じの書類です↓)
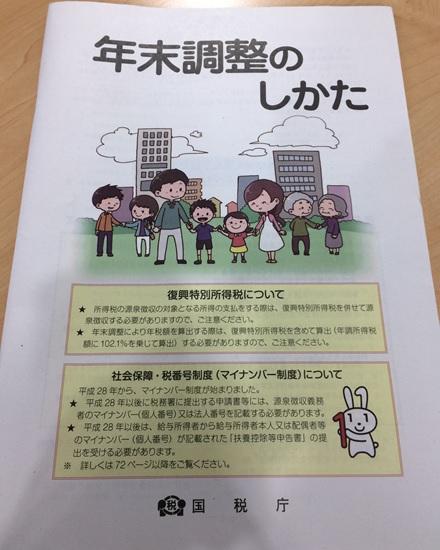
年末調整・年調とは何か?そのやり方や作成方法
個人事業主でも、会社を経営されている場合でも人を雇用されていると、
毎月、支給される給与から源泉所得税という税金を差し引いています。
【 給与から、税金が差し引かれているにもかかわらず、なぜ年末調整を行うのでしょうか。 】
これは、毎月給与からひかれている源泉所得税は、給与が毎月概ね一定であり、
生命保険の加入など個別の状況は加味せずに、
給与から社会保険を天引きしているようなケースを想定して税金を【 概算 】で計算しているからです。
給与からひかれている源泉所得税は、1月1日から12月31日までの期間で計算・集計が行われます。
しかし、【 概算で 】源泉所得税を計算しても、従業員の方の各人ごとの最終的な正しい金額を計算しなければ、
正しい所得税・住民税を納付することができません。
そこで、概算計算していた税額を、年末に調整して、正しい金額にするという年末調整が必要になります。
【 年末調整することで 概算税額 と 最終税額 に差が出る主なケース 】①年間を通して毎月の給与に変動がある場合(退職や就職)
②年の途中で扶養などに異動があった時
③配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料、小規模企業共済等掛金控除の控除などがある場合
このようなケースの場合には毎月の源泉所得税と
年間で計算をした源泉所得税との間に納付漏れや、過剰納付が発生します。
この不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末に
その年に納めるべき税額を正しく計算することが必要となります。
この結果、年末の給与に追加で還付される場合や徴収される場合が出てくるということになるのです。

年末調整の例外と源泉徴収票の作成方法
年末調整は、原則として全員社員の方が対象となります。
しかし一部、例外的に年末調整の対象とならないケースがあります。
・主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
・災害被害者に対する租税の減免等により猶予又は還付を受けた人
・月額表又は日額表の乙欄適用者
2か所以上から給与の支払を受けている人(乙)
年末調整時までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
・年の中途で退職した人(死亡退職等一部除く)
源泉徴収票の作成
年末調整を行った後に会社から源泉徴収票が発行されます。
これによって一年間の給与と源泉所得税の額が確定します。
源泉徴収票を作成することで、会社で働く社員さんは、年間の収入証明としても利用できますし、
この源泉徴収票のデータを給与支払報告書という形で、各市区町村に提出報告することで、
来年度からの住民税の額が決定されます。
このように源泉徴収票は、さまざまな場面で必要となります。
コピーをとったり、紛失をさけるなど取り扱いには十分に気を付ける必要があります。
年末調整をしないとどうなるか?
年末調整をしないと働く社員さんの住民税決定に必要な給与支払報告書を作成・提出ができず、
各市区町村から社員さんあてに問い合わせがくるなどして、
社員さんにご迷惑をかけることになりますし、会社にとっても源泉徴収した税額を正しく納付しないことになると、
税務署からペナルティを課されるということになりますので、期限までにしっかりと対応するようにしましょう。
匠税理士事務所の特徴、どんな税理士がいてどんな事務所?
弊所は、起業支援と経営支援に力を入れている会計事務所です。
お客様の起業成功と経営支援を行うには、人材の質とサービスの質が重要と考えており、これらを通じて、お客様満足度の最大化を目指しております。
匠税理士事務所の税理士や提携先の専門家・料金や所在地などの事務所全体につきましては、
こちらより事務所概要をご確認いただけますと幸いです。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

匠税理士事務所の年末調整・源泉徴収票作成サービス
匠税理士事務所では年末調整や源泉徴収票の作成代行を承っております。
人事労務の専門家である社会保険労務士と連携することで、
毎月の給与計算の代行から社会保険の手続き代行にも対応しております。
サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。
【 → 年末調整や源泉徴収票の作成・給与計算の代行サービス 】

◇バックナンバーはこちら→
年末調整以外の税務や会計のサービスラインにつきましては、以下よりTOPページへ移動の上で
ご確認をお願いします。
【 → 世田谷や目黒、品川の税理士は匠税理士事務所 】
税理士の対応エリアは、世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域となります。
最後までお読みくださりまして、ありがとうございました。
人材を最大限に活用し、黒字経営を実現するには (13/10/12)
中小企業は人材の確保が難しいのが現状です。
しかし、中小企業にも上場企業に負けない人材が来てくれることがあります。
それは何故でしょうか。
色々な理由があると思いますが、
中小企業なら大企業には無いような昇進・昇給ができるのではないか、
自分の能力を最大限に引き出した仕事ができるのではないかという期待が
主な理由だと思います。
そして、このような期待を抱いて来てくれた人材を最大限に活用して、
会社を発展させて、
社員の期待にしっかりと応えていくには
部門別管理がとても有効に機能します。
社員の能力を最大限に引き出す、部門別管理
部門別管理とは、
端的にいえば優秀な人材には、
権限を与えると同時に、責任を与え、
成果を出せば、昇格・昇給を随時行うという至ってシンプルで公平な評価制度です。
そのため、会社の事業ごとに部門を編成し、
部門ごとの収益を測定し、これに基づき評価していくことになります。
実際に伸びている会社は、
この部門別管理を導入しており、
優れた成果を上げた部門の社員は、
スピード昇進しています。
会社の成功と自分の成功
『 会社が成功すれば、自分も成功できる。』
部門別管理などを通じて、
このように社員に思ってもらうことができれば、
社員の潜在能力を引出して、
業績を大きく伸ばすことも可能になります。
中小企業は、
上場企業のような知名度はありませんが、
上場企業に無いようなスピードと自由性があります。
社内で全員が能力を引き出すことができるような
風土・仕組みを作り黒字経営を実現することは、
経営者の重要な仕事です。
※ 黒字経営支援の匠税理士事務所 匠税理士事務所TOPページへ
匠税理士事務所は、経営支援を通じてお客様の黒字率100%を目指します。
※税理士水野智史の黒字経営コンサルティング ※女性税理士宮崎の起業館
更新日時:25.10.12
奥沢近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所へ (13/10/08)
匠税理士事務所は、世田谷区の奥沢(おくさわ)すぐ自由が丘駅徒歩2分の会計事務所です。
東急大井町線自由が丘駅で下車をしていただくか、
目黒線にて奥沢駅徒歩5分の立地にございます。
匠税理士事務所は、サービス品質をできる限り 高めるため、人材や提携先の質にこだわり、 世界4大会計事務所出身の税理士を中心に、 各分野トップレベルの提携専門家で構成されます。所属税理士やサービスはこちらをご確認下さい。

奥沢で会社設立など独立開業・起業支援
これから奥沢で会社設立をお考えの方で、
会社設立手続きの代行をご検討されている方には、
起業支援に強い税理士が会社設立を行います。
また、独立開業し会社設立後の経理や経営など
起業支援も充実しておりますので、
起業後は本業に集中して頂けるよう努めています。サービスの詳細はこちらで確認をお願いします。
起業支援を担当する税理士・専門家はこちら
【→匠税理士事務所の概要】

奥沢での会社設立代行のみも承ってます。
会社設立など起業支援詳細はこちらから

奥沢で創業融資による創業支援
また、起業後に必要な資金の一部を政府系の
創業融資や世田谷区の自治体による制度融資で、
資金調達したいとお考えの方につきましては、
城南信用金庫の奥沢支店など世田谷区のエリアに
対応した各種金融機関と連携して、
起業時の資金調達・創業融資も行ってます。
これまで多数の融資支援実績がありますので、
起業資金でお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
税理士によるサービスの詳細はこちらから。
ご希望の場合には、日本政策金融公庫以外にも
制度融資や助成金などのサポートも行ってます。

世田谷区奥沢の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は奥沢など世田谷全域対応)
奥沢の経営支援や経理、確定申告、決算サービス
匠税理士事務所は、会社を大きくしたい社長様向け
経営コンサルティングや戦略的な会計による
事業の見える化をお手伝いする税理士です。
これまで世田谷の奥沢でお付き合いいただきました
お客さまの経営パートナーとして税理士が
経営や経理に一緒になって取り組みます。
会社を大きくするためには、
≪ 販売や商品、営業 ≫だけではなく
≪ 儲かる仕組みや、資金のバランス、経営者の感覚と会計の一致 ≫ これらの要素も重要となります。

売上などの本業部門が大きくなるなか
管理部門の成長が追い付かないお客様や、
社長の感覚の数字と、会計にかい離があるといった
お客様に対して会計や管理体制を整え
感覚と会計を一致させ事業の意思決定となる
戦略的な会計をご提案致します。
また経営革新等支援機関認定を受けており、
奥沢の会社様のコンサルティングにも
積極的に取り組んでおります。
会社様向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向け確定申告や法人化など
サービスはこちらからご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
奥沢で税理士・会計事務所による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

奥沢の税理士事務所による法人化・法人成り
匠税理士事務所は、奥沢で独立開業して、
個人事業主から会社設立する法人化・法人成りを
支援する会計事務所です。
奥沢など世田谷区で法人化・法人成り代行を
お考えの方はこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
奥沢で会社設立されたお客様の声
<奥沢の小売業 F株式会社様>
これまで会社では、仕入れを担当していたので、
事業のことは良く理解していたつもりでしたが、
実際に独立し会社設立してみると、
経理や社会保険など知らないことが多かったので、
自宅近くの匠税理士さんにお願いしました。
経理は、全て会計事務所さんでやって下さりますし、
社会保険についても社労士さんをご紹介頂き、
丁寧に対応してもらって満足しております。

<奥沢近くホームページ制作 法人化T様>
これまでは、自分で経理ソフトを買って
経理をしていたのですが、業績が全然つかめず、
これから先、どうやっていくかを考えずに
事業し、これは良くないと思い相談しました。
実際に税理士さんにお願いしてみると、
毎月の業績も分かりやすく教えてもらえて、
面白い提案もいただけるので助かっています。
これからも宜しくお願いします。

奥沢駅から会計事務所までのアクセス
奥沢から匠税理士事務所までの場合
①奥沢の駅 出入口1を出ていただくと
目の前が自由通りとなっております。
②自由通りをまっすぐ直進します。
郵便局世田谷奥沢局や神社方面となります。
③自由通りを下り踏切や東急ストアを通過すると
城南信用金庫自由が丘支店、セブンイレブンが見えてきます。
③交差点をセブンイレブン方面(右折)すると
ラボエムというイタリアン料理店がございます。
④ラボエムビル一つ先のビルが弊所です。
東京都目黒区自由が丘1-4-10 カランタ1966 404
電話 03-6272-4704
税理士や会計事務所の対応エリアは、奥沢など世田谷区など東京都23区エリアとなります。
奥沢近くの税理士・会計事務所の採用求人
世田谷区奥沢近くの税理士事務所や
会計事務所の採用や求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
奥沢での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#奥沢税理士
#奥沢起業支援
経営者の仕事とは何か、社長に求められるものとは (13/09/28)
経営者の仕事とは、何でしょうか。
日々様々な業務や判断に追われる中、このようにお考えになったことはないでしょうか。
経営者の仕事について考えるときはいつか?
・事業承継された時
・売上規模などの会社の成長スピードと、組織の成長スピードとがアンバランスになった時
・経営者の考えている利益と、実際の利益がかい離している時
上記にあてはまる場合には、経営者の仕事について立ち止まって考える絶好のチャンスです。
経営者・社長の仕事とは何か
この問いに対しては、色々なお考えがあると思います。
・やれば良いもの
・やらなければならないもの
とを分類し、やらなければならないものについて経営者の仕事とは大きく以下の5つ仕事だと考えます。

1 必ず黒字経営を行うこと
赤字経営を続けていると将来的には潰れます。
会社を経営していく以上は、従業員の方々の生活を守り、取引先や社会に対して責任を果たす義務があります。
これらは、黒字経営を行うこと以外で達成は不可欠です。
(関連記事:経営分析や財務などの指標を抑えた経営戦略)
2 未来の収益事業を生み出すこと
経済環境は絶えず変化します。
こうした中で今の収益事業が将来にわたっても、収益事業である保証はありません。
そこで現在の収益事業の維持は、原則他のスタッフを中心にして行い、
社長は将来の収益事業(新商品や新市場)の開拓に絶えず挑戦することが必要であり、この姿勢が会社の継続的な発展を可能にします。
3 会社を一つにまとめること
会社が大きくなってくると、会社にかかわる人も増えてきます。
これらの方に経営者の考えをしっかりと伝えて、
それぞれがそれぞれの能力を出し、責務を果たせるような仕組みを作ることが、会社の成長に不可欠です。
(関連記事:経営理念と経営計画を作りたい方へ)
4 適切な評価基準を持つこと
社員の頑張りをしっかりと評価し、頑張りに報いれる評価基準を構築することは、
優秀なスタッフを確保し、より成果をあげていくために不可欠です。
そのためには、適切な給与制度を作ることや、
会社への利益貢献度合いを的確に把握するための部門別管理制度などの手法が有効となります。
5 長期的な視点をもち、断固として決断・実行していくこと
会社を経営していく上で、いい時もあれば悪いときもあります。
その際に、時勢を見極めて長期的な視点をもち、
先陣をきって決断、実行してリーダーシップを発揮することが会社を発展させるためには重要です。
きちんとした理念や考えがあっても、会社が赤字では、従業員の生活を満足に保障できません。
そのため優先順位の高いものから順番に列挙をさせていただきました。
匠税理士事務所の経営支援サービス
匠税理士事務所では、社長様が<社長の仕事>に集中できるようにお手伝いし、これらを通じて関与先の黒字率100%を目指しています。
サービスの詳細はこちらから
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
駒沢公園や駒沢大学駅近くの会計事務所は匠税理士事務所 (13/09/27)
匠税理士事務所は、駒沢など世田谷区を中心に
【起業支援】・【経営支援】が得意な事務所です。
世田谷の駒沢(駒沢公園・駒沢大学駅)で、
・これから会社設立をする予定があり、 起業支援に強い税理士を探している ・経営支援に強い税理士を探している ・駒沢や駒沢大学駅など世田谷近くで30代・40代 若手税理士や会計士を探しているといったご希望にお応えできるように
【 人の質・サービスの質 】にこだわって、
駒沢大学駅や駒沢など世田谷エリアのお客様に
起業・経営支援でご好評を頂いております。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の税理士やサービスは、
こちらよりご確認をお願い致します。

駒沢や駒沢大学駅での経営支援
社長の仕事は、【経営】です。
しかし、実際は従業員さんに任せにくい業務が
社長の仕事となり、経営がしづらくなります。
匠税理士事務所では、駒沢公園や駒沢大学駅など
世田谷エリアを中心に経営に集中できるよう
・会計のアウトソーシング
・労務や人事のアウトソーシング
これらの業務により社長の経営以外に使用する時間を短縮し、
本業に集中できる環境整備をお手伝い致します。
会計などのアウトソーシングで生まれた時間に
コンサルティングを通じて、
会社をよくする【 経営 】に取り組みます。

経営には従業員や仕入れ先、得意先や金融機関など
様々な対外的なお取引がございます。
その全ての問題や悩み、さまざまな調整を行う
経営には多くの判断を行い続ける必要があります。
その判断の局面でこれまで数多くの公的機関で
経営セミナー講師を担当してきたノウハウを駆使し、
駒沢や駒沢公園など世田谷エリアの社長様の
経営相談にお応えします。
匠税理士事務所のアウトソーシングサービスや
駒沢での経営支援などはこちらを確認下さい。
駒沢公園や駒沢大学担当の税理士・専門家はこちら【 → 匠税理士事務所の概要 】

対応エリア:駒沢公園や駒沢大学など世田谷区
駒沢の会社設立・創業融資など起業支援
匠税理士事務所は、駒沢で会社を設立する方に
会社設立の代行や設立後の会計や経営支援、
資金調達など起業支援に力を入れる事務所です。
駒沢で会社設立・会計などに関する詳細は
こちらよりご確認をお願いします。
世田谷の駒沢(駒沢公園・駒沢大学駅)で
会社設立時の起業資金調達のための
創業融資はこちらでご確認下さい。

駒沢の会計経理や確定申告・法人化代行
既に駒沢公園や駒沢大学など世田谷エリアで
会社を経営されている方に向けては、
利益戦略会議やキャッシュストック経営など
独自コンサルティングをご用意してます。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
駒沢公園や駒沢大学の方向け確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
駒沢公園や駒沢大学駅で税理士の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

駒沢公園や駒沢大学駅の独立開業・創業支援
駒沢公園や駒沢大学駅の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は駒沢公園や駒沢大学駅など世田谷全域対応)
駒沢公園や駒沢大学駅で会社設立された方
<駒沢公園で会社設立された制作会社W様>
世田谷の産業振興公社で開催されてた会社設立セミナーで、
水野先生の講義を受講し同世代の税理士や会計士が
色々と相談しやすいと思っていたので、
話をしたときのフィーリングもあったので、
駒沢にある会社の税理士をお願いしました。
いつもよい提案を頂いたり、
熱心に相談にのってもらって
会計も任せられて大変助かっています。
<世田谷の駒沢大学駅で法人化の卸売会社K様>
これまでの税理士や会計士と色々とあったので、
駒沢大学駅の近くで税理士を探していたところ、
知り合いから匠税理士事務所を紹介してもらって、
法人化をお願いすることにしました。
税金や会計だけしか税理士さんや会計事務所さんは
対応してくれないと思っていたのですが、
経営でもいいアドバイスをくれるので
任せて良かったです。
これからも宜しくお願いします。
駒沢公園や駒沢大学駅の法人化・会社設立登記
駒沢公園や駒沢大学駅など世田谷区で
個人から会社設立する法人化・法人成りはこちら
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
駒沢公園や駒沢大学駅で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が駒沢公園や駒沢大学駅で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
駒沢公園・駒澤大学駅からのアクセス
駒沢公園や駒沢大学駅方面からのルート
東急バス 渋谷駅から八雲駅にご乗車いただき
自由が丘駅前にて下車をお願いいたします。
バスは、駒沢大学駅前や駒沢公園東口をご利用いただくと便利です。
駒沢方面からお車でお越しの場合には、
隣接に時間貸し駐車場がございますので
こちらをご利用ください。
税理士事務所・会計事務所の求人採用情報世田谷の駒沢公園や駒澤大学駅など近くの
税理士事務所・会計事務所の求人採用情報は
求人ページをご確認をいただければ幸いです。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
駒沢公園や駒沢大学駅での会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#駒沢税理士
#駒沢会社設立
認定支援機関による創業融資支援(日本政策金融公庫) (13/09/21)
サービス起業>創業融資支援サービス>認定支援機関
創業融資のサービスやお役立ち情報はこちら
創業融資サービス 世田谷・目黒・品川に対応
経営革新等支援機関とは?~日本政策金融公庫のメリット~
第9回 匠税理士事務所では、経済産業省より経営革新等支援機関として認定を受けております。これにより起業や創業時の資金面の問題ついて、幅広く手厚いサポートをすることが可能となっております。
経営革新等支援機関の詳細はこちら 中小企業の財務を支援する経営革新等支援機関 へ。
経営革新等支援機関とは
多様化・複雑化する中小企業を巡る経営課題について
中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が
一定レベル以上のものについて、経済産業省が認定を行うものです。
これから起業されるお客様や起業されて間もないお客様の資金需要(創業融資)は、日本政策金融公庫などの提携金融機関と連携してお客様をサポート致します!
日本政策金融公庫など創業融資の種類

創業時に創業融資を検討される方の多くは、
1 日本政策金融公庫の創業融資
2 各行政機関と連携した制度融資
の大きく分けて2つの切り口で、創業融資を検討されると思います。
※創業融資とは、金融機関からの借入を言います。
起業間もない時期を、創業期といい、創業期に借りるお金を創業融資といいます。
上記1の日本政策金融公庫での創業融資では、自己資本の2倍までしか融資を受けることができないということが、
一つの大きな条件としてネックとなっています。
(関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき)
しかし、起業される業種や、一部の起業では、開業時の自己資金を必要資金の2倍枠までそろえることが難しい場合もあります。
このような、しっかりとした事業計画がありながら
通常の創業融資では対応が難しい多額の資金を必要とする起業につきましては、経営革新等支援機関として、融資のサポート致します。
認定支援機関による創業融資サポート

認定支援機関による創業融資の支援のメリットは、 自己資本の制限を超えて
融資を受けることが可能となるケースがあるということです。
これは、日本政策金融公庫との連携による中小企業経営力強化資金という制度になります。
匠税理士事務所では、お客様のお金についての幅広いニーズにお応えするため
経済産業省より認定支援機関の認定を受けることで、一部の創業融資について自己資本の制限を超えた、融資を検討することが可能です。

認定支援機関の支援による融資について
この融資制度は、認定支援機関による事業計画の実行可能性の認証というものが必要となります。
そのため自己資本がゼロという場合には、融資を受けることは難しいですが、
自己資本はしっかりと用意できたものの、初期の設備投資が多額になってしまうようなビジネスなどの場合には、ご利用が可能となるサービスです。
創業融資を受ける際の利率につきましても、大幅に引き下げを行うことができるといったメリットがございます。
ただし認定支援機関としての融資制度を利用した場合には、事業計画書の進捗度会いを3年ほど日本政策金融公庫へ/>レポーティングする必要が出てきます。
ご利用いただける方
次のすべてに当てはまる方
1.経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
※日本政策金融公庫より 2015年6月現在の条件です。
その他の、創業融資のお役立ち情報(バックナンバー)をご覧になりたい方は、こちらです。
創業融資の情報館 バックナンバー
匠税理士事務所の創業融資支援サービスについて
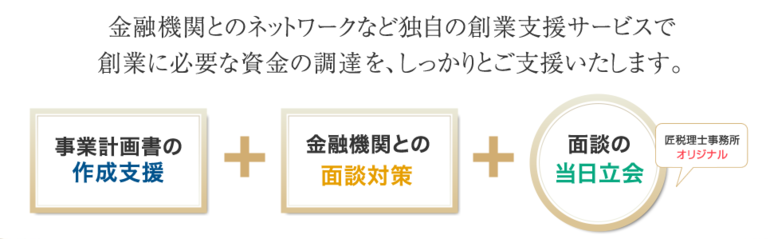
匠税理士事務所では、これまで多くの創業融資をサポートさせて頂き、認定支援機関の制度を活用した融資の実績も重ねてまいりました。こうした活動を通じて大変多くの起業家の方からご好評を頂いております。
認定支援機関による創業融資支援に関するサービスの詳細については、お問い合わせください。
創業融資支援サービス
創業融資についてお役立ち情報のバックナンバーは、、創業融資の情報館 バックナンバー へ。
経営革新等支援機関の詳細はこちら 、中小企業の財務を支援する経営革新等支援機関 へ。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
起業支援サービス一覧
会社設立の代行や起業後の経理や、給与計算・社会保険、経営サポート
匠税理士事務所の特徴
創業融資・資金調達支援サービス
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
利益を確保し黒字経営するのためには何が必要か、経営のポイント (13/09/21)
利益を出すためには、どうしたら良いか。
時代によって、人やモノ、売価や商品は常に変化し続けるため、黒字経営は永遠のテーマです。
・赤字の会社を黒字にする
・黒字経営の会社であっても業績改善が必要な場合
には、どんなところから始めるべきでしょうか。
黒字会社の経営者様の共通項として、自社の損益に対して、
儲かる型(経営戦略)をお持ちであり、かつ、下記のポイントを抑えているという共通項があります。
会社を経営されていると、沢山の問題に直面するので、問題が複雑になってきます。
今回は、利益を出すためのポイントを、シンプルに考えられるよう、大きく3つにしぼります。
◇目次
① 売上を確保する販路の点検
② 粗利を確保する商品と得意先の点検
③ 役立たない固定費がうまれていないかの点検
黒字経営のポイント(経営分析と財務指標)

売価に対する粗利(付加価値)の割合が適正か
・・売価の〇〇%の粗利を確保する商品や得意先の構成
売価に対する営業など売上につながる経費割合は適正か
・・目標売上を達成するために、どのように営業経費を使うか
売価に対する管理に要する経費は妥当か
・・事務所賃料や管理部門の人件費が前年比でどう変化したのか
売上を確保する販路の点検
売上至上主義の落とし穴と売上総利益(粗利)の重要性
売上を伸ばすことは、とても難しいことです。
社長様の多くの時間は、この売上を伸ばすことに注力されます。
売り上げを伸ばすためには、商品の開発や改良、人の教育(技術力向上)
売価の設定、販路の開拓が必要となります。


売上は伸びれば伸びる程、良いことなのですが、
注意すべきことがあります。
社長の仕事に必要な利益とお金が確保できる売り上げが必要となるという点です。
例えば
長期工事にもかかわらずほとんど利益が出ていないケース。
こうしたことから、取引するかを決める前に、
○粗利がどれだけ会社に入るかを見極める
○適正在庫を保てるような在庫管理ができるか見極める
○その得意先と取引をして大丈夫か見極める
をよくよく検討してから、会社として取引きを行うべきか判断すべきです。
◇関連記事
粗利を確保する商品と得意先の点検
商売の源である粗利をしっかりと確保できているのか、を確認します。
低すぎる場合には、この立て直しが急務となります。
この粗利(売上総利益)を改善しない限り、コストカットで利益を出していくしかないのですが、
コストカットも限界があるため、
ビジネスの根幹である粗利を改善することが必要になってきます。
◇関連記事
役立たない固定費がうまれていないかの点検
◇営業など売上につながる経費は適正か
粗利を確保するために、攻めである営業面に経費が使われているのかを検証します。
少なすぎると売上UPは難しくなりますし、
長い目で見ると、ライバルとの力関係も悪化していきますので、売上が下がっていくことになります。
市場における地位の確保のためにも営業という攻めに適正な投資を行うことが重要です。
営業では、自社の広告宣伝の他
良い取引先へのアプローチのため、新しい商品や技術の研究、外注先との交渉といったことも含まれます。
売価に対する管理に要する経費は妥当か
粗利を確保して、ここから会社の家賃や、人件費などの固定費を引いて、会社の本業の力を示す利益が算定されます。
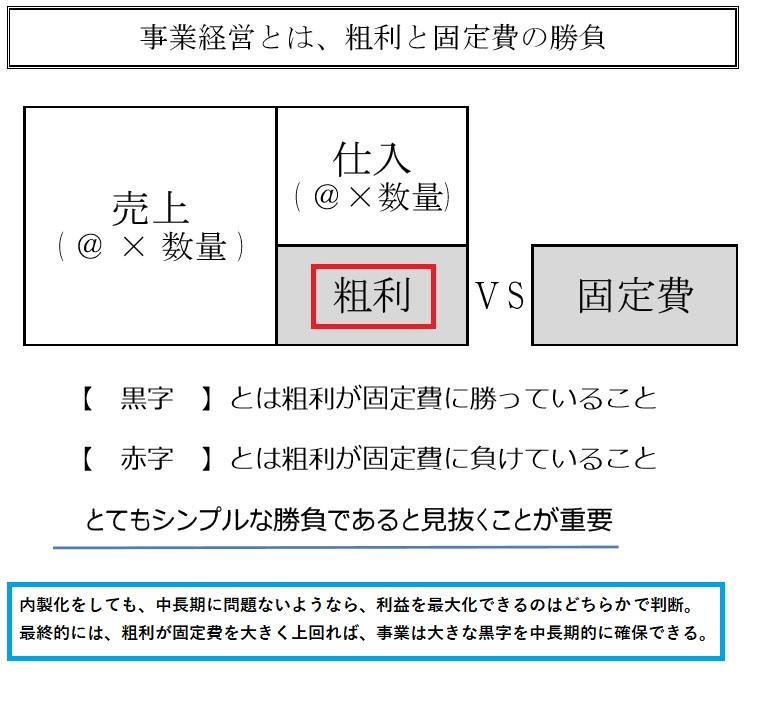
そのため固定費については常に見直しを行うことが、最終利益を確保するためには不可欠になってきます。
固定費の見直しは、必要な管理費(固定費)を削ってしまうと、
逆に売上総利益(粗利)に悪影響が出てしまうこともあります。
をしっかりと見極めて役割を果たしていないものがないか検討することが重要です。
人件費などは、簡便的な日報も有効です。
こうした改善を一つ一つしっかりと行っていくことで、最終的に利益が会社に残りやすい体質になってきます。
ある程度の管理機能を持っている方が利益は出やすくなります。
粗利別得意先一覧なども有効です。
経営分析や財務指標を用いた経営戦略
各種指標を用いた経営分析を行って、こうした大きく分けて3つの視点から会社全体を見ていくことで、
黒字経営のための改善点や経営の戦略が浮かび上がってきます。
経営戦略という大枠が決まれば、経営の戦術という細かい打ち手は、容易に浮かんできますので、
この戦略という大枠を、見誤らないためにも大きな視点で自社の課題を抑えることが重要です。
サービスの詳細はこちらから
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
世田谷の税理士は匠税理士事務所...TOPページへ
年次有給休暇や欠勤、遅刻、休暇の給与計算≪p10≫ (13/09/18)
年次有給休暇とは何か? 有給日数の計算方法
有給休暇とは、 継続勤務し、
所定労働日数のうち一定の割合の日数を出勤した労働者に対して
給与が支払われる休暇を言います。
≪有給の日数≫
この有給休暇を得るための条件は、
「雇い入れの日から起算して6カ月以上継続勤務し、
全労働日の8割以上出勤した労働者に
継続又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定されています。
詳細な日数 年次有給休暇とはどのような制度ですか。
≪条件≫
全労働日の8割以上出勤した労働者が対象となります。
この場合の全労働日とは、
就業規則に定められた会社の所定休日と法定休日を差し引いた日数をいいます。
ただし次のような休業期間は出勤したものとみなされます。
1. 業務行の傷病のために休んだ期間
2. 育児休業介護法による育児休業又は介護休業した期間
3. 6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産する予定の女子が
休業した期間及び産後8週間休業した期間
4. 年次有給休暇を取得した日
有給休暇中の給与計算と給与の支払い
有給休暇の期間中は、下記のいずれかから選択した方法により支給します。
これは労働基準法に定められています。
1. 平均賃金
2. 所定の労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3. 健康保険法に定める標準報酬月額に相当する額
※1.2の場合は事前に就業規則に定めておく必要があります
※3の場合は、労使協定が必要で1.2の支払いは選択できません
有給休暇の時効と買取
有給休暇の時効は2年です。
当年で消化しきれなかった有給は、翌年度に限り繰り越しができます。
時効で消滅した年次有給休暇については
法定付与日数分は買取禁止です。
ただし法定付与日数を超える分については
買い上げをしても良いことになっています。
(買取の義務はありません。)
【特別休暇】
その他会社で定めている家族の結婚式や、
創立記念日など特別の休暇を定めている場合には
就業規則などにおいて、
休暇日数、有給か無給かを明示することで
有給とするか、無給とするかなどを
それぞれの会社で定められることとなっています。
この場合の計算方法は就業規則の定めによって、
つまり会社によって決定することができます。
【欠勤】
欠勤控除は労働基準法に定めがありませんので
会社が定めた就業規則によって決定することができます。
一般的には、
欠勤控除する給与項目 /一年間における一か月の平均労働日数 × 欠勤日数
【遅刻や早退】
遅刻や早退は給与を減額することができます。
この時には労働基準法に規定する下記の金額を超えないことがポイントです。
① 遅刻や早退など一つの案件に対する一回の減給制裁の額が
労働者の平均賃金一日分の1/2
② 減給制裁の総額は、一賃金支払期間の賃金総額の1/10
つまり、遅刻や早退の時間に相当する給与控除額を超えて
減額をするときには、労働基準法に定める制裁を超えないようにしなければなりません。
年次有給休暇などの勤怠管理と給与計算や社会保険のアウトソーシング
弊所では社会保険労務士事務所と共に、
年次有給休暇の勤怠管理や給与計算・社会保険のアウトソーシングを
行っております。
給与計算や社会保険の代行サービスの詳細は、下記よりご確認下さい。
経理のアウトソーシングや会社経営支援はこちらからご確認下さい。
その他の給与計算トピックスはこちら
≪p1≫給与計算と社会保険料の概要
≪p2≫社会保険や労働保険の役割とは?
≪p3≫給与計算の年間スケジュール
≪p5≫法定労働時間と残業手当の計算方法
◇バックナンバーはこちら→
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:26.2.25
品川区の匠税理士事務所 TOPへ
休日出勤の割増し賃金などの給与計算について≪p9≫ (13/09/14)
協定を結んだ上で、
休日労働を行う場合の割増賃金に
該当するか否かの判断はどのように行えば良いのでしょうか。
休日労働を行う場合の割増賃金
結論は、法定休日に出勤をした場合には、
割増賃金30%以上を支払う必要があります。
※ただし、法定休日には法定労働時間というものが存在しません。
休日労働をさせた場合は
時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
(関連記事:法定労働時間と残業手当の計算方法
)
≪法定休日とは≫
労働基準法に定められている
休日としなければならない日を言います。
具体的には
「毎週少なくとも1日以上の休日を与えなければならない」
「4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない」
とされています。
この休日を法定休日をいいます。
この法定休日は、特に日曜でなくても良いとされています。
代休と振替休日の違いとは
「代休」とは
休日労働が行った後に、他の出勤日を休みとすることです。
休日労働の代償として他の労働日を休みとするものであって、
前もって休日を振り替えることではありません、
代休では、
休日労働分については割増賃金を支払う必要があります。
代休日については有給・無休は就業規則に定めます。
代休日が無給であれば
会社は休日手当の割増分だけ負担がでることになります。
「振替休日」とは
予め休日と定められていた日を労働日として、
そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
ポイントは、あらかじめということです。
また就業規則に振替の定めが必要です。
この場合には、
「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
※ただし振り替えた週の労働時間が40時間を超えるときには割増賃金が必要です。
休日出勤の割増し賃金などの給与計算や社会保険のアウトソーシングサービス
匠税理士事務所では、
提携の社労士事務所と連携して
休日出勤の割増し賃金などの給与計算や社会保険の手続きなどについて
アウトソーシングを承っております。
会社の経営支援や経理のアウトソーシングはこちらから
◇バックナンバーはこちら→
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:26.2.25
TOPページへ世田谷の税理士は匠税理士事務所
上目黒や下目黒の税理士・会計事務所なら匠税理士事務所 (13/09/11)
匠税理士事務所HPに訪問ありがとうございます。
弊所は上目黒や下目黒など目黒を中心に起業支援や経営支援に力を入れている会計事務所です。
2008年税理士事務所を設立して目黒区を拠点に、地元密着でお客様のお役に立ち、
【 会社に利益・お金を残す事 】を使命としてます。
上目黒や下目黒から便利な税理士事務所
匠税理士事務所は、
世界4大会計事務所出身の40代税理士が所属し 高度な専門性による経営支援が強い事務所です。また、上目黒や下目黒など目黒区を中心とする
各種金融機関や専門家などと連携することで
地元密着の会社設立、創業融資等の起業支援や
商工会議所目黒支部で経営セミナー講師も担当します。
上目黒や下目黒を担当する税理士や、
サービスは、こちらでご確認をお願いします。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士対応エリア:上目黒や下目黒など目黒区
上目黒や下目黒の会社設立や創業支援
当会計事務所は40代の税理士2名を中心に、
税理士有資格者や科目合格者など計10名が所属し
【高度な専門性】と【ノウハウ】を活用して
上目黒や下目黒で起業支援に力を入れてます。
起業支援サービスでは、お客様の会社が10年後も20年後も生き残れるよう 本業に集中できる環境整備、資金調達・経営支援等で黒字率100%を目指してます。
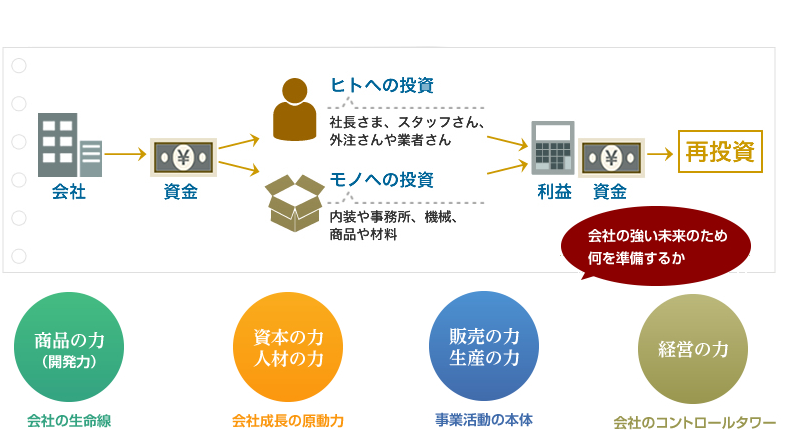 また、一生に一度の起業成功のために、
また、一生に一度の起業成功のために、
資本金はどのようにしたらよいのか、
株主構成や役員構成はどうしたらよいのか、
自己資金と必要資金とのバランスを考えて
創業融資を受けた方がよいのかなど
【 匠税理士事務所に任せてよかった 】といって頂けるように丁寧にサポートします。
上目黒や下目黒担当の税理士や専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

上目黒や下目黒での会社設立など創業支援は、
こちらから確認願います。
(上目黒や下目黒などの近くで、これから会社設立をされたいお客様向け会社設立支援です。)
上目黒や下目黒の創業融資など起業支援
これから上目黒・下目黒で会社設立したいが、
全てを自己資金で用意するのは難しいので
一部借入を検討しているという方や、
借入と並行し利用できる助成金がないかを
知りたいという方に向けて、
創業融資や助成金など創業支援も行ってます。
また、会社設立後の会計経理・決算・経営など
起業に必要な全てがそろう創業支援は、
こちらから確認をお願いします。
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
これから上目黒や下目黒で会社設立を行って
借入を受けたい方に向けた政策金融公庫や
目黒区を拠点とする金融機関との連携した
創業融資サービスはこちらをご確認下さい。
【→ 創業融資や資金調達支援サービス】
上目黒や下目黒で会社設立をして人を雇いたいが
助成金制度を知りたいという方や、
大変そうなので申請代行したい起業家の方に
上目黒・下目黒対応の社会保険労務士による
助成金など創業支援サービスもございます。
大変そうなので申請代行したい起業家の方に
詳細はこちらからご確認をお願いします。
会計経理や決算確定申告・法人化の代行
匠税理士事務所は、会社設立以外に、
会社や事業を経営されている方には
会計経理や決算・税務申告をご用意しております。
また個人の方に向けましては、
確定申告や法人化などの代行も承っております。
【事業に伴う全てがそろう会計事務所】を軸に、日々サービスラインの充実と提携専門家と
スタッフの充実に取り組んでおります。
上目黒や下目黒での各サービスはこちらから
ご確認をいただければ幸いです。
会社様向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
個人の方向けサービスはこちらからご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
上目黒・下目黒で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

上目黒や下目黒の会社様向けの経営支援
弊所では担当させて頂いてる会社様全てを
黒字にすることを目標に経営コンサル業務に
注力しております。
経営セミナーは商工会議所目黒支部様をはじめ
講師を歴任しご好評をいただいております。
また上目黒や下目黒などの会社様向け
経営コンサルティング以外にも、
会計や経理、給与計算や社会保険などの
アウトソーシングも承っております。
具体的なサービスは上記よりご確認下さい。

下目黒地域や上目黒で会社設立の場合
<下目黒 製造業 株式会社S様>会社設立後の経理や、
創業融資などを全てお願いできる下目黒に
近場の会計事務所を探していたところ、
下目黒の会社近く雅叙園で行われた創業支援の
セミナーで匠さんを知り顧問契約しました。
株式会社の会社設立の手続きや経理など
しっかりと対応して頂き大変助かりました。
製造業という関係で会社設立など起業時に
多くのお金が必要になるという悩みに対し、
創業融資でも大変お世話になりました。
採用などでもお世話になると思いますが、
今後も宜しくお願いします。
<上目黒 アパレル 合同会社B様>
上目黒で会社設立してしばらく知人に
紹介された税理士にお願していたのですが、
会社の経営を相談しても、職員さんからは、
あまり参考になる意見を頂けず、
経営の相談できる方を上目黒近くで探した際、
経営セミナーで匠税理士事務所さんの話を聞き
お願いすることにしました。
会社利益やお金の状況・改善策を分かりやすく
説明してくれて会社も随分良くなりました。
これからも宜しくお願いします。

目黒区の匠税理士事務所の概要
匠税理士事務所は、上目黒にある中目黒駅からの
アクセスや下目黒にある目黒駅からアクセスに
便利な目黒区の自由が丘駅2分の会計事務所です。
(奥沢駅から徒歩約5分の立地の事務所です。)
事務所概要や上目黒・下目黒から自由が丘駅までの経路や駅からのアクセスなどに
つきましては、下記よりご確認下さい。
上目黒や下目黒の会社設立・法人化登記情報
上目黒・下目黒など目黒区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
上目黒や下目黒など目黒区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 渋谷出張所 】管轄区域 目黒区
〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号
(渋谷地方合同庁舎)
上記が上目黒や下目黒で会社設立や、
法人化・法人成りに伴う登記の際に、
対応する行政窓口となります。
上目黒や下目黒近くの会計事務所の求人採用情報
弊所では、上目黒や下目黒などの近くの方で、
会計事務所での勤務経験のある方を募集してます。
正社員スタッフとパートスタッフ・アルバイトを
上目黒・下目黒近くの会計事務所勤務にご興味の方は
匠税理士事務所へお気軽にご連絡下さい。
求人に関する詳細な情報はこちらから
上目黒(かみめぐろ)や下目黒(しもめぐろ)地域の方はもちろん、それ以外の地域の方からの
ご応募もお待ちしております。
上目黒・下目黒で会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い税理士や会計事務所を
お探しなら匠税理士事務所へ相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#上目黒税理士
#上目黒会社設立
健康保険や厚生年金の計算方法と手続き(標準報酬月額の算定基礎届)≪p7≫ (13/09/09)
健康保険や厚生年金の計算方法の基礎となる給与には、
基本給の他に、各種手当や、残業などの時間外労働も含まれます。
健康保険や厚生年金の計算の基礎となる標準報酬月額
給与が変動するたびに毎月健康保険や厚生年金を変更すると
毎月納める健康保険や厚生年金の手続きや計算方法が
煩雑になるため一年に一度改定をし、
そこで決定した健康保険や厚生年金の金額を継続して給与から控除します。
一年に一度給与の額を決定し(標準報酬月額)
これに対する健康保険や厚生年金料を一定期間引き続けることとなります。
これが健康保険や厚生年金の計算方法です。
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決定するタイミングや手続き
次に手続きに関しては
≪健康保険や厚生年金の標準報酬月額の決定≫
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決定するタイミングは

1.資格取得時決定
2.定時決定
3.随時改定
この3つのタイミングがあります。
【資格取得時決定】
新たに従業員が入社したときに健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決めます。
入社から5日以内に手続きをします。
このとき残業手当などの項目については
自社で同じ仕事や役職の人の実態に合わせて見積もります。
【定時決定】
一年に一度、7月1日現在で在籍する被保険者全員を対象に
健康保険や厚生年金の標準報酬月額の見直しをします。
4月、5月、6月の総支給賃金の一か月平均により
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を計算します。
毎年7月1日から7月10日までの指定された日に届け出ます。
ここで決定された健康保険や厚生年金の標準報酬月額は
原則として、その年の9月1日から翌年の8月31日までの一年間使用され
新しい健康保険や厚生年金の標準報酬月額の保険料は
10月に支払われる給与からひかれます。
【随時改定】
健康保険や厚生年金の標準報酬月額は原則として、
その年の9月1日から翌年の8月31日までの一年間使用されます。
ただし次の3つの要件のいずれにも該当するときには
健康保険や厚生年金の標準報酬月額を改定する手続きが必要です。
①固定的給与が変わった時
②固定的給与が変動した月以降
3か月の給与支払基礎日数が各月とも17日以上あるとき
③変動した月以降3か月間の平均額でみる標準報酬月額の等級と
従来の等級との差が2等級以上あるとき
※ただし最低等級と最高等級は特例あり
この随時改定は
昇給があった3か月目の給与の支給後すみやかに手続きを行い
昇給後4か月目の給与から標準報酬月額が変更されるため
給与計算では昇給後5か月目の給与から
新しい標準報酬月額の保険料が給与からひかれます。
~固定的給与の変動とは~
固定的給与の変動とは
基本給などの昇減給、諸手当の新規・増額・減額支給
賃金体系や時給・日給などの基礎的単価の変更
時間外労働手当の割増率の変更をいいます。
残業手当などの変動的給与が増減しても
随時改定は行われません。
※変動的給与...各月の労働時間や勤務状況によって変動する給与
時間外労働手当、休日労働手当、深夜労働手当、宿日直手当、精勤・皆勤手当
健康保険や厚生年金の標準報酬月額算定基礎届出
匠税理士事務所では、
社会保険労務士事務所と共に
上記の健康保険や厚生年金の標準報酬月額算定基礎届出作成にも対応しております。
≪p7≫ 給与計算や社会保険の加入や変更手続きのアウトソーシングをご検討中の方は、
下記よりサービス内容をご確認頂けましたら幸いです。
その他の会計アウトソーシングや経営支援はこちらから
◇バックナンバーはこちら→
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:27.9.5
起業と確定申告の匠税理士事務所TOPへ
賞与の給与計算方法や社会保険などの手続き≪p6≫ (13/09/04)
賞与も給与と同じく、
社会保険料など控除される項目を計算する必要があります。
また、賞与の社会保険手続きも必要となるため
合わせて確認が必要です。
賞与から引かれる税金や社会保険料の計算方法
総額を計算したら、その総額についてかかる
①厚生年金や健康保険、介護保険料
②雇用保険料
③所得税
これらを計算します。
① 厚生年金や健康保険料、介護保険料の計算方法
年4回以上支払う賞与
→給与の標準報酬月額を決めるときに、標準報酬月額に含むことになっています。
年3回以下で支払う賞与
→給与の標準報酬月額を決めるときに含めていませんので
給与の社会保険料とは別に
賞与を支払う都度保険料を徴収して、納付する必要があります。
【保険料の計算方法】
賞与の支給総額(1,000円未満を切り捨て)に保険料率をかけて計算します。
健康保険・厚生年金・介護保険
保険料には上限があり
健康保険と介護保険は年度の累計額540万円
厚生年金保険料は150万円です。
ただし育児休業中は被保険者分、事業主負担分ともに免除となります。
② 雇用保険料の計算方法
賞与総額に保険料率をかけて計算します。
50銭以下は切り捨て 51銭以上は切り上げとなります。
③ 賞与に伴う所得税の計算方法
賞与の総額から社会保険料を控除した残額に
よって所得税が決定されます。
賞与の支給に伴う社会保険などの各種手続き
≪ 賞与を支給する ≫
この計算結果を賞与明細として、発行し
従業員さんへお渡しします。
≪ 国などに天引きした社会保険料などを納める作業 ≫
給与から天引きした社会保険料などは、
会社から各公的機関にお支払します。
また、賞与特別の社会保険の手続きとして
賞与の支払日から5日以内に賞与支払届出を提出する必要があります。
給与計算・社会保険アウトソーシングサービス
匠税理士事務所では、
≪p6≫社会保険労務士と連携して会社の賞与などの給与計算のアウトソーシングサービスや、
社会保険の手続きを代行するサービスを提供しております。
給与計算や社会保険加入手続き・人事労務のコンサルティング
サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
その他の会計アウトソーシングサービスや経営支援サービスはこちらから
◇バックナンバーはこちら→
※税理士水野智史の黒字経営館 ※女性税理士宮崎千春の起業情報館
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:27。9.8
ベンチャーのための制度融資や創業融資 (13/08/29)
これから事業をはじめるにあたっては、
まず資金を用意することが最も重要です。
ベンチャー時には、
事業を始めるために多くの資金を必要としたり
事業が安定し軌道にのるまでの間、
安定した経営を行うためにも資金を確保する必要があります。
そこで、
ベンチャー支援を専門とする匠税理士事務所では、
制度融資や創業融資といった事業の守りの要である資金についても
社長様と一緒になって問題に取り組んでおります。
ベンチャー企業が利用できる制度融資や創業融資について
ベンチャー企業が利用できる資金調達の制度として
制度融資や創業融資という制度がございます。

ベンチャー時は、
経営歴が何十年とある企業とは異なり
過去の業績がなく
金融機関との取引実績がないため
通常は、
金融機関からの資金調達が
難しいケースが多くなります。
しかし、
ほとんどのベンチャー企業は
スタート時に金融機関からの支援が
受けられなければ
事業を開始することが
できません。
国はベンチャー企業を資金面で支援し
起業率の向上を図る政策を進めております。
創業時には、
ベンチャー企業を支援するための制度融資や
創業融資といった資金調達の制度をうまく活用し、
資金面を充実させておくことも大切です。
制度融資や創業融資を受けるためには何が必要か

制度融資や創業融資を利用するためには、
事業計画書を作成し、
金融機関との面談を行う必要がございます。
制度融資や創業融資は、
過去の取引実績や業績がない
ベンチャーのための資金調達の制度となりますので
事業計画書による将来性や
面談による社長様個人の業界での経験といった
人間性により資金を貸すか否かの決定が行われます。
制度融資や創業融資でのポイントは、
①事業計画書の作成
②面接
この2つが最重要ポイントです。
通常の創業時には、
事業計画書を作成しなくとも事業はスタートできます。
しかし、お金を借りて、事業を始めるということは、
大きく初期投資を行ってから事業を開始することですので
返済が可能な商売ができるかどうかの計画(=事業計画)を行ってから
お金を動かす方が得策です。
(関連記事: 起業や創業融資での創業計画書の作成のポイント )
ベンチャーのための資金調達の制度を利用するにあたっては
① 創業をするために必要な資金総額
少なくとも1/3程度 理想は1/2程度
② 事業が軌道にのるまでの生活費
少なくとも3か月 理想は半年程度
これらの資金を準備してから創業されることをお勧め致します。
( 関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき? )
ベンチャーのための融資支援サービス
ベンチャーのための制度融資や創業融資をご利用のお客さまで
事業計画書の作成や、面談のサポートをご希望のお客さまは
ベンチャー支援の匠税理士事務所までご連絡ください。
起業時の資金調達や創業融資の支援はこちらから
会社の設立やその後の経理についてはこちらから
既に会社を経営されている方の経理・決算・税務アウトソーシングはこちらから
≪ベンチャーのための融資支援サービス≫
創業融資や制度融資をご支援するため各種金融機関との提携を行っております。
提携先などの一覧はこちらからご確認下さい。
制度融資や創業融資のご相談につきましては
お問い合わせフォームからご連絡いただければ幸いです。
その他の情報につきましては、
下記よりトップページにてご確認をお願いします。
最終更新日:平成26年1月19日
目黒や世田谷、品川での起業サポートやベンチャー支援 (13/08/27)
匠税理士事務所のホームページをご覧いただきまして
ありがとうございます。
私共は、地元の目黒や世田谷、品川での
起業サポートやベンチャー支援を専門としております。

匠税理士事務所の特色としましては、
30代の女性及男性の税理士が所属しており
お客様も30代から40代の方が中心となっております。
起業サポートやベンチャー支援において
目黒区や世田谷区、品川区の地域における
多くのお客様からご指示をいただいております。
起業サポートやベンチャー支援に関する私共のサービスや
他社との違いについて、簡単ではございますが
ご案内をさせていただきます。
起業サポート・ベンチャー支援の他社との違い
起業サポートやベンチャー支援では
会社を軌道に乗せるためのコンサルティングを大切にしております。
起業サポートやベンチャー支援が
他のコンサルティングと違う点は、
1. 得意先などの売り上げの確保といったマーケティングの視点
2. ベンチャー時の不安定な資金に対応する資金管理を支援する視点
3. 起業後、会社の損益がきちんと掴めるよう経理の仕組みをサポートする視点
これらの視点を総合的に勘定して
お客様の経営をご支援するという点です。
通常の会社経営に加え
これらの1 2 3 の安定性がない起業間もない時には
安定性を増すためのサービスが重要であると考えております。
私共の起業サポートやベンチャー支援は
これらの要素を取り入れ、コンサルティングを行ったり
お客さまが本業に集中できる環境を整備することが特徴です。
ベンチャー支援・起業支援サービスについて
起業サポートやベンチャー支援のサービス内容
起業サポートやベンチャー支援は、
売上の確保に専念できる環境を最重要課題として
各種アウトソーシングサービスをご用意しております。(給与計算もご相談ください。)
法人のお客様向けベンチャー支援
株式会社の設立とその後の経理や税務などをサポートするサービスです。
詳細はこちらからご確認下さい。
目黒区や世田谷区、品川区での創業融資など資金調達をサポートするサービスです。
詳細はこちらからご確認下さい。
既に会社を経営されている方への会計や決算のアウトソーシングサービスです。
個人のお客様向け起業サポート
個人事業で既に事業をされている方への経理や青色申告サポートサービスです。
個人事業の形態で起業される方に向けた起業支援サービス
≪対応地域について≫
世田谷や目黒、品川など東京都、神奈川県全域
≪起業サポートやベンチャー支援の実績について≫
世田谷産業振興公社 東京商工会議所 丸の内本部
品川、目黒での企業さまご依頼による経営支援セミナー
会社概要などにつきましてはこちらとなります。
起業サポートやベンチャー支援のサービスについての
お問い合わせはこちらとなります。
最終更新日:平成26年1月19日
法定労働時間と残業手当の計算方法≪p5≫ (13/08/23)
従業員さんを所定の労働時間を超えて労働させる場合には
残業手当を支給する必要があります。
この残業手当を計算するためには、どの時間からが割増し賃金の対象か
残業をさせるためにはどのような整備が必要がなどを知っておく必要があります。
≪労働基準法の定める労働時間≫
使用者は、
原則として、1日に8時間、1週間に40時間(休憩時間除く)
を超えて労働させてはいけません。
この労働時間を法定労働時間といいます。
労働基準法に定める法定労働時間は、最低基準の労働条件となります。
会社で定める就業規則や、労働協定、労働契約はこの基準以上のものでなければなりません。
週40時間労働制を実現するには、次のような方法があります。
1) 1日8時間、完全週休2日制とする(8時間×5日=40時間)方法
2) 各日の所定労働時間を短縮する方法
【例えば月~金7時間、土5時間(7時間×5日+5時間=40時間)】
3) 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制などにより、週平均40時間とする方法
この法定労働時間を超えて労働をする場合や、
法定休日の労働条件の取り扱いについては
あらかじめ時間外労働についての労使協定(36協定)を結び、
所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。
なお、法定時間外労働をさせる際には、割増賃金を支払う必要があります。
≪会社の定める労働時間≫
これに対して、会社が就業規則などで定める労働時間を所定労働時間といいます。
所定労働時間は、
例えば、「1日7時間、1週35時間」というように、
上記の法定労働時間以内に設定します。
所定労働時間を超えていても法定労働時間の「1日8時間」までの残業時間は
法定労働時間の枠内ですので、通常の賃金の支払いをすればよく
割増賃金の支払いは不要となります。
≪36協定≫
原則として、労働基準法で定められた法定労働時間を超えて働かせてはいけませんが、
あらかじめ労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、
時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には
法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働を行うことができます。
(ポイント:厚生労働省所定の様式を用いましょう)
※ただし時間外労働時間には限度があります。 時間外労働の限度に関する基準
≪割増賃金の割増率≫
36協定に基づいて法定労働時間外、法定休日、深夜に労働させた場合には
以下の割増賃金を支払う必要があります。
原則
時間外労働(法定8時間を超える労働) 25%以上
深夜労働(22:00~翌5:00) 25%以上
休日労働 35%以上
重複
時間外労働と深夜労働の重複 50%以上
休日労働と深夜労働の重複 60%以上
休日労働と時間外労働の重複 35%以上
※休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は
時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
割増賃金の計算方法
月給制
月額給与合計/一か月の平均所定労働時間数※ × 割増率
※年間労働日×一日の所定労働時間 /12
又は
(365-所定休日) ×一日の所定労働時間 /12
日給制
日額給与合計額/一日の所定労働時間 × 割増率
時給制
時間給 × 割増率
端数処理
30分未満は切り捨て 30分以上は一時間に切り上げること
一円未満の端数は50銭未満切り捨て 50銭以上切り上げ
≪p5≫割増残業が多くなると、従業員さんへの負担も強くなり、会社経営上もコストが膨らんでしまいます。
残業の管理体制をしっかりと行ったり、無駄な作業、不採算の事業などの見直しを
かけることも重要です。
給与計算や社会保険の加入手続き、人事労務のコンサルティングサービスは、
こちらからご確認下さい。
◇バックナンバーはこちら→
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:27.8.23
TOPページへ目黒区の匠税理士事務所
産前産後、介護休業、育児休業の各種規定や制度≪p4≫ (13/08/19)
労働基準法では、
母性の保護を目的とする規定があります。
この規定によって労働をさせてはならない期間や、
本人からの求めがあった場合には、
休暇を与えなければならないケースもあるため
従業員さんを採用する際には知っておくと便利です。
産前産後の休業に関する規定・制度と対応策
(規定)
・6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産をする予定の女性が休業を請求した場合
・産後の8週間(産後6週間からは医師が支障がないと認めた仕事はOK)
これらの期間は、
労働をさせてはいけないことになっています。
(ポイント)
これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう
※無給の場合には、健康保険から標準報酬月額の2/3に相当する出産手当金が支給されます。
妊産婦の労働時間の規定
(規定)
・妊娠中の女子
・産後一年を経過しない女性
から労働できない旨の請求があった場合には、
1日8時間1週間40時間を超えて労働せることはできません。
育児休業の規定と対応策
(規定)
原則として生後一年未満の(保育所の入所待ちでは1歳6か月未満)子供を育てる労働者
育児休業の申し出があった場合には休業させなければならない。
この休業の申し出は、
産前産後の休業とことなり、男性もできることになっています。
(ポイント)
これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう
介護休業の規定と対策
(規定)
2週間以上にわたって常時介護が必要となる一定の者を介護するとき
休業の申し出があった場合には最大93日間の休業をさせなければならない。
(ポイント)
これらの期間の賃金を無給とするか、有給とするかは就業規則に定めましょう。
育児や介護を行う者の残業時間の制約
・小学校就学前の子を養育する従業員
・家族を介護する従業員
で一定の要件を満たし、本人が請求をした場合には
①1月に24時間、一年150時間を超えて時間外労働
②深夜(22:00~翌5:00)
の労働が禁止となります。
その他にも
・従業員が3歳未満の子を育児している
・家族を介護している
これらの場合には勤務時間短縮の義務があります。
(関連記事:社会保険や労働保険の役割とその内容とは? )
≪p4≫ 給与計算や社会保険手続きのアウトソーシングや、
人事労務に関するコンサルティングサービスはこちらからご確認下さい。
→世田谷区や品川区、目黒区などでの給与計算や社会保険加入手続き
その他、経理のアウトソーシングや経営コンサルティングサービスは
こちらからご確認下さい。
◇バックナンバーはこちら→
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:27.9.9
起業の税理士をお探しなら匠税理士事務所 TOPページへ
給与計算や社会保険手続きに関する年間スケジュール≪p3≫ (13/08/15)
≪p3≫従業員さんを採用すると、
毎月の給与計算を行う必要があります。
その他にも年間を通して
行わなければならない業務がございます。
そこで今回は給与計算について
簡単な一年間の流れをイメージして、各論を確認しましょう。
ここでは4月に社員さんを採用したものとして流れを確認していきます。
具体例を踏まえた給与や給料計算についての年間の流れ
≪4月≫
① 新入社員さんの社会保険の加入や標準報酬月額の登録手続きを行います。
② 同じように雇用保険の加入手続きを行います。
③ 入社に関する必要書類を整備します。
※ 4月は、昇給や人事異動が多い月ですので合わせて確認しましょう。
※ 雇用保険率の変更や、4/1現在で64歳の人からの雇用保険天引きのSTOPを行います。
≪5月≫
労働保険の年度更新準備を行います。
※労働保険の仕組み
(基礎)
労働保険は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算します。
労働保険は、概算で保険料を納付して
保険年度末に賃金総額が確定したあとに確定と概算の差額を精算する方法になっています。
つまり、前年度の概算と確定の保険料誤差をを精算するための申告・納付と
新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
(期限)
年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
≪6月≫
給与から天引きする住民税の改定を行います。
※住民税の仕組み
住民税は、1月1日から12月31日までの期間の給与から税金を計算します。
この期間の税金を翌年の6月から5月までの12か月にわたって均等額を給与から天引きします。
≪7月≫
7月1日現在で雇用している従業員の健康保険と厚生年金の決定を行います。
(給与)
7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を
「算定基礎届」により届出します。
決定し直された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)は固定され、
納めていただく保険料額の計算の基礎となります。
(期限)
毎年7月10日まで。
※給与の昇給や降給が行われた場合には昇給などが行われた月以後4か月目に
健康保険や厚生年金の随時改定を行う必要があります。
(賞与)
また、夏は賞与の時期となります。
賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を
納付することになっています。
(期限)
事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
(関連記事:賞与の給与計算方法や社会保険などの手続き)
≪9月≫
厚生年金の料率が変わります。
多くの会社では7月に行った改定により変更された新しい標準報酬月額で
10月からの給与計算を行います。
≪12月≫
年末調整を行います。
一年間の給与から生命保険などを考慮して、
年間の税金を計算します。
毎月概算で給与から天引きしている税金との差額を
従業員さんへお返ししたり、徴収したりします。
この一年の給与の計算結果を従業員さんへお渡しします。
これを源泉徴収票と言います。
賞与がある時には健康保険・厚生年金保険の手続きが必要で
支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
≪1月≫
給与支払報告書という書類を提出して住民税の申告を行います。
従業員さんの一年分の給与に関する書類を市区町村役場へ提出して
住民税の申告を行います。
≪3月≫
健康保険や介護保険の料率変更があります。
給与計算や社会保険手続きなどを担当する際のポイント
上記の給与計算や社会保険手続きの年間スケジュールに記載した
7月の算定基礎届 と 12月の年末調整業務 が
給与計算や社会保険の手続きを担当する方にとって、
繁忙期になります。
忙しいときは、
ミスが生じやすいものですので、
出来る限り前倒しで業務を進めるのがポイントです。
そのためにも一年間のおおまかな流れを抑えることで
手続きの漏れ防止や、繁忙期への準備を進めるすることが効果的です。
給与計算や社会保険手続きアウトソーシングサービス
匠税理士事務所では、
各種専門家と連携した給与計算や社会保険手続きなどの
アウトソーシングサービスをご提供しております。
給与計算や社会保険のサービス内容につきましては、こちらからご確認下さい。
→ 品川区や目黒区、世田谷区など東京での給与計算や社会保険の加入手続き
会計や経営支援サービスはこちらからご確認下さい。
◇バックナンバーはこちら→
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:27.9.10
目黒区で税理士をお探しなら匠税理士事務所 TOPページへ
社会保険や労働保険の役割とその内容とは?≪p2≫ (13/08/06)
≪p2≫そもそも、社会保険とは、
何のために支払うもので、
どのようなものがあるのでしょうか。
社会保険(広義)には、
健康保険(国民健康保険)
介護保険
厚生年金(国民年金)
労災保険
雇用保険
があります。
健康保険、労災保険、厚生年金や雇用保険の概要について
このうち、健康保険や労災保険は、
怪我や病気のときのための保険であり、
厚生年金は、老後や障害などの時の
生活保障のための保険となります。
雇用保険は、
失業などのときのための保険となります。
また、介護保険は、
介護を必要とするときのための保険となります。
各種社会保険についての加入手続きや窓口について
これらの保険の加入などの手続きについては、
各保険によって手続きを行う窓口が異なります。
健康保険※や厚生年金は、
年金事務所
国民健康保険や国民年金、介護保険は、
各市区町村役場
労災保険は、
労働基準監督署
雇用保険は、
ハローワークにて手続きを行います。
(※組合管掌健康保険除く)
各種社会保険の給付と内容について
それでは具体的に、
一つ一つの社会保険について確認をしていきましょう。
≪健康保険≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 病気や怪我により病院へかかる際の医療費の負担
→健康保険証を提示すれば個人負担は医療費の3割等になる
② その他労働者やその被扶養者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産への保険給付
→高額療養費、入院食事療養費、傷病手当金、出産一時金、出産手当金、埋葬料
≪厚生年金≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 老齢年金
→老後の生活資金として支給
② 障害年金
→被保険者が病気やけがによって一定基準の障害者になったときに支給
③ 遺族年金
→被保険者が死亡したときに、その人に生計を維持されていた家族に支給
(関連記事:健康保険や厚生年金の計算方法と手続き)
≪労災保険≫
仕事中や通勤中の事故などによる労働者の負傷、疾病、障害、死亡についての保険です。
雇用主が全額負担をします。
① 療養(補償)給付
病気やけがの治療への給付
② 休業(補償)給付
病気やけがにより休業したときに受けられる給付
③ 障害(補償)給付
障害が残った時に受けられる給付
④ 遺族(補償)給付
労働者が死亡した場合に遺族に支払われる給付
≪雇用保険≫
本人と会社とで保険料を折半して支払います。
① 求職者給付
失業期間中の生活保障として支給されます
② 雇用継続給付
育児休業者や定年後の再雇用、介護休業者を援助する目的で支給されます
≪介護保険≫
要介護者への介護サービスを受けるために支給されます
社会保険手続き代行や給与計算アウトソーシングについて
匠税理士事務所では、
≪p2≫ 給与計算や社会保険について、
社会保険労務士と連携して代行やコンサルティングサービスを
提供しております。
サービス内容につきましては、
下記よりご確認下さい。
→ 世田谷区や目黒区、品川区など東京都での給与計算や社会保険の加入手続き
経理のアウトソーシングや経営コンサルティングサービスはこちらから
◇バックナンバーはこちら→
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:27.9.9
東京都の匠税理士事務所 トップページへ
社長の営業能力が起業後は重要です。 (13/08/06)
起業後に重要なことは、得意先や販路を築き、
売上を安定化し毎月の固定的な経費を賄うこと。
つまり、【 生き残ること 】です。
そのため起業後の社長様の最重要課題は営業です。
販売営業・マーケティングは社長の重要な仕事
商品を売るためには、当然営業ですが、
営業の人材を採用しその担当者に任せるのでなく
【 社長様自らが 】営業をすべきです。
人によって営業に対する考えは異なると思います。
それでも営業についてもう一度しっかりと
勉強し営業活動を継続することが大切です。

社長の営業力が起業後に重要な理由
何故、営業が重要なのでしょうか。
多くの会社の場合、売りたい商品と、
お客さまに買って頂ける商品は乖離します。
また商品の値段や仕様についても市場ニーズと
会社の理想では差異が生じます。
当然のことですが起業時には、
こんな会社にしたいという想いが強く
これが見えなくなることがあります。
このとき社長様が営業活動を行っていると
このお客様・市場ニーズを直接聞くチャンスが増え
自社商品の開発に取り入れる事が可能となります。
その結果として、
なども見えてきて、
【販売や価格などの戦略】も見えてきます。

また、社長が現場のお客様の声を聞くことで、
どんな販売方法・販売戦略が最適かが分かるようになります。
会社員の営業と自分の会社での営業は違う
会社員の時の商品や営業、社内の仕組みと
起業後の価格や、会社の信頼、商品への信頼は全く異なります。
これに気が付くためにも社長様自ら営業を行うことは非常に重要です。
失敗や苦い思いをすることもありますが
自ら率先して、得意先をていねいに回り、
お客様の声を集め魅力的な商品を作ることをお勧め致します。
起業家を支援する匠税理士事務所のサービス
匠税理士事務所では、世田谷区・目黒区・品川区
大田区などで創業塾の講師を担当しました。
これらの創業塾の経験を踏まえまして、
少しでも起業される方のお役にたてるように
起業・開業・創業支援サービスをご用意致しました。
サービスの内容としましては、
起業するに際し資金調達や起業後の経理立ち上げ
決算書作成や税務署など手続きはもちろんのこと
会社の設立などもサポートしています。
サービスの目的としましては、
起業後多くの企業が数年先にはなくなる
厳しい経済環境下で経営者の方にできる限り、
本業に集中して頂きお役にたてる事務所でありたいという考えが原点になっています。

匠税理士事務所は、2008年の創業以来、
起業と黒字戦略に専門特化しております。その中で私たちがお客様に役立てるサービスを
追及しお客様の会社存続と発展に役立ちことを
使命として参りました。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

随時頂くご要望を踏まえまして、起業・開業・創業支援サービスの内容をよりお客様に沿ったものにしていきたいと考えております。
起業されるに際しまして、ご相談などがございましたらお気軽にご連絡ください。
(関連記事:販売戦略は重要!自社販売か、代理店等の委託販売か? )
社長さまが自ら先頭にたって営業できるかどうかで社内の士気も異なります。
(関連記事:経営者が現場にいる会社と現場と乖離し距離ある会社 )
(関連記事:多角化経営・多角化企業それとも集中化戦略? )
(関連記事:売上総利益・粗利を決める売価決定の重要性 )
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
→ 世田谷区や目黒区、品川区の会社設立を専門とする匠税理士事務所
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
税理士 目黒区、世田谷区や品川区の会計事務所匠税理士事務所TOPへ ...TOPページへ
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
給与計算と社会保険料の概要や全体的な仕組み≪p1≫ (13/08/02)
従業員さんを採用した場合や、
アルバイトさんを採用した場合には
給与計算を行う必要がございます。
そもそも給与計算とは、
どんなことを行う必要があり、
社会保険に加入したことにより、
従業員さんや会社にどんなメリットがあるのでしょうか。
給与計算をするための仕組みや必要な準備とは
~ 従業員さんへお支払する金額を決定する給与計算の仕組み ~
給与計算とは、
大まかにいえば
その従業員さんへの給与の総額(基本給や諸手当)を計算し、
給与の総額から
厚生年金保険料や雇用保険料、健康保険料などの社会保険料、
所得税、住民税などの各種税金を差し引いて
従業員さんにお支払する金額を計算することを言います。
≪ 給与計算のために必要な事前準備 ≫
給与計算を始めるためには下記の書類を準備しましょう
① 就業規則、給与規程
② 給与台帳
③ タイムカード
④ 健康保険(介護保険)・厚生年金標準報酬月額表
⑤ 給与所得者の扶養控除申告書
⑥ 住民税の特別徴収税額通知書
⑦ 通勤手当支給申請書
⑧ その他の手当や控除に関する書類
≪ 給与総額を決定する ≫
給与の総額を決定するためには
① 基本給 アルバイトさんの場合には時給
② 諸手当 交通費や役職手当 <固定項目>
③ 残業手当<変動項目>
これらを決定することからスタートします。
具体的な流れとしては
a)人事情報の収集
入社、退職、転勤、結婚、出産などの給与に関する人事情報を収集します。
b)出勤簿やタイムカードの回収と集計
給与の締日以後にタイムカードなどを回収し残業時間や欠勤状況などを集計します。
c)給与計算
就業規則や給与規定から従業員各人の給与総支給額を計算します。
≪ 給与から引かれる税金や保険料を計算する ≫
総額を計算したら、その総額についてかかる
① 厚生年金や健康保険、介護保険料<固定項目>
② 雇用保険料<変動項目>
③ 所得税 <変動項目>
④ 住民税 <固定項目>
これらを計算します。
(関連記事: 給与計算や給料計算の年間スケジュール)
社会保険料の計算方法など概要や全体的な仕組みについて
① 厚生年金や健康保険料、介護保険料の計算方法や概要
社会保険は、
各人の給与から標準報酬月額を決定して保険料を計算します。
この標準報酬月額は、
A) 入社をして被保険者となったとき (資格取得決定)
B) 毎年1回、7月1日現在で見直して再決定 (定時決定)
C) 固定給に一定の変動があったとき改定 (随時改定)
これらときに決定され、
原則として、翌年の8月31日まで使用されます。
※ただし介護保険は40歳以上65歳未満の人が対象です。
この厚生年金や健康保険料、介護保険料は
毎月会社が支給する給与から前月分が差し引かれます。
【入社時】
資格を取得した日が初日であっても末日であっても
一か月分の社会保険料を給与から引きます
【退職時】
資格を喪失した日が、初日であっても末日であっても
その月の保険料は徴収されません。
ただし例外として退職日が末日の場合には、
資格の喪失は翌月1日となります。
当月分を当月に支給している会社では
退職月の末日までの社会保険料の徴収漏れに気を付けましょう。
(関連記事:健康保険や厚生年金など社会保険の計算方法と手続き)
② 雇用保険料
給与を支払う都度、給与総額に保険料率をかけて計算します。
50銭以下は切り捨て 51銭以上は切り上げとなります。
③ 所得税
給与の総額から所得税が非課税となる項目と、
社会保険料を控除した残額によって所得税が決定されます。
なお、給与から天引きする家賃や生命保険料がある場合には
賃金控除に関する協定が必要となります。
≪ 給与を支給する ≫
この計算結果を給与明細として、発行し
従業員さんへお渡しします。
≪ 国などに天引きした社会保険料などを納める作業 ≫
給与から天引きした社会保険料などは、
会社から各公的機関にお支払します。
匠税理士事務所の給与計算や社会保険代行サービス
匠税理士事務所では、
提携の社会保険労務士と共に、
≪p1≫会社の給与計算や社会保険手続きの
代行・アウトソーシングサービスを提供しております。
サービスの詳細は、こちらからご確認下さい。
目黒区や世田谷区、品川区等の給与計算や社会保険代行やアウトソーシング
その他の会社経営者向けの
会計アウトソーシングや経営支援サービスは
こちらからご確認下さい。
◇バックナンバーはこちら→
匠税理士事務所の事務所概要や料金などは、
下記よりTOPページにてご覧いただけます。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:26.2.14
目標の利益から必要売上を決める(黒字経営) (13/07/29)
事業を開始し、事業から経営に発展するときにはいくつかのステップがあります。
第一のステップは、商売が成立するかどうかです。
つまり、毎月安定した売上が確保できるかどうかが最初のハードルとなります。
そのため起業間もないときには
マーケティングの知識や、人脈、販路などどのようにして売るかどうかが最大のテーマとなります。
売上がある程度確保できるようになったときに次のステップが見え始めます

それは、いかに利益を出すかということです。
「 いくら利益が必要か 」
その考えをもち、この商品を売ればいくらの利益が出るのか
即座に計算できるほどの商売の数的感覚を磨きあげる時期です。
いくら利益が必要か、この考えが何故重要なのでしょうか。
会社を大きくするためには、当然、先行投資が必要です。
先行投資は、新しい商品や市場への挑戦人材やモノなどの確保などがあります。
企業は、安定を考えた時点から衰退してしまいます。
常に失敗はつきものであっても先行投資を行って、
新しいことに挑むことが必要です。
そのうちの、何点かが成功するときもあれば全てが失敗に終わることもありますが、
その繰り返しで、市場から評価される商品やサービスが
ようやく見つかり、会社に利益をもたらしてくれます。
常に新しいことに挑戦を続けてこそ生き残りが可能となります。
新しいことへの挑戦のために利益は必要
いくらの利益が必要か
これが頭に入っている経営者とは次にやるべきことが見え始めており
継続することで、先読み経営が可能となる状態です。
自分の業界の5年後10年後のリスクを洗い出し
どんどんと新しいことに挑戦しリスクを回避していくことを意識し始めると、経営の段階に入ります。
商売を考える、利益を考える、将来を考えるこれが一度できるようになると、
将来を考える から 利益を考える ために 商売を考える や、
将来を考える から 商売を見つめなおす ことで 利益を改善する
など利益を上げるための流れを様々な視点から組み合わせて攻めの戦略を広げることができます。
何事も経験したことは、財産となり経験値の積み重ねにより色々な応用ができ幅がでるようになります。
商売 → 利益 → 将来への投資 このルートを一通り経験することで
攻めの幅が広がります。
現状のことで、手が一杯になってしまった時や先々の攻め方をもう一度考えるときに使える考え方です。
そのため、
「 毎月、常に、黒字経営であること。 」これを意識することはとても重要です。
(関連記事:経営者の仕事とは何か、社長に求められるものとは)
(関連記事:黒字化のための経営分析や財務などの指標を抑えた経営戦略)
黒字経営を支援するための匠税理士事務所のサービス紹介
匠税理士事務所では、関与させて頂いた会社様の黒字率100%を目指して経営コンサルティングなど経営支援に力を入れております。会社の経営を支援するサービスはこちらからご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
匠税理士事務所の事務所紹介はこちら
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
目黒区の匠税理士事務所なら匠税理士事務所...TOPページへ
◇経営お役立ち情報
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
更新日時:26.12.6
開業後の店舗経営に有効な看板広告等の販売促進や営業促進 (13/07/24)

K26 飲食店やネイルサロン、美容院、アパレルなど
お客さまに来店していただく形態で、
起業をされる際に
知っておくと便利な販売促進や営業促進など広告方法について
解説をしていきたいと思います。
店舗経営では、
お客さまのいつもの通勤通路にたまたまあったから
よく通る道に気になる看板の店舗があった
このような通りがかりをきっかけとして
来店されるお客さまが非常に多くあります。
クーポンやホームページ、紹介などでお店を探していらっしゃるお客様以外に
この通りががりのお客さまをいかに集客できるかということも非常に重要です。
つまり、お客様が通りがかって思わず来店したくなるような看板や店舗の外観は
とても強力な宣伝効果があります。
起業をするときには、販売促進や営業促進方法が重要
このことを起業時に把握をしていないと
余った予算で安く看板を作ってしまったり、人が入りにくい雰囲気の内装を行ってしまいます。
よく、何となく入りにくいお店、何のお店か分からない
しばらくしたら他のお店に変わっていたということがご自身の近所で起きていないでしょうか。
看板や店舗は最も有効な販売促進や営業促進など
広告効果があるということを念頭に置いて
集客効果を取り入れた看板や内装を行わなければなりません。
日頃、ご自身がよく行くお店について入店するきっかけとなったことや、
何となく毎回行ってしまう喫茶店や飲食店、美容院などが
行列のできている店に何回も足を運んでみる
こんなことを考えながら、お店をもう一度見てみると色々な発見ができます。
看板を設置する際のポイント(開業後の販売促進や営業促進広告)
通りかかったお客さまが一瞬で何のお店か分かることが一番重要です。
遠く離れてみたときに、
実際に設置をしてみて離れた場所から、近い場所から確認をしてきちんと分かるか?
お店に立ち寄ってみようかと思えるかチェックすることです。
ぜひ、ご友人やご家族に沢山のご意見をうかがってください。
(印象が強いと販売促進や営業促進広告効果も高いと言えます。)
店舗経営に有効な印象に残る看板広告とは
店舗経営において集客に効果を発揮する有効な看板広告かどうかは、
つまるところ印象に残るかどうかがポイントです。
看板広告が、印象に残るかどうかは
・ 写真や看板のサイズが大きいかどうか
・ デザインや色合いにインパクトがあるか
・ 設置してある場所が、人の目につく場所、車で通った時に目立つ場所か
などによって決まります。
お店を出店される地域の周辺の看板の色や競合の看板設置場所、色、状況によってこれらは変化します。
ご自身の出店する地域によってどんな看板が良いのか
よくよく吟味してしっかりとした看板を作成されることをお勧めします。
それだけ、看板は販売促進や営業促進広告として有効です。
色々な看板を試してみてお客様の来店率が高い看板を設置しましょう。
起業時は、色々な試行錯誤で何が当たるか挑戦することが大切です。
開業支援に強い自由が丘の匠税理士事務所からのご挨拶
匠税理士事務所は、起業と黒字戦略を専門とする税理士事務所です。
目黒区の自由が丘駅より徒歩2分です。
弊所では、会社の経営者の方を支援する法人の会計・決算・確定申告サービスをご用意しております。
会社経営者の方の多くは、人の管理や資金繰り、新商品開発や他社の動向など様々なことに神経を使われています。
その上、会計や決算、確定申告などといった本業以外のこれらの作業までかかえてしまうと、上記のような重要な事項に手が届かなかくなってしまいます。このような状況が続いてしまうと、本来伸ばせるべき売上を伸ばせなかったりして、機会損失にもつながりかねません。
そこで、会社の経理といった会計処理はもちろんのこと、決算書作成から確定申告書の作成まですべて担当させて頂くサービスをご用意しております。
会計処理や税務申告以外にもご要望がございましたら、給与計算や社会保険手続き、登記などにつきましても提携専門家との連携でしっかりとサポートさせて頂きます。
対応エリアとしましては、世田谷区・目黒区・品川区などのご近所の会社様はもちろん、これらの地域以外の会社様につきましても東京都の全域に対応しておりますので、ご興味のある方は、お気軽にご連絡ください。
◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
< その他の起業支援サービス >
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
税理士 目黒区、世田谷区や品川区の会計事務所匠税理士事務所TOPへ ...TOPページへ
目黒区祐天寺すぐの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (13/07/02)
ご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所は、祐天寺すぐの会計事務所です。
弊所は、世界4大会計事務所出身の税理士を中心に
【上場企業にも対応できる高度税務】と
【経営セミナー講師を務めるコンサルティング】を軸とした
女性税理士、税理士科目合格等10名の事務所です。また、書籍を執筆する社会保険労務士が給与計算や助成金、人事労務コンサルティングを担当し、
法律問題は契約書作成や訴訟対応まで企業弁護士がチームで担当します。
個ではなく、【 総合力 】でサポートすることで、【 起業支援 】・【 経営支援 】に評判があり、
あらゆるご相談に対応できる体制を用意してます。

これらの専門家による【 総合力 】を発揮し、
【お客様の会社に利益とお金を残すこと】を使命にチームで業務に取り組んでいます。また、祐天寺など目黒区の地域性もあり、
ITやデザイン関連のお客様が多いのも特徴で、
30~40代の起業家様が多くいらっしゃいます。
弊所の所属税理士や税務会計スタッフ紹介、
サービス概要は、こちらで確認をお願い致します。
【 →目黒区の税理士は匠税理士事務所 】

祐天寺の会社設立や創業融資など起業支援
これまで会社設立や創業融資では、
目黒区でもトップレベルの実績を有しております。
特に2008年に事務所を開業以来、
創業融資の【 成功率は9割 】を超えております。これまでのノウハウと実績を活かし、
祐天寺近くで創業されたいお客様に向け、
会社設立や日本政策金融公庫の創業融資、
会社設立後の黒字経営のご支援を行っています。
祐天寺担当の税理士・事務所概要はこちら↓
【 → 匠税理士事務所の概要 】

会社設立や創業融資、経営支援サービスの詳細は
こちらからご確認をお願い致します。

また、祐天寺で起業されるお客さまに向けて
資金面の問題につきましても祐天寺エリアに対応の金融機関や政策金融公庫と連携して、
創業融資などの起業支援も行っております。

祐天寺すぐ目黒が地元の匠税理士事務所
祐天寺で税理士をお探しのお客さまで
経理や会計、確定申告などの業務内容や
料金を確認されたいお客様は、
上記TOPページ又は確定申告や税務会計サービスへのリンクをご確認いただければ幸いです。
弊所は、品質で【 目黒NO1の会計事務所 】を目指しています。
匠税理士事務所の法人経営者向けサービスは、
こちらからご確認をお願い致します。
【 →法人のお客様向けサービス 】

祐天寺での法人化や確定申告代行
祐天寺で既に事業をされているお客様や、
これから祐天寺で個人事業を会社にしたい
お客様向けのサービスとしましては、
・個人事業主の方への会計代行・確定申告代行
・個人事業を株式会社へ変更する法人化
・土地や建物の確定申告や会計経理の代行
などがございます。
【 →個人事業のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
祐天寺で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】
目黒区祐天寺での経営・創業支援
祐天寺のお客様で利益や会社にお金を残すための
経営支援のコンサルティングをご要望のお客様には
東京商工会議所目黒支部などで経営セミナー講師を
務めるスタッフが担当させて頂きます。
また、会社設立後の経理会計や決算・節税対策など
創業支援も充実しております。
創業支援の詳細はこちらから確認願います。
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
祐天寺など目黒近くの会計事務所の求人や採用情報
当会計事務所ではアルバイトスタッフ
パートスタッフ・正社員を募集しております。
祐天寺など目黒近くの会計事務所での
勤務を検討中の方は下記より詳細をご確認の上、
ご連絡を頂けましたら幸いです。
働きやすさNo1の会計事務所を目指しており、
ここ5年間の退職者ゼロです。
最後までお読み頂きありがとうございました。
これからも祐天寺(ゆうてんじ)など目黒の会社様や
会社設立される起業家の方にご支持頂ける税理士であるよう努めます。
ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問合せ下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#祐天寺税理士
#祐天寺会社設立
北千束や南千束近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (13/05/13)
ご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所所は、北千束や南千束近くで
【経営支援・創業支援】に力をいれる事務所です。 世界4大会計事務所出身の税理士を中心に経理・会計・確定申告・決算などの代行から
経営コンサルティングや創業融資の対応など
【経営に必要な全てがそろう事務所】を事務所の指針としております。
匠税理士事務所の税理士や
業務内容・料金はこちらでご確認下さい。
【→ 起業・黒字戦略の匠税理士事務所】

北千束・南千束の税理士による起業支援
匠税理士事務所の起業支援や経営支援は、
北千束や南千束で給与計算や社会保険手続き、
契約書作成やレビュー、建設業許可申請など
一般の会計事務所の業務以外にも 社労士・弁護士・行政書士と連携し、 幅広く対応することが可能です。
北千束や南千束で起業支援を担当する税理士や、
提携先の専門家はこちらでご確認下さい。
【→ 匠税理士事務所の概要 】

北千束や南千束の会社設立など創業支援
独立開業や創業支援の一環として、
会社設立の代行も承っております。
会社のフレーム設計・登記対応から
登記後の経理・決算などの税務申告、
黒字化のための創業支援も対応しております。
経営セミナーで講師を担当する税理士が在籍し 関与先の黒字割合は9割を超えています。匠税理士事務所の北千束や南千束の方向け
会社設立はこちらでご確認下さい。
北千束や南千束で創業融資による独立開業支援
また、会社設立と同時に創業融資による
資金調達のご要望も対応しております。
日本政策金融公庫や北千束や南千束に
対応の城南信用金庫など金融機関と
連携して創業融資をご活用頂けます。
またご要望の方には、大田区による
制度融資もご利用頂くことが可能です。
当会計事務所の北千束や南千束向け
創業融資による創業支援はこちらから
【→創業融資や資金調達】

北千束や南千束の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 →東京都の創業・起業支援は匠税理士】
(創業支援は、北千束や南千束なども対応)
確定申告や決算、経理会計、法人化も対応
北千束や南千束などで自宅売却された確定申告や
個人事業から会社にするための法人化などの
ご相談も承っております。
北千束や南千束近くでの申告について
お気軽にご相談下さい。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
北千束や南千束の方向け確定申告や経理代行
法人化など個人サービスはこちらで確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
北千束・南千束で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

北千束・南千束の法人化・会社設立関連情報
北千束・南千束の近くの税理士・会計事務所による
個人事業主から株式会社など会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
北千束・南千束の税理士事務所・会計事務所の採用求人
北千束・南千束近く税理士・会計事務所勤務を
検討中なら匠税理士事務所の求人採用をご覧下さい。
正社員スタッフとパートアルバイトスタッフを
募集致しております。
【 → 大井町線の税理士・会計事務所の採用求人】
皆様からのご応募をお待ちしております。
(北千束・きたせんぞく)や(南千束・みなみせんぞく)
で会社設立などの起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#北千束税理士事務所
#南千束法人化
株式会社や合同会社で会社を作る|会社設立の情報館 (13/04/08)
匠税理士事務所は、起業と黒字戦略に専門特化した会計事務所です。
黒字戦略のための利益戦略会議やキャッシュストック経営など独自のサービスでお客様の利益とお金を守ることを使命としている税理士事務所です。
こちらは、起業前の経営知識や、株式会社や合同会社などの設立、独立・開業についてのノウハウをまとめた記事のバックナンバーとなります。
起業と株式会社や合同会社の会社設立ノウハウのTOPICS 目次
これまでのノウハウを活用した起業の情報をまとめております。お役に立てば幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
→ 登記など自分で会社を作るか、それとも税理士の会社設立かを検討されている方に向けた情報...
→ なぜ青色申告がお勧めなのかについてまとめてみました。...
→ 【 どのような税金をいつ、いくらほど支払う? 】についてまとめました。...
→ どんな届出書を税務署などの官公庁へ最低限出しておく必要があるのでしょうか...
→ 設立後の会社を大きく育て有利な経営を行うために、知っておきたい...
→ 会社を設立するに際して、どのような専門家がいてその得意とする分野は何かを記載します。...
→ どのような会社を作りたいのか、その上で、資本金、役員と決めていきましょう。...
→ 合同会社や株式会社など会社にするのか、迷うこともあると思います。...
→ 30代・40代・50代で起業される方は、比較的早く事業が軌道にのるケースが多く感じます。...
→ 他人の権利を侵害しないため、自分の商標を守るためにも商標登録することをおすすめいたします。...
匠税理士事務所では、個人事業主の方が法人化する場合の会社設立や、サラリーマンを辞めて起業される方の会社設立を支援しております。
匠税理士事務所の会社設立・法人設立支援サービスでは、
資本金などに関する税務上のポイントのご説明や、
会社を設立した後の税務署・都税事務所などへの官公庁への税務上の届出はもちろんですが、
会社設立に伴う飲食店の許認可申請や、建築業の許認可申請、
社会保険加入に伴う諸手続きにつきましても
行政書士や社会保険労務士などの各種専門家と連携して万全の体制で臨みます。
会社を設立した後で、お客様からのご要望がある場合には、
事業計画書の作成サポートや提携金融機関のご紹介などの創業融資のサポートも行っております。
世田谷区・目黒区・品川区・大田区などの東京都で会社設立・法人設立をご検討の方は、
匠税理士事務所にお任せください!
◇TOPページはこちら→世田谷や目黒、品川の税理士なら匠税理士事務所
世田谷・目黒・品川など東京都の全域に対応しております。
東中延や西中延近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (13/03/14)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は東中延・西中延など品川区を中心に、
【創業支援・経営サポート】に実績ある事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に、黒字化戦略・キッシュストック経営の独自サービスを提供し
【 関与先の黒字率9割超 】が特徴です。匠税理士事務所の税理士やサービスは、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

東中延・西中延で税理士の会社設立や起業支援
匠税理士事務所は、東中延・西中延で
【 黒字化 と お金がたまる仕組み作り を 】活かして創業支援や起業支援を行っております。
株式会社や合同会社などの会社設立代行や
会社設立後の会計税務などの代行、
経営全般のコンサルティングなども対応してます。
東中延や西中延担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

東中延や西中延など品川区で起業される方は、
こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。
東中延や西中延で創業融資による創業支援
東中延・西中延エリアで会社設立される
起業家のほとんどが創業融資を利用されます。
開業資金を全て自己資金で用意する方は、
ほとんどおらず、融資・借入を利用する方が多く、
弊所でも創業融資を推奨しています。
借り入れと聞くと抵抗がある方も
いらっしゃるかもしれませんが、
必要なければ使わなければよいわけですし、
金利は2%程で、経営に影響がない金額です。
逆に起業してすぐに売上が立たないと、
精神的にきついですが、資金調達しておくと、
ゆとりをもって経営が行えます。
匠税理士事務所は、起業支援に多くの実績があり、
その中でも東中延や西中延など品川区では、
日本政策金融公庫の五反田支店様や、
城南信用金庫様と提携することで
【 成功率9割超の実績 】を有しております。匠税理士事務所の東中延や西中延エリア向け
創業融資による創業支援はこちらから

東中延・西中延の経理会計・決算確定申告・法人化
匠税理士事務所では、東中延や西中延で
経理や会計のアウトソーシング、決算確定申告の代行を
承っております。
また、会計事務所業務以外にも、
契約書作成・給与計算・社会保険手続きなど
事業経営に必要な全てご用意しております。東中延や西中延など品川エリアで、
税務会計や給与計算、社会保険などに対応する
税理士事務所をお探しの方は気軽に相談下さい。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
東中延や西中延の方向け確定申告や経理代行
法人化など個人サービスはこちらで確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
東中延や西中延で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
東中延・西中延で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

(東中延・ひがしなかのぶ)・(西中延・にしなかのぶ)
品川区のお客様に向けた匠税理士事務所の紹介を
最後までご覧頂きありがとうございました。
品川区の会計事務所の採用求人はこちらから
東中延や西中延で会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所の案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#中延税理士
#東中延法人化
創業融資でやっていけないこと・注意点や服装のNG集 (13/03/06)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
匠税理士事務所HPに訪問ありがとうございます。
日本政策金融公庫の創業融資で、やっていけない事
【 注意点や服装のNG集 】をまとめました。
融資は基本、一回きりの真剣勝負。
泣きの一回は、ありません。失敗はできません。一度結果が出ると再申請までに、
【 半年以上 】は、待たないといけません。
だから、失敗がないように服装など注意点を
しっかりと把握することが重要です。
創業融資で気を付けるべきNG・失敗集
【 NG・失敗集 】
金融機関の担当者の方に面談当日の服装や、
身なり、格好や髪形などから、
本当にこれからこの人はしっかり事業をしていけるのだろうかと不安を感じさせてしまう。
→ 「人を外見で判断してはいけない。」
と言われますが、金融機関の担当者の方は、
創業融資するのに計画書などの書類審査に加え
この人に貸して大丈夫かの人間性も審査します。
その一度の面談で、最初の外見から不安を抱かせてしまうと、その後の面談でも悪影響が出ます。
当日は就職の面接などのように、しっかりした服装・身だしなみで臨み、相手から貴重な時間を頂いている意識を持ち、礼儀をもって臨みましょう。
そうなるとスーツや綺麗な恰好がベストです。
【 NG・失敗集 2 】
事業計画書と審査面談回答に整合性がなく
どちらが本当なのか分からない。
→面談はあくまで申請書類に書いてあることを、
実際面談で会って確かめるもの。
ここで書類と面談に整合性がないということは
論外ということになります。綺麗な日本語でなくても良いので、
自分の言葉で、事業計画の中身を伝えましょう。
相手に誠意でビジョンを伝えることが第一です。
【 NG・失敗集 3 】
「幾らまでなら借りれますか?」という発言。
→ 創業融資は、先に事業計画などで、必要資金を決めた上で申し込みをするものです。
「この金額が必要なため、借りられませんか?」
という流れになるべきです。
しかし、時折面談で「 いくら借りられますか? 」とついつい口走る方がいらっしゃいます。
これはいけません。
これでは金融機関の方から、
「 この事業計画は本当なのだろうか? 何か他に使う気でないのだろうか? 」
という疑いにを持たせてしまいます。
そのようなことがないように事業計画の時点で、
どうしても必要な資金は幾らなのか、
それをいつまでに用意しなければならないのか、
どのようにして返していくのかについて
しっかりと理解しておくようにしましょう。

【 NG・失敗集4 】
「担当者の質問に対して感情的になってしまう」
融資担当者も仕事です。
初めてあった人間にお金を貸すリスク負担を
するため、できる限りの角度から質問します。
この質問についつい感情的になってしまうと、
・この人は仕事でも感情的になるタイプで、
本当にうまくやっていけるのか。
・質問が図星だったのか。
などあまりいい結果にはつながりません。
常に冷静適切な受け答えをするようにしましょう。
面接ではこれら最低4項目は抑えておくことで、 致命的なミスを防ぐことができます。
創業融資は一発勝負、しっかりと準備をして
後々悔いのないようにしましょう。
起業資金調達を支援する創業融資支援
弊所は経済産業省から経営革新等支援機関として
認可を受け、経営財務コンサルティングに力を入れてます。
起業を成功に導く経営財務コンサルティングで
開業・起業資金で融資面談の事前シュミレーションや
当日の面談立会いの同席などサポートを行います。
お客様のご協力のおかげ融資実行率9割超です。
詳細はこちらからご確認下さい。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】はこちら

所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

創業融資の最終関門である金融機関の審査面談で
ポイントになる事項は以前に記載致しました。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資の審査面談内容や面接質問事項 】
基本的にはこのポイントを抑えていれば、多少の変化球にも対応できます。
といいながら、「 融資でこれだけは気を付けて下さい。 」ということが幾つかあります。
上記を通じてお役に立てれば幸いでございます。
会社設立とその後の経理や経営支援も充実
匠税理士事務所は、起業を成功に導くため
起業サービスが充実しております!
本業に集中したい社長様のための経理、
給与計算や社会保険などのアウトソーシングも
行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】

法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

記事はお知らせの免責事項をご確認下さい。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#創業融資注意点 #創業融資服装
法人設立届出など会社設立後に税務署に提出する書類や手続き<K4> (13/03/01)
会社設立後には、どんな届出書を税務署などの
官公庁へ最低限出す必要があるのでしょうか。
このようなご質問をセミナーの際に、
起業家の方から頂くことがあります。
そこで今回は、会社を設立した場合に税務署などへ
【 1 必ず出しておいた方がよい届出書 】 【 2 該当する場合、検討した方がよい届出書 】
についてまとめました。
税務上の届出書において最重要なのは、【 提出期限 】です。
起業した際に、申告期限ぎりぎりまで
税理士をつけない方もいらっしゃいますが、
そのような方の一番のリスクは、提出漏れです。
【税務申告期限】と【届出の提出期限】は、
異なるものが多いので、注意が必要です。

この提出期限を一日でも過ぎてしまうと
届出の恩恵が受けられず大きな損害を被ります。
必要な資料を確認したうえで、誤りのないように
しっかりと提出をしましょう。
法人設立届出書など必ず出した方がよい会社設立時の書類や手続き
① 法人設立届出書
→設立日以後2か月以内に提出の必要があります。
許認可申請など手続きをする際に、
届出コピーを求められることがあります。
また、法人名義での契約の際に届出書や
登記簿謄本が必要になる場合もございます。
控えをいただいて保管をしましょう。
② 青色申告の承認申請書
→設立第1期目から青色申告の承認を受ける場合
提出期限は設立日以後3か月を経過した日と
設立第1期の事業年度終了の日とのうち
いずれか早い日の前日までです。
これを出さないと赤字の繰越などの青色申告の
特典を受けることができません。
またいつの事業年度から適用をうけたいのか、
しっかりと記載しておくことも重要です。
(関連記事:会社を設立した後は、青色申告を行いましょう)

給与支払事務所等の開設届出など提出を検討した方がよい書類
① 棚卸資産の評価方法の届出書
→提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。
② 減価償却資産の償却方法の届出書
→提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までになります。
③ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
→開設の日から1か月以内になります。
【 関連記事: 会社設立後の社会保険・雇用保険加入(義務や必要書類) 】
④ 源泉所得税納期の特例承認の申請
→ 随時
申請書提出した月の翌月末まで通知なければ
申請の翌々月の納付から特例が適用されます。
毎月のお給与から差し引いた源泉所得税の納付を、
毎月納付から半年に一度の納付にするための
承認申請を行う書類です。
源泉所得税は、原則、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与支給人員が常時9人以下の会社は、
源泉税を半年まとめて納める特例があります。
これを、【 納期の特例 】といいます。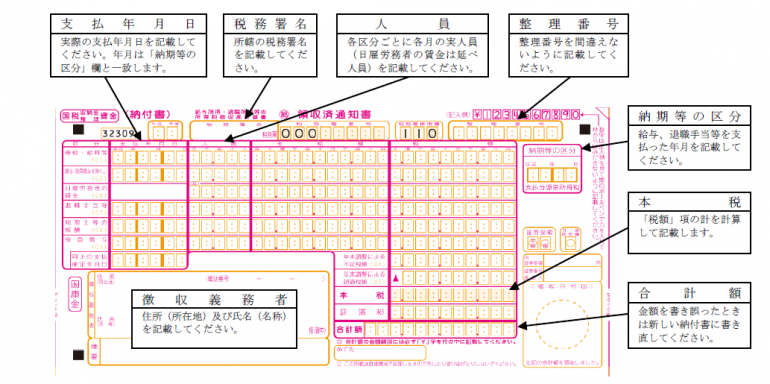
特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収した所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
この申請書を提出すると、給与の支給人員が
常時10人未満であるような会社は、
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について
徴収をした所得税を次のように年2回にまとめて
納付できる特例制度を受けることができます。

1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした
所得税及び復興特別所得税・・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収した
所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
7月10日が土曜なら7月12日(月)が納期限です。
納期限を遅れるとペナルティがあります。
⑤消費税課税事業者選択届出手続
→選択しようとする課税期間が事業を開始した
日の属する課税期間等である場合は
その適用を受けようとする課税期間中になります。
免税事業者の期間などを加味したうえで、
この届出を選択するか否か検討しましょう。
上記の他に税務上の届出が多数ございますが、
今回は説明の都合で代表的なものに限定してます。
会社設立後の届出の税務上の効果
税務上の届出書は一度提出すると、
その効果が半永久的に残りますので、
提出では、将来の税務的なトラブルを避けるため
コピーも必ず保存しましょう。
(これが意外に忘れがちで注意です。)自分の分のコピーを取り忘れてしまうと
第三者に開業届出の提出を求められたり、
税務上の取り扱いが不明確になってしまうなど
トラブルにつながりますので注意しましょう。
匠税理士事務所の会社設立などの起業支援
匠税理士事務所では起業を成功に導くために
会社設立や、会社設立後の税務署などへの官公庁の届出書作成の代行をはじめとして、
起業後の経理や経営支援、給与計算や社会保険手続きなど人事労務のサポートに力を入れております。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇関連記事
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
◇その他の起業支援サービス
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所 ...TOPページへ
対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域
◇個人の起業サービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#法人設立届出 #会社設立届出書類
給与所得控除と法人化・法人成りでの節税対策 (13/02/24)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 >サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化のポイント>給与所得控除と節税
法人化についてのお役立ち情報
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリットとは 】第3回 法人化・法人成りと資産の引き継ぎ
業種別編 建設業や建築業の個人から法人化・法人成りは匠税理士事務所
全回はこちら 法人化バックナンバー
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
法人化による節税で、よく聞く話として
【 給与所得控除利用の 】メリットがございます。
【 給与所得控除 】と聞いて、
会社員しか関係ないのではないか?
と思われる方もいらっしゃるかと思います。
【 給与所得控除 】とは、給与という収入を得るため
会社員もスーツ・靴など一定経費がかかるので、
【 概算での経費 】を認めるものです。
これは、会社員の方だけが対象となるのではなく、
株式会社を作り、法人役員となる方も、
給与所得控除の恩恵を受けることができます。
給与所得控除は法人化節税メリットで代表的です。
給与所得控除と法人化節税の関係

何故、給与所得控除で節税できるのかにつき
以下の例を通して、説明致します。
Aさんは飲食店を個人で営んでます。
売上は20,000,000円として、
説明の便宜上、経費はゼロとします。
Aさんの確定申告は、20,000,000円に対して
税金がかかってくることになります。
Bさんは飲食店を株式会社で営んでます。
売上は20,000,000円とし、諸経費はゼロとします。
ただし、社長である自分に給与は、
月700,000円×12カ月=8,400,000円です。
そうすると、会社の税金計算では
20,000,000-8,400,000=11,600,000円に対して税金がかかってきます。

社長の個人の所得には、
給与の8,400,000円に税金がかかりそうですが、
ここで思い出して下さい。
会社員の方など給与所得者は、
給与という収入に対して概算経費である給与所得控除が認められています。
社長にもこの概算経費は認められることになり、
概算経費(給与所得控除)は下表で計算されます。
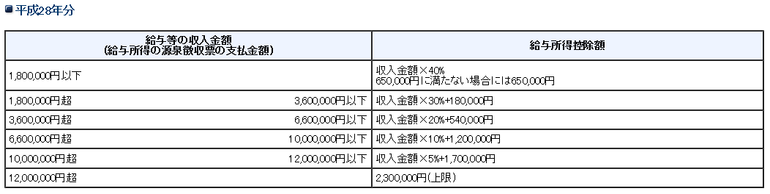
仮にこの年収が8,400,000円の社長の場合には、
8,400,000×10%+1,200,000=2,040,000円
が給与所得控除額となります。
給与所得控除額を加味すると、
8,400,000 - 2,040,000 = 6,360,000円に対して税金がかかってくることになります。

結果として会社で飲食店を営んでいるBさんは、
・会社の所得である11,600,000円と、
・個人所得6,360,000円の合計17,960,000円
に対して税金がかかるため、
個人で飲食店を営むAさんに比べて
給与所得控除分の課税所得を圧縮することができ、
結果、節税できるメリットが得られるわけです。
法人化のメリットや法人化支援サービス
匠税理士事務所では法人化を支援しております。
制度の説明からメリットデメリットの解説を交え、
法人化の相談会もおこなっております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

法人化や法人成りのメリット
このように利益が伸びてきた場合には、
法人化によるメリットがございます。
もちろん、税金面以外にもいろいろな恩恵がございます。
詳細はこちらから確認下さい。
会社にする?個人のまま? 法人化するポイント(メリット・デメリット)
法人化のサービス
個人事業から株式会社にするための法人化について
サービスは下記のリンクよりご確認下さい。
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
【1】法人化・法人成り支援サービス の詳細はこちら
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
記事はお知らせの免責事項を確認下さい。
執筆者・文責 税理士水野智史
#法人化節税 #法人化給与所得控除
税務調査で、職員への質問や私物検査は拒否できますか。<Z13> (13/02/22)
ご質問:
税務調査が行われる場合、税務署の調査官から質問や検査がなされますが、
会社の全ての従業員が対象となるのでしょうか。
また、私物やプライバシーに係るものについては拒否できないのでしょうか?
税務署職員による税務調査の質問検査権の範囲
法人の役員や経理責任者は、質問や検査に応じる必要があります。
しかし事業に関係のない私物や居宅については、
本人の明示の同意がない限り、検査することはできません。
法人の場合、調査官の質問に回答する義務があるのは、法人の役員や経理責任者となり、従業員にその義務はありません。
ただし、その従業員が会社に対して借入や貸付などの関係がある場合には
その借入や貸付については、税務調査に応じる必要があります。
また私物への検査については、税務調査は事業に関係のあるものに限られています。
税務調査の質問での注意点・気を付けたいこと

特にプライバシー保護の要請が、強いものについては
「黙示の承認」(相手が黙っている場合、
承認されたとみなすこと)ではダメで、
「明示の承認」(相手方への明確な承認)が
必要とされています。
実務上よくある事例として税務調査の時に思わず、感情的になってしまい、
「 勝手にしろ!! 」と、許可をしてしまったケースなどがあります。
このような時には許可をしてしまったことになってしまいますので注意をしましょう。
(→ 税務調査では冷静な対応が最も重要です。)
(関連記事:税務調査の対応ポイントや注意点について)
したがって税務調査では「明示の承認」を理解し、
調査対象と無関係のプライバシー部分については
はっきりとその旨を伝えて対処することが大切です。
また、このような調査に関係のない私物は>不要なトラブルを避けるため会社には持ち込まないことも大切です。
特に私的なメールや、個人の取引を会社のパソコンで行うことは避けましょう。
税務調査対策コンサルティング
匠税理士事務所の税理士による税務調査コンサルティングサービスでは、
税務調査の立ち合いと、事前の税務調査対策や調査を想定した経理体制でお客様をしっかりとサポートします。
◇サービスページ
会社の会計や経理、決算については世田谷の税理士なら匠税理士事務所 TOPページへ
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成26年1月23日
法人化の良い点・悪い点 (13/02/18)
法人化のメリット・デメリットに関する解説ページ引っ越しのお知らせ
法人化のメリット・デメリットに関する解説ページは、より良いコンテンツと情報の最新化を目的に、
リニューアルを行い下記に移行しました。宜しくお願い申し上げます。
【 → 個人事業を会社にする法人化のメリットやデメリット 】
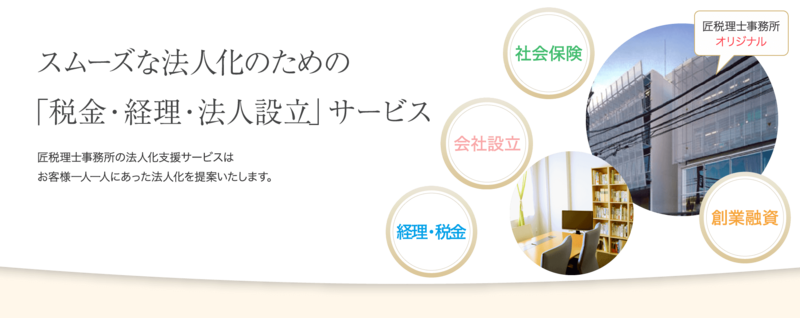
日本政策金融公庫の創業融資の審査面談内容や面接質問事項 (13/02/16)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
第6回 匠税理士事務所は、創業融資を通じて起業支援に力を入れている会計事務所です。
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)で創業融資を受ける際に行われるのが審査面談・面接です。
こう聞くと何となく緊張してしまうのですが、審査面談や面接はポイントがあります。
そこで今回は、創業融資における審査面談や面接の質問事項や内容とそのポイントを記載します。
実際の審査面談や面接では金融機関の担当者ごとに内容が変わりますが、中でも重要点を紹介します。
日本政策金融公庫の創業融資の審査面談の質問事項と内容

日本政策金融公庫の面談時間は、30分から1時間程です。時間は、創業される方の自己資金や事業内容などで短い方と長い方に分かれます。
面談質問事項 1. これまでの経験やキャリア:
これまでの職歴でどのようなことを経験してきて、創業でどのように武器となってくるのかについて確認されます。
面談質問事項 2. 何故創業するのかの理由:
美辞麗句ではなく自分の言葉で、日本政策金融公庫担当者に熱意をしっかりと伝えることが重要です。
その際には、これまでのキャリアと整合性が取れていると理想的です。
面談質問事項 3. 商流など事業の仕組み:
一般的な事業であれば、日本政策金融公庫の担当者の方も理解されているケースが多いですが、
これまでにないようなITのソーシャルビジネスなどのような複雑なビジネスでは、
日本政策金融公庫の担当の方が、内部で稟議をかける際に説明しやすいようにプレゼン資料を作成することも重要です。
面談質問事項 4. 差別化:
【 日本政策金融公庫の担当の方が一番気にされるのが、貸したお金が無事返ってくるかどうか。】
これは、起業家が企業との競争に無事勝ち抜けるかどうかを意味します。
しっかりと勝ち抜くためには、そのための戦略や戦術が必要なのは当然であり、
こうしたものをしっかりと用意して無事競争に勝ち抜くことができる根拠を証明する必要があります。

面談質問事項 5. 創業予定場所:
「創業予定場所はどこになるのか?」
これは上記4にあるように貸したお金が無事に返ってくるのか?
という視点で見れば、
そもそもこの融資の話は、実際に事業のためのものなのかについて確認されるのは当然です。
その際には、賃貸契約書などを用いてしっかりと説明するのが重要です。
面談質問事項 6. 自己資金を貯めるプロセス:
貸したお金を無事返せる = 創業までに資金を貯められる人と考えられます。
自己資金があればいいわけではなく、その自己資金を貯めるまでのプロセスを通帳などを通じてしっかりと説明できることが大切です。
(関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべきか)
面談質問事項 7. 創業後の事業計画:
計画にある売上の根拠や仕入の根拠を通じて
毎月の利益の根拠を自分の言葉でしっかりと説明できる必要があります。
またその数字は希望的数字ではなく、
現実的な数字であることが求められます。
面談質問事項 8. リスク管理について:
創業計画通りに進まなかった場合の対応策について
しっかりと準備できているかについても確認される場合があります。
創業計画のうち日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)などに提出する通常パターンのものと、
金融機関へ提出はしないが、想定外に売上が立たなかった場合のパターンのものを用意しておくと
本番で的確な返答をすることが可能になります。
日本政策金融公庫の創業融資の審査面接成功させるには

このように全ての事項について共通して言えるのは、日本政策金融公庫の方にしっかりと創業融資のお金は返済できるということをお伝えするというのがポイントとなります。
そのためには、入念な準備がとても重要です。
自分で創業計画書などを作成していれば、数字の根拠などはしっかりと答えられます。
また自分で計画をしっかりと作っていると、会社が困った時、創業当初の原点に戻り、思わぬヒントが浮かんだりすることもあります。
資料を自分で用意することはもちろんですが、想定される質問に返答を考えておくようにすると
面談当日、緊張でうまく表現できないということを避けられます。
匠税理士事務所の創業融資支援サービス
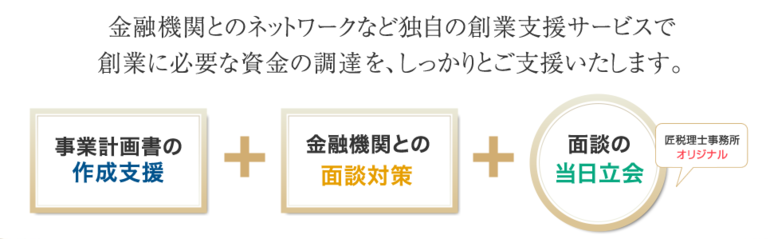
匠税理士事務所では、起業家の方に向けて創業計画書の作成支援から、創業融資の審査面談の事前シミレュレーションや当日の面談立会いの同席などの創業融資サポートを行っております。

世界4大会計事務所出身の税理士や、大手金融機関の元取締役が顧問として在籍しておりますので、
高度な専門性と豊富なノウハウが特徴の税理士事務所です。
日本政策金融公庫の創業融資をご検討されている方は、お気軽にご相談下さい。
お客様のご協力のおかげ融資実行率9割超なっております。詳細はこちらからご確認下さい。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】はこちら

所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】
起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

創業融資に際しまして、会社設立をご希望の方には、会社設立の代行も承っております。
詳細はこちらからご確認下さい。

会社設立や創業融資以外のサービスや料金などはTOPページからご確認下さい。
日本政策金融公庫の創業融資の面談や面接の内容や質問事項など起業家様に向けたご案内をお読み下さりありがとうございました。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
損益分岐点売上(損益分岐点)と会社経営 (13/02/13)
自己資金もしっかりと貯めて、創業融資などと合わせて必要なお金をしっかり準備し、
店舗も家賃が安いところを借りられて、人もまずは最低限の数から始めることで営業を開始。
ここまでの準備は万全です。
しかし、実際営業を開始してみると、
・勤務時代のように集客がうまくいかない・・・・
・当初想定していたように売上がなく、不安だ・・・・・・
というように、最初からうまくいかない方も少なくないと思います。
赤字経営と黒字経営の境界線である損益分岐点売上(損益分岐点)とは
ここで一番怖いのは、何が問題なのか、よく分からなくなり場当たり的な経営をしてしまうということです。
創業当初は、中々うまくいかないという状況に陥りがちですが、
こうした状況で経営者の方に、一番意識して頂きたいのが損益分岐点売上です。
損益分岐点売上は、
会社が黒字になるか、赤字になるかの境界線となる売上です。
この境界線となる損益分岐点売上を達成できれば、お金は減らない状態になります。
お金が減らない以上は、生き残れますし、改善策を練れば黒字にすることも可能です。
また、損益分岐点売上は経営する上での最低限の目標なので、努力すれば多くの場合は到達できるという売上になります。
まずは目先の目標を一つ一つ超えていくことで経営が安定してきます。
損益分岐点売上は経営者にとって重要な指標となります。
損益分岐点売上(損益分岐点)の計算方法
< それではこの損益分岐点売上は、どのようにして計算するのでしょうか? >
損益分岐点売上 = 固定費 ÷ (100% - 変動比率* ) で計算できます。
*上記でいう変動比率とは、変動費 ÷ 売上 で計算します。
<参考:用語の意義>
固定費・・・売上とは関係なく毎月定額で発生する経費。
例:家賃・人件費・機材のリース料・借入金に対する金利など
変動費・・・売上に応じて金額が変動する経費
例:飲食店の材料など
損益分岐点売上をしっかりと抑えていくことが、黒字経営を実現するための第一歩です。
損益分岐点売上(損益分岐点)と経営について
更にこの損益分岐点を起業してしばらくすると超えてきますが、それでもまだまだ安全圏ではありません。継続的に購入してくれる安定した得意先などの売上のみでこの損益分岐点を超えて初めて、経営が安定するといえます。
◇会社の経営についてのお役立ち情報はこちらからご覧ください。
匠税理士事務所の起業・経営支援サービス
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
東京都の税理士なら匠税理士事務所...TOPページへ
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
日本政策金融公庫の創業融資での創業計画書の作成ポイント (13/02/09)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は世界4大会計事務所出身の税理士を中心に、
起業支援に力を入れている会計事務所です。
今回、日本政策金融公庫の創業融資を利用する上で
創業計画書作成のポイントをまとめてみました。
創業計画書作成では、次の2つの視点が重要です。
日本政策金融公庫の創業融資の計画書の目的は、
どこのどんな経歴を持った人が、
【 1 何に幾ら必要で、幾ら借りたいのか】、
【 2 無事に返せるのか 】を説明することです。
日本政策金融公庫の創業融資で用いる創業計画書は、実際次の通りです。
【 1 何に幾ら必要で、幾ら借りたいのか】は、
赤い罫線エリアがこれに当たります。
【 2 無事に返せるのか 】は青い罫線エリアで説明し
それ以外のエリアでどこのどんな人なのかを説明することになります。
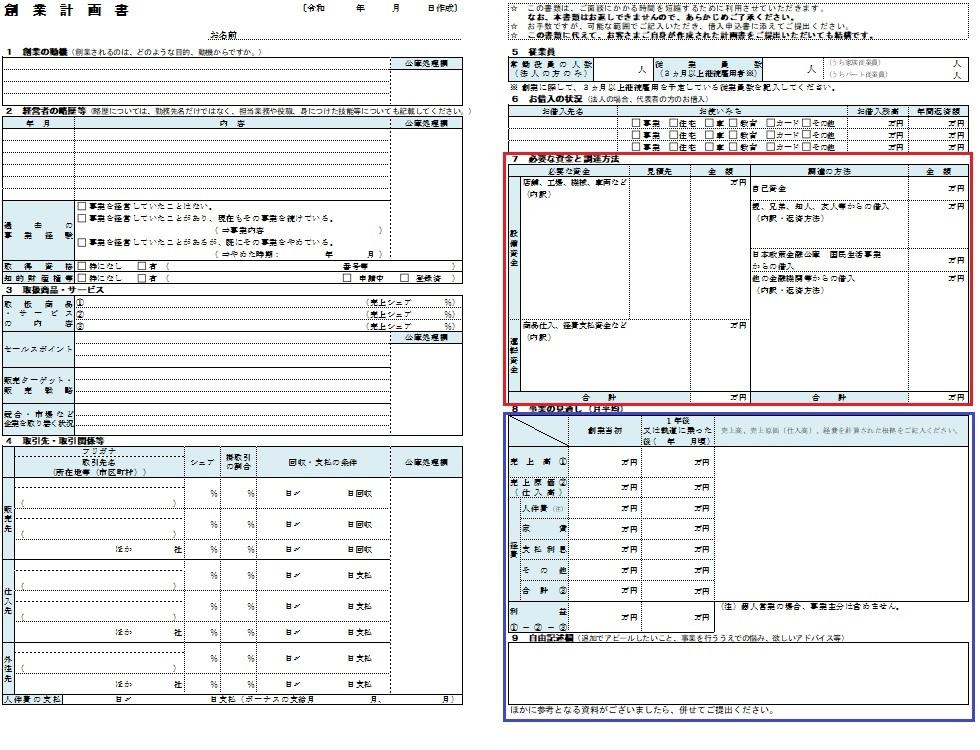
それでは、これらのポイントを掘り下げましょう。
創業計画書の財産面のポイント、何に幾ら必要なのか
1つ目のポイントは、
何に幾ら必要で、どれ位の融資が必要かという財産面の視点です。
これは簡単に言えば、
【幾らの機材を買って、オフィス保証金がどれほどになるのかといった必要資金】と、
【自己資金は幾らほどあり、不足額をどのようにして調達してくるか】を考える視点です。
ここでは、自分が欲しいもの(最新鋭の機器など)を考えてから、必要資金を考えるという方法がありますが、これはあまり良いこととは言えません。
なぜなら、スーパーで食べたいステーキやお刺身を買い
レジでお金が足りないことに気が付き返品あるいは無理をして買って後悔と同じ結果になるからです。
自分が幾らまで用意できて、
これに対して日本政策金融公庫の創業融資で幾らまで検討してもらえるのか把握し、必要機材を予算内でそろえていく方法が理想です。

日本政策金融公庫などの金融機関は、
自己資金の2倍を一つの目安にしています。
自己資金が500万円なら、この2倍の1,000万までということになります。
こうした資金面の予算をしっかりと把握した上で、何にお金をかけるべきなのか、
逆に削るのはどこなのかを考えることが重要です。
予算的に厳しい場合には、当面は中古品やダウングレードしたもので対応したり、事業が軌道に乗ってから用意するという現実的な思考になります。
事業を行う上で、現実的な思考が極めて重要です。

創業計画書損益面ポイント、無事に返せるか
2つ目の重要な視点は、借入を返せる利益を出せるかという損益を把握するという視点です。
日本政策金融公庫の創業融資で用いる創業計画書は、非常にシンプルなフォームです。
1 売上
2 仕入などの原価
3 家賃や人件費などの経費
4 利益 ( 1 - 2 - 3 )
この利益 > 借入金の返済額なら、借入を返せるということになります。
上記2と3は、仕入条件やオフィス物件や雇用の契約が決まれば、確定します。
そのため、創業計画書で最大のポイントは、【 売上を無事に上げられるか。】
こちらを日本政策金融公庫の担当の方に、無事説明できれば概ね成功と言えます。
これらのポイントをしっかりおさえて、
現実的な数字で損益計画を立てる必要があります。

創業計画書作成の苦労は、融資面談で役に立ちます。
創業融資をご検討されている方は、
日本政策金融公庫のご担当者との面談でも理論的に自分の事業の資金調達計画書と、
創業融資の面談は、詳しく売上や経費の数字の根拠を求められます。
したがって、数字の根拠を聞かれて、
・他の人に作成してもらった
・何となくなど
という回答は、論外ということになります。
過去の経験や、各数字を構成する各種資料、様々な統計値を基に日本政策金融公庫担当者を説得できるようになるまで創業計画書を作り込みましょう。
このようにして作成した創業計画書は面談での大事な台本ですので、
必ずご自身を支えてくれます。
台本がしっかりしていれば、
融資面談成功の確率は格段に上がります。
創業融資は一発勝負、悔いのないようチャンスをしっかりとモノにしましょう。
※日本政策金融公庫などの創業融資で
必要になる書類についてお知りになりたい方は、
下記よりご確認下さい。
(創業融資を申し込むために必要な書類とは)
日本政策金融公庫の創業融資支援サービス
匠税理士事務所では、経済産業省より認定支援機関としての認定を受け、中小企業様の経営・財務支援を行っております。
起業家の方に向けた創業計画書の作成支援や、融資の面談の事前シミュレーションなど起業時の資金調達サポートも充実しております。
※弊所は、日本政策金融公庫や各種金融機関と連携し、数多くの創業融資での成功事例がございます。
お客様のご協力のおかげ融資実行率9割超なっております。詳細はこちらからご確認下さい。
【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所 】はこちら

所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

起業支援以外の業務内容や料金などは、
下記よりTOPページに移動の上で、ご確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】
日本政策金融公庫の融資での計画書の作成ポイントを最後までお読み頂きましてありがとうございます。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
自己資本比率の重要性とは(計算方法・計算式) (13/02/05)
会社を経営していると建設業の入札であったり、
融資の条件であったりと様々な場面で、己資本比率について目にすることがあると思います。
そこで今回は、自己資本比率について簡単にまとめてみました。
自己資本比率の計算方法や計算式について
まず自己資本比率を算式にすると次のようになります。
自己資本比率 = 自己資本 ÷ 総資本
ここでいう自己資本とは、貸借対照表にある資本の部、
つまり社長などの株主から調達したお金など借入金と違って返済義務のないものをいいます。
総資本とは、この自己資本に、
銀行などの外部から借り入れた負債を加えたものになります。
つまり自己資本比率とは自分(株主)で集めた資金が、
全体で集めた資金に対してどれくらいの割合であるのかを示します。
重要な自己資本比率を上げるためにはどうすれば良いのか
自己資本比率の割合が高ければ高いほど、会社は返す必要がない資金で運営されているため
会社の経営は安定することになります。
こうしたことから、
自己資本比率は、その会社の安全性を図る一つの指標となるのです。
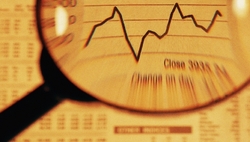
それでは自己資本比率はどうすれば上がるのでしょうか?
それは、
1 分母(総資本)を下げる。
・・使ってない資産を売って、
その売却代金で負債を返済する。
これらを通じて資産と負債を減少させることで総資本が下がります。
2 分子(自己資本)を上げる。
・・社長個人や第三者から増資を受けたり、
利益を上げて内部に蓄えていくということになります。
3 1と2の両方を実行する。
このように自己資本比率を上げるには比較的時間を要します。
自己資本比率改善を意識した経営を心掛けましょう
将来的に自己資本比率を、~%まで改善して、
その先にどのような事業を展開していくのかをしっかりと見据えておくと
自己資本比率を意識的に積み上げていくことも可能です。
自己資本比率は短期的には中々改善しづらいものですので、
長期的な視点を持って自己資本比率に注意して、
財務状態の良い会社経営を心掛けていきましょう。
匠税理士事務所の経営支援業務
自己資本比率の改善など弊所は経営支援に力を入れている税理士事務所です。
会社の経営支援サービスは、こちらからご覧下さい。
◇コンサルティングサービス
自己資本比率以外にも、会社の決算書についてのお役立ち情報はこちらからご覧ください。
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
世田谷で税理士をお探しなら匠税理士事務所...TOPページへ
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
日本政策金融公庫とは?創業融資の借り方と必要書類のコツ! (13/02/02)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
匠税理士事務所の創業融資担当の税理士水野です。
私は両親が金融機関に勤務していたため、金融機関の本音や考え方にふれてきました。
税理士となってこの経験を活かし、お客様の気持ちになりながらも、金融機関はどのように考えるかを頭に置き、創業融資サポートをさせて頂いてます。
今回は、会社を作って創業するにあたって、
設備や事務所を借りるためなど必要資金の一部を
日本政策金融公庫 ( 旧国民生活金融公庫 )からの創業融資で調達したいと考えているが、
そもそも日本政策金融公庫とは何なのか、 また創業融資の制度や流れについて知りたい。 どのような書類が必要なのか分からない・・・
このようにお悩みの起業家の方に向け、創業融資を申込む際の必要書類とコツを説明します。
日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)とは何か?
日本政策金融公庫とは、何なのでしょうか?
〇〇銀行なら町でもよく店を見かけますが、日本政策金融公庫は見かけません。
これは、日本政策金融公庫は100%政府が出資する金融機関であるため、預金業務などを行わず、
普通に生活していると関わることがないからです。
これに対して民間金融機関は、預金でお金を仕入、
このお金を貸し出しています。
このように公庫と民間金融機関は一線を画す存在となります。

つまり、民間の金融機関がリスクをとれない案件でも、国の起業家支援という方針に基づき、
起業家を支援してくれる心強い存在ともいえます。
民間金融機関は、起業家支援のために無担保無保証で融資することは、ほぼありえませんが、
日本政策金融公庫では普通にありえます。
次は起業家の大半が利用する【創業融資】です。
創業融資とは何か? 利率や返済期間は?
日本政策金融公庫の創業融資とは、新たな事業開始 又は 開始後に必要となる設備資金及び運転資金を貸してくれるという制度です。
設備資金とは、店舗の場合は内装や機械などの設備のために使う資金をいい、
運転資金とは、社員の方への給与や仕入の支払いなど事業を維持するための資金をいいます。
通常の創業融資は、最大1,000万円が一般的な限度額となります。
また、設備資金は、7年返済(84回)となり、運転資金は、5年返済(60回)となることが多いです。
利率は経済環境により変化しますが、2024年時点では、2%前後となります。
起業時は創業融資の活用がお勧めな理由
創業される方には、日本政策金融公庫きの創業融資のご利用をお勧めします。
【 最初は融資を考えていなかったけれど、借りておいて良かったです。】
実際の起業支援の現場で多くの社長様からこのようなお声を頂きました。
最初は中々事業が軌道にのるまで時間がかかったが、資金があって助かった。
起業後、想定外の事が起きたが、余裕資金があって助かったということかもしれません。

創業1年後、必ず決算(業績確定)を行います。
最初から黒字にできる方もいらっしゃいますが、
多くの場合、何年後に黒字化される方が一般です。
決算が終わると金融機関は、成績表である決算書を基に判断して、融資の是非を決めます。
つまり、結果が重視されることになるのです。
逆に、創業間もない頃は、決算書がありませんので、金融機関は会社の将来性で判断します。
黒字経営で結果を出す VS 将来性の説明という構図になった場合、
会社の将来性の説明の方が容易で、融資成功の確率が高く、かつ創業融資で資金調達をしておけば、
黒字化に時間がかかったとしても、会社にはお金がありますので生き残る確率も上がります。
このような理由から、創業される方には日本政策金融公庫の創業融資の活用をお勧めしております。
日本政策金融公庫の創業融資の流れ
創業融資の流れは、以下のような流れとなります。
1 創業融資必要書類の作成 と 提出・申込
2 金融機関担当者との審査面談
3 問題がなければ資金獲得
大きくこの3工程で進み、
この申込から獲得に1か月~1カ月半を要します。
それでは創業融資では、どのような書類が必要になるのでしょうか。
日本政策金融公庫の創業融資の申込必要書類
創業融資では、必ず次の書類が必要となります。
(補足:事業内容などにより追加で書類が求められることもございますが、ここでは省略します。)
1 借入の申込書
日本政策金融公庫URLよりダウンロードできます。
https://www.jfc.go.jp/n/service/dl_kokumin.html
2 登記簿謄本
法務局で入手できます。会社の履歴書です。
ここまでの1~2は所定の記載事項などにしたがって記載しますので難しくはありません。
しかし融資で重要なのは、以下3・4の書類です。
創業融資では、上記1~2は入試願書だとすれば、これから取り上げる創業計画書と通帳の写しは、実際の試験と例えても良いほど重要な書類です。
3 創業計画書
日本政策金融公庫に限らず、金融機関は融資の際に何を見極めたいのでしょうか?
これは、お金を貸す側の気持ちに立てば、
【 1 どこの誰に 】
【 2 幾らをいつまでに貸して、何に使うのか? 】
【 3 無事に期限までに返ってくるのか? 】
この3点を見極めたいという結論に行きつきます。
これらを【創業計画】・【審査面談】で見ます。
そのため創業計画書では、
・どこの誰がどのような事をやってきたのか
・何に使うため、幾ら必要なのか
・利益を出し、無事返せるのかを見たいのです。
そのため、ライバル企業より優れている点はどのような点なのかを説明した上で、
融資を受けたお金を返済することができるかをこの創業計画書を通じ証明する必要があるのです。

4 自己資金があることを示す通帳
希望額1/3は自分で用意してる事が重要ですが、
【 その貯めてきたプロセスはもっと重要です。 】
夢の実現にあたって、これまでしっかりと定期的に預金をしてきたという方は、
お金を貸しても期限まで返せる確率が高いので、日本政策金融公庫からは好評価を得られます。
創業するための知識と経験をしっかりとつけた上で、きちんとお金を準備できる創業する社長様の人間性が知りたいのです。
つまり、通帳の単なる残高だけではなくて、
それまでの < 行動 > という創業までの過程をしっかりと示すことが重要です。
論より証拠、新創業融資で資金を借りる上では、創業計画書・自己資金を準備する過程など
その数字がどのような根拠に基づいてはじき出されたものなのかを証明することが重要です。
このように創業する上で創業融資を受けるためには、沢山の書類が必要になります。
これは貸す側の日本政策金融公庫さんの気持ちになってみると当然ですが、無担保で、実績がない状況で大金を貸すわけですから、資金が回収できることを確認しないといけないのです。
そこで、これらの書類を通して、
1 しっかりとした信頼できる人であり、
2 幾らの資金を用意できて、
3 借入をする目的もしっかりとしていて、使い道も安全であること、
4 コツコツ貯金が出来て、利益で返せる人なのかを
審査することになります。その手順として書類と面談の両方の面から創業融資が適切なのか否かが、確認されることになります。
融資は一発勝負。起業に資金は必要不可欠、
創業融資には悔いのないように、万全の準備をして臨みましょう!
匠税理士事務所の創業融資支援サービス
匠税理士事務所では、日本政策金融公庫と連携して起業成功のため資金調達をサポートします。
世界4大会計事務所出身の税理士が、ノウハウを駆使してこれまで多くの実績を上げて参りました。
創業時の会社設立から、そもそも融資を受けたほうが良いのか否かのご相談、創業計画書の作成支援から創業融資の面談リハーサルと当日の面談立ち合いなど、【 起業に必要な全てがそろう会計事務所です。 】
連携をしておりますので、お客様の起業を支援できる万全の態勢を用意しております。
サービスはこちらからご確認をお願いします。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

株式会社や合同会社など会社設立も承っております。
会社設立から創業融資、起業後の経理や給与計算、社会保険の手続きなど全てご用意致しております。
詳細は、こちらからご確認下さい。

創業融資のお役立情報バックナンバーは
創業融資の情報館 バックナンバー へ。
記事については免責事項をご確認下さい。
起業支援以外のサービスラインや料金などにつきましては、 こちらからご確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所 】
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
税理士による日本政策金融公庫の創業融資支援サービス対応地域:世田谷や目黒、品川など東京都
今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?<Z14> (13/01/28)
普通に会社を経営していても、税務調査は避けて通れません。
そして、税務調査はいつやってくるか分かりません。
そこで、税務調査官とのトラブルを避けるために最低限行っておきたい税務調査対策をご案内致します。
(関連記事: 税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象となる会社の決め方 )
税務調査への準備や対策と注意点について
その1 会社と個人の取引注意点
中小企業では、社長さまのお金と会社のお金がはっきり分かれないことや口約束での契約や売買が多くあります。
会社と個人(社長さま、ご親族)の取引については、恣意的になりがちです。
第三者との契約や売買と同じように客観的な合理性のある内容で取引を行うことが大切です。
税務調査に備えて、客観的な合理性のある内容を証明できる資料や契約書を作成しましょう。
( 関連記事: 役員貸付金と税務調査でのトラブル )
その2 公私混同の防止
会社と個人(社長様やそのご家族)の間での、お金の貸し借りを極力なくしましょう。
会社の通帳から社長様個人の引き落としや入金があるケース
社長様個人の通帳から会社の引き落としや入金があるケースは税務調査トラブルのもとです。
このような取引があるときには、すぐに口座変更をしましょう。
また、個人と会社間に頻繁にお金の出入りがあると、本来調査の対象とはならない個人の通帳が、税務調査対象となってしまうケースもあります。
その3 売上管理
税務調査で最もウェイトが置かれるものが、売上調査です。
売上伝票や受領書、領収書の控、請求書その他の書類を整理して保存し個々の売り上げの金額や引き渡し時期などについて疑問点が生じないようにしておきましょう。
(関連記事:税務調査と売上等の収益の認識基準)
その4 仕入管理
仕入れについては、棚卸をもれなく、しっかりと行いましょう。
特別な理由により原価率が大きく変動したときなどは、税理士にしっかりと伝え、税務申告書類を作成してもらうようにしましょう。
(関連記事:棚卸資産の評価損(在庫の評価替え) )
その5 経費管理
経費について、税務調査で最もトラブルになるものが、私的経費の混入です。
経費については、それが事業に関係のあるものだという客観的な証拠をきちんと残しましょう。
内容を改ざんしたような領収書が一枚見つかれば、税務調査の日程延長や、
重加算税の対象会社などになってしまう可能性もあります。
私的経費が混ざることのないようしっかりと注意しましょう。
(関連記事:税務調査で一番怖い税金、重加算税とは)
その6 現金管理
○現金について税務調査のポイント
1.現金に関する補助簿の有無及びその記録が正しいか
2.補助簿の残高と実際残高の一致
3.事業の規模に不釣り合いな多額の帳簿残高となっていないか
○現金調査の手順
1.調査日の直前の帳簿残高と、実際残高の確認
2.現金出納帳の記載に誤りが無いかの確認
3.月中に現金残高がマイナスになっていないかの確認
※現金の実際残高との不一致の原因~現金不足の場合~
1.出金伝票、領収書などの支払帳票よりも多く現金を支払った
2.支払帳票無しに出金を行った
3.一部現金を補充したが、その金額と補充先が不明である
※現金の実際残高との不一致の原因~現金過剰の場合~
1.支払帳票よりも少なく現金を支払った2.入金伝票なしに現金を受け入れた(売上計上もれ、売掛金計上もれなど)
現金商売の時には、売り上げの除外であったり、使い道の不明なお金と印象をもたれないよう日々充分に気を付ける必要があります。
税務調査で税務署と不要なトラブルを避けるために重要なこと
会社でできる税務調査対策をしっかりと行うだけでも、
税務調査で税務署と不要なトラブルを小さくすることができます。
正しい税務申告を行うのと同時に、
税務調査に疑われるような余地のある取引を
行わないこともとても大切です。
そのためには、取引の内容を正確に立証できる
客観的な証拠資料の用意が重要です。
匠税理士事務所では、税務調査で調査官に反論できるような
資料作成支援にも力を入れております。
匠税理士事務所の税務調査対策コンサルティング
匠税理士事務所による税務調査コンサルティングでは、将来の税務調査を想定した事前の税務調査対策と、実際の税務調査の立ち合いでお客様の大事な会社ををしっかりとお守りします。
◇サービスページ
会社の会計や経理、決算については 目黒の税理士なら匠税理士事務所TOPへ。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
起業・開業の貯金や自己資金はいくらまで貯める、用意すべき? (13/01/26)
創業融資のサービス内容 創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館 バックナンバー
起業のために準備すべきことは、沢山あります。
中でもどの業種でも最優先すべきことがあります。
それは【起業に必要な貯金・自己資金の用意】です。
開業に必要な自己資金平均は、600万~800万程。
もちろん、開業費用はビジネスモデルで変わります。

起業・開業の貯金はいくらまで貯める、
用意するべきかは
① 起業にどの程度のお金が必要かを、資金計画を立てて見積もり
② 必要なお金の内、どれだけを自分の貯金で用意するか
によって決定します。
必要なお金のうち貯金しなければならないお金を、
会社員の時にどれ位準備できるかが大切です。
起業前に貯めた1万円は融資で2万円に化けることにつながるからです・・その理由は続きで
起業・開業前に準備すべきは貯金・自己資金
会社員のうちは、収入が安定していますので、
資金を計画的に用意することが可能です。
しかし、起業すると収入は変動します。
お金がなくなれば、必要な設備や人材、材料などの
選択肢も限られ、ビジネスモデルの変化を求められ、
打開策が限られ、精神的に苦しくなります。
起業成功確率を高めるため、必要な貯金・自己資金を
用意し万全態勢で起業することが大切です。
起業に必要な自己資金は、幾らまで自分で用意・貯金すべきか?

【 それでは、起業や開業の自己資金は、いくらまで用意・貯金すれば良いのでしょうか? 】
起業するために必要なお金のうち、
自分の貯金・自己資金でまかなえないお金は、
金融機関から調達することになります。
そのため、いくらまで貯めるべきかは、資金調達先の求める条件までは、最低限用意すべきです。
創業時の資金調達先のメインとなるのは、
1 日本政策金融公庫
2 制度融資(目黒区など行政機関の制度融資)
が代表的なものとなります。
このうち、
1 日本政策金融公庫については、
開業資金の3分の1以上の自己資金を用意することが求められます。
つまり600万円借りたいのであれば、
300万円は自分で用意することが必要となります。
創業資金総額の10分の1以上の自己資金と要件
でなってますが、現場では上記の自己資金の
【 2倍 】が一つの目安となります。 つまり起業前に1万円でも多く貯金して自己資金を増やしておくと、 融資でも2倍に相当する2万円分の枠が増加して資金調達がしやすくなるということです。2 制度融資(目黒区など行政機関の制度による融資)については、各行政機関によって自己資金の要件が異なります。
自己資金の要件がないところもあれば、
開業資金の2分の1以上の自己資金を用意することが求められるところもあります。
この求める条件までは、自分の貯金・自己資金で
用意できるよう準備をしたいところです。
貯金・自己資金など起業や開業までの準備プロセスも重要
ここで気を付けたいのが
いずれも 「自己資金というお金さえあれば良い 」というわけではなく、
その自己資金(貯金)を、どのような過程を踏まえて貯められたのかも重要です。
コツコツと夢に向かって努力(貯金)された方は、
しっかりと期限までに返済できると、日本政策金融公庫など各金融機関の創業融資でも評価されます。
反対に、一例として、お金があっても
競馬で得たお金など自分で貯蓄したお金で
ないと金融機関からの評価は悪くなります。
過去に返済が滞っている場合は難しくなります。
今からはじめる貯金と起業準備
将来起業をしたいとお考えの方は
まずは、ざっくりとどれくらいのお金が必要になるのかを計算してみることが重要です。
そうすると、
必要なお金のいくらまでを、いつまでに用意して
残りは、どの創業融資を受けるかを検討できるようになります。
いつかは起業したい・・という漠然な思いが、
〇年〇月〇日に起業するという現実的になり
これにより起業の貯金と自己資金確保の行動が
大きく変わります。
また、自己資金を貯める過程もしっかりします。
起業して夢を叶える人、
夢が夢のまま終わってしまう人、
この差は行動をできるか否かにあります。
最短のスピードと手間で行動をするには、
起業までの創業計画書を立てることが重要です。

起業成功のポイント まとめ
ポイント1 いつまで幾ら用意し
どの事業で起業するか決める
ポイント2 コツコツと地道に準備(貯金)
計画をたてて慎重に行動する
ポイント3 思い切って起業する実行力
ポイント4 人を統率するリーダーシップ
起業した後も、経営者は、利益を蓄えておく堅実な経営を行う必要があります。
貯金など自己資金を準備は、経営者になるための重要な第一歩です。
起業や開業支援サービスのご紹介
弊所は、日本政策金融公庫等の金融機関と
起業開業に必要な資金調達をサポートします。
これから起業される方向け融資支援はこちらから
【 → 日本政策金融公庫の創業融資に強い税理士は匠税理士事務所】

所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら

起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

(参考:起業や創業融資での創業計画書の作成のポイント )
(参考:創業融資を申し込むために必要な書類とは )
創業融資のお役立情報バックナンバーは
創業融資の情報館 バックナンバー へ。
記事については免責事項をご確認下さい。
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
起業開業して株式会社や合同会社など
会社設立サービスはこちらから
起業や開業時の資金調達など
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
独立開業後の会計経理や経営支援など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で起業した後に株式会社に変更する
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#起業貯金
#起業自己資金
売上が伸びているのにお金が足りない原因とは (13/01/21)
会社の資金繰りについて聞かれた場合、
当面の資金繰りは、社長さまの頭にある方も
多いのではないでしょうか。
経営を安定させ、規模の拡大には
【長期視点で】、収支を予測した経営が必要です。売上が伸びると、会社の資金繰りは一時的に苦しくなる?
ある日経理担当M様より連絡をいただきました。
Q:順調に売上が伸びて儲かっているのに
資金繰りが苦しいです。
どうしたら良いでしょうか?
A:社長、売掛金・在庫状況は点検されてますか?
売上が伸び、利益がでていれば十分なお金があり、
本来は資金繰りを気にする必要がありません。
それなのになぜ資金繰りが苦しいのでしょうか。

多くの会社では、毎月の業績を見るときに
売上を増やしてもっと利益をだそうとすると、
先に在庫確保の必要があるので在庫が増えます。
利益が増えるのですから、営業の戦略としては
正しいのですが、拡大に伴って必要な運転資金を
【 増加運転資金 】といい、
この増加運転資金をコントロールすることが、
黒字経営で、かつ資金繰りが良い会社になる
経営上、一つのポイントとなります。
売上を伸ばすと同じ位、資金管理は重要
しかし、お金を考えず、売上拡大しようとすると
先に仕入のお金を支払い、代金を後から回収までに
給料や家賃など経費支払・借入金返済などで在庫を
仕入れるためのお金が、なくなってしまいます。

このように表面上、利益が伸びていても
会社にお金がない事態がしばしば発生します。
どれだけ売上が上がり儲かっていても、
手元に支払う現金がなければ、【 倒産 】します。
このようなときには、売上を伸ばすことと同じく
現金不足管理も重要であるということを
再度、認識し直す必要があります。
増加運転資金問題を解決する資金繰り表
経理担当M様と資金繰り表の作成をしました。
資金繰り表を作成し、いつのタイミングで
いくら資金が不足するのか一緒に確認しましょう。
初めは、誤差が出ることも多かった資金繰り表も
次第にわずかな誤差で作成できるようになり、
会社のお金の動きが把握できるました。
あわせて、在庫改善や売掛金改善、
売上商品別改善、借入金改善など
経営改善を、毎月根気よく続けました。
資金繰りというと資金調達(お金を借りてくる)
イメージが強いですが、経営改善が一番重要です。
なぜならば、経営改善で根本を改善しないと
資金不足は、繰り返されるためです。
売上が急激に伸びている社長様は今日からでも
資金繰り改善に取り組むべきです。
匠税理士事務所の経営コンサルティング
匠税理士事務所では、資金繰り表の作成支援から
キャッシュストック経営のためのコンサルティング
経営革新等支援機関として融資支援も行ってます。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
執筆者・文責 税理士 水野智史
#売上が伸びているのにお金が足りない #運転資金
税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?≪Z10≫ (13/01/16)
税務調査で申告内容に誤りがあったときには
計算を直し、不足税金を納める必要があります。
このとき、本来納めるべき税金に加えて
罰則的税金を追加で納めなければなりません。今回は罰則的な税金はどのような時に課せられ、
どれくらいの税金がかかるのかを説明致します。
(説明のため一部省略で記載しております。)
税務調査で誤りが判明した場合の罰金の種類に関する説明
①過少申告加算税
提出済みの申告書に計算の誤りがあり、
税務署の調査を受けて修正申告をしたり、
税務署からの更正を受けたりすると、
新たに納める税金の外、過少申告加算税が生じます。
過少申告加算税は、新たに納めることになる
【 税金の10%相当額(又は15%)】。
②無申告加算税
提出すべき確定申告書を提出期限までに提出せず
期限後に申告をしたり、税務署の決定を受けると、
新たに納める税金の外、無申告加算税が課されます。
この無申告加算税は、納めるべき税金に対して、
【 50万円までは15%(又は20%)】です。
(一定の場合には5%になります。)
③重加算税
税金の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を
隠ぺい又は仮装不正の場合、重加算税が課されます。
【 重加算税は、35%(又は40%) 】で通常の罰則的税金より高い税率が課されます。
(関連:税務調査で一番怖い税金、重加算税とは)

④延滞税
追加で納める税金について、本来の納付期限から
遅れたことによる利子として課されるものです。
延滞税は納期限までの期間及び納期限の翌日から
2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、
原則として年7.3%の割合が適用されます。
(利率は毎年見直しが入ります。)納期限翌日から2月を経過する日の翌日以後につき
年14.6%の割合で計算した金額となります。
※申告書を提出し1年以上経過してから修正申告
したとき(重加算税が課された場合を除く)には
法定納期限から1年を経過日の翌日から修正申告を
提出した日まで延滞税計算期間から控除されます。
税務調査の罰金は経費にならない
ここまで税務調査で誤りなどがあった場合の
いろいろな罰則的税金を紹介させて頂きましたが、
最大のポイントは、
この罰則的税金は、当然支払っても経費にならないということです。
このような無駄な罰則的税金をとられないためにも
将来の税務調査を意識した経理が非常に重要です。
(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)
匠税理士事務所の税務調査対策サービス
弊所ではお客様の大事な会社をお守りするため、
経験15年以上の税理士が調査対策を行います。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

税務調査対策サービスの詳細につきましては、
下記よりご確認をお願いします。
◇サービスページ
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
会社設立から会計・経理代行までサポートする
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
節税対策から税務調査対応もサポートの
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
確定申告から会社にする手続き代行まで
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。

記事は<お知らせの免責事項を確認下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#税務調査修正申告 #税務調査罰金
税務調査の対応ポイントや注意点についてZ8 (13/01/04)
Q:法人や個人事業主は、税務調査に応じる義務があると聞きました。
税務調査を拒否した場合には、何か罰則はあるのでしょうか。
A:税務調査の対応を拒否した場合には、≪ 罰則 ≫がありますので、注意が必要です。
税務調査とは何か、そして税務調査への正しい対応とは
税務調査とは、税務署が『税金の計算に誤りがないかどうかを確認すること』です。
これは任意の調査であり、強制調査ではありません。
(関連記事:税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象となる会社の決め方)
しかし税務調査で
下記のようなことを行うと
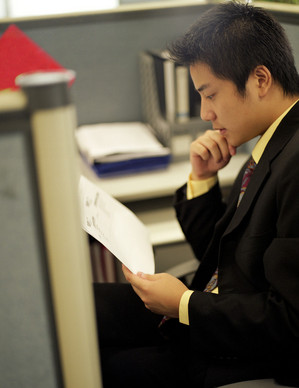
<一年以下の懲役>又は<50万円以下の罰金>
という法律があります。
①質問に関する不答弁
②質問に対する偽りの答弁
③検査拒否
④検査妨害
⑤検査忌避
⑥偽りの記載又は記録をした帳簿書類の提出
つまり調査官の質問や検査を妨害したり、
嘘の答弁をすれば
≪罰則≫がありますので注意が必要です。
しかし、税務調査であれば、何でも自由に調査して良いという訳ではありません。
税務調査官は、「質問検査権の範囲内」で税務調査を行うことができるとされています。
したがって税務調査に際して、任意調査であるにもかかわらず
職権により相手方を拘束したり、
捜索したり、差し押さえたりすることはできません。
(関連記事:税務調査で、職員への質問や私物検査は拒否できますか。)
税務調査の正しい対応には、セーフとアウトのラインの見極めが重要
裁判例では、事業主の不在中に税務調査官が、抜き打ち調査を行い
店舗兼住宅の2階居宅部分へ専従者の妻の承認なしに上り込み、
タンスやベットの引き出しを検査し、
パート従業員のハンドバックを取って中を開け手帳を取り出した事件の判決がありました。
このような行為は、プライバシー保護の観点から違法となるだけでなく
捜索令状による強制調査以外の税務調査は任意であるため、
調査は本人の承諾がなければならないという点でも問題のある調査として
損害賠償の支払いを国側に命じました。
このように税務調査では会社側でやってはいけないこと。
税務調査官がやってはいけないこと。
これらが法律で規定されています。
このアウト、セーフのラインを見極めて、
会社側でやってはいけないことは、税務調査の前にご説明し
税務調査官側がやってはいけないことを税務調査当日に指摘することが
税務調査においては、大切なことです。
税務調査への対応は、専門知識が必要なため税理士に任せるのが一番です。
もし、会社側で準備をするのであれば、やってはいけないこととしては、税務調査の妨害や、嘘の返答です。
やっておくべきこととしては、
プライベートなものは、税務調査当日までに家に持ち帰っておくこと
必要な書類はすべてプリントアウトしておくこと。
調査官から求められたら必要な書類を提出すること。
その他、日々の経理も税務調査を意識して行うことです。
会社と社長のお金が混じっている会社は、とても危険です。
(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)
税理士がいる会社では税務調査では
・日々の経理処理で、税務調査でトラブルにならないような仕組みの提案
・税務調査で、社長さまに代わって税務調査官への説明を行う
・過去の判例や法律によって税務調査官と交渉を行う
・セーフアウトのラインを意識した税務調査の対応を行う
これらを顧問税理士が行ってくれるかどうかを、しっかり確認しましょう。
これらが税務調査にとっては非常に重要となります。
匠税理士事務所による税務調査対策コンサルティング
匠税理士事務所では、税務調査の経験豊富な税理士による務調査対策コンサルティングサービスを提供しております。
税務調査の不要なトラブルを避けるためには、日々の経理などの会社側の事前準備と、税務調査に立ち会う税理士のサポートが非常に重要です。
◇サービスページ
会社の会計や経理、決算については 税理士 目黒 匠税理士事務所TOPへ。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間Z1 (12/12/27)
税務調査とは、税務署が会社などに税金の申告納付が、正に行われているか一定期間ごとにチェックすることですが、
この税務調査はどのような会社に対して行われるのでしょうか?
税務署が行う税務調査の実施割合はどの位なのか
皆様は、税務調査が【どの程度の割合】で行われているのかご存知でしょうか。
~国税庁ホームページによると~
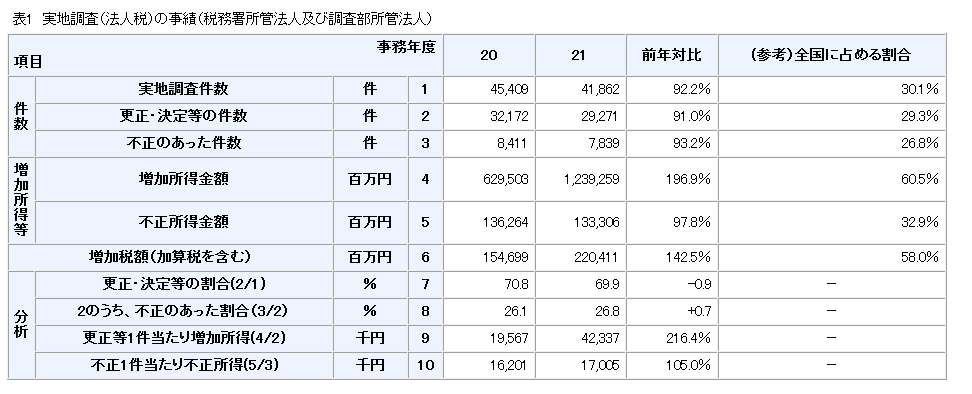
国税庁ホームーページ引用
税務調査は、年間、これだけの件数が行われています。
そして、税務調査の結果
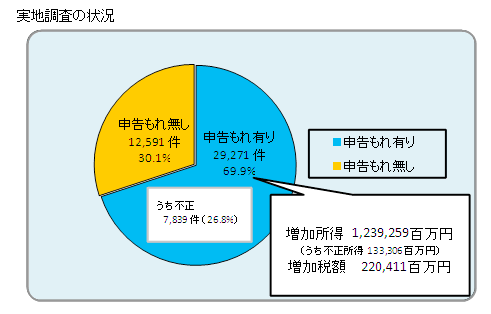
国税庁ホームーページ引用
これだけの割合で、申告漏れが発見されています。
赤字の会社(法人)でも税務調査は行われます
私の会社は、
≪ 赤字なので関係ないでしょう。 ≫
と思われている方、ちょっと待ってください!

国税庁ホームーページ引用
赤字でもこれだけの割合で、
税務調査が行われています。
赤字企業の調査の結果
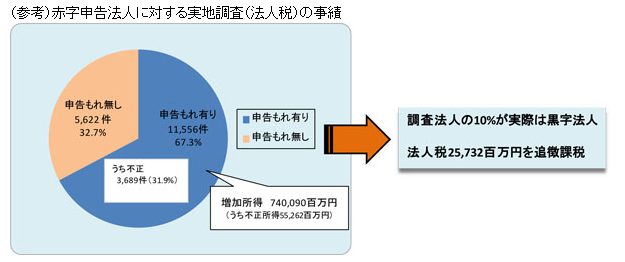
これだけの割合で、申告漏れが発見されています。
この数字を見て、
【7割弱も申告漏れがある 】 とびっくりされるかと思います。
税務署は何故7割もの申告漏れを発見しているのでしょうか?
それは、
≪ 何かある ≫可能性を秘めている会社に調査に来るからです。
それでは、調査先はどのように選定されるのでしょうか?
解説をしていきたいと思います。
税務調査の対象会社(法人)や対象期間はどうやって決まるのか?
・・税務調査の対象はどう決まるか?・・
税務署は、
税金の計算が正しいかどうかをチェックするために税務調査を行います。
実際には、
税金の計算が誤っているかどうか をチェックします。
つまり、
誤っている可能性がある会社を、探します。
ただ、調査官の人数にも限りがあり、
全ての会社に訪問して調査を行うことはできません。
そこで税務署内で、
税務調査の対象となる法人を選定する作業を行います。
税歴表という書類を作成して、
会社の申告書や決算書などから
<利益の状況>
<売上高や経費・原価の前年比>
<過去の調査実績>
<調査の指導事項>
<同業他社との比較>
その他にも日々集められる<資料や情報(資料せんや反面調査)>
などをチェックします。
上記の他にも、
"内部告発"や"匿名情報"など重要資料のあるもの
"接触度が低いもの"など
これらの項目を税務署内でチェックして、
≪税務調査の対象を選定します≫。
特に、過去の一定期間に
"不正を行った法人や、取引先の"不正に加担した法人"、
"重点調査業種" に指定された業種に属する法人については
【調査対象】になりやすいといえます。
赤字法人はどうでしょうか?
国税庁では このようにホームページで公表しています。
全体の約75%を占める赤字申告法人の中には、
税負担を逃れるために故意に赤字に仮装している法人もあることから、
赤字申告法人に対しても積極的に調査を行っている。
このように述べています。
赤字でも、もちろん対象となります。
税務調査の対象となりやすい会社について
下記では税務調査対象になりやすい傾向がある会社について記載しております。
1.好況業種、特定業種、売上階級区分の高いもの
毎年国税庁や税務署で選定される好況業種(重点業種)に該当するもの。
2.同業者との比較によるもの
同業他者と比較して、所得が少なすぎる、
経費が増加しているなどの不審事項や不明事項がある。
3.決算内容に不明点があるもの
代表者からの借入金が急増したり、多額の変動があるもの
経理処理がずさんで、法人と個人が混同しているもの
4.取引先の不正に加担してるもの
査察をうけたものと取引があるものなど、取引先の不正に加担していると認められるもの
5.事業数値に著しい変動があるもの
売上や仕入れ、外注費の比率の激変や、重要資産の取得や売買があるものなど
各種数字に異常があるもの
6.前回の調査事績によるもの
前回の調査で不正計算が発見された会社で、3年程度の調査周期に該当しているもの。
税務署側も、ある程度あたりを付けて税務調査を行っています。
そのため、上記のような異常値が申告書などの資料から判明したときには
税務調査の選定対象会社となりやすくなります。
また税務調査の対象期間としては、
直近3年間が一般的ですが、
過去に重加算税が課せられていたり、
何かしらの追徴課税するための根拠を
税務署が入手しているようなケースでは、
税務調査の対象期間が3年より延長されるケースもあります。
上記で分かるように不正をしていなくとも好況業種であれば税務調査に来ることもありますし
赤字の会社でも、同業と比較して経営数値がかい離していれば税務調査が入りますし、
秋は比較的税務調査が多い時期になり、1月から3月は税務調査が比較的少なくなります。
いずれにせよ法人経営には、
税務調査に対する準備を行うことは非常に重要です。
◇サービスページ
会社の会計や経理、決算については 税理士 目黒 匠税理士事務所TOPへ。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
在庫が資金繰りを圧迫している場合の経営改善 (12/12/24)

卸売業や、製造小売業などでは、在庫を制するものが
経営を制するといっても過言ではありません。このような業種では、在庫のコントロールによって資金繰りが大きく変わってしまいます。
過剰在庫を避ける在庫管理の重要性と資金繰りの関係
~こんなことがありました。~
ある日Z社の社長さまよりご連絡をいただきました。
Q:需要の多様化で在庫を沢山抱えてしまいました。過剰在庫の結果、資金繰りが心配です。
どうしたら良いでしょうか?
A:ビジネスモデル・在庫管理に問題はないでしょうか?
Z社では、お客さまのニーズを取り入れた商品の開発を進めてきました。
お客さまからのニーズがあれば、原材料を仕入れ、商品を開発し、多種多様の商品を作ってきました。
お客さまのニーズを取り入れた商品の開発は大変素晴らしいものです。
一方このビジネスモデルには以下のポイントがあります。
① 在庫の商品数が多く、管理が大変であること。
② 多くの在庫を保有し、倉庫や在庫管理の人件費が多いこと。
③ 原材料を仕入れてから、商品を開発し、商品を作り、一般店頭に並べ、お客さまが購入するまでのリードタイムが長いこと。

ここで大切なのは当たり前ですが、
在庫をしっかりと分析することつなわち在庫管理です。
最低限として、
仕入れてから、売れるまでどのくらい時間がかかるのかを
商品別に把握し、その維持するためのコストは
いくらかかるのかは知っておきたいものです。
在庫管理の徹底は、資金繰り改善に有効です
このような在庫管理を徹底することで、売れ筋の商品に絞り込むことが可能になる上、
商品が実際に売れるまでの時間も計算できるようになり、過剰在庫といった問題も生じにくくなります。
結果として、仕入のタイミングや量も適正になるので、資金繰りも改善されていきます。
在庫管理が、何となくになってしまっている場合には、
資金繰りに悪化にも最終的にはつながりますので、要注意です。
在庫管理をしっかりと行って、資金繰り・経営を改善していきましょう。
( 関連記事:期末棚卸しとは? 月末在庫管理は利益や売上原価の計算で重要 )
( 関連記事:中小企業と資金繰り対策(資金繰り表の作成) )
( 関連記事:売上が伸びているのにお金が足りない原因 )
匠税理士事務所のキャッシュストック経営のためのサービス
匠税理士事務所では、資金繰り表の作成支援からキャッシュストック経営のためのコンサルティング、経営革新等支援機関として融資の支援サービスも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
棚卸資産の評価損(在庫の評価替え)と税務調査Z11 (12/12/20)
卸売業や小売業など物の販売に携わる方にとって
【棚卸】と【決算数字】は、綿密な関係があります。
棚卸資産価値が、購入時の価額より減少したため、
評価損を計上したい方もいらっしゃると思います。
しかし、法人税では原則、評価損は認めていません。
評価損計上は、税務調査で基本トラブルになります。
税務上で棚卸資産評価損(在庫の評価替え)が認められる場合
税務上評価損が認められるのは、
次のようなケースです。
1 棚卸資産が風水害など災害で著しく損傷
2 棚卸資産が著しく陳腐化したこと
◇◇陳腐化とは?◇◇
棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないが
経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく
減少し価額が今後回復しない状態。
具体例:
(1)いわゆる季節商品で売れ残ったものについて
今後通常の価額では販売することができないことが
既往の実績その他の事情に照らして明らかなこと。
(2)その商品と用途面が同様で型式・性能・品質が
著しく異なる新製品が発売されたことによって、
その商品が今後通常の方法により販売することが
できないようになったこと。
(3)会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に
関する法律の規定による更生手続における評定が
行評価替えの必要が生じたこと
(4) 1~3に準ずる特別の事実
評価損が認められるのは、上記ケースです。
棚卸資産の評価損(在庫の評価替え)が認められない場合
棚卸資産の時価が、単に物価変動、過剰生産、
建値の変更等の事情によって低下しただけでは、
評価損は認められません。また、税務調査では評価損については詳細に
その算定根拠などの内容も確認されますので
立証できるよう資料の保管も注意しましょう。
匠税理士事務所の税務調査コンサルティング
匠税理士事務所では、税務調査での対策を含めた
総合的なコンサルティングを行っております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは? )
(関連記事:税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間)
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
棚卸資産など資金需要が多い方のための
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
棚卸など在庫が多い業種も対応の
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
個人事業主で購入した在庫や棚卸などを
新設法人に売買するための税務申告など
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
◇サービスページ
記事はお知らせの免責事項をご確認下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#棚卸資産評価損 #在庫評価替え
税務調査で一番怖い税金、重加算税とは・・Z4 (12/12/15)
税務調査によって、
提出した申告書に誤りがあったときには 計算をやり直して、差額分の税金を納めなくてはいけません。
このとき通常の申告と違う点があります。
それは、罰則的税金がかかることです。
この罰則的税金のうち、<特に影響が大きいのは、重加算税という税金です。
(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?)
税務調査で避けたい重加算税とは何か
重加算税とは、事実の全部又は一部を隠ぺい、又は仮装して税務申告を行った場合に>罰金として支払わなければならない税金です。
その税率は、35%から40%と非常に大きな罰金がかかります。
しかし、重加算税がかかる恐ろしさは、これではありません。
罰金のなかに、延滞税というものがあります。
これは本来支払うべき税金を、
支払うべき時期までに支払っていないものとして納付遅延に対しての延滞金(利息的のようなもの)です。
重加算税がかかるときには本体は【最長一年間】の延滞税が納付遅延の全期間にかかります。
年14.6%の延滞税ですから場合によっては、その負担は、重加算税を超えることになります。
そのため税務調査では、
重加算税が最も怖い税金と言えます。
税務調査で重加算税を課せられる要件とは
この重加算税がかかるときとは
(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。
(2) 次に掲げる事実(以下「帳簿書類の隠匿、虚偽記載等」という。)があること。
帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、
棚卸表その他決算に関係のある書類(以下「帳簿書類」という。)を破棄又は隠匿していること
帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との
通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、
帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること
帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、
売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること
以下省略 >このようなケースです。
・軽い気持ちで領収書の内容を変えて発行してもらった
・売上や棚卸を除外してしまった
軽い気持ちで行った行為が重加算税という税金と、延滞税という税金がかかりケースによっては会社の経営にも重大な影響を及ぼしかねない税金の支払いが発生することもあります。
重加算税からお客様を守る税務調査対策サービス
税務調査で重加算税を付加するには、上記のような要件があります。
正しい税務申告をしていて、重加算税をかけられる覚えがないという場合には、<しっかりと反証することも重要です。
また、税務調査には、日々の正しい経理が一番重要です。
(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは?)
匠税理士事務所の税務調査コンサルティングでは、税務調査の立ち合いと、事前の税務調査へのコンサルティングでお客様の大事な会社をしっかりとお守りします。
◇サービスページ
会社の会計や経理、決算については 税理士 目黒 匠税理士事務所へ。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
最終更新日:平成26年1月23日
利益・経費などの損益とお金の増減は一致しない? (12/12/07)
『 儲かって、お金が残る会社 』 を作るには、儲かる仕組み作り(黒字経営)をするのと同じくらいにお金が残る仕組み作り(資金繰りの改善)は重要です。
黒字経営なら資金繰りは問題ないのではないかと思われている方や、
決算書では儲かっているのに手元に資金がないという方は意外に多いです。

これは損益計算書にある会計の利益が、
一定期間の会社の儲けを測定するために算出された値であり、
実際の売上・経費の増減と、お金の増減は、
ほとんどの場合、一致しないことに起因します。
一見、当たり前のように感じる売上・経費の増減と、
お金の増減が一致しないことを、
経営に取り入れている会社は意外と少ないものです。
しかし、これは非常に危険な状態で、黒字倒産は、このようなお金の増減と利益の増減分けて考えないことで起こります。
損益とお金が一致せず、危険な状態になる前に、対策しましょう。
まずは、お金の増減と、売上や経費の増減の違いを簡単な例で説明したいと思います。
売上
売上については、会計上は原則としてお客さまに納品をしたときに認識します。
これに対してお金は、お客さまからお金をいただいた時にお金が増えます。
つまり、お客さまに納品をしたときに
お客さまからお金を入金されていなくても、売上は認識することになりますが、
お金が実際に入ってくるのは納品して数か月後が一般的ですので、
売上の計上時期と入金時期にタイムラグが生じます。

棚卸資産 (商品)
棚卸資産(商品)については、お客さまに販売したときに経費となります。
一方、お金は、商品を仕入れてその支払期限までに支払うこととなります。
ここでも、商品を仕入れてから代金を支払い
お客さまに販売するときまでは在庫となるため経費にならず、
販売されたときに経費となるので、<お金が出ていく時期、
経費になる時期の間にタイムラグが生じます。
固定資産 (ここでは例えとして車で説明します。)
タイムラグの一番分かりやすい例が固定資産です。
車は、使用可能な年数(軽以外の普通乗用車であれば6年)で按分計算したものが経費となります。
お金はローンを除けば、当然その車を納品してもらって一時に支払います。
お金は一括で支払っているのに、経費となるのは6年で按分した金額です。
このようなタイムラグは1つ1つは単純なことですが
これらの要素が複雑に組み合わさり利益と資金繰りが複雑になっていくのです。
儲かっている会社や、伸びている会社は売上を上げる前に大量に仕入れや外注先への支払が出てきます。
結果、この先行した支払の分売り上げの代金が入金されるまで一時的に資金繰りが悪化するのです。
当たり前のことのように見えますが、入金先・支払先のサイクルがバラバラになっていると
こうした問題が更に見えなくなってきます。
このようなことが原因で、儲かっているのに倒産する『 黒字倒産 』 が起こるのです。
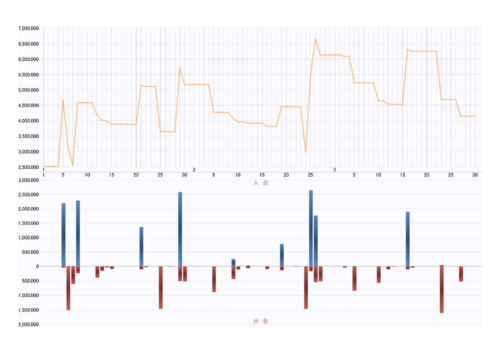
利益・経費等の損益と、お金の増減のズレに対する経営者の正しい姿勢とは
これに対する経営者の仕事として、
儲かる仕組み(黒字経営の仕組み)
お金が残る仕組み(入金サイト・支払サイトの管理や在庫管理)を築くことが重要です。
黒字経営は、
決算書(損益計算書や貸借対照表)を的確に読み取り自社の課題が、
粗利の改善にあるのか、
販売管理費などのコスト削減にあるのかを把握したうえで、しっかりと改善していくことで実現できます。
また、お金が残る仕組みは、社長自身が得意先と入金や支払のサイトについて交渉したり、在庫について社内での管理体制やルールを作ることで構築できます。
そして、どの会社も自社で作るべき必須の計画表である資金繰り表で
お金が残る仕組みが有効に機能しているか否かを見極めます。
ここで重要なことは、資金繰り表は、1円単位で合わせるものではなく、ある程度アバウトなものでかまわないということです。
なぜなら、資金繰り表は完璧に作ることが目的ではなく将来予測のための経営判断資料として使うものだからです。
この予測資料が仮に10円ズレていても会社は潰れませんし、経営判断を誤ることはありません。
資金繰り表は最低半年先を見通し、自社のお金の流れが見えるようにすることが目的です。
こうした理由から、この資金繰り表だけは外部に作成をアウトソースせずに、自社で作成することが重要であると考えます。
『 儲かって、お金が残る。』
このような理想的な状況を作り上げることも、社長の重要な仕事の一つです。
匠税理士事務所のキャッシュストック経営のためのサービス
私たちは、経営支援を通じてお客様の黒字率100%を目指します。
匠税理士事務所の経営支援やコンサルティングサービスなどはこちらから
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
ソフトウェアをスクラップ(除却)した場合(税務調査)Z7 (12/12/04)
ソフトウェアの技術革新は目まぐるしく、
最新だったものが、すぐに使い物にならなくなる。
こうしたことが、よく起こりえます。
Q:この使い物にならなくなったソフトウェアについて支払った経費はどうなるのでしょうか?
税務調査で注意点はあるのでしょうか?
ソフトウェアをスクラップ(除却)した場合の注意点
このようなソフトウェアのスクラップについて
税務調査上の争点を説明いたします。
ソフトウェアの処分について
税務調査での論点となる事項は
スクラップなどの事実の確認です。ソフトウェアは、外注さんや社内で開発を行ったり
他の会社から購入したりします。
このソフトウェアに支払ったお金は、
税法で定められた期間で按分計算を行います。
では、使えなくなったソフトウェアの経費は、
どうするのでしょうか?

税法(税金に関する法律)では、
ソフトウェアは固定資産というものになります。
この固定資産は、
固定資産を解体撤去、廃棄などした場合は、
その解体や廃棄をしたときに経費となります。
例外で実際にスクラップ(除却)してなくても
既に寿命で利用価値がないことが明らかなときは、
一定の金額を経費にすることが可能です。
ソフトウェア除却に関する税務上の取り扱い
法人税法基本通達 7-7-2の2
ソフトウェアに物理的な除却・廃棄・消滅等がない場合も
次のようにソフトウェアを今後事業に供しない事が
明らかな事実があるときは、
当該帳簿価額(処分見込額がある場合、控除後)を
当該事実が生じた年で損金算入できる。
(1)自社利用のソフトウエアについて
ソフトウェアによるデータ処理対象となる業務が廃止され
当該ソフトウェアを利用しなくなった事が明らかな場合ソフトウェア又はハードウェアやオペレーティングシステム・OS変更で
他のソフトウエアを利用することになり、
従来ソフトウェアを利用しないことが明らかな場合
(2)複写販売するための原本となるソフトウェア
新製品の出現、バージョンアップ等により、
今後、販売を行わないことが
りん議書・販売業者へ通知文書等で明らかな場合

つまり、上記(1)(2)に該当するときには、
帳簿ソフトウェアの価値から処分見込額を引いた残りを
(1)・(2)に該当することとなった時の経費とできる
というものです。【 これを除却損といいます。】
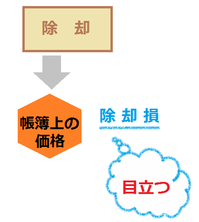
長くなりましたが、
それでは税務調査上のポイントや争点は、何でしょうか?
このスクラップの除却損は、
決算書上、特別損失というところに記載がされ税務署側も、目がとまる項目になります。
そのため、税務調査ではこの除却損について
その事実関係が【 重点的に 】確認されます。
ソフトウェア除却では、税務調査で何を用意すべき
このときポイントとなることは、上記の要件を
満たしていることを立証できるような稟議書、
証拠書類がきちんと揃っていて税務調査官を
納得させられるかが重要です。
匠税理士事務所では、IT業界に強い
世界4大会計事務所出身の税理士が証拠書類用意や
法解釈など税務をサポート致します。所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

税理士による税務調査対策サービス
税務調査とは、税法に従って経費にしているかを
税務調査官が確認していく作業となります。
(関連記事:税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間)
会社側としては、会社の税理士や会計士が、
上記のような税務上の取り扱いをきちんと理解し
税法に従って経費にしていることを、
客観証拠書類と法解釈で立証します。この税法の理解誤りや、会計処理に際して
客観証拠が不足すると税務調査でトラブルになります。
そして除却損が否認されてしまうと
追加税金の支払いやペナルティの税金がかかります。
除却損を経費とするときには、
税務調査も視野に入れ、慎重な検討が必要です。
担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?)
◇サービスページ
◇ITのお客様向けページ
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
ソフトウェア制作の株式会社など
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
アプリやゲームなど制作コスト確保など
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
IT業の会計経理や経営支援、節税対策など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で始めたソフトウェア制作を会社にする
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#ソフトウェア税務調査
#ソフトウェア経費
ホームページ制作費用は経費になる?経費と資産の経理処理や取扱<Z5> (12/12/02)
匠税理士事務所へ訪問ありがとうございます。
最近は、企業の営業ツールでホームページを
持たれている会社がほとんどだと思います。
ホームページは制作に費用がかかりますが、
この費用の取り扱いはどうなるのでしょうか?
という質問をよく頂きます。
そこで、このホームページ制作のために業者さんに
委託経費の取扱と税務調査の論点を紹介します。
ホームページ費用は広告宣伝で一時経費?
Q HP作成費用は広告宣伝費等で一時経費で大丈夫ですか?
まずは、ホームページ制作費の経理上で
原則的な取扱について記載します。
HP作成経費は、原則は公開時の経費にできます。
まずホームページの費用は会社のことや商品を
広告するために作られますので、広告宣伝費で支出時損金となります。
ホームページは事業内容や新商品のPR、
リクルート目的等で作成されることが一般的で、
その内容は頻繁に更新されるため、
制作費効果が1年以上及ぶことはまれだからです。

しかし、ホームページの中には高度なプログラムや
ソフトウェアも含めて開発されるものもあります。
この場合、プログラム・ソフトウェア部分の費用は、
無形固定資産で5年減価償却することになります。
制作費用内訳がプログラムやソフトウェアの部分と
それ以外の部分に区分できない場合は、
支出額全額を無形固定資産で5年減価償却することになります。
ホームページ費用の経理処理の注意点
しかし、HP費用の取り扱いで例外があります。
HPの内容が、長中期的な運用目的のため、
更新されず使用期間が、1年を超えるような場合は、
その制作費用は、使用期間に応じ均等償却します。
また、制作費に自社データベースアクセスが可能など
プログラムの作成費用が含まれるようなHPは、
その制作費用でプログラム作成費に該当する部分は、
5年で按分計算して経費とすることとなります。
(例:ショッピングページ⇒プログラミング言語で
データベースやネットワークにアクセスする仕組みがある。)

ホームページ費用の税務調査のポイントや注意点
税務調査では、
支払時に損金(経費)としたものの中に、
資産計上すべきものはないかが確認されます。
数百万円もするようなホームページ制作の中に、
プログラミングや長期目的のものがあれば
HP経費を税務調査で5年で経費にして下さい!と指摘されてしまうこともありえます。
不利な取り扱いを受けないためにも、
ホームページを制作する時は業者さんにしっかりと
請求書などに内訳を区分してもらいましょう。
このような時は、延滞税・過少申告加算税などの
罰金も科されてしまいますので
経理処理の際には特に注意しましょう。
ITに強い税理士がいる匠税理士事務所の詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

税理士やスタッフ・提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→匠税理士事務所の概要】

関連記事:
(税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間)
◇サービスページ
◇ITのお客様向けページ
執筆者・文責:税理士 水野智史
#ホームページ制作費用
#ホームページ経費
免責事項を確認の上、判断は自己責任でお願いします。
中小企業に大切な資金繰りの基礎知識と資金繰り表作成の必要性 (12/11/29)
中小企業にとって、資金繰りが重要であることはよく耳にします。
この資金繰りを簡単にいうと資金繰りとは、資金の動きを予測して把握することです。
資金繰り表の重要性
「月末までにこれだけのものを支払わなければならない。」
しかし、実際に月末にいくら残高があるのかは今日の残高に月末までの入金予定や、支払予定を考慮しないと計算することはできません。

それは、取引先などへの支払ができなければ会社は存続できないためです。
そこで月末にどれだけの余裕資金があるのかどれだけの不足があるのかを予測する必要があるのです。
これが資金繰り・収支計画です。
まだ、資金繰り表を作成したことがないという方も、これを機会に資金繰り表による財務管理をしてみることをお勧めします。
中小企業の資金繰り対策 (資金繰り表の作成目的)
Q: 毎月、月末の支払いの時期になると通帳の残高や売上の請求書を見ながら、お支払ができるかどうか確認しています。毎月経理をしていて心配で仕方ありません。どうしたら良いでしょうか
A: 資金繰り表は作成されているでしょうか?
月末に預金残高を見ながら行う経営では、本業に集中できません。
経営の安定化には、黒字などの利益をだすことだけではなくお金をしっかりと確保できることも非常に重要なことです。
利益と資金繰りは一致しませんので損益の計画以外に、必ず資金の計画も必要となります。
< 関連記事: 利益・経費などの損益とお金の増減は一致しない?
一度でも上記のようなことに該当をしたときには資金繰り表による資金計画を始める良い機会です。
まずは、簡単な資金繰り表を作成することからはじめてみましょう。
決まったフォーマットや難しい表を使わず自分が分かりやすいもので、あまり時間がかかりすぎないラフなものからはじめてください。
目的は、大まかな資金の計画をたててざっくりとした資金不足を把握することからはじめ
何が問題で、資金ショートするのかを把握し
改善案をたてて、改善することに真の目的があります。
資金繰り表を作ることが目的になってしまい細かい支払いまでチェックするようになると
本来の目的が見えなくなってしまいますので必ず本来の目的を忘れずに資金繰り表を作成しましょう。
< 関連記事: キャッシュフロー計算書と資金繰り表の作成目的の違い >
資金繰り表を用いた資金繰りの改善案や改善策
最後に、一番重要となるのは作成した資金繰り表をもとに、問題点の改善案、改善策を立てることです。
この資金繰り表で先の資金計画を作ることでいくらの案件までは受注できるという会社の体力も分かるようになり大型案件も安心して受注できます。
≪資金繰りの現場から 事例の紹介≫
毎月月末になると預金の残高が不足してしまい社長からお金を入れてもらう状況が度々発生するようになりました。
資金繰り表を作成してみると月末に全てのお支払が集中していることが判明。
また、売上代金の回収が担当者によってまちまちとなっており
一部の得意先では、得意先の資金の都合によって分割入金をしていたりすることが分かりました。
さらに、売上が末締めの翌々月末入金なのに対して
仕入代金の支払いが代引きが多くあり、これらが資金繰りを難しくさせていました。
A社では、月末の支払いを、5日や15日に変え、売上の回収の早期化、
代引きの支払い方法を変更し、資金繰り計画をしてみると資金は不足することなく順調に回ることが分かりました。
「当初は、銀行に行く手間を省こうと月末に全ての支払いを集中させていました。
ついお客さま優先で取引条件もうやむやになってしまっていました。
月末に残高がなくなる理由が分かり、安心しました。
こんな単純なことだったのですね。」
資金繰り表の作成段階で、このような意外な入金条件や支払い条件の 落とし穴に気が付くことがあります。
A社では、以降は、年間の資金繰り表を作成して、新たな事業に参入する場合、設備を購入する場合
キャッシュフロー(お金の流れ)を考えながらビジネスの戦略を立てています。
利益がでているということと・資金に余裕があるということ、両方がバランスよいことが、ビジネスにとっては大切です。
匠税理士事務所のキャッシュストック経営のためのサービス
匠税理士事務所では、資金繰り表の作成支援からキャッシュストック経営のためのコンサルティング、経営革新等支援機関として融資の支援サービスも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
◇経営お役立ち情報
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
世田谷区、目黒区や品川区の税理士なら匠税理士事務所 ...TOPページへ
ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の取扱(税務調査) (12/11/26)
ソフトウエアは、色々な問題に応えるため
プログラム修正の【VER UP】が行われます。
プログラム修正等のバージョンアップにかかった
経費で経理上、気を付けることはあるでしょうか?
ソフトウエアバージョンアップは修繕費?
このようなご質問を頂きましたので、
今回はプログラム修正等のバージョンアップ費用の
税務上(税金計算上)の取り扱いを記載致します。
法人税の計算では、この修正などが
①プログラムの機能上の障害の除去
(バグとりなど)
②現状の効用の維持等
そのプログラム修正などにかかった経費は
【 修繕費として一括 】で経費となります。

ソフトウエアVER UP費用が減価償却の場合
一方、そのプログラム修正などが、
・ 新たな機能を追加する、
・ 機能が向上する
といったものに該当するときは、
このプログラム修正などの経費は、減価償却といって
複数年で期間按分して経費とします。
つまり、一括で経費にはならず、
用途にあわせて税法上決めた年数で
ゆっくり期間按分し経費となります。
【 参考:耐用年数 】
ソフトウエア耐用年数は利用目的で異なります。
1「複写し販売する原本」又は「研究開発用」・・3年
2「その他のもの」・・5年
また、現在あるソフトウェア、購入したパッケージ仕様を
大幅変更し新たなソフトウエアを製作する費用も、
減価償却で期間按分し経費にすることになります。
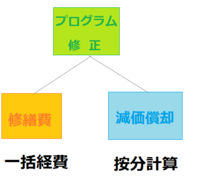
一括経費? 按分経費?
支払ったときに、全て経費?【修繕費】
期間案分して経費?【資本的支出】
この判断はその支払いによって、
そのソフトウェア本体の価値が増加し、
または使用できる年数が延長するか、あるいは、その事実はなく維持修繕(破損箇所直し・通常維持に必要な修正)かで判断します。
このようにプログラム修正等のバージョンアップ内容で、
損金(経費)になるタイミングが異なります。
ソフトウエアバージョンアップの税務調査
税務調査では、
支払ったときに経費となっているもので、そのソフトウェア本体の価値が増加し、
または使用できる年数が延長するような
「期間按分すべき経費」が混じってないか
という視点で確認作業が行われます。

仮に支払ったときに経費としたもので、
本来按分計算すべきものが見つかると、
税金の計算誤りがあるとして、計算をやり直して
差額の税金の支払いを求められるとともに、
税金が少なくかったこと罰金が課せられます。税務調査でトラブルにならないためにも、
プログラムバージョンアップに関する支払いは
その内容を吟味し慎重に取り扱うことが重要です。
弊所にはIT業界に強い税理士が所属しております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇ITのお客様向けページ

◇関連記事
◇サービスページ
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
ソフトウエアなどIT業で会社を作る
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
ソフトウエア制作のため建替資金の
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
ソフトウエアなどIT業の会計代行など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
IT業で独立開業し、会社に変更するための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#ソフトウエアバージョンアップ費用
#ソフトウエア税務調査
接待に係わるタクシー代の取扱(交際費のポイント)<Z2> (12/11/23)
新規案件受注などを目的とした接待のために、

得意先と会食を行うといったこともあるかと思います。
その際にうっかりとミスしがちなのが、
この接待のために得意先をお店まで招いたり、
得意先を自宅に送るために
支出したタクシー代です。
このタクシー代はうっかりと
旅費交通費として処理されがちですが、
税務上はこれら一連の行為を
一つとしてとらえますので、
このようなタクシー代は交際費となってしまいます。
税務上、交際費の処理には注意が必要です
旅費交通費も交際費も同じ費用だからいいじゃないか。
と思われる方もいらっしゃいますが、ここがポイントです。
旅費交通費は全額が費用となりますが、交際費となった場合には、下記のように取り扱われます。
中小企業の交際費の税務上の取り扱いに関する税制改正
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費について、
平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、
定額控除限度額(注)が年600万円から年800万円に引き上げられるとともに、
定額控除額に達するまでの金額の損金不算入額が0とされました。
(注)平成25年3月31日までに開始する事業年度については、
定額控除限度額に達するまでの金額について10%は損金の額に算入されません。
↓
・交際費が600万円以下の場合
交際費×10%
・交際費が600万円超の場合
(交際費-600万円)+600万円×10%
上記で計算した金額が経費となりません。
つまり最低10%は経費として認められないことになります。
*事業年度が12カ月に満たない場合、
「600万円×(事業年度の月数/12)」と読み変え計算します。
平成26年4月1日以後の開始する事業年度からは、
下記①か②の選択適用になります。
① 800万円を超える金額は損金にならない。→800万円までを損金とする。
② 飲食のために支出する費用の50%のみを損金算入する。
つまり飲食費が1,600万を超える会社は、②が有利となります。
②が有利になるような飲食はあまりありませんので、ほとんどの会社は、①の選択となりそうですね。
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
(1) 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額
(2) 800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
交際費の取り扱いと税務調査
交際費は資本金の額に応じて、税務上の取り扱いが異なります。
自社が税務上でどのような取り扱いになるのか確認しておくことが大切です。
税務調査では、接待に関連するもので交際費として処理せず、旅費交通費などになっていないかなど
他勘定交際費について確認作業が行われます。
税務調査において旅費交通費として処理していたタクシー代が、 交際費とされその一部を費用から除かれないように、接待に関連したタクシー代は、特に注意が必要です。
(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?)
匠税理士事務所の税務調査対策サービス
匠税理士事務所では、税務処理や税務調査での対策、税務調査を見越した準備などのコンサルティングに力を入れております。
◇サービスページ
会社の会計や経理、決算についても税理士 目黒 匠税理士事務所へご相談下さい。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
税務調査と売上等の収益の認識基準変更に関する注意点 (12/11/20)
売上などの収入の認識基準については、
【 税務調査 】で、よく争点となります。
収入の認識基準とは、【 いつのタイミング 】で、
売り上げに計上するかということです。
この売上の認識基準は、いつでも良いわけでなく
【 法人税法という税金の法律で定め 】があります。
今回はこの計上基準を取り上げます。(管理NoZ12)
税務上はいつ売上を収益として認識すべきか
【 商品の販売など棚卸資産の販売による収益の額は
引渡しがあった日の属する年の益金に算入する】
と税法では規定されております。

つまり会社は、原則、引き渡しの時点で、
売上として計上とする必要があります。
【 お金が入金された日ではありません。】
税務調査で最も厳しい検査事項は【 売上 】です。
つまり売上の認識ポイントは、
【 税務調査では争点となりやすい 】のです。
棚卸資産の引渡しの日が、いつであるかは、
出荷した日、相手方が検収した日、
相手方において使用できるようになった日、
検針等で販売数量を確認した日などがあります。

税金の法律では、その販売する棚卸資産の種類や
性質、販売の契約内容等によってその引渡し日で
合理的であると認められる日のうち、
【 法人が継続して 】収益計上を行うことする
日によるものとされています。
ここでポイントになるのは、
売上計上基準は、一度採用したら継続適用なのです。売上等の収益認識基準の変更は、税務調査でトラブルになるので要注意
実務では事業規模の拡大にともなって、
現在採用している売上の計上基準で、
対応できなくなることも起きてきます。
その際に売上など収益の計上基準の変更に
合理的な理由があることが重要になります。
仮に合理的な理由なしに変更をしてしまうと、
税務調査では利益調整のための変更であると
指摘を受け、変更が認められない事も起こります。
その場合には、修正申告になってしまい、
【 罰金 】が生じることもあります。
(関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの?)
このような税務調査で、トラブルにならないよう
初回の収益認識基準の選定は、慎重にしましょう。

また止むを得ず、売上計上基準を変更する場合は、
税務調査に備えしっかりと立証できる資料を
用意しておくことが重要です。
(関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは? )
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
2-1-1棚卸資産販売による収益の額は、
その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
2-1-2 2-1-1の場合において、
棚卸資産引渡し日がいつであるかは、
例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
匠税理士事務所の税務調査対策
匠税理士事務所は、売上などの収益認識に関する
アドバイスやお客様の会社を税務調査から守る
税務コンサルティングを行っております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇サービスページ
記事はお知らせの免責事項を確認下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#売上計上 #収益計上
総資産回転率・総資本回転率とは (12/11/17)
総資産回転率や総資本回転率などの用語について、
会社を経営されている社長さまは一度は耳にされたことがあると思います。
この総資産回転率は、総資本回転率と同じ内容で、
計算式にすると、
総資本回転率 = 売上高÷総資産(総資本)(総資産回転率)の算式で表されます。
総資本回転率(総資産回転率)とは、
事業に投資した総資本(総資産)が、
有効活用されて売上に結びついているか否かを
判定する経営分析の指標となります。
つまり、1年間の売上で資本が、
何度回収できるかが判定できます。

この資本には、資本金などの自己資本以外にも、
借入などの他人資本も含めて考えますので、
全部でいくらの資本を使って、その何倍の売上を
獲得することができたのかがわかります。
回転率が大きくなればなるほど、
少ない資産で大きな売上を獲得できることになり
効率よく運用できてることになります。
具体的には、総資本回転率(総資産回転率)が、
2であれば、365日÷2≒180となるので、
約半年で資本が回収できることになります。
自社の総資本(総資産)有効に活用できてるか
一度分析されるとよいかもしれませんね。

◇経営お役立ち情報
★総資本回転率(総資産回転率)以外にも、
貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)など会社の財務諸表の見方・読み方について、
全体的なことをお知りになりたい方はこちらからご確認下さい。
→貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)など会社の財務諸表の見方・読み方 へ
★その他の経営お役立ち情報については、こちらからご確認下さい。
総資産回転率・総資本回転率など経営財務分析
匠税理士事務所では経営支援や
財務分析に力を入れております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

担当所属税理士や提携専門家は、
こちらからご確認をお願いします。

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
独立開業資金の確保のための
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
株式会社や合同会社などを作るための
会社設立サービスはこちらから
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
総資産回転率・総資本回転率など経営支援や
会計経理・給与計算・決算代行など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で起業創業して会社に変更するための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。
その他の会社の会計や経理、決算、確定申告などの税金に関するご相談や、資金繰り・創業融資などにつきましては 税理士 目黒 匠税理士事務所へご相談下さい。
*:記事についてはお知らせの免責事項を確認して下さい。
執筆者・文責 税理士水野智史
#総資産回転率
#総資本回転率
経常利益率の計算方法:売上高と経常利益 (12/11/14)
社長同士の会話の中で、「借入金が増えちゃって、ケイツネ~がね~・・・・」
といったことを耳にしたことはないでしょうか?
売上高から経常利益までの計算方法
これは経常利益(けいじょうりえき)を、
このように呼んでいらっしゃる方もいるというわけなのですが、
経常利益は、売上高から売上原価を除いた売上総利益(粗利)から、
販売管理費といった会社を運営するために、通常必要とされる費用項目を除き、
この会社の本業の損益である営業利益から、
預金利息などの受取利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益など
営業外収益を加味し、
借入金などの支払利息や社債利息、有価証券売却損、為替差損を
除いた利益をいいます。
この経常利益は、借り入れ依存の会社では、
支払利息が多くなるので、経常利益が出づらくなる傾向があり、
貿易会社では、為替差損がこの区分に表示されるので、
これらのような借り入れ依存の会社や貿易会社の社長は、
特にこの営業外損益を加味した経常利益を注意する必要があります。
経常利益率の計算・算出方法
この経常利益について算式にすると、
経常利益=売上高 ― 売上原価 ― 販売管理費 + 営業外収益 - 営業外費用
となります。
分析指標としたものが、
売上高経常利益率です。
経常利益 ÷ 売上高 =売上高経常利益率
経常利益を分析することで、
借入金の影響など
本業以外の損益も把握することが
可能になります。
経常利益率や経常利益に対して経営者はどのように取り組むべきか
経常利益は上記の算式のように、特別損失・特別利益など臨時的な損益を除いて、
会社の経常的な損益の最終値として用います。
つまり、この経常損益が赤字の場合には、
会社の基本的な構造に問題があることを意味していますので、
問題を先送りにせずに、抜本的な改善策を経営者が打っていくことが求められます。
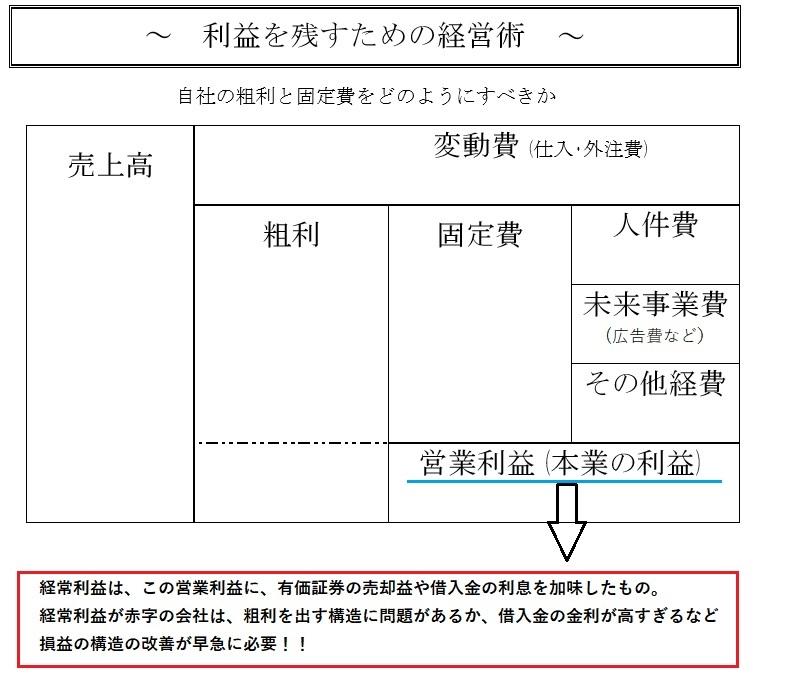
◇経営お役立ち情報
★【 関連記事: 売上総利益率と売上高と売上総利益(粗利)の計算式・計算方法 】
★税理士 水野智史の経営お役立ち情報・経営コンサルティング情報館はこちらから
税理士 水野智史の経営お役立ち情報・経営コンサルティング情報館
★貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)など>会社の財務諸表の見方・読み方についてはこちらから
匠税理士事務所の経営支援サービス
ここでは会社経営者を支援するための弊所サービスについてご紹介致します。サービス内容にご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談下さい。
◇コンサルティングサービス
その他の会社の会計や経理、決算、確定申告などの税金に関するご相談や、
資金繰り・創業融資などにつきましては 税理士 目黒 匠税理士事務所へご相談下さい。
免責事項→お知らせ
IT事業における特許権使用に伴う契約一時金と使用料の扱い (12/11/13)
スマートフォンの普及などに伴って、
アプリケーション・システムの開発などを行う
IT関連企業の方も増えてきています。
今回は、IT事業における特許権使用に伴う
【 契約一時金と使用料 】の扱いをまとめました。
IT事業での経費の取扱は特に注意が必要
ITは税務でも特殊な論点が多い業種です。
代表的なものとしてましては、
税務上のソフトウェア要件に該当する場合、
支払ったときに損金(経費)になるのでなく、
一度資産計上し税法の定める複数年で経費化の
減価償却(期間按分方法)で損金・経費にします。例えば、自社でアプリケーションを開発して、
一般使用者から使用料を徴収するモデルの場合
アプリケーション開発コストなどが該当します。

IT事業の特許権使用に伴う契約一時金・使用料
その他にもITは、特殊な技術を使うことが多く
これに伴い特許権の使用契約もよく出てきます。
特許権の使用契約では他社の保有する技術を
利用する代わり、契約一時金・特許使用料を
毎月払うという形式がよく見られます。
このような取引の取り扱いはどうなるのでしょう?
まず、契約一時金は工業所有権に準じ扱うため、
【 無形固定資産で減価償却 】を行います。

原則としてその耐用年数は8年となりますが、
特許技術の利用権の存続期間が耐用年数の8年に
満たない場合にはその存続期間をもとに
定額法にて減価償却を行うことになります。
また毎月の特許使用料は減価償却概念は出ません。
このようにITは業種的に複雑な論点が多くあり
金額も一取引あたり多額になりがちです。
匠税理士事務所によるIT事業支援
匠税理士事務所では、これまで大手のIT会社
PC製造会社の税務申告を担当したITに強い税理士が
IT分野の経理・決算・税務申告をサポートする
IT企業向けサービスをご用意しております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇IT事業を経営されているお客様向けサービスページ
匠税理士事務所では、世界4大会計事務所出身で
IT業界に強い税理士が税務会計を担当します。
所属税理士や提携先についてはWEBから
お問い合わせをお願い致します
執筆者・文責 税理士 水野智史
#IT特許権使用 #IT契約一時金
世田谷区での起業セミナー! 創業・開業をお考えの方へ (12/11/11)
匠税理士事務所では、
世田谷区で起業される方に向けて起業セミナーを
開催しております。

開催は毎月第4金曜日の夜に、
匠税理士事務所(自由が丘駅徒歩2分)にて
セミナーを行っております。
セミナー講師は、起業支援を実際の現場で
担当する税理士の水野が努めさせて頂き、
【 出来る限り分かりやすく、かつ実践的であること 】 をコンセプトにしております。
世田谷区で起業される方に向けた起業セミナーの内容詳細につきましては、
下記よりご確認を頂けましたら幸いです。
世田谷区での起業セミナー実績紹介
匠税理士事務所では世田谷区の産業振興公社で、
創業や起業・独立される方に向けた塾のセミナーの講師を担当させて頂いております。
世田谷区の産業振興公社セミナーは、
毎年30名程度の創業や起業を志されている方に向けて、
創業に必要な知識を
全20回程度ののセミナーを通じて解説しております。
匠税理士事務所では、
このうち起業・創業される方に向けた
税務・会計のセミナー講師を
担当させて頂いております。
これから起業や創業される方に対して、会社経営上、必要となる税務の基礎を
個人形態での創業と、法人形態での起業に分けて解説しております。
また、起業される際に、どのような組織形態があるのか、
LLP・LLC・NPOなど特殊な形態も合わせてセミナーにてご説明する予定です。
明日にでも使える知識であるよう、
起業セミナーは実践問題を踏まえた形式で、約2時間程度を予定しております。
起業支援専門の匠税理士事務所について
匠税理士事務所は、起業を専門とする会計事務所として、
これまで多くの起業創業支援やセミナーをご支援してまいりました。
私共の会計事務所は、男女の税理士2名が所属しており
スタッフも全員が30代という構成で
これから起業される社長様と同世代の構成にすることにより
より、気軽に、親密に何でもご相談できるようなパートナーとなる税理士を目指しております。
経験と知識豊かなスタッフによる高品質なサービスをお届けするため
サービスや人の質にこだわった税理士事務所の運営を行っております。
起業専門の税理士としてコンサルティングを取り入れた起業支援を行っております。
世田谷区でこれから起業される方
世田谷区で創業するにあたって創業融資を検討されている方
起業に強い税理士をお探しのお客さまは
下記のサービスをご覧いただければ幸いです。
今後も起業さる方の成功を支援するためのサービス充実を行っていく予定です。
世田谷区の起業セミナーで講師をお探しの方へ
匠税理士事務所が世田谷区の起業・創業される方に向けて
これまで数多くの起業セミナーを担当させて頂きました。
世田谷区で起業や創業・開業を支援するためのセミナー開催をお考えの方で、
起業セミナー講師をお探しの方は、お気軽にご相談下さい。
セミナー講師のご依頼などはこちらからご確認下さい。
匠税理士事務所の詳細につきましては、
世田谷の税理士事務所 匠税理士事務所TOPごご覧ください。
建物付き土地の購入と1年以内の建物の取壊の注意点(税務調査)Z6 (12/11/10)
会社を経営されていると、

建物付き土地を購入されることも
将来的には出てくると思います。
しかし、建物の取り壊しが
当初から予定されてる場合は、
建物の帳簿価額や取り壊し費用は
損金(経費)として認めず、【土地取得価額】に算入する必要があるため、
【想定外の税額】が発生することにも
つながるという落とし穴があります。
土地付き建物、税務調査のポイント
【 当初から土地を利用する目的 】で、
土地付き建物を取得しているか否かが、
税務署や国税の税務調査上での争点です。

たまたま、土地付き建物を取得したが、
突然の大震災などを理由に取得後一年以内に
取り壊し、立て直さなくてはいけなくなった場合は、
当初から土地利用目的で建物取得したわけでなく
この取り扱いを適用するのは適切ではありません。
また、土地付き建物の購入の建物の帳簿価額や
取り壊し費用は、金額的に大きな金額になるため、
税務調査でチェックポイントとなります。
(関連記事:税務調査とは何か、税務署が行う税務調査の対象会社や対象期間 )
税務調査で事実証明し、反論するには何が必要か
これらを踏まえ調査にしっかりと対応できるよう、
建物の取り壊しに至った経緯を説明できる資料や、これらを決議した議事録など保管しておき、
万全の態勢で税務調査に臨むようにしましょう。
( 関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点とは? )
<根拠>
法基通7-3-6
法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。
匠税理士事務所の税務調査対策サービス
匠税理士事務所は、世界4大事務所出身の税理士が、
税務調査対策や経営支援に力を入れております。
所属税理士やサービス詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 世田谷区の税理士は匠税理士事務所】

担当税理士や提携専門家詳細は、
こちらからご確認をお願いします。

◇サービスページ
会社の会計や経理、決算については、
上記法人のお客様向けサービスから確認下さい。
記事はお知らせの免責事項を確認して下さい。
執筆者・文責 税理士 水野智史
#建物付き土地の購入取り壊し #取り壊し税務調査
売上高と営業利益:営業利益率の計算方法・算出方法 (12/11/09)
・ 【 金融機関で融資を申し込んだところ、営業利益の推移について説明を求められた 】
・ 【 ~ の影響 ? A社 前年比営業利益20%減~ の新聞見出し など 】
営業利益は会社の決算書を分析する上で、とても重要な指標です。
営業利益は何故重要な指標なのか
営業利益は、なぜ重要なのでしょうか。
それは、売上高から売上原価を除いた売上総利益(粗利)から、
販売管理費といった会社を運営するために、通常必要とされる費用項目を除いた利益であり、
いうなれば会社が本業の商取引からどれだけの利益を
出すことができたかが分かる指標だから重要なのです。
ちなみに販売管理費の代表的な費用項目としては、以下のような費用が挙げられます。

役員報酬・給料・賞与・退職金 (人件費など)
福利厚生費 (社員への結婚祝いなど)
法定福利費 (社会保険料など)
会議費 (打ち合わせ費用など)
交際費 (得意先への接待費など)
旅費交通費 (タクシー代や電車代など)
保険料 (会社で入っている保険料)
水道光熱費 (水道・電気・ガス代など)
減価償却費 (建物などの価値の減少分)
広告宣伝費 など
営業利益 = 売上高 ― 売上原価 ― 販売管理費と表せます。
営業利益が赤字の会社 = 粗利 < 固定費 となり、粗利が固定費に負けている状態なので、
粗利(売上と原価)を見直すのか、固定費(会社維持費)を見直すのかという話になります。
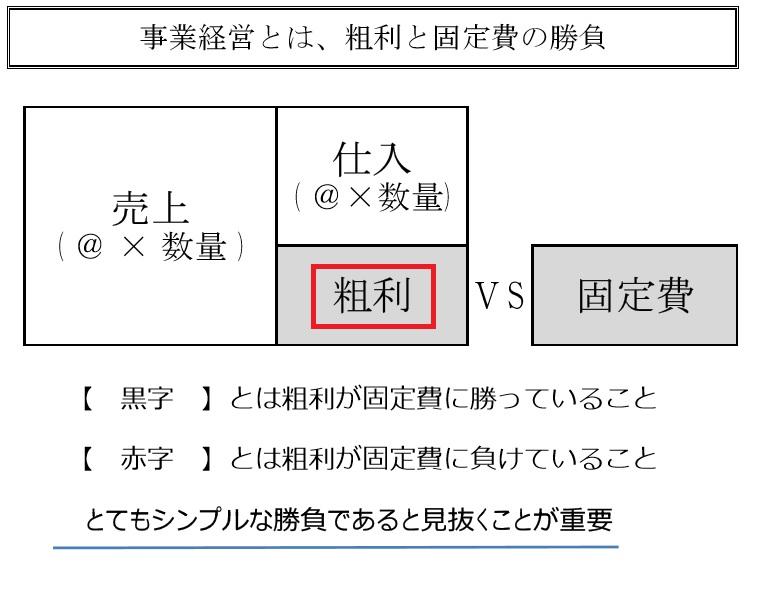
営業利益率の計算・算出方法について
売上高に占める営業利益の割合を、分析指標としたものが売上高営業利益率です。
営業利益 ÷ 売上高 =売上高営業利益率
現在のような企業間の競争が厳しい時代では、
売上高や売上総利益(粗利)を伸ばすのが難しい状況なので、
会社の余分な経費を削り込むことで、営業利益を出している企業が多く見られます。
このように営業利益とは、会社の純粋なモノやサービスを介して稼ぐ力と、
会社の内部をいかに適切に管理出来ているのかが、数字となって表れるため経営者の能力が、
もっとも分かる指標です。
営業利益が赤字ということにならないように、売上総利益(粗利)と営業利益を
しっかりと意識した経営を心掛けましょう。
このように粗利(売上と原価)と固定費(会社維持費)に高い意識をもって経営を行っていると
金融機関の融資面談などの場でも、あらゆる質問に的確に回答できるようになります。
固定費は取り組む意欲さえあれば、削減は容易です。
そして一度削減すれば、油断をしなければ増えていきませんので、
まずは守り(固定費の見直し)、そして攻め(粗利の見直し)が理想な展開です。
営業利益以外の決算書の読み方情報
営業利益以外にも、貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)など会社の財務諸表の見方・読み方について全体的なことをお知りになりたい方はこちらからご確認下さい。
その他の経営お役立ち情報やコンサルティング情報につきましては、
こちらよりご確認をお願い致します。
◇経営お役立ち情報

売上や営業利益の改善など会社経営支援サービス
匠税理士事務所では、会社の黒字化支援のコンサルティングに力を入れております。
匠税理士事務所の起業・経営支援サービス
◇コンサルティングサービス
◇経営お役立ち情報
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
目黒区の税理士なら匠税理士事務所...TOPページへ
記事についてはお知らせの免責事項を確認して下さい。
売上総利益率と売上高と売上総利益(粗利)の計算式・計算方法 (12/11/07)
今回は会社の売上総利益(粗利)を紹介します。
売上から仕入などの原価を除いた利益が、
これが売上総利益(粗利)です。
売上高 - 売上原価 = 売上総利益
そして、売上高に占める売上総利益の割合、
これが売上総利益率(粗利率)です。
売上総利益 ÷ 売上高 =売上総利益率

売上総利益率はモノやサービスを販売して、
単純にいくら稼いだのかを示す利益率で、
会社のモノやサービスで稼ぐ力の指標です。
つまり、会社のサービス・商品がどれだけ魅力あるかが分かる大切な指標なのです。
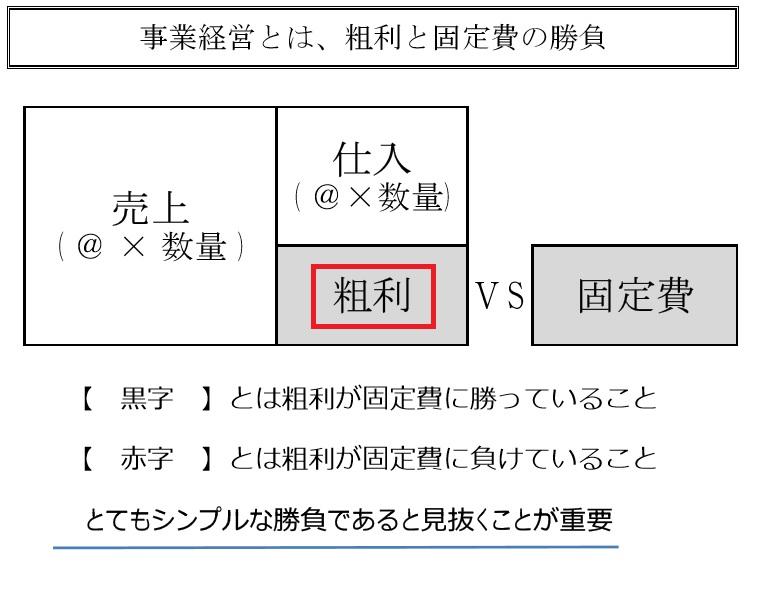
売上総利益率の重要性について
稼ぐ力を知る売上総利益率は重要な値です。
「 デフレで価格競争が激しく粗利率が下がった。」
「 年々、特定の商品の粗利率が下がっている。」
などというのは、
まさしくこの会社の純粋なモノやサービスを介して稼ぐ力が下がってしまったことを意味します。
それでは売上総利益(粗利)の変動は何故生じ、
これらが下がることで何が問題なのでしょうか。
売上総利益(粗利)が下がる原因
売上総利益(粗利)が下がる原因としては、
1. 値引きによる売価の下落
2. 販売数や来客数を落としている
3. 特定の商品や得意先の売価設定に誤りがある
このようなことから起こるためです。

会社はモノやサービスを売って利益を稼ぐことを
目的として設立されていますので、
利益源泉となる売上総利益(粗利)が下がるのは、
会社にとって死活問題で、売上総利益(粗利)を
取り巻く経済環境変化を的確に読取り、
しっかりと対応していくことが重要です。
売上総利益率や売上総利益(粗利)に経営者はどのように取り組むべきか
経営者であれば、
売上総利益率(粗利率)1%の上がり下がりに
目を光らせ売上総利益率(粗利率)変化が
会社の最終利益にどの程度影響を及ぼすのか
すぐに計算できなければなりません。

また、商品別に売上総利益率(粗利率)をおさえて
どの商品が会社の利益に大きく貢献しているのか、
競争力があるのかを把握することができ、
【 注力すべき商品は何かが分かります。】。
しかし、売上総利益率(粗利率)が低い商品が全て悪いわけではありません。
粗利が低い商品をもとに粗利が高い商品が売れるのであれば高い商品と低い商品とを一組でとらえるべきです。
ただし、戦略がなく売上高や得意先数だけを追うような粗利率の低い商品販売や値引販売は注意です。
会社はモノやサービス販売で利益を稼ぐことが目的としているからです。
経営者は、売上総利益率(粗利率)や粗利を確認し、市場や商品、得意先や仕入先に変化がないか把握し、お客さま・現場を見る行動力が重要です。
匠税理士事務所経営支援サービス
弊所では会計の力を活用した経営支援で
関与先黒字率100%を目指しております。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
株式会社や合同会社などを作る
会社設立サービスはこちらから
【 → 世田谷区の税理士による会社設立】
独立開業時の資金調達など
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
売上総利益・粗利確保の経営支援など
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人で起業して株式会社に変更する
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
◇経営お役立ち情報
○経営者にとっての粗利(売上総利益)を左右する値決めの重要性について記載したものはこちらから
○建設業の方に向けた粗利率・売上総利益率改善のポイント
★建設業・建築業で粗利率はどのくらいが平均?経営改善ポイント
○貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)など会社の財務諸表の見方・読み方はこちらから
★貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)など会社の財務諸表の見方・読み方
○税理士 水野智史の経営お役立ち情報・経営コンサルティング情報館はこちらから
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
税理士 世田谷の匠税理士事務所...TOPページへ
お知らせ...記事についての免責事項
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#売上総利益率と売上高 #売上総利益の計算式計算方法 #売上総利益率 #粗利計算方法 #粗利計算式 #売上総利益計算式 #売上総利益計算方法
BSやPLなど会社の決算書や財務諸表の読み方や見方 (12/11/05)
会社経営や、金融機関との打ち合わせで、
決算書の話題になることも多いと思います。
しかし、簿記は勉強してこなかったので、
何となく会計や経理にはアレルギーが・・・・
このような方も多いのではないでしょうか。
今回は経営セミナーの際に評判でしたテキストを基に
分かりやすく貸借対照表(BS)と損益計算書(PL)の読み方を記載します。

BSとは、会社の決算書・財務諸表のわかりやすい読み方や見方
---貸借対照表(BS)とは?--
まず、貸借対照表のBSは、Balance Sheetの略です。
貸借対照表BSの目的は、会社の財産状態を明らかにすることです。貸借対照表BSの構成要素は、大きく分けて資産・負債・資本の3部で構成されます。
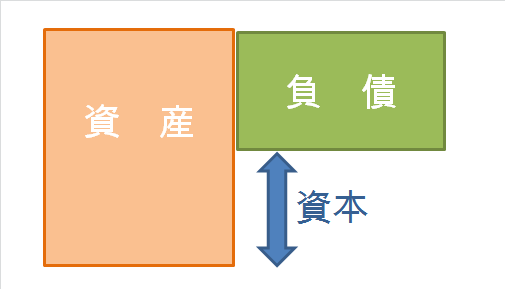
1 資産の部
現金や預金、得意先の売掛金(債権)などです。
イメージとして貯金や車や家などの会社がもっている財産と考えてみてください。
2 負債の部
借金や仕入先などへの買掛金などです。ようするに借金です。銀行からの借入以外にも、
クレジットカードや、つけ払のイメージです。
3 資本の部
会社設立の際に払い込んだ資本金に、これまで獲得した利益(損失)の累積を加味したものです。
要は 資産 - 負債 をひいた残り、つまり、会社の本当の財力です。
この資本の部は、銀行からの融資のとき、新規取引開始時の与信調査でみられます。
この資本の部が、プラスであることが望ましく、
この資本の部がマイナスになってしまった状態が、債務超過です。
貸借対照表(BS)が債務超過になってしまった場合、
融資ではマイナスの評価になってしまいますので、
経営者はこの資本の部が債務超過になってないか
どうか気を付ける必要があります。

そしてこの債務超過を解消する方法は、
大きく①利益を出すか、②増資かの二つになります。
中小企業で増資は、基での資金確保が難しいので
現実的には利益を出し、しっかり会社に残しておく(内部留保)に努めるのが得策です。
また債務超過以外にも、貸借対照表(BS)の
資本の部では自己資本比率も重要です。
入札などの応募要件であったり、融資の要件であったりと様々な場面で確認されますので、
自己資本比率についてはしっかりと確認し、
自己資本比率を上げるために努力しましょう。
中小企業は自己資本比率30%が一般的な目安です。
(関連記事→自己資本比率の重要性)
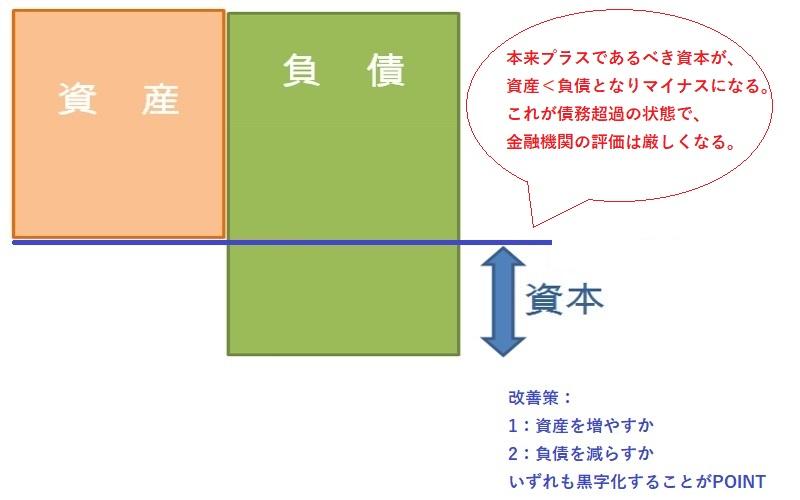
更に貸借対照表(BS)の資本の部では、上記の他にも繰越利益剰余金という重要な項目があります。
繰越利益剰余金は、過去利益や赤字の累積であり、ここを読むことで、
その会社の財務的な力、つまり、その会社がこれまでどれだけの利益を
出してきた会社かどうかが分かります。
(会社を設立されてからこれまでの利益の累積は、利益剰余金 で確認できます。)
黒字の会社の貸借対照表(BS)は当然ですが、
繰越利益剰余金はプラスとなります。
しかし、これまでずっと赤字の会社の貸借対照表(BS)繰越利益剰余金の項目はマイナスとなります。
新規で取引する場合、この資本の部を読むとその会社状態や歴史が分かるというのはそのためです。
貸借対照表の読み方とBSを活用した財務分析
貸借対照表(BS)の分析では、その企業の安全性について読むことが可能になります。

◇貸借対照表でできないこと
貸借対照表でできることは、
月末や決算など一時点の財産や借金の状態が分かることでしたが、
貸借対照表でできないことは、
月末や決算などの一時点の財産や借金の状態しか把握できない。こちらが弱点となります。
次は損益状況を示す、損益計算書(PL)の読み方についての説明に移ります。
損益計算書(PL)とは、会社の決算書・財務諸表の読み方
---損益計算書とは?-------------
次に損益計算書・PLの読み方について記載します。
PLは、Profit and Loss statementの略です。
損益計算書・PLの最大の目的は、【 会社の経営成績(儲け)】を明らかにすること
そのため、会社が1年間でどれだけの利益をあげたかを各区分に分けて報告することになります。
一般的に次のような項目を上から下のとおりの順番で記載します。
【 損益計算書・PLの形式 】
Ⅰ売上高・・・本業である事業活動で獲得した収入
Ⅱ売上原価・・材料仕入などの費用
【Ⅰ-Ⅱ売上総利益(粗利益) 】
Ⅲ販売費及び一般管理費
売上を獲得するためにかかった原価以外費用
【Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ営業利益 】
Ⅳ営業外収益・・本業以外で獲得した収益
Ⅴ営業外費用・・本業以外での活動でかかった費用
【Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ+Ⅳ-Ⅴ 経常利益 】
Ⅵ特別利益・・臨時かつ巨額に生じた収益
Ⅶ特別損失・・臨時かつ巨額に生じた費用損失
【 税引前当期純利益 】
法人税、住民税及び事業税額(つまり税金)
【 当期純利益 】
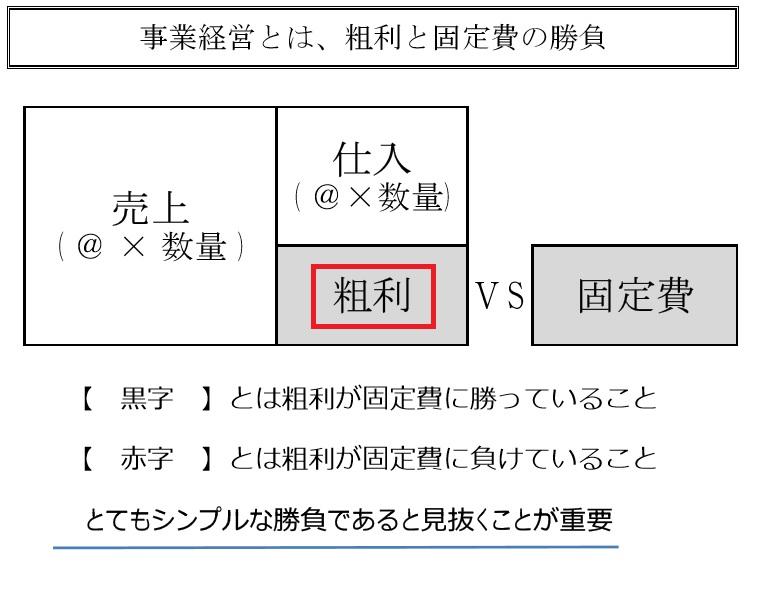
~利益というような専門用語が沢山でてきますが
大きくまとめると以下のような性格です。
損益計算書(PL)の売上総利益(粗利益)とは、売上から原価(仕入)を除いた利益です。
売上総利益が多ければ多いほど仕入に付加価値を付けて売上をあげていることになります。
 営業利益 *2
営業利益 *2
営業利益とは、売上総利益から人件費や家賃などの
会社を維持するのに必要な経費を除いた利益です。
本業で幾ら利益を出しているか示していますので、
金融機関はこの営業利益を重点的に見ます。
赤字が続いているような会社は、営業利益で黒字にする必要があります。

 経常利益*3
経常利益*3
経常利益は、利息・配当金など本業以外の収入と
借入金の利息、保証料などの本業以外の費用を加味した利益をいいます。
 税引前当期純利益*4
税引前当期純利益*4
税前利益は突発的な利益や損失を引いた利益です。
ここで税金の計算を行う利益です。
 当期純利益*5
当期純利益*5
これで最後となります。沢山ありましたね。
当期純利益は、税金を除いた最終利益です。
上場をしている会社であったり、
第三者(取引先信用調査)に決算を開示のときは
ここを見ます。
損益計算書PLの利益はそれぞれ内容が違います。
損益計算書(PL)の読み方や中身を理解して、
数字に基づく経営から黒字経営を目指しましょう。

これらの力をうまくバランスさせるのが、
会計の最終的な役割です。
匠税理士事務所の経営支援サービス
弊所では会計の力を活用した経営支援に力を入れ
関与先黒字率100%を目指しております。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】
税理士や提携専門家など事務所概要はこちら
【→自由が丘の匠税理士事務所の概要 】

起業家向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
個人の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】

上記外にも経営のお役立ち情報を収録しております。
匠税理士事務所のお役立ち情報・経営コンサルティング情報館はこちらから ↓
◇経営お役立ち情報
会社設立・創業融資など起業支援と法人化
匠税理士事務所では会社設立・創業融資など
起業支援や法人化に力を入れております。
各サービスラインは以下でご確認下さい。
会社設立時など起業資金確保のための
創業融資サービスはこちらから
【 → 税理士による創業融資 】
これから起業創業される方に向けた
会社設立サービスはこちらから
【 → 目黒区の税理士による会社設立】
BSやPLなど決算書や財務諸表の読み方教室や
会計経理の代行から経営サポートなど
起業・創業支援はこちらから確認下さい。
【 → 東京都で税理士の起業支援】
個人事業主から会社に変更するための
法人化・法人成りはこちらでご確認下さい。
【 → 東京都で税理士の法人化・法人成り】
建設業許可申請はこちらにて確認下さい。
バランスシートなど決算書・財務諸表を活用した経営支援サービス
また、起業される方や、会社経営者の方に向けたサービスラインの詳細は下記よりご確認下さい。
◇コンサルティングサービス
◇その他のサービス
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
世田谷区の税理士なら匠税理士事務所...TOPページへ
【 関連記事 】
( 売掛金などの売上債権回転率・売上債権回転期間の計算式 )
( 棚卸商品など在庫回転期間、在庫回転率の計算式と計算方法 )
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#BS #PL #決算書 #財務諸表 #貸借対照表 #損益計算書 #PL読み方 #BS読み方 #PL見方 #BS見方 #決算書読み方 #決算書見方 #財務諸表読み方 #財務諸表見方 #貸借対照表読み方 #貸借対照表見方 #損益計算書読み方 #損益計算書見方 #試算表読み方 #試算表見方 #TB読み方 #TB見方
役員貸付金、社長貸付金やその利率や利息に対する税務調査Z3 (12/10/26)
会社を経営してきて、役員給与以外に引出をしてしまい、
社長や役員への貸付金が発生してしまった・・・・
しかし、会社内には
社長や役員に対する
貸付金や利率、利息に関する資料が
いらっしゃるかと思います。
このような場合には、
社長や役員への賞与とみなされないように、
社長や役員と、
会社との間での金銭消費貸借契約書を作成し、
できれば社長や役員への
貸付金に対する取締役会の議事録や
返済予定表を残すことが大切です。
社長貸付金や役員貸付金に関する税務調査でのトラブル
社長や役員への貸し付けという事実を残して置かなければ、
役員への賞与という指摘を受ける可能性があり、
役員への賞与は経費とならないばかりではなく、
源泉所得税を追加で納付することになってしまいます。
( 関連記事:税務調査での修正申告、罰金はどんな種類があるの? )
これらのため、社長や役員への貸付金については、社長貸付金、役員貸付金であるという事実をしっかりと証明する資料(契約書や返済予定表)を用意することはとても重要です。
社長貸付金や役員貸付金の利率や利息も税務調査では重要です。
また、下記のような例外を除いて、社長貸付金や役員貸付金は、
他人にお金を貸した場合と同様に、市中金利などの相当な利息を計上しなければいけないという点もポイントです。
税務調査では
( 関連記事:今すぐ、会社でできる、税務調査の準備・注意点 )
社長貸付金や役員貸付金に対する税務調査対策
社長貸付金、役員貸付金となっても、
税金がかかってきますし、
役員賞与になってしまうと、
更に大きな金額の税金(源泉所得税)が
出てきます。
どちらにしてもあまり会社にとっては
良いことではありませんので、
やはり役員給与以外の引出がなくてもいいように、
しっかりと役員給与の金額を
決めておくことが最重要です。
<税法が定める特別な場合>
所基通36-28
使用者が役員又は使用人に対し金銭を無利息又は36-49により評価した利息相当額に満たない利息で貸し付けたことにより、その貸付けを受けた役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げるものについては、課税しなくて差し支えない。(平11課法8-11、課所4-23改正)
(1) 災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し、その資金に充てるために貸し付けた金額につき、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益
(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき、使用者における借入金の平均調達金利(例えば、当該使用者が貸付けを行った日の前年中又は前事業年度中における借入金の平均残高に占める当該前年中又は前事業年度中に支払うべき利息の額の割合など合理的に計算された利率をいう。)など合理的と認められる貸付利率を定め、これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益
(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で、その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には、その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円(使用者が事業年度を有する法人である場合において、その事業年度が1年に満たないときは、5,000円にその事業年度の月数(1月未満の端数は1月に切り上げた月数)を乗じて12で除して計算した金額)以下のもの
匠税理士事務所の税務調査対策コンサルティング
匠税理士事務所では、
◇サービスページ
確定申告や起業は 税理士 世田谷 匠税理士事務所へ
記事についてはお知らせの免責事項を確認し、専門家にご相談ください。
最終更新日:平成26年1月24日
仕入や経費の帳簿記載事項と省略項目 (12/10/05)
匠税理士事務所のホームぺ―ジをご覧いただきありがとうございます。
今回は、個人事業主の帳簿の作成について記載を致します。
個人事業主で帳簿の作成義務がある方は、
その仕入れや経費について
一定の事項を記載した帳簿を作成しなければなりません。
この帳簿の記載事項としては原則
①取引の年月日
②相手方の名称
③金額
④取引の内容
を帳簿に記載します。
原則として、例えば領収書であれば一件一件
仕入れであれば、一取引毎に記帳すべきものです。
また、基本的には商品を仕入れた都度記載するものです。
しかし、実務上は、下記のような項目については
簡易な方法での帳簿作成が認められています。
この制度を理解して
賢く帳簿作成をしましょう。
<仕入について>
(1) 少額な現金仕入→日々の合計金額のみを一括記載
(2) 請求書等により内容を確認できる取引→日々の合計金額のみを一括記載
(3) 掛仕入(請求書等により内容を確認できるもの)→日々の記載を省略、現実に代金を支払つた時に現金仕入として記載。(年末に買掛金を記載)
<経費について>
(1) 少額な経費→その項目ごと、日々の合計金額のみ一括記載
(2) 現実に出金した時に記載。(年末に未払を記載)
なお帳簿の作成には、複式簿記による帳簿作成で貸借対照表まで作成できるときには65万円の控除が認められます。
しかし、簡易な帳簿によって帳簿を作成しているときには10万円の控除のみ
受けられることになります。
いずれにおいても帳簿の作成と
青色申告の承認申請が必要となりますので
注意しましょう。
<用語解説>
※「複式簿記」→損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式。
※損益計算書→企業のある一定期間における収益と費用の状態を表すために、複式簿記により作成されるもの。その企業の経営成績に関する情報が集約されているもの。
P/L と略称されることがある。
※貸借対照表→企業のある一定時点における資産、負債、純資産の状態を表すために 複式簿記と呼ばれる手法によりに作成される。その企業の経営状態に関する情報が集約されているもの。
B/S と略称されることがある
★書類を送るだけの簡単経理で青色申告65万の節税
確定申告や起業に関するお悩みは、匠税理士事務所にお任せください!
税理士 世田谷 なら匠税理士事務所 TOPページへ
世田谷・目黒・品川など東京都の全域に対応
※記事に関するご質問は受け付ておりません。
記事についてはお知らせの免責事項を確認し、専門家にご相談ください。
個人事業を株式会社へ 法人化(法人成り)の情報館 (12/09/18)
匠税理士事務所では、世田谷区や目黒区、品川区、大田区などの東京都の全域において個人事業主の方の法人化に力を入れております。
法人化は個人から法人への財産引き継ぎに伴う譲渡税額の算定や事業税の見込み計算、事業廃止後の必要経費算入など税務申告において、特殊な論点が多いのが特徴ですが、匠税理士事務所にはこれまで毎年多数の法人化を担当させて頂くことを通じて、法人化に関して多くのノウハウがございます。
これらの法人化のノウハウを通じて、お客様の負担をできる限り減らして、スムーズな法人化の実行を常に心がけております。
匠税理士事務所の法人化支援サービスの詳細について、ご覧になりたい方は下記のリンク先よりご確認いただけましたら幸いです。
法人化支援サービス の詳細はこちらから
法人化(法人成り)の情報館
これまでのノウハウを活用した法人化(法人成りの)情報館をまとめております。お役に立てば幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
法人化無料相談会について
個人事業を株式会社にする法人化に関するお悩みなどは、中小企業や個人事業主を専門とする会計事務所匠税理士事務所にお任せください!
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。

法人化の無料相談会のご予約はお手数ではございますが、下記よりお願い致します。
1.無料お問い合わせフォームかお電話にてご相談内容とご予約をお願いいたします。
2.決算書など必要な資料をお持ちいただき、ご来所ください。
※お客様へお願い
いただきました個人情報はお客様との打ち合わせ後削除し、勧誘の連絡等一切致しません。
無料相談でお答えできない事項がございますことをご理解いただけましたら幸いです。
個人事業から会社にする法人化や法人成りは、色々ありますが、大きく分けて次のようなものが挙げられます。
法人化や法人成りについては、専門家に依頼してスムーズに手続きされ本業に集中することをお勧めします。
税理士 世田谷なら匠税理士事務所 TOPページへ
(事務所までのアクセスや税理士・スタッフの詳細などもこちらからご確認下さい。)
創業融資のお役立ち情報バックナンバー<資金調達> (12/09/15)
起業と黒字戦略の匠税理士事務所 > サービス起業>創業融資支援サービス>創業融資情報バックナンバー
この度は、匠税理士事務所のホームページへご訪問頂きまして、ありがとうございます。
匠税理士事務所では、黒字戦略や財務支援(会社に利益をお金を残す仕組みづくり)に定評のある事務所です。
起業などの会社設立後は、お金利益とも不安定になりやすい時期です。
そこで安定した強い会社をつくるため起業後のお金(創業融資)の支援も力を入れております。
会社を設立して多くの方が利用される創業融資ですが、ご自身でやると中々大変なものです。
創業融資につきまして、お客様からよくいただくご質問などをまとめました。
みなさまのお役に立てれば幸いです
創業融資サービスの詳細は、創業融資サービス 世田谷区・目黒区・品川区などに対応 へ。
会社設立後の創業融資についてのお役立ち情報バックナンバー
第1回 起業家が苦労すること第一位は資金調達 創業融資
すでに起業された社長さまの声から創業融資について、これから準備すべき点は何かをまとめてあります。
第2回 起業・開業の貯金はいくらまで貯める、用意するべき?
会社員のうちにしっかりと貯蓄しておきたい、起業に必要なお金とは?どれくらいなのか。
第3回 起業に必要な開業資金の計算方法と計画。融資との関係
事業に必要な開業資金は、具体的にどうやって計算したらよいか?
第4回 創業融資を申し込むために必要な書類とは(日本政策金融公庫)
創業融資に必要な書類には、どんなものがあり、その記載のポイントはどんな点か
第5回 起業や創業融資での創業計画書の作成のポイント
事業計画書が完成したら、完成した事業計画書の見直しをしたいポイントをまとめております。
第6回 日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)などの融資審査・面談のポイント
仕上がった事業計画書をもとに融資の面談を受ける場合には、どのような点に気をつけたらよいのでしょうか。
第7回 創業融資でやってはいけないこと・注意点や服装のNG集
創業融資の面談で、やってはいけないNG集をまとめております。
第8回 保証人がいない、保証人なしでの融資は受けられる?
融資の多くは、保証人(担保)が必要になります。保証人がいないときにはどうしたらよいのでしょうか。
第9回 認定支援機関による創業融資支援(日本政策金融公庫)
経営革新等支援機関が取り扱う融資にはどのような制度があるのでしょうか。
第10回 創業期の資金調達 日本政策金融公庫と制度融資の違い
創業期にはどのような融資制度を検討することができるのかをまとめたものです。
第11回 創業融資では何に気をつけるべき?融資担当者の視点から
創業期にはどのような融資制度を検討することができるのかをまとめたものです。
第12回 目黒区の制度融資や日本政策金融公庫 起業時のお金はどうする?
目黒区の創業者向け融資であれば、地方自治体による融資制度も検討ができます...
第13回 起業や創業の味方!日本政策金融公庫とはどんな組織
日本政策金融公庫、名前は聞いたことがあるけど、どこにある銀行?このように...
第14回 日本政策金融公庫の創業融資とは?成功のため6つのポイント
日本政策金融公庫とは、日本政府が100%出資の政府系金融機関です。こうしたことから...
記事については免責事項をご確認下さい。
匠税理士事務所の創業融資や会社設立サービス
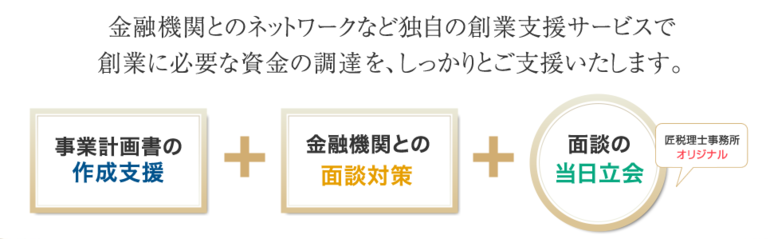
匠税理士事務所では、創業における今後の展開をヒアリングさせて頂き、そこから事業計画書の作成サポートや、金融機関との融資における面談の事前練習と、金融機関担当者との面談当日の立会いなどまでサポートする創業融資支援サービスをご用意しております。
起業支援サービス一覧
また、創業融資と一緒に会社設立をご検討されている場合には、会社の設立と会社設立後の経理も丸ごとバックアップする会社設立代行サービスをご用意しております。会社設立代行サービスの詳細はこちらからご確認下さい。
世田谷・目黒・品川の会社設立の代行...会社を作るお客様向けの会社の設立・経理や税金、経営のサービス。
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
給与計算サービス...給与計算の代行や、社会保険の加入手続き、人事労務のサポートサービス。
助成金サービス...正社員化や社員教育についての助成金代行とコンサルティングサービス。
法人のお客様向けサービス...黒字戦略や財務強化などのオリジナルサービスのご紹介
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。皆さまからのご連絡をお待ちしております。
税理士 世田谷なら匠税理士事務所 TOPページへ
給与計算や社会保険のお役立ち情報 バックナンバー (12/09/05)
初めて人を採用される方に向けた社会保険の基礎知識です。
給与計算の仕組みや、社会保障の役割、手続きなどについてまとめたもののバックナンバーとなります。
◇サービスページはこちら→
社会保険や給与計算TOPICS 目次
これまでのノウハウを活用した社会保険や給与計算の情報をまとめております。お役に立てば幸いです。
記事についてはお知らせの免責事項をご確認下さい。
◇TOPページはこちら→税理士 世田谷なら匠税理士事務所
記事につきましては免責事項をご確認ください。
免責事項
匠税理士事務所では、ウェブサイト(https://takumi-tax.jp/)(以下、「当サイト」と言う。)に掲載する情報について細心の注意を払い掲載を行っておりますが、その内容の完全性・正確性・有用性・安全性等については、いかなる保証を行うものでもありません。また当サイトに掲載されている情報は、匠税理士事務所の発信する情報の一部であって、その全てを網羅するものではありません。掲載情報に基づいて利用者が下した判断および起こした行動によりいかなる結果が発生した場合においても、匠税理士事務所はその責を負いません。 当サイト上の全ての掲載情報は、あくまでも掲載時点における情報であり、当サイト上の全ての掲載情報について、事前に予告することなく名称や内容等の改変を行ったり、削除することがあります。また、当サイト内のコンテンツは法令に改正が入った際などにおいても、最新の法令への変更は行いません。当サイトのコンテンツの情報を利用し起こりうる損害その他一切の影響や利用者の皆様に発生する損害について、匠税理士事務所はその責を負いませんのであらかじめご了承ください。
法人化・法人成りと資産の引き継ぎ (12/08/27)
起業と黒字化の匠税理士事務所 > サービス個人>法人化・法人成りの支援>法人化資産の引き継ぎ
法人化のサービスの詳細は、法人化・法人成り支援サービス よりご覧いただけます。
法人化・法人成りで気を付けたい資産引き継ぎのポイント

個人でこれまで事業をしてきたが、株式会社などの法人にしたい。
このようにお考えになる方も多いと思います。
法人化・法人成りの際には、数多くの論点がございますが、
その中でも個人でこれまで使用していた事業用の個人の財産を
法人へ引き継ぐということが大きな論点として挙がります。
そこで今回は、個人から法人への資産の引き継ぎについてです。
個人から法人へ資産を引き継ぐ場合には、
個人から法人へ資産を譲渡することが一般的です。
それでは、個人が事業で使用していた資産を法人へ引き継ぐ場合には、どのような金額で引き継げばよいでしょうか。
資産の譲渡対価は、基本的には適正な時価を用います。
この時価よりも低い金額で引き継いだ場合には、税務調査があった際に
時価との差額について指摘がされ、追加で税金を払うこととなってしまいます。
また、時価よりも高い金額で引き継いだ場合には、
時価との差額については役員への賞与となります。
法人の場合には、役員への賞与は経費とならないため、税務調査で指摘をされると
追加で支払う税金の負担は重くなってしまいます。
そして重要なのは、
資産ごとに所得税に定める適切な所得の区分に割り振って計算することです。
例えば、
土地建物の譲渡なら分離課税による譲渡所得で計算。
事業用車両の譲渡なら総合譲渡所得で計算。
などです。
譲渡する資産の種類によって税額の計算方法が異なります。
★ 法人化の資産引継のポイント まとめ ★
① 譲渡をする時の時価について、税法で定めがありますので、
これらを参考にしなければなりません。
② 資産ごとに所得税の定める適切な所得の区分に割り振って計算しなければなりません。
これらに個人で使用していた事業の資産(車や機械、器具や内装など)を法人へ引き継ぐ場合には、ぜひ、これらのポイントに注意して申告をしましょう。
法人化で誤りやすいところは?

こうした個人から法人への資産の引き継ぎだけでも大変ですが、
これら以外にも、法人化には減価償却の月割り計算や、
事業廃止後の必要経費の取り扱いなど様々な論点がございます。
誤って経費に入れ忘れたということがないよう、事業廃止後の経費の特殊論点も気を付けたいポイントです。
匠税理士事務所の法人化や法人成り支援サービス
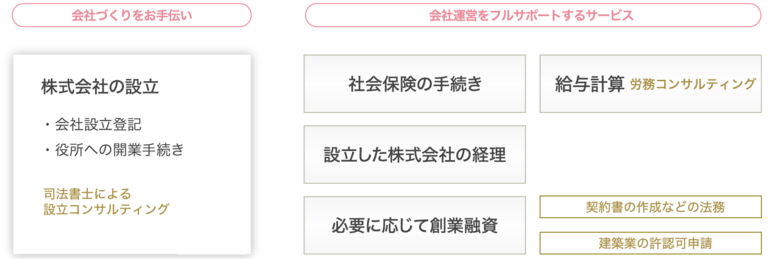
匠税理士事務所では個人事業主の法人化を支援するために、法人化・法人成り支援サービスをご用意いております。
法人化前後に混乱がなくスムーズに立ち上げができるよう税務申告を代行させていただくと共に
漏れがちな社会保険についてのサポートや経理についてもしっかりとフォローします。
法人化・法人成り支援サービスの詳細についてはご覧になりたい方は、下記のリンクよりご確認下さい。
法人化サービスは下記のリンクよりご覧ください。
【1】法人化・法人成り支援サービス の詳細はこちら
法人化や法人成りをした後のサービスは、下記のリンクよりご覧ください。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
起業 税理士なら匠税理士事務所 TOPページへ
世田谷区産業振興公社での起業・創業セミナー (12/08/10)
2012年11月末に(公財)世田谷区産業振興公社で、
今年度も創業塾の講師を、
匠税理士事務所の税理士が担当させて頂くことになりました。
この創業塾は、
毎年30~40名の起業を志している方々が、
参加されているセミナーです。
今年度の創業塾への参加募集は既に締め切られたとのことでしたが、
ご興味のある方は来年度是非ご参加下さい。
今回の世田谷区産業振興公社の創業塾では、
創業に際しての税務知識の全般をはじめとして、
創業時に気をつけるべき事項を幾つか説明させて頂きたいと考えております。
また、講義の中で随時質疑応答を踏まえたディスカッション形式で進めていくことで、
より講義内容を実践的にしたいとも考えています。
世田谷区で創業を志している方、
創業に興味があるが今一歩踏み出せないという方は、次回是非ご参加下さい。
税務以外にも
資金繰り・事業計画書作成・創業融資対策・マーケティング・販売促進・経営分析などについては
中小企業診断士の方など幅広い分野の専門家の方々が
数多く担当されていますので大変勉強になると思います。
税務分野のセミナー終了後に、また詳細を記載したいと思いますのでお楽しみに。
また、匠税理士事務所の
開業・独立・創業のための週末起業セミナーについては
こちらから
匠税理士事務所は目黒区の自由が丘にある税理士事務所です。
確定申告や決算・起業や創業融資などの具体的なご相談につきましては、下記のTOPページよりご確認下さい。
確定申告や起業に関するお悩みは、中小企業や個人事業主を専門とする会計事務所
匠税理士事務所にお任せください!
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
皆さまからのご連絡をお待ちしております。
世田谷の税理士 なら匠税理士事務所 TOPページへ
東京商工会議所の起業創業セミナー (12/08/02)

東京で起業セミナーをお探しのお客さまへ
匠税理士事務所では、東京商工会議所の丸の内の本部にて、
東京商工会議所の指導員様に向けた創業セミナーの講師を担当致しました。
セミナーの当日は約70名の方にご参加いただき、
約3時間にわたってご清聴頂きました。
講義の内容としては、資金繰り、創業時の融資、損益分岐点などの経営上のポイントなど
幅広くにわたって解説させて頂きました。
これから創業される方にむけてのご指導に役立つよう、
法人と個人で起業する場合の税金面での注意点や、
LLP、LLC、NPOなど各組織形態によってどんなメリットやデメリットがあるのか、
またどんな時にその組織を活用すると有効かなどについても補足で解説致しました。
起業前の組織形態の選択から
起業直後に必要となる創業融資、
起業後の経営に必要となる損益分岐点の考え方、
その後の会社経営に必要となる税金の基礎知識など
起業から事業を軌道に乗せる過程で必要なる全般的な知識を
起業の立ち上げから一貫し流れでサポートできるような>構成のセミナーを作成させていただきました。
年末には世田谷区の産業公社にて、起業家向けの創業セミナーの開催を予定しております。
こちらは、事業計画書の作成など起業前に必要な基礎知識の構成となっており
私共で担当させていただく部門としましては、
税務会計を中心としたセミナー内容となっております。
創業するに際しての
・個人面での税務の基礎知識
・法人面での税務の基礎知識
これらを中心に講義をさせて頂いております。
この他にも匠税理士事務所独自の
起業向けセミナーの開催予定がございます。
ご興味のある方はご覧いただければ幸いです。
これからもセミナーを通じて、
より多くの起業家の方に向けた有益な情報を発信していきたいと思います。
東京でのセミナーや講演のご依頼がございましたら、下記よりお気軽にご連絡下さい。
匠税理士事務所は東京都の目黒区自由が丘にある税理士事務所です。
起業や創業融資などのご相談につきましては、
下記のTOPページよりご確認下さい。
ご相談は無料です。
東京の起業を支援する
目黒の税理士 匠税理士事務所 TOPページへ
登記など自分で会社を作る?税理士の会社設立?(会社設立時の注意事項)K1 (12/08/01)
起業するに際し会社設立しようと思うのですが、
気を付けるべきことはありますか?
このような質問を頂きましたので、今回は会社設立する場合に気を付けるべきことを記載しました。
会社を設立する場合に気を付けるべきことの中でも
今回は以下5つにしぼって記載してます。
株式会社や合同会社など会社設立の注意点
1 株主構成 および 資本金の額の注意点
2 定款に記載する事業目的についての注意点
3 株式の譲渡に関する制限事項についての注意点
4 本店の所在地を決める際の注意点
5 役員の任期を決める上での注意点
これらの5つの事項は、
起業する際に特に気を付けるべき事項です。

これらの点を無視して会社を設立してしまうと
後々思いもよらぬ税金や、
登記などのための専門家への報酬といった費用が発生してしまう場合がありますので、
会社を設立される場合にはこれらの点を慎重に検討するようにしましょう。
会社設立のポイント 株主構成の注意点
株主は社長だけにしておくことが無難
多くの事業資金を集めるために、
広く株主を集める大企業の手法もありますが
会社は株主のものですので、
出資をしてもらった=会社の経営に口をだされる
ことになる点を留意すれば、
あとから不都合なことが生じないよう
経営者=株主でスタートすることが望ましいです。
≪株主決議で決定できること≫
2/3以上 事業譲渡 定款変更 解散
1/2以上 役員給与の決定 役員の解任
3/100以上 会社の帳簿の閲覧
こうしてみると結構な事が出来ますね。
社長以外の他人が入っていると・・・
面倒くさいことが起きる確率は上がります。
会社設立のポイント 役員の任期 株式の譲渡に関する制限事項の注意点
役員の任期は最長10年とすることができます。
役員が複数のときは、任期は短く
社長さまお一人が取締役の場合には、
登記の手間から最長の10年で
定めておくことも良いでしょう。
しかし、複数の取締役がいる場合などに、
任期を10年と定めてしまうと、
任期途中で解任することは、トラブルのもとです。
解任の損害賠償や、
第三者でも閲覧可能な謄本という会社の履歴に
役員の解任が掲載されてるといった点を
避けるためには、任期短めにすることを勧めます。
これも会社設立の重要ポイントです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q:会社を作るにあたって、共同経営をしようと思っています。
株式をもたせるかどうか迷っています。
問題はありますか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A:原則は、株主=オーナーです。株主の権限を知ってから決めてください。
匠税理士事務所では、起業後の経理や申告などを多数ご依頼いただいております。
そのなかで、共同経営については、設立後トラブルとなるケースがとても多いことを、ぜひ知っていただき、それでも共同経営を行うかどうかを決めていただきたいと思います。
設立の時に、友人や前の会社の同僚などで共同経営を行いたいと考える方も多いかと思います。
そして共同で経営をするのだから、お互いに出資をしあって責任をもって会社を運営していこうという考えで、会社の株式も均等にもちあいます。

しかし、起業して何年か経ったとき、少しの考え方のズレから起業当初のメンバーと意見が合わなくなってしまうことがしばしばおこります。
この時に役員を解任する。
株式を買い戻す。
このような問題点がおきます。この問題解決の過程で、意見の食い違いで争いになってしまい
話もできないほど関係が悪化して交渉もできない状況になり、損害賠償や裁判といった言葉がでてくるケースもございます。

このような共同経営の問題点は、
・株式をもたせるという意味、つまり株主の権限を理解していないこと
・複数役員がいるということの意味、つまり役員の解任について理解をしていないこと
などが挙げられます。
まず、会社とはだれのものでしょうか?
現行の制度では、会社は株主のものです。
株主は、役員を解任することができますが、
役員は株主を辞めさせることができません。
つまり自分が代表取締役で、友人が共同経営者で全ての株式をもっている場合
友人があなたを解任することは可能なのです。
そのため、会社にとって株式とはとても重要なものであり、後々のトラブルを避けるためにも
代表取締役=株主としておくことでリスクを回避できます。
会社設立のポイント 定款に記載する事業目的についての注意点
許認可申請が関係する方は、定款に注意を!
定款の事業目的は慎重に。
許認可申請の場合に、定款に○○事業という限定的な記載しか許可を受けられなかったり、
定款に許認可に関連事業の記載がないなど
後々に定款変更の必要が出るケースがあります。
許認可申請が関係する方は、後々に定款を変更することのないよう
定款の事業目的をしっかりと定めましょう。
また、税務調査の際にも定款に記載されていない事業に関する経費などは
事業との関係性でトラブルになりかねません。
将来的に行うかもしれない内容についても、定款に記載しておくようにしましょう。
会社設立のポイント 本店の所在地を決める際の注意点
本店の所在地は、どこでも登記が可能ですが、
本店を移動するたびに、登記費用がかかるほか、税務署などへの手続きも必要になります。
そのため会社設立の時は、インキュベーションオフィスなどすぐに移転が予想される場合には、
自宅を本店としておくことも、選択肢の一つです。
会社設立のポイント 資本金の額の注意点
会社を作るときに、資本金の金額は税金に大きく影響します。
こちらは論点が多いので、会社設立と会社の資本金 をご参照ください。
スムーズな株式会社の会社設立のために税理士がおすすめすること。
<1> 会社設立の日
起業される方の多くは、大安などの縁起の良い日に設定することが多いです。
この日が会社の創業記念日となるので覚えやすい日が良いなどの決め方も一つです。
<2> 会社の名前
会社名は、立ち上げる会社でこんなことがしたいう理念から会社名をつける方が多いです。
長期的には、お客さまやお取引に覚えてもらいやすい名前ということも大切なポイントです。
<3> 決算月
これは、必ず税理士と相談して決めましょう。
節税対策に大きく影響するのでとても重要です。
儲かる忙しい時期を決算月としてしまうと、
利益が出たら、すぐに決算(会社の締日とイメージして下さい)を迎えてしまって、
有効な節税対策を打つ時期が短く、税額が多額に出てしまうということにつながりますので、
決算月は、比較的忙しくない時期に設定するのがおすすめです。
会社設立の代行や創業融資など起業支援
弊所は起業と黒字戦略に強い会計事務所です。
独立開業や創業に強い税理士をお探しの方はお気軽にご相談下さい。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

◇関連記事
◇個人の起業サービス
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
株式会社を作る、設立するには?重要な起業家精神(創業のポイント)<K5> (12/07/29)
起業をする際に重要なことは何なのか?
と気になる方も多いと思います。
匠税理士事務所では起業・創業されるに際し
ポイントになる自己資金の考え方や、
起業後にポイントになる本業への知識について
幅広く記載致しました。
会社設立前に知っておきたい起業家精神
会社設立し設立後の会社を育て有利な経営を行うために、これから起業・独立開業をされる方が知っておきたいポイントをご紹介致します。
起業の現実
「中小企業白書2017」のデータによれば、起業後5年間で18.3%の企業が市場から退出しています。
倒産の理由には、
① 売上先の確保ができなかった ② 人・モノの過剰投資で資金繰りが困難になった ③ 価格競争で、利益があがらす生活が困難になったなどの理由があります。
起業するにあたり考えすぎるのも問題ですが、
最低用意しなければならない事もあります。

会社設立前に、
には起業後1期目から、大幅黒字になり税金対策が必要となるような会社が多いことも事実です。
起業するための準備は万全か、まずはチェックしてみましょう。
商品やサービスの独自性と顧客確保(その業界への知識などは充分か)
起業したばかりの時には、組織力もなければ、
認知度もありません。
そういった中で、何年もその業界で商売をしているライバル企業と勝負をしてお客さまを獲得していかなければなりません。
☆ここが重要
起業時されたばかりの会社で一番の財産は、
長年勤務した会社などで蓄積したノウハウ・キャリア・人脈です。これらが起業後の会社経営には重要となります。
つまり会社設立は、全くの経験のない分野での起業ではなく、自分が今までに積み上げてきたキャリアを活かした起業であることが最低限、必要となります。
自分のキャリア、業界への知識を活かし、
ライバルに負けない商品、儲けが出せる商品の開発、お客さまを獲得するための販売戦略、
これらは会社設立前にする必要があります。
チェックポイント
株式会社を作った後の資金繰り難を防ぐ(会社設立時の自己資金準備は充分?)
創業融資を受けたい場合には、自己資金は最低1/3まで準備する必要があります。
(関連記事:起業・開業はいくらまで貯める、用意するべき?)
融資を利用しない人にとっても、十分な運転資金を確保してから起業する必要があります。
会社設立前の心得として知っておきたい資金のイロハについて解説をします。
会社設立など起業前に検討すべき運転資金と設備資金とは?
起業する際に必要な資金は、「設備資金」と「運転資金」があります。
運転資金とは、事業をしていくのに必要な資金をいいます。
設備資金は、開業するときに必要になる設備を用意するお金いいます。
運転資金の例...商品や材料の仕入代金|人件費|家賃|光熱費|電話代|広告宣伝費|消耗品など事務所(店舗)維持費用(会社設立費用含む)
設備資金の例...不動産賃貸の敷金、礼金、保証金|内装工事代|パソコンなどの事務機器|製造用の機械|接客用の食器やメニューなど|営業車の購入代

☆ここが重要
![]() 運転資金はどの程度確保するのか?
運転資金はどの程度確保するのか?
会社設立後、起業もない時には、売上の確保が思ったように進まないときもあります。
目安として、毎月の生活費と会社のひと月運転資金とを合わせて6か月分程度の資金を準備してから起業したいところです。
運転資金は、計画しても、実際はその通りにいかないことも多いですから、ざっくりと設定して構わないと考えます。
![]() 設備資金はどの程度確保するのか?
設備資金はどの程度確保するのか?
設備資金については、会社設立前にお買いものリストを作成して、どの程度かかるのかリストアップして求めます。
チェックポイント
削れるところは削って起業することが重要です。
会社設立後は、固定客が少ない状態で過度に初期投資をしてしまうと後々の会社経営が苦しくなってしまいます。
お客様の目につくような部分は別として、過度にこだわりすぎて、初期投資がかさんだということには十分に気をつけなければなりません。
創業融資のお役立ち情報 創業融資の情報館
(関連記事:起業や創業融資での創業計画書の作成のポイント)
会社設立や創業融資など起業支援
匠税理士事務所では、世田谷区・目黒区・品川区など東京都を中心にこれまで数多くの起業家の方の立ち上げに携わらせて頂きました。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。
【 → 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

また、当事務所の所属税理士は世田谷区の産業公社や東京商工会議所その他数多くの場所で起業に関するセミナーの講師を担当させて頂いております。
これらの起業家向けのセミナーや、日々の起業家の方とのやり取りの中で感じたことを、より多くの起業家の方に役立てたいと思っておりますので、今後も起業や創業に関して起業家の方たちの少しでもお役にたてる情報を発信していきたいと思います。

起業に際してお困りの方や、起業してみたいが、どうしたら良いのかわからないという方は、下記の起業・創業にあたってのポイントをご覧下さい。
◇関連記事
匠税理士事務所は目黒区の自由が丘にある税理士事務所です。
確定申告や決算・起業や創業融資などの具体的なご相談につきましては、下記よりご確認下さい。ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇法人化・法人成りサービス
◇その他の起業支援サービス
起業支援サービス...すでに会社を設立されたお客様向けの経理や税金、経営のサポートサービス。
世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所 ...TOPページへ
対応地域:世田谷区や目黒区、品川区など東京都23区全域
◇個人の起業サービス
匠税理士事務所は世田谷区、目黒区、品川区など東京都や川崎市、横浜市など神奈川県全域で
起業時の資金調達・創業融資を行う会計事務所です。お気軽にご相談下さい。
執筆者・文責:税理士 水野智史
IT業界が得意な税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (12/07/11)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 【高度な専門性】・【技術力】が定評の事務所です。東京都・川崎市・横浜市・神奈川県でIT業のお客様と
多くの取引があり、IT業の税務会計が得意です。

目次
① IT業界の経営のポイント
② IT業界特有の税務や会計のポイント
③ IT業界の税理士事務所選びのポイント
IT業界の経営ポイントと税理士事務所選び
税理士からみたIT業界の経営ポイント
IT業はソフトウェアやシステム開発など論点が多く
また一取引当たり利益金額も多額になるため、
税務でも豊富な経験やITの知識が必要です。
経営面では一件当たりの取引金額が大きい一方で、
制作期間が長期にわたり、その間の外注費・人件費など多くの経費が先行するため、
多くのお金を必要とするという
ハイリスク・ハイリターンな事業でもあります。更に時代の先端をゆく事業であるため、
現在の仕様では想定していないようなリスクが、
納品後に発生し問題になる場合もあります。
例えば技術的な問題であったり、責任の線引き、
著作権など権利問題や代金回収などです。
また、社内では残業などの認識違いで
労務トラブルも起きがちな業種でもあります。

◇税理士からみたIT業界の経営ポイント
→融資を活用して余裕をもった資金運用をする
→会社の要望を反映した契約書を作成し、
リスクに対応して案件を受注する。
→就業規則で労使のルールを明確にして
トラブルを回避する
このように事が起きてから対応するのではなく、起きる前に会社で予防線をはることが重要です。
IT業界特有の税務や会計のポイント
例えば、システムの開発について、
はシステムの用途に応じて減価償却を通じて
複数年で経費にするという論点が出てきます。
(経費化する年数も用途に応じ3年や5年など様々)
ITの税務会計のポイントを何も意識せずに、
外注費や給与で全額経費としてしまうと、
本来は減価償却で期間按分した経費に比べて、
経費過大となり、将来の税務調査の指摘で、
修正申告の対象にもなりかねません。
このようにITの税務・会計は特殊論点が多いので
特に注意が必要になります。
IT業に強い税理士・会計事務所選び
弊所は、東京都や川崎市・横浜市など神奈川県で
これまで数多くのIT企業を担当してきおり、
ITの税務会計に詳しい税理士が在籍しています。
システムやソフトウェア開発・WEB制作の会社様など
IT業界の経営者の方を支援するため独自の会計や
経営支援サービスを用意している会計事務所です。
東京都という土地柄、IT事業のお客様が多く
IT税務や経営支援の事例が豊富で、
30代と40代が中心でITへの柔軟性もございます。
・会計や経理のアウトソーシングを検討中の方
・給与計算など人事労務サポートを検討中の方
・節税対策に強い会計事務所をご要望の方
・お金を残す仕組みを作りたい方や、
資金調達で相談したい方
このようなIT業ご要望に対し税理士のみでなく、
各業界トップレベルの弁護士・弁理士・社労士など連携し
お客様の経営をサポート致します。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

税理士は東京都・川崎市や横浜市など神奈川県対応
会計アウトソーシング・経営コンサルティング
IT業は利益率が高い一方、受注時期が重なったり
納期が短いなどで残業が多いなど労使トラブルに
つながらないよう事前対策が重要です。
また、会社の内部の利益やお金などの会計情報を
会計スタッフを雇用し内製化すると、
機密情報が漏れるなど難しい問題が出てきます。

ただ、会計を社長自ら行うわけにもいきませんので
【 利益やお金などの会計や給与計算 】といった
機密情報は外部委託される方が多い業界です。
またIT業は案件次第で大きな利益が出るため
【 効果的な節税対策 】が必要になったり、
大規模案件を受注すると納品まで長い期間、
外注費や人件費などが先払いとなるため
資金繰りに工夫が必要な業種でもあります。
このようなIT業界の社長様を支援するため、
弊所ではIT業界の税務会計に詳しい税理士が
専門性を駆使した経営コンサルティングや
会計アウトソーシングを提供しております。
サービスはこちらよりご確認をお願いします。

◇税理士変更をご検討のお客様のサービスは、
こちらよりご確認をお願いします。
税理士は東京都・川崎市・横浜市など神奈川県対応
東京都・川崎市・横浜市・神奈川県での会社設立
匠税理士事務所の起業支援では、
これからIT業界で起業したい起業家の方に向け
会社設立や会計経営の支援を行っております。
・会社設立後に資金調達をご要望という方には、
IT事業対応の創業融資もお手伝い可能です。
・外国人の方のプログラマーを雇用したい方に向け
外国人の方の就労ビザ取得サポート
・起業に伴う人材採用の助成金の申請代行
・各種契約書の作成やレビューなど法務相談
にも対応しております。
【起業に必要な全てがそろう会計事務所】です。
◇サービスはこちらで確認をお願いします。
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
→起業家向けサービス..給与計算その他サービス
東京都・川崎市や横浜市など神奈川県全域対応
IT事業に強い匠税理士事務所の会社概要

弊所は目黒の自由が丘にある会計事務所です。
IT税務会計顧問サービス以外のサービスライン
アクセス・会計スタッフ紹介などについては、
下記よりご確認下さい。
東京都・川崎市や横浜市など神奈川県全域対応
◇匠税理士事務所について
自由が丘の匠税理士事務所...会社概要
税務論点は下記コンテンツをご覧ください
◇IT経営の税務ノウハウ 関連記事
免責事項
掲載情報に基づいて利用者が下した判断および起こした行動によりいかなる結果が発生した場合においても、匠税理士事務所はその責を負いません。 また、当サイト内のコンテンツは法令に改正が入った際などにおいても、最新の法令への変更は行いません。当サイトのコンテンツの情報を利用し起こりうる損害その他一切の影響や利用者の皆様に発生する損害について、匠税理士事務所はその責を負いませんのであらかじめご了承ください。
執筆者・文責:税理士 水野智史
下高井戸や羽根木近く税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (12/07/09)
匠税理士事務所へご来訪ありがとうございます。
弊所は下高井戸や羽根木など世田谷区で
創業セミナーや経営セミナーなどを通じて
【起業支援・経営支援】に力を入れております。
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に高度な専門性を通じた節税対策や、
黒字率9割超の経営コンサルティングが評判です。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】このような関係を築いて仕事進めております。
所属税理士やサービスはこちらを確認下さい。

下高井戸や羽根木の会社設立や起業支援
下高井戸や羽根木でこれから会社設立される方に
株式会社や合同会社など会社設立の代行から
その後の会計経理や給与計算アウトソーシングなど
【全てお任せ】の起業支援をご用意してます。

お客様にとって大きな出来事である起業が
成功するよう税理士・社労士・司法書士・行政書士が
チームを編成して対応致しますので、
税務会計以外の人事労務や登記、各種許可申請にも
対応可能な事務所です。
【起業に必要な全てがそろう事務所】をコンセプトに
起業支援No1の会計事務所を目指しております。
下高井戸や羽根木担当税理士・専門家はこちら
【→起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】
起業家向けサービス一覧はこちらを確認下さい。
【 → 起業家向けサービス一覧 】

これから下高井戸や羽根木など世田谷区で
株式会社や合同会社を設立される方向けた
会社設立サービスはこちらからご確認下さい。
下高井戸や羽根木の創業融資など創業支援
起業する際に必要な資金を全て自己資金で
用意対応するのは中々難しいです。
匠税理士事務所では下高井戸や羽根木に
対応する金融機関と連携することで、
世田谷区制度融資や日本政策金融公庫による
会社設立時の創業融資も対応しております。

自治体の制度融資と日本政策金融公庫という
両チャネル対応可能ですので創業融資では
最大2,000万円の調達実績がございます。
また起業セミナー講師を務める税理士が
創業計画書作成など融資全般をコンサルティングし、
【融資成功率は9割超】の実績を有しております。
創業融資による創業支援はこちらでご確認下さい。
弊所紹介で優遇がある金融機関もございます。
下高井戸や羽根木対応の融資詳細はこちら。

下高井戸や羽根木など世田谷区の自治体の
制度融資による資金調達はこちら
【 → 世田谷区の制度融資の仕組みと創業融資 】
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は下高井戸・羽根木など世田谷全域対応)
下高井戸・羽根木の経理会計・決算確定申告代行
下高井戸や羽根木で個人事業を経営されている方や
自宅・投資不動産を売却された方、賃貸中の方に
会計や経理の代行から青色決算・確定申告の代行も
行っております。
また既に会社を経営されている方には、
経営支援や資金調達など経営支援も行っています。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
下高井戸や羽根木の方向け経理や会計、確定申告や
法人化などサービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
下高井戸や羽根木で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

下高井戸・羽根木の法人化・会社設立お役立ち情報
下高井戸・羽根木など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
下高井戸・羽根木の法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が下高井戸や羽根木で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
下高井戸や羽根木近くの会計事務所の採用求人情報
匠税理士事務所では、お客様の会社を一緒になって
盛り上げていって下さる社員の方を募集してます。
下高井戸や羽根木など世田谷区近くの会計事務所の
採用求人をお探しの方は匠税理士事務所のWEBを
ご確認下さい。ご応募お待ちしております。
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
下高井戸(しもたかいど)や羽根木(はねぎ)など
世田谷区のお客様に向けた会社設立など起業支援・創業支援や
法人化・法人成りなど匠税理士事務所案内を
最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#羽根木会社設立
#下高井戸法人化
法人化・法人成りについて (12/06/10)
税理士 目黒の匠税理士事務所HPへご訪問頂きまして誠にありがとうございます。
匠税理士事務所では、個人事業から会社に形態を変更する法人化・法人成り(法人なり)サービスを行っています。
・将来的には会社で退職金などを用意できるように生命保険などを活用したい。
・融資をうけて事業を拡大していきたいが法人の方が有利と言われた。
・これまでは、個人でやってきたけれど本格的に人を採用して、事業を拡大していきたい。
・得意先から会社でないと取引できないと言われた。
・会社にした場合の節税などにも興味がある など。
様々な理由から会社にしてみたいというお客様のニーズにお応えしております。
具体的には、法人化・法人成り(法人なり)に伴う個人事業の最後の確定申告(譲渡所得税の申告や事業税の見込み計算など特殊な論点が多いです。)や法人化後の経理・決算の支援、各種届出作成を代行しております。また、ご希望の方には行政書士や司法書士と連携して会社設立代行も行っております。
ただ、法人化はお客さまの事業にとって、とても大きな影響を与えるためお客様の事業を完全に把握した上でのみ提案・実行させて頂いております。
そのため、個人事業主の経理・申告 サービスをご利用のお客様のみのサービスとさせて頂いており、
法人化・法人成り(法人なり)サービスのみでは扱ってはおりません。
ご興味のある方は、お気軽にご連絡下さい。
世田谷・目黒・品川以外の渋谷・港のエリアのお客様は下記リンク先をご確認下さい。
渋谷 会計事務所 なら匠税理士事務所HPへ
個人事業主の税金(節税対策) (12/06/08)
確定申告が終わり、今年も6月になりました。
今年はまだ帳簿をつけていないので、利益が何となくしか分からない。
このような個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
このような方は、出来るだけ早めに経理をされて、
利益がどれだけ出ているのかつかむ必要がございます。
なぜなら、個人事業主の方は12月末で締めとなりますので、この12月末を過ぎてしまうとほとんどの経費は来年の経費になってしまいます。そこで、どれだけ利益が出ているかを早めに把握して、その利益の範囲内で適切に節税を行うと効果的だからです。
過度の節税対策は資金繰りを圧迫しますので、現状の利益をしっかりとつかんだ上で、効果的に節税対策を行うのが重要です。
また、分かっているけれど、経理は仕事が忙しくて手が回らないという方につきましては、匠税理士事務所では、個人事業主の経理・申告 を代行するサービスもございますので、ご興味のある方はリンク先よりサービスの詳細をご覧頂ければ幸いです。
サービス内容や料金などについてご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
皆さまからのご連絡を心よりお待ちしております。
その他、匠税理士事務所についてお知りになりたい方で世田谷区・目黒区・品川区・大田区などの地域の方は税理士 目黒の匠税理士事務所HPよりご確認下さい。
また、渋谷区・港区のお客様につきましては
渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPよりご確認下さい。
以上、宜しくお願いします。
法人化サービス (12/05/04)
これまで確定申告をされてきた個人事業主の方で、節税や取引上の都合から会社形態にしたいとお考えの方もいらっしゃると思います。
法人化の際には、個人から法人への棚卸資産の譲渡や事業税の見込み計算などといった特殊な論点も多数ございます。
また、法人化した後には法人の各種届出を所轄官公庁へ提出する必要もございますし、法人化した後は税制も大きく変わります。
これらを全てご自身で理解し、ご自身で手続きをされるとなると大変です。
そこで匠税理士事務所では、法人化の際の個人の確定申告や法人の各種届出の作成代行をはじめ、法人化した場合の税制上のポイントをしっかり説明する法人化サービスをご提供しております。
もちろん、法人化の際の法人設立も全て代行致しますので、お客様は社名と決算期の決定など最小限の労力で済むようになります。
これまで個人事業の形態をとられてきた方で、法人化にご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
ご連絡お待ちしております。
匠税理士事務所の法人化サービス詳細はこちらから
→ 法人化サービス へ
税理士 目黒の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
瀬田や成城近くの税理士や会計事務所は匠税理士事務所 (12/04/30)
弊所サイトへ来訪ありがとうござます。
匠税理士事務所は瀬田や成城に近い事務所で、
約20年前に事務所を設立してから
瀬田・成城など世田谷で事業展開してきました。
匠税理士事務所の最大の強みは、
世界4大会計事務所出身の税理士を中心とした 【 経営支援 】と【 創業支援 】です。高い技術力と豊富なノウハウを用いて、
お客様の94%が黒字経営を実現されております。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
当会計事務所の税理士やサービスは、
こちらからご確認下さい。

瀬田・成城の会社設立・創業融資と起業支援
瀬田や成城という世田谷で株式会社設立をされる
起業家に対して法人設立サービスを提供してます。
会社の構造設計から設立後の経理税務申告など
会計事務所で行う業務はもちろんですが、
会社設立後に資金に困らないように
瀬田や成城などに対応する金融機関と連携した
創業融資による資金調達も行っています。
瀬田や成城担当の税理士や専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

政府系の創業融資機関である日本政策金融公庫とも
提携することによって、
【最大2,000万円の調達枠】をご検討頂けます。匠税理士事務所が提供する瀬田や成城など
世田谷区の創業融資は、こちらから
【 世田谷区の創業融資・資金調達 】

瀬田や成城という世田谷区で会社設立時の
制度融資はこちらにて確認下さい。
株式会社などの会社設立代行は、
こちらにてご確認をお願いします。
瀬田や成城エリア向け会計経理や決算の代行
匠税理士事務所経営支援では、
成城・瀬田など世田谷で経営支援に注力してます。
・利益戦略会議
・キャッシュストック経営 など
独自のサービスラインもご用意しております。
瀬田や成城など世田谷エリア向けた
当会計事務所の法人サービス案内は
こちらからご確認をお願いします。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】

成城や瀬田での確定申告や法人化
当会計事務所は、瀬田や成城のお客様に向けて
会計や決算確定申告代行を承っております。
事業に専念するため会計や経理の代行、
青色申告や確定申告のご依頼がございましたら、
お気軽にご相談下さい。
給与計算や契約書の作成・レビューなど
会計事務所以外の業務も対応しております。
瀬田や成城の方向けの確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
瀬田や成城で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

独立開業支援や創業支援に強い税理士事務所
匠税理士事務所では、瀬田や成城などでの
独立開業支援や創業支援に力を力を入れてます。
瀬田や成城の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は瀬田や成城など世田谷全域対応)
瀬田や成城の法人化・会社設立関連情報
瀬田や成城など世田谷区で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 世田谷区など東京都の法人化・法人成り】
瀬田や成城で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記はこちらで手続きとなります。
【 →東京法務局 世田谷出張所 】管轄区域 世田谷区
〒154-8531
世田谷区若林4丁目22番13号
世田谷合同庁舎2階
上記が瀬田や成城で法人化・会社設立など
登記の際に対応する行政窓口となります。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
瀬田(せた)・成城(せいじょう)など世田谷で
会社設立など起業支援・創業支援や法人化・法人成りなど
当会計事務所紹介を最後までご覧下さりありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#成城税理士
#成城会社設立
WEB・HPとの相互リンク募集などの受付に関して (12/04/16)
ホームページへのご訪問ありがとうございます。
匠税理士事務所のHPでは相互リンクを受け付けております。
弊所のHPはできるかぎり分かりやすいホームページを目標に、日々励んでおります。
まだまだ至らないところが多々ありますが、
すこしずつ改善していきたいと思いますので、弊社HPと相互リンクをして頂ける方は、
以下のようにしてタイトルを記載の上、相互リンクの設置をお願いします。
*なお、紹介文は省略して頂いてかまいませんが、
サイト名に関しては以下のようにお願いします。
URL https://www.takumi-tax.jp/services/takumi-3tsu.html
サイト名:世田谷区の会社設立は匠税理士
紹介文:
匠税理士事務所は、目黒区や世田谷区、品川区対応の経済産業省認定の経営革新等支援機関です。
世界4大会計事務所出身の税理士が会社設立を支援します。
相互リンクが完了いたしましたら、
お手数ではございますが、リンクを希望されるサイト名、
URL、設置して頂いたリンク先のURLも明記し、お問い合わせよりご連絡下さい。
ご連絡いただいた内容を確認し、こちらからもリンク設置致します。
(繁忙期などはリンクの設置が一週間ほどかかる場合がございますことをご了承ください。)
以上、よろしくお願いします。
【 相互リンク集1 】
安心・スピーディーなSMS配信はSMS-FourS で匠税理士事務所が紹介されました。
SMS FourSは、株式会社りーふねっとが提供する業界最安水準の法人向けSMS配信サービスです。携帯キャリアとの直接接続により安定したメッセージ配信を実現。API連携や2段階認証、一括・予約送信など法人利用に適した機能も充実しております。
みんなが選んだ終活 で匠税理士事務所が紹介されました。
みんなが選んだ終活では、評価員の調査とお客様評価によって厳選された、優良なお葬式、お墓のみをご紹介しています。年間お問合せ件数は「21,000件」以上。専門のカウンセラーが24時間365日いつでもご相談に承ります。
資金調達ニュース.com|資金繰りに悩む経営者様・個人事業主様のための情報発信メディア で匠税理士事務所が紹介されました。
株式会社seedが運営する資金調達ニュースでは、資金繰りに悩む方に向けて様々な資金調達の方法を発信しています。
ハブスペ(Hub Spaces)公式サイト で匠税理士事務所が紹介されました。
ハブスペ(Hub Spaces)では、自分に合ったぴったりのコワーキングスペース・レンタルオフィスを規模関係なく探すことが可能です。月額費用やエリア、キーワード検索ができるので、希望に合ったオフィスを見つけることができます。
DAINOTE で匠税理士事務所が紹介されました。
DAINOTEは株式会社インディバースが運営する、キャリア情報を発信しているメディアです。主に、転職・フリーランス・副業・プログラミングなどを取り扱っています。
ファクタリング口コミ・比較サイト「ファクログ」 で匠税理士事務所が紹介されました。
rimad株式会社が運営するファクタリング口コミ・比較サイト「ファクログ」ではファクタリングやビジネスローンなどの、資金調達について紹介しています。

確定申告や起業に関するお悩みは、
中小企業や個人事業主を専門とする会計事務所
匠税理士事務所にお任せください!
税理士 世田谷 なら匠税理士事務所 TOPページへ
世田谷・目黒・品川など東京都の全域に対応
※記事に関するご質問は受け付ておりません。
匠税理士事務所 ホームページ担当
#相互リンク
#相互リンク募集
祖師谷や上祖師谷近く税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (12/03/14)
祖師谷や上祖師谷すぐの匠税理士事務所に
ご来訪ありがとうござます。
弊所は、世界4大会計事務所出身の税理士を中心に【コンサルティング】・【高度税務】が特徴です。
1 儲かって、お金が残る会社作りの支援 2 節税を通じ、利益の内部留保を行うことこれらを使命にお役に立てるよう取り組みます。
もちろん、通常税理士事務所で扱う決算確定申告、
会計経理のアウトソーシングにも対応しています。
【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の税理士やサービス内容は、
こちらにてご確認下さい。

祖師谷や上祖師谷での会社設立や起業支援
匠税理士事務所は、祖師谷や上祖師谷のある
世田谷区の産業振興公社でセミナー講師担当など、
起業支援の実績が多数ございます。
【 起業に必要な全てがそろう事務所 】を起業支援のポリシーにしています。
祖師谷や上祖師谷担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

起業支援エリア:祖師谷・上祖師谷など世田谷区
会社設立や経理決算など経理代行業務は
こちらをご確認下さい。
祖師谷や上祖師谷の創業融資など創業支援
創業支援活動の中で構築した世田谷が
地元の各種金融機関との付き合いも多いため、
祖師谷や上祖師谷がある世田谷区自治体の
制度融資による資金調達も可能です。
また世田谷区ではなく、財務省出資の
日本政策金融公庫とも提携しておりますので、
双方向からの創業融資による起業資金の調達できる税理士事務所という特徴もございます。
当会計事務所の祖師谷や上祖師谷など
世田谷区の創業融資による創業支援はこちら
【 →世田谷区の創業融資・資金調達 】

世田谷が地元の各種金融機関による制度融資は
こちらで確認をお願いします。
祖師谷や上祖師谷の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 世田谷区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は祖師谷や上祖師谷など世田谷全域対応)
祖師谷・上祖師谷で決算確定申告や法人化も対応
弊所は、祖師谷や上祖師谷での
経営コンサルティングや会社設立・創業融資などの
起業支援以外のご相談も承っております。
経理や確定申告・決算代行・法人化など
会計事務所業務はもちろんですが、
給与計算や社会保険手続き代行、
就業規則作成・助成金・補助金・労務も対応します。
祖師谷や上祖師谷の経営者に向けて
【 経営に必要なものは全てご用意しております 】詳細はこちらからご確認下さい。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
祖師谷や上祖師谷の方向け確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
祖師谷や上祖師谷で税理士による相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 世田谷区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

祖師谷・上祖師谷で税理士による法人化・法人成り
土地マンション、不動産など売却した場合の確定申告や
相続や贈与に伴う確定申告なども対応してます。
特に不動産の法人化・法人成りによる節税対策も
祖師谷や上祖師谷など世田谷区で提供してます。
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
ただ、10名程の税理士事務所ですので、
人的リソースのため対応が難しい場合もございます。
その場合には、出来る限り提携先を
ご紹介させて頂くことで、
出来る限り祖師谷や上祖師谷のある世田谷区の
お客様のお役に立てるよう心掛けてます。
世田谷区の会計事務所の採用求人はこちらから
【 → 世田谷区近くの匠税理士事務所・会計事務所の採用求人】
祖師谷(そしがや)上祖師谷(かみそしがや)など
世田谷区のお客様への会社設立など起業支援や
法人化・法人成りの匠税理士事務所の案内を
最後までご覧頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#祖師谷法人化
#祖師谷税理士事務所
大井町駅や西大井駅近くの匠税理士事務所・会計事務所 (12/03/14)
ご来訪ありがとうございます。
弊所は大井町駅や西大井駅など品川区を中心に
【 お客様黒字率100% 】をめざす事務所です。そのため、【専門性・人材の質】を重視しており、
世界4大会計事務所出身の税理士を軸に【 高度な専門性 ・ 高い技術力 】が評判で
税務会計や起業支援・経営コンサルティングを行います。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】
そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の概要やサービス内容は、
こちらよりご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

大井町駅・西大井で税理士の会社設立・起業支援
匠税理士事務所では、起業セミナー講師のノウハウを活かし
早期黒字化が重要な起業支援に力を入れてます。会社の維持費である固定費を出来る限り削減し
一方、【売価の最大化】・【原価の最小化】を通じ
【利益の最大化】を行うことを軸にして
関与先の【 黒字割合は9割 】を超えております。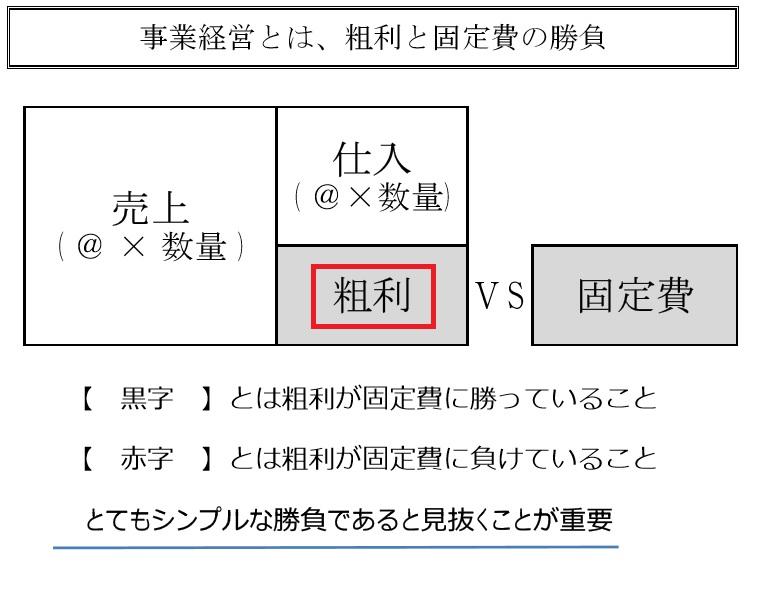
もちろん、大井町駅や西大井駅地域での
会社設立の登記や経理代行、給与計算や
決算・税務申告にも対応しております。
大井町駅や西大井で起業支援担当の税理士は
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

大井町駅や西大井駅など品川区での
株式会社や合同会社などの会社設立など
起業支援サービスは、こちらでご確認下さい。
大井町駅や西大井で創業融資による創業支援
当会計事務所では、上記起業支援の一環で
会社設立時の創業融資でノウハウがございます。
日本政策金融公庫や大井町駅や西大井駅近くの
城南信用金庫などの金融機関と連携して
創業融資による創業支援も行っています。
創業融資の成功率は、【 9割超 】になっており、
大井町駅・西大井駅など品川区トップレベルです。
創業計画書の作成から審査面談にも同席など
弊所独自のサービスをご用意しております。
匠税理士事務所の創業融資による創業支援は、
こちらよりご確認をお願いします。
【 → 品川区の創業融資・資金調達 】

大井町・西大井の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は大井町・西大井など品川全域対応)
大井町・西大井近く経理代行・決算申告対応
当会計事務所では、起業や経営支援以外の
会計経理の代行から決算税務申告も対応してます。
人手不足のため会計経理の代行を検討中の方、
決算税務申告のアウトソーシングを検討中の方は、
お気軽にご相談下さい。
個人事業主から会社にするための法人化や、
税額控除・税務調査など複雑案件も対応可能です。大井町駅や西大井駅など品川近くで
若手の税理士事務所・会計事務所を
お探しの方はお気軽にご相談下さい。
匠税理士事務所のサービスにつきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
法人様向けサービスライン様
大井町駅や西大井駅近く方向け個人サービス
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
大井町・西大井で税理士・会計事務所の相続対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

大井町駅や西大井駅近くの税理士事務所求人情報
匠税理士事務所では、
正社員とパートスタッフを募集しています。
大井町駅や西大井駅近くの税理士事務所、
会計事務所での勤務をご検討中の方は、
弊所の採用情報をご確認の上、ご応募下さい。
【社員とその家族の幸福のために、お客様利益と企業価値の最大化】が当会計事務所理念です。

大井町近くの税理士事務所お役立ち情報
大井町駅東京都品川区大井1-1-1にあり、
JR・東急・東京臨海高速鉄道の乗り入れ
路線で接続駅となっています。
大井町は、上記に立地しますので、
大井町で会社設立など起業した場合や、
会社経営をされている場合の税務申告書、
届出書提出先は以下のようになります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 税務申告書、届出書提出先→品川税務署
管轄区域:品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区
〒108-8622
港区高輪3丁目13番22号
事業税・住民税の申告書、届出書提出先→品川都税事務所
管轄区域・品川区・大田区
〒140-8716 品川区広町2-1-36
※品川区役所 本庁舎・議会棟の2階です。
社会保険関連書類の提出や相談先 【 →日本年金機構 品川年金事務所 】〒141-8572
東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階
上記が大井町や西大井の方の税務申告や社会保険の
届出書の提出先・税務調査所轄となります。
期限までに決算関連書類の提出を行いましょう。
大井町や西大井の会社設立・法人化登記情報
品川区の大井町・西大井で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
大井町や西大井など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が大井町や西大井で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
大井町駅や西大井駅など品川地域の方に向けた
匠税理士事務所紹介ページをご覧頂きありがとうございました。
会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い大井町や西大井近くの
会計事務所をお探しならご相談ください。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#大井町税理士
#大井町税理士事務所
#大井町会社設立
資本的支出と減価償却 (12/02/27)
事業所の一部を改築したが、どうやって経費にするのでしょうか。
こんなご質問を頂きました。この改築のように事業所の建物(減価償却資産)へ資本的支出(固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出)を行った場合には、その資本的支出は減価償却の方法により各年分の必要経費に算入することになります。
この資本的支出を行った場合の減価償却は以下のようになります。
平成19年4月1日以後に行った資本的支出 (平成19年3月31日以前の支出は扱いが異なります。)
(1) 原則
当該資本的支出を行った減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行います。
(2) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出を行った場合の特例
上記(1)の原則にかかわらず、当該資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、当該資本的支出を加算し減価償却を行うことができます。
(3) 定率法を採用している場合の特例
平成19年4月1日以後に取得した定率法を選定している減価償却資産に資本的支出を行った場合は、資本的支出を行った翌年1月1日において、当該資本的支出を行った減価償却資産の期首未償却残高と上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)の期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
(4) 同一年中に複数回の資本的支出を行った場合の特例
同一年中に複数回行った資本的支出につき定率法を採用している場合で、上記(3)の適用を受けない場合には、資本的支出を行った翌年1月1日において、上記(1)の原則により新たに取得したものとされた減価償却資産(資本的支出の部分)のうち、種類及び耐用年数を同じくするものの期首未償却残高の合計額を取得価額とする一の減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却を行うことができます。
このように減価償却を通じて経費としていきますが、その方法には選択があり、納税者で有利な方法を選択することが出来ます。どの方法でも結果は同じというわけではありませんので、どのパターンなら今年の減価償却費が一番多くなるかなど試算をされると最善の選択ができますのでご検討下さい。
*判断は自己責任でお願いします。記事に関するご質問はご遠慮ください。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
法人化・法人成パック (12/02/06)
早い方は、既に確定申告の準備も終わり出すだけという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
去年も今年も税金がだんだん増えてきた・・・・
節税対策をやっているけどそれ以上に売上が伸びてきて税金も増えたな~
確定申告後にこのようなお悩みをお持ちの方は法人化を検討されても良い時期かもしれません。
やはり法人になると個人よりも節税の選択肢は大きく広がります。
勿論、自分で会社を作ることも可能ですが、その前に法人化のメリット・デメリットをしっかりと
理解してから会社を作ると良い結果につながります。
匠税理士事務所では年間かなりの数の法人化のサポートに携わっておりますので、
法人化前のご相談から、会社設立のサポート、法人化後の経理代行から決算申告までを丸ごとサポート致します。
ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡下さい。
目黒 税理士の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
相続税の物納について (11/09/02)
日本の税金は金銭納付が原則です。
ただし相続税は、その税金の性質から延納を活用しても金銭納付が難しいような場合は、納付ができない金額を限度として相続財産を納める「物納」が認められています。
物納できるのは相続税の課税価格計算の基礎になった財産のうち、①国債、地方債、不動産、船舶②社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券③動産――とされています。原則的に、①から③の順番で優先的に納めます。なお、美術品の美術館における公開の促進に関する法律で規定された「特定登録美術品」として登録されている財産は、一定の書類を提出することで優先順位に関わらず物納できるとされています。
物納するためには納税者の申請が必要になります。平成5年度前後は1万件を超える申請がありましたが、現在は申請が減少傾向にあります。平成19年度には、18年ぶりに1千件を割り込み、383件の申請。20年度698件、21年度727件となっています。処理件数と処理金額を見てみると、21年度は914件・912億円でした。
物納が減少している理由は、納税者が相続の事前対策をしていることや土地売却で金銭化することで、多くの納税者が金銭納付できている実態もあるといわれます。もうひとつ、物納制度の手続きが見直されたことも関係しているという見方があります。
平成18年4月以後の相続からは、物納申請書と物納手続関係書類を同時に提出することになりました。これによって申請だけを先に行い、物納手続関係書類を提出するまでの間に物件売却や資金繰りを行う、いわゆる「とりあえず物納」が原則的に使えなくなりました。
物納手続関係書類が用意できなければ、物納手続き関係書類提出期限延長届出書を提出することで期限を最長1年間延長できますが、延長期間中は利子税が掛かりますのでご注意ください。
記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
記事の一部はエッサムより引用しております。
税理士 東京都 の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
中小企業倒産防止共済の改正 (11/05/17)
会社を経営されていて税金が出そうなときの選択肢の一つとして中小企業倒産防止共済への加入があります。
この加入は、掛け金が全額損金で落ちることと万が一取引先で売掛金が焦げ付いた場合に、一時的に融資が受けられるという中小企業にとって大きなメリットがあります。
そして掛け金も、一定期間掛けると満額返ってくるという優れものです。保険にも似た性格はありますが、返戻率が100%近くになるためには相当の年数掛け続ける必要があるのが大きな違いです。
そしてこの中小企業倒産防止共済に平成23年10月までに(具体的な施行日は未定)、「共済金の貸付限度額の引上げ」や「償還期間の延長」、「申込金の廃止」などの改正が行われます。
この改正の中でも特に掛金の積立限度額が、320万円(現行)から800万円に引き上げられることは、節税対策の枠が広がるという意味では大きな効果があります。
すでに320万円まで積み立てている方も、掛金の納付を再開することにより、320万円を超えて掛金を積み立てることができます。
また、掛金月額の上限額が、8万円(現行)から20万円に引き上げられます。
改正後は、掛金月額を5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選ぶことができるようになります。
この改正により、中小企業倒産防止共済はより節税効果が高まりましたので、今黒字が出て対策に困っている方はぜひ一度検討されても良いかと考えます。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
東京都 税理士 の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
災害時の取引先への売掛債権の免除などについて (11/04/15)
今回の地震で得意先が大きな損害を受けて困っているので、売掛金などを帳消しにするなど何とかして力になりたいと考えている会社も多いと思います。
しかし、このような際に税務上の寄付金になり一部だけ経費になるのか、、、、、、とお悩みの方。 このような場合の減免は、寄付金には該当しません。
したがって、寄付金の場合の一部だけ損金(経費)になるという規制は受けません。
<根拠>
9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加)
(注) 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
東京都 税理士 の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
寄付金と税制優遇について(個人の場合) (11/03/27)
今回の地震で寄付を考えられている方も多いと思います。
そこで今回は出来るだけ簡単に寄付をした場合の税務上の優遇措置を記載します。
まず、寄付をした場合、その寄付が国で認められているか否かがポイントになります。一つ一つ記載していては多数になりますので、寄付をする際に寄付金控除の証明書が出るか確認してみて下さい。これが出る場合には、大体の場合で寄付金控除が受けられます。
また、この書類は原則添付する必要がございますのでしっかり保存しましょう。
そして、上記の書類が出た場合、寄付した金額を以下の算式に当てはめ、寄付金控除とします。
<寄付金控除の算式>
次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額
イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額
総所得金額等とは、給与所得や事業所得などの合計です。たいていの場合は、上記のイになりますので、寄付をした金額から2,000円を控除した金額が寄付金控除の対象となります。
税制でのメリットを考えて寄付をする方は、ほとんどいないと思いますが、ご参考まで・・・・・
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
東京都 税理士 の匠税理士事務所HPへ
港区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
IT事業に強い税理士による起業や創業サポート(創業融資) (11/03/23)
IT化が進むにつれスマートフォン向けのアプリケーション開発、システムの開発やWEBデザイナーなど
IT系の事業で起業される成功される方が多くなってまいりました。
日々、技術の進歩が目まぐるしく大型案件の受注も多いIT企業ですが、税務や経営にはどのようなポイントがあるのでしょうか。
こちらはIT事業でこれから起業されるお客様に向けた記事です。
◇既に顧問税理士さんがおり、税理士変更をお考えのIT事業のお客様はこちらです。
複雑なIT事業の経理、会計、税務も起業・創業期からサポート
IT事業は成長速度が比較的他の業種と比べて早い反面、システム開発で多額の資金が必要となったり、
次々と技術が進み、現在の最先端が少しすると時代遅れという難しい経営的要素も含んだ業界です。
また、会計・税務の中でも、IT関連事業はソフトウェアの処理など特殊な論点が多くあります。
匠税理士事務所は、渋谷区や港区から近いということなどもあり
IT系の事業のお客様が多数いらっしゃることから、IT関連の起業や創業支援に豊富な実績がございます。
起業後の経理や決算などの代行や、創業時の資金調達の支援はもちろんですが、
起業と黒字戦略に特化した会計事務所のためビジネスモデルを含めた経営相談のご依頼が非常に多いです。
IT事業で創業・起業する際のポイント 税理士によるポイント解説
IT業界は、人材の確保が重要です。
IT業界は、現在の最先端が少しすると時代遅れという、経営にはスピードが求められる事業です。
そのため優秀な人の雇用や育成し、常に流行の先端を発信し続けるという長期的なマラソンにも耐えられる持久力のある経営が必要です。
最新の技術をサービスとして提供するためには有能な技術者を確保しなければなりません。
また、その技術も日々進化をしていくため、技術者の人材育成を継続的に行わなければなりません。
<ポイント> IT業界は、利益を人材の確保や、人材の育成に投資することが重要です。
IT業界で起業する際の創業計画書のポイント
IT事業は、利益率の高い得意分野(デザインやソフトウェア開発、ライティング、音楽、映像、ディレクション)があるか
その得意分野と定期的なアフターフォローなどの継続収入を受注できるかなどが、セールスポイントとなります。
売上計画
売上の根拠としての「受注契約書」などが確保できているかが重要です。
また、大型案件であれば、取引先が安定した企業が(大手であれば資金は必ず回収できるため)好まれます。
独立前に、受賞した履歴などがあれば裏付けとして有効です。
一般消費者向けのアプリなどの場合には、プロトタイプなど、融資の担当者が具体的に分かるようなものを用意されるとなお良いです。
資金計画
ITの大規模案件では、納期が長期にわたり、売上回収までの期間が長期になります。
その期間は、人件費・外注費などの運転資金が必要となります。
自己資金の割合、返済額のバランスがとれているかが重要です。
優秀な人材を雇用するために人件費や家賃などの固定費が膨らみやすい事業ですので資金繰り表などの作成があると好印象です。
◇創業融資については、こちらの情報館をご活用ください
税理士によるIT事業の方向け税務や経営のノウハウ お役立ち情報
IT事業における税務についてのお役立ち情報を記載しております。
これらはいずれも金額が大きくなりがちで、税務署などとの将来的なトラブルを避けるためにも注意が必要です。
◇IT経営のノウハウ 関連記事
IT関連事業の経営者様に向けた税務や経営お役立ち情報を更新してます。
また、匠税理士事務所は起業と黒字戦略を専門とする会計事務所で、キャッシュストック経営や利益戦略会議というサービスを得意とする会計事務所です。IT事業のお客様のお役に立てそうな経営のノウハウ情報は、下記よりご確認下さい。
◇関連記事
IT事業の経営者様向けの起業・創業サポートサービス紹介
IT関連事業で、法人(株式会社や合同会社)での起業をご検討されている方に向けたサービスはこちらです。
◇創業融資サービス

◇会社設立サービス
◇その他のサービス
○その他のサービスはTOPページのサービス一覧からご確認ください。
世田谷区や目黒区、品川区の税理士は匠税理士事務所...TOPページへ
匠税理士事務所の税理士がこれまで担当したIT事業の内容
・システム開発会社
・アプリケーション開発会社
・WEB制作会社
・大手PCメーカー
・IT広告代理店
・IT事業コンサルタント
・ポータルサイト運営会社 など
目黒区という土地柄、IT事業を経営されているお客様とのお付き合いが多く、IT業の税務や経営コンサルティングの事例が豊富です。
匠税理士事務所の税理士は、40代です。
IT事業は、日々変化を遂げている事業のため、ある程度の若さと経験値が大切かと考えております。
IT分野で事業をされている方、IT分野で起業、創業をご検討中の方は、お気軽にご相談下さい。
◇匠税理士事務所について
自由が丘の会計事務所なら匠税理士事務所...会社概要
補足:申告、納付等の期限延長申請書について (11/03/18)
地震について被災地以外の納税者に関する納期限・申告期限の延長に関する記事が国税庁のHPに掲載されました。以下国税庁のHPより転載致します。
今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難
4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難
なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。
と国税庁のHPに記載されております。
国税当局も今回の地震については臨機応変に対応して下さっています。
上記に該当する方は一度検討されてもよろしいと考えます。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任にてお願いします。
大田区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
東京都 税理士 の匠税理士事務所HPへ
池上線・目黒線沿線の税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (11/03/15)
ご訪問ありがとうございます。
弊所は池上線や目黒線沿線を地元に
【起業支援】と【経営支援】に力を入れてます。
2008年設立から現在まで
【規模】ではなく、【お客様満足度】を追い続け、
関与先様の付き合いは平均10年以上となります。 また、世界4大会計事務所出身の税理士を軸に 経営コンサルティングや高度税務でご好評を頂いてます。匠税理士事務所の所属税理士やサービスは、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 起業・黒字戦略の匠税理士事務所 】

池上線や目黒線沿線の会社設立や起業支援
匠税理士事務所は、30・40代の税理士が中心なため同世代のお客様からのご支持が多く、
起業支援・開業独立支援に力を入れてます。
池上線や目黒線沿線で会社設立をしたいと
お考えの方に会社の基本構造の設計から
会社設立登記、会計経理のアウトソーシングにも
対応しております。
起業セミナーで講師を務める税理士も在籍しており黒字化のための起業支援には評判がございます。
匠税理士事務所の池上線や目黒線沿線での
会社設立など起業支援はこちらから確認下さい。
池上線・目黒線沿線の創業融資による創業支援
会社設立と同時に起業資金の一部について
創業融資により資金調達したいというご要望にも
創業支援で対応致しております。
池上線や目黒線沿線の城南信用金庫や
みずほ銀行など金融機関とも連携しており
制度融資による資金調達にも対応しております。
また日本政策金融公庫の創業融資も得意ですので、
両方向からの資金調達も可能な事務所です。 創業融資成功率は9割超とトップレベルとなります。池上線や目黒線沿線で会社設立時の創業融資による
創業支援は、こちらからご確認下さい。
【 →創業融資による資金調達 】

池上線や目黒線の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 →東京都の創業・起業支援は匠税理士】
(創業支援・起業支援は、池上線や目黒線対応)
池上線や目黒線沿線の税務会計・経理決算
匠税理士事務所では、池上線や目黒線沿線で
事業と営まれている方の確定申告や、
ご自宅や投信マンションの売却に伴う申告、
会社を経営されている方の決算・経理代行の
ご相談も承っております。
確定申告や経理会計、決算の代行を通じて
お客様には本業に集中していただけるよう心掛けております。

また上記の会計事務所の業務以外にも、
弁護士や社労士、行政書士など専門家提携を通じ
契約書の作成やレビュー、社会保険手続きや
給与計算、各種許可申請代行にも対応してます。
【 匠税理士事務所に任せれば安心。 】このお声を頂けるように、
【人の質】・【サービスの質】にはこだわります。池上線・目黒線担当の税理士・専門家のは、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

全専門家:池上線/目黒線沿線に対応してます
池上線や目黒線沿線の決算確定申告や法人化
当会計事務所では、決算確定申告や経理代行、
経営支援や法人化にも対応しています。
サービス内容はこちらから確認下さい。
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
池上線・目黒線の方向けの確定申告や経理代行
法人化など個人サービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
池上線・目黒線で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

池上線・目黒線の法人化・会社設立関連情報
池上線・目黒線の沿線などで個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 東京都での法人化・法人成り】
池上線・目黒線で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記も提携の司法書士が対応致します。
匠税理士事務所の求人や採用について
匠税理士事務所は池上線や目黒線沿線で通勤便利な
目黒区自由が丘駅徒歩2分の位置にございます。
当会計事務所では一緒になって頑張ってくれる
正社員やパートスタッフを募集しています。
池上線や目黒線沿線で勤務をお考えの方は、
弊所採用ページを確認の上でご応募ください。
【 → 武蔵小杉など東横線・目黒線の税理士・会計事務所の採用求人】
(池上線・いけがみせん)・(目黒線・めぐろせん)
沿線で税理士や会計事務所をお探しの方に向け
会社設立など起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りに強い匠税理士事務所の案内ページを
最後までご覧頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#池上線会社設立
#目黒線会社設立
新丸子や多摩川近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (11/03/14)
ご来訪ありがとうございます。
匠税理士事務所は、
新丸子や多摩川など目黒線沿線で
【起業支援と経営支援】に力を入れる事務所です。 世界4大会計事務所出身の税理士を軸に弁護士・社会保険労務士・行政書士など
各分野でトップレベルの専門家が、チームを編成して対応します。
結果、会計や税務申告など会計事務所業務に加え、
契約書作成・法務DD、給与計算、社会保険、労務相談
建設業許可申請やVISA取得代行など
【経営に必要な全てがそろう事務所】です。匠税理士事務所の詳細はこちらで確認下さい。
【 → 起業と黒字戦略の匠税理士事務所 】

新丸子・多摩川の税理士の会社設立・起業支援
匠税理士事務所では、新丸子や多摩川など
東横線や目黒線沿線を中心に
【起業支援】・【経営支援】を行っております。
起業セミナーや経営セミナーで講師を務める税理士が在籍しており、当該分野で豊富なノウハウがあり
結果、多くのご相談を頂いております。
新丸子や多摩川で会社設立など起業支援や、
経営支援を担当する税理士はこちらから
【 → 匠税理士事務所の概要 】

税理士対応エリア:新丸子や多摩川など川崎市
新丸子や多摩川の創業融資による創業支援
これから新丸子や多摩川で株式会社や
合同会社など会社設立したい方に向け、
会社の設計から登記手続きの代行、
設立後の経理や会計のアウトソーシング、
税務申告・決算は全てお任せして頂けます。
経理など本業以外は全てお任せ頂き、
【 独立開業に必要な全てがそろう事務所 】を心掛けた創業支援を提供しております。
新丸子・多摩川で会社設立など創業支援はこちら
会社設立とあわせて起業資金の一部につき
創業融資による調達をお考えの方には、
日本政策金融公庫や新丸子や多摩川対応の
金融機関と連携し創業融資支援も行ってます。
創業計画書の作成から融資面談まで
丁寧にサポートし、金融機関OBが顧問のため
【 融資成功率は90% 】を超えております。会社設立時の創業融資による創業支援はこちら
【→創業融資による資金調達】

(会社設立・創業融資対応エリア:新丸子・多摩川等)
新丸子や多摩川の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちら
(創業支援・起業支援は新丸子や多摩川に対応)
経理会計や確定申告、決算、法人化も対応
当会計事務所では、新丸子や多摩川で
会計や経理をご自身で入力されているが
事業が拡大してきたので代行を検討している方、
確定申告や決算について自分でやってきたが、
将来税務調査などが怖いのでそろそろ専門家に
任せたいと考えている方などの税務や会計につき
代行サービスも提供しております。
節税対策や税務調査などにもしっかりと対応し 社長様は本業に専念できるように支援します。新丸子や多摩川の方に向けた申告サービスは、
こちらにてご確認下さい。
法人の会社様向けサービスはこちらを確認下さい。
【 → 法人のお客様向けサービス一覧 】
新丸子や多摩川の方向け経理や会計、確定申告や
法人化など個人サービスはこちらを確認下さい。
【 → 個人事業のお客様サービス 】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
新丸子や多摩川で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

新丸子や多摩川の法人化・会社設立関連情報
新丸子や多摩川の近くの税理士・会計事務所による
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
【 → 東京都の税理士による法人化・法人成り】
新丸子や多摩川で法人化・会社設立に伴う
商業法人登記も提携の司法書士が対応致します。
新丸子や多摩川近く税理士事務所採用・求人
匠税理士事務所では正社員スタッフや
パートスタッフを募集しています。
新丸子や多摩川近くで勤務を検討中の方は
採用ページよりご応募ください。
【 → 匠税理士事務所の採用求人】
(新丸子・しんまるこ)や(多摩川・たまがわ)の近くで
税理士・会計事務所をお探しの方に向けた
会社設立など創業支援・起業支援や
法人化・法人成りに強い匠税理士事務所の案内を
ご覧頂きありがとうござます。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#多摩川税理士事務所
#新丸子会社設立
原町や青葉台近くの税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (11/02/25)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は青葉台や原町など目黒区で
【経営支援】・【節税対策】に定評ある事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士が在籍し、 【高度な専門性】と【技術力】を軸に、経営支援では、黒字化するためのコンサルティングを
節税対策では、税額控除やシミュレーションを駆使し、
会社に利益をお金として残すよう努めます。税理士やサービスラインは、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 目黒区の税理士は匠税理士事務所】

(青葉台や原町など目黒区全域対応)
青葉台や原町近く起業支援に強い会計事務所
匠税理士事務所は、起業支援セミナー講師を担当したり、
利益戦略会議やキャッシュストック経営など独自経営支援で
【 お客様黒字率100% 】を目指しております。【 儲かって、お金が残る 】会社作りには、
独自サービスとこれを実現する【人材の質】が
必要不可欠と考えております。
そのため、税理士や弁護士、社労士、行政書士など
専門家の質とサービス品質にこだわります。
原町や青葉台担当の税理士・専門家はこちら
【 → 匠税理士事務所の概要 】

会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
原町や青葉台での起業家向け会社設立など
起業支援はこちらからご確認下さい。
【 → 目黒区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
個人の方向けの確定申告や経理の代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 目黒区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

青葉台や原町の会社設立や独立開業・創業支援
弊所の税理士やスタッフは30代~40代のため、
同世代の起業家の方からのご相談を頂きます。
弊所では【起業に必要な全てがそろう事務所】
をサービスの軸に起業支援をしております。
会社社設立からその後の会計経理や給与計算代行
経営支援から節税対策も対応致します。
青葉台や原町での会社設立サービスは、
こちらからご確認をお願いします。
青葉台や原町の創業融資・資金調達
起業支援の一環で会社設立時の創業融資の
資金調達にも対応致しております。
日本政策金融公庫や目黒区制度融資に対応の
城南信用金庫やみずほ銀行とも連携しており、
原町や青葉台で資金調達に強みがあります。
創業融資の成功率は90%を超える実績があり、目黒区でもトップクラスの事務所です。
原町や青葉台の創業融資支援サービスは、
こちらからご確認をお願いします。
【 →目黒区の創業融資・資金調達 】

原町(はらまち)や青葉台(あおばだい)近くで税理士・会計事務所を
お探しの方に向けた案内をご覧頂き感謝致します。
当会計事務所では正社員やパートスタッフを募集してます。
原町や青葉台近くで勤務をご検討中の方は、
採用ページをご確認下さい。
【 → 東京都目黒区の会計事務所の求人・採用は匠税理士事務所】
原町や青葉台の会社設立・法人化登記情報
目黒区の原町や青葉台で
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
原町・青葉台など目黒区で個人から会社設立する
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 渋谷出張所 】管轄区域 目黒区
〒150-8301
渋谷区宇田川町1番10号
(渋谷地方合同庁舎)
上記が原町や青葉台で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
会社設立などの起業支援・創業支援や、
法人化・法人成りなどに関する匠税理士事務所案内を
最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#青葉台会社設立
#原町法人化
生命保険・損害保険代理店と会計事務所の提携募集 (11/01/31)
匠税理士事務所では、お客様の利益の最大化に貢献していただける
生命保険・損害保険代理店の方との提携を募集しております。
お客様の利益の最大化が目的となりますので、
複数の保険会社の商品の中からお客様に最適の商品をご提案できることを提携先には求めております。また、保険事故発生時やお客様が保険適用の是非についてお悩みの際に、
しっかりとお客様目線でお仕事をして頂ける方との提携を考えております。
弊所は世田谷区や目黒区、品川区など東京都を中心に建設業や建築業の会社様が多くお客様にいらっしゃるため、
賠償責任保険など損害保険加入についてニーズが多くございます。
つきましては、損害保険の商品が豊富で取り扱いの実績やノウハウが豊富な代理店様だと大変助かります。

法人向け生命保険の提携募集について
法人加入の様々な生命保険に対応し、
複数の生命保険会社の商品の中でお客様のご要望にそったベストの保険をご提案頂き、
お客様にご納得された最善のものを選んで頂きます。
特定の生命保険会社 や 損害保険会社しかお取り扱いのない方は、今回の提携先募集では考えていません。ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。
なお、複数の生命保険会社・損害保険会社などの保険商品をお取り扱いで、
お客様に最善の保険をご提案していただける方で、代理店の代表者の方との提携が条件となります。
大変申し訳ございませんが、
代理店の営業の方との提携は行っておりません。
その後、保険事故の発生時や契約者貸付などお客様からご連絡を頂いた際には、
スピーディーにご対応頂くことを求めております。

損害保険の提携について
建設業の方の工事保険や賠償保険から、
自動車保険など幅広いお客様のニーズにきめ細やかにご対応頂ければと考えております。
上記の内容をご確認頂き、
匠税理士事務所との生命保険や損害保険に関する業務で、
提携をご検討頂ける場合には、お問い合わせフォームからご連絡を頂けましたら幸いです。
今後も提携先の充実を通してお客様のニーズに応えられる会計事務所づくりに取り組んでいきたいと思います。
匠税理士事務所の税理士や社員、専門家など提携先など概要につきましてはこちらからご確認下さい。
目黒区自由が丘の40代若手税理士や会計事務所は匠税理士事務所
匠税理士事務所
対応地域:目黒区や品川区、世田谷区など東京都23区と神奈川県
戸越公園や戸越駅の税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (11/01/31)
ご来訪ありがとうございます。
弊所は戸越公園や戸越駅など品川区を中心に
【創業支援 と 経営支援】に取り組む事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士が在籍し、品川商工会議所で経営セミナー講師を務めるなど
黒字化のための経営コンサルティングが評判で、
【高度な専門性】と【技術力】を活かして、
関与先の黒字割合は9割超となっております。 【 匠税理士事務所に任せておけば安心 】そんな事務所であり続けたいと努めております。
匠税理士事務所の税理士・サービスは、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

戸越公園・戸越駅で税理士の確定申告や経理
匠税理士事務所では、戸越公園や戸越駅など
品川区エリアでの決算確定申告や経理会計の代行も
対応しております。
お客様には事業に専念していただきたいため会計経理のデータ入力は全て弊所で対応致します。
また、節税対策や税務調査にも対応した決算や
確定申告を行いますので安心してご依頼頂けます。

決算確定申告や経理会計の代行など一般の
会計事務所サービス以外にも、
弁護士や社会保険労務士、弁理士、行政書士と提携で
法務や労務、許可申請やVISAなど幅広く経営者の
ご相談に対応できる事務所になっております。
戸越公園や戸越駅担当税理士・専門家は、
こちらからご確認をお願いします。
【 → 匠税理士事務所の概要 】

会社設立や創業融資など起業支援は
こちらからご確認下さい。
【→ 起業の方向けサービス一覧】
会社様向け財務経営支援や会計サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
戸越公園や戸越駅の方向け確定申告や経理代行
法人化など個人サービスこちらをご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
個人事業主で独立開業し、会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
戸越公園・戸越駅で税理士・会計事務所の相続対策、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

戸越公園や戸越駅など品川区全域に対応
戸越公園・戸越で税理士の会社設立・起業支援
匠税理士事務所では、戸越公園や戸越駅などで
株式会社や合同会社など会社設立の代行から
起業後の経理や会計のアウトソーソングを承ってます。
また起業支援セミナーで講師を務める税理士による 経営コンサルティングは大変ご好評を頂いております。会社設立など起業支援に関するご相談など
お気軽にお問い合わせ下さい。
匠税理士事務所の会社設立など
起業支援は、こちらからご確認下さい。
戸越公園や戸越駅で創業融資による創業支援
会社設立や起業と同時に開業資金の一部を
戸越公園や戸越駅など品川区制度融資や
政府系創業融資の調達も支援します。
起業計画書作成から金融機関と面談立会いまで
弊所独自のサービスで対応しております。
創業融資では成功率90%超の実績となっており 品川区でもトップレベルとなっています。匠税理士事務所の創業融資による創業支援は、
こちらからご確認をお願いします。

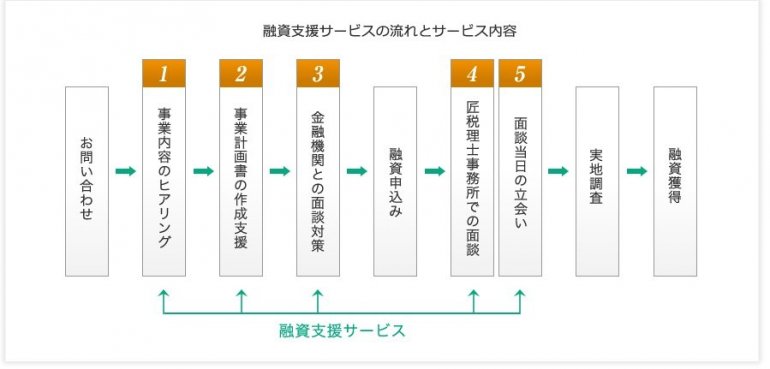
戸越公園や戸越駅の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
(税理士は戸越公園や戸越駅など品川全域対応)
税理士事務所・会計事務所の採用や求人
匠税理士事務所では、会社設立や起業支援など
関与先様のため頑張って下さる方を募集します。
戸越公園や戸越駅など品川区近くの会計事務所を
お探しなら弊所採用をご確認下さい。
品川区の会計事務所の採用求人はこちらから
(戸越公園・とごしこうえん)や(戸越駅・とごしえき)
品川区近くで税理士や会計事務所をお探しの方へ
起業支援・創業支援や、法人化・法人成りなどに関する
匠税理士事務所の案内を最後までご確認頂きありがとうございました。
執筆者・文責:税理士 水野智史
#戸越税理士
退職金の受給形式(一時金・年金方式)と所得税 (10/11/10)
企業に勤めていて今年早期退職をして起業しようと考えている。
こんな方も多いと思います。
起業に際して退職金は大事な自己資金。できるだけ課税されずに多くの資金を残したい。
こんな要望を抱く人がほとんどだと思います。そこで今回は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受けるお金で加入者の退職により支払われるものの取扱いを述べます。
ずばりポイントは、年金形式で受け取るかあるいは一時金形式か。
年金形式なら一般的に多少の利回りが付きます。そして、税金は所得税では雑所得として課税されます。一定の控除額がありますが、控除額を控除して他の給与等と一緒に合算し税額計算します。
これに対して一時金なら1年当たり40万円の非課税枠があり、20年超の勤務なら1年当たり70万円の非課税枠が追加されます。つまり21年勤務したなら40万円×20年+(21年-20年)×70万円=870万円まで非課税です。
そして870万円を超える部分は、他の所得とは合算せず、1/2を乗じた上で所得税を計算します。
したがって、殆どのケースでは、一時金でもらうほうが税負担は軽くなりますし、今の時代は年金形式の利回りより節税による効果のほうが大きいのが一般的です。大事な資金できるだけ手元に残したいものですね。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
東京都 税理士 の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ
税制適格合併と繰越欠損金の引継ぎについて(M&A) (10/10/11)
親会社は好調なんですが、最近、子会社の業績が悪いのでたたんじゃえばいいのか、どうしようかと迷っています。
このようなときに検討するのが、合併です。
合併の中でも一定の要件と満たした税制適格合併であること及び繰越欠損金の引継ぎに関する税務上一定の要件はありますが、これを満たした場合、子会社のもっている欠損を親会社に引き継いで親会社の利益と相殺することで一定の節税効果が見込めます。
(詳細な要件などは省略いたします。)
もちろん、税務上要件は厳しくはなりますが、単純に解散・清算するよりも税務面でメリットがあるケースもございますので慎重な対応が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
品川区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
目黒 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ
10月以降の解散・清算申告の注意点 (10/10/04)
10月に入って解散される場合には注意が必要です。
というのも税制改正の影響を受けるからです。
従来までは、解散後に行う残余財産確定後の清算申告は財産法でした。
つまり債務超過の場合は、税額が原則は生じませんでした。
しかし、10月1日以後解散した法人から通常の損益法による所得計算となります。
これにより債務超過の会社が、債務免除益を受けた場合は課税所得が生じる可能性もありますが、期限切れ欠損金の損金算入の特例も設けられました。
つまり7年間のみ繰り越せる青色申告の繰越欠損金以外に過去に使用出来なかった欠損金を使用することが出来ます。
この改正は、従来と計算方法が大きく異なる上、様々な特例が設けられていますので要注意です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
品川区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
目黒 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ
特殊会社に対する資本圧縮措置と連結納税について (10/09/24)
連結納税を採用しているグループの親会社は、持株会社(ホールディングカンパニー)であることが、多いのですがこのような会社で以外に盲点になるの外形標準課税の特例です。
親会社の資産のほとんどは子会社株式であることが多く、これに対してそのまま資本割を課税することになると相当な税負担となります。
そこで資本割の課税標準の資本金等の算定に際し、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。
(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。)
これを特殊会社に対する資本圧縮措置といいます。
連結納税にのみ目がいって以外に忘れがちな論点ですのでご注意下さい。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
品川区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
目黒 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ
相続時精算課税制度について (10/08/14)
相続時精算課税という制度があるのは知っているけど、どんな方が使うのだろう?
この制度を使用される多くの方は、一般的に最終的な相続税が課税されない人といわれています。
というのも、相続時精算課税は、原則2,500万円まで贈与税を課税しないというメリットがあるものの、課税を繰り延べた財産については、相続時に課税されてしまう制度だからです。
結果、相続税が最終的に課税されるような方には、贈与税の毎年の基礎控除である110万円の枠が使用できなくなり、相続対策の選択肢が狭まり、デメリットが生じる可能性が生じます。
これに対し、相続税が最終的にかからないような方は、贈与時も課税がなく、相続税も課税がないため、早目に財産の移転が行えるというメリットがあります。
これらのことから、最終的な相続税が課税されない人がよく利用されています。
相続税が生じるか否かは、以下の算式の相続税の基礎控除額を相続財産が超えるか否かで概ね判断できます。(細かな特例などは省略します。)
基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
目黒 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ
法人税法上の使用人兼務役員について (10/07/07)
使用人兼務役員は、使用人部分の賞与が損金算入となるため、中小企業でもよく採用が検討されます。そこで、今回は使用人兼務役員を取り扱います。
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。
1 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5 1から4までのほか、同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員
特に、同属会社がほとんどの中小企業では、持ち株の割合の要件が重要となりますので、実施の際は慎重な判断が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
確定申告 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ
グループ税制と中小企業について (10/06/19)
平成22年度税制改正のメインは、と聞かれればグループ税制といっても過言ではありません。
グループ税制とは、
1 100%グループ法人間での1,000万円以上の固定資産、金銭債権等一定資産の譲渡損益の繰延
2 グループ法人間の寄付について、寄与者は全額損金不算入、受贈者は益金不算入
3 受取配当について、負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用する
この他にも細かい規定は多数あります。
これは、今まで連結納税で行われていた取り扱いの一部を、連結納税を採用していなくても、100%出資の完全親子関係などでは同様に取り扱うというものです。
さらに、
今までは資本金1億円以下であれば認められていた以下A~Eの特例が資本金5億円以上の親会社の100%子会社は、使えなくなります。
A 軽減税率
B 特定同族会社の特別税率の不適用
C 貸倒引当金の法定繰入率
D 交際費の損金不算入制度における定額控除
E 欠損金の繰戻還付制度
このように、今回の改正は、子会社を含めると上場企業に与える影響は大きいものです。
また、上記1.2.3は中小企業にも場合によっては影響しますので注意が必要です。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。
世田谷区 税理士 の匠税理士事務所HPへ
確定申告 会計事務所 の匠税理士事務所HPへ
給与計算や就業規則を担当する社会保険労務士の業務提携募集 (10/03/23)
匠税理士事務所では、
起業や会社経営などお客様の社会保険手続や給与計算の代行、
就業規則の作成などをご担当して頂ける社会保険労務士の業務提携先を募集しております。
匠税理士事務所の事務所概要
弊所は目黒区の自由が丘にある税理士事務所で、
起業支援や経営支援に力を入れている会計事務所です。
お客様は30代・40代の方が多いので、
 同世代の社会保険労務士の先生で、
同世代の社会保険労務士の先生で、
給与計算・社会保険加入手続き、
就業規則作成などを通じて、
お客様のお力になって頂ける方を募集しております。
弊所の事務所概要につきましては、
こちらよりご確認をお願いします。
匠税理士事務所が業務提携先・事業提携先に求めること
労務コンサルティングや給与計算、社会保険などで
お力をお貸し頂ける先生は以下のURLを
ご確認の上、ご連絡を頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。
匠税理士事務所のサービスラインやアクセスなどは、
下記よりTOPページへ移動の上でご確認をお願いします。
世田谷区 税理士 弊社HPはこちらへ
事業所得 (09/09/26)
確定申告が初めての個人事業主の方のため、今日は個人事業主の方の所得である
事業所得の取扱を取り上げます。
事業所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費=事業所得の金額
(1) 総収入金額
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
イ 金銭以外の物や権利などによる収入
ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等
ニ 空箱や作業くずなどの売却代金
ホ 仕入割引やリベート収入
(2) 必要経費
必要経費とは、収入を得るために必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものなどがあります。
なお、家事上の経費は必要経費になりません。家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できることができる場合のその部分に相当する経費の金額が必要経費となります。
イ 売上原価
ロ 給与、賃金
ハ 地代、家賃
ニ 減価償却費
(3) 必要経費の特例
イ 家内労働者など
家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。
ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。
(イ) 青色申告
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。
(ロ) 白色申告
事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の必要経費に算入することができます。
個人事業の決算処理~棚卸表の作成~(所) (08/12/06)
個人事業主の決算作業について個人事業の決算処理~棚卸表の作成~をお知らせします。
個人事業での仕入れのうち経費となるのは今年売れた商品に対する原価である商品のみです。
つまりまだ売れていない商品は棚卸として経費となりません。
このまだ、売れていない商品を調べて原価から外す処理のために個人の決算では棚卸を行わなければなりません。
今回は、この棚卸について記載をします。
★棚卸を行う時期
個人は12月31日に行います。
★棚卸の方法
商品や材料などの種類、数量、品質、型べつにその数量を調べます。
★棚卸の金額の計算方法
調べた数量をもとに、あらかじめ税務署に届け出た評価方法で評価をします。
ここでは、特に何も届出を行っていないときの評価方法での計算の仕方を説明します。
数量 × 年末の一番近い時期に仕入れたその商品の単価= 棚卸の金額となります。
※この棚卸が終わったら棚卸表を作成します。
この書類は、確定申告書や帳簿と一緒に保管する義務があります。
★棚ざらし品
この棚卸をしている中で著しい損傷や流行遅れの商品で
通常価格で販売できないもの
通常の方法で使用に耐えないものはほかの棚卸と区別して評価するため<別に棚卸を行いましょう。
★棚卸を行う対象となるもの
商品 製品 半製品 仕掛品 原材料 副産物 仕損じ品 作業屑 消耗品など
個人事業主の決算では、この棚卸を忘れがちです。
確定申告の重要ポイントですのでお忘れのないようご注意ください。
◇サービス(税理士変更のお客様)
書類を送るだけの簡単経理で、青色申告65万の控除を行う個人事業主向けプラン
◇サービス(開業予定のお客様)
開業をするために修業を積みノウハウや資金をためてきて、実際に開業したいと思うが具体的にはどのように進めればよいか分からない。 というお客様向けのサービスです。
○青色申告のための経理代行・節税・確定申告サービス
個人事業での開業に際してお困りの方は、こちらをご覧いただければ幸いです。
○創業融資支援サービス
起業予定のお客様に、開業に必要な資金をヒアリング形式でお伺いしながら自己資金で足りないところは、事業計画書の作成のサポートや 提携している金融機関を紹介する開業資金の調達をお手伝いしております。
○会社設立サービス
会社でスタートしたい場合には会社の設立手続き代行も承っております。
○給与計算代行・社会保険サービス
最初から人を雇用して始める場合には、社会保険の手続きや給与計算のサービスがございます。
-----------------------------------------------------------------------------------
◇会社概要など
税理士 世田谷 TOPページ(世田谷・目黒・品川 東京都全域対応)
※記事に関するご質問は受け付ておりません。
記事についてはお知らせの免責事項を確認し、専門家にご相談ください。
五反田駅近く税理士・会計事務所は匠税理士事務所 (08/03/14)
匠税理士事務所へご訪問ありがとうございます。
弊所は五反田駅など品川区を中心に
【起業支援】と【経営支援】が評判の事務所です。
世界4大会計事務所出身の税理士を中心に、 【高度な専門性と技術力】を軸とした税額シミュレーションによる節税対策や、
関与先黒字割合が9割超のコンサルティングが強みです。
五反田近く匠税理士事務所の詳細は、
こちらからご確認をお願いします。
【→ 品川区の税理士は匠税理士事務所】

五反田近くの税理士の会社設立と経営支援
弊所は品川商工会議所で経営セミナー講師を
担当するなど経営支援に力を入れてます。
会社設立から経営が軌道に乗る支援として、
【お客様に利益と、お金を残すこと】をポリシーに
利益戦略会議やキャッシュストック経営など
独自の経営支援サービスをご用意してます。
現在赤字の会社様や黒字だが利幅が減っているなど
経営改善をサポート致しております。
次に、儲かってるが中々お金がたまらない会社様に
利益をお金で残すキャッシュストック経営で
資金繰りの改善も行っております。
このような取り組みを通じて
【お客様の会社に利益と、お金を残すこと 】でお客様のお役に立つことを使命としております。
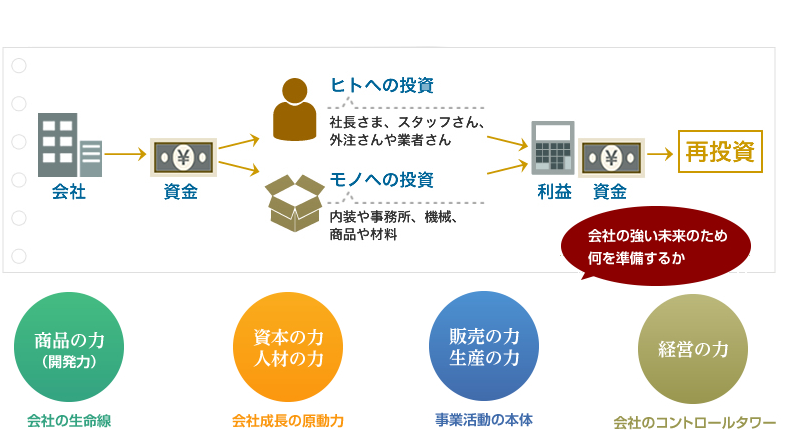
また、上記経営支援を通じ、経営改善できても
税金で減少では、財務的に強固な会社になりません。
そこで匠税理士事務所は、上場企業などで用いる
税金見込計算や税効果検証(tax accrual)の考えで
決算3か月前に会社様に独自開発したシステムにより
決算時点の利益を予測した上で、
税額の予測を実施し、効果的な節税対策を提案する 納税シミュレーションを行っています。・以前の事務所では税額の通知が決算後に行われ、
急に資金が必要となり困った・・・・・
・全く節税対策をしてくれないので困っている・・
という悩みの経営者から納税シミュレーションは
大変ご好評を頂いております。
五反田駅エリア担当の税理士・専門家はこちらから
【 → 匠税理士事務所の概要 】

会社様向け財務経営支援や会計税務サービスは
こちらからご確認下さい。
【→ 法人のお客様向けサービス一覧】
五反田の起業家向け創業支援サービスや
会社設立などこちらから確認下さい。
【→ 起業家向けサービス一覧】
五反田駅近くで個人の方向け確定申告や経理代行
法人化などサービスはこちらでご確認下さい。
【→ 個人のお客様サービス一覧】
土地や家、マンションやアパートなど不動産で、
五反田で税理士・会計事務所の相続税対策や、
相続税申告・贈与税の確定申告はこちらから
【 → 品川区で税理士の相続税申告・相続対策は匠税理士事務所 】

五反田駅など品川の会社設立や起業支援
匠税理士事務所は経営支援のノウハウを活かし
早期黒字化ニーズがある起業支援に注力してます。
役員構成や資本金など基本フレーム作りから、
株式会社や合同会社の会社設立の登記代行まで
税理士と司法書士が連携して対応します。
また起業セミナーで講師を務める税理士が、
起業後の経理や会計のアウトソーソングを承ってます。
給与計算や社会保険手続きの代行も対応しており
【起業に必要な全てがそろう事務所】です。五反田駅近くの会社設立サービスは、
こちらからご確認をお願いします。
五反田など品川区の創業融資による創業支援
独立開業や起業に必要資金の一部を品川区や
日本政策金融公庫創業融資で創業支援します。
制度融資と政府融資の両方に対応可能なため、
最大資金調達の枠は、2,000万円となります。
また、会社設立など起業に伴う事業計画作成から
各金融機関と融資面談の立会いまでサポートの
こだわりの創業融資サービスで対応します。
創業融資では成功率90%超の実績となっており、 品川区の税理士の中でもトップレベルの水準です。匠税理士事務所の創業融資による創業支援は、
こちらからご確認をお願いします。

五反田の株式会社・合同会社の
会社設立や独立開業後の会計経理や、
決算確定申告の代行から節税対策は勿論、
中小企業診断士による補助金申請代行や、
社会保険労務士による助成金対応などの
創業支援も充実しております。
匠税理士事務所の創業支援はこちらから
【 → 品川区など東京都の創業・起業支援は匠税理士 】
会社設立・創業融資対応エリア:五反田など品川区全域
五反田駅近くの税理士事務所・会計事務所求人
五反田近く税理士事務所で勤務を検討中の方は
当会計事務所の求人採用もご確認下さい。
ご応募お待ちしております。
匠税理士事務所の採用求人は、
こちらからご確認をお願いします。
五反田近く税理士事務所お役立ち情報
五反田駅(ごたんだえき)は、
東京都品川区東五反田2-1-1にあり、
以下の3社3路線が乗り入れ
相互間の接続駅となってます。
JR東日本 山手線
東急電鉄 池上線
都営地下鉄 浅草線
五反田は、上記に立地しますので、
五反田で会社設立など起業した場合や、
会社経営をされている場合の税務申告書、
会社設立時の届出書提出先は以下になります。
法人税や消費税・所得税など国税に関する 税務申告書、届出書提出先→品川税務署
管轄区域:【品川区のうち品川地区】・大崎地区・大井地区・八潮地区
〒108-8622
港区高輪3丁目13番22号
事業税・住民税の申告書、届出書提出先→品川都税事務所
管轄区域・品川区・大田区
〒140-8716 品川区広町2-1-36
※品川区役所 本庁舎・議会棟の2階です。
上記が税務申告関連や会社設立時の届出書の提出先となります。
期限までに税務関連書類の提出を行いましょう。
五反田駅の会社設立・法人化登記情報
品川区の五反田駅で個人から会社設立する
法人化・法人成りはこちらからご確認下さい。
五反田駅など品川区エリアで
会社設立・法人化に伴う登記をする場合は、
こちらでの手続きとなります。
【 →東京法務局 品川出張所 】管轄区域 品川区
〒140-8717
品川区広町2丁目1番36号
(品川区総合庁舎)
上記が五反田駅で会社設立・法人化の際、
登記手続き対応する行政窓口となります。
五反田駅(ごたんだえき)近くで会社設立など
起業支援・創業支援や法人化に強い税理士や会計事務所を
お探しの方に向けた弊所案内をご覧頂きありがとうございました。
税理士対応エリアは五反田など品川区全域
執筆者・文責:税理士 水野智史
#五反田税理士
#五反田創業融資
#五反田会社設立